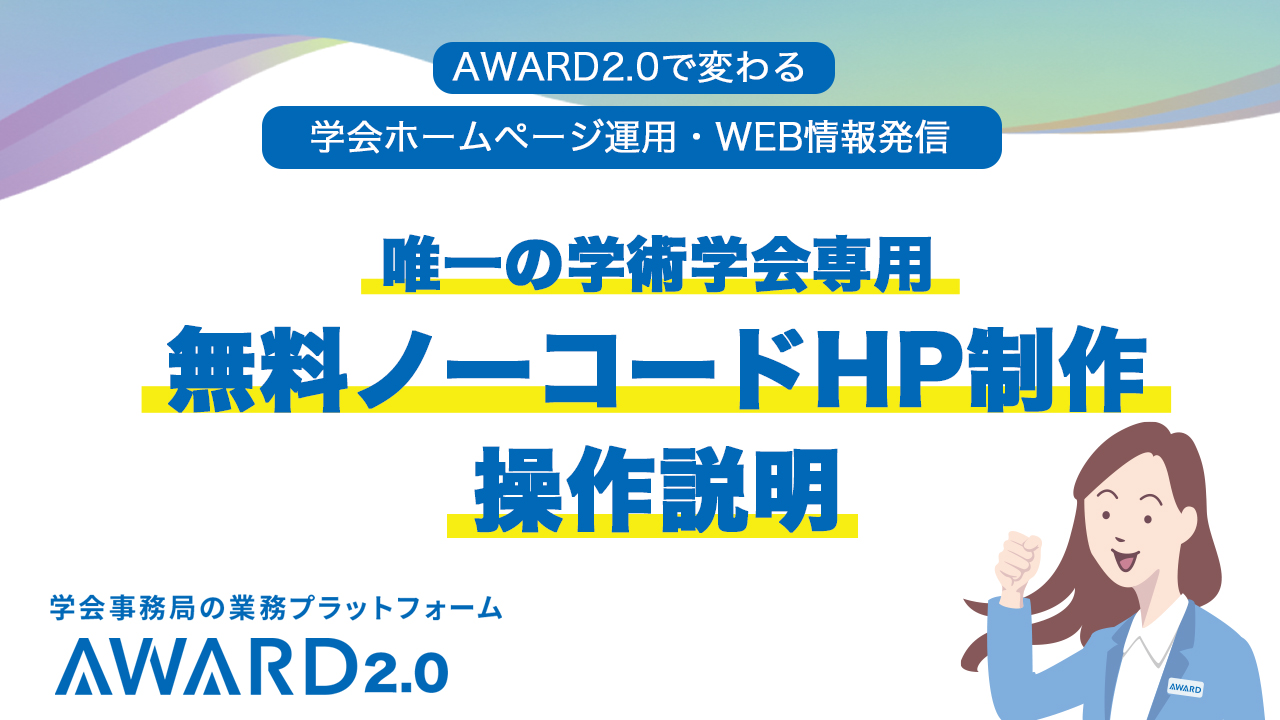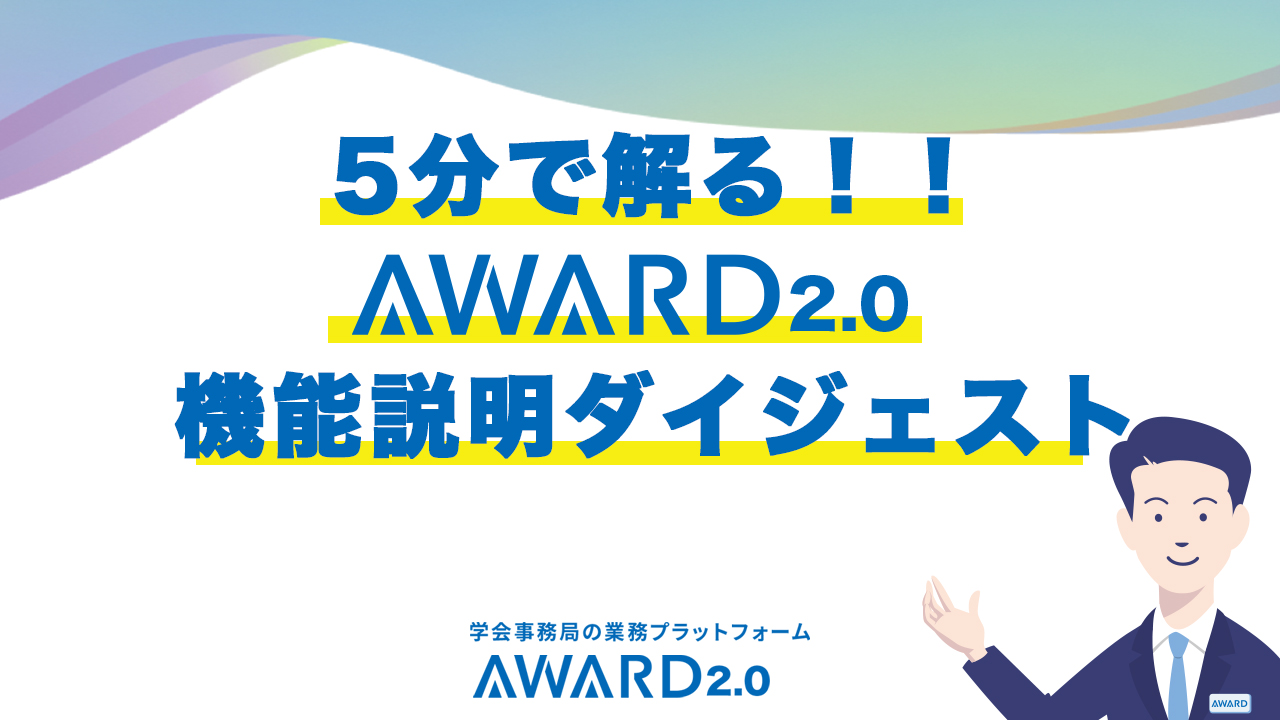学会運営の成功事例に学ぶ ~学術イベントを”持続可能”にする運営戦略~
2025年08月08日
はじめに:学会運営における「成功」とは何か
学会運営と聞くと、会場の手配や参加者の管理といった実務的な側面を思い浮かべる方が多いかもしれませんね。しかし、真の学会運営は、単なる事務作業に留まりません。知の交流を促進し、新たな発見を育む場を創造する、まさに未来へと繋がる重要な「営み」なんです。
では、私たちが考える学会運営における“成功”とは何を意味するのでしょうか?それは、ただイベントを無事に終えることだけではありません。参加者の深い満足度、研究成果の社会への波及力、そして何よりも「持続可能性」という多角的な視点から考察されるべきものです。
この記事では、これまでの学会運営における多様な事例から成功の要因を抽出し、皆さんの学会運営が次世代へと繋がる「持続可能」なものになるよう、具体的な運営戦略について一緒に考えていきましょう。
1. 成功事例に共通する要素と運営ポイント
1.1. 学会運営成功の5つの共通要素
多くの学会が運営において顕著な成功を収めていますが、そこにはいくつかの共通した要素が存在します。
・明確な目的意識の共有
・参加者中心の視点
・効率的な運営体制
・積極的な情報発信
・継続的な改善姿勢
第一に、明確な目的意識とビジョンの共有です。学会が何を達成しようとしているのか、その学術的な使命は何か。これらの基本的な問いに対する答えを運営メンバー全体が深く理解し、共有することが重要です。この共通認識こそが、運営の一貫性を保つ揺るぎない基盤となります。例えば、特定の研究分野の発展加速、若手研究者の育成強化、社会問題解決への貢献といった具体的な目標がその根底にあるはずです。
第二に、参加者中心の視点です。学会は研究者間の交流を深め、最新の研究成果を発表し議論する場です。そのため、参加者が何を求め、どのような環境であれば最も有意義な時間を過ごせるのかを常に考慮する必要があります。実際に、プログラム構成、会場設営、情報提供などにこの視点を反映させている学会は、参加者満足度90%以上を継続的に達成しているケースも少なくありません。具体的には、発表形式の多様化、活発な質疑応答を促す工夫、ネットワーキング機会の創出などが考えられるでしょう。
第三に、効率的かつ効果的な運営体制の構築です。限られたリソースの中で最大限の成果を追求するためには、役割分担の明確化、適切なデジタルツールの導入、そして迅速な意思決定が不可欠と考えられます。近年では、学会運営システムの活用やクラウドツールの導入により、事務作業の負担を軽減し、より本質的な企画・運営に資源を集中できる状況が実現されています。
第四に、積極的な情報発信と広報活動です。学会の存在意義や魅力を外部に伝えることは、新たな参加者や賛助会員を獲得し、学会の持続的な発展に寄与します。WEBサイト、ソーシャルメディア、ニュースリリースなどを活用した多角的な情報発信は、学会の認知度向上に不可欠です。
最後に、継続的な改善への意欲です。一度の成功に満足せず、参加者アンケートや運営メンバーからのフィードバックを真摯に受け止め、次回の運営に活かす姿勢が、学会を常に発展させる原動力となります。
1.2. 効果的な学会運営の4つのポイント
前述の共通要素を踏まえ、具体的な運営のポイントをまとめてみましょう。
・事前計画と準備
・コミュニケーション戦略
・各種ツールの選定
・リスクマネジメント
まず、事前の計画と綿密な準備の徹底です。学会の規模や内容に依存しますが、開催の1年以上前(地域研究会:6ヶ月~1年前、全国大会:1年~2年前、国際学会:2年~3年以上)から準備を開始し、周到なスケジュールを策定することが極めて重要です。特に、会場の確保、予算計画、演題募集期間の設定などは、早期に着手すべき要件でしょう。
次に、効果的なコミュニケーション戦略です。学会内外の関係者との円滑な意思疎通は、運営を成功に導く上で不可欠です。運営委員会内部での定期的な会合はもちろんのこと、演題発表者、参加者、スポンサーなど、それぞれのステイクホルダーに対して、適切なタイミングで正確な情報を提供できる仕組みを構築することが求められます。例えば、自動送信メールシステムや専用の会員向けポータルサイトの活用が有効です。
さらに、テクノロジーの積極的な活用が挙げられます。前述の通り、学会運営システムは、演題登録、査読、参加登録、要旨集作成、参加費徴収など、多岐にわたる業務を効率化します。また、オンライン開催やハイブリッド開催を検討する際には、ウェビナーツール(Zoom Webinar、Teams Live Eventsなど)やオンラインイベントプラットフォームの選定も重要なポイントです。
そして、リスクマネジメントの視点も不可欠です。自然災害、システムトラブル、参加者の急なキャンセルなど、予測不可能な事態に備え、事前に対応策を検討しておくことが重要です。具体的には、緊急時の連絡体制の確立、予備の機材の準備、キャンセルポリシーの明示などが挙げられます。各種保険の検討、選定も有効な手段です。
(参考)
学会を効率化する方法を徹底解説! おすすめのシステムもご紹介します。|これからの学会.com
興行中止保険|東京海上日動
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/risk/kougyo
2. 成功事例の分析から見える課題と工夫
2.1. 学会運営で直面する5つの主要課題
多くの成功事例に見られる明るい側面の裏には、運営者が直面した多様な課題と、それを克服するための努力が存在します。学会運営でよく直面する主要な課題を見ていきましょう。
・属人化からの脱却
・予算制約と収益源確保
・参加者ニーズの多様化への対応
・タイムリーな情報伝達
・過去からの脱却と新しい試みの導入
まず、人手不足と運営体制の属人化は、多くの学会が共通して抱える課題です。特に、大学の教職員が兼務で運営を担う場合、本業との両立が困難となり、特定の担当者に業務が集中しがちです。これにより、担当者の負担が増大し、引き継ぎが困難になるといった問題が生じます。
次に、予算の制約と収益源の確保も大きな課題です。学会運営には、会場費、システム利用料、印刷費など、多額の費用を要します。参加費や年会費だけでは賄いきれない場合も多く、企業からの協賛金や各種の助成金の獲得が不可欠となりますが、その交渉や管理には専門的な知識と労力が求められます。
また、参加者のニーズの多様化への対応も課題の一つです。若手研究者とベテラン研究者、国内参加者と海外参加者など、参加者の背景や期待は様々です。全員のニーズを満たすプログラムや運営体制を構築することは容易ではありません。例えば、英語での発表機会の拡充、託児サービスの提供、インクルーシブ支援(Inclusive Support)、多様なネットワーキング機会の創出などが求められます。
さらに、情報伝達の課題も挙げられます。学会の重要なお知らせやプログラムの変更などが、参加者や関係者に正確かつタイムリーに伝わらないことで、混乱が生じることがあります。効果的な情報伝達チャネルの確保と、重複や齟齬のない情報管理が重要です。
最後に、過去の慣習からの脱却と新しい試みの導入です。長年続いている運営方法やプログラムは、時に新しいアイデアやテクノロジーの導入を妨げることがあります。属人化や保守主義は進歩の妨げとなります。時代とともに変化するニーズに対応するためには、既存の枠組みにとらわれず、積極的に新しい試みを取り入れる勇気が求められます。
2.2. 成功に導く工夫を考える
これらの課題や問題を克服し、学会運営を成功に導くためには多様な工夫が求められます。
人手不足と属人化に対しては、業務の標準化とマニュアル化が極めて有効です。一例としては、要旨集作成プロセスのように、定型業務については詳細な手順書を作成し、誰もが同じ品質で業務できるようにすることで、担当者の負担を軽減し、引き継ぎを容易にします。さらに、学会運営システムの導入により、事務作業の多くを自動化・効率化することも可能です。
(参考)
業務の属人化とは?原因や解消方法、成功事例を紹介|ITトレンド
https://it-trend.jp/knowledge_management/article/25-0037
予算の制約に対しては、多様な収益源の確保とコスト削減の検討が不可欠です。企業協賛の積極的な働きかけはもちろんのこと、参加費の複数設定(早期割引、学生割引など)、オンライン参加枠の設定、物品販売なども検討に値します。近年ではクラウドファンディングなども有効な手段として注目されています。また、ペーパーレス化の推進や、オンラインツールの活用による印刷費や郵送費の削減も効果的です。
参加者のニーズの多様化への対応としては、パーソナライズされた体験の提供を目指すことが挙げられます。例えば、発表テーマごとにセッションを細分化したり、興味関心に応じたネットワーキングイベントを企画したりすることで、参加者一人ひとりの満足度を高められます。また、参加者アンケートを詳細に分析し、次回のプログラムに反映させることで、より参加者のニーズに適合した学会へと進化させることが可能です。
情報伝達の課題には、多チャネルでの情報発信と一元管理が有効です。学会ウェブサイトを情報の中核としつつ、メールマガジン、SNS(LINE、Slack、X、Facebook、LinkedInなど)、参加者専用のポータルサイトなどを併用することで、より多くの参加者に情報を届けられます。そして情報は常に最新の状態に保ち、過去の情報もアーカイブとして残しておくことで、参加者の利便性を高めます。
新しい試みの導入においては、段階的なアプローチと小規模な試行が成功の鍵となります。具体的には、すべてのプログラムをオンライン化するのではなく、一部のセッションのみをオンラインで開催してみる、特定のセッションで新しいインタラクティブツールを試してみるなど、リスクを抑えながら新しいアイデアを実践できます。成功した場合は本格導入を検討し、うまくいかなかった場合は改善点を分析することで、着実に学会運営を向上させられるでしょう。
(参考)
日本癌学会、若手研究者表彰の対象者公表―クラファンで支援|Medical Note
https://medicalnote.jp/nj_articles/221226-004-ST
3. 学術イベントを”持続可能”にする運営戦略
「持続可能」な学会運営とは、単に学会の大会や各種イベントを毎年開催し続けることだけを意味しません。それは、学術的な価値を創出し続け、社会に貢献し、そして次世代の研究者へとその役割を引き継いでいくことを含みます。この持続可能性を実現するための運営戦略として、次の5つの要件を重視しましょう。
・若手研究者の確保
・社会連携の強化
・デジタル技術の最大活用
・コンプライアンス遵守
・PDCA
まず挙げられるのが、若手研究者の積極的な巻き込みと育成です。学会の未来を担うのは若手研究者です。彼らが運営に携わる機会を提供し、経験を積んでもらうことで、将来の運営委員を育成できます。若手研究者向けの研究発表会や、キャリアパスに関するセッションの企画も、学会へのエンゲージメントを高める上で非常に重要です。
次に、社会との連携強化です。学会は閉鎖的なコミュニティではなく、社会に対して開かれた存在であるべきです。企業や自治体、他の学術団体との連携を深めることで、新たな研究テーマの創出や共同プロジェクトの推進、そして社会実装への貢献が可能になります。シンポジウムの共同開催や、産学連携のセッション設置なども有効な手段です。
さらに、デジタル技術の最大限の活用は、持続可能な運営に不可欠です。前述の運営システムはもちろんのこと、要旨集のデジタル公開、J-STAGEなどでのDOI(Digital Object Identifier:デジタルオブジェクト識別子)付与、オンライン発表のアーカイブ化、バーチャル展示の導入などは、地理的・時間的な制約を超えて学術情報を共有し、学会のリーチを広げます。これにより、より多くの研究者や一般市民が学会の成果にアクセスできるようになり、学会の社会貢献度が高まるでしょう。
そして、倫理的な運営の推進も重要な要素です。学会は、多様性と包摂性を尊重し、公正な運営を心がける必要性に迫られます。ハラスメント対策の徹底、多様な背景を持つ研究者の参加促進、環境負荷の低減を目指す運営(例えば、ペーパーレス化、フードロスの削減)などは、学会の社会的信頼を高め、より多くの人々に支持される要因となります。
最後に、評価と改善のサイクルを確立することです。学会運営は一度きりのイベントではなく、継続的なプロセスです。毎回の開催後に、参加者アンケートの結果、運営メンバーからのフィードバック、財務状況などを総合的に評価し、次回の運営計画に反映させることで、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回し、常に改善していく姿勢が持続可能性を担保します。
(参考)
【学術大会運営を効率化】J-STAGEで抄録集を公開・管理・活用する3ステップ|日本印刷出版株式会社
おわりに:学会運営の成功に向けたポイントの整理
学会運営は、学術の発展を支え、社会に貢献するための重要な活動です。その成功は、単なる効率性だけでなく、参加者の満足度、情報発信力、そして何よりも持続可能性という多角的な視点から評価されるべきものだとご理解いただけたでしょうか。
この記事では、成功する学会運営における明確な目的意識、参加者中心の視点、効率的な運営体制、積極的な情報発信、そして継続的な改善への意欲といった共通の要素を考察してきました。これらの要素を基盤として、事前の計画、効果的なコミュニケーション、テクノロジーの活用、リスクマネジメントといった運営のポイントが重要であると考えられます。
また、人手不足、予算制約、ニーズの多様化といった課題に対しては、業務の標準化とシステム導入、多様な収益源の確保、パーソナライズされた体験の提供、多チャネルでの情報発信、そして段階的な新しい試みといった工夫が求められます。
そして、最終的に学術イベントを”持続可能”にするためには、若手研究者の育成、社会との連携強化、デジタル技術の最大限の活用、倫理的な運営の推進、そして評価と改善のサイクルの確立が不可欠です。
PDCAを回し続けることで運営の質を高め、若手に運営のバトンを渡し、そしてその成果を社会実装へと繋げていく。この流れこそが、学会運営に携わる多くの方々の活動が、学術の未来を拓き、社会の発展に寄与する道となるでしょう。この一歩が、あなたの学会の未来を確かに築いていくことに繋がります。
(参考)
関連法規集|日本学術会議
https://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/index.html
《第10回》楽しい学会組織運営|筑波大学システム情報系教授伊藤誠
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicejl/56/10/56_805/_pdf