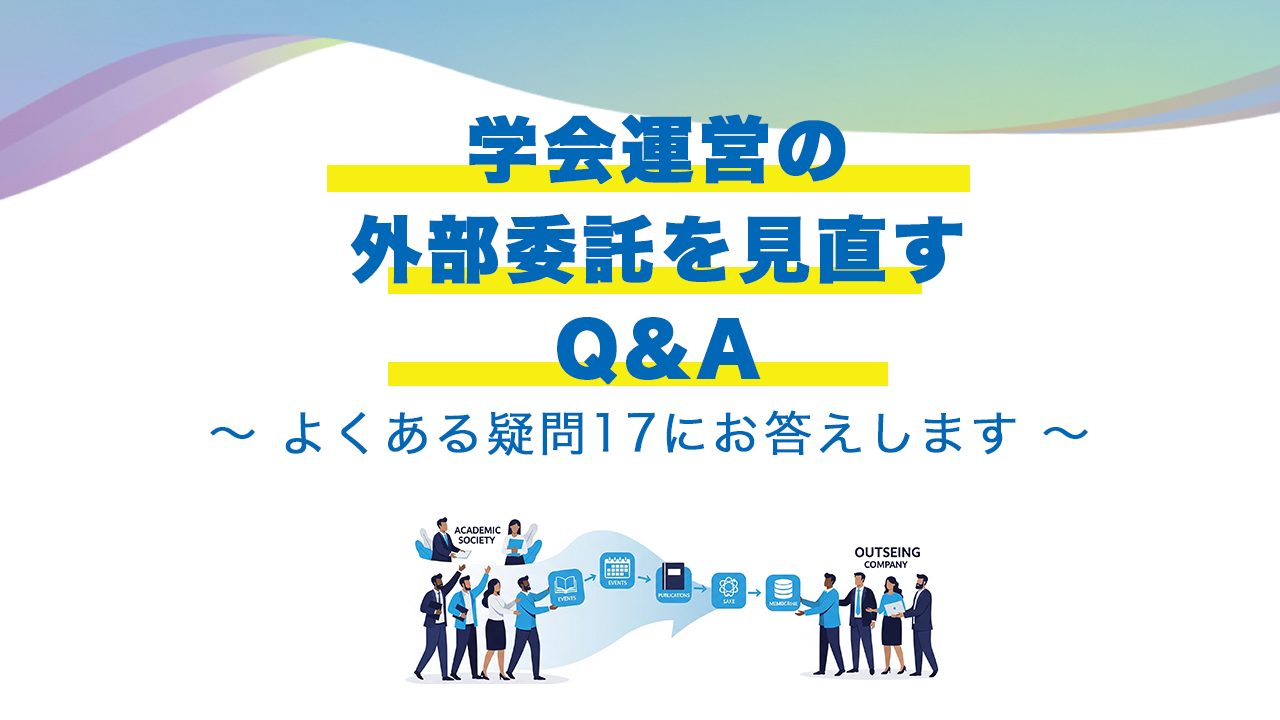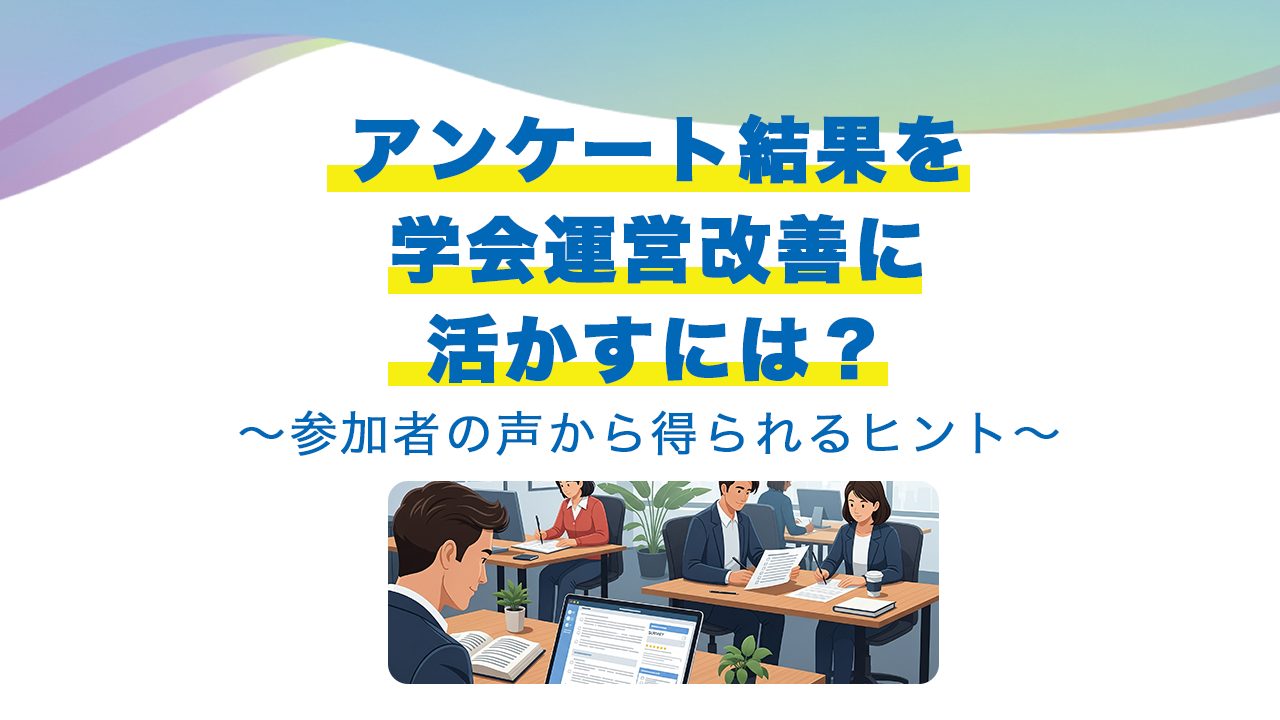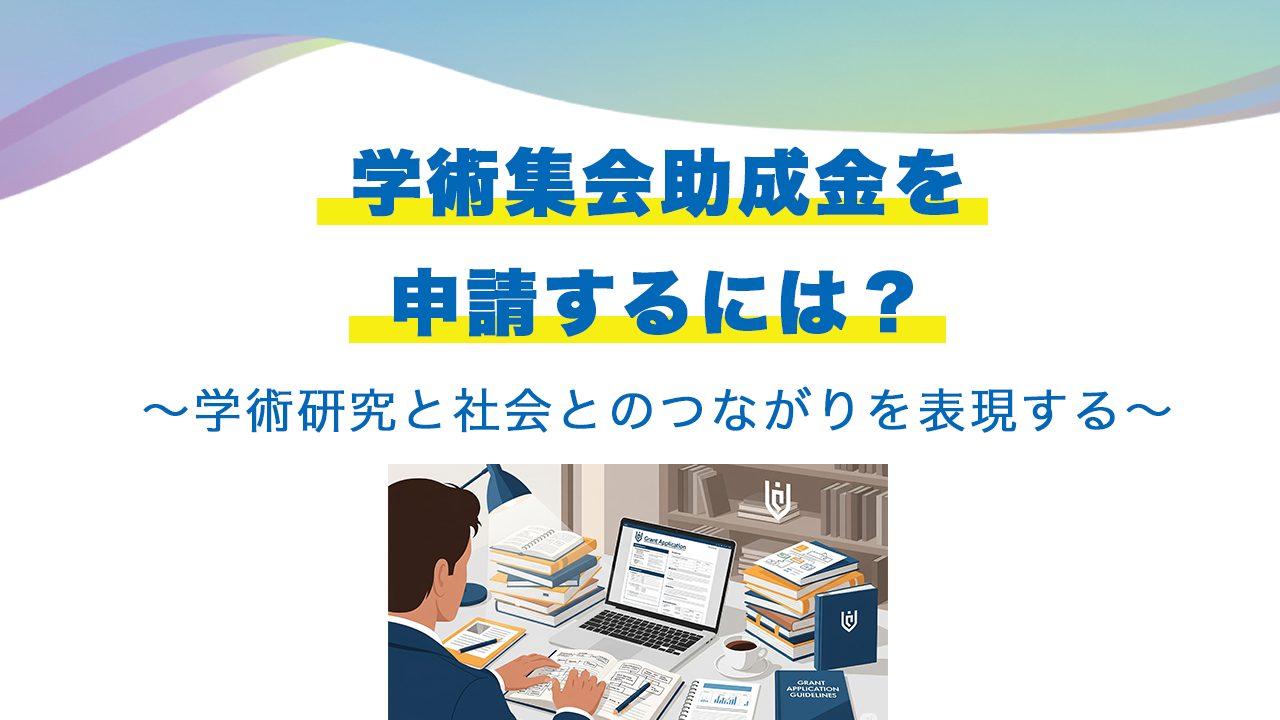対面開催とオンラインの良さを活かす! ~ハイブリッド学会の設計と運営の実践ガイド~
2025年08月08日
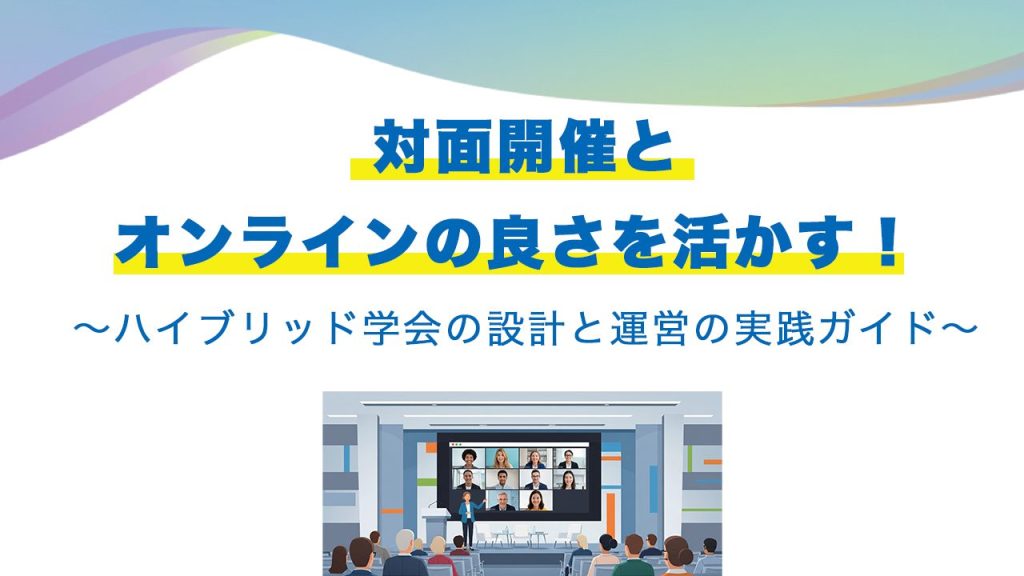
はじめに:多様な参加形態を叶えるハイブリッド開催の重要性
多くの学会がオンラインまたはハイブリッド形式に移行し、その重要性が高まっています。かつては学会といえば、参加者全員が一堂に会し同じ空間と時間を共有する「対面開催」が中心でした。
けれども近年、遠隔地や海外からの参加者、育児・介護等多様な事情を抱える方々、さらにはパンデミックなど、現地への移動が困難な状況が続いたことで、「オンライン開催」という選択肢が急速に普及しました。
このような時代を迎え、今、学会運営の現場で最も注目されているのが「ハイブリッド開催」です。対面とオンライン双方の特性と利点を融合し新しい参加形態のスタンダードとして定着しつつあります。
ハイブリッド開催の意義は、単に“現地とオンラインの併用”という表面的なものに留まりません。
多様なライフスタイル、働き方、地理的・身体的制約を抱えた研究者や学生へ平等な参加機会を提供するという学術的・社会的意義を担っています。
実際、「対面」は現場ならではの臨場感やエンカウンター(偶発的邂逅)、濃密な議論を可能にします。
一方で「オンライン」は時間や場所にとらわれない柔軟性、より広い層への情報提供を実現します。もちろん、体験格差や運営負荷、技術的対応といった新たな課題も顕在化していますがこれらを乗り越えることでより包摂的な学会運営が実現できます。
この記事では、こうした課題を一つ一つ乗り越え学会運営初心者でも迷わず取り組めるハイブリッド学会の設計・運営ノウハウについて紹介します。
また、学術団体の事務局を担う教職員や、運営に携わる企業・自治体・関連団体の担当者の方々もヒントとなる実践事項を多角的な視点で紹介します。
(参考)
本連載シリーズの記事も参考にしてください。
「Zoom活用で実現する新しい学会会議スタイル~対話と参加を支えるハイブリッドの仕組み~」
ハイブリッドイベント開催のポイント|これからの学会.com
ハイブリッド開催とは何か?その定義と登場の背景
ハイブリッド開催とは、学会やイベントを「現地」(いわゆる会場=対面)と「オンライン」(WEB配信等の遠隔参加)という二つの形態で同時開催し、いずれか、または両方で参加できる方式のことです。
従来の対面開催では、物理的な会場への来場が必須でした。オンライン開催の普及により、会場に行けない参加希望者も場所を問わず参加できるようになったものの、「直接交流したい」という参加体験への強いニーズも根強く残ります。例えば、オンライン疲れや孤独感、偶然の出会いによる発見、“空気感”のもたらす高揚感などです。
そこで誕生したのが、対面とオンラインの“いいとこどり”ともいえる「ハイブリッド方式」です。学会や学術集会、各種イベントでも多様な参加者に柔軟かつ公平な参加機会を広げ現代社会の多様性を反映する開催方法として国内外で急速に標準化してきたのです。
(参考)
【学会・大学向け】セミナーや学会のハイブリッド開催 |日本印刷出版株式会社
学会のハイブリッド開催って何?|フリート合同会社
普及と定着の背景
何故ここまで急速に定着したのかを日本と世界の事例を踏まえてみてみましょう。
(1) 感染症蔓延・多様なリスク対応
2020年以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大は、従来の「全員一堂に会す」開催方式の危機となりました。
これを契機に、多くの学会・大規模イベントが全面オンラインやハイブリッド方式へと移行。どのような社会情勢下でも“学び・意見交換・研究発表”を持続できる体制が強く求められました。
(2) 地理的・経済的バリアフリーの実現
遠方居住者、育児・介護従事者、障がいや疾病のある方々が移動や宿泊をせずに研究発表や意見交換に参加できることは“学術の裾野拡大”に直結します。国際学会であれば現地へ渡航できない海外研究者にも平等なアクセス機会を提供できます。また、複数の学会日程が重なった場合にも、参加機会を確保できます。
(3) 技術革新による体験格差の低減
数年前に比べオンライン配信・録画、双方向Q&Aや討論、資料共有、双方向投票・チャット等を実現するIT基盤が各段に進化。加えて、多様なサポートやトラブル対応ノウハウも洗練され、現地/オンライン双方にとって「参加しやすい」「満足度が高い」環境づくりが一般化しました。
(4) サステナビリティ(持続可能性)の観点
長距離移動や出張を減らすことは、CO2削減や家計負担の低減に直結します。また、学び直しや生涯学習社会の進展にも大きく貢献しており、持続可能な社会への貢献という側面からも注目されています。
(5) 実施事例の蓄積と標準化
昨今では大規模学会から小規模研究会、地域イベントまで幅広くハイブリッド開催の実績とノウハウが蓄積され定着への「安心材料」となり、さらなる定着を後押ししています。
1. 現場とオンラインの調和を意識した運営設計
ハイブリッド開催成功の鍵は、参加者のニーズを把握し現地とオンラインそれぞれの利点を生かしたプログラム設計です。参加者体験の格差をなくすため双方向性の高いチャットや質疑応答システムを活用し現地とオンラインの「つながり」や「発見」を促進する工夫が重要です。運営側は、幅広い視点からニーズを吸い上げ、参加者目線で改善に取り組むことが求められます。
1.1. ハイブリッド学会の参加者ニーズ分析と体験格差解消への設計
ハイブリッド開催の最初の一歩は、
「どんな参加者が、どのような動機や事情でどちらの手段を希望するか」
という本質を見極めることです。
会員や参加希望者への事前アンケート、過去データの分析を通して地理的・経済的・時間的・デジタルリテラシー格差といった障壁を丁寧に洗い出すことからのスタートです。
例えば、現地ならではの強み(「偶然の出会い」や「多様な関係者との雑談」「レセプションなどでの五感を使った交流」など)、一方でオンラインの強み(「どこからでも気軽に参加」「録画や資料を好きなタイミングで復習」「言語の壁を乗り越えた交流」など)を一つ一つリストアップが必要です。それらを明確にすることで、効果的なプログラム設計へと繋がるでしょう。
その上で「どのセッションを現地中心」「どの企画をオンライン中心」「どちらも提供」と切り分けることが、効果的なプログラム設計につながります。
また、WEBサイトやプログラム案内も見やすさやキーワード動線を重視すれば初参加者や経験の浅い方も戸惑うことなく情報や参加方法にアクセスできます。
1.2. 双方向性・一体感を高めるプログラム構成
ハイブリッド開催最大の課題の一つが現地とオンライン双方の“参加体験格差”です。
「ただ映像を配信するだけ」ではオンライン参加者が「傍観者」になってしまう懸念があります。
この解決策として、チャットモデレーターの配置や質疑応答・投票システムの活用が効果的です。現地・オンラインどちらからでも意見・感想・質問が投稿できる仕組みを整えたり、ポスターセッションを「バーチャル」+「現地巡回」の両方で実施したりするなど、参加形態を超えて“つながり”や“発見”を体験できる工夫が大切です。
例えば、ZoomウェビナーやMicrosoft Teamsなどのウェブ会議ツールに標準搭載されたチャット機能やQ&A機能、あるいはSlidoやLiveQのような質疑応答・投票に特化した外部ツールを活用し、チャットモデレーターが質問の選別、類似質問の統合、不適切な発言の監視・削除を行うことで、円滑なコミュニケーションを促進できます。
「運営者の自己満足」や一部関係者だけの視点に陥らず“すべての参加者目線に立つ”ことが、次なる成功への扉となります。
(参考)
すべて会議をインタラクティブに!|slido
リアルタイムQ&Aツール|LiveQ
2. 技術支援・運営体制・参加者ケアの具体的な工夫
ハイブリッド学会の成功には、安定した技術インフラ(配信基盤、ネットワーク、会場機器)の選定と事前準備が不可欠です。また、多岐にわたる役割分担と連携を明確化した運営体制の確立が重要です。さらに、オンライン・現地双方の参加者への丁寧なサポートや発表資料の著作権管理を含む法的側面への配慮も欠かせません。そのポイントをみてゆきましょう。
2.1 信頼性を支える技術インフラの選定と準備
ハイブリッド学会運営の要となるのは「配信基盤」「ネットワーク」「会場機器」等の整備と、その運用ノウハウです。
配信プラットフォーム選定では「同時接続数」「双方向性」「投票・チャット・字幕機能」「セキュリティ」など参加者人数や属性に応じて必要条件を明確化しましょう。
現地会場ではネットワークの安定性・音響、カメラ設置、照明等の環境を事前リハーサルでチェック、映像音声の遅延・乱れを防ぐ工夫が肝要です。万一のトラブル対応計画も必須といえるでしょう。
さらに近年では「ベクトル検索」など先進的な情報検索技術もメインサイトやプログラム情報ページに組み込むことで、参加者・運営の双方の負担を減らす事例も増えています。
公式ホームページでは、「参加方法」「技術問合せ窓口」「FAQ」といった導線も分かりやすく整え、検索から迷わず各種サポートへ到達できるよう設計しましょう。
(参考)
ベクトル検索とは?|Elastic
https://www.elastic.co/jp/what-is/vector-search
ベクトル検索におけるテキスト構造化の効果分析|言語処理学会
https://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2025/pdf_dir/P8-13.pdf
2.2 持続可能な運営体制の確立
ハイブリッド運営では現地・オンライン両面の「司会」「配信担当」「モデレーター」「トラブル対応」等、多様な役割を明確にし、連携体制・緊急時のフローを委員会で標準化しましょう。
各担当責任者が事前リハを重ねスムーズな進行と柔軟な対応力を身につけることが理想的なチーム運営につながります。
また、オンライン専用ヘルプデスク・チャット対応、現地の案内スタッフの連携、セッション進行マニュアル化やFAQの整備など、「初めての職員や関係者も迷わず安心して動ける」工夫が重要です。加えて、継続的な委員会による多重チェックやノウハウ共有、定期的な情報交換も推進しましょう。
(参考)
学会におけるモデレーターとは?|学会ビズ
https://gakkai.biz/gakkai-dictionary/043-Moderator.html
2.3 参加者一人ひとりへの配慮と法的サポート
オンライン参加者には、接続マニュアルや事前テスト会、当日のチャット・メールでのサポート窓口設置が重要です。現地参加者に対しても、Wi-Fiや電源、オンライン参加との連携スペース、感染症対策やバリアフリー支援を準備しましょう。
また、発表資料の著作権管理・録画配信も慎重に。著作権法第35条や各種運用指針を調べ、学会環境に即したガイドラインを構築・提示してください。
全ての参加者が安心して発表し、質疑・意見交換できる「コンプライアンスの担保」も現代学会運営の要となっています。
(参考)
東京大学「著作権法第35条と教育機関等」|東京大学
https://utelecon.adm.u-tokyo.ac.jp/articles/copyright/article35-and-educational-institutions
SARTRAS運用指針|一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会
3. 評価と継続的改善のためのフィードバックサイクル
ハイブリッド学会運営は、多角的な評価指標(参加者数、セッション活性度、録画視聴など)で定量・定性的に分析することが重要です。満足度アンケートや登壇者所感も活用し、GoogleのE-E-A-Tも考慮してウェブサイトの充実を図りましょう。これらのフィードバックを基に、トラブル事例や改善策を組織知として蓄積し、継続的な改善の仕組みを構築することが、持続可能な学会運営には不可欠です。
3.1.多角的評価指標の設定と運用
ハイブリッド運営の良否は、一度の開催では完結しません。
「何名が現地、オンラインに参加したか」「各セッションの活性度はどうだったか」「録画視聴の利用状況」「質問件数・回答率」など多様な指標を集計・可視化することで、次の改善点が明確化します。
定量分析・定性分析の両方が必要です。
また、満足度アンケートや登壇者からの所感も貴重な“現場の声”です。サイト管理や検索流入などWebの観点からも、Googleが重視する”E-E-A-T”の観点で学会サイトの情報充実を心がけましょう。これらのことで、ハイブリッド運営の成功の可能性を高めることができます。
E-E-A-Tとは、Experience(経験)-Expertise(専門性)-Authoritativeness(権威性)-Trustworthiness(信頼性)の頭文字で、Googleの「検索品質評価ガイドライン」で定義されているWEBサイトの評価基準のことです。
(参考)
Devo「E-E-A-T強化のポイント」|株式会社ディーボ
3.2 フィードバックを生かした継続的改善の仕組み
単発開催で「終わり」にせず、アンケートやヒアリング、トラブル対応記録などを標準化し属性別集計や現場職員からの知見をドキュメント化しましょう。実際の運営現場では「こんな困りごとがありました」という形での具体例や失敗事例とその改善策の収集が大切です。
それらを委員会や運営チーム内で共有し、暗黙知ではなく形式知、”組織知”として蓄積することで新しいメンバーでも高品質な運営を実現できます。この“仕組み化”こそ、属人的な運営から脱却し安心して続けられる学会組織の生命線です。
実践的なタイムラインや予算規模別の対応指針の確立、トラブルシューティング集やFAQ集の編纂も改善の仕組みづくりに有効です。
おわりに:新時代の「学会運営」スタイルとして
この記事では、ハイブリッド開催がもたらす多様性と包摂性そして技術進歩・運営ノウハウの蓄積によって大きく進化した学会運営の現場についてその基本と実践のポイントを紹介してきました。
まとめると、ハイブリッド開催は単なるトレンドではなく “変化し続ける学術コミュニティの基盤” として今や不可欠な運営手法です。
その本質は、「すべての参加者にとって等しく開かれた知の場」を実現し、地理的・身体的・時間的な壁を乗り越えた学びの機会とつながりを創出する点にあります。
もちろん、新しい運営スタイルには技術的・人的な課題や、継続的な改善が求められます。時には、専門家(専門家集団)やアウトソーシング先の支援や援助を検討する必要もあります。
現場ごとの知恵と経験、思い切って一歩踏み出す柔軟性を重ねていくことで、より良い学会運営へと進化させることが可能です。
これから学会事務局を担う若手研究者や関連団体の担当者の方々も、“誰一人取り残さない安心の場づくり” “新しい知の拠点づくり”という視点を基に、それぞれの現場に合った最良のハイブリッド運用を探求し続けてください。
将来的には、AIによる自動翻訳やリアルタイム解析、VR技術を活用した没入感のあるバーチャル会場(例えば「VR空間でのポスターセッションで、まるで隣にいるかのように議論できる未来」)などが、ハイブリッド学会の体験をさらに進化させるでしょう。
(参考)
持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)|文部科学省