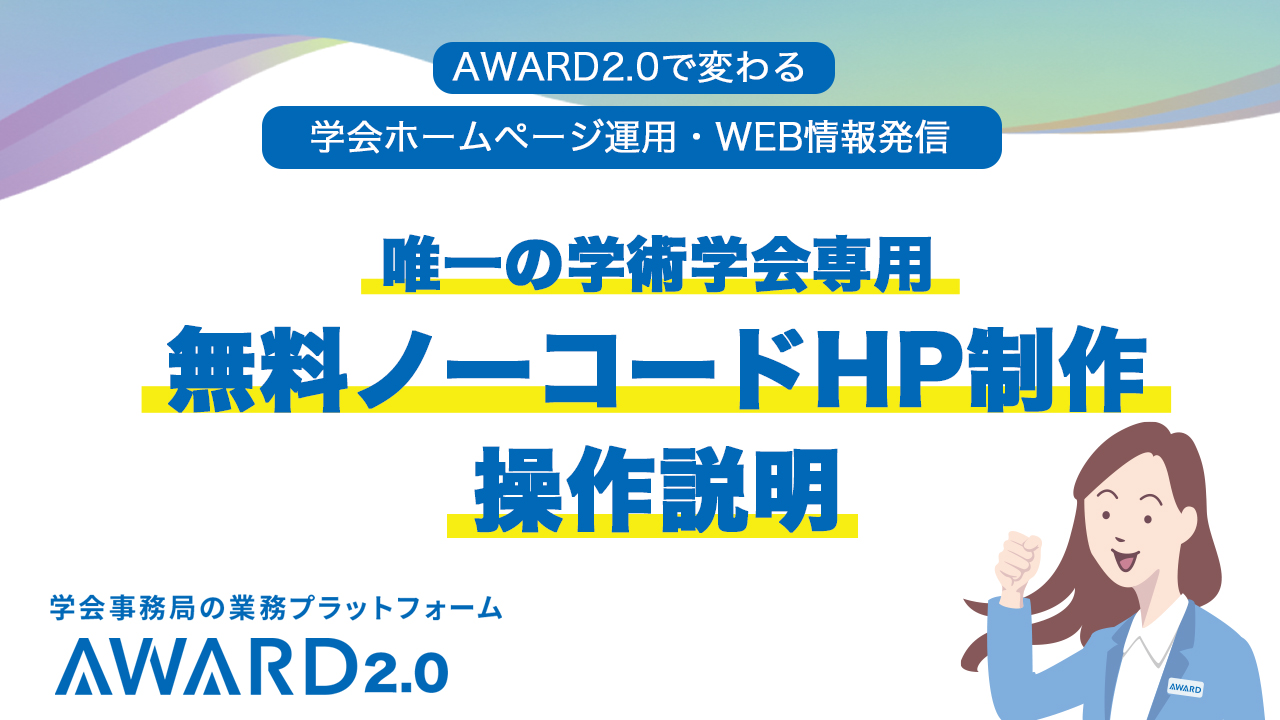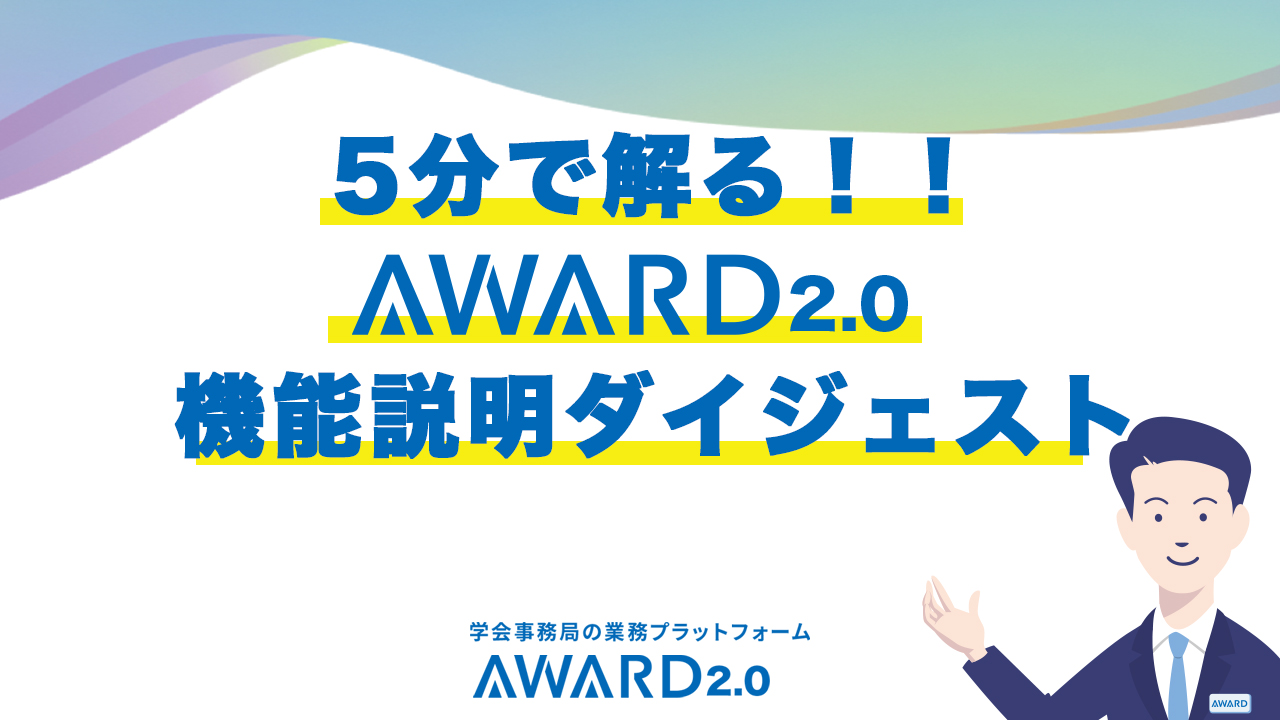学会要旨集作成が驚くほどスムーズに進む実践術 〜効率と正確性の両立に資するポイント〜
2025年08月08日
はじめに
学会運営においては、多岐にわたる準備や調整が必要とされますが、その中でも要旨集の作成は、学術的成果を明確に伝達するために不可欠な作業です。
要旨集は研究を魅力的に紹介する媒体
近年、オンライン開催やハイブリッド形式の普及に伴い、要旨集の役割も変化しています。参加者にとっては研究内容を把握するためのガイドとして、登壇者にとっては自身の研究を正確かつ魅力的に紹介する媒体として機能しています。
一方で、学会事務局を担う関係者にとっては、演題の整理、体裁の統一、校正作業など、多大な手間を要する工程が多数存在し、人的・時間的な負担が大きいという課題が指摘されています。
初めて学会の要旨集作成を担当される方は、不慣れなことも多く、どのように進めるべきか戸惑うことも多いでしょう。
本記事では、そんな方々の手助けとなるポイントを具体的に解説します。
ここでは、要旨集作成プロセスをより円滑に進めるためのポイントを、標準化およびデジタル化の観点から考察し提示します。
学会運営に携わる教職員や関連業務に関心を持つ方に、実務のヒントとして活用いただければと思います。
要旨集作成の効率化を図るためには、業務の標準化とデジタルツールの導入が不可欠です。これにより、作業時間の短縮に加えて、ヒューマンエラーの防止や情報の一元管理が可能となります。
さらに、今後のAIやクラウド技術の活用により、要旨集の作成はよりスマートで持続可能な形態へと進化することが期待されます。
要旨集の効率的な作成が今日不可欠である理由
学会の開催形式が多様化する中で、要旨集の提供方法も紙媒体からPDFやWeb形式へと変化しています。この変化に対応するためには、事務局の作業プロセス自体が柔軟かつ効率的である必要があります。
しかし、限られた人員や予算のなかで、従来の手作業に依存した業務体制では対応が困難になりつつあります。
また、要旨集は学会の「顔」とも言える存在です。誤字脱字や体裁の不統一は、学会全体の印象や信頼性に大きく影響するため、高精度な作成体制が求められています。
1. 要旨集作成プロセスの標準化とデジタル化が学会運営を変革する
1.1.業務の標準化とデジタル化
作成業務の標準化は、担当者間の連携を円滑にし、作業の属人化を防ぐ上で有効です。共通フォーマットの活用により、体裁の統一が実現し、査読、分類、番号付けといった事務処理の効率化に繋がります。また、過去大会のデータを活用することで、構成の改善や継続的な品質向上も実現可能です。
一方、デジタル化は作成業務そのものに変革をもたらします。例えば、要旨集の自動作成機能を有する「AWARD2.0」のようなシステムでは、参加登録時に集約された演題情報を、要旨集として自動的に成形することが可能です。
さらに、J-STAGEのような学術公開サービスを活用することで、XML形式による登録、検索性の強化、公開範囲の拡大などが可能となり、研究発信力の向上にも貢献します。
(参考)
学会を効率化する方法を徹底解説! おすすめのシステムもご紹介します。|これからの学会.com
【学術大会運営を効率化】J-STAGEで抄録集を公開・管理・活用する3ステップ|日本印刷出版株式会社
1.2.記載ガイドライン
標準化を進める際には、単にテンプレートを用意するだけでなく、作成者向けの「記載ガイドライン」や「記入例」の提示が効果的です。
例えば、目的・方法・結果・考察の記述例や文字数上限を明示することで、著者によるばらつきを抑制できます。また、原稿受付から校正までのフロー図を共有することで、業務全体を俯瞰しやすくなり、抜け漏れの予防に繋がります。
デジタル化においては、Googleフォームやクラウドストレージでも、小規模な学会においては一定の成果が得られる可能性があります。もし可能であれば、まず小規模な部分からGoogleフォーム等の無料ツールを採用してみて、運用感を掴むことも一考です。
一方で、AWARD2.0のような投稿管理特化サービスを導入することで、演題登録から査読、抄録作成までの全プロセスを一気通貫で管理でき、複数担当者が関与する業務でも混乱なく進行可能となります。
加えて、要旨集をJ-STAGEに登録しDOI(Digital Object Identifier:デジタルオブジェクト識別子)を付与することで、論文への引用や外部評価にも繋がる学術資源としての価値が高まります。
2. 要旨集作成プロセスにおける問題・課題と解決策
2.1.制作現場での困りごと
要旨集作成の現場では、演題のフォーマット不統一、著者情報の入力ミス、確認作業の煩雑さ、印刷コストの高さなど、様々な問題や課題が発生しやすい傾向にあります。これらを解決するためには次のような対策が有効です。
Web投稿システムを導入することで、演題登録から査読、採択、要旨成形までのプロセスを一元管理できます。クラウド型データベースを活用することで、著者情報や演題の変更履歴をリアルタイムで共有でき、確認作業も円滑になります。
また、PDFの自動生成機能により、検索機能付きの要旨集を効率的に作成できます。
印刷・製本・発送業務は、専門業者への外部委託により、事務局の負担を軽減しつつ品質の安定化を図ることが可能です。
(参考)
オンライン用要旨集PDF|株式会社創文社
データの作り方|学会印刷ドットコム
https://gakkaiprint.com/contents/tukurikata.html
2.2.要旨本文の質を高める
加えて、要旨本文の質を高めるためには、「目的・方法・結果・考察」という構造を明確にし、専門用語を正確に用いることが重要です。曖昧な表現の排除や簡潔さを意識することで、AI検索における引用可能性を高めることができます。
(参考)
要旨作成の注意点|日本機械学会 2023年度大会資料
https://2023.jsme-conference.net/wp-content/uploads/2023/09/7a5e3c8ebd1da0ee967f7096f015747c.pdf
2.3.UI設計のポイント
運用上、著者によるフォーマット違反は頻出する課題です。これに対し、演題受付時に「チェックリスト形式」のガイドを導入することが有効です。提出前に著者自身が規定の形式・文字数を確認できる仕組みを設けることで、修正依頼の手間を削減できます。
著者情報についても、氏名の表記(漢字・英字)、所属の正式名称、共同著者との関係性などを入力時点で明確にさせるようなUI(ユーザーインターフェース)設計を行えば、後工程の確認が容易になります。これにはCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)ツールの併用も効果的です。
また、印刷業務の外部委託先には、入稿フォーマットの整備、色校正の自動化、追跡可能な発送システムなどを提供する企業もあり、単なる委託先ではなく「パートナー」としての連携が求められる局面も増加しています。
一部の学会では、本文内の「研究倫理に関する記述の有無」や「資金提供者の開示」についても要旨集作成時点で確認するルールを設けています。これは研究の透明性や信頼性を担保するための重要なステップです。利益相反(COI:Conflict of Interest)状態の開示なども近年では求められています。
(参考)
学術集会におけるCOI 開示|利益相反委員会|日本臨床検査医学会
https://www.jslm.org/committees/coi/jslm.html
3. 要旨集作成の将来展望とデジタル化の進展
3.1.ペーパーレス化の加速
今後の要旨集作成は、完全なペーパーレス化が進むと予測されます。Web形式の要旨集は検索性や閲覧性が高く、参加者にとって利便性の向上が期待されます。また、環境負荷の削減やコスト削減の面でも有効です。
さらに、AIの活用によって、要旨の自動分類、誤字脱字の検出、関連演題とのリンク生成などが可能になってきています。
Webシステムには、お気に入り登録やタグ機能などUX(User eXperience)向上のための工夫も加えられており、より使いやすいサービスへと進化しています。
日本地質学会ではWeb抄録システムへの移行によって、業務効率化と参加者満足度の両立を図っています。
日本鳥学会では、PDF版のみに絞ることで紙資源の削減と事務負担の軽減に成功しています。
3.2.インタラクティブ要旨集の登場
今後注目されるのは、読者視点での「インタラクティブ要旨集」の登場です。例えば、Web要旨集にタグ機能や検索フィルターが実装されることで、専門領域やキーワードに基づく情報探索が可能になります。参加者は自身の関心分野の演題を見つけやすくなり、事前準備も効率的に行えます。
AIによる分類機能を活用すれば、提出された演題を自動的に分類し、セッションごとの構成案を事前に出力することも可能です。主催者にとっては、プログラム編成の手間が軽減されるだけでなく、演題の偏りや重複も早期に把握できます。
UXの観点でも、スマートフォン対応のレスポンシブデザイン、マーカー機能、PDFダウンロード機能など、閲覧性を高める工夫が求められています。これらの機能は、要旨集を「読み物」から「活用ツール」へ進化させる鍵となります。
近年ではSDGsやカーボンニュートラルの観点から「紙印刷ゼロ」を目指す学会も増えています。紙の代替としてタブレット端末を貸与する方式や、会場内にQRコードを設置する方式など、持続可能性の観点からも要旨集のあり方が変化しつつあります。
情報処理学会は、会場では印刷物の代わりにUSBメモリ(現在はクラウドへ移行)で資料提供をしていました。
(参考)ペーパーレス研究発表会の開催手順&良くある質問|情報処理学会
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/manual/paperless.html
おわりに
要旨集作成は、学会運営において最も精度と労力が求められる作業の一つです。しかし、標準化とデジタル化を進めることで、作業の効率化と品質向上の両立が可能となります。
AIやクラウド技術の進展により、要旨集の作成はよりスマートで持続可能な形態へと進化していくでしょう。
要旨集は単なる記録やアーカイブではありません。学術知識の発見や発掘のための重要な資源であり、新たな研究の創出を支える貴重な基盤です。効率的な要旨集作成は、学会の価値向上と学術発展に直結する重要な取り組みと言えます。