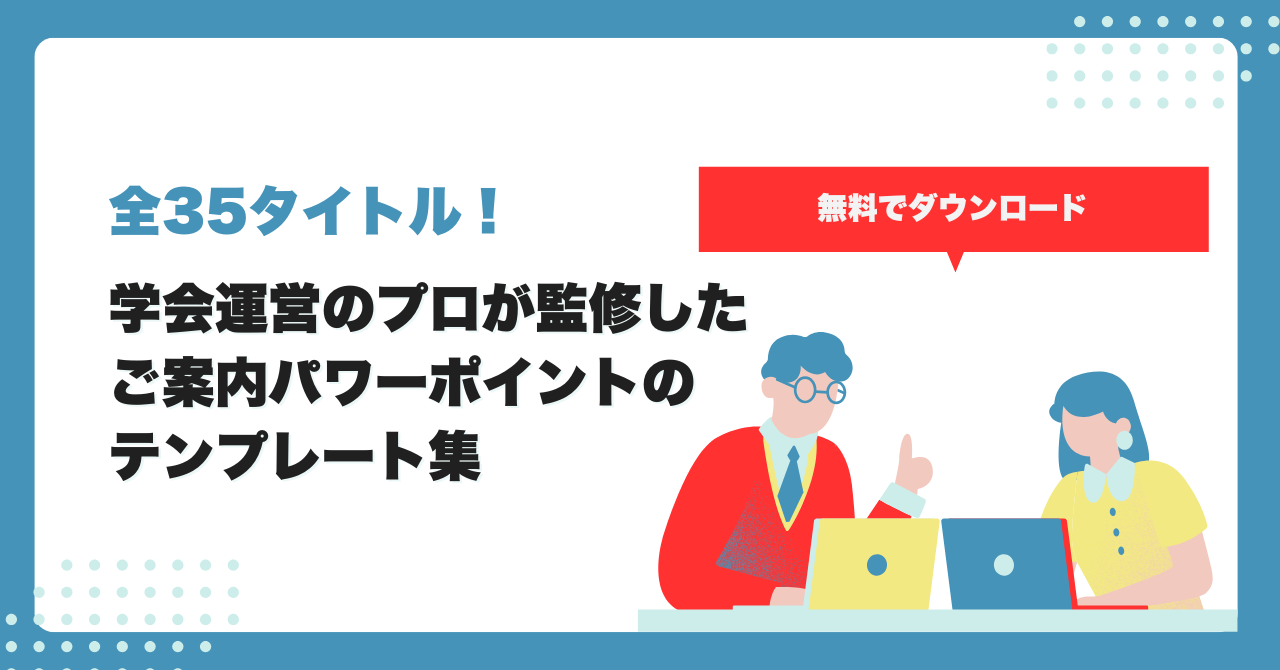学会運営の効率化を徹底解説!スムーズな運営を実現する方法
2025年06月14日
学会運営の効率化を徹底解説!スムーズな運営を実現する方法
学会運営の負担を軽減し、より円滑な運営を目指すための「効率化」は、多くの学会にとって重要な課題です。
会員管理、演題募集、参加受付、会計処理、そして当日の運営といった多岐にわたる業務は、限られた人員と時間の中で大きな負担となりがちです。
本記事では、学会運営の効率化に焦点を当て、その具体的な方法と、効率化を強力に推進するツールの活用について詳しく解説します。
学会運営・準備の現状と課題
学会の運営と準備は、多岐にわたる業務を伴うため、多くの人手と時間を必要とします。
特に、会員管理、演題募集、参加登録の受付、予算管理、会場手配、当日の運営などは、限られた人員でこなさなければならないため、「時間が足りない」「人手が足りない」「コストがかかる」といった課題を抱える学会運営者も少なくありません。
これらの業務は、主に当該分野の研究者や学者、そして学会事務局のスタッフによって担われています。
大規模な学会では専任の職員がいる場合もありますが、中小規模の学会では大学の研究室が事務局機能を兼ねることが多く、教員や助手が業務を兼任するケースも珍しくありません。
近年では、人手不足や業務負担の増大に対応するため、外部の専門業者に運営業務の一部または全部を委託する学会も増えています。
学会運営を「効率化」する重要性
学会運営の負担を軽減し、持続可能な活動を続けるためには、業務の「効率化」が不可欠です。
効率化を進めることで、限られた人員でもスムーズに大会準備を進められ、人手不足の解消にも繋がります。
また、事務処理に費やす時間を削減できれば、学術プログラムの充実や参加者へのサービス向上といった、学会本来の目的である核心業務にリソースを集中させることができます。
これにより、学会全体の質が向上し、参加者の満足度も高まることが期待されます。
さらに、効率化はヒューマンエラーのリスクを低減し、手作業による入力ミスや漏れを防ぐことにも貢献します。
作業時間の短縮や重複作業の削減は、コスト圧縮にも直結し、学会の経済面においても大きなメリットをもたらします。
学会運営の「効率化」を実現する方法
学会運営を「効率化」するための方法は多岐にわたりますが、主に以下の3つのアプローチが挙げられます。
デジタルツールの活用による効率化
デジタルツールの活用による効率化策として、学会運営管理システムや各種クラウドサービスを導入することで、手作業を減らし業務を自動化できます。
例えば、参加登録をオンライン化して電子チケット発行やQRコードによる受付を導入すれば、当日の受付業務負担を大幅に削減できます。
また、演題登録・査読をオンラインシステムで行えばメールや紙でのやり取りが不要となり進行管理が容易です。
業務プロセスの見直しによる効率化
業務プロセスの見直しによる効率化策では、タスクの見える化と標準化が効果的です。
学会準備に必要なタスクを洗い出してチェックリスト化し、進捗管理シートで管理すると漏れ防止になります。
近年はTodoistやTrelloなどチームでタスクを共有できる無料のタスク管理ツールもあり、これらを使えば複数人での準備作業も一目で状況把握が可能です。
テンプレートやひな形を活用するのも有効で、過去の大会の案内文や議事録フォーマットなどを使い回せば、一から書類を作成する手間が省けます。
人員配置の工夫による効率化
人員配置の工夫による効率化策としては、短期スタッフやボランティアの活用も挙げられます。
大会当日や直前期のみアルバイトを雇用したり、大学院生や若手研究者にボランティア参加を募ったりすることで、人的リソースを一時的に増強できます。
アルバイトを活用すれば一定の戦力を確保でき、人手不足解消に役立ちます。
一方ボランティアであれば、学会に興味を持つ人に経験の場を提供するメリットもあり、将来的な学会運営者育成にもつながります。
「学会運営管理システム」を活用した効率化
「学会運営管理システム」は、学会事務局業務の多くをオンライン上で一元管理し、自動化することで、多方面から「効率化」を推進します。
具体的な機能としては、以下のようなものがあります。
会員情報の一元管理
会員データベースをクラウド上で統合管理し、入退会処理や会員情報更新をオンラインで完結できます。
担当者間でリアルタイムに最新情報を共有できるため、複数人で作業しても情報齟齬が生じません。
氏名検索や属性による絞り込みなど検索機能も充実し、必要な情報に素早くアクセスできます。
会費徴収・決済管理の自動化
年会費や参加費の請求・入金確認をシステムが自動で行います。
クレジットカード決済や口座振替にも対応し、未納者へ自動リマインドメールを送信することも可能です。
これにより入金状況の管理や督促作業の手間を大幅に削減できます。
学会大会の演題登録・参加登録管理の効率化
演題募集から参加登録までWeb上で受付でき、効率化が可能です。
演題投稿をオンラインで受け付けてデータ管理し、そのままプログラム編成に活用可能です。
参加登録もオンラインフォームで行い、参加区分に応じた料金設定や決済を受け付けることができます。
登録データはリアルタイム集計されるため、参加者数や収支を随時把握できます。
大会当日の受付・認証の効率化
事前発行した電子チケットやQRコードを活用し、会場受付をスムーズに行えます。
参加者は受付でQRコードを提示するだけで確認が済み、スタッフは専用アプリで読み取るだけなので、従来必要だった名簿チェックやネームカード配布の作業が大幅に省力化されます。
メール配信・情報共有における効率化
会員や参加者への一斉メール送信機能があり、案内や連絡事項を属性ごとに配信できます。
例えば新人会員のみに特定のお知らせを送る、未入金者だけに督促メールを出す、といった柔軟なコミュニケーションが可能です。
システム上に「お知らせ」を掲載し、会員専用ページで周知する機能も備わっており、情報伝達を効率化します。
各種帳票・証明書の発行時の効率化
領収書や参加証明書、請求書などをシステムから発行できます。
自動発行により手書きや個別対応の手間が省け、英語表記の請求書発行など国際学会対応もワンクリックで行えます。
Webサイト・抄録集作成の効率化
システムによっては簡易的な大会ホームページを生成したり、登録済みの演題データから抄録集PDFを自動作成する機能もあります。
デザインやレイアウトをテンプレートから選ぶだけで大会案内ページを公開できるため、専門のWeb制作知識がなくても情報発信が可能です。
学会運営システムの導入メリット・デメリット
「学会運営システム」の導入は、「効率化」の大きな恩恵をもたらしますが、同時に考慮すべき点もあります。
メリット
学会運営管理システム導入のメリットは、効率化やコスト削減などになります。
効率化と正確性向上
学会運営システムを導入する最大のメリットは、事務局業務の効率化と正確性向上です。
手作業を減らし自動化できることで、担当者の負担軽減とヒューマンエラー削減につながります。
例えば、会員情報をクラウドで一元管理すれば最新データの共有が容易になり、重複管理や入力ミスが防げます。
また、会費や参加費のオンライン決済により徴収漏れを防ぎ、未納者への対応もシステム任せで済むため事務処理がスピーディになります。
さらに、参加登録や問い合わせ対応もオンライン化されることで、会員サービスの質が向上します。
会員専用ページから自分の登録情報を確認・更新できたり、イベント申込みもWeb上で完結できるため、会員にとっても利便性が高まります。
データが一箇所にまとまり蓄積されることで、過去の問い合わせ履歴や参加履歴を参照しやすくなり、世代交代があってもスムーズに運営を引き継げる点もメリットです。
時間短縮・コスト削減
また、時間とコストの削減効果も見逃せません。
オンライン化により郵送費や紙の印刷費を削減し、データ入力の手間を省くことで残業代など人件費の圧縮にもつながります。
クラウド型の学会システムであれば自前でサーバーを持つ必要がなく、システム保守もベンダー側で行われるため運用コストが明瞭である点も利点でしょう。
さらに、最近の学会システムはセキュリティ対策も充実しており、個人情報保護やアクセス制御がしっかりしているため安心して利用できます。
地理的な制約もなくなるため、どこからでも事務局業務にアクセスでき、テレワーク環境下でも業務継続が可能になるといった柔軟性もメリットと言えます。
デメリット
一方で、学会運営システムの導入には注意すべき点もあります。
初期費用・ランニングコスト
まず初期導入コストやランニングコストです。
システムによっては導入費用が高額だったり、利用人数や機能に応じた月額費用がかかるものもあります。
小規模学会向けに初期費用無料や成果報酬型のサービスも出てきていますが、それでも利用状況によっては手数料などコスト負担が発生します。
予算に限りがある場合、「低コストのシステム=必要十分な機能が揃っていない可能性」も考慮しなければなりません。
安価なプランでは利用できる機能やユーザー数に制限があったり、大会規模が大きくなると追加料金が必要になるケースもあります。
導入前に所属学会の必要とする機能要件を洗い出し、候補システムがそれを満たしているか、将来的な規模拡大にも対応できるかを確認することが重要です。
運用面の課題
次に運用面の課題もあります。
新しいシステムを導入すると、事務局スタッフや学会員への周知・教育が必要になります。
ITリテラシーに差がある場合、システムの使い方を覚えるまで一時的に負担が増えることも考えられます。
また、高齢の会員が多い学会ではオンライン化に抵抗感があったり、問い合わせ対応がかえって増える可能性もあります。
「ツールを導入すれば万事解決」というわけではなく、運用フローを整備し人員のスキル習得をサポートする運用設計が欠かせません。
さらに、システムトラブルが発生した際のリスクも考慮すべきです。
ネットワーク障害やサーバーダウンが起これば業務が止まってしまうため、ベンダーのサポート体制やバックアップ計画を把握しておくことが必要です。
学会運営の外部委託業者は何をしてくれるのか?
学会運営を外部委託(いわゆる学会運営代行)すると、専門業者が学会開催にまつわる様々な業務を代行してくれます。
外部委託業者、例えば学会運営を専門とする企業やイベント会社は、以下のような業務を引き受けてくれます。
企画全般のサポート
学会大会のテーマ策定やプログラム構成の立案、スケジュール作成など企画段階から支援します。
経験豊富なスタッフがいる会社であれば、過去の事例に基づいたアドバイスも受けられます。
会場選定・手配
開催地の選定から会場の予約交渉、レイアウト設計まで行います。
適切な会場や設備を提案してもらえるため、会場探しの手間が省けます。
参加募集・登録管理
参加者の募集告知、事前の参加登録受付、当日の参加者受付まで一括して管理します。
参加費の決済処理や名札の準備も代行してくれるため、煩雑な受付業務を任せられます。
予算管理・会計処理
学会開催にかかる費用見積もりから予算策定、収支管理まで担当します。
支出の管理や精算処理もプロに任せられるので、金銭管理の負担が軽減します。
広報・集客活動
学会開催の案内を学会員や関連分野に周知する広報業務も実施します。
ウェブサイトやSNSでの情報発信、スポンサー企業との調整、プレスリリース配信など集客面の支援も期待できます。
当日の運営
学会当日の受付運営、進行サポート、スタッフ配置管理、懇親会運営までトータルにサポートします。
トラブル対応やタイムキープも行い、主催者に代わって現場を仕切ってくれます。
オンライン配信対応
オンライン学会やハイブリッド開催の場合、配信用の機材設営や配信オペレーションも担います。
Zoom等の設定から配信映像のスイッチング、リハーサル運営まで専門ノウハウで対応してくれます。
記録・報告業務
学会記録映像の撮影・編集や、開催報告書の作成支援、アンケート集計など事後処理も任せられます。
これにより終了後のフォローアップまで一貫して業務を代行してもらえます。
このように、外部委託業者に依頼すれば学会開催に必要な業務をほぼ網羅的に任せることが可能です。
学会事務局や主催者は、全体の方向性決定や学術的内容の確認に集中でき、煩雑な運営業務から解放されます。
特にノウハウのない初めての形式(例えば初のオンライン開催など)でも、業者側に蓄積された知見を活かして円滑に対応してもらえるのも大きな利点です。
外部委託を利用することで、学会運営のプロの力を借りて質の高い大会を実現し、自前では難しい部分もカバーできるのです。
学会運営の外部委託のメリット・デメリット
メリット
外部委託のメリットは何と言ってもプロの知見と労力を活用できることです。
経験豊富なスタッフによるサポートで、学会運営が効率的かつスムーズに進みます。
専門業者は多数の学会開催実績を持っているため、適切な進行管理や的確なトラブル対処が期待できます。
結果として参加者や発表者の満足度向上につながり、学会の評価も高まるでしょう。
また、委託により学会役員や事務局は定型業務から解放され、より重要な企画や研究業務に時間を割けるようになります。
さらに、外部委託はニーズに応じて柔軟な範囲で依頼できるのもメリットです。
例えば全てを丸ごと任せる「トータルサポート」も可能ですし、参加登録受付だけ委託するといった部分的な利用もできます。
また、規模拡大や新企画への対応力も高く、オンライン開催やハイブリッド開催など未経験の形式でも専門業者ならすぐに実現可能です。
自前では手が届かない最新のツールやノウハウも享受できるため、学会運営のDX(デジタル化)推進にも寄与します。
デメリット
一方で外部委託にはコストがかかります。
業務範囲にもよりますが、委託料として毎月数十万円規模の費用が発生するケースもあります。
学会の財政状況によっては継続的な委託が難しいこともあるでしょう。
企画や運営の細部まで業者任せにすると、思い描いた通りの運営とならない可能性もあります。
外部スタッフとの意思疎通に時間を割く必要があったり、学会側の意図を正確に伝える調整コストも発生します。
加えて、業者選定を誤るとサービス品質にばらつきがあったり、経験不足の業者だと逆に手間が増える懸念もあります。
依頼内容と実際のサービス範囲を事前に明確化し、信頼できる実績のある業者を選ぶことが大切です。
さらに長期的に見ると、全部委託に頼りきりでは学会内部にノウハウが蓄積されないという側面もあります。
外部委託のメリットは大きいものの、費用対効果や主導権のバランスを考慮しながら活用することがポイントです。
オンライン学会・ハイブリッド学会対応で必要なこと
オンライン開催・ハイブリッド開催は上手く活用すれば会場運営の負担を減らし、人員不足の解消に役立ちます。
例えば一部セッションをオンライン化すれば現地スタッフを絞り込め、運営コストも削減できます。
しかし慣れない形態だとかえってオンライン対応のスタッフ負担が増える場合もあります。
新しい開催形式では、不慣れなうちは想定外の課題も起こり得るため、段階的に導入しノウハウを蓄積することが大切です。
必要に応じて配信のプロに協力を仰ぐなど、無理なく質を確保する手段を取りましょう。
総じて、オンライン・ハイブリッド学会対応には「通信環境」「人員体制」「双方向コミュニケーション設計」の3点が鍵となります。
通信環境
まず重要なのはICTインフラの整備です。
オンライン発表やライブ配信を円滑に行うため、高速で安定したインターネット回線と配信用の機材・ソフトウェア(マイク、カメラ、配信ツールなど)が欠かせません。
専用プラットフォームの利用やZoomウェビナーの設定、参加者への接続案内など、技術面の準備に十分な時間を割く必要があります。
人員体制
次にスタッフ体制の構築もポイントです。
オンライン配信にはテクニカルサポート要員が必要であり、現地会場とオンライン双方を同時に管理するハイブリッド開催ではスタッフの役割分担が一段と重要になります。
例えば、現地会場スタッフのほかにオンライン上の司会進行役、チャットでの質問受付担当、配信映像の切替担当などを配置しなければなりません。
事前に綿密なリハーサルを行い、通信トラブル時の対応や緊急連絡系統も決めておくことが必要です。
オンライン学会では「見えない参加者」を意識した運営が求められるため、対面以上に準備と確認が重要と言えます。
双方向コミュニケーション設計
また、ハイブリッド開催の場合は現地とオンラインの両方の参加者に配慮した設計が求められます。
現地の様子を高品質な映像と音声で配信し、オンライン参加者にも臨場感を提供すること、逆にオンライン参加者の質問を現地会場にスムーズに伝えることなど、双方向のやりとりを可能にする仕組みが必要です。
専用の配信スタジオを用意したり、質疑応答用にオンライン専用セッションを設けるなど工夫すると良いでしょう。
学会運営・準備の効率化に悩んだら
学会運営や準備の「効率化」に悩んだら、専門のサービスやツールの活用を検討してみましょう。
例えば学会運営プラットフォーム「AWARD(アワード)」は、学会事務局向けに開発された包括的なサービスで、学会運営に必要な機能をワンストップで提供しています。
AWARDには学術大会開催システムと会員管理・イベント決済システムが用意されており、演題登録から参加登録、会場でのQRコード受付まで対応したオールインワンの大会管理機能や、初期費用・月額費用0円で導入できる会員管理・会費徴収とイベント参加費決済の機能があります。
こうしたサービスを利用すれば、自前でシステムを構築することなく最新の効率化ツールを導入でき、金銭的負担を抑えつつ学会運営をスリム化できます。
特にAWARDのようにコストを抑えて導入できるサービスは、小規模な学会でも活用しやすく、必要に応じた分だけ費用を支払う成果報酬型の料金体系が魅力です。
また、学会運営者の声を取り入れて継続的に機能改善が行われているため、現場のニーズに沿った使い勝手が期待できます。
実績面でも中小規模の学会で数多く利用されており、従来比5分の1のコストで学会開催を実現した例も報告されています。
人手不足や予算不足でお困りの学会事務局であっても、こうした外部サービスを上手に活用することで、負担軽減と学会運営の質向上を両立させることが可能です。
学会の効率化方法に悩んだら、専門サービスを提供している会社に問い合わせをしてみましょう。
プロの視点からアドバイスをもらうことで、新たな解決策が見つかるかもしれません。
まとめ
学会運営・準備の「効率化」は、現代の学会事務局にとって避けて通れない課題です。
煩雑で人手のかかる業務をそのままにせず、デジタル技術の導入や外部リソースの活用によってスマートに運営していくことが、これからの学会の発展につながります。
効率化の手法としては、学会運営管理システムの導入やタスク管理ツールの活用、業務フローの見直し、人材の有効活用、そして必要に応じた専門業者への委託など様々な選択肢があります。
学会運営の効率化によって生まれた時間とリソースは、本来の目的である研究交流・知的発見の促進に振り向けましょう。
効率化は学会運営者と参加者双方にメリットをもたらすWin-Winの取り組みです。
ぜひできるところから改革を始め、持続可能で発展的な学会運営を目指していきましょう。