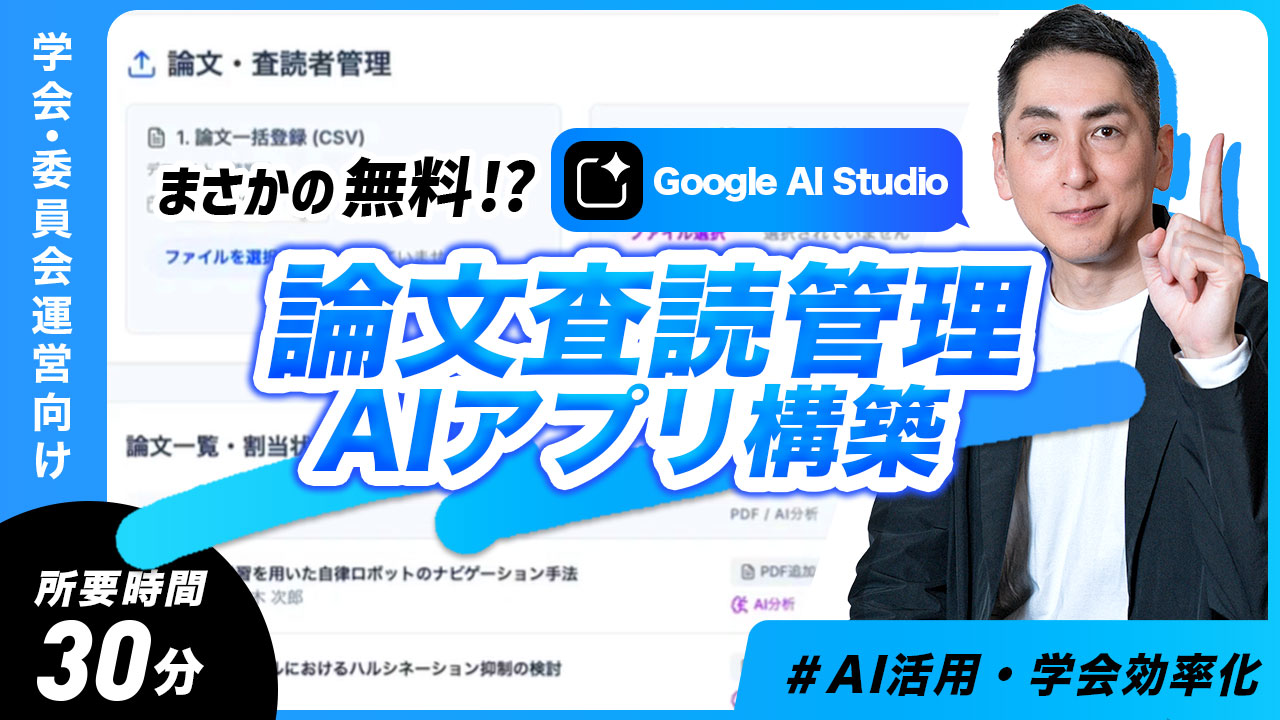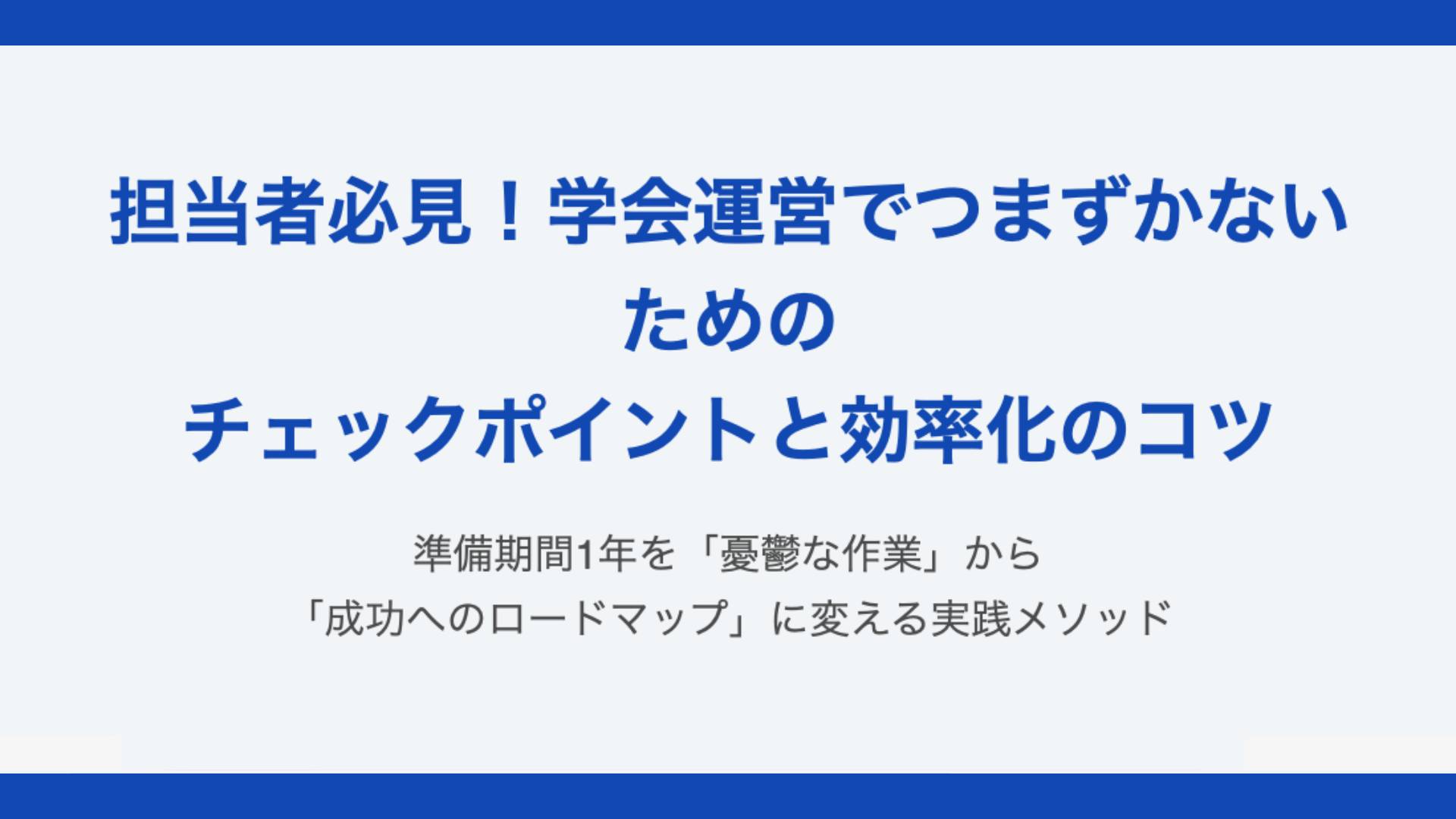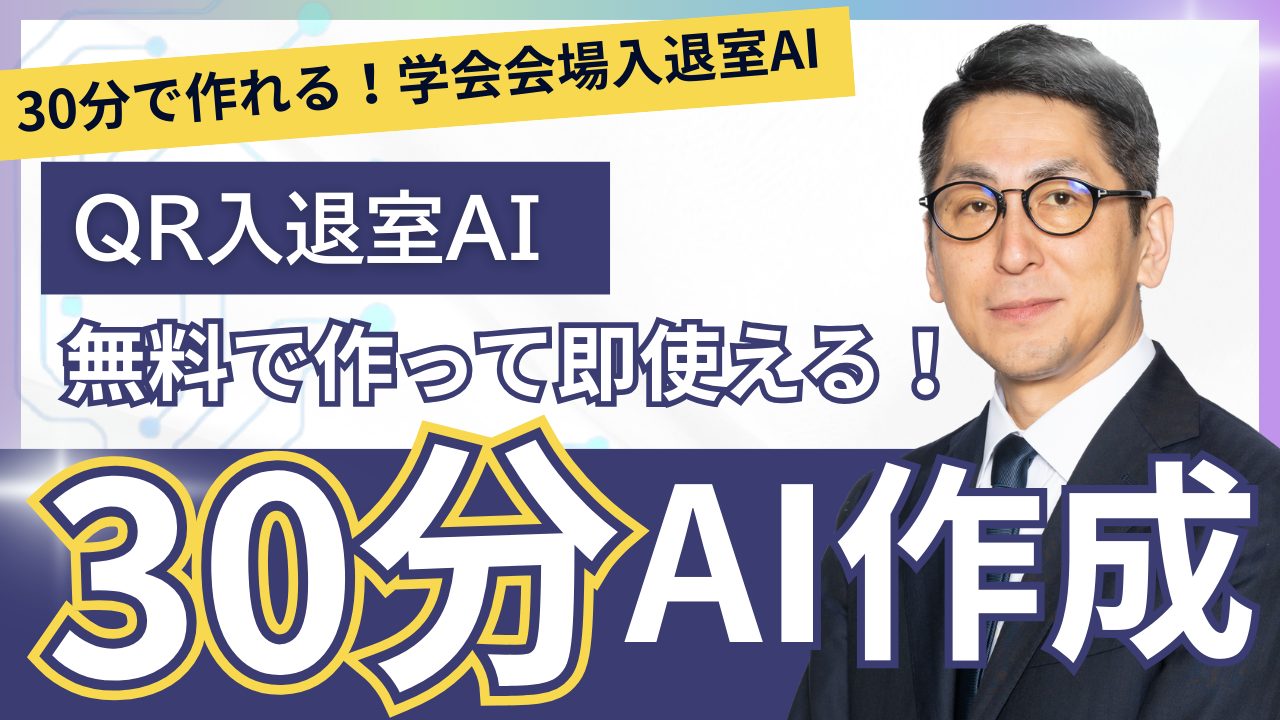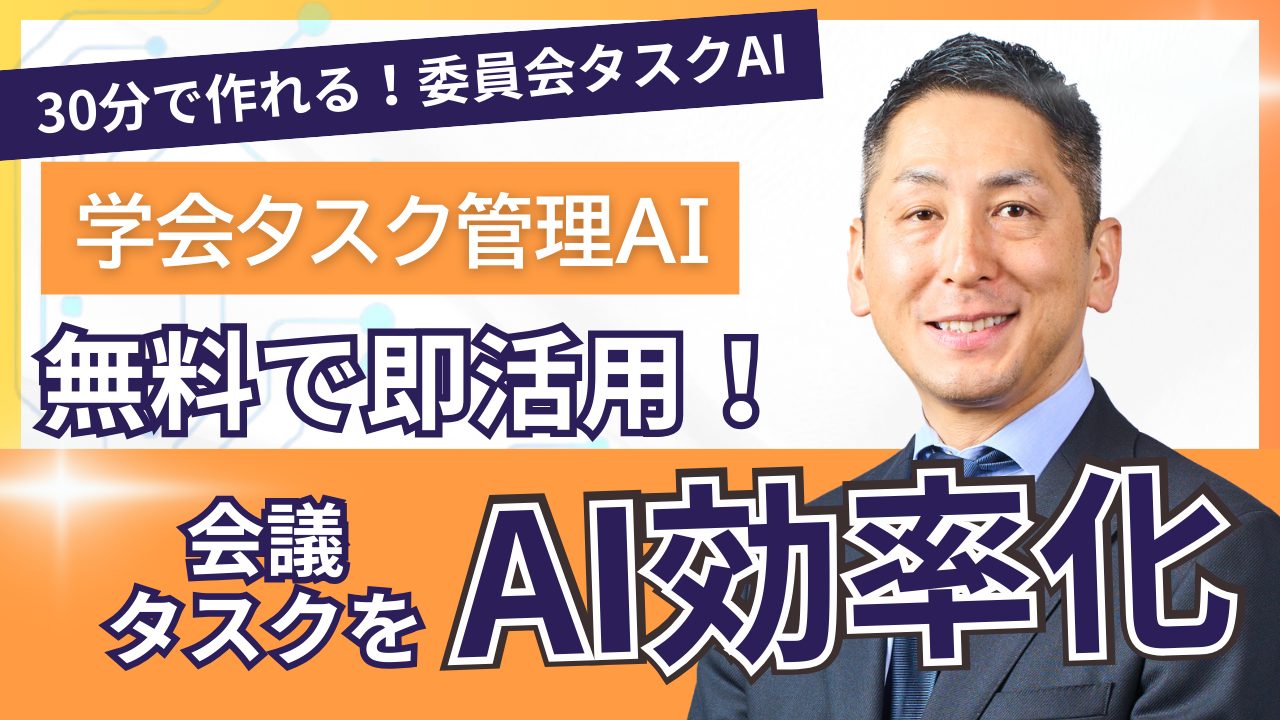еӯҰиЎ“гҒ®йӣҶз©Қең°пјҡгҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚдҪ•гҒӢпјҹгҒқгҒ®ж©ҹиғҪгҒЁеҸӮеҠ гҒ®ж„Ҹзҫ©
2025е№ҙ07жңҲ08ж—Ҙ

еӯҰе•ҸгҒ®дё–з•ҢгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒз ”з©¶иҖ…гӮ„е°Ӯй–Җ家гҒҢдә’гҒ„гҒ®зҹҘиҰӢгӮ’е…ұжңүгҒ—гҖҒиӯ°и«–гӮ’ж·ұгӮҒгӮӢе ҙгҒЁгҒ—гҒҰдёҚеҸҜж¬ гҒӘгҒ®гҒҢгҖҢеӯҰдјҡгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжғ…е ұдәӨжҸӣгҒ®е ҙгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒж–°гҒҹгҒӘз ”з©¶гҒ®иҗҢиҠҪгӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҖҒеӯҰиЎ“еҲҶйҮҺе…ЁдҪ“гҒ®зҷәеұ•гӮ’зүҪеј•гҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘеӯҳеңЁгҒ§гҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзө„з№”гҒ§гҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҙ»еӢ•гӮ’иЎҢгҒ„гҖҒеҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§дҪ•гҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгӮ’еҢ…жӢ¬зҡ„гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒӢгӮүеӯҰиЎ“гҒ®дё–з•ҢгҒ«и¶ігӮ’иёҸгҒҝе…ҘгӮҢгӮӢеӯҰз”ҹгҖҒз ”з©¶иҖ…гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«жҗәгӮҸгӮӢж–№гҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒеӯҰдјҡгҒ®жң¬иіӘгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жүӢеҠ©гҒ‘гҒЁгҒӘгӮӢжғ…е ұгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚпјҡгҒқгҒ®е®ҡзҫ©гҒЁеӨҡж§ҳжҖ§
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҖҒзү№е®ҡгҒ®еӯҰиЎ“еҲҶйҮҺгӮ„з ”з©¶й ҳеҹҹгҒ«й–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒӨдәәгҖ…гҒҢйӣҶгҒҫгӮҠгҖҒз ”з©¶жҲҗжһңгҒ®зҷәиЎЁгҖҒжғ…е ұдәӨжҸӣгҖҒзҹҘиӯҳгҒ®е…ұжңүгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰзө„з№”гҒ•гӮҢгҒҹеӯҰиЎ“еӣЈдҪ“гӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҪўж…ӢгӮ„иҰҸжЁЎгҒҜеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠгҖҒеӣҪйҡӣзҡ„гҒӘеӨ§иҰҸжЁЎеӯҰдјҡгҒӢгӮүзү№е®ҡгҒ®гғҶгғјгғһгҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹе°ҸиҰҸжЁЎгҒӘз ”з©¶дјҡгҒҫгҒ§ж§ҳгҖ…гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚеӯҰиЎ“зҷәеұ•гҒ®жӢ зӮ№
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚеӯҰиЎ“зҷәеұ•гӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҹәзӣӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒз ”з©¶иҖ…гҒҹгҒЎгҒҢжңҖж–°гҒ®зҹҘиҰӢгӮ„з ”з©¶жҲҗжһңгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҖҒжҙ»зҷәгҒӘиӯ°и«–гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰдә’гҒ„гҒ®зҗҶи§ЈгӮ’ж·ұгӮҒгӮӢе ҙгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӨжөҒгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒж–°гҒҹгҒӘз ”з©¶гғҶгғјгғһгҒҢзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҖҒе…ұеҗҢз ”з©¶гҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚиӢҘжүӢз ”з©¶иҖ…гҒ®иӮІжҲҗгҒ«гӮӮйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒ„гҖҒеҪјгӮүгҒҢиҮӘиә«гҒ®з ”究гӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҖҒзөҢйЁ“иұҠгҒӢгҒӘз ”з©¶иҖ…гҒӢгӮүгғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгӮ’еҫ—гӮӢиІҙйҮҚгҒӘж©ҹдјҡгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚе…¬зҡ„гҒӘдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮ’жҢҒгҒӨеӣЈдҪ“гӮӮ
ж—Ҙжң¬гҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬еӯҰиЎ“дјҡиӯ°гҒ«зҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҒҹеӯҰеҚ”дјҡгҒҢзҙ„2,000еӣЈдҪ“еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚе…¬зҡ„гҒӘиӘҚеҸҜгӮ„иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢеӣЈдҪ“гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒҜгҒқгҒ®еӯҰе•ҸеҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢд»ЈиЎЁзҡ„гҒӘеӯҳеңЁгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮҲгӮҠй«ҳгҒ„еӯҰиЎ“зҡ„дҝЎй јжҖ§гӮ’жҢҒгҒӨгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе…¬зҡ„гҒӘдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮ’жҢҒгҒӨгҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҖҒз ”з©¶иІ»гҒ®й…ҚеҲҶгӮ„ж”ҝзӯ–жҸҗиЁҖгҒӘгҒ©гҖҒзӨҫдјҡе…ЁдҪ“гҒёгҒ®еҪұйҹҝеҠӣгӮӮеӨ§гҒҚгҒ„еӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚиЎҢгҒҶжҙ»еӢ•гҒЁжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢж©ҹдјҡ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҖҒеӯҰиЎ“еӨ§дјҡгҒ®й–ӢеӮ¬гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢжҙ»еӢ•гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеӯҰиЎ“гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҡжңҹзҡ„гҒӘеӯҰиЎ“еӨ§дјҡгҒ®й–ӢеӮ¬
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҖҒйҖҡеёёгҖҒе№ҙгҒ«дёҖеәҰгҒҫгҒҹгҒҜиӨҮж•°еӣһгҖҒеӯҰиЎ“еӨ§дјҡгӮ’й–ӢеӮ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒз ”з©¶иҖ…гҒҢиҮӘиә«гҒ®жңҖж–°гҒ®з ”究жҲҗжһңгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҖҒиіӘз–‘еҝңзӯ”гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҒқгҒ®еҶ…е®№гӮ’ж·ұгӮҒгӮӢжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘж©ҹдјҡгҒ§гҒҷгҖӮеҸЈй ӯзҷәиЎЁгҖҒгғқгӮ№гӮҝгғјзҷәиЎЁгҖҒгӮ·гғігғқгӮёгӮҰгғ гҖҒгғҜгғјгӮҜгӮ·гғ§гғғгғ—гҒӘгҒ©гҖҒж§ҳгҖ…гҒӘеҪўејҸгҒ§з ”究зҷәиЎЁгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮиҝ‘е№ҙгҒ§гҒҜгҖҒгӮӘгғігғ©гӮӨгғігӮ„гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүеҪўејҸгҒ®й–ӢеӮ¬гӮӮеў—еҠ гҒ—гҖҒең°зҗҶзҡ„гҒӘеҲ¶зҙ„гӮ’и¶…гҒҲгҒҹеҸӮеҠ гӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӯҰиЎ“иӘҢгҒ®зҷәиЎҢгҒЁжғ…е ұжҷ®еҸҠ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҖҒжҹ»иӘӯеҲ¶еәҰгҒ®гҒӮгӮӢеӯҰиЎ“иӘҢгӮ’е®ҡжңҹзҡ„гҒ«зҷәиЎҢгҒ—гҖҒдјҡе“ЎгҒ®з ”究жҲҗжһңгӮ’е…¬иЎЁгҒҷгӮӢе ҙгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еӯҰиЎ“иӘҢгҒҜгҖҒе°Ӯй–ҖеҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжңҖж–°гҒ®и«–ж–ҮгӮ„гғ¬гғ“гғҘгғјгӮ’жҺІијүгҒ—гҖҒзҹҘиҰӢгҒ®жҷ®еҸҠгҒЁи“„з©ҚгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјгӮ„гӮҰгӮ§гғ–гӮөгӮӨгғҲгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒеӯҰдјҡгҒ®жҙ»еӢ•жғ…е ұгӮ„й–ўйҖЈгҒҷгӮӢеӯҰиЎ“гғӢгғҘгғјгӮ№гӮ’дјҡе“ЎгҒ«зҷәдҝЎгҒ—гҖҒжғ…е ұе…ұжңүгӮ’дҝғйҖІгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
з ”з©¶дјҡгғ»еҲҶ科дјҡгҒ®й–ӢеӮ¬гҒЁе°Ӯй–ҖеҲҶйҮҺгҒ®ж·ұеҢ–
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҖҒзү№е®ҡгҒ®гғҶгғјгғһгҒ«з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҒҹз ”з©¶дјҡгӮ„еҲҶ科дјҡгӮ’йҡҸжҷӮй–ӢеӮ¬гҒ—гҖҒгӮҲгӮҠе°Ӯй–Җзҡ„гҒӢгҒӨиёҸгҒҝиҫјгӮ“гҒ иӯ°и«–гҒ®е ҙгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзү№е®ҡгҒ®еҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзҹҘиҰӢгҒ®ж·ұеҢ–гӮ„гҖҒж–°гҒ—гҒ„з ”з©¶й ҳеҹҹгҒ®й–ӢжӢ“гҒҢдҝғйҖІгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
з ”з©¶еҘЁеҠұгғ»иЎЁеҪ°еҲ¶еәҰгҒЁиӢҘжүӢиӮІжҲҗ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҖҒе„Әз§ҖгҒӘз ”з©¶иҖ…гӮ„иӢҘжүӢз ”з©¶иҖ…гӮ’иЎЁеҪ°гҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз ”з©¶жҙ»еӢ•гӮ’еҘЁеҠұгҒ—гҖҒж¬Ўдё–д»ЈгҒ®з ”究иҖ…гҒ®иӮІжҲҗгҒ«еҠӣгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒз ”з©¶иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨ§гҒҚгҒӘгғўгғҒгғҷгғјгӮ·гғ§гғігҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеӯҰиЎ“е…ЁдҪ“гҒ®жҙ»жҖ§еҢ–гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚеҸӮеҠ гҒҷгӮӢж„Ҹзҫ©гҒЁеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚеҚҳгҒ«зҷәиЎЁгҒҷгӮӢе ҙгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҸӮеҠ гҒҷгӮӢз ”з©¶иҖ…гӮ„еӯҰз”ҹгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨҡеӨ§гҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖж–°гҒ®з ”究еӢ•еҗ‘гҒ®жҠҠжҸЎгҒЁзҹҘиӯҳгҒ®ж·ұеҢ–
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҒқгҒ®еҲҶйҮҺгҒ®жңҖе…Ҳз«ҜгҒ®з ”究жҲҗжһңгҒҢдёҖе ӮгҒ«дјҡгҒҷгӮӢе ҙгҒ§гҒҷгҖӮеҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиҮӘиә«гҒ®е°Ӯй–ҖеҲҶйҮҺгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжңҖж–°гҒ®з ”究еӢ•еҗ‘гӮ„жңӘзҷәиЎЁгҒ®зҹҘиҰӢгӮ’зӣҙжҺҘеҗёеҸҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮи¬ӣжј”гӮ„зҷәиЎЁгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҫ—гӮүгӮҢгӮӢзҹҘиӯҳгҒҜгҖҒиҮӘиә«гҒ®з ”究гӮ’ж·ұгӮҒгӮӢдёҠгҒ§иІҙйҮҚгҒӘжғ…е ұжәҗгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®ж§ӢзҜүгҒЁе…ұеҗҢз ”з©¶гҒ®ж©ҹдјҡ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚеҗҢгҒҳеҲҶйҮҺгҒ®з ”究иҖ…гӮ„е°Ӯй–Җ家гҒЁгҒ®ж–°гҒҹгҒӘеҮәдјҡгҒ„гҒ®е ҙгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжҙ»зҷәгҒӘиӯ°и«–гӮ„дәӨжөҒгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒеӣҪеҶ…еӨ–гҒ®з ”究иҖ…гҒЁгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҖҒе…ұеҗҢз ”з©¶гҒ®ж©ҹдјҡгӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮе°ҶжқҘгҒ®гӮӯгғЈгғӘгӮўеҪўжҲҗгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒеӯҰдјҡгҒ§гҒ®дәәи„ҲгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘиІЎз”ЈгҒЁгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иҮӘиә«гҒ®з ”究зҷәиЎЁгҒЁгғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгҒ®зҚІеҫ—
иҮӘиә«гҒ®з ”究жҲҗжһңгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҖҒзөҢйЁ“иұҠгҒӢгҒӘз ”з©¶иҖ…гҒӢгӮүзӣҙжҺҘгғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒз ”з©¶гӮ’гӮҲгӮҠжҙ—з·ҙгҒ•гҒӣгӮӢдёҠгҒ§дёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮиіӘз–‘еҝңзӯ”гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒж–°гҒҹгҒӘиҰ–зӮ№гӮ„ж”№е–„зӮ№гӮ’зҷәиҰӢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзҷәиЎЁзөҢйЁ“гӮ’з©ҚгӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гғ—гғ¬гӮјгғігғҶгғјгӮ·гғ§гғіиғҪеҠӣгҒ®еҗ‘дёҠгҒ«гӮӮгҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
з ”з©¶иҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гғўгғҒгғҷгғјгӮ·гғ§гғіеҗ‘дёҠ
д»–гҒ®з ”究иҖ…гҒ®зҷәиЎЁгҒ«и§ҰгӮҢгҒҹгӮҠгҖҒжҙ»зҷәгҒӘиӯ°и«–гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒз ”з©¶иҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гғўгғҒгғҷгғјгӮ·гғ§гғігӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮӮз№ӢгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиҮӘиә«гҒ®з ”究гҒҢеӯҰиЎ“гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ®дёӯгҒ§гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒӢгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒд»ҠеҫҢгҒ®з ”究жҙ»еӢ•гҒёгҒ®ж„Ҹж¬ІгӮ’ж–°гҒҹгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚйҒӢе–¶гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзҸҫд»ЈгҒ®иӘІйЎҢгҒЁеҠ№зҺҮеҢ–
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҒқгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒйҒӢе–¶еҒҙгҒҜеӨҡгҒҸгҒ®иӘІйЎҢгҒ«зӣҙйқўгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҒӢе–¶жҘӯеӢҷгҒ®иӨҮйӣ‘еҢ–гҒЁиІ жӢ…еў—еӨ§
дјҡе“Ўж•°гҒ®еў—еҠ гҖҒеӯҰиЎ“еӨ§дјҡгҒ®гӮӘгғігғ©гӮӨгғіеҢ–гғ»гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүеҢ–гҖҒеӨҡж§ҳгҒӘгӮӨгғҷгғігғҲгҒ®й–ӢеӮ¬гҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ®жҘӯеӢҷгҒҜе№ҙгҖ…иӨҮйӣ‘еҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӨҡгҒҸгҒ®еӯҰдјҡгҒ§гҒҜгҖҒжң¬жҘӯгӮ’жҢҒгҒӨз ”з©¶иҖ…гӮ„е…јд»»гҒ®дәӢеӢҷиҒ·е“ЎгҒҢйҒӢе–¶гӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®иІ жӢ…гҒҜеў—еӨ§гҒҷгӮӢдёҖж–№гҒ§гҒҷгҖӮ
дәәжүӢдёҚи¶ігҒЁгғҺгӮҰгғҸгӮҰгҒ®з¶ҷжүҝ
гғңгғ©гғігғҶгӮЈгӮўдё»дҪ“гӮ„е°ҸиҰҸжЁЎгҒӘеӯҰдјҡгҒ§гҒҜгҖҒж…ўжҖ§зҡ„гҒӘдәәжүӢдёҚи¶ігҒҢиӘІйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒйҒӢе–¶жӢ…еҪ“иҖ…гҒ®дәӨд»ЈгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®йҒӢе–¶гғҺгӮҰгғҸгӮҰгҒҢеҚҒеҲҶгҒ«з¶ҷжүҝгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘйҒӢе–¶гӮ’еҰЁгҒ’гӮӢиҰҒеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮігӮ№гғҲгҒ®еў—еӨ§гҒЁдәҲз®—гҒ®еҲ¶зҙ„
дјҡе ҙиІ»гҖҒж©ҹжқҗиІ»гҖҒдәә件費гҖҒеҚ°еҲ·иІ»гҒӘгҒ©гҖҒеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®иІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҸӮеҠ иІ»гӮ„еҠ©жҲҗйҮ‘гғ»еҚ”иіӣйҮ‘гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜиі„гҒ„гҒҚгӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒйҷҗгӮүгӮҢгҒҹдәҲз®—гҒ®дёӯгҒ§гҒ„гҒӢгҒ«иІ»з”ЁеҜҫеҠ№жһңгҒ®й«ҳгҒ„йҒӢе–¶гӮ’иЎҢгҒҶгҒӢгҒҢиӘІйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гҒёгҒ®еҜҫеҝң
гӮӘгғігғ©гӮӨгғій–ӢеӮ¬гӮ„гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬гҒ®жҷ®еҸҠгҒ«дјҙгҒ„гҖҒгӮҰгӮ§гғ–гӮөгӮӨгғҲз®ЎзҗҶгҖҒгӮӘгғігғ©гӮӨгғігғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒ®йҒӢз”ЁгҖҒгғҮгғјгӮҝгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒӘгҒ©гҖҒгғҮгӮёгӮҝгғ«жҠҖиЎ“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҒ©еҲҮгҒӘгғ„гғјгғ«йҒёе®ҡгӮ„дәәжқҗзўәдҝқгҒҢжҖҘеӢҷгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҒқгҒ®йҒӢе–¶гӮ’еҠ№зҺҮеҢ–гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҒёжҠһиӮў
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®иӘІйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒ—гҖҒгҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҒқгҒ®жң¬жқҘгҒ®зӣ®зҡ„гӮ’йҒ”жҲҗгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒйҒӢе–¶гҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
еӯҰдјҡйҒӢе–¶гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®е°Һе…Ҙ
дјҡе“Ўз®ЎзҗҶгҖҒдјҡиІ»еҫҙеҸҺгҖҒжј”йЎҢзҷ»йҢІгҖҒеҸӮеҠ зҷ»йҢІгҖҒжғ…е ұзҷәдҝЎгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢжҘӯеӢҷгӮ’дёҖе…ғзҡ„гҒ«з®ЎзҗҶгҒ§гҒҚгӮӢгҖҢеӯҰдјҡйҒӢе–¶гӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒ®е°Һе…ҘгҒҜгҖҒжҘӯеӢҷеҠ№зҺҮеҢ–гҒ®еј·еҠӣгҒӘжүӢж®өгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжүӢдҪңжҘӯгҒ«гӮҲгӮӢгғҹгӮ№гӮ’жёӣгӮүгҒ—гҖҒдәӢеӢҷеұҖгҒ®иІ жӢ…гӮ’еӨ§е№…гҒ«и»ҪжёӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ–йғЁе§”иЁ—пјҲеӯҰдјҡйҒӢе–¶дјҡзӨҫгғ»дәӢеӢҷеұҖд»ЈиЎҢпјүгҒ®жҙ»з”Ё
еӯҰдјҡйҒӢе–¶жҘӯеӢҷгҒ®дёҖйғЁгҒҫгҒҹгҒҜе…ЁгҒҰгӮ’е°Ӯй–ҖгҒ®еӨ–йғЁжҘӯиҖ…гҒ«е§”иЁ—гҒҷгӮӢгҖҢеӯҰдјҡйҒӢе–¶д»ЈиЎҢгҖҚгӮ„гҖҢдәӢеӢҷеұҖд»ЈиЎҢгҖҚгӮӮжңүеҠ№гҒӘйҒёжҠһиӮўгҒ§гҒҷгҖӮгғ—гғӯгғ•гӮ§гғғгӮ·гғ§гғҠгғ«гҒӘзҹҘиӯҳгҒЁзөҢйЁ“гӮ’жҢҒгҒӨжҘӯиҖ…гҒ«д»»гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйҒӢе–¶гҒ®иіӘгӮ’й«ҳгӮҒгҒӨгҒӨгҖҒдәӢеӢҷеұҖгҒ®иІ жӢ…гӮ’и»ҪжёӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘеӯҰиЎ“еӨ§дјҡгӮ„еӣҪйҡӣдјҡиӯ°гҖҒзү№е®ҡгҒ®е°Ӯй–ҖжҖ§гӮ’иҰҒгҒҷгӮӢжҘӯеӢҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒқгҒ®еҠ№жһңгҒҜйЎ•и‘—гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӘгғігғ©гӮӨгғігғ»гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬гҒ®жңҖйҒ©еҢ–
гӮӘгғігғ©гӮӨгғій–ӢеӮ¬гӮ„гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬гҒ®е°Һе…ҘгҒҜгҖҒең°зҗҶзҡ„гҒӘеҲ¶зҙ„гӮ’гҒӘгҒҸгҒ—гҖҒеҸӮеҠ иҖ…ж•°гӮ’еў—гӮ„гҒҷеҸҜиғҪжҖ§гӮ’з§ҳгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйҒ©еҲҮгҒӘгӮӘгғігғ©гӮӨгғігғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒ®йҒёе®ҡгҖҒй…ҚдҝЎжҠҖиЎ“гҒ®жҙ»з”ЁгҖҒгҒқгҒ—гҒҰзҸҫең°гҒЁгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеҸҢж–№гҒ®еҸӮеҠ иҖ…гҒёгҒ®й…Қж…®гӮ’иҖғж…®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҠ№зҺҮзҡ„гҒӢгҒӨйӯ…еҠӣзҡ„гҒӘеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒпјҡгҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚжңӘжқҘгӮ’еүөйҖ гҒҷгӮӢгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢеӯҰиЎ“зҷәиЎЁгҒ®е ҙгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒз ”з©¶иҖ…й–“гҒ®дәӨжөҒгӮ’дҝғйҖІгҒ—гҖҒж–°гҒҹгҒӘзҹҘиҰӢгӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҖҒзӨҫдјҡгҒ«иІўзҢ®гҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®йҒӢе–¶гҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®еҠҙеҠӣгҒЁе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒITгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®жҙ»з”ЁгӮ„еӨ–йғЁе§”иЁ—гҒӘгҒ©гҖҒзҸҫд»Јзҡ„гҒӘеҠ№зҺҮеҢ–жүӢжі•гӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒ§иіӘгҒ®й«ҳгҒ„еӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒҢе®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡгҒЁгҒҜгҖҚдҪ•гҒӢгӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒ—гҖҒгҒқгҒ®ж„Ҹзҫ©гӮ’жңҖеӨ§йҷҗгҒ«еј•гҒҚеҮәгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒйҒӢе–¶иҖ…гҒҜеёёгҒ«ж”№е–„гҒЁйқ©ж–°гӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеӯҰиЎ“гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ®гҒ•гӮүгҒӘгӮӢзҷәеұ•гҒЁгҖҒжңӘжқҘгҒ®з ”究жҲҗжһңгҒ®еүөеҮәгҒ«иІўзҢ®гҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ