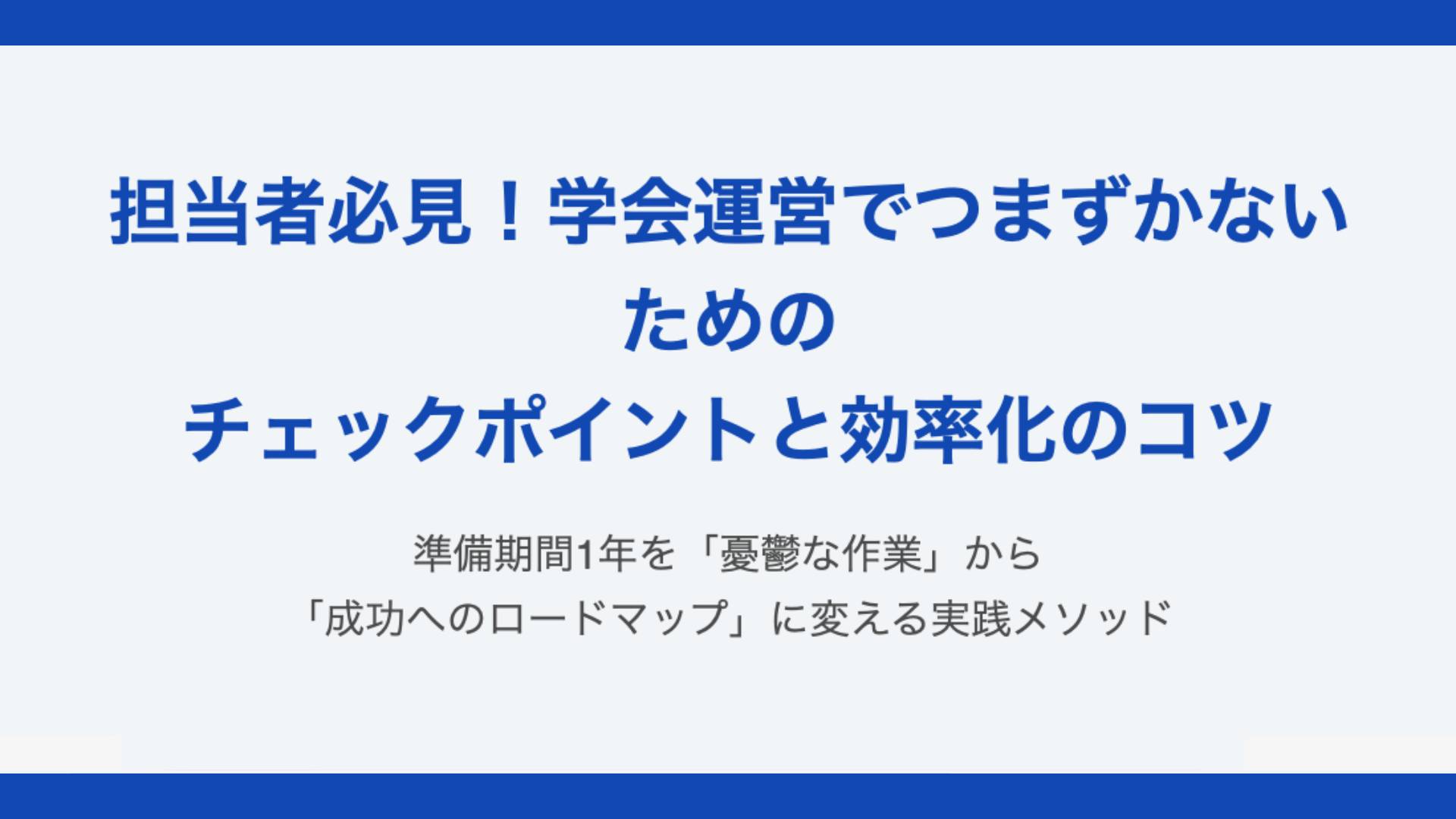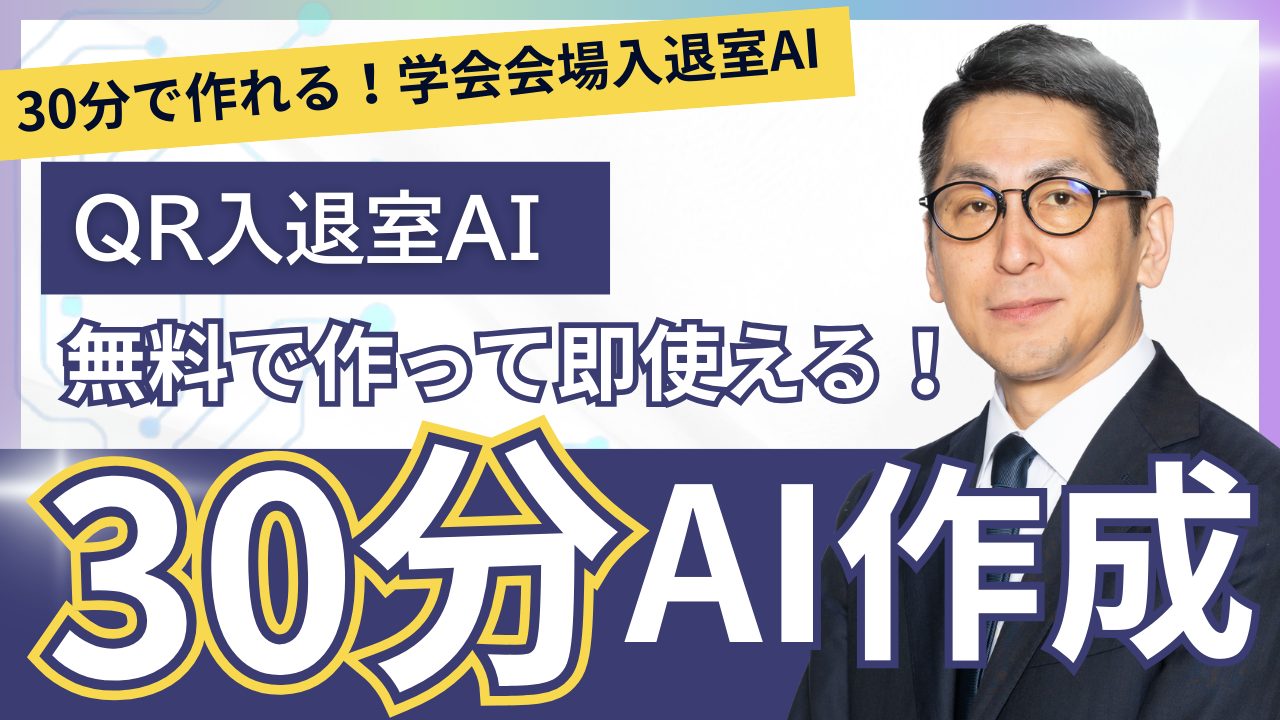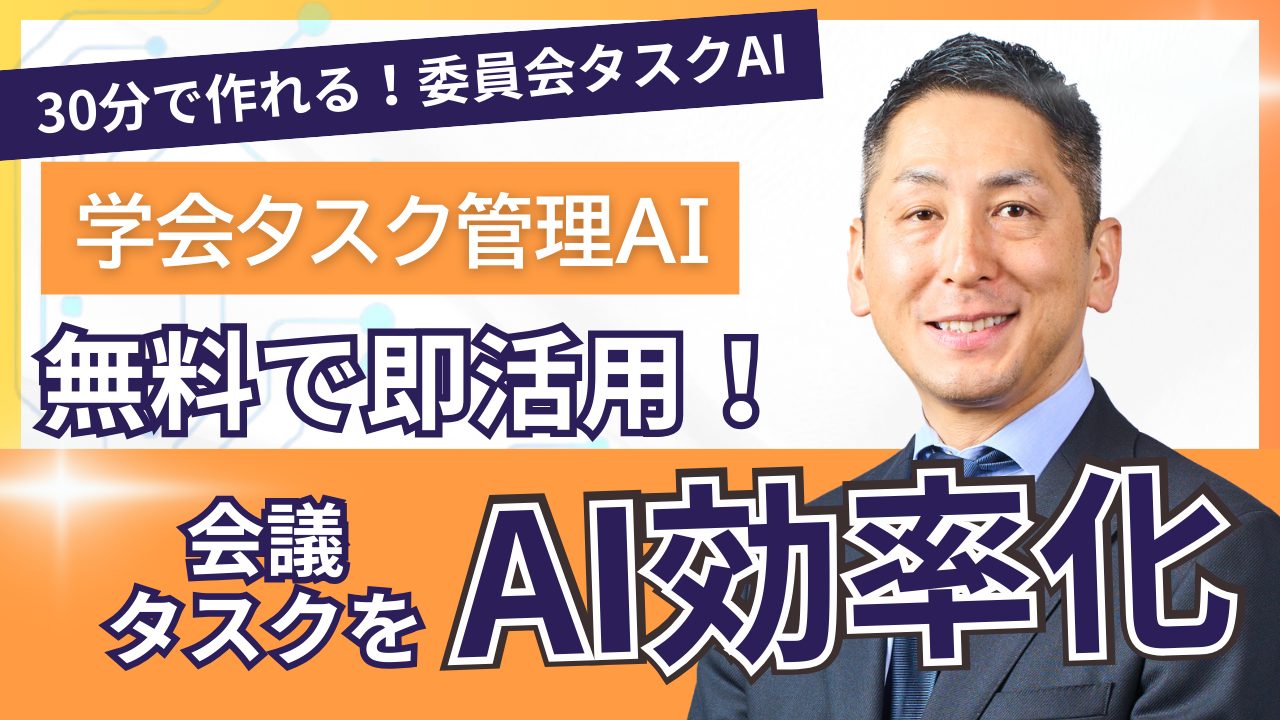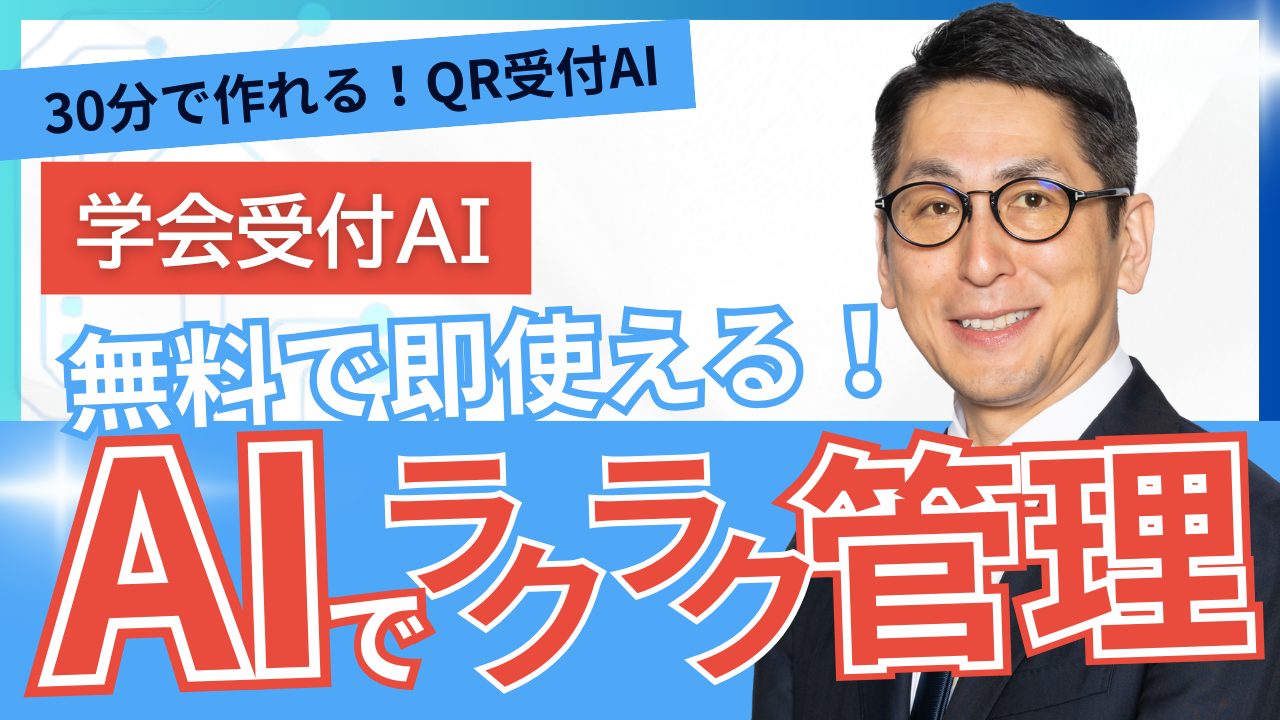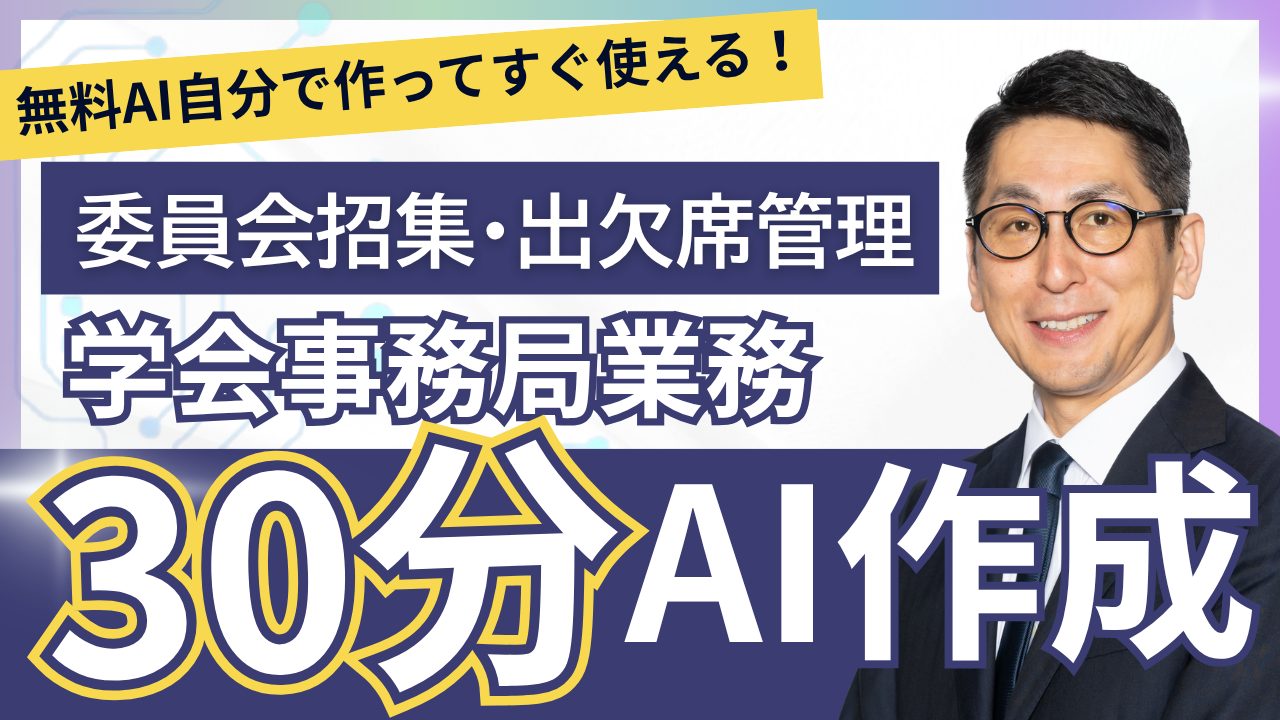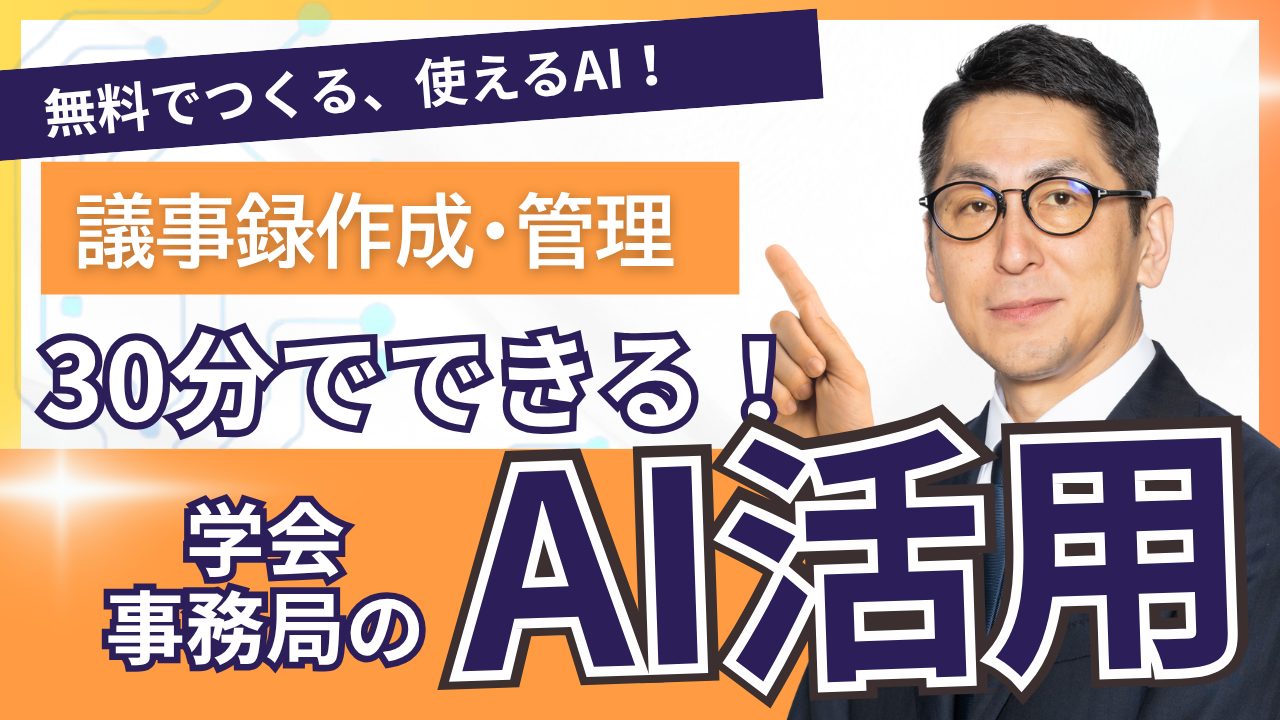ه¦è،“ه¤§ن¼ڑم‚’وˆگهٹںمپ¸ه°ژمپڈï¼په®ںè·µçڑ„مپھم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ¨مپمپ®و´»ç”¨و³•
2025ه¹´07وœˆ08و—¥

ه¦è،“ه¤§ن¼ڑمپ®é–‹ه‚¬مپ¯م€پç ”ç©¶è€…مپ«مپ¨مپ£مپ¦é‡چè¦پمپھç™؛è،¨مپ¨ن؛¤وµپمپ®ه ´مپ§مپ‚م‚‹ن¸€و–¹م€پن¸»ه‚¬è€…هپ´مپ«مپ¨مپ£مپ¦مپ¯è†¨ه¤§مپھو؛–ه‚™مپ¨éپ‹ه–¶و¥ه‹™م‚’ن¼´مپ†ه¤§ن»•ن؛‹مپ§مپ™م€‚特مپ«م€پو‹…ه½“者مپŒه¤‰م‚ڈم‚‹مپںمپ³مپ«م‚¼مƒمپ‹م‚‰و‰‹وژ¢م‚ٹمپ§و؛–ه‚™م‚’進م‚پم‚‹م‚ˆمپ†مپ§مپ¯م€پهٹ¹çژ‡م‚‚و‚ھمپڈم€پو€م‚ڈمپ¬مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«م‚’و‹›مپڈهڈ¯èƒ½و€§م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپمپ“مپ§ن¸چهڈ¯و¬ مپ¨مپھم‚‹مپ®مپŒم€پن½“ç³»هŒ–مپ•م‚Œمپںم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ§مپ™م€‚
وœ¬è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€په¦è،“ه¤§ن¼ڑمپ®ن¼پç”»مپ‹م‚‰ن؛‹ه¾Œه‡¦çگ†مپ¾مپ§مپ®هگ„و®µéڑژمپ«مپٹمپ‘م‚‹é‡چè¦پمپھم‚؟م‚¹م‚¯مپ¨مƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚’網羅مپ—مپںم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ®و§‹وˆگè¦پç´ م‚’解èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م‚’مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«و´»ç”¨مپ—م€پم‚ˆم‚ٹم‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپ§è³ھمپ®é«کمپ„ه¤§ن¼ڑéپ‹ه–¶م‚’ه®ںçڈ¾مپ§مپچم‚‹مپ®مپ‹م€په…·ن½“çڑ„مپھو‰‹é †مپ¨مƒ’مƒ³مƒˆم‚’و™‚ç³»هˆ—مپ«و²؟مپ£مپ¦مپ”ç´¹ن»‹مپ—مپ¾مپ™م€‚هˆم‚پمپ¦ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«وگ؛م‚ڈم‚‹و–¹مپ‹م‚‰çµŒé¨“者مپ¾مپ§م€پèھ°م‚‚مپŒه½¹ç«‹مپ¤ه®ںè·µçڑ„مپھوƒ…ه ±م‚’وڈگن¾›مپ—مپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ®é‡چè¦پو€§ï¼ڑمپھمپœه؟…è¦پمپ‹
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ¯م€په¦è،“ه¤§ن¼ڑم‚’وˆگهٹںمپ«ه°ژمپڈمپںم‚پمپ®ç¾…é‡ç›¤مپ§مپ‚م‚ٹم€پمپمپ®ن½œوˆگمپ¨و´»ç”¨مپ¯ه¤ڑمپڈمپ®مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚’م‚‚مپںم‚‰مپ—مپ¾مپ™م€‚
و¥ه‹™مپ®و¨™و؛–هŒ–مپ¨هٹ¹çژ‡هŒ–
ه¦è،“ه¤§ن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶مپ¯م€په¤ڑه²گمپ«م‚ڈمپںم‚‹è¤‡é›‘مپھو¥ه‹™مپ®é›†هگˆن½“مپ§مپ™م€‚م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپŒمپ‚م‚Œمپ°م€پهگ„م‚؟م‚¹م‚¯مپ®و‹…ه½“者م€پو‰‹é †م€په؟…è¦پمپھ資و–™م€پوœںé™گمپھمپ©مپŒوکژç¢؛مپ«مپھم‚ٹم€پو¥ه‹™مپ®و¨™و؛–هŒ–مپŒه›³م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پ経験مپ®وµ…مپ„و‹…ه½“者مپ§م‚‚è؟·مپ†مپ“مپ¨مپھمپڈن½œو¥م‚’進م‚پم‚‰م‚Œم‚‹مپںم‚پم€پéپ‹ه–¶ه…¨ن½“مپ®هٹ¹çژ‡مپŒه¤§ه¹…مپ«هگ‘ن¸ٹمپ—مپ¾مپ™م€‚ه±ن؛؛هŒ–م‚’éک²مپژم€پ特ه®ڑمپ®ه€‹ن؛؛مپ«و¥ه‹™مپŒé›†ن¸مپ™م‚‹مپ®م‚’éپ؟مپ‘م‚‹هٹ¹وœم‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپ®ç¶™و‰؟مپ¨ه¼•مپچ継مپژمپ®ه††و»‘هŒ–
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ¯é€ڑه¸¸م€پو•°ه¹´مپ”مپ¨مپ«و‹…ه½“者مپŒن؛¤ن»£مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپڈم€پمپمپ®éƒ½ه؛¦م€پéپژهژ»مپ®çµŒé¨“م‚„مƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپŒه¤±م‚ڈم‚ŒمپŒمپ،مپ§مپ™م€‚م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ¯م€پمپ“م‚Œمپ¾مپ§مپ®وˆگهٹںن؛‹ن¾‹م‚„و³¨و„ڈ点م€پè“„ç©چمپ•م‚Œمپںçں¥è¦‹م‚’و–‡و›¸هŒ–مپ—م€پ組織مپ®è²،産مپ¨مپ—مپ¦ه¾Œن¸–مپ«ç¶™و‰؟مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®é‡چè¦پمپھمƒ„مƒ¼مƒ«مپ§مپ™م€‚و¬،وœںو‹…ه½“者مپ¸مپ®ه¼•مپچ継مپژمپŒم‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپ«è،Œم‚ڈم‚Œم€پم‚¼مƒمپ‹م‚‰مپ®م‚¹م‚؟مƒ¼مƒˆمپ§مپ¯مپھمپڈم€پ継ç¶ڑçڑ„مپھو”¹ه–„م‚’é‡چمپمپ¦مپ„مپڈمپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ه“پè³ھهگ‘ن¸ٹمپ¨مƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†
çµ±ن¸€مپ•م‚Œمپںو‰‹é †مپ§و¥ه‹™م‚’進م‚پم‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پéپ‹ه–¶مپ®ه“پè³ھمپŒه®‰ه®ڑمپ—م€پهڈ‚هٹ 者مپ¸مپ®م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مƒ¬مƒ™مƒ«م‚’ن¸€ه®ڑمپ«ن؟مپ¤مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ«مپ¯م€پéپژهژ»مپ®مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«ن؛‹ن¾‹م‚„مپمپ®ه¯¾ç–م€پهچ±و©ںç®،çگ†ن½“هˆ¶مپھمپ©م‚‚ç››م‚ٹè¾¼م‚€مپ“مپ¨مپ§م€پن؛ˆوœںمپ›مپ¬ن؛‹و…‹مپŒç™؛ç”ںمپ—مپںه ´هگˆمپ§م‚‚è؟…é€ںمپ‹مپ¤éپ©هˆ‡مپ«ه¯¾ه؟œمپ—م€پمƒھم‚¹م‚¯م‚’وœ€ه°ڈé™گمپ«وٹ‘مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چï¼ڑé–‹ه‚¬مپ¾مپ§مپ®مƒ•م‚§مƒ¼م‚؛هˆ¥م‚؟م‚¹م‚¯
ه¦è،“ه¤§ن¼ڑمپ®é–‹ه‚¬مپ«مپ¯م€په¤§مپچمپڈهˆ†مپ‘مپ¦م€Œو؛–ه‚™و®µéڑژم€چم€Œé–‹ه‚¬ç›´ه‰چم€چم€Œé–‹ه‚¬ه½“و—¥م€چم€Œé–‰ن¼ڑه¾Œم€چمپ®مƒ•م‚§مƒ¼م‚؛مپŒمپ‚م‚ٹم€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®و®µéڑژمپ§ç•°مپھم‚‹م‚؟م‚¹م‚¯مپŒç™؛ç”ںمپ—مپ¾مپ™م€‚م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ¯م€پمپ“م‚Œم‚‰مپ®مƒ•م‚§مƒ¼م‚؛م‚’網羅مپ—م€پهگ„م‚؟م‚¹م‚¯م‚’詳細مپ«è¨کè؟°مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پéپ‹ه–¶م‚’ه††و»‘مپ«é€²م‚پم‚‹مپںم‚پمپ®وŒ‡é‡مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
و؛–ه‚™é–‹ه§‹مپ¨هں؛وœ¬è¨ˆç”»مپ®ç–ه®ڑ(開ه‚¬2ه¹´ï½1ه¹´ه‰چ)
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ®ه‡؛ç™؛点مپ¨مپھم‚‹مپ®مپŒم€پهˆوœںمپ®è¨ˆç”»و®µéڑژمپ§مپ™م€‚ ه®ںè،Œه§”ه“،ن¼ڑمپ®çµ„ç¹”مپ¨ه½¹ه‰²هˆ†و‹…مپ®وکژç¢؛هŒ–: ه®ںè،Œه§”ه“،é•·م‚’éپ¸ه‡؛مپ—م€پç·ڈه‹™م€پن¼ڑ計م€پن¼ڑه ´م€پمƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ م€په؛ƒه ±م€په؛¶ه‹™مپھمپ©م€پهگ„و‹…ه½“部門مپ®è²¬ن»»è€…مپ¨مƒ،مƒ³مƒگمƒ¼م‚’و±؛ه®ڑمپ—مپ¾مپ™م€‚مپم‚Œمپم‚Œمپ®ه½¹ه‰²مپ¨و¨©é™گم‚’وکژç¢؛مپ«ه®ڑ義مپ—م€پوŒ‡وڈ®ç³»çµ±م‚’ç¢؛ç«‹مپ—مپ¾مپ™م€‚
é–‹ه‚¬و—¥ç¨‹مƒ»ن¼ڑه ´مپ®ن»®ن؛ˆç´„:
é–‹ه‚¬و™‚وœںمپ¨ه€™è£œمپ¨مپھم‚‹ن¼ڑه ´م‚’複و•°éپ¸ه®ڑمپ—م€پن»®ن؛ˆç´„م‚’è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚ن¸»è¦پمپھن¼ڑه ´ï¼ˆمƒ،م‚¤مƒ³مƒ›مƒ¼مƒ«م€پن¼ڑè°ه®¤مپھمپ©ï¼‰مپ®è¦ڈو¨،م‚„è¨ه‚™م€پم‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپھمپ©م‚’ç¢؛èھچمپ—م€په¤§ن¼ڑمپ®ه½¢ه¼ڈ(çڈ¾هœ°م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³م€پمƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ï¼‰مپ«هگˆم‚ڈمپ›مپ¦و¤œè¨ژمپ—مپ¾مپ™م€‚
ن؛ˆç®—و،ˆمپ®ç–ه®ڑ:
هڈ‚هٹ è²»م€پهچ”賛金م€پهٹ©وˆگ金مپھمپ©مپ®هڈژه…¥è¦‹è¾¼مپ؟مپ¨م€پن¼ڑه ´è²»م€پè¨ه‚™è²»م€پن؛؛ن»¶è²»م€پهچ°هˆ·è²»مپھمپ©مپ®و”¯ه‡؛見ç©چم‚‚م‚ٹم‚’ن½œوˆگمپ—مپ¾مپ™م€‚هˆوœںو®µéڑژمپ§ه¤§مپ¾مپ‹مپھن؛ˆç®—م‚’ç«‹مپ¦م€پè²،و”؟çڑ„مپھه®ںè،Œهڈ¯èƒ½و€§م‚’è©•ن¾،مپ—مپ¾مپ™م€‚
ه…¨ن½“م‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«مپ®ç–ه®ڑ:
ن¼پç”»مپ‹م‚‰ن؛‹ه¾Œه‡¦çگ†مپ¾مپ§مپ®مƒم‚¤مƒ«م‚¹مƒˆمƒ¼مƒ³م‚’è¨ه®ڑمپ—م€پهگ„م‚؟م‚¹م‚¯مپ®ç· م‚پهˆ‡م‚ٹم‚’وکژç¢؛مپ«مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®و®µéڑژمپ§ن½œوˆگمپ™م‚‹م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ®éھ¨هگمپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒ†مƒ¼مƒمپ¨مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ مپ®ه…·ن½“هŒ–(開ه‚¬1ه¹´ه‰چ)
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ§مپ¯م€په¤§ن¼ڑمپ®éھ¨و ¼م‚’وˆگمپ™مƒ†مƒ¼مƒمپ¨مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ مپ«é–¢مپ™م‚‹é …ç›®م‚’詳è؟°مپ—مپ¾مپ™م€‚ ه¤§ن¼ڑمƒ†مƒ¼مƒمپ®و±؛ه®ڑ: ه¦è،“çڑ„مپھو„ڈ義مپ¨هڈ‚هٹ 者مپ®é–¢ه؟ƒم‚’ه¼•مپڈمƒ†مƒ¼مƒم‚’è¨ه®ڑمپ—مپ¾مپ™م€‚ه®ںè،Œه§”ه“،ن¼ڑمپ§è°è«–مپ—م€په¦ن¼ڑمپ®و–¹هگ‘و€§مپ¨هگˆè‡´مپ™م‚‹م‚‚مپ®م‚’éپ¸مپ³مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
特هˆ¥è¬›و¼”مƒ»و‹›ه¾…講و¼”者مپ®éپ¸ه®ڑمپ¨ن¾é ¼:
ه¤§ن¼ڑمپ®ç›®çژ‰مپ¨مپھم‚‹è‘—هگچمپھç ”ç©¶è€…م‚„وœ‰èک者م‚’éپ¸ه®ڑمپ—م€پو—©م‚پمپ«è¬›و¼”م‚’ن¾é ¼مپ—مپ¾مپ™م€‚
م‚·مƒ³مƒم‚¸م‚¦مƒ مƒ»مƒ¯مƒ¼م‚¯م‚·مƒ§مƒƒمƒ—مپ®ن¼پç”»:
مƒ†مƒ¼مƒمپ«و²؟مپ£مپںم‚»مƒƒم‚·مƒ§مƒ³م‚’ن¼پç”»مپ—م€پم‚ھمƒ¼م‚¬مƒٹم‚¤م‚¶مƒ¼م‚’éپ¸ه®ڑمپ—مپ¾مپ™م€‚ ç™؛è،¨ه½¢ه¼ڈمپ®و¤œè¨ژ: هڈ£é ç™؛è،¨م€پمƒم‚¹م‚؟مƒ¼ç™؛è،¨م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³ç™؛è،¨مپھمپ©م€پوœ€éپ©مپھç™؛è،¨ه½¢ه¼ڈم‚’و±؛ه®ڑمپ—مپ¾مپ™م€‚
مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ و§‹وˆگمپ®ه…·ن½“هŒ–:
هگ„م‚»مƒƒم‚·مƒ§مƒ³مپ®و™‚é–“é…چهˆ†م€پç™؛è،¨é †ه؛ڈمپھمپ©م€پ詳細مپھمƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ و،ˆم‚’ن½œوˆگمپ—مپ¾مپ™م€‚
و¼”é،Œه‹ں集مپ¨هڈ‚هٹ 登録مپ®و؛–ه‚™ï¼ˆé–‹ه‚¬10مƒ¶وœˆه‰چï½6مƒ¶وœˆه‰چ)
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ«مپ¯م€پو¼”é،Œمپ¨هڈ‚هٹ 者مپ«é–¢مپ™م‚‹é‡چè¦پمپھو‰‹é †م‚’è¨ک載مپ—مپ¾مپ™م€‚
و¼”é،Œه‹ں集è¦پé …مپ®ن½œوˆگمپ¨ه‘ٹçں¥:
ه‹ں集وœںé–“م€پç™؛è،¨ه½¢ه¼ڈم€پو–‡ه—و•°هˆ¶é™گم€پوڈگه‡؛و–¹و³•مپھمپ©م‚’وکژç¢؛مپ«مپ—مپںè¦پé …م‚’ن½œوˆگمپ—م€پم‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆم‚„مƒ،مƒ¼مƒ«مپ§ه؛ƒمپڈه‘ٹçں¥مپ—مپ¾مپ™م€‚
و¼”é،Œç™»éŒ²م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®éپ¸ه®ڑمپ¨و؛–ه‚™:
م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ§و¼”é،Œم‚’هڈ—مپ‘ن»کمپ‘م‚‹مپںم‚پمپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’éپ¸ه®ڑمپ—م€پè¨ه®ڑم‚’è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚
وں»èھ者مپ®éپ¸ه®ڑمپ¨وں»èھن½“هˆ¶مپ®و§‹ç¯‰:
و¼”é،Œمپ®ه°‚é–€هˆ†é‡ژمپ«هگˆم‚ڈمپ›مپ¦وں»èھ者م‚’éپ¸ه®ڑمپ—م€پوں»èھمƒ—مƒم‚»م‚¹مپ¨هں؛و؛–م‚’وکژç¢؛مپ«مپ—مپ¾مپ™م€‚
هڈ‚هٹ 登録è¦پé …مپ®ن½œوˆگمپ¨ه‘ٹçں¥:
هڈ‚هٹ è²»م€پ登録وœںé–“م€پو”¯و‰•مپ„و–¹و³•مپھمپ©م‚’è¨ک載مپ—مپںè¦پé …م‚’ن½œوˆگمپ—م€پم‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆمپ§ه‘ٹçں¥مپ—مپ¾مپ™م€‚
هڈ‚هٹ 登録مƒ»و±؛و¸ˆم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®éپ¸ه®ڑمپ¨و؛–ه‚™:
م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ§هڈ‚هٹ 登録مپ¨و±؛و¸ˆم‚’è،Œمپ†مپںم‚پمپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’و؛–ه‚™مپ—مپ¾مپ™م€‚م‚¯مƒ¬م‚¸مƒƒمƒˆم‚«مƒ¼مƒ‰و±؛و¸ˆم‚„éٹ€è،ŒوŒ¯è¾¼مپھمپ©م€په¤ڑو§کمپھو±؛و¸ˆو–¹و³•مپ«ه¯¾ه؟œمپ§مپچم‚‹م‚‚مپ®مپŒوœ›مپ¾مپ—مپ„مپ§مپ™م€‚
و؛–ه‚™مپ®وœ¬و ¼هŒ–مپ¨ه؛ƒه ±ï¼ˆé–‹ه‚¬6مƒ¶وœˆه‰چï½3مƒ¶وœˆه‰چ)
مپ“مپ®و™‚وœںمپ¯م€پم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ«و²؟مپ£مپ¦ه®ںه‹™çڑ„مپھو؛–ه‚™م‚’وœ¬و ¼هŒ–مپ•مپ›م‚‹مƒ•م‚§مƒ¼م‚؛مپ§مپ™م€‚
وٹ„録集مƒ»مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ 集مپ®و؛–ه‚™:
وژ،وٹمپ•م‚Œمپںو¼”é،Œمپ®وٹ„録م‚’集م‚پم€پ編集مƒ»و ،و£م‚’è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚مƒ¬م‚¤م‚¢م‚¦مƒˆم‚’و±؛ه®ڑمپ—م€پهچ°هˆ·و¥è€…م‚’éپ¸ه®ڑمپ—مپ¾مپ™م€‚
م‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆمپ®ه……ه®ںمپ¨وƒ…ه ±و›´و–°:
مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ 詳細م€پن؛¤é€ڑم‚¢م‚¯م‚»م‚¹م€په®؟و³ٹوƒ…ه ±مپھمپ©م€پهڈ‚هٹ 者مپŒه؟…è¦پمپ¨مپ™م‚‹وƒ…ه ±م‚’م‚؟م‚¤مƒ مƒھمƒ¼مپ«و›´و–°مپ—مپ¾مپ™م€‚
ن¼ڑه ´è¨ه–¶مƒ»ه‚™ه“پو‰‹é…چ:
هڈ—ن»کم€پç™؛è،¨ن¼ڑه ´م€پن¼‘و†©م‚¹مƒڑمƒ¼م‚¹مپھمپ©مپ®مƒ¬م‚¤م‚¢م‚¦مƒˆم‚’و¤œè¨ژمپ—م€په؟…è¦پمپھه‚™ه“پ(وœ؛م€پو¤…هگم€پéں³éں؟م€پوک هƒڈو©ںوگمپھمپ©ï¼‰م‚’و‰‹é…چمپ—مپ¾مپ™م€‚م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³é…چن؟،مپ«ه؟…è¦پمپھو©ںوگم‚‚هگ«مپ¾م‚Œمپ¾مپ™م€‚
م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•ن½“هˆ¶مپ®و§‹ç¯‰:
ه½“و—¥éپ‹ه–¶مپ«ه؟…è¦پمپھم‚¹م‚؟مƒƒمƒ•ï¼ˆهڈ—ن»کم€پن¼ڑه ´و،ˆه†…م€پم‚؟م‚¤مƒ م‚مƒ¼مƒ‘مƒ¼م€پوٹ€è،“م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپھمپ©ï¼‰م‚’ç¢؛ن؟مپ—م€په½¹ه‰²هˆ†و‹…م‚’و±؛ه®ڑمپ—مپ¾مپ™م€‚
هچ±و©ںç®،çگ†è¨ˆç”»مپ®ç–ه®ڑ:
è‡ھ然çپ½ه®³م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«م€پمƒ‘مƒ³مƒ‡مƒںمƒƒم‚¯مپھمپ©م€پوƒ³ه®ڑمپ•م‚Œم‚‹مƒھم‚¹م‚¯مپ«ه¯¾مپ™م‚‹ه¯¾ه؟œè¨ˆç”»م‚’ç–ه®ڑمپ—م€پم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ«وکژè¨کمپ—مپ¾مپ™م€‚
وœ€çµ‚و؛–ه‚™مپ¨é–‹ه‚¬ç›´ه‰چ(開ه‚¬2مƒ¶وœˆه‰چï½2週間ه‰چ)
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ®وœ€çµ‚مƒپم‚§مƒƒم‚¯مپ¨م€پé–‹ه‚¬مپ«هگ‘مپ‘مپںوœ€çµ‚èھ؟و•´م‚’è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚
وœ€çµ‚مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ مپ®ç¢؛ه®ڑمپ¨é…چه¸ƒ:
ه…¨مپ¦مپ®èھ؟و•´م‚’終مپˆم€پç¢؛ه®ڑمپ—مپںمƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ م‚’هڈ‚هٹ 者مپ«é…چه¸ƒمپ—مپ¾مپ™م€‚
ç™؛è،¨è³‡و–™مپ®ن؛‹ه‰چوڈگه‡؛مپ¨ç¢؛èھچ:
ç™؛è،¨è€…مپ«ه¯¾مپ—م€پوœںو—¥مپ¾مپ§مپ«ç™؛è،¨è³‡و–™م‚’وڈگه‡؛مپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپ„م€په‹•ن½œç¢؛èھچم‚’è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚
ه½“و—¥مپ®م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•ç ”ن؟®مپ¨مƒھمƒڈمƒ¼م‚µمƒ«:
ه…¨م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ§م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چم‚’ه…±وœ‰مپ—م€په½¹ه‰²مپ«ه؟œمپکمپںç ”ن؟®مپ¨م€پن¼ڑه ´مپ§مپ®ç·ڈهگˆمƒھمƒڈمƒ¼م‚µمƒ«م‚’ه®ںو–½مپ—مپ¾مپ™م€‚特مپ«م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³é…چن؟،م‚’هگ«م‚€ه ´هگˆمپ¯م€په؟µه…¥م‚ٹمپھمƒ†م‚¹مƒˆمپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚
وœ€çµ‚و،ˆه†…مƒ»مƒھمƒم‚¤مƒ³مƒ€مƒ¼مپ®é€پن؟،:
هڈ‚هٹ 者مپ«ه¯¾مپ—م€پن؛¤é€ڑو،ˆه†…م€پوŒپمپ،物م€پو³¨و„ڈن؛‹é …مپھمپ©م‚’مپ¾مپ¨م‚پمپںوœ€çµ‚و،ˆه†…م‚’é€پن؟،مپ—مپ¾مپ™م€‚ هڈ—ن»ک資و–™مپ®و؛–ه‚™: هڈ‚هٹ 者هگچç°؟م€پهگچوœم€پ資و–™م€پé کهڈژو›¸مپھمپ©م‚’و؛–ه‚™مپ—مپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چï¼ڑé–‹ه‚¬ه½“و—¥مپ¨é–‰ن¼ڑه¾Œمپ®م‚؟م‚¹م‚¯
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ¯م€پé–‹ه‚¬ه½“و—¥مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پé–‰ن¼ڑه¾Œم‚‚é‡چè¦پمپھه½¹ه‰²م‚’وœمپںمپ—مپ¾مپ™م€‚
é–‹ه‚¬ه½“و—¥ï¼ڑه††و»‘مپھéپ‹ه–¶مپ®ه®ںو–½
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ¯م€په½“و—¥مپ®و··ن¹±م‚’éک²مپژم€پم‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپھéپ‹ه–¶م‚’ه®ںçڈ¾مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®è،Œه‹•وŒ‡é‡مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
هڈ—ن»کو¥ه‹™مپ¨هڈ‚هٹ 者èھکه°ژ:
هڈ‚هٹ 者مپ®هڈ—ن»کم€پهگچوœمƒ»è³‡و–™مپ®é…چه¸ƒم€پن¼ڑه ´و،ˆه†…م‚’م‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپ«è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚
م‚»مƒƒم‚·مƒ§مƒ³مپ®é€²è،Œç®،çگ†:
هگ„ن¼ڑه ´مپ§م‚؟م‚¤مƒ م‚مƒ¼مƒ‘مƒ¼مپŒو™‚é–“م‚’ç®،çگ†مپ—م€په††و»‘مپھم‚»مƒƒم‚·مƒ§مƒ³é€²è،Œم‚’م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ—مپ¾مپ™م€‚ه؛§é•·م‚„ç™؛è،¨è€…مپ¨مپ®é€£وگ؛م‚‚é‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
و©ںوگمƒˆمƒ©مƒ–مƒ«ه¯¾ه؟œ:
éں³éں؟م€پوک هƒڈم€پم‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆوژ¥ç¶ڑمپھمپ©م€پو©ںوگمƒˆمƒ©مƒ–مƒ«ç™؛ç”ںو™‚مپ«مپ¯è؟…é€ںمپ«ه¯¾ه؟œمپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†م€پوٹ€è،“م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ¨é€£وگ؛مپ—مپ¾مپ™م€‚
è³ھç–‘ه؟œç”مپ®م‚µمƒمƒ¼مƒˆ:
م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ¨çڈ¾هœ°مپ‹م‚‰مپ®è³ھه•ڈم‚’éپ©هˆ‡مپ«وچŒمپچم€پهڈŒو–¹هگ‘مپ®م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³م‚’ن؟ƒمپ—مپ¾مپ™م€‚
ن¼‘و†©مƒ»و‡‡è¦ھن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶:
هڈ‚هٹ 者مپŒه؟«éپ©مپ«éپژمپ”مپ›م‚‹م‚ˆمپ†م€پن¼‘و†©و™‚é–“مپ®و،ˆه†…م‚„و‡‡è¦ھن¼ڑمپ®é€²è،Œم‚’م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ—مپ¾مپ™م€‚
é–‰ن¼ڑه¾Œï¼ڑه ±ه‘ٹمپ¨و¬،مپ¸مپ®ç¶™و‰؟
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ¯م€پو¬،ه›مپ®é–‹ه‚¬مپ«ç¹‹مپŒم‚‹é‡چè¦پمپھوƒ…ه ±م‚’è¨ک録مƒ»و•´çگ†مپ™م‚‹ه½¹ه‰²م‚‚و‹…مپ„مپ¾مپ™م€‚
م‚¢مƒ³م‚±مƒ¼مƒˆمپ®ه®ںو–½مپ¨هˆ†وگ:
هڈ‚هٹ 者مپ‹م‚‰مپ®مƒ•م‚£مƒ¼مƒ‰مƒگمƒƒم‚¯م‚’هڈژ集مپ—م€پéپ‹ه–¶مپ®è‰¯مپ‹مپ£مپں点م‚„و”¹ه–„点م‚’هˆ†وگمپ—مپ¾مپ™م€‚
ن¼ڑ計ه‡¦çگ†مپ¨هڈژو”¯ه ±ه‘ٹو›¸مپ®ن½œوˆگ:
ه¤§ن¼ڑمپ§ç™؛ç”ںمپ—مپںه…¨مپ¦مپ®هڈژه…¥مپ¨و”¯ه‡؛م‚’مپ¾مپ¨م‚پم€پو£ç¢؛مپھهڈژو”¯ه ±ه‘ٹو›¸م‚’ن½œوˆگمپ—مپ¾مپ™م€‚
وœ€çµ‚ه ±ه‘ٹو›¸مپ®ن½œوˆگمپ¨ه…±وœ‰:
هڈ‚هٹ 者و•°م€پç™؛è،¨و•°م€پم‚¢مƒ³م‚±مƒ¼مƒˆçµگوœم€پهڈژو”¯و±؛ç®—مپھمپ©م‚’ç››م‚ٹè¾¼م‚“مپ وœ€çµ‚ه ±ه‘ٹو›¸م‚’ن½œوˆگمپ—م€پé–¢ن؟‚者مپ«ه…±وœ‰مپ—مپ¾مپ™م€‚
مƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپ®و•´çگ†مپ¨و¬،وœںمپ¸مپ®ه¼•مپچ継مپژ:
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چم‚’و›´و–°مپ—م€پو¬،وœںه®ںè،Œه§”ه“،ن¼ڑمپ¸مپ®ه¼•مپچ継مپژ資و–™مپ¨مپ—مپ¦و´»ç”¨مپ—مپ¾مپ™م€‚وˆگهٹںن؛‹ن¾‹م‚„èھ²é،Œç‚¹م€پو”¹ه–„وڈگو،ˆمپھمپ©م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«è¨کè؟°مپ—م€پهڈ£é مپ§مپ®ه¼•ç¶™مپژم‚‚è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚
م‚¢مƒ¼م‚«م‚¤مƒ–مپ®ن½œوˆگمپ¨ه…¬é–‹:
講و¼”録画م€پç™؛è،¨è³‡و–™م€په†™çœںمپھمپ©مپ®مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’و•´çگ†مپ—م€په؟…è¦پمپ«ه؟œمپکمپ¦م‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆمپھمپ©مپ§ه…¬é–‹مپ—مپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ®هٹ¹وœم‚’وœ€ه¤§هŒ–مپ™م‚‹مƒ’مƒ³مƒˆ
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چم‚’م‚ˆم‚ٹوœ‰هٹ¹و´»ç”¨مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پمپ„مپڈمپ¤مپ‹مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ه®ڑوœںçڑ„مپھ見直مپ—مپ¨و›´و–°
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه½¢ه¼ڈم‚„مƒ„مƒ¼مƒ«مپ¯ه¸¸مپ«é€²هŒ–مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپمپ®مپںم‚پم€پم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چم‚‚ن¸€ه؛¦ن½œوˆگمپ—مپںم‚‰çµ‚م‚ڈم‚ٹمپ§مپ¯مپھمپڈم€په¤§ن¼ڑمپ”مپ¨مپ«ه†…ه®¹م‚’وŒ¯م‚ٹè؟”م‚ٹم€پو”¹ه–„点م‚’هڈچوک مپ•مپ›مپ¦ه®ڑوœںçڑ„مپ«و›´و–°مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚وœ€و–°مپ®çٹ¶و³پمپ«هگˆم‚ڈمپ›مپ¦م€په¸¸مپ«وœ€éپ©هŒ–م‚’ه›³م‚ٹمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«هŒ–مپ¨ه…±وœ‰مپ®ه®¹وک“مپ•
ç´™مƒ™مƒ¼م‚¹مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پGoogle Driveم‚„Microsoft SharePointمپھمپ©مپ®م‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’و´»ç”¨مپ—مپ¦م€پم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چم‚’مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«هŒ–مپ—م€پé–¢ن؟‚者間مپ§ه®¹وک“مپ«ه…±وœ‰مپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€په¸¸مپ«وœ€و–°ç‰ˆمپ«م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ§مپچم€په…±هگŒç·¨é›†م‚‚هڈ¯èƒ½مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
وں”è»ںمپھéپ‹ç”¨مپ¨è‡¨و©ںه؟œه¤‰مپھه¯¾ه؟œ
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ¯مپ‚مپڈمپ¾مپ§وŒ‡é‡مپ§مپ‚م‚ٹم€په…¨مپ¦م‚’هژ³ه¯†مپ«ç¸›م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚ن؛ˆوœںمپ›مپ¬ن؛‹و…‹م‚„ه€‹هˆ¥مپ®çٹ¶و³پمپ«ه؟œمپکمپ¦م€پ臨و©ںه؟œه¤‰مپھه¯¾ه؟œمپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œم‚‹ه ´é¢م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«مپ«ه›؛هں·مپ—مپ™مپژمپڑم€پçٹ¶و³پمپ«ه؟œمپکمپںهˆ¤و–مپŒمپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپھوں”è»ںمپھéپ‹ç”¨م‚’ه؟ƒمپŒمپ‘مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
مپ¾مپ¨م‚پï¼ڑم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپŒو”¯مپˆم‚‹وŒپç¶ڑهڈ¯èƒ½مپھه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ¯م€په¦è،“ه¤§ن¼ڑمپ®ه††و»‘مپھé–‹ه‚¬مپ¨م€پéپ‹ه–¶و¥ه‹™مپ®هٹ¹çژ‡هŒ–م€پمپمپ—مپ¦مƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپ®ç¢؛ه®ںمپھ継و‰؟م‚’هڈ¯èƒ½مپ«مپ™م‚‹ن¸ٹمپ§ن¸چهڈ¯و¬ مپھمƒ„مƒ¼مƒ«مپ§مپ™م€‚ن¼پç”»مپ‹م‚‰ن؛‹ه¾Œه‡¦çگ†مپ¾مپ§مپ®هگ„مƒ•م‚§مƒ¼م‚؛مپ§ç™؛ç”ںمپ™م‚‹ه¤ڑه²گمپ«م‚ڈمپںم‚‹م‚؟م‚¹م‚¯م‚’ن½“ç³»هŒ–مپ—م€پو¨™و؛–هŒ–مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پéپ‹ه–¶و‹…ه½“者مپ®è² و‹…م‚’軽و¸›مپ—م€په¦ن¼ڑه…¨ن½“مپ®éپ‹ه–¶ه“پè³ھم‚’é«کم‚پمپ¾مپ™م€‚
çڈ¾ن»£مپ®ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ¯م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هŒ–م‚„مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰هŒ–مپ®é€²ه±•مپ«م‚ˆم‚ٹم€پن¸€ه±¤è¤‡é›‘مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ†مپ—مپںه¤‰هŒ–مپ«ه¯¾ه؟œمپ™م‚‹مپںم‚پمپ«م‚‚م€په®ں用çڑ„مپھم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چمپ®ن½œوˆگمپ¨و´»ç”¨مپ¯م€په¦ن¼ڑمپ®وŒپç¶ڑçڑ„مپھç™؛ه±•م‚’و”¯مپˆم‚‹é‡چè¦پمپھهں؛盤مپ¨مپھم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚وœ¬è¨کن؛‹مپ®ه†…ه®¹م‚’هڈ‚考مپ«م€پè²´ه¦ن¼ڑ独è‡ھمپ®م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م€چم‚’ن½œوˆگمپ—م€په¦è،“م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹مƒ†م‚£مپ®مپ•م‚‰مپھم‚‹و´»و€§هŒ–مپ«è²¢çŒ®مپ—مپ¦مپڈمپ مپ•مپ„م€‚