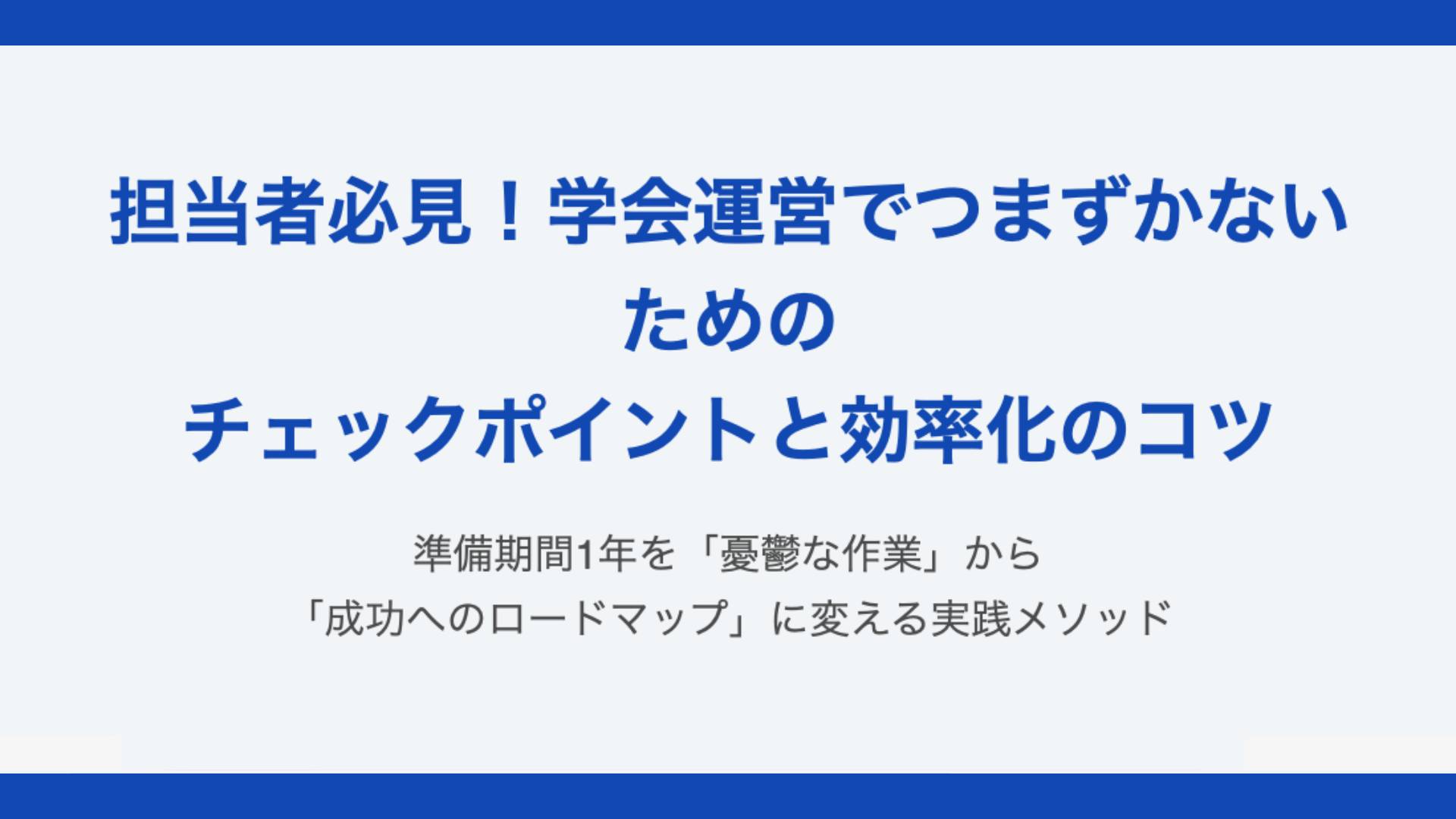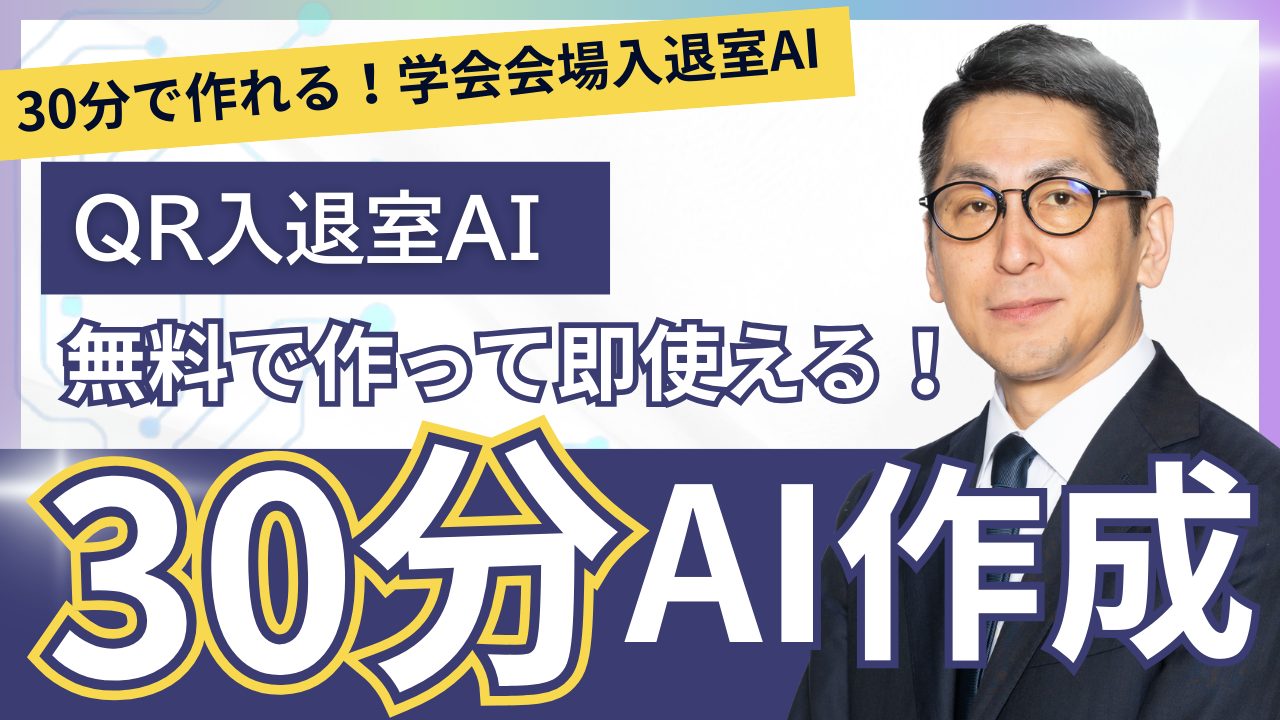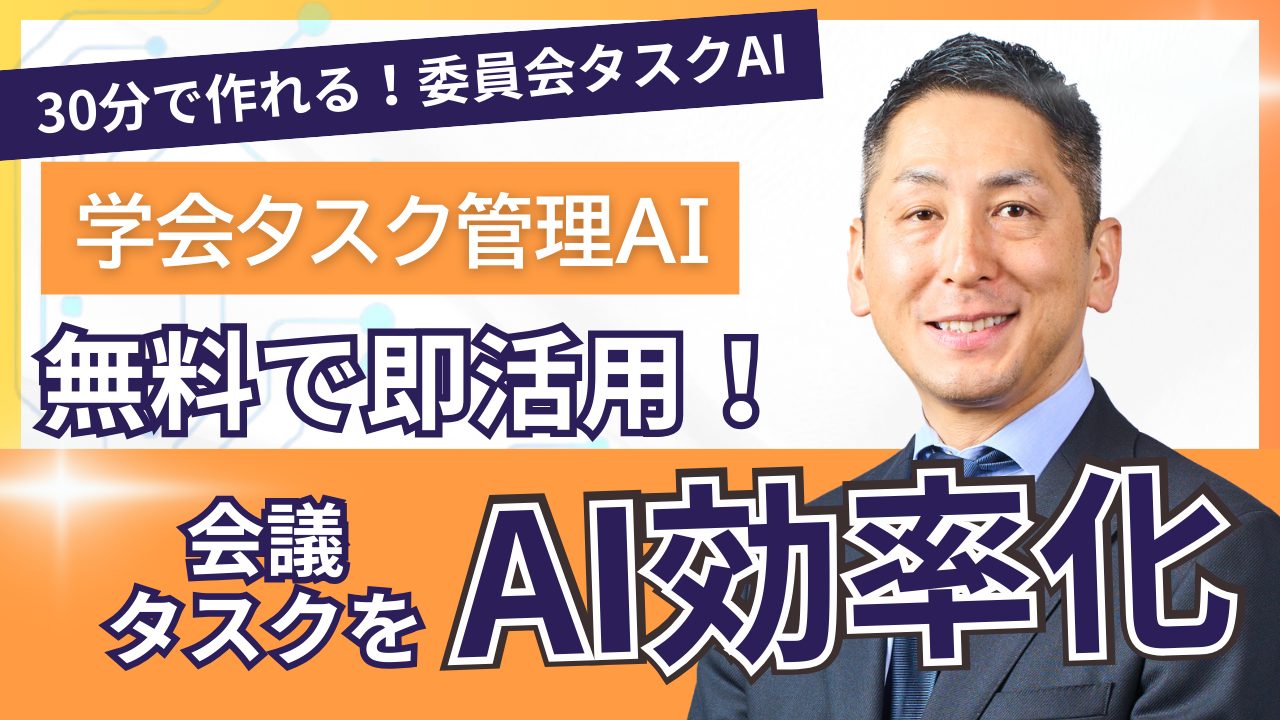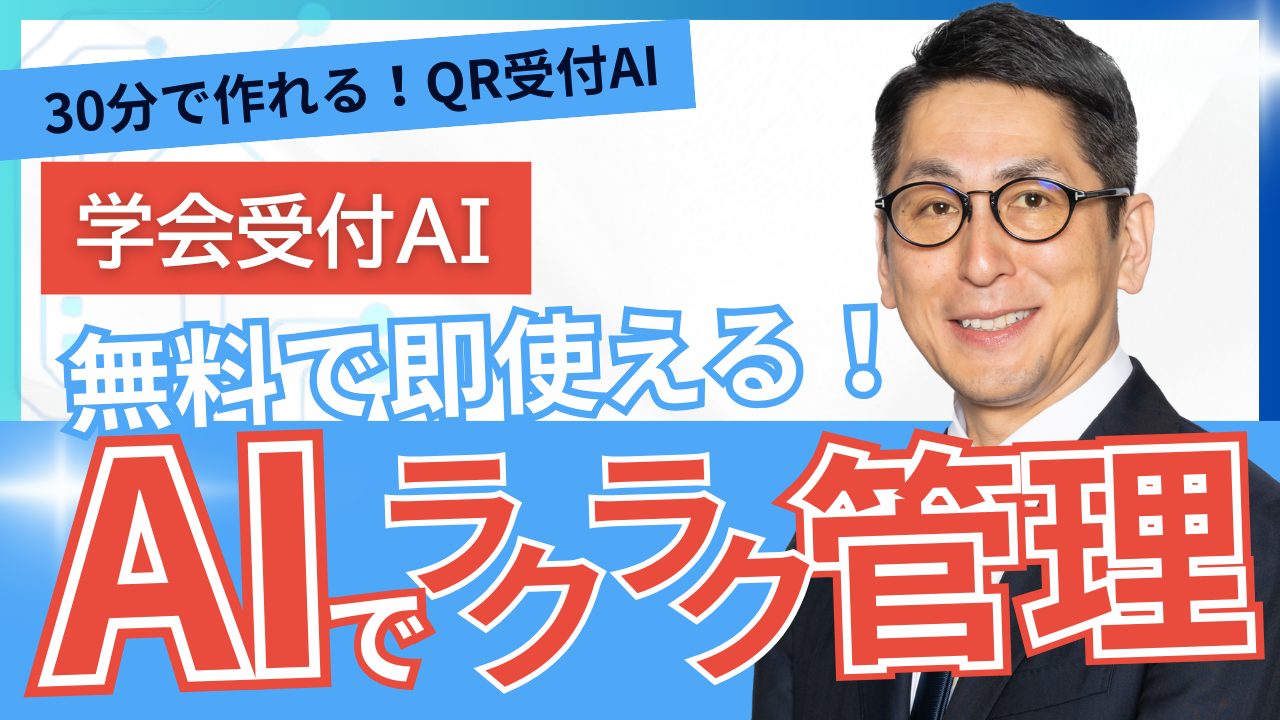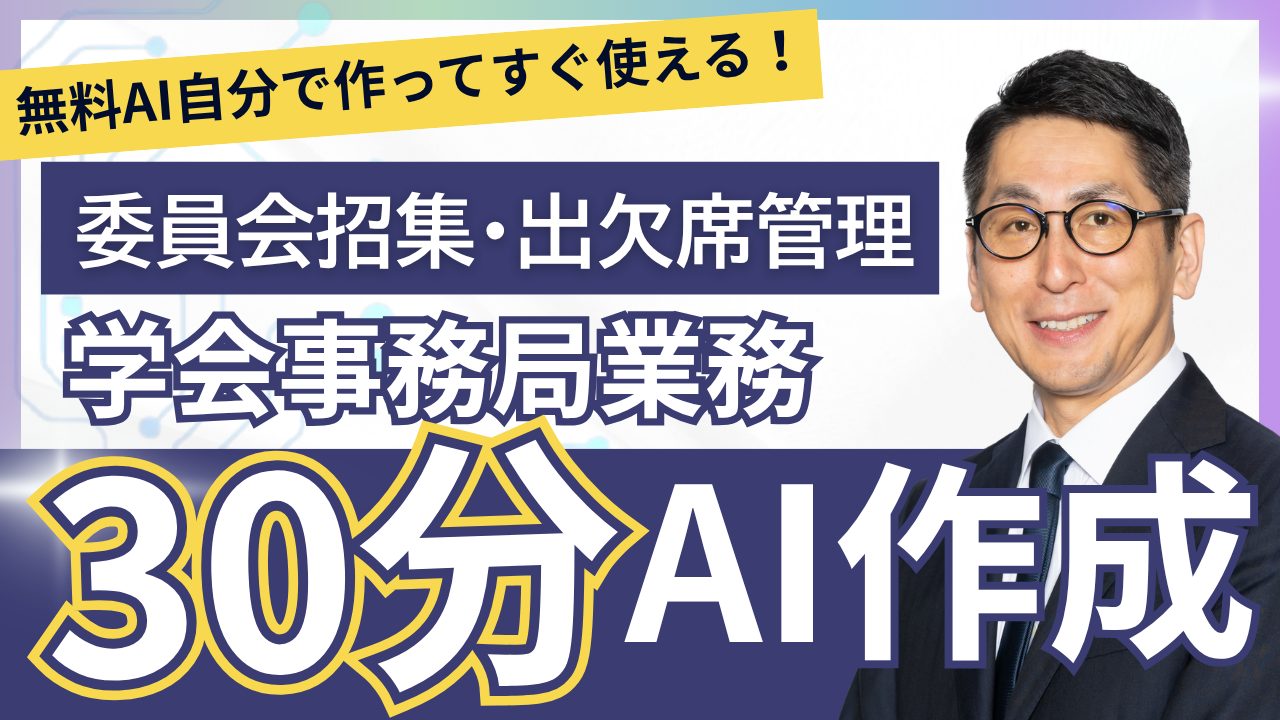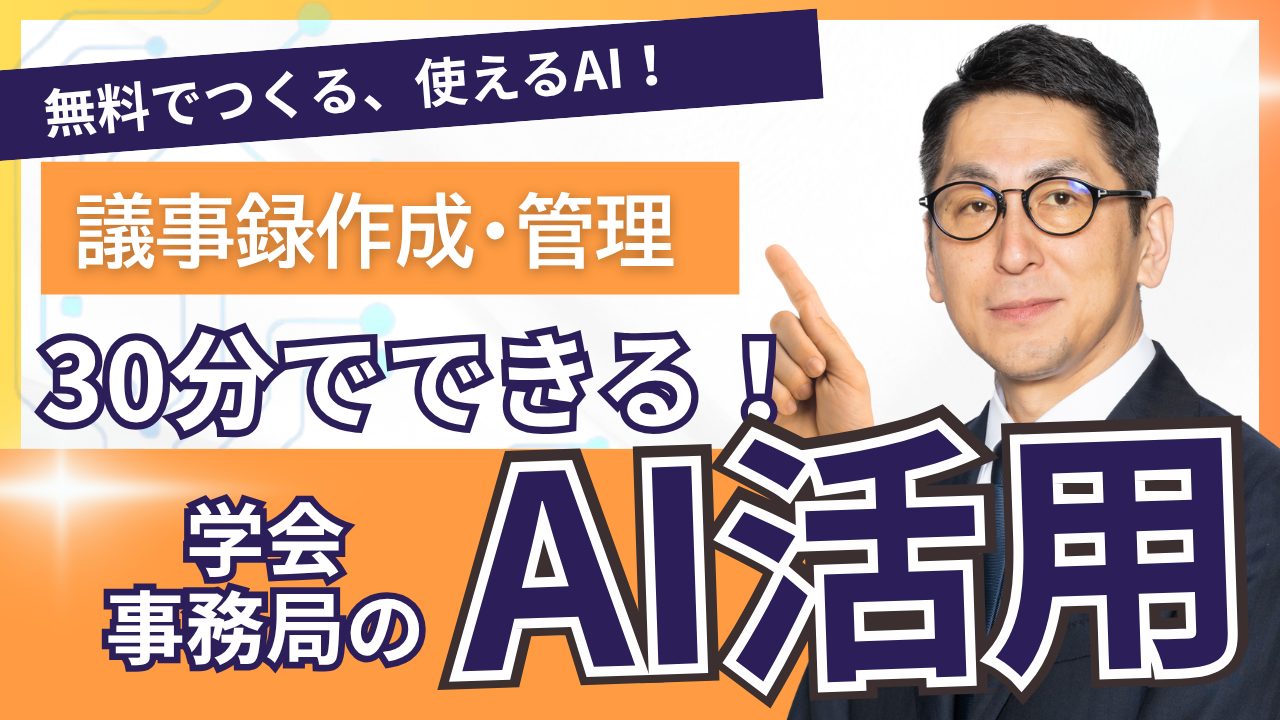еӯҰдјҡйҒӢе–¶гӮ’йқ©ж–°гҒҷгӮӢгҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚпјҡж©ҹиғҪгҒЁе°Һе…ҘгӮ¬гӮӨгғү
2025е№ҙ07жңҲ08ж—Ҙ

еӯҰдјҡгӮ„еҚ”дјҡгҒ®йҒӢе–¶гҒҜгҖҒдјҡе“Ўз®ЎзҗҶгҖҒгӮӨгғҷгғігғҲдјҒз”»гҖҒжғ…е ұзҷәдҝЎгҒӘгҒ©гҖҒеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢжҘӯеӢҷгҒ«ж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®з…©йӣ‘гҒӘдҪңжҘӯгӮ’еҠ№зҺҮзҡ„гҒӢгҒӨгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«йҒӮиЎҢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеӯҰдјҡгҒ®з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘзҷәеұ•гҒЁдјҡе“ЎгҒёгҒ®иіӘгҒ®й«ҳгҒ„гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒзҸҫд»ЈгҒ®еӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒЁгҒҜе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒӢгҖҒгҒқгҒ®дё»иҰҒгҒӘж©ҹиғҪгҖҒе°Һе…ҘгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁиҖғж…®гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ігҒ—гҒҸи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ йҒёе®ҡжҷӮгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгӮ„гҖҒе°Һе…ҘгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒ®гғ’гғігғҲгӮӮгҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гӮ’еӣігӮҠгҖҒгӮҲгӮҠгӮ№гғһгғјгғҲгҒӘйҒӢе–¶гӮ’зӣ®жҢҮгҒҷж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒеҪ№з«ӢгҒӨжғ…е ұгҒЁгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒЁгҒҜпјҹгҒқгҒ®еҪ№еүІгҒЁжҰӮиҰҒ
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒеӯҰиЎ“еӣЈдҪ“гӮ„еҚ”дјҡгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзө„з№”гҒ®йҒӢе–¶жҘӯеӢҷе…ЁиҲ¬гӮ’гӮӘгғігғ©гӮӨгғідёҠгҒ§дёҖе…ғзҡ„гҒ«з®ЎзҗҶгҒ—гҖҒиҮӘеӢ•еҢ–гӮ’жҺЁйҖІгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®з·ҸеҗҲзҡ„гҒӘITгғ„гғјгғ«гӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§жүӢдҪңжҘӯгӮ„иӨҮж•°гҒ®з•°гҒӘгӮӢгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹдјҡе“Ўжғ…е ұз®ЎзҗҶгҖҒдјҡиЁҲжҘӯеӢҷгҖҒгӮӨгғҷгғігғҲйҒӢе–¶гҖҒжғ…е ұе…ұжңүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҘӯеӢҷгӮ’зөұеҗҲгҒ—гҖҒеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘйҒӢе–¶гӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’е°Һе…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӯҰдјҡдәӢеӢҷеұҖгҒ®жҘӯеӢҷгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸеӨүеҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдјҡе“ЎгҒ®е…ҘдјҡжүӢз¶ҡгҒҚгӮ„зҷ»йҢІжғ…е ұгҒ®еӨүжӣҙгҒҜдјҡе“ЎиҮӘиә«гҒҢгӮҰгӮ§гғ–дёҠгҒ®е°Ӯз”ЁгғһгӮӨгғҡгғјгӮёгҒӢгӮүиЎҢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒдәӢеӢҷеұҖгҒҜеёёгҒ«жңҖж–°гҒ®дјҡе“Ўжғ…е ұгӮ’гғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ§жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮе№ҙдјҡиІ»гҒ®зҙҚе…ҘзҠ¶жіҒгӮӮгӮ·гӮ№гғҶгғ дёҠгҒ§з®ЎзҗҶгҒ•гӮҢгҖҒжңӘзҙҚиҖ…гҒёгҒ®иҮӘеӢ•гғӘгғһгӮӨгғігғүгӮ„дёҖжӢ¬гҒ§гҒ®гғЎгғјгғ«йҖҒдҝЎгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеӯҰиЎ“еӨ§дјҡгӮ„гӮ»гғҹгғҠгғјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮӨгғҷгғігғҲгҒ®йҒӢе–¶гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘеҠӣгӮ’зҷәжҸ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжј”йЎҢпјҲжҠ„йҢІпјүгҒ®гӮӘгғігғ©гӮӨгғіжҠ•зЁҝеҸ—д»ҳгҖҒеҸӮеҠ зҷ»йҢІгҒ®еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҖҒзҷәиЎЁгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ®з·ЁжҲҗгҖҒеҸӮеҠ иІ»гҒ®гӮӘгғігғ©гӮӨгғіжұәжёҲгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдјҡе ҙгҒ§гҒ®еҸ—д»ҳеҮҰзҗҶгҒҫгҒ§гҖҒдёҖйҖЈгҒ®гӮӨгғҷгғігғҲйҒӢе–¶гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’гӮ·гӮ№гғҶгғ дёҠгҒ§еҶҶж»‘гҒ«йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒҜдјҡе“ЎеҜҫеҝңгҒӢгӮүеӨ§дјҡй–ӢеӮ¬гҒҫгҒ§е№…еәғгҒ„жҘӯеӢҷгӮ’гӮ«гғҗгғјгҒ—гҖҒдәӢеӢҷеұҖгҒ®иІ жӢ…гӮ’еӨ§е№…гҒ«и»ҪжёӣгҒҷгӮӢеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚе°Һе…ҘгҒ®еҲ©зӮ№гҒЁиҖғж…®гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒ®е°Һе…ҘгҒҜгҖҒеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«ж§ҳгҖ…гҒӘжҒ©жҒөгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷдёҖж–№гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ«иӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ№гҒҚиҖғж…®зӮ№гӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮе°Һе…ҘгҒ«гӮҲгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгӮ’жңҖеӨ§йҷҗгҒ«дә«еҸ—гҒ—гҖҒжҪңеңЁзҡ„гҒӘиӘІйЎҢгҒ«йҒ©еҲҮгҒ«еҜҫеҮҰгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒжҲҗеҠҹгҒёгҒ®йҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒҢгӮӮгҒҹгӮүгҒҷдё»гҒӘеҲ©зӮ№
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚе°Һе…ҘгҒ®жңҖгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘеҲ©зӮ№гҒҜгҖҒйҒӢе–¶жҘӯеӢҷгҒ®гҖҢеҠ№зҺҮеҢ–гҖҚгҒЁгҖҢжӯЈзўәжҖ§гҖҚгҒ®еҗ‘дёҠгҒ§гҒҷгҖӮжүӢдҪңжҘӯгҒ«гӮҲгӮӢжҘӯеӢҷгӮ’жёӣгӮүгҒ—гҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гӮҲгӮӢиҮӘеӢ•еҢ–гӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәӢеӢҷеұҖгӮ№гӮҝгғғгғ•гҒ®дҪңжҘӯиІ жӢ…гҒҢеҠҮзҡ„гҒ«и»ҪжёӣгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғ’гғҘгғјгғһгғігӮЁгғ©гғјгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮӮдҪҺжёӣгҒ—гҖҒгғҮгғјгӮҝе…ҘеҠӣгғҹгӮ№гӮ„жғ…е ұе…ұжңүгҒ®йҪҹйҪ¬гӮ’йҳІгҒҗгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдјҡе“Ўжғ…е ұгӮ„гӮӨгғҷгғігғҲеҸӮеҠ гғҮгғјгӮҝгҒҢгӮҜгғ©гӮҰгғүдёҠгҒ§дёҖе…ғз®ЎзҗҶгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеёёгҒ«жңҖж–°гҒ®жғ…е ұгӮ’гғҒгғјгғ е…ЁдҪ“гҒ§е…ұжңүгҒ§гҒҚгҖҒжҘӯеӢҷгҒ®йҖҸжҳҺжҖ§гҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жҷӮй–“зҹӯзё®гҒЁгӮігӮ№гғҲеүҠжёӣгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдјҡиІ»гӮ„еҸӮеҠ иІ»гҒ®гӮӘгғігғ©гӮӨгғіжұәжёҲгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе…ҘйҮ‘зўәиӘҚдҪңжҘӯгҒҢдёҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжңӘзҙҚиҖ…гҒёгҒ®еҜҫеҝңгӮӮиҮӘеӢ•еҢ–гҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдәӢеӢҷеҮҰзҗҶгҒҢиҝ…йҖҹеҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮйғөйҖҒиІ»гӮ„зҙҷгҒ®еҚ°еҲ·иІ»гӮӮеүҠжёӣгҒ§гҒҚгҖҒзөҗжһңзҡ„гҒ«дәә件費гҒ®ең§зё®гҒ«гӮӮз№ӢгҒҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈеҜҫзӯ–гҒҢеј·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҖӢдәәжғ…е ұдҝқиӯ·гҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүгӮӮе®үеҝғгҒ—гҒҰйҒӢе–¶гӮ’иЎҢгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§гҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒе ҙжүҖгӮ’йҒёгҒ°гҒҡгҒ«жҘӯеӢҷгӮ’иЎҢгҒҲгӮӢжҹ”и»ҹжҖ§гӮӮгғЎгғӘгғғгғҲгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚе°Һе…ҘжҷӮгҒ®иҖғж…®зӮ№
дёҖж–№гҒ§гҖҒгҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒ®е°Һе…ҘгҒ«гҒҜгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®иҖғж…®зӮ№гӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒеҲқжңҹиІ»з”ЁгӮ„жңҲйЎҚгҒ®гғ©гғігғӢгғігӮ°гӮігӮ№гғҲгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®ж©ҹиғҪгӮ„иҰҸжЁЎгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиІ»з”ЁгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеӯҰдјҡгҒ®дәҲз®—гҒЁгғӢгғјгӮәгҒ«еҗҲиҮҙгҒ—гҒҹгғ—гғ©гғігӮ’йҒёгҒ¶еҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдҪҺгӮігӮ№гғҲгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒҜж©ҹиғҪгҒҢйҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеҫҢгҒӢгӮүж©ҹиғҪиҝҪеҠ гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮиҖғж…®гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒйҒӢз”ЁйқўгҒ§гҒ®иӘІйЎҢгӮӮиҖғж…®гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж–°гҒ—гҒ„гӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’е°Һе…ҘгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒдәӢеӢҷеұҖгӮ№гӮҝгғғгғ•гӮ„дјҡе“ЎгҒёгҒ®е‘ЁзҹҘгҒЁж•ҷиӮІгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮITгғӘгғҶгғ©гӮ·гғјгҒ«е·®гҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®зҝ’еҫ—гҒ«дёҖжҷӮзҡ„гҒ«жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҢеў—гҒҲгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮ·гӮ№гғҶгғ гғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹйҡӣгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮӮиҖғж…®гҒ—гҖҒгғҷгғігғҖгғјгҒ®гӮөгғқгғјгғҲдҪ“еҲ¶гӮ„гғҮгғјгӮҝгҒ®гғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—иЁҲз”»гӮ’дәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮе°Һе…ҘгҒҷгӮҢгҒ°е…ЁгҒҰгҒҢи§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒйҒӢз”Ёгғ•гғӯгғјгҒ®ж•ҙеӮҷгӮ„гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒ®гӮ№гӮӯгғ«гӮўгғғгғ—гӮ’ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢдҪ“еҲ¶гҒҘгҒҸгӮҠгҒҢгҖҒгҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒ«гӮҲгӮӢеҠ№зҺҮеҢ–гҒ®е®ҹзҸҫгҒ«гҒҜдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒ®дё»иҰҒж©ҹиғҪгҒЁжҙ»з”Ё
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒҜгҖҒеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ®еӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢеҒҙйқўгӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢж©ҹиғҪгӮ’еӮҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҘдёӢгҒ«гҖҒгҒқгҒ®дё»гҒӘж©ҹиғҪгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
дјҡе“Ўз®ЎзҗҶж©ҹиғҪ
дјҡе“ЎгҒ®е…Ҙдјҡз”іиҫјгҖҒжғ…е ұжӣҙж–°гҖҒйҖҖдјҡеҮҰзҗҶгӮ’гӮҰгӮ§гғ–дёҠгҒ§еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҖҒдјҡе“ЎгғҮгғјгӮҝгғҷгғјгӮ№гӮ’дёҖе…ғз®ЎзҗҶгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдјҡе“Ўжғ…е ұгҒҜгғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ§жӣҙж–°гҒ•гӮҢгҖҒж°ҸеҗҚгҖҒжүҖеұһгҖҒйҖЈзөЎе…ҲгҖҒдјҡе“ЎеҢәеҲҶгҒӘгҒ©гӮ’е®№жҳ“гҒ«жӨңзҙўгғ»зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮдјҡе“Ўе°Ӯз”ЁгҒ®гғһгӮӨгғҡгғјгӮёж©ҹиғҪгӮӮжҸҗдҫӣгҒ•гӮҢгҖҒдјҡе“ЎиҮӘиә«гҒҢжғ…е ұгҒ®зўәиӘҚгӮ„еӨүжӣҙгӮ’иЎҢгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдәӢеӢҷеұҖгҒ®иІ жӢ…гҒҢи»ҪжёӣгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒ®жңҖгӮӮеҹәжң¬зҡ„гҒӘж©ҹиғҪгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ
дјҡиІ»з®ЎзҗҶгғ»жұәжёҲж©ҹиғҪ
дјҡе“ЎгҒ®е№ҙдјҡиІ»зҙҚе…ҘзҠ¶жіҒгӮ’гӮ·гӮ№гғҶгғ дёҠгҒ§з®ЎзҗҶгҒ—гҖҒжңӘзҙҚиҖ…гҒёгҒ®иҮӘеӢ•зқЈдҝғгғЎгғјгғ«йҖҒдҝЎгӮ„гҖҒз¶ҷз¶ҡжЎҲеҶ…гҒ®иҮӘеӢ•еҢ–гҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүжұәжёҲгӮ„йҠҖиЎҢжҢҜиҫјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиӨҮж•°гҒ®жұәжёҲж–№жі•гҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҖҒе…ҘйҮ‘зўәиӘҚгҒӢгӮүй ҳеҸҺжӣёзҷәиЎҢгҒҫгҒ§гӮ’иҮӘеӢ•гҒ§иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒз…©йӣ‘гҒӘдјҡиЁҲеҮҰзҗҶгӮ’еҠ№зҺҮеҢ–гҒ—гҖҒдјҡиІ»еӣһеҸҺзҺҮгҒ®еҗ‘дёҠгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еӯҰиЎ“еӨ§дјҡгғ»гӮӨгғҷгғігғҲйҒӢе–¶ж©ҹиғҪ
жј”йЎҢпјҲжҠ„йҢІпјүгҒ®гӮӘгғігғ©гӮӨгғіжҠ•зЁҝеҸ—д»ҳгҖҒжҹ»иӘӯгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ®з®ЎзҗҶгҖҒжҺЎеҗҰйҖҡзҹҘгҒ®дёҖжӢ¬йҖҒдҝЎгҖҒзҷәиЎЁгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ®з·ЁжҲҗгҒӘгҒ©гҖҒеӯҰиЎ“еӨ§дјҡгҒ®жә–еӮҷжҘӯеӢҷгӮ’еҠ№зҺҮеҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҸӮеҠ зҷ»йҢІгҒ®гӮӘгғігғ©гӮӨгғіеҸ—д»ҳгҖҒеҸӮеҠ иІ»гҒ®жұәжёҲгҖҒеҸӮеҠ иЁјпјҲQRгӮігғјгғүгҒӘгҒ©пјүгҒ®зҷәиЎҢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҪ“ж—ҘгҒ®еҸ—д»ҳеҮҰзҗҶгҒҫгҒ§гҖҒдёҖйҖЈгҒ®гӮӨгғҷгғігғҲйҒӢе–¶гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’гӮ·гӮ№гғҶгғ дёҠгҒ§еҶҶж»‘гҒ«йҖІгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ
жғ…е ұе…ұжңүгғ»гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғіж©ҹиғҪ
дјҡе“ЎгӮ„еҸӮеҠ иҖ…гҒёгҒ®дёҖж–үгғЎгғјгғ«й…ҚдҝЎж©ҹиғҪгӮ’еӮҷгҒҲгҖҒгҒҠзҹҘгӮүгҒӣгӮ„йҖЈзөЎдәӢй …гӮ’зү№е®ҡгҒ®дјҡе“ЎеҢәеҲҶгӮ„гӮӨгғҷгғігғҲеҸӮеҠ иҖ…гӮ°гғ«гғјгғ—гҒ«зөһгҒЈгҒҰй…ҚдҝЎгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгӮ·гӮ№гғҶгғ еҶ…гҒ«гҖҢгҒҠзҹҘгӮүгҒӣгҖҚгӮ„гҖҢFAQгҖҚгӮ»гӮҜгӮ·гғ§гғігӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдјҡе“ЎгҒӢгӮүгҒ®е•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгӮ’еүҠжёӣгҒ—гҖҒжғ…е ұдјқйҒ”гӮ’еҠ№зҺҮеҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еұҘжӯҙз®ЎзҗҶгғ»гғҮгғјгӮҝеҮәеҠӣж©ҹиғҪ
дјҡе“ЎгҒ®е…ҘйҖҖдјҡеұҘжӯҙгҖҒдјҡиІ»зҙҚе…ҘеұҘжӯҙгҖҒгӮӨгғҷгғігғҲеҸӮеҠ еұҘжӯҙгҖҒжј”йЎҢжҠ•зЁҝеұҘжӯҙгҒӘгҒ©гҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢжҙ»еӢ•еұҘжӯҙгҒҢгӮ·гӮ№гғҶгғ дёҠгҒ«иЁҳйҢІгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғҮгғјгӮҝгҒҜгҖҒзөұиЁҲеҲҶжһҗгӮ„е ұе‘ҠжӣёдҪңжҲҗгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«CSVеҪўејҸгҒӘгҒ©гҒ§еҮәеҠӣеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ®ж”№е–„гӮ„е°ҶжқҘгҒ®иЁҲз”»з«ӢжЎҲгҒ«еҪ№з«ӢгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚйҒёе®ҡгҒЁе°Һе…ҘгҒ®гғқгӮӨгғігғҲ
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгӮ’е°Һе…ҘгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«жіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚгғқгӮӨгғігғҲгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮиҮӘеӯҰдјҡгҒ®гғӢгғјгӮәгҒ«еҗҲгҒЈгҒҹгӮ·гӮ№гғҶгғ йҒёе®ҡгҒЁгҖҒгӮ№гғ гғјгӮәгҒӘе°Һе…ҘиЁҲз”»гҒҢжҲҗеҠҹгҒ®йҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғӢгғјгӮәгҒ®жҳҺзўәеҢ–гҒЁж©ҹиғҪиҰҒ件гҒ®ж•ҙзҗҶ
гҒҫгҒҡ第дёҖгҒ«гҖҒиҮӘеӯҰдјҡгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘгғӢгғјгӮәгҒЁзҸҫзҠ¶гҒ®иӘІйЎҢгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиӮқеҝғгҒ§гҒҷгҖӮдјҡе“Ўж•°гӮ„еӨ§дјҡеҸӮеҠ иҖ…иҰҸжЁЎгҖҒзҸҫеңЁгҒ®йҒӢе–¶дҪ“еҲ¶гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҢдјҡе“Ўз®ЎзҗҶгҒҢдёӯеҝғгҒӢгҖҚгҖҢеӨ§дјҡйҒӢе–¶ж©ҹиғҪгӮӮеҝ…иҰҒгҒӢгҖҚгҖҢеӨҡиЁҖиӘһеҜҫеҝңгҒҜеҝ…й ҲгҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҝ…иҰҒгҒӘж©ҹиғҪгӮ’ж•ҙзҗҶгҒ—гҖҒе„Әе…Ҳй ҶдҪҚгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ йҒёе®ҡгҒ®еҹәжә–гҒҢжҳҺзўәгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж—ўеӯҳгғҮгғјгӮҝгҒЁгҒ®йҖЈжҗәгҒЁз§»иЎҢиЁҲз”»
зҸҫеңЁдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдјҡе“ЎеҗҚз°ҝгғҮгғјгӮҝгӮ„йҒҺеҺ»гҒ®жј”йЎҢгғҮгғјгӮҝгҒӘгҒ©гӮ’ж–°гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«з§»иЎҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮж—ўеӯҳгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгӮ„жұәжёҲжүӢж®өгҒЁгҒ®йҖЈжҗәгҒҢеҸҜиғҪгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгӮӮгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…ҘеҫҢгҒ®йҒӢз”ЁгӮ’иҖғж…®гҒҷгӮӢдёҠгҒ§зўәиӘҚгҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгғҮгғјгӮҝ移иЎҢгҒ®гӮөгғқгғјгғҲдҪ“еҲ¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮдәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҖҒ移иЎҢиЁҲз”»гӮ’з«ӢгҒҰгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гӮөгғқгғјгғҲдҪ“еҲ¶гҒЁгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгғ»дҝЎй јжҖ§
гӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…ҘжҷӮгҒ®иЁӯе®ҡгӮ„ж“ҚдҪңж–№жі•гҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮөгғқгғјгғҲгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгғҲгғ©гғ–гғ«зҷәз”ҹжҷӮгҒ«иҝ…йҖҹгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮөгғқгғјгғҲдҪ“еҲ¶гҒ®е……е®ҹеәҰгҒҜгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®з¶ҷз¶ҡеҲ©з”ЁгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҒ§гҒҷгҖӮе°Ӯд»»гҒ®гӮөгғқгғјгғҲжӢ…еҪ“гӮ„гғҒгғЈгғғгғҲгӮөгғқгғјгғҲгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒдјҡе“ЎгҒ®еҖӢдәәжғ…е ұгҒӘгҒ©ж©ҹеҜҶгғҮгғјгӮҝгӮ’й җгҒӢгӮӢд»ҘдёҠгҖҒгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгҒЁдҝЎй јжҖ§гӮӮз„ЎиҰ–гҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгғ—гғ©гӮӨгғҗгӮ·гғјгғһгғјгӮҜеҸ–еҫ—гӮ„ISMSиӘҚиЁјгҒӘгҒ©гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘжғ…е ұз®ЎзҗҶгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®зЁјеғҚзҺҮгӮ„гғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—дҪ“еҲ¶гҒҜгҒ©гҒҶгҒӢгҒӘгҒ©гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҖҒдҝЎй јгҒ§гҒҚгӮӢгғҷгғігғҖгғјгӮ’йҒёгҒігҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒпјҡгҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒ§йҒӢе–¶гӮ’жңҖйҒ©еҢ–
гҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒҜгҖҒеӨҡеҝҷгҒӘеӯҰдјҡйҒӢе–¶иҖ…гҒ®еј·еҠӣгҒӘе‘іж–№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҒӢе–¶гҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®дёҚеҸҜж¬ гҒӘгғ„гғјгғ«гҒ§гҒҷгҖӮдјҡе“Ўз®ЎзҗҶгҒӢгӮүгӮӨгғҷгғігғҲйҒӢе–¶гҖҒжғ…е ұе…ұжңүгҒҫгҒ§гҖҒз…©йӣ‘гҒӘжҘӯеӢҷгӮ’дёҖе…ғеҢ–гғ»иҮӘеӢ•еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәӢеӢҷеұҖгҒ®иІ жӢ…гӮ’еӨ§е№…гҒ«и»ҪжёӣгҒ—гҖҒгӮҲгӮҠжң¬иіӘзҡ„гҒӘеӯҰиЎ“жҙ»еӢ•гҒ«йӣҶдёӯгҒ§гҒҚгӮӢз’°еўғгӮ’ж•ҙгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ·гӮ№гғҶгғ е°Һе…ҘгҒ«гҒҜеҲқжңҹиІ»з”ЁгӮ„йҒӢз”ЁйқўгҒ®иҖғж…®зӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮүгӮ’дёҠеӣһгӮӢеҠ№зҺҮеҢ–гҒЁгӮігӮ№гғҲеүҠжёӣгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮйҒ©еҲҮгҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’йҒёгҒігҖҒиЁҲз”»зҡ„гҒ«е°Һе…ҘгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӯҰдјҡгҒҜгӮҲгӮҠеҶҶж»‘гҒ«гҖҒгҒқгҒ—гҒҰжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒӘеҪўгҒ§зҷәеұ•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҖҢеӯҰдјҡ з®ЎзҗҶгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒжңӘжқҘеҝ—еҗ‘гҒ®еӯҰдјҡйҒӢе–¶гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ