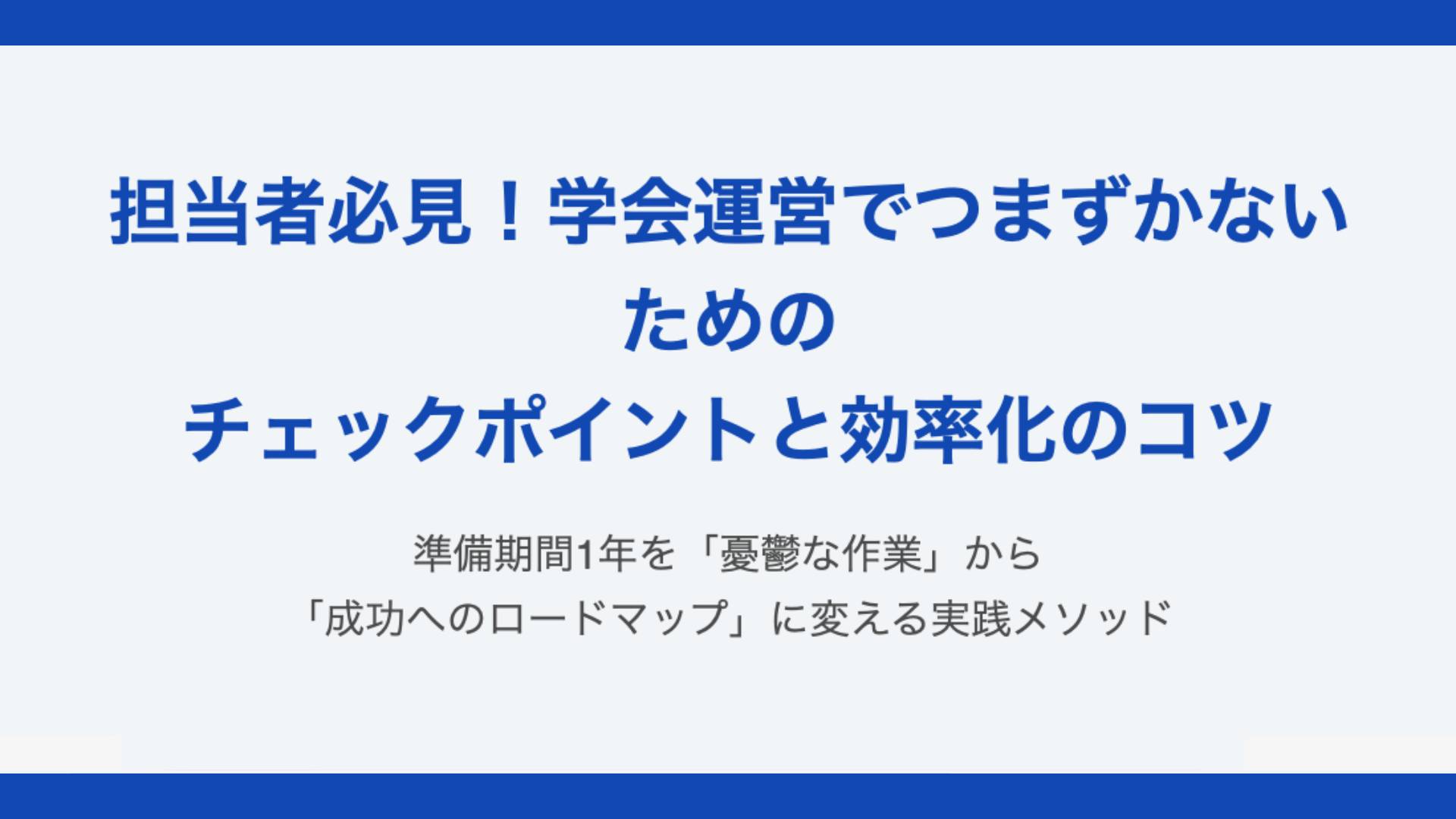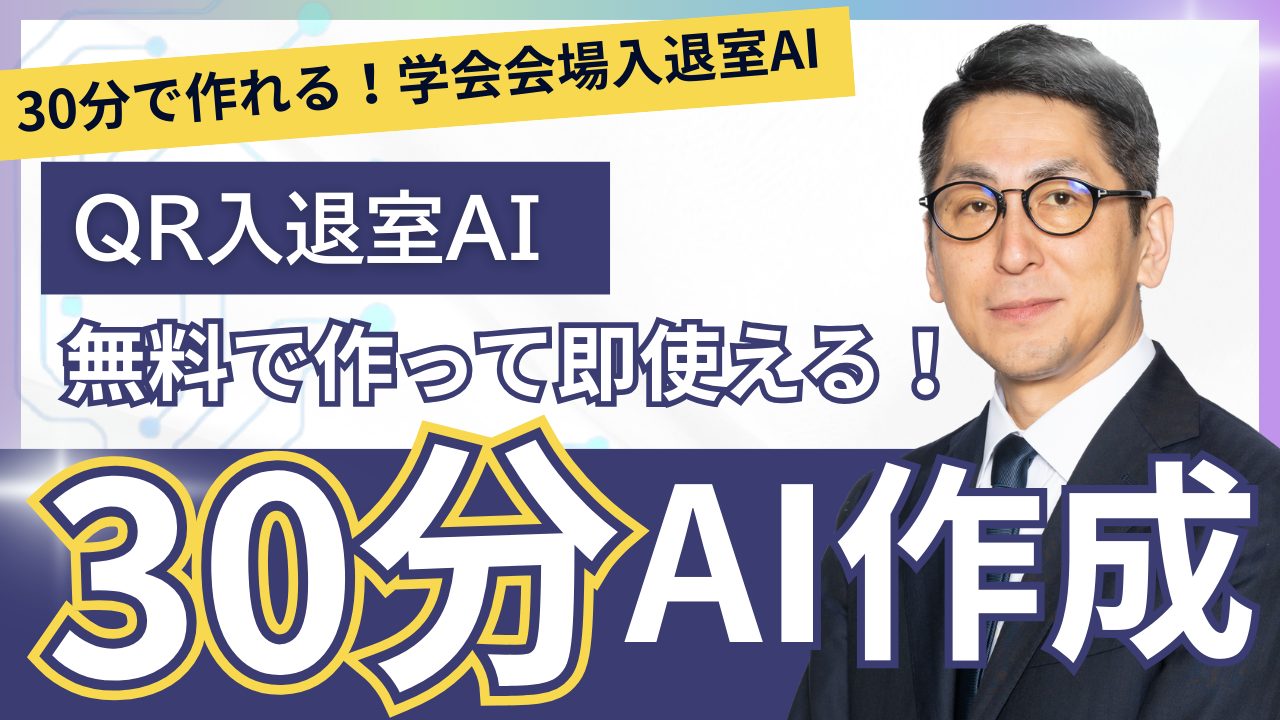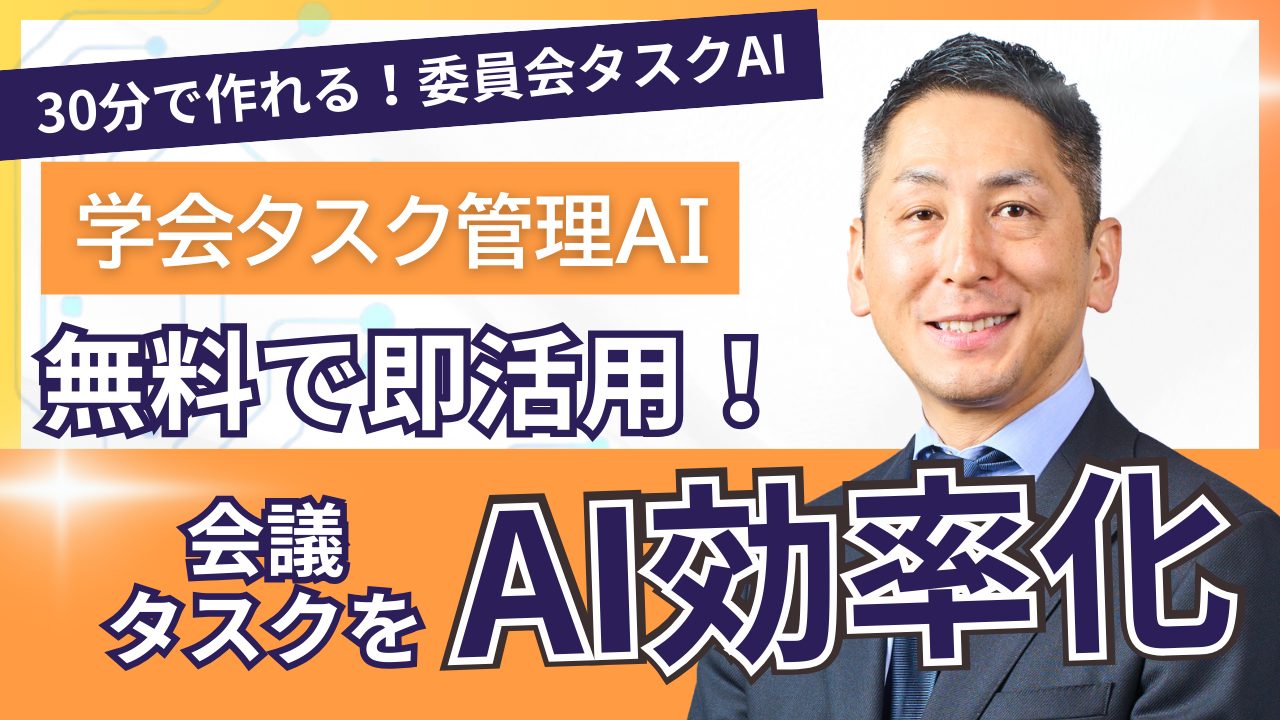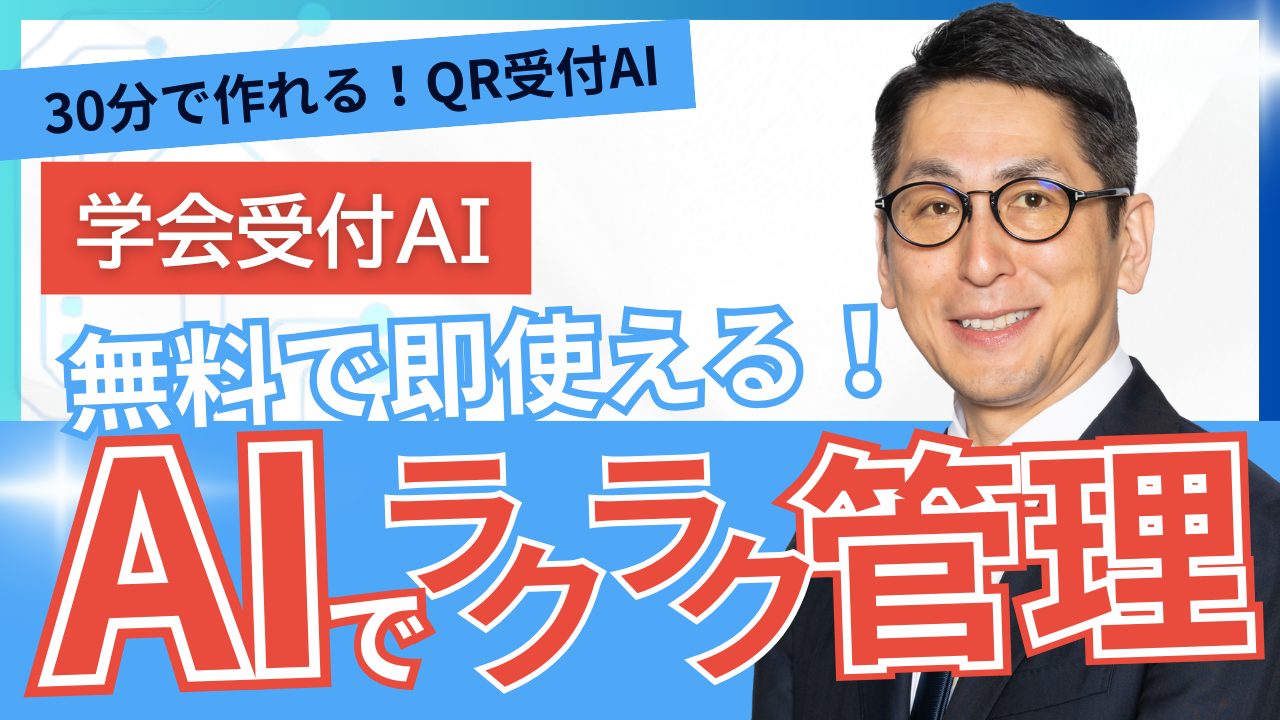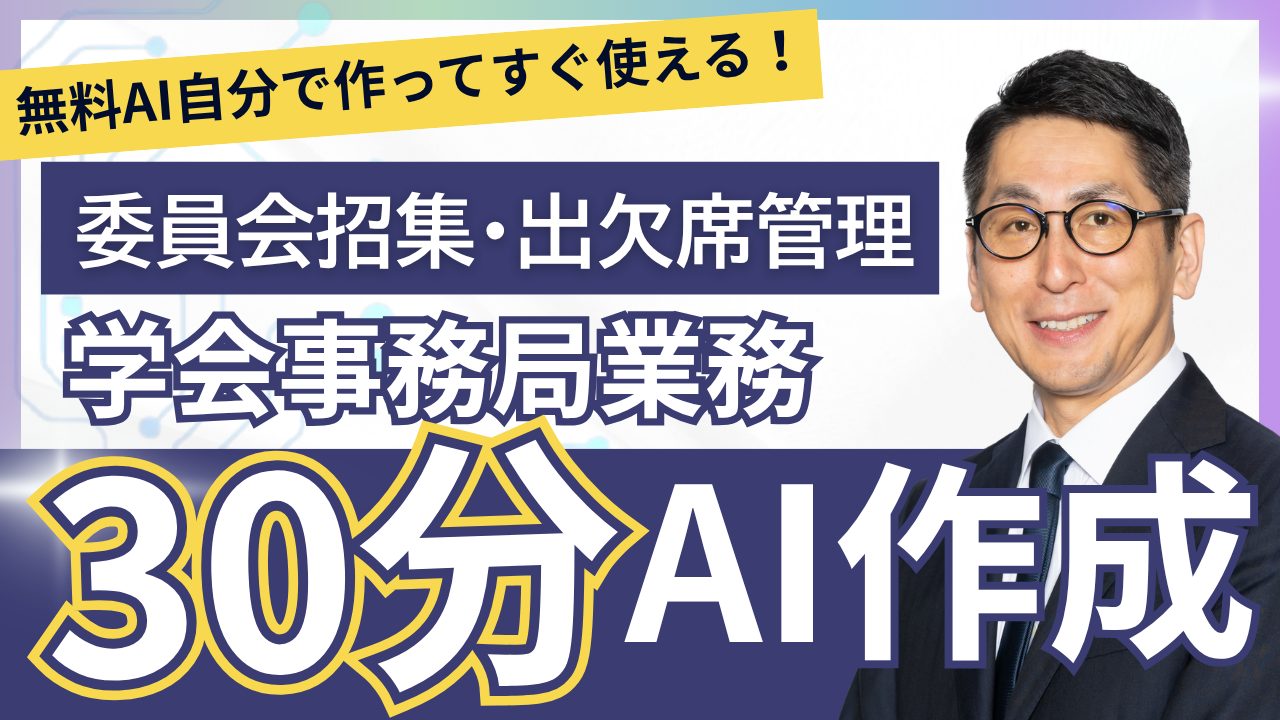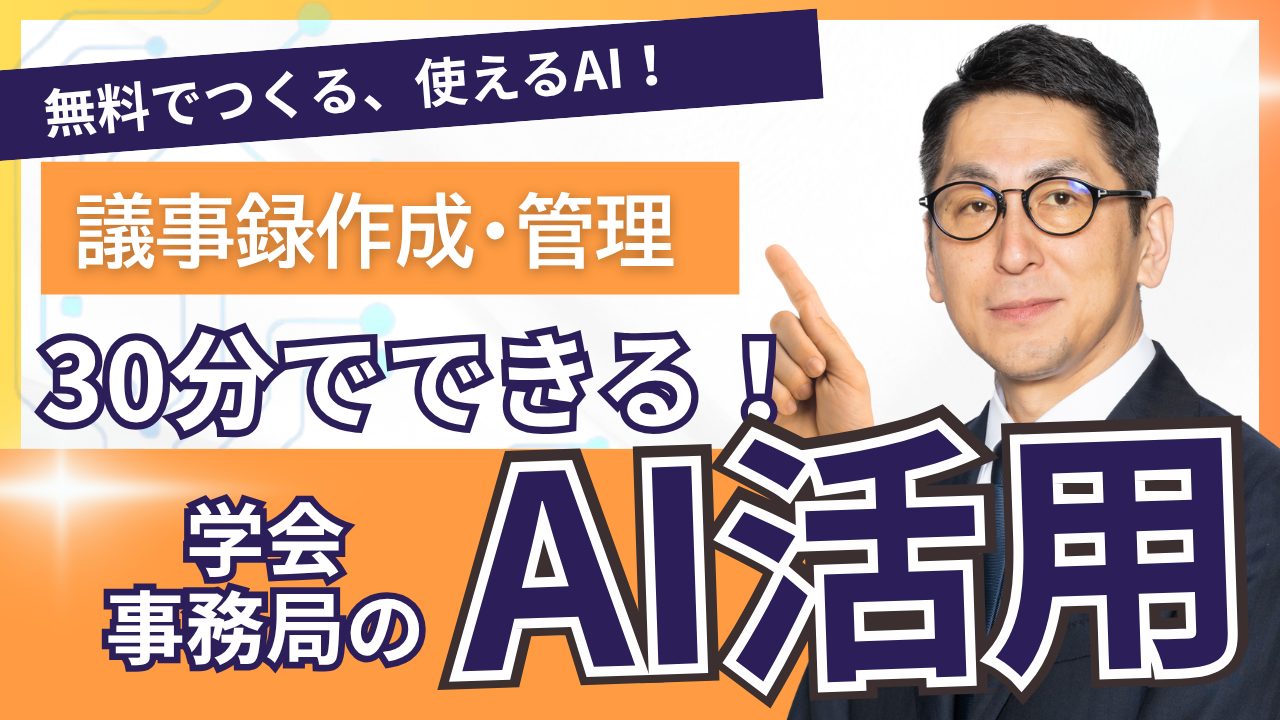тГдУАЊС║цТхЂсЂ«Тќ░сЂЪсЂфтйб№╝џсђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂДт«ЪуЈЙсЂЎсѓІТЪћУ╗ЪсЂфтЈѓтіаСйЊжеЊсЂежЂІтќХТѕљтіЪсЂ«жЇх
2025т╣┤07Тюѕ08ТЌЦ

У┐Љт╣┤сђЂтГдУАЊтцДС╝џсѓёуаћуЕХС╝џсЂ«жЂІтќХсЂФсЂісЂёсЂдсђЂсђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂїСИ╗ТхЂсЂесЂфсѓісЂцсЂцсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂ»сђЂтЙЊТЮЦсЂ«уЈЙтю░№╝ѕт»ЙжЮб№╝ЅжќІтѓгсЂ«УЅ»сЂЋсЂесђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│жќІтѓгсЂ«тѕЕСЙ┐ТђДсѓњУъЇтљѕсЂЋсЂЏсЂЪТќ░сЂЌсЂётйбт╝ЈсЂДсЂЎсђѓтЈѓтіаУђЁсЂ»сђЂС╝џта┤сЂФУХ│сѓњжЂІсѓЊсЂДт»ЙжЮбсЂДсЂ«С║цТхЂсѓњТЦйсЂЌсѓђсЂЊсЂесѓѓсђЂУЄфт«ЁсѓёУЂита┤сЂІсѓЅсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сЂДтЈѓтіасЂЎсѓІсЂЊсЂесѓѓсЂДсЂЇсѓІсЂЪсѓЂсђЂсѓѕсѓітцџТДўсЂфсЃІсЃ╝сѓ║сЂФт┐юсЂѕсѓІсЂЊсЂесЂїтЈ»УЃйсЂФсЂфсѓісЂЙсЂЌсЂЪсђѓсЂЌсЂІсЂЌсђЂсЂЮсЂ«СИђТќ╣сЂДсђЂсђїТ║ќтѓЎсЂїУцЄжЏЉсЂФсЂфсѓІсђЇсђїСйЋсЂІсѓЅТЅІсѓњсЂцсЂЉсЂдсЂёсЂёсЂІтѕєсЂІсѓЅсЂфсЂёсђЇсЂесЂёсЂБсЂЪтБ░сѓѓУЂъсЂІсѓїсѓІсЂ«сЂїт«ЪТЃЁсЂДсЂЎсђѓ
ТюгУеўС║ІсЂДсЂ»сђЂсђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂ«тЪ║ТюгуџёсЂфТдѓт┐хсЂІсѓЅсђЂсЂЮсЂ«сЃАсЃфсЃЃсЃѕсЃ╗сЃЄсЃАсЃфсЃЃсЃѕсђЂсѓ╣сЃасЃ╝сѓ║сЂфжЂІтќХсѓњт«ЪуЈЙсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«тЁиСйЊуџёсЂфсЃЮсѓцсЃ│сЃѕсђЂсЂЮсЂЌсЂдУхисЂЊсѓісЂєсѓІсЃѕсЃЕсЃќсЃФсЂИсЂ«т»ЙуГќсЂЙсЂДсѓњуХ▓уЙЁуџёсЂФУДБУфгсЂЌсЂЙсЂЎсђѓтГдС╝џсѓњСИ╗тѓгсЃ╗жЂІтќХсЂЎсѓІТќ╣сђЁсЂїсђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсѓњТѕљтіЪсЂЋсЂЏсѓІсЂЪсѓЂсЂ«т«ЪУихуџёсЂфсЃњсЃ│сЃѕсѓњТЈљСЙЏсЂЎсѓІсЂЊсЂесѓњуЏ«ТїЄсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂесЂ»№╝ЪсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сЂет»ЙжЮбсЂ«УъЇтљѕ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂесЂ»сђЂтГдУАЊтцДС╝џсѓёуаћуЕХС╝џсѓњуЈЙтю░сЂДсЂ«т»ЙжЮбтйбт╝ЈсЂесѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│тйбт╝ЈсЂ«СИАТќ╣сЂДтљїТЎѓсЂФжђ▓УАїсЂЎсѓІжЂІтќХтйбТЁІсѓњТїЄсЂЌсЂЙсЂЎсђѓтЁиСйЊуџёсЂФсЂ»сђЂуЎ║УАеУђЁсѓётЈѓтіаУђЁсЂ«СИђжЃесЂїуЅЕуљєуџёсЂфС╝џта┤сЂФжЏєсЂёсђЂТ«ІсѓісЂ«уЎ║УАеУђЁсѓётЈѓтіаУђЁсЂїсѓцсЃ│сѓ┐сЃ╝сЃЇсЃЃсЃѕсѓњжђџсЂўсЂдсЃфсЃбсЃ╝сЃѕсЂДтЈѓтіасЂЌсЂЙсЂЎсђѓС╝џта┤сЂДУАїсѓЈсѓїсЂдсЂёсѓІсѓ╗сЃЃсѓисЃДсЃ│сЂ«ТДўтГљсѓњсЃфсѓбсЃФсѓ┐сѓцсЃасЂДсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│жЁЇС┐АсЂЌсЂЪсѓісђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сЂДуЎ║УАесЂЎсѓІТ╝ћУђЁсѓњС╝џта┤сЂ«сѓ╣сѓ»сЃфсЃ╝сЃ│сЂФТўасЂЌтЄ║сЂЌсЂЪсѓісЂЎсѓІсЂфсЂЕсђЂтЈїТќ╣сЂ«тЈѓтіаУђЁсЂїуЏИС║њсЂФС║цТхЂсЂДсЂЇсѓІсѓѕсЂєсЂфС╗ЋухёсЂ┐сѓњТДІу»ЅсЂЌсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсЂ«УъЇтљѕсЂФсѓѕсѓісђЂтю░уљєуџёсЃ╗ТЎѓжќЊуџёсЂфтѕХу┤ёсѓњУХЁсЂѕсЂдтцџТДўсЂфуаћуЕХУђЁсЂїжЏєсЂёсђЂтГдУАЊС║цТхЂсЂ«ТЕЪС╝џсѓњт║ЃсЂњсѓІсЂЊсЂесЂїтЈ»УЃйсЂДсЂЎсђѓсЂЙсЂЋсЂФсђЂсђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂ»уЈЙС╗БсЂ«тГдУАЊсѓ│сЃЪсЃЦсЃІсЃєсѓБсЂ«сЃІсЃ╝сѓ║сЂФт┐юсЂѕсѓІсђЂТЪћУ╗ЪТђДсЂ«жФўсЂёжќІтѓгТќ╣т╝ЈсЂеУеђсЂѕсѓІсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
сЂфсЂюС╗ісђЂсђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсѓІсЂ«сЂІ№╝Ъ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂїТ│еуЏ«сЂЋсѓїсѓІУЃїТЎ»сЂФсЂ»сђЂсЂёсЂЈсЂцсЂІсЂ«жЄЇУдЂсЂфУдЂтЏасЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
Тќ░тъІсѓ│сЃГсЃісѓдсѓцсЃФсѓ╣ТёЪТЪЊуЌЄсЂ«тй▒жЪ┐сЂетцЅтїќсЂЎсѓІсЃІсЃ╝сѓ║
Тќ░тъІсѓ│сЃГсЃісѓдсѓцсЃФсѓ╣ТёЪТЪЊуЌЄсЂ«сЃЉсЃ│сЃЄсЃЪсЃЃсѓ»сЂ»сђЂтГдС╝џжЂІтќХсЂФтцДсЂЇсЂфУ╗бТЈЏсѓњС┐ЃсЂЌсЂЙсЂЌсЂЪсђѓуЅЕуљєуџёсЂфуД╗тІЋсЂїтѕХжЎљсЂЋсѓїсђЂтцџсЂЈсЂ«тГдС╝џсЂїсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│жќІтѓгсЂФтѕЄсѓіТЏ┐сѓЈсѓІСИГсЂДсђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│тйбт╝ЈсЂ«сЃАсЃфсЃЃсЃѕсЂїт║ЃсЂЈУфЇУГўсЂЋсѓїсЂЙсЂЌсЂЪсђѓСИђТќ╣сЂДсђЂт»ЙжЮбсЂДсЂ«уЏ┤ТјЦуџёсЂфС║цТхЂсЂ«жЄЇУдЂТђДсѓѓтєЇУфЇУГўсЂЋсѓїсђЂсЂЮсЂ«СИАТќ╣сѓњтЁ╝сЂГтѓЎсЂѕсЂЪсђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂїсђЂуиіТђЦТЎѓсЂФсѓѓт»Йт┐юсЂДсЂЇсѓІжЂІтќХтйбт╝ЈсЂесЂЌсЂдТ│еуЏ«сЂЋсѓїсЂЙсЂЌсЂЪсђѓуЈЙтюесЂДсѓѓсђЂТИАУѕфтѕХжЎљсЂ«уХЎуХџсѓёсђЂтЈѓтіаУђЁсЂ«т«ЅтЁежЮбсЂИсЂ«жЁЇТЁ«сЂІсѓЅсђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│СйхућесЂ«тГдС╝џжЂІтќХсЂИсЂ«жюђУдЂсЂ»уХџсЂёсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
тцџТДўсЂфтЈѓтіаУђЁсЂ«сЃІсЃ╝сѓ║сЂИсЂ«т»Йт┐ю
уЈЙС╗БсЂ«уаћуЕХУђЁсЂ»тцџт┐ЎсЂДсЂѓсѓісђЂтЏйтєЁтцќсѓњтЋЈсѓЈсЂџуД╗тІЋсЂ«У▓аТІЁсЂїтцДсЂЇсЂёта┤тљѕсѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓжЂажџћтю░сЂ«уаћуЕХУђЁсѓёсђЂУѓ▓тЁљсЃ╗С╗ІУГисЂфсЂЕсЂДуЅЕуљєуџёсЂфтЈѓтіасЂїжЏБсЂЌсЂёуаћуЕХУђЁсЂФсЂесЂБсЂдсђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сЂДсЂ«тЈѓтіасѓфсЃЌсѓисЃДсЃ│сЂ»жЮътИИсЂФСЙАтђцсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓСЙІсЂѕсЂ░сђЂтГљУѓ▓сЂдСИГсЂ«уаћуЕХУђЁсЂїсђЂУЄфт«ЁсЂІсѓЅуЪГТЎѓжќЊсЂасЂЉуЅ╣т«џсЂ«сѓ╗сЃЃсѓисЃДсЃ│сЂФтЈѓтіасЂДсЂЇсѓІсЂфсЂЕсђЂсЂЊсѓїсЂЙсЂДсЂ«уЈЙтю░жќІтѓгсЂДсЂ»жЏБсЂЌсЂІсЂБсЂЪтЈѓтіаТЕЪС╝џсѓњтЅхтЄ║сЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂФсѓѕсѓісђЂсѓѕсѓітцџсЂЈсЂ«С║║сђЁсЂїтГдУАЊС║цТхЂсЂФтЈѓтіасЂДсЂЇсѓІсѓѕсЂєсЂФсЂфсѓісђЂтГдС╝џсЂ«жќђТѕИсЂїт║ЃсЂїсѓІті╣ТъюсЂїТюЪтЙЁсЂЋсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
жќІтѓгУдЈТеАсЂ«ТІАтцДсЂесѓ│сѓ╣сЃѕті╣ујЄ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂ»сђЂС╝џта┤сЂ«тЈјт«╣С║║ТЋ░сЂФуИЏсѓЅсѓїсѓІсЂЊсЂесЂфсЂЈтЈѓтіаУђЁТЋ░сѓњтбЌсѓёсЂЎсЂЊсЂесѓњтЈ»УЃйсЂФсЂЌсЂЙсЂЎсђѓсЂЊсѓїсЂ»сђЂтцДУдЈТеАсЂфтГдС╝џсЂФсЂісЂёсЂдуЅ╣сЂФТюЅтѕЕсЂДсЂЎсђѓсЂЙсЂЪсђЂС╝џта┤жЂІтќХсЂФсЂІсЂІсѓІУ▓╗ућесЂ«СИђжЃесѓњтЅіТИЏсЂДсЂЇсѓІтЈ»УЃйТђДсѓѓуДўсѓЂсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓСЙІсЂѕсЂ░сђЂТЮЦта┤УђЁсЂїт░ЉсЂфсЂёсѓ╗сЃЃсѓисЃДсЃ│сЂ»сѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сЂ«сЂ┐сЂФсЂЎсѓІсЂесЂёсЂБсЂЪТЪћУ╗ЪсЂфжЂІућесЂФсѓѕсѓісђЂтЁеСйЊуџёсЂфсѓ│сѓ╣сЃѕті╣ујЄсѓњжФўсѓЂсЂцсЂцсђЂтГдУАЊС║цТхЂсЂ«ТЕЪС╝џсѓњТюђтцДтїќсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂФсЂісЂЉсѓІУф▓жАїсЂеТ║ќтѓЎсЂ«сЃЮсѓцсЃ│сЃѕ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂ»тцџсЂЈсЂ«сЃАсЃфсЃЃсЃѕсѓњТїЂсЂцСИђТќ╣сЂДсђЂсЂЮсЂ«УцЄжЏЉсЂЋсѓєсЂѕсЂФсђЂуХ┐т»єсЂфТ║ќтѓЎсЂеУеѕућ╗сЂїт┐ЁУдЂсЂДсЂЎсђѓуЅ╣сЂФсђЂуЈЙтю░сЂесѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сЂ«тЈїТќ╣сѓњтєєТ╗ЉсЂФжђБТљ║сЂЋсЂЏсѓІсЂЪсѓЂсЂ«тиЦтцФсЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
ТіђУАЊуџёсЂфУф▓жАїсЂеУеГтѓЎТіЋУ│Є
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂФсЂісЂЉсѓІТюђтцДсЂ«Уф▓жАїсЂ«СИђсЂцсЂ»сђЂТіђУАЊуџёсЂфТ║ќтѓЎсЂДсЂЎсђѓт«Ѕт«џсЂЌсЂЪсѓцсЃ│сѓ┐сЃ╝сЃЇсЃЃсЃѕуњ░тбЃсЂ«ТЋ┤тѓЎсђЂжФўтЊЂУ│фсЂфжЪ│тБ░сЃ╗ТўатЃЈТЕЪТЮљсЂ«Т║ќтѓЎсђЂсЂЮсЂЌсЂдсЃЕсѓцсЃќжЁЇС┐Асѓёжї▓ућ╗сЂ«сЂЪсѓЂсЂ«т░ѓжќђсѓйсЃЋсЃѕсѓдсѓДсѓбсѓёсЃЌсЃЕсЃЃсЃѕсЃЋсѓЕсЃ╝сЃасЂ«жЂИт«џсЂїСИЇтЈ»ТгасЂДсЂЎсђѓуЈЙтю░С╝џта┤сЂ«жЪ│жЪ┐сЃ╗уЁДТўјУеГтѓЎсЂесѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│жЁЇС┐Асѓисѓ╣сЃєсЃасЂесЂ«жђБТљ║сѓѓУђЃТЁ«сЂЎсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісђЂсЂЊсѓїсЂФсЂ»СИђт«џсЂ«УеГтѓЎТіЋУ│Єсѓёт░ѓжќђуЪЦУГўсЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
жЂІтќХсѓ╣сѓ┐сЃЃсЃЋсЂ«уб║С┐ЮсЂетй╣тЅ▓тѕєТІЁ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂ»сђЂуЈЙтю░жЂІтќХсЂесѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│жЂІтќХсЂ«тЈїТќ╣сѓњтљїТЎѓсЂФжђ▓УАїсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсђЂсѓѕсѓітцџсЂЈсЂ«сѓ╣сѓ┐сЃЃсЃЋсЂесђЂсЂЮсѓїсЂъсѓїсЂ«тй╣тЅ▓сЂФт┐юсЂўсЂЪт░ѓжќђсѓ╣сѓГсЃФсЂїт┐ЁУдЂсЂДсЂЎсђѓуЈЙтю░С╝џта┤сЂ«жђ▓УАїу«АуљєсђЂтЈѓтіаУђЁтЈЌС╗ўсђЂуЎ║УАеУђЁсѓхсЃЮсЃ╝сЃѕсЂФтіасЂѕсђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│жЁЇС┐АсЂ«ТіђУАЊсѓфсЃџсЃгсЃ╝сѓ┐сЃ╝сђЂсЃЂсЃБсЃЃсЃѕсЃбсЃЄсЃгсЃ╝сѓ┐сЃ╝сђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│тЈѓтіаУђЁсЂІсѓЅсЂ«У│фтЋЈт»Йт┐юсЂфсЂЕсђЂтцџт▓љсЂФсѓЈсЂЪсѓІтй╣тЅ▓сѓњТўјуб║сЂФсЂЌсђЂжЂЕтѕЄсЂфС║║тЊАсѓњжЁЇуй«сЂЌсЂфсЂЉсѓїсЂ░сЂфсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓсѓ╣сѓ┐сЃЃсЃЋжќЊсЂ«жђБТљ║сѓњт»єсЂФсЂЌсђЂсЃѕсЃЕсЃќсЃФуЎ║ућЪТЎѓсЂФУ┐ЁжђЪсЂФт»Йт┐юсЂДсЂЇсѓІСйЊтѕХсѓњТДІу»ЅсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїТЦхсѓЂсЂджЄЇУдЂсЂДсЂЎсђѓ
сЃЌсЃГсѓ░сЃЕсЃаУеГУеѕсЂесѓ│сЃЪсЃЦсЃІсѓ▒сЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂ«тиЦтцФ
сѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сЂет»ЙжЮбсђЂСИАТќ╣сЂ«тЈѓтіаУђЁсЂїТ║ђУХ│сЂДсЂЇсѓІсЃЌсЃГсѓ░сЃЕсЃаУеГУеѕсѓѓжЄЇУдЂсЂДсЂЎсђѓуЈЙтю░тЈѓтіаУђЁтљЉсЂЉсЂ«С║цТхЂТЕЪС╝џсЂесђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│тЈѓтіаУђЁтљЉсЂЉсЂ«тЈїТќ╣тљЉсѓ│сЃЪсЃЦсЃІсѓ▒сЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂ«ТЕЪС╝џсѓњсЃљсЃЕсЃ│сѓ╣сѓѕсЂЈТЈљСЙЏсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓСЙІсЂѕсЂ░сђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│тЈѓтіаУђЁсЂІсѓЅсЂ«У│фтЋЈсѓњсЃЂсЃБсЃЃсЃѕсЂДтЈЌсЂЉС╗ўсЂЉсђЂС╝џта┤сЂ«т║ДжЋисЂїТІЙсЂёСИісЂњсѓІС╗ЋухёсЂ┐сѓёсђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│ТЄЄУдфС╝џсЂ«жќІтѓгсЂфсЂЕсѓѓТюЅті╣сЂДсЂЎсђѓ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсѓњТѕљтіЪсЂЋсЂЏсѓІсЂЪсѓЂсЂ«т«ЪУихуџёсѓбсЃЌсЃГсЃ╝сЃЂ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсѓњТѕљтіЪсЂФт░јсЂЈсЂЪсѓЂсЂФсЂ»сђЂС╗ЦСИІсЂ«т«ЪУихуџёсЂфсѓбсЃЌсЃГсЃ╝сЃЂсЂїТюЅті╣сЂДсЂЎсђѓ
С║ІтЅЇТ║ќтѓЎсЂесЃфсЃЈсЃ╝сѓхсЃФсЂ«тЙ╣т║Ћ
жќІтѓгтйбт╝ЈсЂ«Т▒║т«џсђЂУЕ│у┤░сЂфсѓ╣сѓ▒сѓИсЃЦсЃ╝сЃФуГќт«џсђЂС╝џта┤сЂесѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сЃЌсЃЕсЃЃсЃѕсЃЋсѓЕсЃ╝сЃасЂ«жЂИт«џсђЂТ╝ћжАїтІЪжЏєсЂетЈѓтіауЎ╗жї▓сѓисѓ╣сЃєсЃасЂ«УеГт«џсЂфсЂЕсђЂС║ІтЅЇсЂ«Т║ќтѓЎсЂ»тцџт▓љсЂФсѓЈсЂЪсѓісЂЙсЂЎсђѓуЅ╣сЂФжЄЇУдЂсЂфсЂ«сЂ»сђЂТюгуЋфсѓњТЃ│т«џсЂЌсЂЪуХ┐т»єсЂфсЃфсЃЈсЃ╝сѓхсЃФсЂДсЂЎсђѓТіђУАЊсѓ╣сѓ┐сЃЃсЃЋсђЂуЎ║УАеУђЁсђЂт║ДжЋисЂїтЈѓтіасЂЌсђЂжЪ│тБ░сђЂТўатЃЈсђЂућ╗жЮбтЁ▒ТюЅсђЂУ│фуќЉт┐юуГћсЂ«ТхЂсѓїсЂфсЂЕсђЂтЁесЂдсЂїтєєТ╗ЉсЂФТЕЪУЃйсЂЎсѓІсЂІсѓњтЁЦт┐хсЂФуб║УфЇсЂЌсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓсЃѕсЃЕсЃќсЃФуЎ║ућЪТЎѓсЂ«т»Йт┐юТЅІжаєсѓѓсЂЊсЂ«Т«хжџјсЂДуб║уФІсЂЌсЂдсЂісЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
т░ѓжќђТЦГУђЁсЂесЂ«жђБТљ║
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂ«жЂІтќХсЂФсЂ»сђЂжФўт║дсЂфжЁЇС┐АТіђУАЊсѓёсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сѓцсЃЎсЃ│сЃѕсЂ«т░ѓжќђуЪЦУГўсЂїТ▒ѓсѓЂсѓЅсѓїсѓІсЂЪсѓЂсђЂУЄфтЅЇсЂДсЂ«т»Йт┐юсЂїжЏБсЂЌсЂёта┤тљѕсЂ»сђЂт░ѓжќђсЂ«сѓ│сЃ│сЃЎсЃ│сѓисЃДсЃ│С╗БУАїС╝џуцЙсѓёсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сѓцсЃЎсЃ│сЃѕТЦГУђЁсЂФтЇћтіЏсѓњСЙЮжа╝сЂЎсѓІсЂЊсЂесѓњТцюУејсЂЌсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓсЃЌсЃГсЂ«сЃјсѓдсЃЈсѓдсѓњТ┤╗ућесЂЎсѓІсЂЊсЂесЂДсђЂУ│фсЂ«жФўсЂёжЁЇС┐Асѓњт«ЪуЈЙсЂЌсђЂжЂІтќХтЂ┤сЂ«У▓аТІЁсѓњтцДт╣ЁсЂФУ╗йТИЏсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓуЅ╣сЂФтцДУдЈТеАсЂфтГдС╝џсѓётѕЮсѓЂсЂдсЂ«сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсЂДсЂ»сђЂтцќжЃесЃЉсЃ╝сЃѕсЃісЃ╝сЂ«Тћ»ТЈ┤сЂїТѕљтіЪсЂ«жЇхсЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
тЈѓтіаУђЁсЂИсЂ«СИЂт»ДсЂфсѓгсѓцсЃђсЃ│сѓ╣сЂесѓхсЃЮсЃ╝сЃѕ
сѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│тЈѓтіаУђЁсЂїсѓ╣сЃасЃ╝сѓ║сЂФтГдС╝џсЂФтЈѓтіасЂДсЂЇсѓІсѓѕсЂєсђЂС║ІтЅЇсЂФтѕєсЂІсѓісѓёсЂЎсЂёсѓисѓ╣сЃєсЃатѕЕућесЃъсЃІсЃЦсѓбсЃФсѓёFAQсѓњСйюТѕљсЂЌсђЂжЁЇтИЃсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїжЄЇУдЂсЂДсЂЎсђѓТјЦуХџТќ╣Т│ЋсђЂУ│фуќЉт┐юуГћсЂ«Тќ╣Т│ЋсђЂТіђУАЊуџёсЂфТјетЦеуњ░тбЃсЂфсЂЕсѓњУЕ│у┤░сЂФТАѕтєЁсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂДсђЂтйЊТЌЦсЂ«сЃѕсЃЕсЃќсЃФсѓњТюфуёХсЂФжў▓сЂљсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓсЂЙсЂЪсђЂжќІтѓгСИГсѓѓТіђУАЊсѓхсЃЮсЃ╝сЃѕсЂ«уфЊтЈБсѓњУеГсЂЉсђЂтЈѓтіаУђЁсЂІсѓЅсЂ«тЋЈсЂётљѕсѓЈсЂЏсЂФУ┐ЁжђЪсЂФт»Йт┐юсЂДсЂЇсѓІСйЊтѕХсѓњТЋ┤сЂѕсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂФсЂісЂЉсѓІжЂІтќХСИісЂ«Т│еТёЈуѓ╣
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂ»УцЄжЏЉсЂфтйбт╝ЈсЂДсЂѓсѓІсЂЪсѓЂсђЂжЂІтќХтЂ┤сЂїуЅ╣сЂФТ│еТёЈсЂЎсЂ╣сЂЇуѓ╣сЂїсЂёсЂЈсЂцсЂІтГўтюесЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сѓ╣сѓ┐сЃЃсЃЋсЂ«тй╣тЅ▓тѕєТІЁсЂеС║║тЊАжЁЇуй«сЂ«ТюђжЂЕтїќ
уЈЙтю░жЂІтќХуЈГсЂесѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│жЂІтќХуЈГсЂФТўјуб║сЂФтй╣тЅ▓сѓњтѕєсЂЉсђЂсЂЮсѓїсЂъсѓїсЂ«сЃЂсЃ╝сЃасЃфсЃ╝сЃђсЃ╝сѓњт«џсѓЂсЂдТїЄТЈ«у│╗ух▒сѓњсЂ»сЂБсЂЇсѓісЂЋсЂЏсѓІсЂЊсЂесЂїжЄЇУдЂсЂДсЂЎсђѓСЙІсЂѕсЂ░сђЂуЈЙтю░уЈГсЂ»С╝џта┤УеГтќХсѓётЈЌС╗ўсђЂсѓ┐сѓцсЃасѓГсЃ╝сЃЉсЃ╝сѓњТІЁтйЊсЂЌсђЂсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│уЈГсЂ»жЁЇС┐АТЊЇСйюсђЂсЃЂсЃБсЃЃсЃѕт»Йт┐юсђЂсЃфсЃбсЃ╝сЃѕУгЏТ╝ћУђЁсЂ«сѓ▒сѓбсЂфсЂЕсѓњТІЁтйЊсЂЎсѓІсЂфсЂЕсђЂтЁиСйЊуџёсЂФтй╣тЅ▓сѓњт«џсѓЂсЂЙсЂЎсђѓсѓ╣сѓ┐сЃЃсЃЋсЂїСИЇУХ│сЂЎсѓІта┤тљѕсЂ»сђЂтГдућЪсЃюсЃЕсЃ│сЃєсѓБсѓбсѓёТЦГтІЎтДћУеЌсЂФсѓѕсѓІт░ѓжќђсѓ╣сѓ┐сЃЃсЃЋсЂ«уб║С┐ЮсѓѓТцюУејсЂЌсђЂтЁетЊАсЂїУЄфтѕєсЂ«ТІЁтйЊсѓњУфЇУГўсЂЌсђЂтЇћтіЏсЂДсЂЇсѓІСйЊтѕХсѓњТЋ┤сЂѕсѓІсЂЊсЂесЂДсђЂтйЊТЌЦсЂ«жЂІтќХсЂїтєєТ╗ЉсЂФжђ▓сЂ┐сЂЙсЂЎсђѓ
сЃѕсЃЕсЃќсЃФуЎ║ућЪТЎѓсЂ«т»Йт┐юсЃъсЃІсЃЦсѓбсЃФТЋ┤тѓЎ
СИЇТИгсЂ«С║ІТЁІсЂФтѓЎсЂѕсђЂсЃѕсЃЕсЃќсЃФуЎ║ућЪТЎѓсЂ«т»Йт┐юсЃъсЃІсЃЦсѓбсЃФсѓњС║ІтЅЇсЂФТЋ┤тѓЎсЂЌсЂдсЂісЂЈсЂЊсЂесЂїСИЇтЈ»ТгасЂДсЂЎсђѓТЃ│т«џсЂЋсѓїсѓІсЃѕсЃЕсЃќсЃФ№╝ѕСЙІ№╝џжЁЇС┐АСИГТќГсђЂУгЏТ╝ћУђЁТјЦуХџСИЇУЅ»сђЂжЪ│тБ░сЃѕсЃЕсЃќсЃФсЂфсЂЕ№╝ЅсЂћсЂесЂФт»ЙтЄдТ│ЋсѓњтЁиСйЊуџёсЂФсЂЙсЂесѓЂсђЂтЁесѓ╣сѓ┐сЃЃсЃЋсЂДтЁ▒ТюЅсЂЌсђЂС║ІтЅЇсЃЪсЃ╝сЃєсѓБсЃ│сѓ░сЂДсѓисЃЪсЃЦсЃгсЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂЌсЂдсЂісЂЈсЂет«Ѕт┐ЃсЂДсЂЎсђѓсЃъсЃІсЃЦсѓбсЃФсѓњТЅІтЁЃсЂФуй«сЂЇсђЂСИЄСИђсЂ«С║ІТЁІсЂФсѓѓУ┐ЁжђЪсЂІсЂцух▒СИђуџёсЂфт»Йт┐юсЂїтЈќсѓїсѓІсѓѕсЂєсЂФсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂДсђЂтЈѓтіаУђЁсЂФт«Ѕт┐ЃТёЪсѓњСИјсЂѕсђЂУбФт«│сѓњТюђт░ЈжЎљсЂФТіЉсЂѕсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
УЉЌСйюТеЕсЃ╗сЃЌсЃЕсѓцсЃљсѓисЃ╝сЂИсЂ«жЁЇТЁ«сЂет»Йт┐юТќ╣жЄЮ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂДсЂ»сђЂТўатЃЈжЁЇС┐АсѓёУеўжї▓сЂїжќбсѓЈсѓІсЂЪсѓЂсђЂУЉЌСйюТеЕсЂесЃЌсЃЕсѓцсЃљсѓисЃ╝сЂИсЂ«жЁЇТЁ«сЂїжЮътИИсЂФжЄЇУдЂсЂДсЂЎсђѓуЎ║УАеУ│ЄТќЎсѓёУгЏТ╝ћтєЁт«╣сЂ«УЉЌСйюТеЕтЄдуљєсђЂтЈѓтіаУђЁсЂ«УѓќтЃЈТеЕсЂИсЂ«жЁЇТЁ«сђЂжЁЇС┐АсЂЋсѓїсЂЪсѓ│сЃ│сЃєсЃ│сЃёсЂ«тЈќсѓіТЅ▒сЂёсЂФсЂцсЂёсЂдсђЂТўјуб║сЂфТќ╣жЄЮсѓњт«џсѓЂсЂдтЈѓтіаУђЁсѓёуЎ║УАеУђЁсЂФС║ІтЅЇсЂФтЉеуЪЦсЂЎсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓжї▓ућ╗сѓ│сЃ│сЃєсЃ│сЃёсѓњсѓфсЃ│сЃЄсЃъсЃ│сЃЅжЁЇС┐АсЂЎсѓІта┤тљѕсѓѓсђЂжќбС┐ѓУђЁсЂІсѓЅжЂЕтѕЄсЂфУе▒УФЙсѓњтЙЌсѓІсѓѕсЂєсЂФсЂЌсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
сЂЙсЂесѓЂ№╝џсђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂДтГдУАЊС║цТхЂсЂ«ТюфТЮЦсѓњТІЊсЂЈ
сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂ»сђЂуЈЙС╗БсЂ«тГдУАЊсѓ│сЃЪсЃЦсЃІсЃєсѓБсЂїуЏ┤жЮбсЂЎсѓІУф▓жАїсЂФт»Йт┐юсЂЌсђЂтГдУАЊС║цТхЂсЂ«ТЕЪС╝џсѓњТІАтцДсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«т╝итіЏсЂфУДБТ▒║уГќсЂДсЂЎсђѓсѓфсЃ│сЃЕсѓцсЃ│сЂет»ЙжЮбсЂ«тѕЕуѓ╣сѓњУъЇтљѕсЂЋсЂЏсѓІсЂЊсЂесЂДсђЂсѓѕсѓітцџсЂЈсЂ«уаћуЕХУђЁсѓётГдућЪсЂїтЈѓтіасЂДсЂЇсѓІТЪћУ╗ЪсЂфуњ░тбЃсѓњТЈљСЙЏсЂЌсђЂтГдС╝џсЂ«Т┤╗ТђДтїќсЂФУ▓буї«сЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
уб║сЂІсЂФсђЂтЙЊТЮЦсЂ«жќІтѓгтйбт╝ЈсЂФТ»ћсЂ╣сЂдТ║ќтѓЎсѓёжЂІтќХсЂїУцЄжЏЉсЂФсЂфсѓІтЂ┤жЮбсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЎсЂїсђЂуХ┐т»єсЂфУеѕућ╗сђЂжЂЕтѕЄсЂфТіђУАЊсЂ«т░јтЁЦсђЂсЂЮсЂЌсЂдт░ѓжќђт«ХсЂесЂ«жђБТљ║сЂФсѓѕсЂБсЂдсђЂсЂЊсѓїсѓЅсЂ«Уф▓жАїсЂ»тЇЂтѕєсЂФтЁІТюЇтЈ»УЃйсЂДсЂЎсђѓсђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсЂ«ТѕљтіЪсЂ»сђЂтЇўсЂФтГдС╝џсѓњуёАС║ІсЂФухѓсЂѕсѓІсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈсђЂтГдУАЊуџёсЂфТѕљТъюсЂ«ТІАТЋБсѓњС┐Ѓжђ▓сЂЌсђЂуЪЦсЂ«С║цТхЂсѓњСИђт▒цТи▒сѓЂсѓІсЂЊсЂесЂФсЂцсЂфсЂїсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂюсЂ▓сђїтГдС╝џ сЃЈсѓцсЃќсЃфсЃЃсЃЅжќІтѓгсђЇсѓњуЕЇТЦхуџёсЂФт░јтЁЦсЂЌсђЂтГдУАЊсѓ│сЃЪсЃЦсЃІсЃєсѓБсЂ«ТюфТЮЦсѓњтЁ▒сЂФу»ЅсЂёсЂдсЂёсЂЇсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ