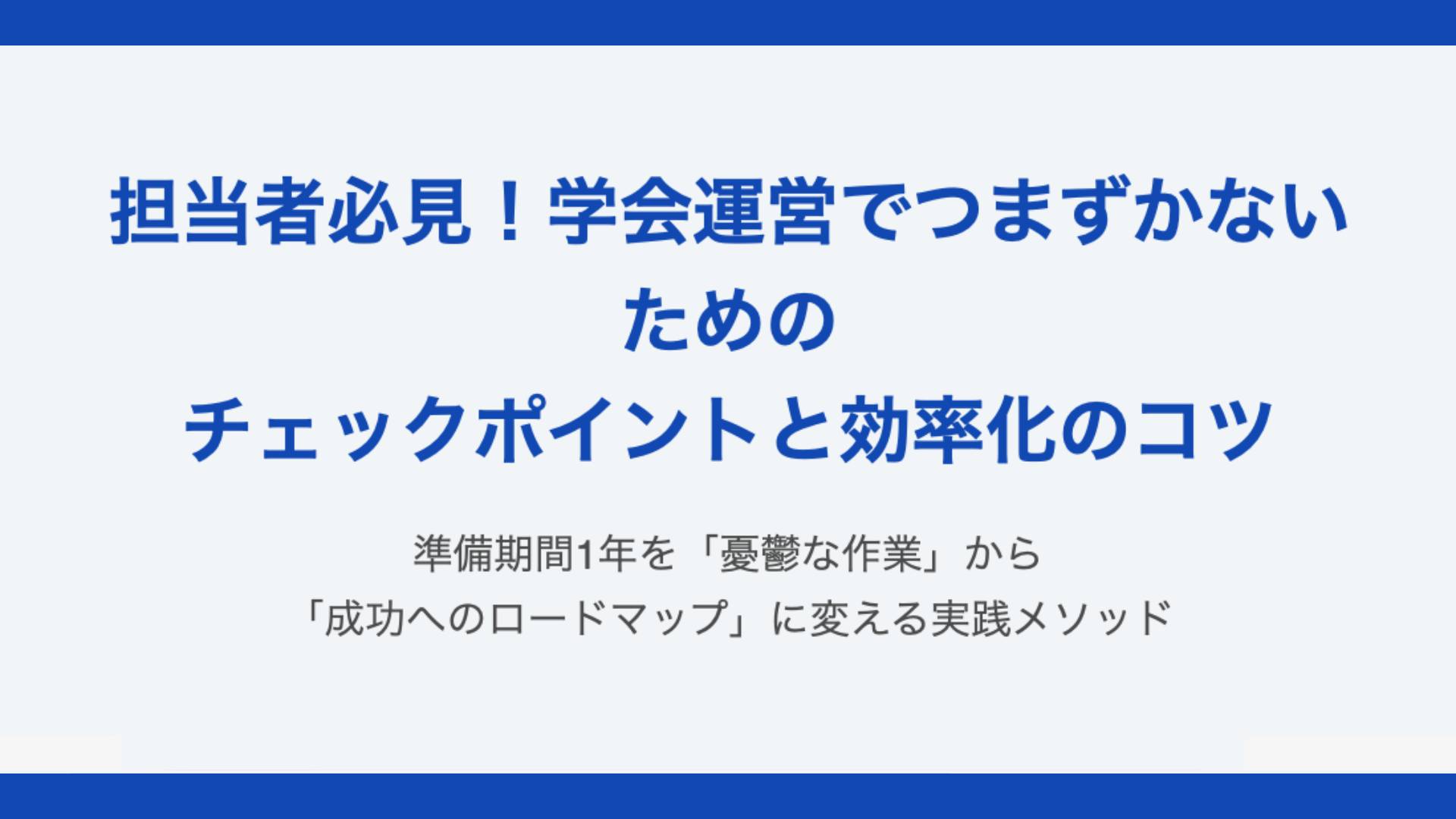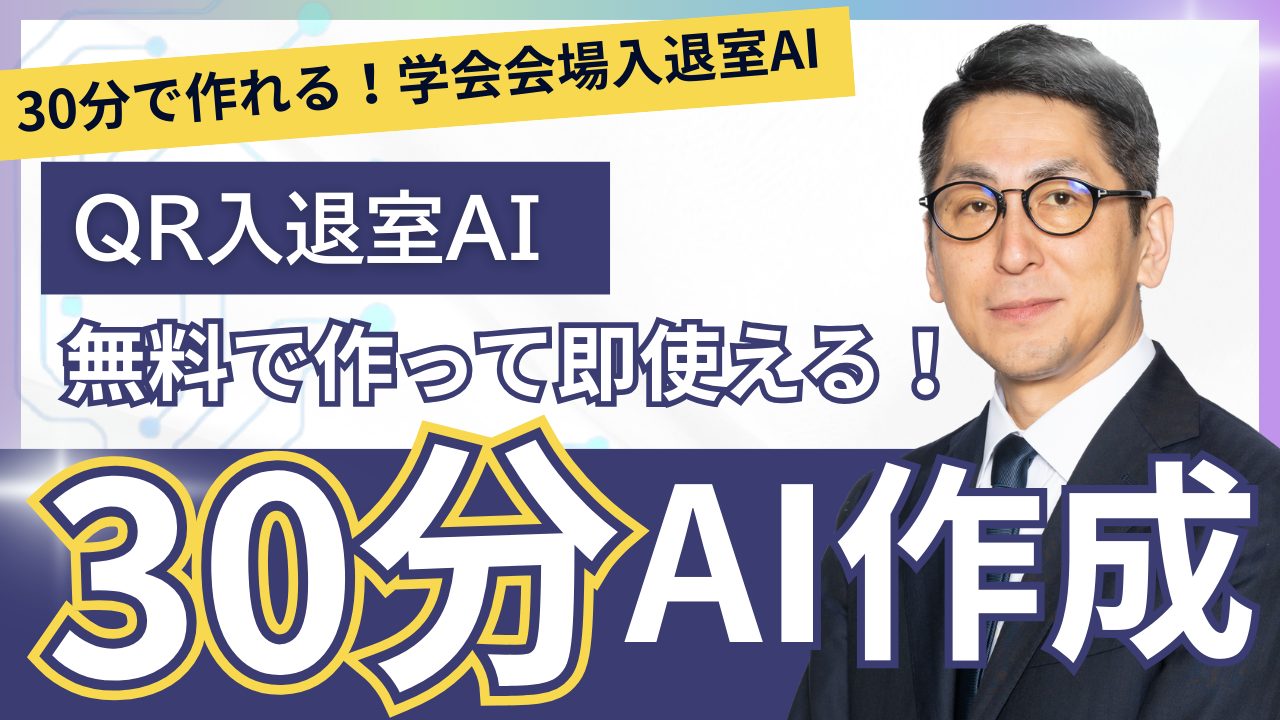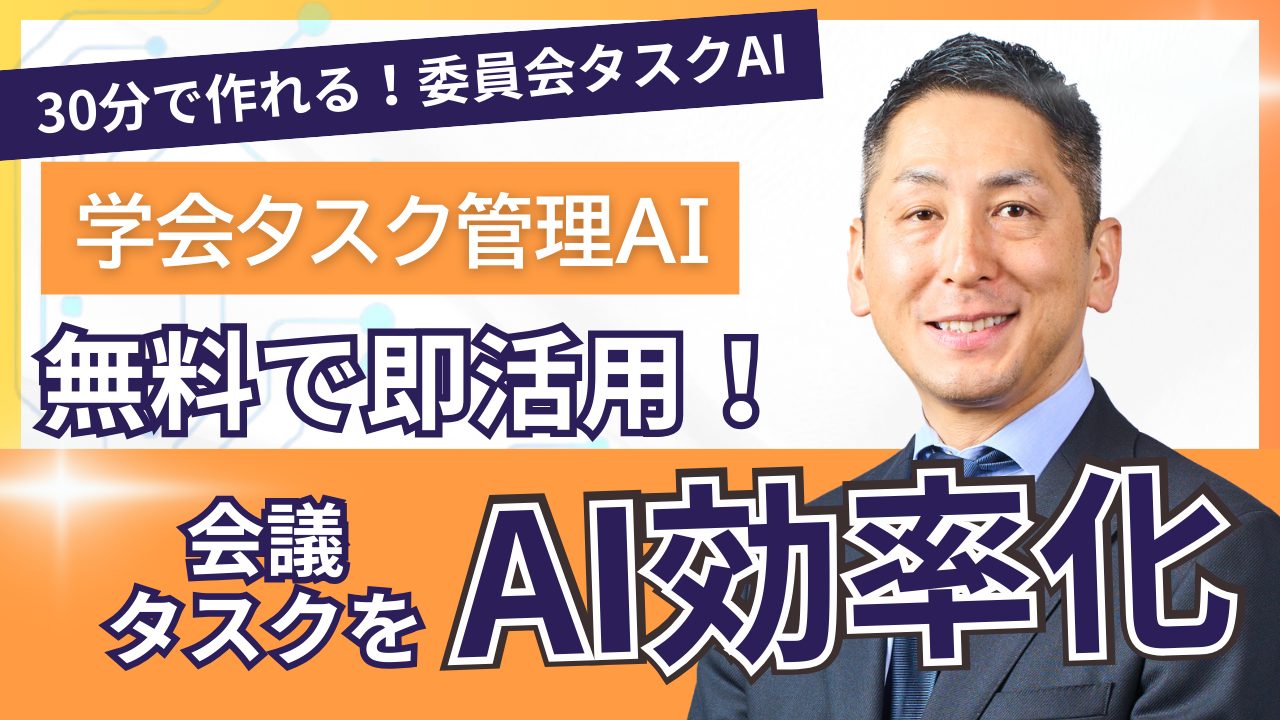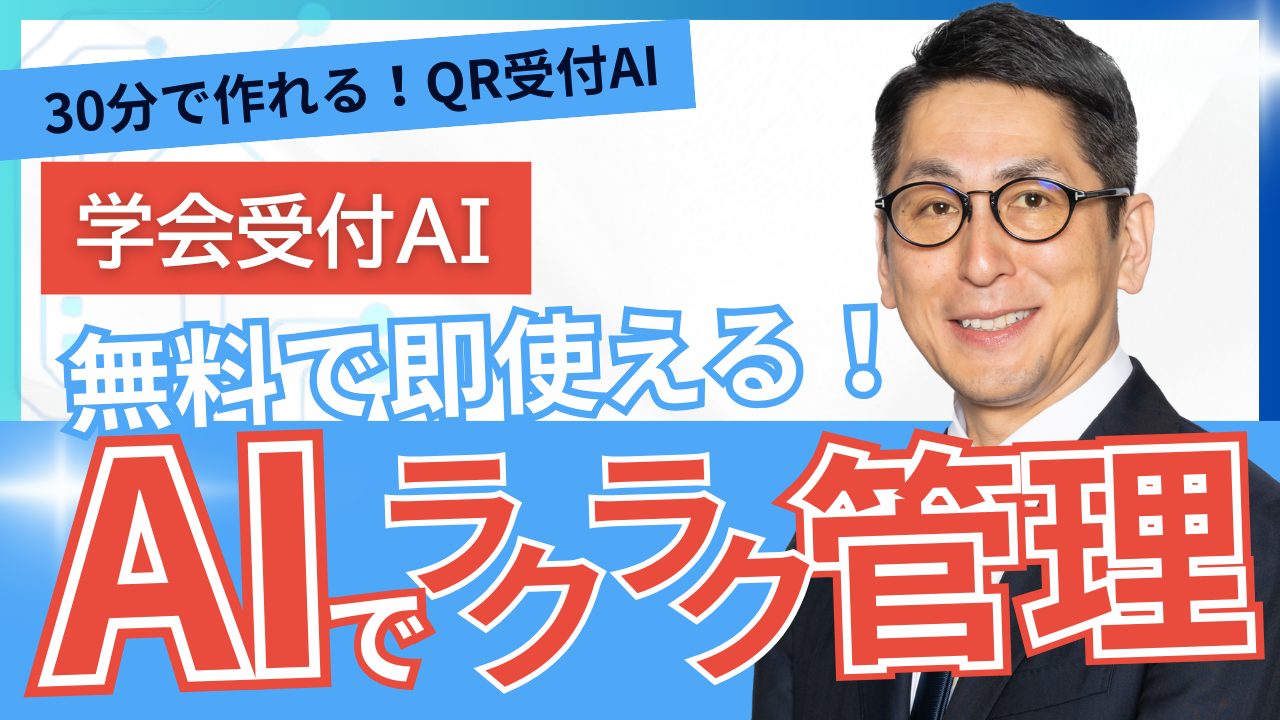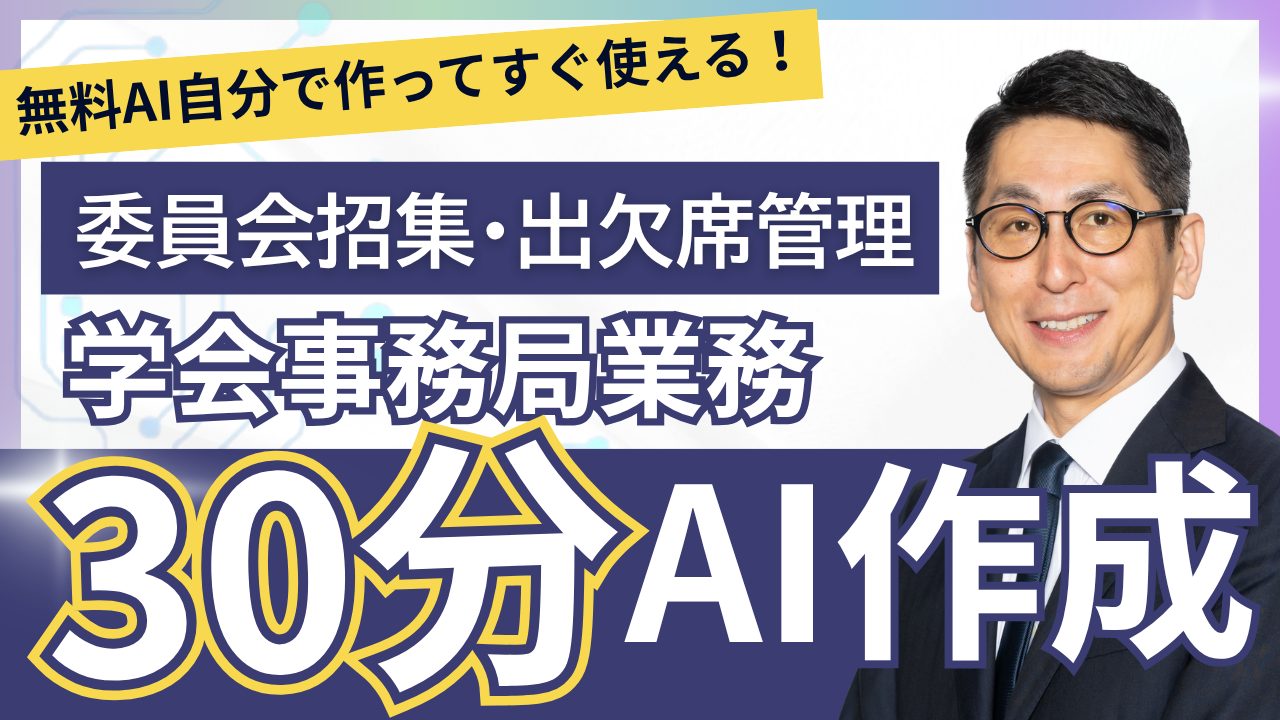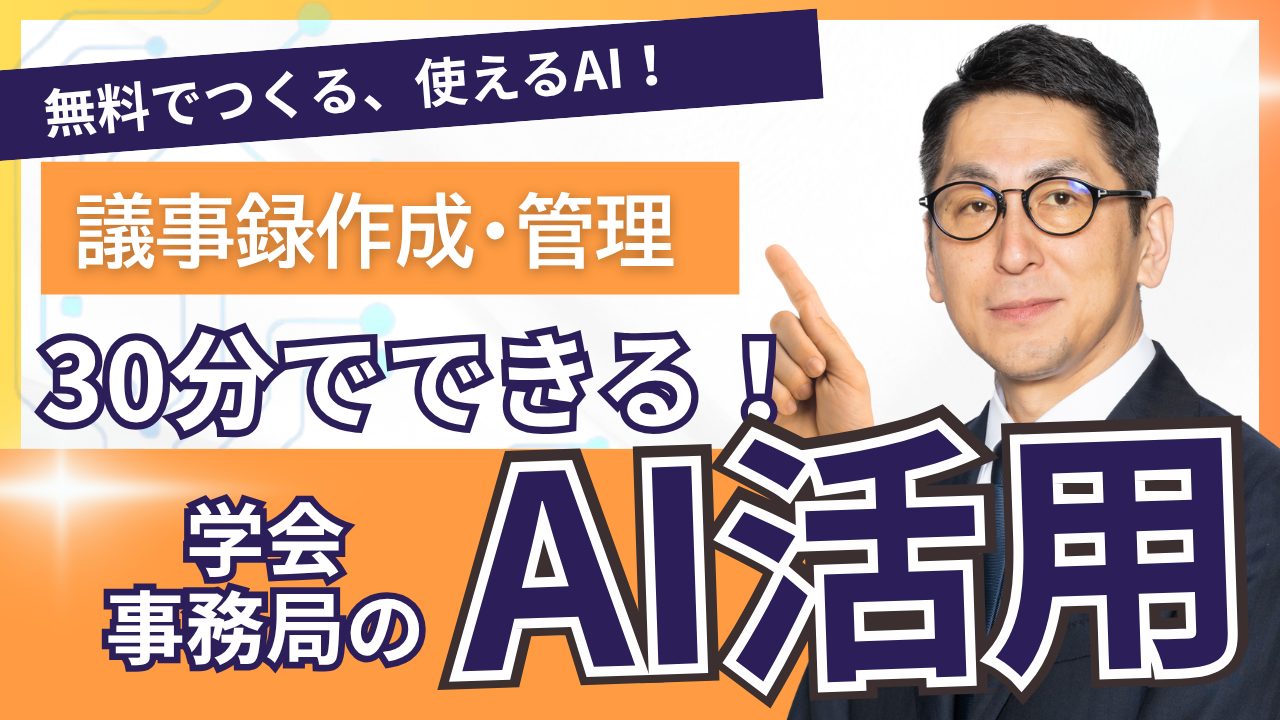еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲеҮҰзҗҶгӮ’гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«йҖІгӮҒгӮӢгҖҖпҪһгғҹгӮ№гӮ’йҳІгҒҗгғҒгӮ§гғғгӮҜгғқгӮӨгғігғҲгҒЁеҠ№зҺҮеҢ–гҒ®гӮігғ„пҪһ
2025е№ҙ08жңҲ19ж—Ҙ
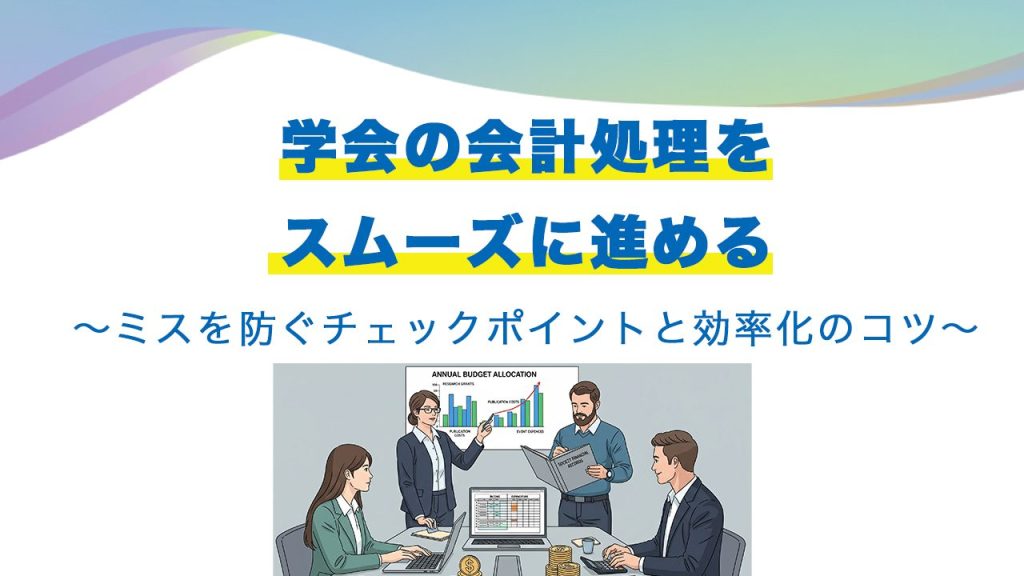
гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«гҖҖеӯҰдјҡгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®дјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҒЁгҒҜпјҹеӯҰдјҡдјҡиЁҲгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘзү№жҖ§гҒЁеҺҹеүҮ
еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢйҮ‘йҠӯз®ЎзҗҶгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзө„з№”гҒ®йҖҸжҳҺжҖ§гӮ„е…¬е…ұжҖ§гӮ’зӨәгҒҷйҮҚиҰҒгҒӘжҘӯеӢҷгҒ§гҒҷгҖӮгғ«гғјгғ«гӮ’е®ҲгӮҠгҖҒдёҒеҜ§гҒ«йҒӢз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиӘ°гҒ§гӮӮйҒ©еҲҮгҒ«йҒӮиЎҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҺеј•гҒҚз¶ҷгҒҺгҒҢгҒҶгҒҫгҒҸгҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гҖҸгҖҺжұәз®—дҪңжҘӯгҒ«иӢҰеҠҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҸгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжӮ©гҒҝгӮӮгҖҒжң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒ3гҒӨгҒ®гӮ№гғҶгғғгғ—гҒ§гҒ“гӮҢгӮүгҒ®жӮ©гҒҝгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘж–№жі•гӮ’и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еӯҰдјҡзү№жңүгҒ®дјҡиЁҲгғ«гғјгғ«гӮ„еҮҰзҗҶгғқгӮӨгғігғҲгӮ’дҪ“зі»зҡ„гҒ«ж•ҙзҗҶгҒ—гҖҒгғҹгӮ№гӮ’йҳІгҒҺгҒӘгҒҢгӮүе®үе®ҡгҒ—гҒҹжҘӯеӢҷйҒӮиЎҢгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғҠгғ“гӮІгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲеҮҰзҗҶгӮ’гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«йҖІгӮҒгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгғһгғӢгғҘгӮўгғ«дҪңжҲҗгҒЁPDCA пјҲPlan[иЁҲз”»]-Do[е®ҹиЎҢ]-Check[и©•дҫЎ]-Action[ж”№е–„]гҒ®4ж®өйҡҺпјүгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒ®гғ’гғігғҲгҒҢгҖҒйқһе–¶еҲ©еӣЈдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дҝЎй јжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгҖҒдјҡе“ЎгӮ„зӨҫдјҡгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиӘ¬жҳҺиІ¬д»»гӮ’жһңгҒҹгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢе®ҹеӢҷгҒ®гғҷгғјгӮ№гғ©гӮӨгғігҖҚгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’йЎҳгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
1. гғ«гғјгғ«гҒ«жІҝгҒЈгҒҹеҮҰзҗҶгҒҢгғҹгӮ№гҒ®дәҲйҳІгҒЁе®үеҝғж„ҹгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢ
еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҒ§жңҖгӮӮйҮҚиҰ–гҒҷгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒгҖҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгғ«гғјгғ«гҖҚпјҲеҗ„зЁ®жі•д»ӨгҖҒеӯҰдјҡиҰҸеүҮгҖҒеӣҪйҡӣеҹәжә–пјүгӮ’йҒөе®ҲгҒ—гҒҰжҘӯеӢҷгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®е®ҹи·өгҒҢгҖҒдјҡиЁҲдёҠгҒ®гғҹгӮ№гҒ®зҷәз”ҹгӮ’жңӘ然гҒ«йҳІгҒҺгҖҒй–ўдҝӮиҖ…е…Ёе“ЎгҒҢе®үеҝғгҒ—гҒҰеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«жҗәгӮҸгӮҢгӮӢеј·еӣәгҒӘеҹәзӣӨгӮ’зҜүгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
1.1. еӯҰдјҡдјҡиЁҲгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҹәжң¬зҡ„гҒӘдјҡиЁҲеҺҹеүҮгҒЁиҰҸзЁӢгҒ®зҗҶи§ЈгӮ’ж·ұгӮҒгӮӢ
еӯҰдјҡдјҡиЁҲгҒ®дјҒжҘӯдјҡиЁҲгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢзӢ¬иҮӘгҒ®зү№жҖ§
еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲгҒҜгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘдјҒжҘӯдјҡиЁҲгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢзӢ¬иҮӘгҒ®зү№жҖ§гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е–¶еҲ©гӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒӘгҒ„жҙ»еӢ•гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒдјҡе“ЎгҒӢгӮүгҒ®дјҡиІ»гӮ„еҜ„д»ҳйҮ‘гҖҒеӨ§дјҡеҸӮеҠ иІ»гҒӘгҒ©гҒҢдё»гҒӘеҸҺе…ҘжәҗгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒқгҒ®дҪҝйҖ”гҒҢеӯҰиЎ“жҢҜиҲҲгӮ„зӨҫдјҡиІўзҢ®гҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢзӮ№гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒҷгҖӮ
дёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәәгӮ„NPOжі•дәәгҒЁгҒ—гҒҰзҷ»иЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®жі•дәәж јгҒ«йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢдјҡиЁҲеҹәжә–гӮ„зү№е®ҡйқһе–¶еҲ©жҙ»еӢ•дҝғйҖІжі•пјҲNPOжі•пјүгҒ«е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹдјҡиЁҲеҺҹеүҮгҒ«еҫ“гҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзү№жҖ§гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҰйҒ©еҲҮгҒӘдјҡиЁҲеҮҰзҗҶгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеӯҰдјҡгҒ®еҒҘе…ЁгҒӘйҒӢе–¶гӮ’дҝқгҒЎгҖҒзӨҫдјҡгҒӢгӮүгҒ®дҝЎй јгӮ’зўәеӣәгҒҹгӮӢгӮӮгҒ®гҒ«гҒҷгӮӢдёҠгҒ§дёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«йҮ‘йҠӯгҒ®еҮәе…ҘгӮҠгӮ’иЁҳйҢІгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮдәҲз®—гҒ®зӯ–е®ҡгҒӢгӮүжұәз®—е ұе‘ҠгҒҫгҒ§гҒ®дёҖйҖЈгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒжҙ»еӢ•гҒ®йҖҸжҳҺжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒ—гҖҒдјҡе“ЎгҒёгҒ®иӘ¬жҳҺиІ¬д»»гӮ’жһңгҒҹгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҺҹеүҮгҒҜгҖҒдјҡиЁҲеёіз°ҝгҒ®жӯЈзўәгҒӘиЁҳеёігӮ„гҖҒиЁҲз®—жӣёйЎһгҒ®зңҹе®ҹжҖ§гҒ®жҳҺзӨәгҖҒдјҡиЁҲеҮҰзҗҶеҹәжә–гҒ®з¶ҷз¶ҡйҒ©з”ЁпјҲдјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҒ®жұәгҒҫгӮҠгҒҜдёҖеәҰжҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’жҜҺжңҹз¶ҷз¶ҡгҒҷгӮӢпјүгҒӘгҒ©гӮ’еҺігҒ—гҒҸжұӮгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӯҰдјҡеҶ…гҒ«зӢ¬иҮӘгҒ®дјҡиЁҲиҰҸзЁӢгӮ„зҙ°еүҮгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒҫгҒҡгҒқгӮҢгӮүгӮ’жіЁж„Ҹж·ұгҒҸзҶҹиӘӯгҒ—гҖҒеҶ…е®№гӮ’ж·ұгҒҸзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиӮқиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒеҸҺзӣҠдәӢжҘӯгҒ®жңүз„ЎгҖҒдјҡиІ»гҒ®еҸ–гӮҠжүұгҒ„гҖҒеҜ„д»ҳйҮ‘гҒ®дҪҝйҖ”еҲ¶йҷҗгҒӘгҒ©гҖҒеӯҰдјҡзү№жңүгҒ®й …зӣ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒи©ізҙ°гҒӘзўәиӘҚгҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иҰҸзЁӢгҒҜгҖҒеӯҰдјҡгҒ®иІЎеӢҷжҙ»еӢ•гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢжҶІжі•гҖҚгҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®дјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҒ®жҸәгӮӢгҒҺгҒӘгҒ„ж №жӢ гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгӮўгғ¬пјҹгҖҚгҒЁе°‘гҒ—гҒ§гӮӮж„ҹгҒҳгҒҹгӮүгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ«гҒӣгҒҡгҖҒеҝ…гҒҡдәӢеүҚгҒ«е°Ӯй–Җ家гӮ„й–ўдҝӮзңҒеәҒгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҖҒз–‘е•ҸгӮ’и§Јж¶ҲгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮеҗ„зЁ®гҒ®дјҡиЁҲеҹәжә–гӮ„жі•д»ӨгҒҜйғҪеәҰеӨүжӣҙгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжҖқгҒ„иҫјгҒҝгҒ§гҒ®еҮҰзҗҶгҒ«гҒҜгғӘгӮ№гӮҜгҒҢдјҙгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§иҰҒжіЁж„ҸгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»NPOжі•дәәгҒ®дјҡиЁҲгҒЁгҒҜпјҹ NPOжі•дәәдјҡиЁҲеҹәжә–гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒЁеҪ№еүІгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ігҒ—гҒҸи§ЈиӘ¬пҪңгғ•гғӘгғјж ӘејҸдјҡзӨҫ
гғ»зү№е®ҡйқһе–¶еҲ©жҙ»еӢ•дҝғйҖІжі•гҒ«гӮҲгӮҠиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹNPOжі•дәәгҒ®жі•дәәзЁҺжі•дёҠгҒ®еҸ–жүұгҒ„пҪңеӣҪзЁҺеәҒ
1.2. дәҲз®—зӯ–е®ҡгҒЁе®ҹзёҫз®ЎзҗҶгҒ§йҖҸжҳҺжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢ
еӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдјҡиЁҲгҒ®йҖҸжҳҺжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢдёҠгҒ§гҖҒдәҲз®—зӯ–е®ҡгҒҜжңҖеҲқгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮдәҲз®—гҒҜгҖҒеӯҰдјҡгҒҢд»ҠеҫҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҙ»еӢ•гҒ«гҖҒгҒ©гҒ®зЁӢеәҰгҒ®иіҮйҮ‘гӮ’жҠ•е…ҘгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгӮ’зӨәгҒҷе…·дҪ“зҡ„гҒӘиЁҲз”»гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӯҰдјҡгҒ®ж–№еҗ‘жҖ§гӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒҷгӮӢзҫ…йҮқзӣӨгҒ®еҪ№еүІгӮӮжһңгҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҸҺе…ҘгҒЁж”ҜеҮәгӮ’з¶ҝеҜҶгҒ«дәҲжё¬гҒ—гҖҒеҗ„дәӢжҘӯгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘиІ»з”ЁгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«иЁҲдёҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒ無駄гӮ’жҺ’гҒ—гҒҹеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘиіҮйҮ‘йҒӢз”ЁгҒҢе®ҹзҸҫеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮдәҲз®—зӯ–е®ҡеҫҢгҒҜгҖҒгҒқгҒ®дәҲз®—гҒЁе®ҹйҡӣгҒ®еҸҺж”ҜгӮ’жҜ”ијғгҒҷгӮӢе®ҹзёҫз®ЎзҗҶгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҡжңҹзҡ„гҒ«дәҲз®—гҒЁе®ҹзёҫгҒ®е·®з•°гӮ’и©ізҙ°гҒ«зўәиӘҚгҒ—гҖҒд№–йӣўгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҒқгҒ®еҺҹеӣ гӮ’еҫ№еә•зҡ„гҒ«еҲҶжһҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒдәҲз®—гҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гӮ„дәӢжҘӯиЁҲз”»гҒ®жҹ”и»ҹгҒӘиӘҝж•ҙгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәҲжңҹгҒӣгҒ¬иөӨеӯ—гҒ®зҷәз”ҹгӮ’жңӘ然гҒ«йҳІгҒҺгҖҒеҒҘе…ЁгҒӘиІЎеӢҷзҠ¶жіҒгӮ’з¶ӯжҢҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘеӯҰиЎ“еӨ§дјҡгӮ„еӣҪйҡӣдјҡиӯ°гӮ’й–ӢеӮ¬гҒҷгӮӢйҡӣгҒҜгҖҒеҸӮеҠ иҖ…ж•°гӮ„еұ•зӨәдјҡеҮәеұ•ж–ҷеҸҺе…ҘгҒӘгҒ©гҖҒеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢй …зӣ®гӮ’и©ізҙ°гҒ«дәҲжё¬гҒ—гҖҒжҹ”и»ҹгҒӘдәҲз®—з®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»еӣҪйҡӣеӯҰдјҡгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘдәҲз®—дҪңжҲҗгҒЁгҒҜпјҹ | гҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒ®еӯҰдјҡ.com
гғ»гҒ“гҒ“гҒҢзҹҘгӮҠгҒҹгҒ„гӮігғігғҷгғігӮ·гғ§гғігҖҢдәҲз®—дҪңжҲҗгҒЁеҸҺж”Ҝз®ЎзҗҶгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰпҪңж—Ҙжң¬ж”ҝеәңиҰіе…үеұҖпјҲJNTOпјү
2. ж”Ҝжү•гҒ„гғ»зІҫз®—гғ»иЁҳйҢІгҒ®жөҒгӮҢгӮ’ж•ҙзҗҶгҒ—гҖҒдҪңжҘӯиІ иҚ·гӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢ
ж—ҘгҖ…гҒ®дјҡиЁҲжҘӯеӢҷгӮ’еҶҶж»‘гҒ«йҖІгӮҒгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒж”Ҝжү•гҒ„гҖҒзІҫз®—гҖҒгҒқгҒ—гҒҰиЁҳйҢІгҒ®дёҖйҖЈгҒ®жөҒгӮҢгӮ’жҳҺзўәгҒ«ж•ҙзҗҶгҒ—гҖҒеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘд»•зө„гҒҝгӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒе®ҹеӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒ®дҪңжҘӯиІ иҚ·гӮ’еӨ§е№…гҒ«и»ҪжёӣгҒ—гҖҒдјҡиЁҲдёҠгҒ®гғҹгӮ№гӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«жҠ‘еҲ¶гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
2.1. еҠ№зҺҮзҡ„гҒӘж”Ҝжү•гҒ„гғ»зІҫз®—гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’ж§ӢзҜүгҒҷгӮӢ
еӯҰдјҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж”Ҝжү•гҒ„гҒЁзІҫз®—гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’еҠ№зҺҮеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжҘӯеӢҷгҒ®иҝ…йҖҹеҢ–гҒЁжӯЈзўәжҖ§гҒ®еҗ‘дёҠгҒ«зӣҙзөҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҖҒж”Ҝжү•гҒ„гҒ®йҡӣгҒ«гҒҜгҖҒи«ӢжұӮжӣёгҒ®еҸ—й ҳгҒӢгӮүжүҝиӘҚгҖҒйҠҖиЎҢжҢҜиҫјгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ®жүӢй ҶгӮ’жҳҺзўәгҒ«е®ҡгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢиӮқиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
еҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеӯҰдјҡеҗҚзҫ©гҒ®йҠҖиЎҢеҸЈеә§гҒӢгӮүгҒ®жҢҜиҫјгӮ’еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҖҒж”ҜеҮәгҒ®дәӢе®ҹгҒЁйҮ‘йЎҚгӮ’жҳҺзўәгҒ«иЁҳйҢІгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгғҚгғғгғҲйҠҖиЎҢпјҲжҘҪеӨ©йҠҖиЎҢгӮ„дҪҸдҝЎSBIгғҚгғғгғҲйҠҖиЎҢгҖҒгӮӨгӮӘгғійҠҖиЎҢгҒӘгҒ©пјүгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҗ„зЁ®гғҮгғјгӮҝгҒ®еёізҘЁгӮ’гҒ„гҒӨгҒ§гӮӮе®үдҫЎгҒ«еҸ–гӮҠеҮәгҒӣгӮӢгҒҹгӮҒдҫҝеҲ©гҒ§гҒҷгҖӮ
е°‘йЎҚгҒ®дәӨйҖҡиІ»гҒӘгҒ©гҖҒй ҳеҸҺжӣёгӮ’еҫҙгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„гӮӮгҒ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеҮәйҮ‘дјқзҘЁгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒж”ҜеҮәгҒ®дәӢе®ҹгҖҒйҮ‘йЎҚгҖҒ科зӣ®гӮ’и©ізҙ°гҒ«иЁҳйҢІгғ»дҝқз®ЎгҒҷгӮӢгғ«гғјгғ«гӮ’еҫ№еә•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢй ҳеҸҺжӣёгҒҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜеҮәйҮ‘дјқзҘЁгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҖҒдҪ•гҒ«гҒ„гҒҸгӮүдҪҝгҒЈгҒҹгҒӢгӮ’жҳҺзўәгҒ«иЁҳйҢІгҒҷгӮӢгҖҚпјҲгҖҮгҖҮ委員дјҡгҒ®дәӨйҖҡиІ»2,000еҶҶгӮ’з«ӢгҒҰжӣҝгҒҲгҒҹе ҙеҗҲпјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…·дҪ“зҡ„гҒӘгғ«гғјгғ«гӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
зөҢиІ»зІҫз®—гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒй ҳеҸҺжӣёгҒ®з®ЎзҗҶгҒҢзү№гҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеӯҰдјҡеҸӮеҠ иІ»гӮ„дәӨйҖҡиІ»гҒӘгҒ©гҖҒзөҢиІ»гҒЁгҒ—гҒҰиЁҲдёҠгҒҷгӮӢе…ЁгҒҰгҒ®й …зӣ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж”Ҝжү•йҮ‘йЎҚгӮ„ж—Ҙд»ҳгҒҢжҳҺиЁҳгҒ•гӮҢгҒҹй ҳеҸҺжӣёгӮ’зўәе®ҹгҒ«дҝқз®ЎгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒй–ўдҝӮиҖ…гҒёгҒ®е‘ЁзҹҘеҫ№еә•гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгӮӮгҖҢжүӢжӣёй ҳеҸҺжӣёгҖҚгҒҜйҒҝгҒ‘гҒҰгҖҒгғ¬гӮёгҒ®гғ¬гӮ·гғјгғҲгӮ„гғ—гғӘгғігғҲгӮўгӮҰгғҲгҒ•гӮҢгҒҹй ҳеҸҺиЁјгҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжі•дәәгӮ«гғјгғүпјҲVISAгӮ„MasterCardгҒӘгҒ©пјүгҒ®е°Һе…ҘгҒҜгҖҒз«Ӣжӣҝжү•гҒ„гӮ’и§Јж¶ҲгҒ—гҖҒзөҢиІ»гҒ®гғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ жҠҠжҸЎгӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒзІҫз®—жҘӯеӢҷгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гҒ«еӨ§гҒҚгҒҸиІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҮәејөгҒ«дјҙгҒҶж—ҘеҪ“гҒ®ж”ҜзөҰгӮӮгҖҒе®ҹиІ»зІҫз®—гҒ®жүӢй–“гӮ’зңҒгҒҚгҖҒжҘӯеӢҷеҠ№зҺҮеҢ–гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғ«гғјгғ«гҒҜгҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒ«иҰӢзӣҙгҒ—гҖҒеӯҰдјҡгҒ®е®ҹж…ӢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰжҹ”и»ҹгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
2.2. дјҡиЁҲиЁҳйҢІгҒ®жӯЈзўәжҖ§гҒЁдҝқз®ЎгӮ’еҫ№еә•гҒҷгӮӢ
е…ЁгҒҰгҒ®дјҡиЁҲеҸ–еј•гҒҜгҖҒжӯЈзўәгҒӢгҒӨгӮҝгӮӨгғ гғӘгғјгҒ«иЁҳйҢІгҒ•гӮҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҸҺе…ҘгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒдјҡиІ»гҖҒеӨ§дјҡеҸӮеҠ иІ»гҖҒеҜ„д»ҳйҮ‘гҒӘгҒ©гӮ’гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢйҒ©еҲҮгҒӘеӢҳе®ҡ科зӣ®гҒ§д»•иЁіпјҲеҸ–еј•еҶ…е®№гӮ’еӢҳе®ҡ科зӣ®гҒ«еҲҶгҒ‘гҒҰиЁҳйҢІгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁпјүгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒж¶ҲиІ»зЁҺгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеӯҰдјҡиІ»пјҲе№ҙдјҡиІ»пјүгҒҜиӘІзЁҺеҜҫиұЎеӨ–пјҲдёҚиӘІзЁҺпјүгҒЁгҒ—гҒҰжүұгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒи¬ӣзҝ’дјҡеҸӮеҠ иІ»гӮ„жҮҮиҰӘдјҡеҸӮеҠ иІ»гҒӘгҒ©гҒҜиӘІзЁҺеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҸ–гӮҠжүұгҒ„гҒ«гҒҜзҙ°еҝғгҒ®жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮзЁҺеҲ¶дёҠгҒ®еҢәеҲҶпјҲиӘІзЁҺ/йқһиӘІзЁҺ/дёҚиӘІзЁҺ/е…ҚзЁҺпјүгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒ—гҒҰиҮЁгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗзЁҺеҲ¶дёҠгҒ®еҢәеҲҶпјҲиӘІзЁҺ/йқһиӘІзЁҺ/дёҚиӘІзЁҺ/е…ҚзЁҺпјүгҒЁе…·дҪ“дҫӢгҖ‘
| еҢәеҲҶ | жҰӮиҰҒ | д»ЈиЎЁзҡ„гҒӘеҸ–еј•дҫӢ |
| иӘІзЁҺ | ж¶ҲиІ»зЁҺгҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢеҸ–еј• | жҠ„йҢІйӣҶгғ»и¬ӣжј”иҰҒж—ЁгҒ®иІ©еЈІгҖҒйҖҡдҝЎиІ»гҖҒеҚ°еҲ·д»ЈгҖҒи¬ӣзҝ’дјҡеҸӮеҠ иІ»гҖҒжҮҮиҰӘдјҡеҸӮеҠ иІ»гҖҒеұ•зӨәж–ҷпјҲдјҒжҘӯеҮәеұ•гғ–гғјгӮ№зӯүпјүгҒӘгҒ© |
| йқһиӘІзЁҺ | жі•д»ӨгҒ«гӮҲгӮҠж¶ҲиІ»зЁҺгҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„еҸ–еј• | еӯҰдјҡгҒ®й җйҮ‘гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҲ©жҒҜгҖҒдҝқйҷәж–ҷгҒӘгҒ© |
| дёҚиӘІзЁҺ | ж¶ҲиІ»зЁҺгҒ®еҜҫиұЎеӨ– | дјҡе“ЎгҒӢгӮүгҒ®е№ҙдјҡиІ»гғ»е…ҘдјҡйҮ‘гҖҒдјҡе“ЎгҒӢгӮүгҒ®еӨ§дјҡеҸӮеҠ иІ»гҖҒжө·еӨ–гҒ®еӯҰдјҡгҒёгҒ®еҸӮеҠ иІ»гҒӘгҒ© |
| е…ҚзЁҺ | жқЎд»¶гҒ«гӮҲгӮҠж¶ҲиІ»зЁҺгҒҢе…ҚйҷӨгҒ•гӮҢгӮӢеҸ–еј• | жө·еӨ–гҒ®иіје…ҘиҖ…гҒёгҒ®еӯҰдјҡиӘҢгҒӘгҒ©гҒ®зӣҙжҺҘиІ©еЈІгҖҒеӣҪйҡӣйғөдҫҝгҒ§гҒ®еӯҰдјҡиӘҢгҒ®йҖҒд»ҳгҒӘгҒ© |
пјҲеҮәе…ёпјҡеӣҪзЁҺеәҒWebгӮөгӮӨгғҲгӮ’еҸӮиҖғгҒ«дҪңжҲҗпјү
ж”ҜеҮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒдјҡиӯ°иІ»гҖҒж—…иІ»дәӨйҖҡиІ»гҖҒеҚ°еҲ·иЈҪжң¬иІ»гҒӘгҒ©гҖҒзҙ°гҒӢгҒҸеҲҶйЎһгҒ—гҒҰиЁҳйҢІгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҫҢгҒӢгӮүгҒ®жӨңиЁјгҒҢж јж®өгҒ«е®№жҳ“гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дјҡиЁҲеёіз°ҝгҒҜгҖҒжӯЈиҰҸгҒ®з°ҝиЁҳгҒ®еҺҹеүҮгҒ«еҫ“гҒЈгҒҰжӯЈгҒ—гҒҸиЁҳеёігҒ—гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҸ–еј•гҒҢй ҳеҸҺжӣёгҒӘгҒ©гҒ®е®ўиҰізҡ„гҒӘиЁјжӢ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзўәиӘҚгҒ§гҒҚгӮӢжӨңиЁјжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеј·гҒҸжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒдёҖеәҰжҺЎз”ЁгҒ—гҒҹдјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҒ®еҹәжә–гӮ„жүӢз¶ҡгҒҚгҒҜгҖҒжҜҺдәӢжҘӯе№ҙеәҰз¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҰйҒ©з”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҝгҒ гӮҠгҒ«еӨүжӣҙгҒ—гҒӘгҒ„з¶ҷз¶ҡжҖ§гҒ®еҺҹеүҮгӮ’е®ҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒе№ҙеәҰжҜ”ијғгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иЁҳйҢІгҒҜгҖҒе°ҶжқҘгҒ®зӣЈжҹ»гӮ„зЁҺеӢҷз”іе‘ҠгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒдәӢжҘӯе№ҙеәҰгҒ”гҒЁгҒ®жҜ”ијғеҲҶжһҗгҒ«гӮӮеҪ№з«ӢгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮзү©зҗҶзҡ„гҒӘжӣёйЎһгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғҮгӮёгӮҝгғ«гғҮгғјгӮҝгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰгҖҒе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹжңҹй–“гҖҒйҒ©еҲҮгҒ«дҝқз®ЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»еӯҰдјҡиІ»з”ЁгҒ®еӢҳе®ҡ科зӣ®гҒҜпјҹ | гҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒ®еӯҰдјҡ.com
гғ»гҖҗеӣіи§ЈгҖ‘иӘІзЁҺгғ»йқһиӘІзЁҺгғ»дёҚиӘІзЁҺгғ»е…ҚзЁҺгҒ®йҒ•гҒ„|ж¶ҲиІ»зЁҺгҒ®еҢәеҲҶпҪңзөҢзҗҶгҒ®гҒҠд»•дәӢ.com
2.3. дјҡиЁҲгӮҪгғ•гғҲе°Һе…ҘгҒ§еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲжҘӯеӢҷгӮ’еҠ№зҺҮеҢ–
еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲеҮҰзҗҶгӮ’гҒ•гӮүгҒ«гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒдјҡиЁҲгӮҪгғ•гғҲгҒ®е°Һе…ҘгӮӮжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮгҖҢNPOжі•дәәгҖҚгҖҢдёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәәгҖҚгҒ«гӮӮеҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҪгғ•гғҲгҒ®йҒёе®ҡгҒҜеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гӮҜгғ©гӮҰгғүеһӢгӮҪгғ•гғҲгҒҜпјҲдҫӢпјҡгҖҢгғһгғҚгғјгғ•гӮ©гғҜгғјгғүгӮҜгғ©гӮҰгғүгҖҚпјүгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨ§гҒҚгҒӘгғЎгғӘгғғгғҲгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
(1) дҪңжҘӯгҒ®иҮӘеӢ•еҢ–гҒЁгғҹгӮ№еүҠжёӣ
йҠҖиЎҢеҸЈеә§йҖЈжҗәгҒ§еҸ–еј•гӮ’иҮӘеӢ•д»•иЁігҒ—гҖҒе…ҘеҠӣгҒ®гғҹгӮ№гӮ’еӨ§е№…гҒ«еүҠжёӣгҖӮзөҢиІ»зІҫз®—гӮӮгӮ№гғһгғӣгҒ§е®ҢзөҗгҒ—гғҡгғјгғ‘гғјгғ¬гӮ№еҢ–гҒҢйҖІгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
(2) гғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒӘиІЎеӢҷжҠҠжҸЎ
жңҖж–°гҒ®еҸҺж”ҜзҠ¶жіҒгӮ„иіҮйҮ‘ж®Ӣй«ҳгӮ’гҒ„гҒӨгҒ§гӮӮзўәиӘҚгҒ§гҒҚгҖҒдәҲз®—е®ҹзёҫз®ЎзҗҶгӮ„иҝ…йҖҹгҒӘж„ҸжҖқжұәе®ҡгӮ’ж”ҜжҸҙгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
(3) жұәз®—жҘӯеӢҷгҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гҒЁеј•гҒҚз¶ҷгҒҺгҒ®е®№жҳ“гҒ•
еҝ…иҰҒгҒӘеёізҘЁгҒҢиҮӘеӢ•з”ҹжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒжұәз®—дҪңжҘӯгҒ®иІ жӢ…гӮ’и»ҪжёӣгҖӮгғҮгғјгӮҝгҒҢгӮ·гӮ№гғҶгғ еҶ…гҒ«йӣҶзҙ„гҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжӢ…еҪ“иҖ…й–“гҒ®жғ…е ұе…ұжңүгӮ„еј•гҒҚз¶ҷгҒҺгӮӮгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дјҡиЁҲгӮҪгғ•гғҲйҒёе®ҡжҷӮгҒҜгҖҒйқһе–¶еҲ©дјҡиЁҲгҒёгҒ®еҜҫеҝңгҖҒдҪҝгҒ„гӮ„гҒҷгҒ•гҖҒгӮөгғқгғјгғҲдҪ“еҲ¶гҖҒиІ»з”ЁеҜҫеҠ№жһңгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгӮ»гӮӯгғҘгғӘгғҶгӮЈгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮз„Ўж–ҷгғҲгғ©гӮӨгӮўгғ«гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«ж“ҚдҪңж„ҹгӮ’и©ҰгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
йҒ©еҲҮгҒӘдјҡиЁҲгӮҪгғ•гғҲгӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲжҘӯеӢҷгҒҜгӮҲгӮҠеҠ№зҺҮзҡ„гҒ§дҝЎй јжҖ§гҒ®й«ҳгҒ„гӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҗдјҡиЁҲгӮҪгғ•гғҲе°Һе…ҘгҒ«гӮҲгӮӢеҠ№жһңгҖ‘вҖ»е°ҸиҰҸжЁЎеӯҰдјҡпјҲдјҡе“Ўж•°100еҗҚд»ҘдёӢпјүгҒ®дәӢдҫӢ
| й …зӣ® | е°Һе…ҘеүҚгҒ®иӘІйЎҢ | е°Һе…ҘеҫҢгҒ®еҠ№жһң |
| дјҡиЁҲеҮҰзҗҶ | жӢ…еҪ“иҖ…гҒҢжүӢдҪңжҘӯгҒ§ExcelгҒ«гғҮгғјгӮҝгӮ’е…ҘеҠӣгҖӮе…ҘеҠӣгғҹгӮ№гӮ„иЁҲз®—гғҹгӮ№гҒҢй »зҷәгҖӮжҜҺе№ҙгҖҒжұәз®—дҪңжҘӯгҒ«иҶЁеӨ§гҒӘжҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ | гӮҜгғ©гӮҰгғүеһӢдјҡиЁҲгӮҪгғ•гғҲгӮ’е°Һе…ҘгҖӮйҠҖиЎҢеҸЈеә§гҒЁгҒ®иҮӘеӢ•йҖЈжҗәгҒ§гҖҒе…ҘеҮәйҮ‘гғҮгғјгӮҝгҒҢиҮӘеӢ•гҒ§еҸ–гӮҠиҫјгҒҫгӮҢгҖҒд»•иЁідҪңжҘӯгҒҢдёҚиҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮжӢ…еҪ“иҖ…гҒ®е…ҘеҠӣгғҹгӮ№гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒдҪңжҘӯжҷӮй–“гҒҢ7еүІеүҠжёӣгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ |
| зөҢиІ»зІҫз®— | й ҳеҸҺжӣёгӮ’зҙҷгҒ§з®ЎзҗҶгҖӮзҙӣеӨұгғӘгӮ№гӮҜгӮ„дҝқз®Ўе ҙжүҖгҒ«еӣ°гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮзІҫз®—жүӢз¶ҡгҒҚгҒҢз…©йӣ‘гҖӮз«ӢгҒҰжӣҝгҒҲжү•гҒ„гҒҢеӨҡгҒҸгҖҒжӢ…еҪ“иҖ…гҒ®иІ жӢ…гҒҢеӨ§гҒҚгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ | дјҡиЁҲгӮҪгғ•гғҲгҒ®гӮ№гғһгғӣгӮўгғ—гғӘгӮ’жҙ»з”ЁгҖӮжӢ…еҪ“иҖ…гҒҜй ҳеҸҺжӣёгӮ’гӮ№гғһгғӣгҒ§ж’®еҪұгғ»гӮўгғғгғ—гғӯгғјгғүгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§зөҢиІ»зІҫз®—гҒҢе®ҢдәҶгҖӮгғ¬гӮ№гғҡгғјгғ‘гғјеҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ гҖӮгҒ„гҒӨгҒ§гӮӮгҒ©гҒ“гҒ§гӮӮзІҫз®—гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ |
| еј•гҒҚз¶ҷгҒҺ | жӢ…еҪ“иҖ…гҒ”гҒЁгҒ«ExcelгҒ®гғ•гӮ©гғјгғһгғғгғҲгҒҢйҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгғһгғӢгғҘгӮўгғ«гӮӮдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҖҒеј•гҒҚз¶ҷгҒҺгҒ«2гҖң3гғ¶жңҲгӮ’иҰҒгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ | жӢ…еҪ“иҖ…й–“гҒ®гғҮгғјгӮҝе…ұжңүгҒҢе®№жҳ“гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеј•гҒҚз¶ҷгҒҺдҪңжҘӯгҒҢеӨ§е№…гҒ«з°Ўзҙ еҢ–гҖӮгӮ·гӮ№гғҶгғ еҶ…гҒ«йҒҺеҺ»гҒ®гғҮгғјгӮҝгҒҢгҒҷгҒ№гҒҰйӣҶзҙ„гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжӢ…еҪ“иҖ…д»ҘеӨ–гҒ§гӮӮзҸҫзҠ¶гӮ’жҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ |
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»гҖҗ2025е№ҙзүҲгҖ‘е…¬зӣҠжі•дәәеҗ‘гҒ‘дјҡиЁҲгӮҪгғ•гғҲжҜ”ијғгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒ8йҒёпјҒйҒёгҒіж–№гҒ®гғқгӮӨгғігғҲгӮӮи§ЈиӘ¬пҪңгғҹгғ„гғўгӮў
гғ»NPOжі•дәәдјҡиЁҲеҹәжә–гҒЁгҒҜпјҹеҹәжң¬гҒ®иҖғгҒҲж–№гӮ„ж§ӢжҲҗгҒ®и§ЈиӘ¬пҪңж ӘејҸдјҡзӨҫгғһгғҚгғјгғ•гӮ©гғҜгғјгғү
3. еӨ–йғЁзӣЈжҹ»гғ»зЁҺеӢҷз”іе‘ҠгҒёгҒ®еҜҫеҝңгҒЁжғ…е ұе…¬й–ӢгҒ®иҰ–зӮ№
еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҒҜгҖҒеҶ…йғЁзҡ„гҒӘз®ЎзҗҶгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒеӨ–йғЁгҒӢгӮүгҒ®зӣЈжҹ»гӮ„зЁҺеӢҷз”іе‘ҠгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдјҡе“ЎгҒёгҒ®жғ…е ұе…¬й–ӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҒҙйқўгӮӮжҢҒгҒЎеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еӨ–йғЁгҒЁгҒ®гӮ„гӮҠеҸ–гӮҠгӮ’йҒ©еҲҮгҒӢгҒӨеҶҶж»‘гҒ«иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӯҰдјҡгҒ®дҝЎй јжҖ§гҒҜгҒ•гӮүгҒ«жҸәгӮӢгҒҺгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеӯҰдјҡгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ§гҒҜгҖҒиІЎеӢҷзҠ¶жіҒгӮ’й–ӢзӨәгҒҷгӮӢгғҡгғјгӮёгӮ’еҲ¶дҪңгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
3.1. еӨ–йғЁзӣЈжҹ»гҒёгҒ®жә–еӮҷгҒЁзЁҺеӢҷз”іе‘ҠгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгӮ’жҠјгҒ•гҒҲгӮӢ
иҰҸжЁЎгҒ®еӨ§гҒҚгҒ„еӯҰдјҡгӮ„гҖҒзү№е®ҡгҒ®жі•дәәж јгӮ’жҢҒгҒӨеӯҰдјҡгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеӨ–йғЁзӣЈжҹ»гҒҢзҫ©еӢҷд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеӨ–йғЁзӣЈжҹ»гҒҜгҖҒеӯҰдјҡгҒ®иІЎеӢҷи«ёиЎЁгҒҢйҒ©жӯЈгҒ«дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹ第дёүиҖ…гҒҢжӨңиЁјгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӯҰдјҡдјҡиЁҲгҒ®дҝЎй јжҖ§гӮ’жӢ…дҝқгҒҷгӮӢдёҠгҒ§йҮҚиҰҒгҒӘгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ
зӣЈжҹ»гҒ«йҡӣгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒдјҡиЁҲеёіз°ҝгҖҒй ҳеҸҺжӣёгҖҒи«ӢжұӮжӣёгҖҒйҠҖиЎҢй җйҮ‘йҖҡеёігҒӘгҒ©гҖҒе…ЁгҒҰгҒ®й–ўйҖЈжӣёйЎһгӮ’ж•ҙзҗҶгҒ—гҖҒгҒ„гҒӨгҒ§гӮӮжҸҗзӨәгҒ§гҒҚгӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеүҚеӣһгҒ®зӣЈжҹ»гҒ§жҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҹж”№е–„дәӢй …гҒ®жҳҜжӯЈзҠ¶жіҒгӮӮжӯЈзўәгҒ«жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒе ұе‘ҠгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жә–еӮҷгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеӯҰдјҡгҒҜйқһе–¶еҲ©еӣЈдҪ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒжі•дәәзЁҺжі•гҒ«е®ҡгӮҒгӮӢеҸҺзӣҠдәӢжҘӯгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒзЁҺеӢҷз”іе‘ҠгҒҠгӮҲгҒізҙҚзЁҺгҒ®зҫ©еӢҷгҒҢз”ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒйқһдјҡе“ЎгҒёгҒ®дјҡиӘҢиІ©еЈІгҖҒдјҡиӘҢгҒёгҒ®еәғе‘ҠжҺІијүгҖҒеӯҰдјҡеӨ§дјҡгҒ§гҒ®дјҒжҘӯгғ–гғјгӮ№еҮәеұ•ж–ҷгҒӘгҒ©гҒҢеҸҺзӣҠдәӢжҘӯгҒЁгҒҝгҒӘгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®дәӢжҘӯгҒӢгӮүз”ҹгҒҳгҒҹеҲ©зӣҠгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜжі•дәәзЁҺгҒҢиӘІгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҸҺзӣҠдәӢжҘӯгҒЁйқһеҸҺзӣҠдәӢжҘӯгҒ®еҢәеҲҶпјҲзү©е“ҒиІ©еЈІгҒЁдјҡиІ»гҒӘгҒ©пјүгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒ—гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘзөҢзҗҶеҮҰзҗҶгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮзөҢзҗҶдҪ“еҲ¶гҒҢж•ҙгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒзЁҺйЎҚгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ§гӮӮжӯЈгҒ—гҒҸзҙҚзЁҺйЎҚгӮ’иЁҲз®—гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»д»Өе’Ңпј–е№ҙзүҲгҖҖжі•дәәзЁҺгҒ®гҒӮгӮүгҒҫгҒ—гҒЁз”іе‘ҠгҒ®жүӢеј•пҪңеӣҪзЁҺеәҒ
3.2. дјҡиЁҲжғ…е ұгҒ®йҖҸжҳҺжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒ—гҖҒдјҡе“ЎгҒёгҒ®иӘ¬жҳҺиІ¬д»»гӮ’жһңгҒҹгҒҷ
еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲжғ…е ұгҒҜгҖҒдјҡе“ЎгҒӢгӮүгҒ®дјҡиІ»гӮ„еҜ„д»ҳйҮ‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®дҪҝйҖ”гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜй«ҳгҒ„йҖҸжҳҺжҖ§гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮе®ҡжңҹзҡ„гҒӘдјҡиЁҲе ұе‘ҠгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒеӯҰдјҡгҒ®иІЎж”ҝзҠ¶жіҒгӮ„дәӢжҘӯжҙ»еӢ•гҒ®жҲҗжһңгӮ’дјҡе“ЎгҒ«жҳҺзўәгҒ«дјқгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒдјҡе“ЎгҒ®зҗҶи§ЈгҒЁдҝЎй јгӮ’ж·ұгӮҒгӮӢдёҠгҒ§йқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
е№ҙж¬Ўе ұе‘ҠжӣёгӮ„з·ҸдјҡиіҮж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҙ»еӢ•иЁҲз®—жӣёгҖҒиІёеҖҹеҜҫз…§иЎЁгҖҒиІЎз”Јзӣ®йҢІгҒӘгҒ©гӮ’е…¬й–ӢгҒ—гҖҒиӘ°гҒҢиҰӢгҒҰгӮӮеҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„еҪўејҸгҒ§жғ…е ұгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮжғ…е ұе…¬й–ӢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒй–ІиҰ§иҖ…гҒҢе®№жҳ“гҒ«жғ…е ұгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒеӯҰдјҡгҒ®WebгӮөгӮӨгғҲгҒӘгҒ©гҒ§е…¬й–Ӣжғ…е ұгӮ’жҺІијүгҒ—гҖҒеҚ°еҲ·еҲ¶йҷҗгӮ’гҒӢгҒ‘гҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҒ®й…Қж…®гӮӮеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дјҡиЁҲжғ…е ұгҒ®йҖҸжҳҺжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеӯҰдјҡгҒ®гӮ¬гғҗгғҠгғігӮ№гӮ’еј·еҢ–гҒ—гҖҒзӨҫдјҡзҡ„гҒӘиӘ¬жҳҺиІ¬д»»гӮ’жһңгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдјҡе“ЎгҒҜе®үеҝғгҒ—гҒҰеӯҰдјҡжҙ»еӢ•гҒ«еҸӮеҠ гҒ§гҒҚгҖҒеӨ–йғЁгҒӢгӮүгҒ®ж”ҜжҸҙгӮӮеҫ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒ PDCAгҒ§йҖІеҢ–гҒҷгӮӢпјҒгғһгғӢгғҘгӮўгғ«жҙ»з”ЁгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®5гҒӨгҒ®е·ҘеӨ«
еӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҒҜгҖҒеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢжҘӯеӢҷгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжӢ…еҪ“иҖ…гҒ®дәӨд»ЈгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҘӯеӢҷгҒ®еј•гҒҚз¶ҷгҒҺгҒҢгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒ„гҒӢгҒӘгҒ„гғӘгӮ№гӮҜгӮӮеёёгҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдәӢж…ӢгӮ’йҒҝгҒ‘гҖҒз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«е®үе®ҡгҒ—гҒҹдјҡиЁҲеҮҰзҗҶгӮ’иЎҢгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜйҒӢз”ЁгғһгғӢгғҘгӮўгғ«гҒ®ж•ҙеӮҷгҒҢеҝ…й ҲгҒ§гҒҷгҖӮ
еҠ№жһңзҡ„гҒӘйҒӢз”ЁгғһгғӢгғҘгӮўгғ«гҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢжҘӯеӢҷжүӢй ҶгҒ®зҫ…еҲ—гҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒдјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҒ®зӣ®зҡ„гҖҒеҗ„еӢҳе®ҡ科зӣ®гҒ®жҳҺзўәгҒӘе®ҡзҫ©гҖҒж”Ҝжү•гҒ„гғ»зІҫз®—гғ»иЁҳйҢІгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘжөҒгӮҢгҖҒдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢж§ҳејҸгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгӮҲгҒҸгҒӮгӮӢиіӘе•ҸгҒЁгҒқгҒ®еҜҫеҝңзӯ–гҒӘгҒ©гӮ’з¶Ізҫ…зҡ„гҒ«иЁҳиҝ°гҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒҷгҖӮ
гғһгғӢгғҘгӮўгғ«гҒ®жҙ»з”ЁеәҰгӮ’жңҖеӨ§йҷҗгҒ«й«ҳгӮҒгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®е·ҘеӨ«гҒҢиӮқеҝғгҒ§гҒҷгҖӮ
(1) иӘ°гҒ§гӮӮгӮҸгҒӢгӮӢиЎЁзҸҫгҒ§дҪңжҲҗ
е°Ӯй–Җз”ЁиӘһгӮ’йҒҝгҒ‘гҖҒеҲқеӯҰиҖ…гҒ§гӮӮзҗҶи§ЈгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„е№іжҳ“гҒӘиЁҖи‘үгҒ§иЁҳиҝ°гҒ—гҖҒиӨҮйӣ‘гҒӘгғ•гғӯгғјгҒҜгғ•гғӯгғјгғҒгғЈгғјгғҲгӮ„еӣіи§ЈгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰиҰ–иҰҡзҡ„гҒ«еҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸиЎЁзҸҫгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
(2) жңҖж–°жғ…е ұгҒ®жҸҗдҫӣ
зЁҺеҲ¶ж”№жӯЈгӮ„еӯҰдјҡгҒ®иҰҸзЁӢеӨүжӣҙгҒӘгҒ©гҖҒй–ўйҖЈгҒҷгӮӢжғ…е ұгҒҢжӣҙж–°гҒ•гӮҢгҒҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒйҖҹгӮ„гҒӢгҒ«гғһгғӢгғҘгӮўгғ«гҒ®еҶ…е®№гӮ’дҝ®жӯЈгҒ—гҖҒеёёгҒ«жңҖж–°гҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’дҝқгҒӨеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
(3) жӢ…еҪ“иҖ…гҒ®ж„ҸиҰӢеҸҚжҳ
е®ҹйҡӣгҒ«дјҡиЁҲжҘӯеӢҷгӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢж–№гҖ…гҒ®ж„ҸиҰӢгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгҖҒе®ҹеӢҷгҒ«еҚігҒ—гҒҹеҶ…е®№гҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠе®ҹи·өзҡ„гҒӘгғһгғӢгғҘгӮўгғ«гҒёгҒЁзЈЁгҒҚдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
(4) гғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гӮ’жҺЁйҖІ
гғһгғӢгғҘгӮўгғ«гӮ’гғҮгӮёгӮҝгғ«гғҮгғјгӮҝгҒЁгҒ—гҒҰз®ЎзҗҶгҒ—гҖҒжӨңзҙўжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘжғ…е ұгҒ«зҙ ж—©гҒҸгӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮҜгғ©гӮҰгғүгӮ№гғҲгғ¬гғјгӮёгҒӘгҒ©гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰгҖҒй–ўдҝӮиҖ…й–“гҒ§е…ұжңүгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„з’°еўғгӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮ
(5) е®ҡжңҹзҡ„гҒӘиҰӢзӣҙгҒ—гҒЁз ”дҝ®гҒ§йҖІеҢ–
гғһгғӢгғҘгӮўгғ«гӮ’еҹәгҒ«гҒ—гҒҹе®ҡжңҹзҡ„гҒӘз ”дҝ®гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҖҒж–°д»»иҖ…гҒёгҒ®ж•ҷиӮІгӮ’иЎҢгҒҶгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒж—ўеӯҳгҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гӮӮзҹҘиӯҳгӮ’еҶҚзўәиӘҚгҒҷгӮӢж©ҹдјҡгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮеҠ гҒҲгҒҰгҖҒе№ҙгҒ«дёҖеәҰгҒҜгғһгғӢгғҘгӮўгғ«е…ЁдҪ“гӮ’еҢ…жӢ¬зҡ„гҒ«иҰӢзӣҙгҒ—гҖҒж”№е–„зӮ№гҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгғ¬гғ“гғҘгғјгҒҷгӮӢе ҙгӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
PDCAгӮ’еӣһгҒ—гҖҒйҒ©еҲҮгҒӘдјҡиЁҲеҮҰзҗҶгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеӯҰдјҡгҒ®жҙ»еӢ•гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘжҹұгҒ§гҒҷгҖӮдјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҒ®д»•зө„гҒҝгҒҘгҒҸгӮҠгҒҢгҖҒжҘӯеӢҷгҒ®еј•гҒҚз¶ҷгҒҺгӮ’еҶҶж»‘гҒ«гҒҷгӮӢеҹәзӣӨгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжң¬иЁҳдәӢгҒҢгҖҒеӯҰдјҡгҒ®дјҡиЁҲжҘӯеӢҷгҒ«жҗәгӮҸгӮӢеӨҡгҒҸгҒ®ж–№гҖ…пјҲзөҢзҗҶжӢ…еҪ“иҖ…гҖҒ委員дјҡгӮ№гӮҝгғғгғ•гҖҒ委員長гҖҒзӣЈжҹ»жӢ…еҪ“гҒӘгҒ©пјүгҒ®дёҖеҠ©гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгӮҲгӮҠгӮ№гғ гғјгӮәгҒ§дҝЎй јжҖ§гҒ®й«ҳгҒ„еӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«иІўзҢ®гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жңҹеҫ…гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ