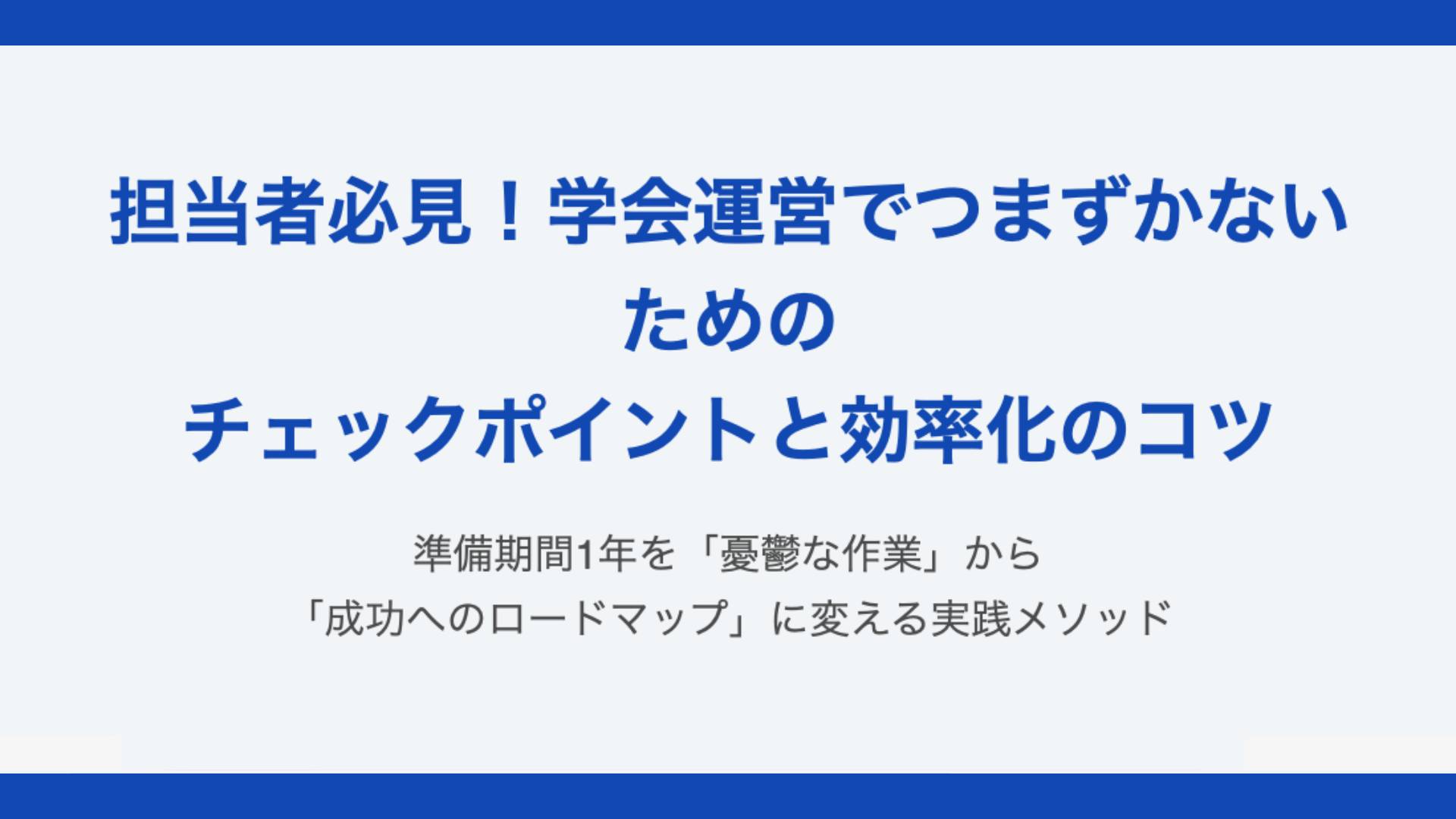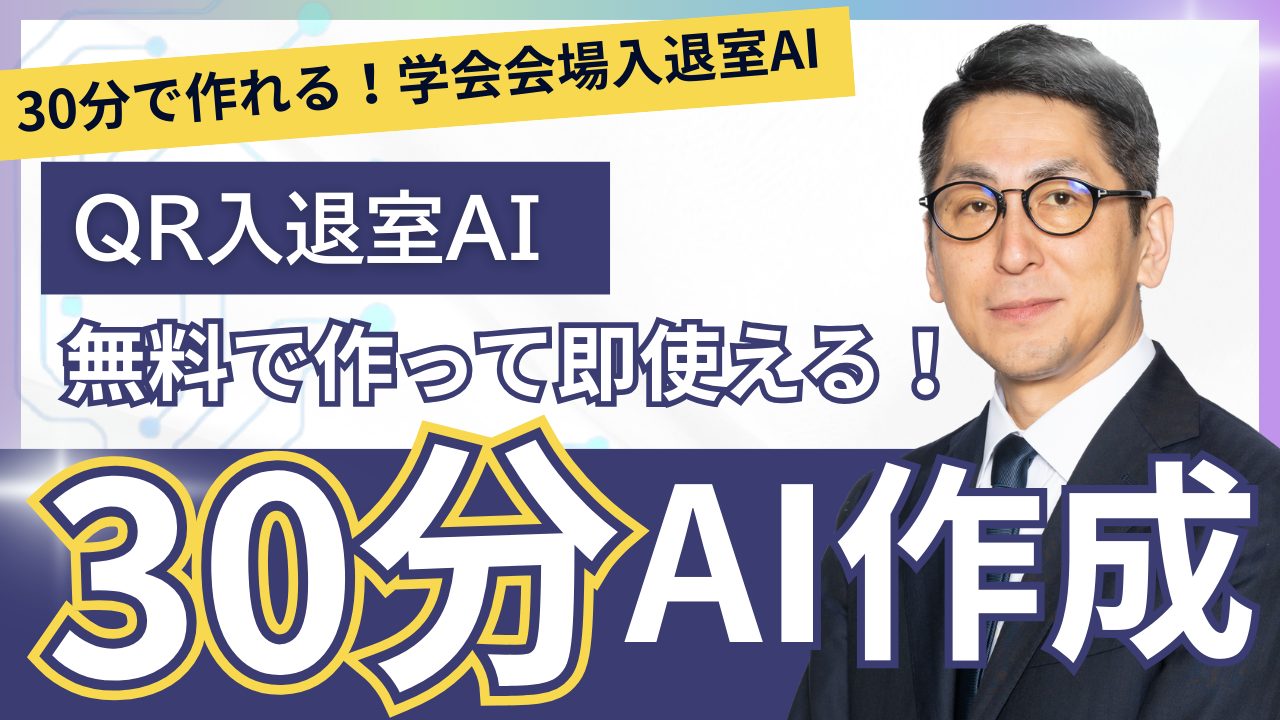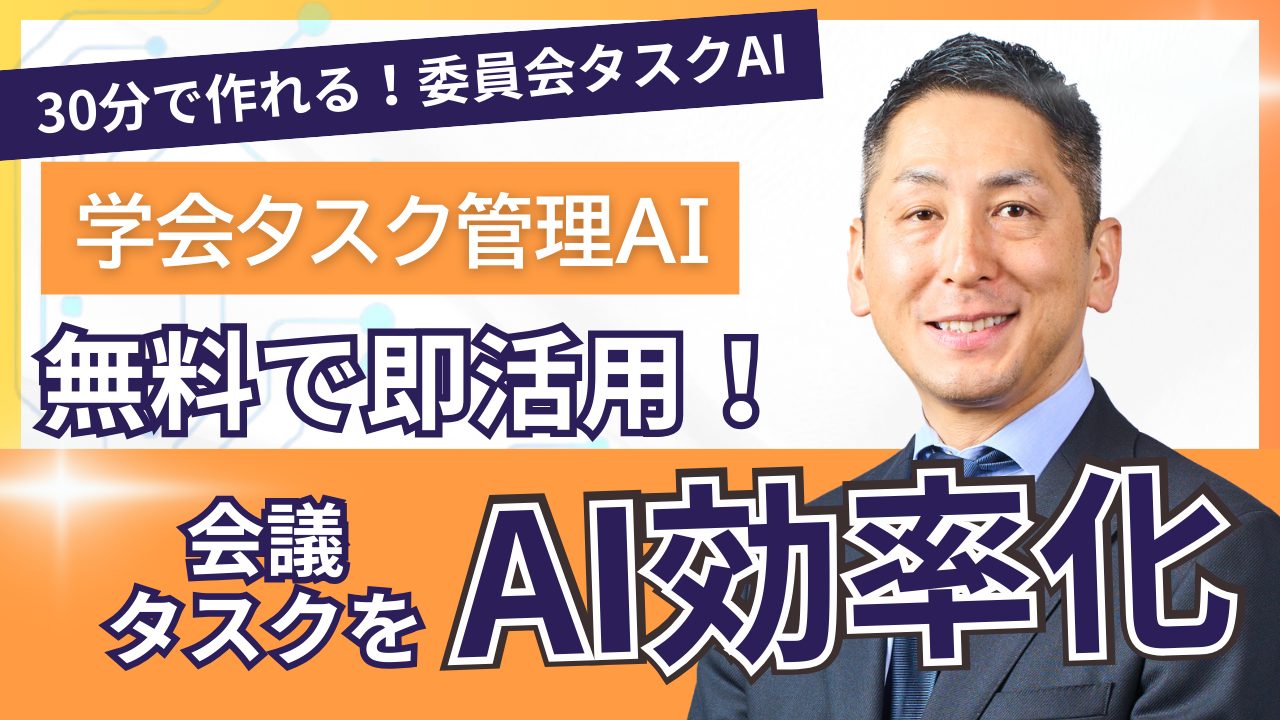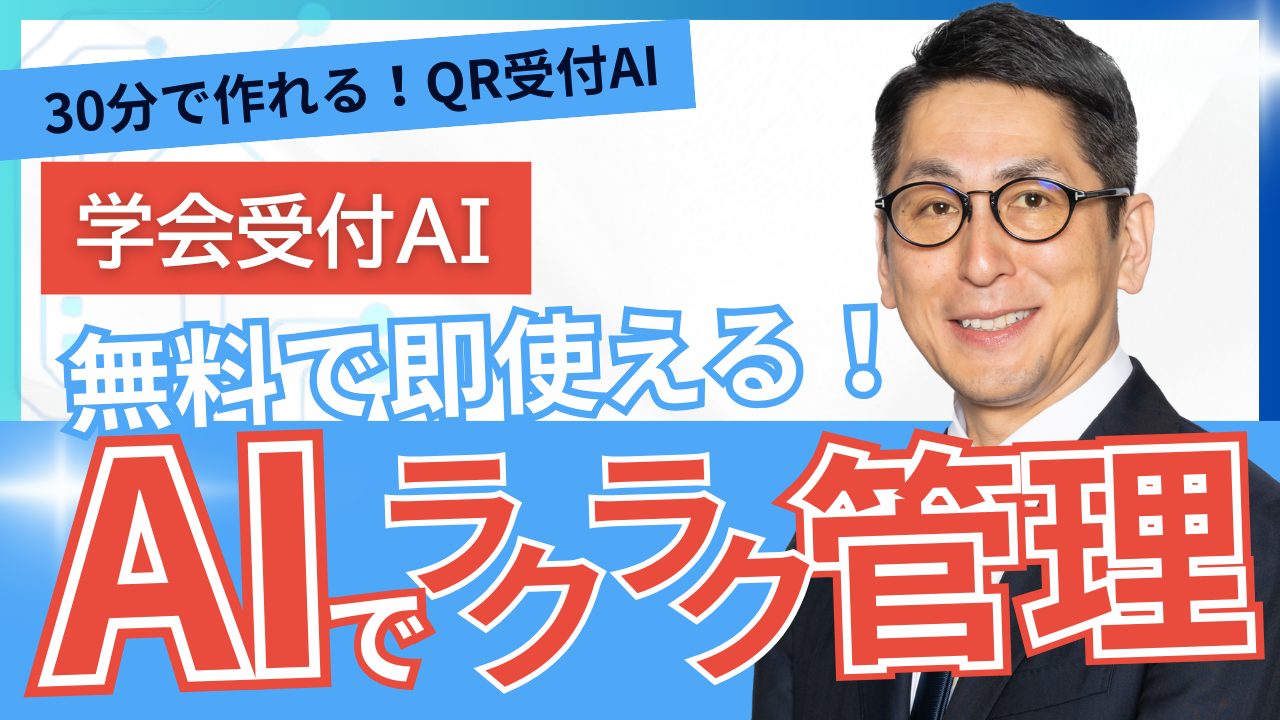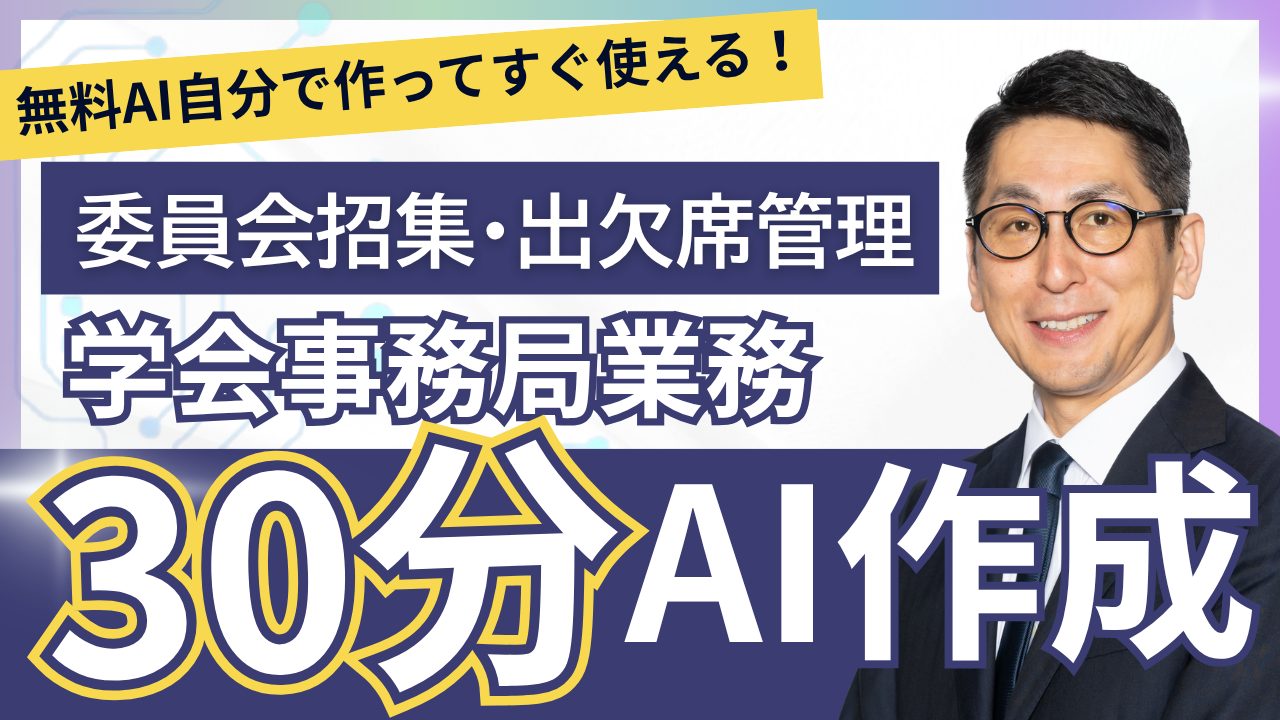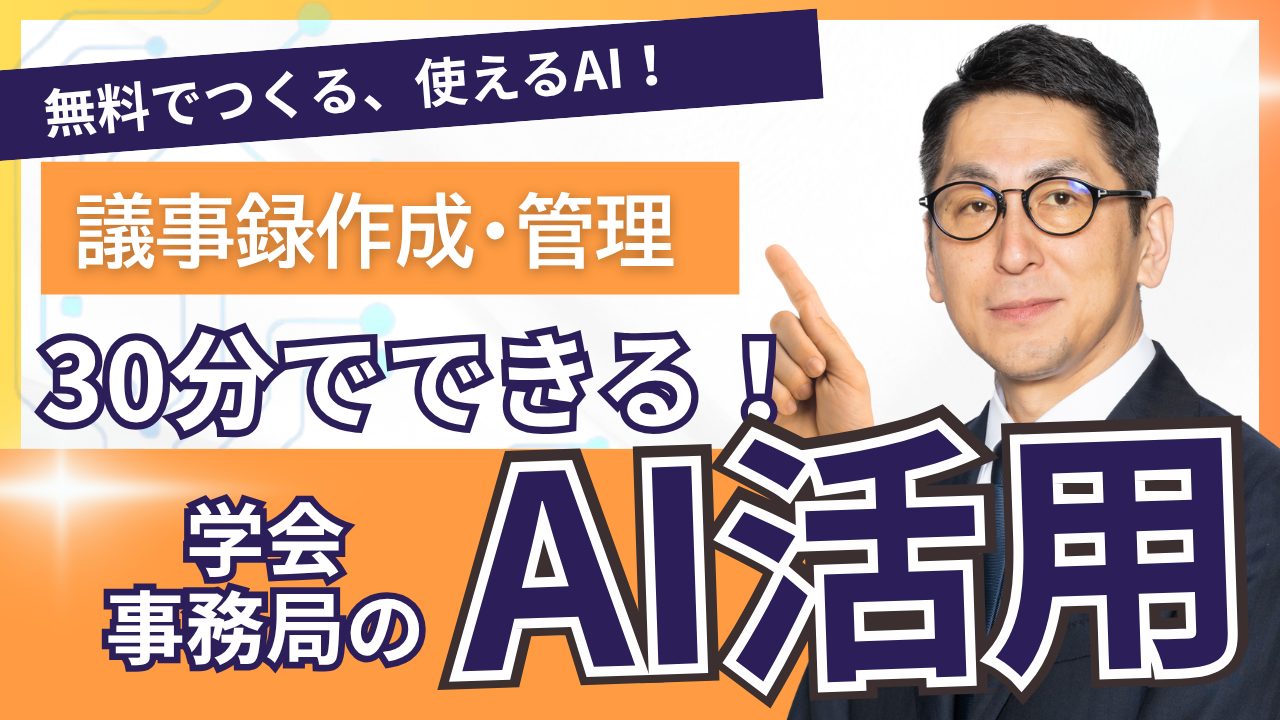ه¦è،“集ن¼ڑهٹ©وˆگ金م‚’申請مپ™م‚‹مپ«مپ¯ï¼ں ï½ه¦è،“ç ”ç©¶مپ¨ç¤¾ن¼ڑمپ¨مپ®مپ¤مپھمپŒم‚ٹم‚’è،¨çڈ¾مپ™م‚‹ï½
2025ه¹´08وœˆ19و—¥
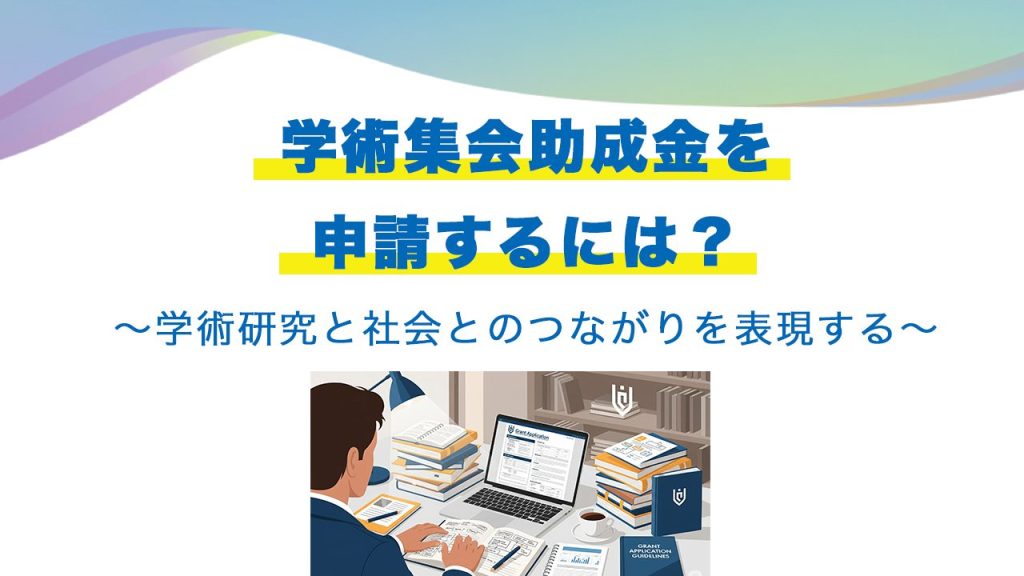
مپ¯مپکم‚پمپ« هˆ¶ه؛¦مپ®و¦‚è¦پمپ¨ç”³è«‹مپ®وµپم‚Œم‚’çگ†è§£مپ™م‚‹
م€Œمپ©مپ†مپ™م‚Œمپ°ه¦ن¼ڑمپ®è²،و”؟هں؛盤م‚’ه®‰ه®ڑمپ•مپ›م‚‰م‚Œم‚‹مپ م‚چمپ†مپ‹ï¼ںم€چم€Œç”³è«‹و›¸مپ®و›¸مپچو–¹مپŒم‚ڈمپ‹م‚‰مپھمپ„…م€چم€‚
ه¦è،“集ن¼ڑمپ®é–‹ه‚¬و؛–ه‚™م‚’進م‚پم‚‹ن¸مپ§م€پ資金èھ؟éپ”مپ®و‚©مپ؟م‚’وٹ±مپˆمپ¦مپ„مپ¾مپ›م‚“مپ‹ï¼ںè³ھمپ®é«کمپ„ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپ¯م€پن¼ڑه ´è²»م‚„و‹›èپک講و¼”者مپ¸مپ®è¬é‡‘مپھمپ©م€په¤ڑه²گمپ«م‚ڈمپںم‚‹è²»ç”¨مپŒç™؛ç”ںمپ—مپ¾مپ™م€‚
مپ“م‚Œم‚‰مپ®èھ²é،Œم‚„ه•ڈé،Œم‚’解و±؛مپ—م€په¦ن¼ڑمپ®وœھو¥م‚’و‹“مپڈéچµمپ“مپمپŒه¦è،“集ن¼ڑهٹ©وˆگ金مپ§مپ™م€‚
مپ“مپ®è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€په¦è،“集ن¼ڑهٹ©وˆگ金مپ®ç”³è«‹م‚’é€ڑمپکمپ¦م€په¦ن¼ڑمپ®è²،و”؟هں؛盤م‚’ه¼·هŒ–مپ—م€پمپمپ®ه¦è،“çڑ„و„ڈ義مپ¨ç¤¾ن¼ڑ貢献مپ®هڈ¯èƒ½و€§م‚’وœ€ه¤§é™گمپ«ه¼•مپچه‡؛مپ™مپںم‚پمپ®ه…·ن½“çڑ„مپھو–¹و³•م‚’解èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚وژ،وٹçژ‡م‚’é«کم‚پم‚‹مپںم‚پمپ®مƒژم‚¦مƒڈم‚¦م‚’م€پن¸€ç·’مپ«ç¢؛èھچمپ—مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
è³ھمپ®é«کمپ„ه¦ن¼ڑé–‹ه‚¬مپ«مپ¯ç ”究هٹ©وˆگ金مپ®و´»ç”¨مپ¯éه¸¸مپ«وœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚هٹ©وˆگ金مپ«مپ¯ه…¬çڑ„هٹ©وˆگ金مپ¨و°‘é–“هٹ©وˆگ金مپŒمپ‚م‚ٹم€پمپم‚Œمپم‚Œç›®çڑ„م€په¯¾è±،م€پ金é،چمپŒç•°مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ه…¬çڑ„هٹ©وˆگ金مپ¯م€په›½م‚„هœ°و–¹ه…¬ه…±ه›£ن½“مپŒه¦è،“وŒ¯èˆˆم‚„社ن¼ڑèھ²é،Œمپ®éپ”وˆگم‚„ه•ڈé،Œè§£و±؛م‚’ç›®çڑ„مپ¨مپ—م€په¤§è¦ڈو¨،مپھç ”ç©¶م‚’و”¯وڈ´مپ™م‚‹ه‚¾هگ‘مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚ن¸€و–¹م€پو°‘é–“هٹ©وˆگ金مپ¯م€پ特ه®ڑمپ®ç ”究هˆ†é‡ژم‚„社ن¼ڑ貢献و´»ه‹•مپ«ç‰¹هŒ–مپ—مپںè²،ه›£مپھمپ©مپ‹م‚‰وڈگن¾›مپ•م‚Œم€په…ˆé§†çڑ„مپ§مƒ¦مƒ‹مƒ¼م‚¯مپھمƒ†مƒ¼مƒمپ§م‚‚وژ،وٹمپ•م‚Œم‚„مپ™مپ„特ه¾´مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م€گهٹ©وˆگ金مپ®ç¨®é،م€‘
| هٹ©وˆگ金مپ®ç¨®é، | ن¸»مپھوڈگن¾›ه…ƒ | ç›®çڑ„مƒ»ç‰¹ه¾´ | 金é،چمپ®ç¯„ه›²(ç›®ه®‰) |
| ه…¬çڑ„هٹ©وˆگ金 | ه›½م€پ独立è،Œو”؟و³•ن؛؛(و—¥وœ¬ه¦è،“وŒ¯èˆˆن¼ڑمپھمپ©ï¼‰م€پهœ°و–¹ه…¬ه…±ه›£ن½“م€په…¬ç›ٹè²،ه›£و³•ن؛؛ï¼ˆç§‘ç ”è²»م€پJSTمƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ مپھمپ©ï¼‰ | ه¦è،“وŒ¯èˆˆم€پç ”ç©¶وˆگوœمپ®ç¤¾ن¼ڑé‚„ه…ƒم€پو”؟ç–èھ²é،Œè§£و±؛م€په›½éڑ›ه…±هگŒç ”究م€پè‹¥و‰‹è‚²وˆگمپھمپ©م‚’ç›®çڑ„مپ¨مپ™م‚‹م€‚競ن؛‰çڑ„資金مپŒه¤ڑمپڈم€پهژ³و ¼مپھه¯©وں»مپŒè،Œم‚ڈم‚Œم‚‹م€‚وژ،وٹه®ں績مپŒه…¬é–‹مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤ڑمپ„م€‚ | و•°هچپن¸‡ه††م€œو•°هچƒن¸‡ه†† (مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ مپ«م‚ˆم‚‹) |
| و°‘é–“هٹ©وˆگ金 | هگ„種è²،ه›£ï¼ˆه†…è—¤è¨که؟µç§‘ه¦وŒ¯èˆˆè²،ه›£مپھمپ©ï¼‰م€پن¼پو¥م€پو¥ç•Œه›£ن½“ | 特ه®ڑهˆ†é‡ژمپ®وŒ¯èˆˆم€پ社ن¼ڑèھ²é،Œè§£و±؛م€پè‹¥و‰‹è‚²وˆگم€په›½éڑ›ن؛¤وµپم€پهœ°هںں貢献م€پن¼پو¥مپ®CSRو´»ه‹•مپ¨مپ—مپ¦ه®ںو–½مپ•م‚Œم‚‹م€‚وڈگن¾›ه…ƒمپ«م‚ˆمپ£مپ¦ç‰¹è‰²مپŒه¤§مپچمپڈç•°مپھم‚ٹم€پ特ه®ڑمپ®مƒ†مƒ¼مƒم‚„ه¯¾è±،者مپ«ç‰¹هŒ–مپ—مپ¦مپ„م‚‹ه ´هگˆمپŒه¤ڑمپ„م€‚ | و•°هچپن¸‡ه††م€œو•°ç™¾ن¸‡ه†† (è²،ه›£م‚„ن¼پو¥مپ«م‚ˆم‚‹) |
資金èھ؟éپ”م‚’ç›®وŒ‡مپ™مپ«مپ¯م€پمپ¾مپڑهگ„هٹ©وˆگو©ںé–¢مپ®ه…¬ه‹ںè¦پé کم‚’ç†ںèھمپ—م€په¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ®è¶£و—¨مپŒهگˆè‡´مپ™م‚‹مپ‹ç¢؛èھچمپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚ه…¬ه‹ںوœںé–“م€پ申請資و ¼م€په¯¾è±،経費م€په¯©وں»هں؛و؛–مپھمپ©م‚’و£ç¢؛مپ«وٹٹوڈ،مپ—م€پ計画çڑ„مپ«و؛–ه‚™م‚’進م‚پم‚‹مپ“مپ¨مپŒوˆگهٹںمپ®éچµمپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
هٹ©وˆگ金申請مپ®ن¸€èˆ¬çڑ„مپھوµپم‚Œï¼ˆï¼—مپ¤مپ®م‚¹مƒ†مƒƒمƒ—)
(1)وƒ…ه ±هڈژ集مپ¨ه…¬ه‹ںè¦پé کمپ®ç¢؛èھچï¼ڑ関連هٹ©وˆگو©ںé–¢مپ®م‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆمپ§مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ م‚’و¤œç´¢م€‚
(2)申請資و ¼مپ¨ه¯¾è±،مپ®ç¢؛èھچï¼ڑه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ®è¶£و—¨مپŒهٹ©وˆگ金مپ®ç›®çڑ„مپ«هگˆè‡´مپ—م€پ申請資و ¼م‚’و؛€مپںمپ™مپ‹ç¢؛èھچم€‚
(3)申請و›¸ن½œوˆگï¼ڑه…¬ه‹ںè¦پé کمپ«و²؟مپ£مپ¦م€په¦è،“çڑ„و„ڈ義م€پ社ن¼ڑ貢献م€په®ںو–½è¨ˆç”»م€پن؛ˆç®—計画م€په®ںو–½ن½“هˆ¶مپھمپ©م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«è¨کè؟°م€‚
(4)ه†…部و‰؟èھچمپ¨وڈگه‡؛ï¼ڑه¦ن¼ڑه†…部مپ§مپ®و‰؟èھچم‚’経مپ¦م€پوŒ‡ه®ڑو–¹و³•مپ§ç”³è«‹و›¸م‚’وڈگه‡؛م€‚
(5)ه¯©وں»مپ¨çµگوœé€ڑçں¥ï¼ڑه¯©وں»ه¾Œم€پوژ،وٹم€پن¸چوژ،وٹمپ®çµگوœمپŒé€ڑçں¥مپ•م‚Œم‚‹م€‚
(6)وژ،وٹه¾Œمپ®و‰‹ç¶ڑمپچمپ¨ه®ںو–½ï¼ڑن؛¤ن»کو±؛ه®ڑé€ڑçں¥مپ«هں؛مپ¥مپچم€پهٹ©وˆگ金هڈ—é کو‰‹ç¶ڑمپچم‚’è،Œمپ„م€پ計画é€ڑم‚ٹمپ«ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑم‚’ه®ںو–½م€‚
(7)ه®ں績ه ±ه‘ٹمپ¨ن¼ڑ計ه ±ه‘ٹï¼ڑه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑ終ن؛†ه¾Œم€پهٹ©وˆگو©ںé–¢مپ«ه®ں績ه ±ه‘ٹو›¸مپ¨ن¼ڑ計ه ±ه‘ٹو›¸م‚’وڈگه‡؛م€‚
هٹ©وˆگ金و´»ç”¨مپ¯م€په¦ن¼ڑمپ®è²،و”؟هں؛盤ه¼·هŒ–مپ«هٹ مپˆم€په›½éڑ›ç ”究ن؛¤وµپن؟ƒé€²م€پè‹¥و‰‹ç ”究者育وˆگم€پهœ°هںں社ن¼ڑ連وگ؛ه¼·هŒ–مپھمپ©ه¤ڑ角çڑ„مپھمƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚’م‚‚مپںم‚‰مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپںم€په¦ن¼ڑمپ®مƒ—مƒ¬م‚¼مƒ³م‚¹هگ‘ن¸ٹمپ¨ه¦è،“م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹مƒ†م‚£ه…¨ن½“مپ®و´»و€§هŒ–مپ«مپ¤مپھمپŒم‚‹é‡چè¦پمپھهڈ–م‚ٹ組مپ؟مپ¨è¨€مپˆم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
1. وژ،وٹçژ‡م‚’é«کم‚پم‚‹ç”³è«‹و›¸مپ®و›¸مپچو–¹ï¼ڑه¦è،“çڑ„و„ڈ義مپ¨ç¤¾ن¼ڑ貢献مپ®مƒگمƒ©مƒ³م‚¹
هٹ©وˆگ金申請و›¸مپ¯م€په¯©وں»ه“،مپ®ه؟ƒمپ«و·±مپڈéں؟مپڈو§‹وˆگمپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚وژ،وٹمپ¸مپ¨ه°ژمپڈمپ«مپ¯م€په¦è،“çڑ„و„ڈ義مپ¨ç¤¾ن¼ڑمپ¸مپ®è²¢çŒ®ه؛¦مپ¨مپ„مپ†2مپ¤مپ®è¦پç´ م‚’مƒگمƒ©مƒ³م‚¹è‰¯مپڈم€په…·ن½“çڑ„مپ«è¨کè؟°مپ™م‚‹و§‹وˆگهٹ›مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ“مپ§مپ¯م€پمپمپ®ç§ک訣م‚’考مپˆمپ¾مپ™م€‚
1.1. ه¦è،“çڑ„و„ڈ義مپ®وکژç¢؛هŒ–مپ¨ç‹¬è‡ھو€§مپ®وڈگç¤؛
ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ®و ¸مپ¨مپھم‚‹مپ®مپ¯م€پمپمپ®ه¦è،“çڑ„ن¾،ه€¤مپ§مپ™م€‚申請و›¸مپ§مپ¯م€پهڈ–م‚ٹ組م‚€مپ¹مپچه¦è،“çڑ„èھ²é،Œم€پوœ€و–°مپ®ç ”究ه‹•هگ‘م€پوœھ解وکژمپھ点م‚’وکژç¢؛مپ«è¨کè؟°مپ—م€پوœ¬ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپŒèھ²é،Œè§£و±؛مپ«مپ©مپ†è²¢çŒ®مپ—م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھو–°مپںمپھçں¥è¦‹م‚„è°è«–م‚’ه‰µه‡؛مپ™م‚‹مپ‹م‚’وکژç¢؛مپ«ç¤؛مپ—مپ¾مپ™م€‚
特مپ«é‡چè¦پمپھمپ®مپ¯ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ®م€Œç‹¬è‡ھو€§م€چمپ§مپ™م€‚éپژهژ»مپ®é،ن¼¼مپ®ه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ¨مپ®éپ•مپ„م‚„م€پمپ“مپ®ه¦ن¼ڑمپ مپ‹م‚‰مپ“مپه®ںçڈ¾مپ§مپچم‚‹مƒ¦مƒ‹مƒ¼م‚¯مپھمƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ م€پو‹›èپکمپ™م‚‹è¬›و¼”者مپ®ه°‚é–€و€§م€پè°è«–مپ®هˆ‡م‚ٹهڈ£مپھمپ©م‚’ه¼·èھ؟مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¦è،“çڑ„ن¾،ه€¤م‚’éڑ›ç«‹مپںمپ›مپ¾مپ™م€‚
ن¾‹مپˆمپ°م€پ特ه®ڑمپ®هˆ†é‡ژمپ«مپٹمپ‘م‚‹ه›½éڑ›çڑ„مپھ第ن¸€ن؛؛者مپ®و‹›èپکم‚„م€پç•°هˆ†é‡ژç ”ç©¶è€…مپ®çµگمپ³مپ¤مپچمپ«م‚ˆم‚‹ه¦éڑ›çڑ„視点مپ®ه‰µه‡؛مپھمپ©م€په…·ن½“çڑ„مپھن؛‹ن¾‹م‚’وŒ™مپ’م‚‹مپ“مپ¨مپŒوœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚
ه¦è،“çڑ„و„ڈ義م‚’وکژç¢؛مپ«مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®ï¼”é …ç›®
(1)ç ”ç©¶مپ®èƒŒو™¯مپ¨ن½چç½®مپ¥مپ‘ï¼ڑه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمƒ†مƒ¼مƒمپ®ه¦è،“هˆ†é‡ژمپ«مپٹمپ‘م‚‹ن½چç½®مپ¥مپ‘مپ¨وœھ解و±؛èھ²é،Œم€په…ˆè،Œç ”究م‚’è¸ڈمپ¾مپˆمپںم‚®مƒ£مƒƒمƒ—مپ®هں‹م‚پو–¹م‚’èھ¬وکژم€‚
(2)ç›®و¨™è¨ه®ڑمپ®ه…·ن½“و€§ï¼ڑه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑم‚’é€ڑمپکمپ¦ç›®وŒ‡مپ™ه¦è،“çڑ„وˆگوœم‚’ه…·ن½“çڑ„مپ‹مپ¤و¸¬ه®ڑهڈ¯èƒ½مپھه½¢مپ§è¨ه®ڑ(ن¾‹ï¼ڑم€Œو–°مپںمپھçگ†è«–و§‹ç¯‰م€چم€Œه›½éڑ›ه…±هگŒç ”究مپ®èگŒèٹ½م€چ)م€‚
(3)ç ”ç©¶ه€«çگ†مپ¨ه…¬و£و€§مپ¸مپ®é…چو…®ï¼ڑç ”ç©¶ه®ںو–½مپ«مپٹمپ‘م‚‹ه€«çگ†çڑ„é…چو…®م‚„ه…¬و£و€§مپ¸مپ®هڈ–م‚ٹ組مپ؟م‚’وکژè¨کم€‚
(4)ه›½éڑ›çڑ„مپھ視点مپ¨é€£وگ؛ï¼ڑه›½éڑ›çڑ„مپھç ”ç©¶ه‹•هگ‘م‚’è¸ڈمپ¾مپˆم€په›½éڑ›ه¦è،“م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹مƒ†م‚£مپ¸مپ®è²¢çŒ®م‚„ه›½éڑ›é€£وگ؛مپ®و·±هŒ–م‚’è¨کè؟°مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ®ه¦è،“çڑ„ن¾،ه€¤م‚’ن¸€ه±¤é«کم‚پمپ¾مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
آ مƒ»ç ”究هٹ©وˆگ金وƒ…ه ±مپ¨ç”³è«‹مپ§وٹ‘مپˆمپ¦مپٹمپچمپںمپ„مƒم‚¤مƒ³مƒˆï½œم‚¨مƒٹم‚´م‚¢م‚«مƒ‡مƒںمƒ¼
1.2. 社ن¼ڑçڑ„م‚¤مƒ³مƒ‘م‚¯مƒˆمپ¨و³¢هڈٹهٹ¹وœمپ®ه…·ن½“هŒ–
ه¦è،“çڑ„مپھو„ڈ義مپ«هٹ مپˆم€په¦ن¼ڑمپŒç¤¾ن¼ڑمپ«ن¸ژمپˆم‚‹ه½±éں؟مپ¨و³¢هڈٹهٹ¹وœم‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«ç¤؛مپ™مپ“مپ¨مپ¯م€پ特مپ«ه…¬çڑ„هٹ©وˆگ金م‚„社ن¼ڑ貢献م‚’é‡چ視مپ™م‚‹و°‘é–“هٹ©وˆگ金مپ®ç”³è«‹مپ§ن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚
ه¦ن¼ڑمپ®ç ”究وˆگوœمپŒم€پ社ن¼ڑèھ²é،Œمپ®è§£و±؛م€پ産و¥مپ®ç™؛ه±•م€پو”؟ç–وڈگ言م€پمپ‚م‚‹مپ„مپ¯ن¸€èˆ¬ه¸‚و°‘مپ®ç§‘ه¦مƒھمƒ†مƒ©م‚·مƒ¼هگ‘ن¸ٹمپ«مپ©مپ†ه¯„ن¸ژمپ™م‚‹مپ‹م‚’وکژç¢؛مپ«è¨کè؟°مپ—مپ¾مپ™م€‚
ن¾‹مپˆمپ°م€پ特ه®ڑمپ®ç–¾ç—…مپ«é–¢مپ™م‚‹وœ€و–°مپ®ç ”究وˆگوœم‚’ç™؛è،¨مپ™م‚‹ه¤§ن¼ڑمپ§مپ‚م‚Œمپ°م€پمپم‚ŒمپŒهŒ»ç™‚çڈ¾ه ´مپ¸مپ®ه¤‰هŒ–مپ¨و‚£è€…QOL(Quality of Life)هگ‘ن¸ٹمپ«مپ©مپ†è²¢çŒ®مپ—مپ†م‚‹مپ‹م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«è¨کè؟°مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پç’°ه¢ƒه•ڈé،Œم‚„éک²çپ½مپ«é–¢مپ™م‚‹ه¤§ن¼ڑمپ§مپ‚م‚Œمپ°م€پمپمپ®è°è«–مپŒو”؟ç–ç«‹و،ˆم‚„هœ°هںںن½ڈو°‘مپ®و„ڈèکه¤‰é©مپ«مپ©مپ†مپ¤مپھمپŒم‚‹مپ®مپ‹م€پمپ¨مپ„مپ£مپںه…·ن½“çڑ„مپھو³¢هڈٹهٹ¹وœم‚’وڈگç¤؛مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپ•م‚‰مپ«م€پن¸€èˆ¬ه…¬é–‹م‚»مƒƒم‚·مƒ§مƒ³مپ®è¨ç½®م‚„م€پمƒ،مƒ‡م‚£م‚¢مپ¸مپ®وƒ…ه ±ç™؛ن؟،計画مپھمپ©م€پ社ن¼ڑé‚„ه…ƒمپ®مپںم‚پمپ®ه…·ن½“çڑ„مپھم‚¢م‚¦مƒˆمƒھمƒ¼مƒپو´»ه‹•م‚’ç››م‚ٹè¾¼م‚€مپ“مپ¨م‚‚م€پ社ن¼ڑçڑ„م‚¤مƒ³مƒ‘م‚¯مƒˆم‚’ه¼·èھ؟مپ™م‚‹ن¸ٹمپ§وœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚
社ن¼ڑçڑ„م‚¤مƒ³مƒ‘م‚¯مƒˆمپ¨و³¢هڈٹهٹ¹وœم‚’ه…·ن½“هŒ–مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®4مپ¤مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆ
(1)م‚؟مƒ¼م‚²مƒƒمƒˆه±¤مپ¨مƒ‹مƒ¼م‚؛ï¼ڑوˆگوœمپŒه±ٹمپڈ社ن¼ڑه±¤مپ¨م€په½¼م‚‰مپ®مƒ‹مƒ¼م‚؛مپ¸مپ®ه¯¾ه؟œم‚’وکژç¢؛هŒ–م€‚
(2)م‚¢م‚¦مƒˆمƒھمƒ¼مƒپو´»ه‹•مپ®ه¤ڑو§کو€§ï¼ڑه¸‚و°‘ه…¬é–‹è¬›ه؛§م€پمƒ،مƒ‡م‚£م‚¢é€£وگ؛م€پو•™è‚²و©ںé–¢مپ¨مپ®é€£وگ؛م€پهœ°هںں連وگ؛مپھمپ©م€‚
(3)وˆگوœمپ®م€Œè¦‹مپˆم‚‹هŒ–م€چمپ¨وŒپç¶ڑو€§ï¼ڑوˆگوœمپ®هڈ¯è¦–هŒ–مپ¨وŒپç¶ڑçڑ„مپھ社ن¼ڑ貢献مپ¸مپ®ç¹‹مپŒم‚ٹم‚’ç¤؛مپ—مپ¾مپ™ï¼ˆن¾‹ï¼ڑه ±ه‘ٹو›¸ه…¬é–‹م€پم‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆç™؛ن؟،م€پو”؟ç–وڈگ言و›¸ن½œوˆگ)م€‚
(4)経و¸ˆçڑ„م€پ社ن¼ڑçڑ„هٹ¹وœمپ®è©¦ç®—ï¼ڑهڈ¯èƒ½مپ§مپ‚م‚Œمپ°م€په¤§ن¼ڑمپŒم‚‚مپںم‚‰مپ™çµŒو¸ˆçڑ„هٹ¹وœم‚„社ن¼ڑçڑ„هٹ¹وœمپ«مپ¤مپ„مپ¦م€په®ڑé‡ڈçڑ„م€په®ڑو€§çڑ„مپھ試算م‚’وڈگç¤؛مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پèھ¬ه¾—هٹ›مپŒه¢—مپ—مپ¾مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»è³‡و–™2 ه¦è،“مپ®و„ڈ義م€پ社ن¼ڑçڑ„ه½¹ه‰²مپ«مپ¤مپ„مپ¦ï½œو–‡éƒ¨ç§‘ه¦çœپ
2. ه¯©وں»هں؛و؛–مپ¨وژ،وٹن؛‹ن¾‹مپ«ه¦مپ¶ن¼مپˆو–¹مپ®ه·¥ه¤«
مپ“مپ“مپ§مپ¯م€په¯©وں»ه“،مپ®è¦–点م‚’çگ†è§£مپ—م€پوژ،وٹمپ•م‚Œم‚‹ç”³è«‹و›¸مپ«ه…±é€ڑمپ™م‚‹م€Œن¼مپˆو–¹م€چمپ®é‡چ点م‚’考مپˆمپ¾مپ™م€‚هٹ©وˆگ金申請و›¸مپ¯م€په¯©وں»ه“،مپ«م€Œمپ“مپ®ه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ¯و”¯وڈ´مپ™م‚‹ن¾،ه€¤مپŒمپ‚م‚‹م€چمپ¨ç´چه¾—مپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپ†مپںم‚پمپ®مƒ—مƒمƒمƒ¼م‚¶مƒ«مپ§مپ™م€‚
مپمپ®مپںم‚پمپ«مپ¯م€په¯©وں»هں؛و؛–م‚’و·±مپڈçگ†è§£مپ—م€پوژ،وٹمپ•م‚Œمپںن؛‹ن¾‹مپ‹م‚‰مپمپ®م€Œن¼مپˆو–¹م€چمپ®ه·¥ه¤«م‚’ه¦مپ¶مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
2.1. ه¯©وں»ه“،مپ®è¦–点م‚’وچ‰مپˆم‚‹ç”³è«‹و›¸مپ®ن½œوˆگ
ه¯©وں»ه“،مپ¯م€پé™گم‚‰م‚Œمپںو™‚é–“مپ®ن¸مپ§ه¤ڑو•°مپ®ç”³è«‹و›¸م‚’è©•ن¾،مپ—مپ¾مپ™م€‚مپمپ®مپںم‚پم€پ申請و›¸مپ¯م€Œèھمپ؟م‚„مپ™مپڈم€پهˆ†مپ‹م‚ٹم‚„مپ™مپڈم€پèھ¬ه¾—هٹ›مپŒمپ‚م‚‹م€چمپ“مپ¨مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚ه¯©وں»هں؛و؛–مپ®é …目(ه¦è،“çڑ„و„ڈ義م€پ社ن¼ڑ貢献م€په®ںو–½è¨ˆç”»م€پن؛ˆç®—مپ®ه¦¥ه½“و€§م€په®ںو–½ن½“هˆ¶مپھمپ©ï¼‰م‚’و„ڈèکمپ—م€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®é …ç›®مپ§و±‚م‚پم‚‰م‚Œم‚‹وƒ…ه ±م‚’و¼ڈم‚Œمپھمپڈم€پمپ‹مپ¤ç°،و½”مپ«è¨کè؟°مپ—مپ¾مپ™م€‚
و³¨و„ڈمپ™مپ¹مپچ6مپ¤مپ®è¦–点
(1)وکژç¢؛مپھç›®çڑ„è¨ه®ڑï¼ڑه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ®ç›®çڑ„م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ‹مپ¤و¸¬ه®ڑهڈ¯èƒ½مپھه½¢مپ§è¨کè؟°مپ—مپ¾مپ™ï¼ˆن¾‹ï¼ڑم€Œم€‡م€‡مپ®ه•ڈé،Œè§£و±؛مپ«è²¢çŒ®مپ—م€پهڈ‚هٹ 者مپ®م€‡م€‡مپ«é–¢مپ™م‚‹çگ†è§£ه؛¦م‚’م€‡م€‡.م€‡%هگ‘ن¸ٹم€چ)م€‚
(2)è«–çگ†çڑ„مپھو§‹وˆگï¼ڑه°ژه…¥مپ‹م‚‰çµگè«–مپ¾مپ§م€پن¸€è²«و€§مپ®مپ‚م‚‹è«–çگ†çڑ„مپھوµپم‚Œم‚’و§‹ç¯‰م€‚
و ¹و‹ مپ®وڈگç¤؛ï¼ڑن¸»ه¼µمپ«مپ¯ه؟…مپڑه®¢è¦³çڑ„مپھمƒ‡مƒ¼م‚؟م‚„ه…ˆè،Œç ”究م€په…·ن½“çڑ„مپھ計画م‚’و ¹و‹ مپ¨مپ—مپ¦ç¤؛مپ—مپ¾مپ™م€‚
(3)ه°‚門用èھمپ®é…چو…®ï¼ڑه°‚é–€ه¤–مپ®ه¯©وں»ه“،مپ«م‚‚çگ†è§£مپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†م€په°‚門用èھمپ«مپ¯éپ©ه®œèھ¬وکژم‚’هٹ مپˆم‚‹مپ‹م€په¹³وک“مپھ言葉مپ§è¨€مپ„وڈ›مپˆم‚‹ه·¥ه¤«م‚’ه‡م‚‰مپ—مپ¾مپ™م€‚ه›³è،¨م‚„م‚°مƒ©مƒ•م‚’هٹ¹وœçڑ„مپ«و´»ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پ複雑مپھوƒ…ه ±م‚‚視è¦ڑçڑ„مپ«هˆ†مپ‹م‚ٹم‚„مپ™مپڈن¼مپˆمپ¾مپ™م€‚
(4)ن؛ˆç®—مپ®é€ڈوکژو€§ï¼ڑن؛ˆç®—計画مپ¯م€پن½؟途مپŒوکژç¢؛مپ§م€پهگ„é …ç›®مپŒهگˆçگ†çڑ„مپھو ¹و‹ مپ«هں؛مپ¥مپ„مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç¤؛مپ—مپ¾مپ™م€‚ه…·ن½“çڑ„مپھç©چç®—و ¹و‹ م‚’وکژè¨کمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
(5)م‚¹مƒˆمƒ¼مƒھمƒ¼مƒ†مƒھمƒ³م‚°مپ®è¦پç´ ï¼ڑ申請و›¸ه…¨ن½“مپ§م€پم€Œèھ²é،Œم€چم€Œه•ڈé،Œم€چم€Œè§£و±؛ç–(ه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑه†…ه®¹ï¼‰م€چم€Œوœھو¥ï¼ˆوœںه¾…مپ•م‚Œم‚‹وˆگوœï¼‰م€چمپ¨مپ„مپ†م‚¹مƒˆمƒ¼مƒھمƒ¼م‚’èھم‚‹م‚ˆمپ†مپ«و§‹وˆگمپ™م‚‹مپ¨م€په¯©وں»ه“،مپ®ه؟ƒمپ«éں؟مپچم‚„مپ™مپڈمپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
(6)視è¦ڑçڑ„مپھه·¥ه¤«ï¼ڑ申請و›¸مپ®مƒ‡م‚¶م‚¤مƒ³م‚„مƒ¬م‚¤م‚¢م‚¦مƒˆم‚‚é‡چè¦پمپ§مپ™م€‚éپ©هˆ‡مپھن½™ç™½م€پèھمپ؟م‚„مپ™مپ„مƒ•م‚©مƒ³مƒˆم€په›³è،¨مپ®و´»ç”¨م€پ箇و،و›¸مپچمپ®ه¤ڑ用مپھمپ©م€پ視è¦ڑçڑ„مپ«و•´çگ†مپ•م‚Œمپں申請و›¸مپ¯م€په¯©وں»ه“،مپ®è² و‹…م‚’軽و¸›مپ—م€په†…ه®¹مپ®çگ†è§£م‚’ن؟ƒé€²مپ—مپ¾مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
2.2. وژ،وٹن؛‹ن¾‹مپ‹م‚‰ه¦مپ¶وˆگهٹںمپ®è¦په› هˆ†وگ
هگ„هٹ©وˆگو©ںé–¢مپ®م‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆمپ§مپ¯م€پéپژهژ»مپ®وژ،وٹن؛‹ن¾‹مپŒه…¬é–‹مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ه ´هگˆمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®ن؛‹ن¾‹م‚’هˆ†وگمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھه†…ه®¹م‚„è،¨çڈ¾مپŒè©•ن¾،مپ•م‚Œم‚„مپ™مپ„مپ®مپ‹م€په…·ن½“çڑ„مپھمƒ’مƒ³مƒˆم‚’ه¾—م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
وژ،وٹن؛‹ن¾‹مپ«ه…±é€ڑمپ—مپ¦è¦‹م‚‰م‚Œم‚‹وˆگهٹںمپ®è¦په› مپ¨مپ—مپ¦مپ¯م€پو¬،مپ®م‚ˆمپ†مپھ点مپŒوŒ™مپ’م‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
5مپ¤مپ®وˆگهٹںمپ®è¦په›
(1)وکژç¢؛مپھمƒ“م‚¸مƒ§مƒ³مپ¨وƒ…熱ï¼ڑه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑم‚’é€ڑمپکمپ¦ن½•م‚’éپ”وˆگمپ—مپںمپ„مپ®مپ‹م€پمپمپ®ه¼·مپ„و€مپ„مپŒن¼م‚ڈم‚‹è¨کè؟°م€‚
(2)ه…·ن½“çڑ„مپھه®ںو–½è¨ˆç”»ï¼ڑم‚؟م‚¤مƒ مƒ©م‚¤مƒ³م€پو‹…ه½“者م€په…·ن½“çڑ„مپھم‚؟م‚¹م‚¯مپŒوکژç¢؛مپ«ç¤؛مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚詳細مپھمƒمƒ¼مƒ‰مƒمƒƒمƒ—م€‚
(3)ه®ںçڈ¾هڈ¯èƒ½و€§مپ®é«کمپ•ï¼ڑن؛ˆç®—م€پن؛؛ه“،م€پوٹ€è،“çڑ„مپھé¢مپ‹م‚‰è¦‹مپ¦م€پ計画مپŒçڈ¾ه®ںçڑ„مپ«ه®ںè،Œهڈ¯èƒ½مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨م€‚éپژهژ»مپ®ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ه®ں績م‚„関連م‚¤مƒ™مƒ³مƒˆçµŒé¨“م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«ç¤؛مپ™مپ“مپ¨مپ§م€په®ںçڈ¾هڈ¯èƒ½و€§مپ®é«کمپ•م‚’ç¤؛مپ—مپ¾مپ™م€‚
(4)連وگ؛ن½“هˆ¶مپ®ه¼·ه›؛مپ•ï¼ڑه…±هگŒé–‹ه‚¬و©ںé–¢م€پهچ”هٹ›ه›£ن½“م€پهœ°هںں社ن¼ڑمپھمپ©م€په¤ڑو§کمپھم‚¹مƒ†م‚¤م‚¯مƒ›مƒ«مƒ€مƒ¼مپ¨مپ®é€£وگ؛ن½“هˆ¶م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«è¨کè؟°م€‚هچ”هƒچم‚’é€ڑمپکمپ¦ه¤§ن¼ڑمپ®ه½±éں؟هٹ›م‚„و³¢هڈٹهٹ¹وœمپŒو‹،ه¤§مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç¤؛ه”†مپ—مپ¾مپ™م€‚
(5)وˆگوœمپ®و³¢هڈٹو€§ï¼ڑه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ®وˆگوœمپŒهچکç™؛مپ§çµ‚م‚ڈم‚‰مپڑم€پ継ç¶ڑçڑ„مپھç™؛ه±•م‚„社ن¼ڑمپ¸مپ®ه؛ƒمپŒم‚ٹمپŒوœںه¾…مپ§مپچم‚‹مپ“مپ¨م€‚
ن¾‹مپˆمپ°م€په¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ§مپ®è°è«–مپŒو–°مپںمپھç ”ç©¶مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ«ç™؛ه±•مپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§م‚„م€پو”؟ç–وڈگ言مپ«مپ¤مپھمپŒم‚‹ه…·ن½“çڑ„مپھéپ“ç‹مپŒç¤؛مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ‹مپھمپ©مپŒè©•ن¾،مپ®ه¯¾è±،مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ن¸چوژ،وٹن؛‹ن¾‹مپ®هˆ†وگم‚‚وœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚مپمپ®çگ†ç”±م‚’وٹٹوڈ،مپ—م€پè‡ھه¦ن¼ڑمپ®ç”³è«‹و›¸ن½œوˆگمپ«و´»مپ‹مپ™مپ“مپ¨مپ§م€پهگŒمپکéپژمپ،م‚’ç¹°م‚ٹè؟”مپ™مپ“مپ¨م‚’éپ؟مپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پهٹ©وˆگو©ں関独è‡ھمپ®مƒںمƒƒم‚·مƒ§مƒ³م‚„é‡چ点هˆ†é‡ژم‚’و·±مپڈçگ†è§£مپ—م€پè‡ھه¦ن¼ڑمپ®ه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپŒمپمپ®ç‰¹و€§مپ«مپ„مپ‹مپ«هگˆè‡´مپ™م‚‹مپ‹م‚’م‚¢مƒ”مƒ¼مƒ«مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»هٹ©وˆگ金 申請م‚’وˆگهٹںمپ•مپ›م‚‹20مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆï½œه¦è،“英èھم‚¢م‚«مƒ‡مƒںمƒ¼ – م‚¨مƒٹم‚´
3. هٹ¹وœçڑ„مپھن؛ˆç®—計画مپ¨ه®ںو–½ن½“هˆ¶مپ®و§‹ç¯‰
مپ“مپ“مپ§مپ¯م€پهٹ©وˆگ金申請مپ®ن؟،é ¼و€§م‚’é«کم‚پم‚‹م€په …ه®ںمپھن؛ˆç®—計画مپ¨ç›¤çں³مپھه®ںو–½ن½“هˆ¶مپ®و§‹ç¯‰و–¹و³•م‚’ç ”ç©¶مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
هٹ©وˆگ金申請مپ«مپٹمپ„مپ¦م€په¦è،“çڑ„و„ڈ義م‚„社ن¼ڑ貢献ه؛¦مپ¨هگŒو§کمپ«é‡چè¦پمپھمپ®مپŒم€پمپمپ®ه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑم‚’مپ„مپ‹مپ«ه®ںçڈ¾هڈ¯èƒ½مپ§مپ‚م‚‹مپ‹م‚’ç¤؛مپ™م€Œن؛ˆç®—計画م€چمپ¨م€Œه®ںو–½ن½“هˆ¶م€چمپ§مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ¯م€پ申請ه†…ه®¹مپ®ن؟،é ¼و€§مپ¨ه®ںçڈ¾هڈ¯èƒ½و€§م‚’è£ڈن»کمپ‘م‚‹و ¹و‹ مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
3.1. é€ڈوکژو€§مپ¨هگˆçگ†و€§م‚’è؟½و±‚مپ—مپںن؛ˆç®—計画
ن؛ˆç®—計画مپ¯م€پ申請مپ™م‚‹ç ”究費مپŒمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«ن½؟م‚ڈم‚Œم‚‹مپ®مپ‹م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«ç¤؛مپ™م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚مپم‚Œمپم‚Œمپ®è²»ç”¨مپŒمپھمپœه؟…è¦پمپھمپ®مپ‹م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«ç®—ه‡؛مپ•م‚Œمپںمپ®مپ‹م‚’èھ¬وکژمپ™م‚‹م€Œهگˆçگ†و€§م€چمپ¨م€پن½؟途مپŒوکژç¢؛مپ§èھ°مپŒè¦‹مپ¦م‚‚çگ†è§£مپ§مپچم‚‹م€Œé€ڈوکژو€§م€چمپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
è¨کè؟°ن¸ٹمپ®و³¨و„ڈ点
(1)é …ç›®مپ”مپ¨مپ®è©³ç´°مپھه†…訳ï¼ڑن¼ڑه ´è²»م€پو—…è²»ن؛¤é€ڑè²»م€پè¬é‡‘م€پهچ°هˆ·è²»م€په؛ƒه ±è²»م€پو¶ˆè€—ه“پè²»مپھمپ©م€پ費目مپ”مپ¨مپ«ه…·ن½“çڑ„مپھه†…訳م‚’وکژè¨کمپ—مپ¾مپ™م€‚مپ•م‚‰مپ«م€پن؛؛ن»¶è²»م€پè¨ه‚™è²»م€پé€ڑن؟،éپ‹وگ¬è²»مپھمپ©م‚‚詳細مپ«هˆ†é،م€‚
(2)ç©چç®—و ¹و‹ مپ®وکژç¢؛هŒ–ï¼ڑهگ„費用مپ®ç©چç®—و ¹و‹ م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«ç¤؛مپ—مپ¾مپ™م€‚見ç©چو›¸و·»ن»کم‚„éپژهژ»ه®ں績هڈ‚考مپھمپ©م€په®¢è¦³çڑ„مپھو ¹و‹ م‚’ç¤؛مپ™مپ“مپ¨مپ§م€پن؛ˆç®—مپ®ه¦¥ه½“و€§مپŒé«کمپ¾م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
(3)è‡ھه·±è³‡é‡‘مپ¨مپ®مƒگمƒ©مƒ³م‚¹ï¼ڑهٹ©وˆگ金مپ مپ‘مپ§ه…¨مپ¦م‚’賄مپ†مپ®مپ§مپ¯مپھمپڈم€په¦ن¼ڑمپ®è‡ھه·±è³‡é‡‘م‚„ن»–مپ®هڈژه…¥و؛گ(هڈ‚هٹ è²»م€پهچ”賛金م€په±•ç¤؛ن¼ڑه‡؛ه±•و–™مپھمپ©ï¼‰مپ¨مپ®مƒگمƒ©مƒ³م‚¹م‚’ç¤؛مپ™مپ“مپ¨مپ§م€پم‚ˆم‚ٹه …ه®ںمپھ計画مپ‹مپ©مپ†مپ‹م‚¢مƒ”مƒ¼مƒ«مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
(4)ن¸چو¸¬مپ®ن؛‹و…‹مپ¸مپ®ه¯¾ه؟œï¼ڑن؛ˆه‚™è²»ï¼ˆç·ڈن؛ˆç®—مپ®5%程ه؛¦وژ¨ه¥¨ï¼‰م‚’計ن¸ٹمپ™م‚‹مپھمپ©م€پن¸چو¸¬مپ®ن؛‹و…‹مپ«م‚‚ه¯¾ه؟œمپ§مپچم‚‹وں”è»ںو€§م‚’وŒپمپںمپ›م‚‹مپ“مپ¨م‚‚و¤œè¨ژمپ«ه€¤مپ—مپ¾مپ™م€‚ن؟é™؛ه¥‘ç´„مپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚‚ه؟…è¦پمپ§مپ‚م‚Œمپ°è¨€هڈٹمپ—مپ¾مپ™م€‚
(5)費用ه¯¾هٹ¹وœمپ®و„ڈèکï¼ڑé™گم‚‰م‚Œمپںن؛ˆç®—مپ®ن¸مپ§م€پمپ„مپ‹مپ«وœ€ه¤§مپ®هٹ¹وœï¼ˆه¦è،“çڑ„وˆگوœم€پ社ن¼ڑ貢献)م‚’ç”ںمپ؟ه‡؛مپ™مپ‹م‚’و„ڈèکمپ—مپںن؛ˆç®—é…چهˆ†مپ§مپ‚م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç¤؛مپ—مپ¾مپ™م€‚
(6)é–“وژ¥çµŒè²»مپ®هڈ–م‚ٹو‰±مپ„ï¼ڑه…¬çڑ„هٹ©وˆگ金مپ®ه ´هگˆم€پé–“وژ¥çµŒè²»ï¼ˆç ”究و©ںé–¢مپ®ç®،çگ†éپ‹ه–¶مپ«ه؟…è¦پمپھ経費)مپ®è¨ˆن¸ٹمپŒèھچم‚پم‚‰م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپمپ®ه ´هگˆم€پéپ©هˆ‡مپ«è¨ˆن¸ٹمپ—م€پمپمپ®ن½؟途مپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚‚وکژç¢؛مپ«èھ¬وکژمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»ç§‘ه¦ç ”究費هٹ©وˆگن؛‹و¥ï¼ˆç§‘ç ”è²»ï¼‰مپ®éپ©و£مپھç®،çگ†ç‰مپ«مپ¤مپ„مپ¦ï½œو—¥وœ¬ه¦è،“وŒ¯èˆˆن¼ڑ
3.2. 盤çں³مپھه®ںو–½ن½“هˆ¶مپ¨ه¦ن¼ڑه†…ه¤–مپ®é€£وگ؛
مپ©م‚“مپھمپ«ç´ و™´م‚‰مپ—مپ„ن¼پç”»مپ§مپ‚مپ£مپ¦م‚‚م€پمپم‚Œم‚’ه®ںè،Œمپ™م‚‹ن½“هˆ¶مپŒن¸چهچپهˆ†مپ§مپ‚م‚Œمپ°م€پهٹ©وˆگ金مپ¯وژ،وٹمپ•م‚Œمپ¾مپ›م‚“م€‚ه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑم‚’وˆگهٹںمپ«ه°ژمپڈمپںم‚پمپ®م€Œه®ںو–½ن½“هˆ¶م€چمپ¯م€پ申請و›¸مپ®é‡چè¦پمپھè©•ن¾،مƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ®ن¸€مپ¤مپ§مپ™م€‚
وٹ¼مپ•مپˆمپ¦مپٹمپچمپںمپ„5مƒم‚¤مƒ³مƒˆ
(1)ه½¹ه‰²هˆ†و‹…مپ®وکژç¢؛هŒ–ï¼ڑه®ںè،Œه§”ه“،ن¼ڑم‚„ن؛‹ه‹™ه±€مپ®مƒ،مƒ³مƒگمƒ¼و§‹وˆگم€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®ه½¹ه‰²مپ¨è²¬ن»»م‚’وکژç¢؛مپ«è¨کè؟°مپ—مپ¾مپ™م€‚ه…·ن½“çڑ„مپھو°ڈهگچم‚„ه½¹èپ·م‚’وکژè¨کمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پن½“هˆ¶مپ®ه…·ن½“و€§مپŒه¢—مپ—مپ¾مپ™م€‚
(2)ه°‚é–€و€§مپ¨çµŒé¨“مپ®وڈگç¤؛ï¼ڑن¸»è¦پمپھو‹…ه½“者مپ®ه°‚é–€هˆ†é‡ژم‚„م€پéپژهژ»مپ®ه¤§ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹ه®ں績مپھمپ©م‚’è¨کè؟°مپ—م€په¤§ن¼ڑم‚’ه††و»‘مپ«éپ‹ه–¶مپ™م‚‹èƒ½هٹ›مپŒمپ‚م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç¤؛مپ—مپ¾مپ™م€‚éپژهژ»مپ«ه¤§è¦ڈو¨،مپھه›½éڑ›ه¦è،“ن¼ڑè°م‚’وˆگهٹںمپ•مپ›مپں経験م‚„م€پ特ه®ڑمپ®هˆ†é‡ژمپ«مپٹمپ‘م‚‹و·±مپ„çں¥è¦‹م‚’وŒپمپ¤مƒ،مƒ³مƒگمƒ¼مپŒمپ„م‚‹مپ“مپ¨م‚’ه¼·èھ؟مپ—مپ¾مپ™م€‚
(3)ه¦ن¼ڑه†…ه¤–مپ®é€£وگ؛ï¼ڑ関連ه¦ن¼ڑم€په¤§ه¦م€پç ”ç©¶و©ںé–¢م€پن¼پو¥م€پهœ°و–¹è‡ھو²»ن½“م€په¸‚و°‘ه›£ن½“مپھمپ©م€په¤ڑو§کمپھم‚¹مƒ†م‚¤م‚¯مƒ›مƒ«مƒ€مƒ¼مپ¨مپ®é€£وگ؛ن½“هˆ¶م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«è¨کè؟°مپ—مپ¾مپ™م€‚ه…±هگŒé–‹ه‚¬م€په¾Œوڈ´م€پهچ”è³›م€پهچ”هٹ›مپ¨مپ„مپ£مپںé–¢ن؟‚و€§م‚’وکژç¢؛مپ«مپ—م€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®ه½¹ه‰²مپ¨è²¢çŒ®م‚’èھ¬وکژمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپ®ه½±éں؟هٹ›م‚„社ن¼ڑ貢献ه؛¦مپŒé«کمپ¾م‚‹مپ“مپ¨م‚’م‚¢مƒ”مƒ¼مƒ«مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚特مپ«م€پهœ°هںں社ن¼ڑمپ¨مپ®é€£وگ؛مپ¯م€په¦ن¼ڑمپ®هœ°هںں貢献و€§م‚’ه¼·èھ؟مپ™م‚‹ن¸ٹمپ§وœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚
(4)مƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†ن½“هˆ¶ï¼ڑن¸چو¸¬مپ®ن؛‹و…‹ï¼ˆن¾‹ï¼ڑè‡ھ然çپ½ه®³م€پمƒ‘مƒ³مƒ‡مƒںمƒƒم‚¯م€پن¸»è¦پ講و¼”者مپ®و€¥مپھم‚مƒ£مƒ³م‚»مƒ«ï¼‰مپ«ه‚™مپˆمپںمƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†ن½“هˆ¶مپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚‚言هڈٹمپ—مپ¾مپ™م€‚ç·ٹو€¥و™‚مپ®é€£çµ،ن½“هˆ¶م€پن»£و›؟و،ˆمپ®و؛–ه‚™م€پن؛ˆه‚™ن؛؛ه“،مپ®ç¢؛ن؟مپھمپ©م€په…·ن½“çڑ„مپھه¯¾ه؟œç–م‚’ç¤؛مپ™مپ“مپ¨مپ§م€پ計画مپ®ه …牢و€§م‚’م‚¢مƒ”مƒ¼مƒ«مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
(5)è‹¥و‰‹è‚²وˆگمپ¨ه¤ڑو§کو€§مپ¸مپ®é…چو…®ï¼ڑه®ںو–½ن½“هˆ¶مپ«è‹¥و‰‹ç ”究者م‚„ه¥³و€§ç ”究者م‚’ç©چو¥µçڑ„مپ«ç™»ç”¨مپ™م‚‹و–¹é‡م‚’ç¤؛مپ™مپ“مپ¨مپ§م€په¦ن¼ڑمپ®وŒپç¶ڑهڈ¯èƒ½و€§مپ¨ه¤ڑو§کو€§مپ¸مپ®é…چو…®م‚’م‚¢مƒ”مƒ¼مƒ«مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚هڈ¯èƒ½مپ§مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
وœ¬é€£è¼‰م‚·مƒھمƒ¼م‚؛مپ®è¨کن؛‹م‚‚هڈ‚考مپ«مپ—مپ¦مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
مƒ»م€Œهٹ©وˆگ金مپ§ه؛ƒمپŒم‚‹ه¦ن¼ڑمپ®هڈ¯èƒ½و€§ï½ç”³è«‹مپ®هں؛وœ¬مپ¨وژ،وٹçژ‡م‚’é«کم‚پم‚‹ن¼پç”»مƒژم‚¦مƒڈم‚¦ï½م€چ
مƒ»ه¦ن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶م€پو؛–ه‚™مپŒه¤§ه¤‰ï¼پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«è§£و±؛مپ™م‚‹ï¼ں|مپ“م‚Œمپ‹م‚‰مپ®ه¦ن¼ڑ.com
مپ¾مپ¨م‚پ هٹ©وˆگ金م‚’و´»مپ‹مپ—مپںه¦ن¼ڑن¼پç”»مپ®è¨è¨ˆمپ¨éپ‹ه–¶مپ¸
ه¦è،“集ن¼ڑهٹ©وˆگ金مپ®ç”³è«‹مپ¯م€پهچکمپ«è³‡é‡‘çچ²ه¾—مپ®مپںم‚پمپ®و‰‹ç¶ڑمپچمپ«ç•™مپ¾م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپم‚Œمپ¯م€پè‡ھهˆ†مپںمپ،مپ®ه¦ن¼ڑمپ®ه¦è،“çڑ„و´»ه‹•م‚’ه®¢è¦³çڑ„مپ«è¦‹مپ¤م‚پç›´مپ—م€پمپمپ®و„ڈ義مپ¨ç¤¾ن¼ڑ貢献مپ®هڈ¯èƒ½و€§م‚’言èھهŒ–مپ™م‚‹è²´é‡چمپھو©ںن¼ڑمپ§م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
وœ¬è¨کن؛‹مپ§è؟°مپ¹مپںم‚ˆمپ†مپ«م€په¦è،“çڑ„و„ڈ義مپ¨ç¤¾ن¼ڑ貢献مپ®مƒگمƒ©مƒ³م‚¹م‚’و„ڈèکمپ—مپں申請و§‹وˆگم€په¯©وں»ه“،مپ®è¦–点مپ«ç«‹مپ£مپںن¼مپˆو–¹مپ®ه·¥ه¤«م€پمپمپ—مپ¦é€ڈوکژو€§مپ¨هگˆçگ†و€§م‚’è؟½و±‚مپ—مپںن؛ˆç®—計画مپ¨ç›¤çں³مپھه®ںو–½ن½“هˆ¶مپ®و§‹ç¯‰مپ¯م€پوژ،وٹمپ¸مپ®éپ“م‚’و‹“مپڈمپںم‚پمپ®é‡چè¦پمپھè¦پç´ مپ§مپ™م€‚
مپ“م‚Œم‚‰مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚’ن¸په¯§مپ«وٹ¼مپ•مپˆم€پè‡ھه¦ن¼ڑمپ®ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑمپŒوŒپمپ¤ç‹¬è‡ھمپ®ن¾،ه€¤مپ¨م€پمپم‚Œم‚‰مپŒç¤¾ن¼ڑمپ«م‚‚مپںم‚‰مپ™وœھو¥م‚’م€پوƒ…熱م‚’وŒپمپ£مپ¦ن¼مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپ§هٹ©وˆگ金çچ²ه¾—مپ®هڈ¯èƒ½و€§مپŒه¤§مپچمپڈé«کمپ¾م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
هٹ©وˆگ金و´»ç”¨مپ¯م€په¦ن¼ڑمپŒم‚ˆم‚ٹè³ھمپ®é«کمپ„ه¦è،“ن¼ڑè°مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑم‚’é–‹ه‚¬مپ—م€پç ”ç©¶وˆگوœم‚’社ن¼ڑé‚„ه…ƒمپ™م‚‹و©ںن¼ڑم‚’و‹،ه¤§مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپ¤مپھمپŒم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€په¦è،“مپ®ç™؛ه±•مپ«ه¯„ن¸ژمپ™م‚‹مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پ社ن¼ڑه…¨ن½“مپ®é€²و©مپ«م‚‚貢献مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚
هٹ©وˆگ金申請مپ®مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ¯م€په¦ن¼ڑه†…部مپ®هچ”هٹ›ن½“هˆ¶م‚’ه¼·هŒ–مپ—م€په¤–部مپ®é–¢é€£و©ںé–¢مپ¨مپ®و–°مپںمپھمƒچمƒƒمƒˆمƒ¯مƒ¼م‚¯م‚’و§‹ç¯‰مپ™م‚‹و©ںن¼ڑمپ§م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپںمپ¨مپˆن¸€ه؛¦مپ§وژ،وٹمپ«è‡³م‚‰مپھمپڈمپ¨م‚‚م€پ申請و›¸ن½œوˆگمپ®çµŒé¨“مپ¯م€په¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®و´»ه‹•م‚’ه†چè©•ن¾،مپ—م€پو¬،مپھم‚‹وŒ‘وˆ¦مپ¸مپ®ç³§مپ¨مپھم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚継ç¶ڑçڑ„مپھو”¹ه–„مپ¨وŒ‘وˆ¦مپ“مپمپŒم€په¦ن¼ڑمپ®وŒپç¶ڑçڑ„مپھç™؛ه±•م‚’و”¯مپˆم‚‹هژںه‹•هٹ›مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
هٹ©وˆگ金مپ®ç”³è«‹مپ¯ç ”究مپ¨هگŒمپکم‚ˆمپ†مپ«â€œه¤±و•—مپ¯وˆگهٹںمپ®ç¬¬ن¸€و©â€œمپ¨è€ƒمپˆم€پ絶مپˆé–“مپھمپ„هٹھهٹ›مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œم‚‹هˆ†é‡ژمپ§مپ™م€‚ن¸€و©ن¸€و©مپ®ç©چمپ؟é‡چمپمپŒم€په؟…مپڑوˆگوœمپ«çµگمپ³مپ¤مپچمپ¾مپ™م€‚