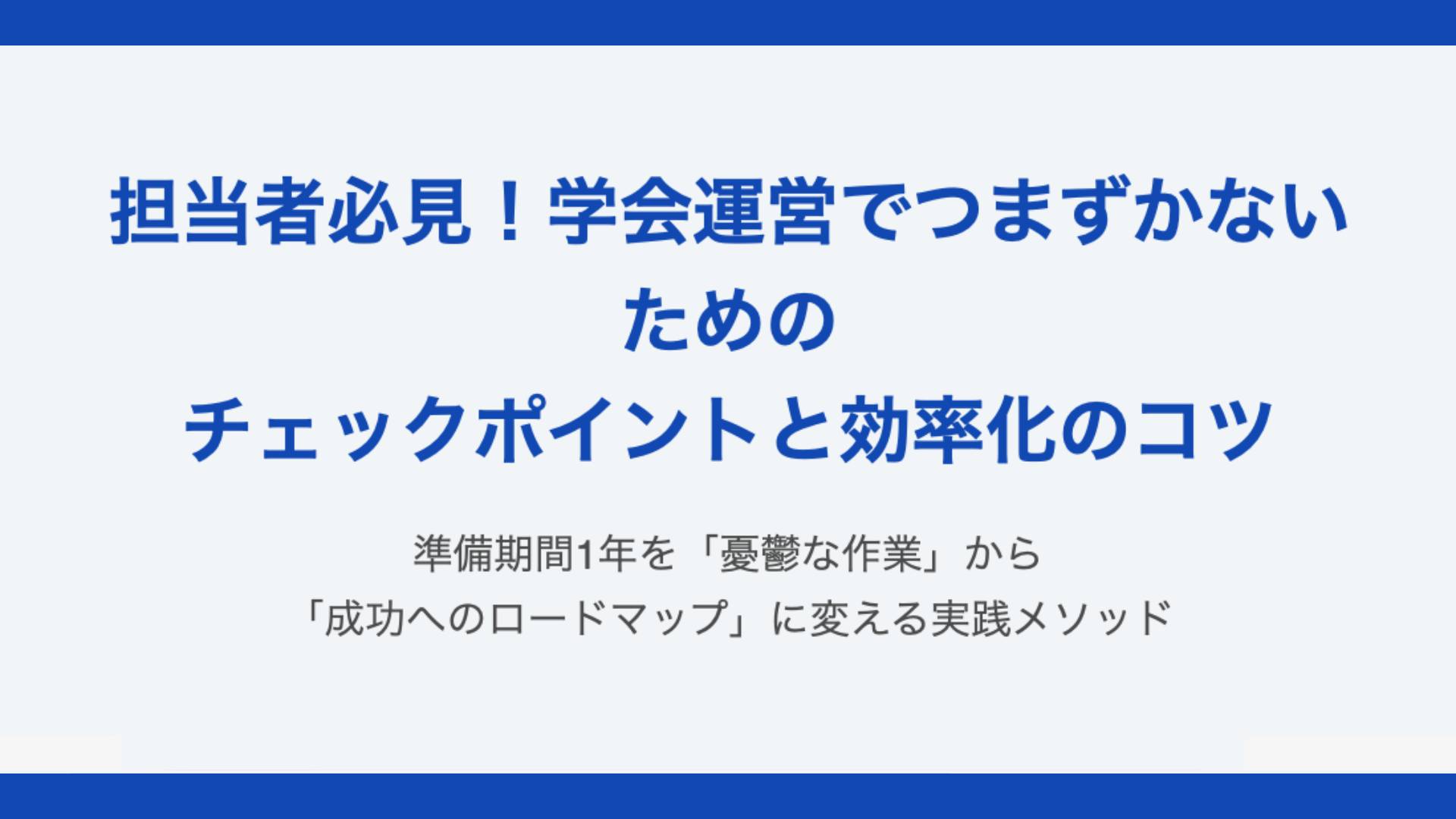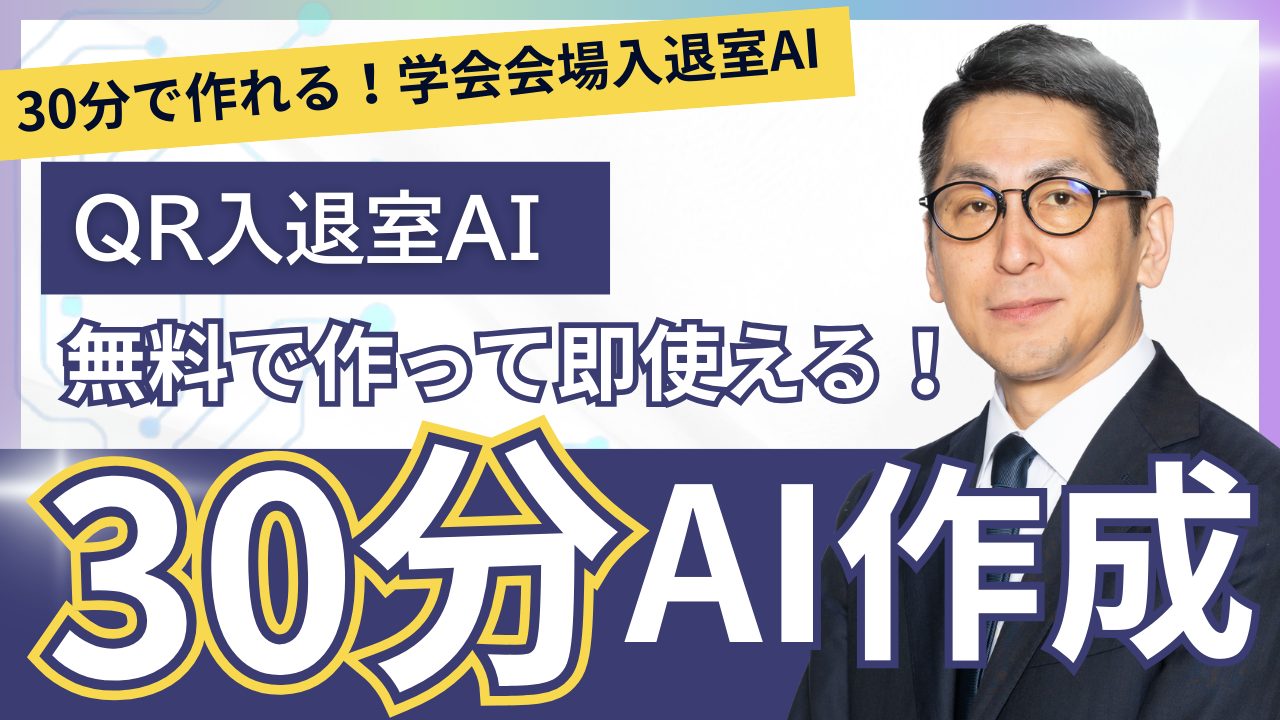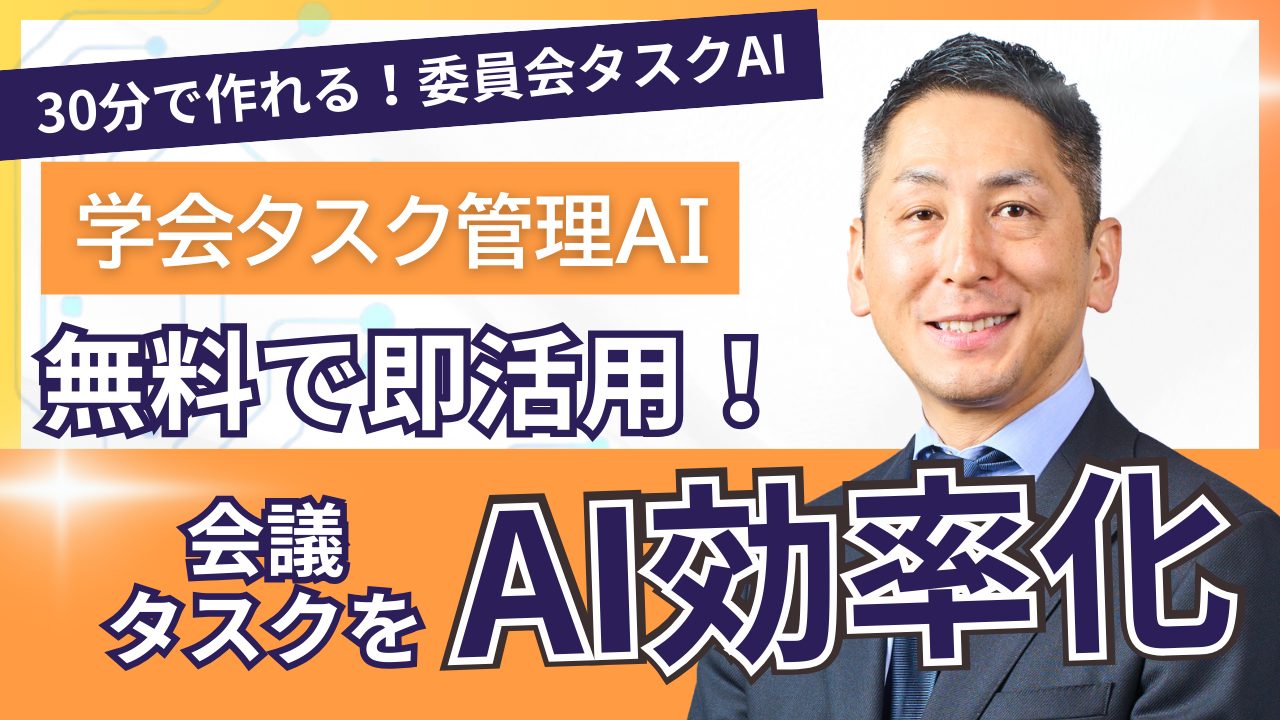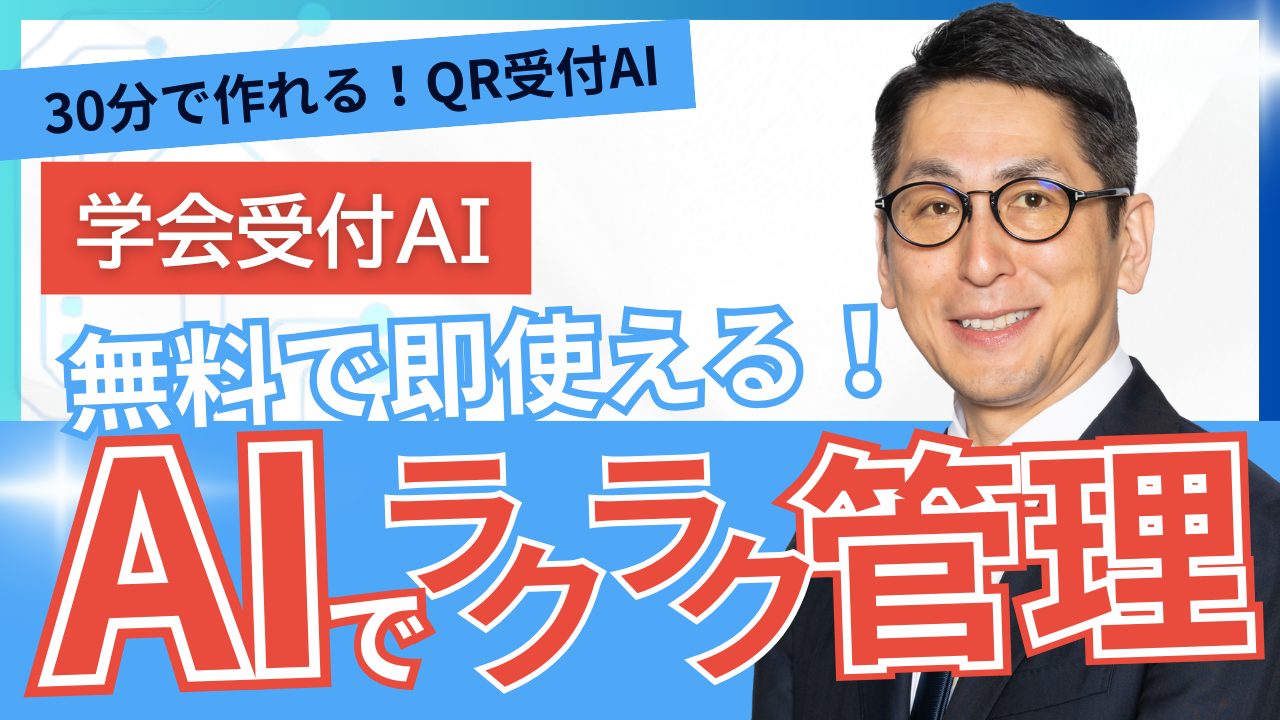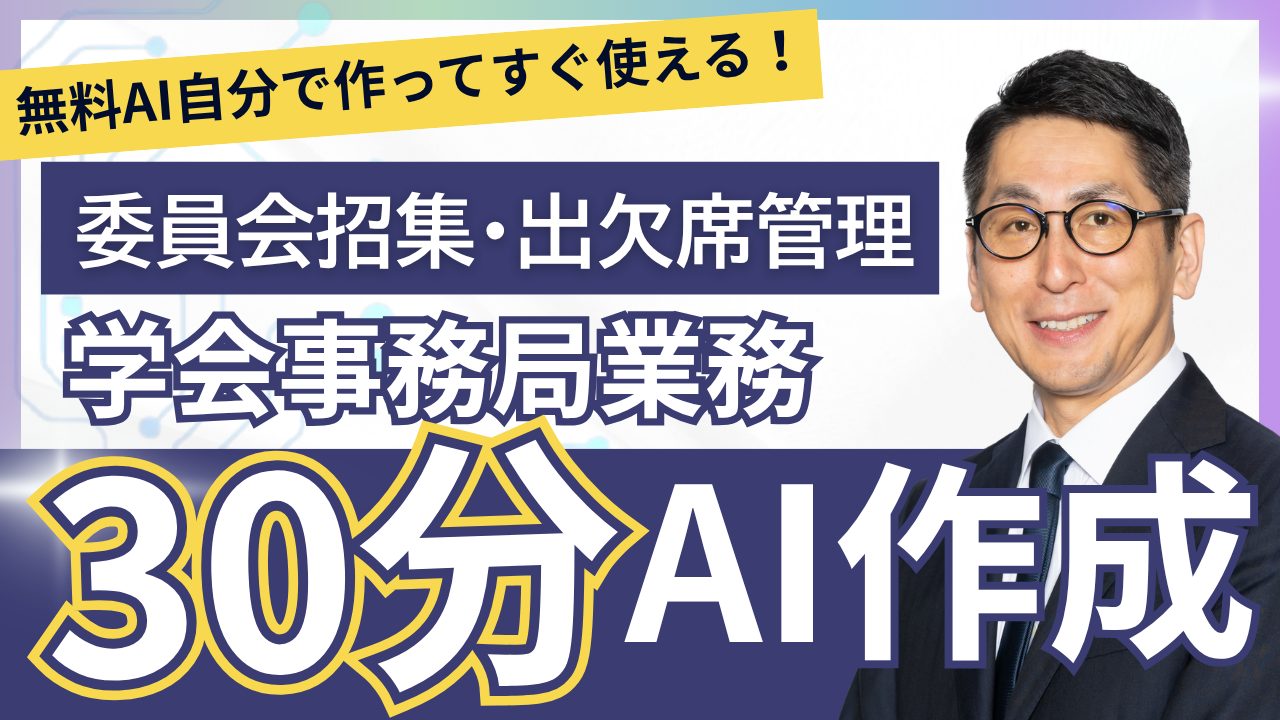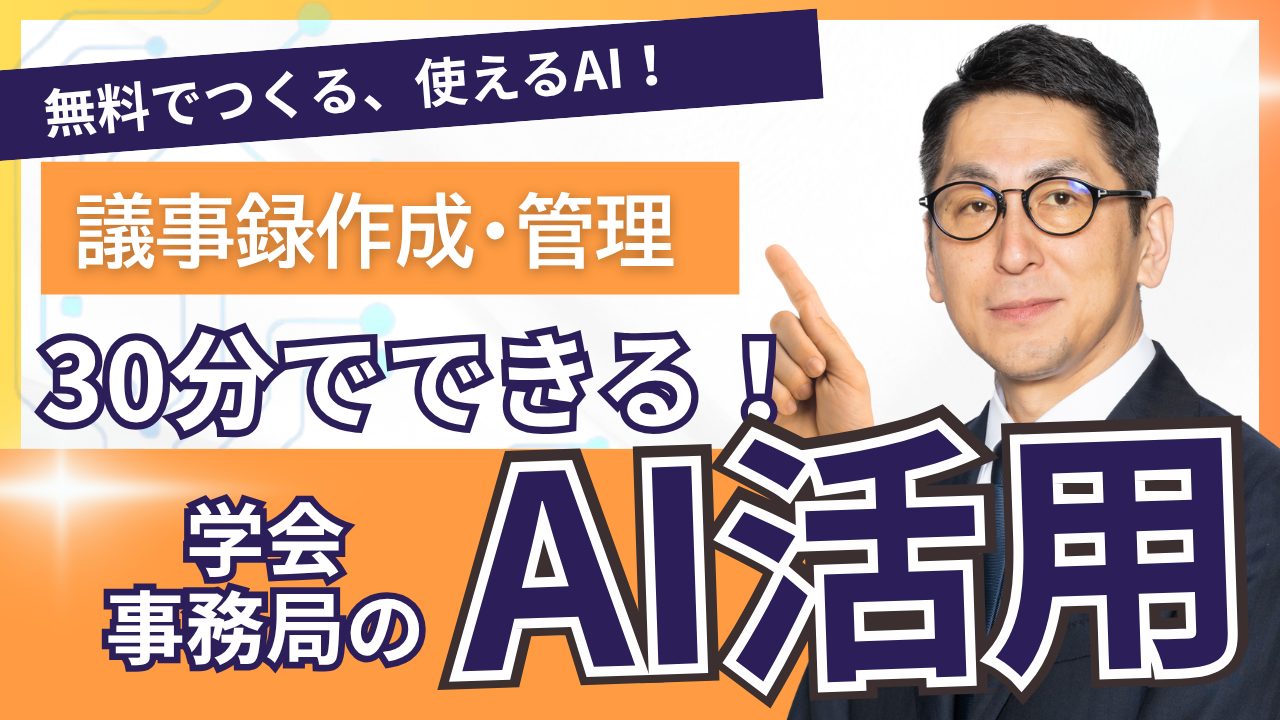еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ§йҷҘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҖҢгӮҲгҒҸгҒӮгӮӢиӘӨи§ЈгҖҚгҒЁжҲҗеҠҹгҒ®гғ’гғігғҲ гҖңжҲҗеҠҹгҒ®йҚөгҒҜжӯЈгҒ—гҒ„зҗҶи§ЈгҒЁгғҒгғјгғ еҠӣгҖң
2025е№ҙ08жңҲ19ж—Ҙ
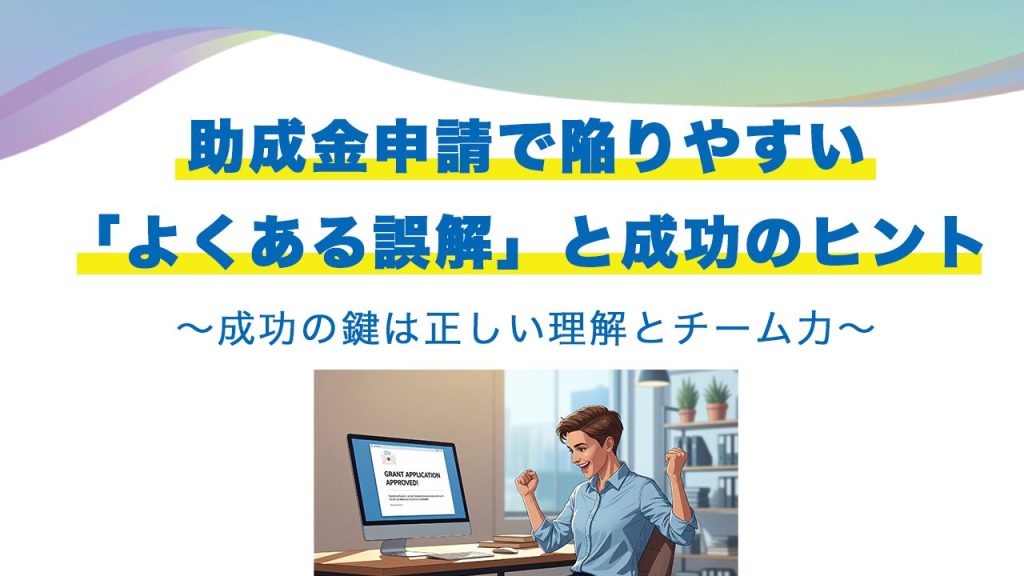
еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢйӣЈгҒ—гҒқгҒҶгҖҚгҖҢжҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒқгҒҶгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҚ°иұЎгӮ’гҒҠжҢҒгҒЎгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮе®ҹгҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®з”іи«ӢиҖ…гҒҢжҠұгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖҺгӮҲгҒҸгҒӮгӮӢиӘӨи§ЈгҖҸгӮ’и§Јж¶ҲгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒз”іи«Ӣгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜй©ҡгҒҸгҒ»гҒ©гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒе®ҹеӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒ®зҡҶгҒ•гӮ“гҒҢжҠұгҒҲгӮӢе…·дҪ“зҡ„гҒӘз–‘е•ҸгҒёгҒ®еӣһзӯ”гҒЁгҖҒжҲҗеҠҹгҒ«е°ҺгҒҸгҒҹгӮҒгҒ®е®ҹи·өзҡ„гҒӘгғ’гғігғҲгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжӯЈгҒ—гҒ„зҹҘиӯҳгҒЁжҲҰз•ҘгӮ’иә«гҒ«гҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжҺЎжҠһгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҒҜж јж®өгҒ«й«ҳгҒҫгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иӘӨи§Ј1пјҡе®Ңз’§гҒӘз”іи«ӢжӣёгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°з”іи«ӢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҖгҖңдәҲз®—иЁҲз”»гҒ®е®Ңз’§дё»зҫ©гҒҢжӢӣгҒҸз”іи«ӢгҒ®йҒ…гӮҢ
гҖҢгҒҫгҒ и©ізҙ°гҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгӮүжқҘе№ҙгҒ«еӣһгҒқгҒҶгҖҚвҖ”гҒқгҒҶиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹеӯҰиЎ“дјҡиӯ°гӮ„еӯҰдјҡеӨ§дјҡгҒ®и©ізҙ°гҒӘиЁҲз”»гҒҜзўәгҒӢгҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еӯҰиЎ“еҠ©жҲҗж©ҹй–ўгҒҢдҪ•гӮҲгӮҠйҮҚиҰ–гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒз”іи«ӢиҖ…гҒ®гҖҢзҶұж„ҸгҖҚгӮ„з ”з©¶гҒ®гҖҢе°ҶжқҘжҖ§гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮе®Ңз’§гӮ’жұӮгӮҒгҒҷгҒҺгҒҰиІҙйҮҚгҒӘз”іи«Ӣж©ҹдјҡгӮ’йҖёгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮгӮӮгҒЈгҒҹгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮзҸҫжҷӮзӮ№гҒ§гҒ®жңҖе–„гӮ’е°ҪгҒҸгҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘгғ“гӮёгғ§гғігӮ’зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ®ж–№гҒҢгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гғ’гғігғҲпјҡ
з”іи«ӢжӣёгҒ§гҒҜгҖҒеӯҰиЎ“йӣҶдјҡгӮ„еӯҰдјҡеӨ§дјҡгҒ®жҲҗжһңзӣ®жЁҷгҒЁгҖҒгҒқгҒ“гҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ®гғӯгғјгғүгғһгғғгғ—гӮ’еҸҜиғҪгҒӘйҷҗгӮҠжҳҺзўәгҒ«зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮеҜ©жҹ»е“ЎгҒҢгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®еӯҰдјҡгҒ®гғ“гӮёгғ§гғігӮ’гҖҢдёҖз·’гҒ«е®ҹзҸҫгҒ—гҒҹгҒ„гҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘе·ҘеӨ«гӮ’еҝғгҒҢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒҚгҒЈгҒЁеҘҪеҚ°иұЎгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»еӯҰдјҡзӯүй–ӢеӮ¬еҠ©жҲҗпјұпјҶпјЎпҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәәеҠ и—ӨиЁҳеҝөгғҗгӮӨгӮӘгӮөгӮӨгӮЁгғігӮ№жҢҜиҲҲиІЎеӣЈ
иӘӨи§Ј2пјҡйҒҺеҺ»гҒ®й–ӢеӮ¬е®ҹзёҫгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁжҺЎжҠһгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖңе®ҹзёҫгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒЁи«ҰгӮҒгӮӢеүҚгҒ«
ж–°гҒ—гҒҸиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹеӯҰдјҡгӮ„гҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ«гҒӘгҒ„гғҶгғјгғһгҒ§гҒ®йӣҶдјҡдјҒз”»гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢе®ҹзёҫгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүжҺЎжҠһгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҖҚгҒЁжңҖеҲқгҒӢгӮүи«ҰгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶж–№гҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘиӘӨи§ЈгҒ§гҒҷгҖӮеӨҡгҒҸгҒ®еҠ©жҲҗж©ҹй–ўгҒ§гҒҜгҖҒдјҒз”»гҒ®гҖҢж–°иҰҸжҖ§гҖҚгӮ„гҖҢе°ҶжқҘжҖ§гҖҚгҖҒгҒқгҒ®йӣҶдјҡгҒҢеӯҰиЎ“еҲҶйҮҺгӮ„зӨҫдјҡгҒ«гӮӮгҒҹгӮүгҒҷгҖҢеҸҜиғҪжҖ§гҖҚгҒ®гҒӮгӮӢгӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгӮ’й«ҳгҒҸи©•дҫЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ’гғігғҲпјҡ
гҒҹгҒЁгҒҲеӯҰдјҡгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еӨ§иҰҸжЁЎгҒӘй–ӢеӮ¬е®ҹзёҫгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒдјҒз”»гҒ®зӢ¬еүөжҖ§гӮ„гҖҒйӣҶдјҡгҒҢзӣ®жҢҮгҒҷжҳҺзўәгҒӘзӣ®зҡ„гҖҒгҒқгҒ—гҒҰ5е№ҙеҫҢгғ»10е№ҙеҫҢгҒёгҒ®еұ•жңӣгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҒҺеҺ»гҒ«е°ҸиҰҸжЁЎгҒӘз ”з©¶дјҡгӮ„гӮӘгғігғ©гӮӨгғігӮ»гғҹгғҠгғјгӮ’й–ӢеӮ¬гҒ—гҒҹзөҢйЁ“гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгӮүгӮ’йҒӢе–¶дҪ“еҲ¶гҒ®дҝЎй јжҖ§гӮ„еҸӮеҠ иҖ…жӢЎеӨ§гҒ®ж №жӢ гҒЁгҒ—гҒҰз©ҚжҘөзҡ„гҒ«жҸҗзӨәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиӘ¬еҫ—еҠӣгҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»дәҢеӣҪй–“дәӨжөҒдәӢжҘӯпҪңзӢ¬з«ӢиЎҢж”ҝжі•дәәж—Ҙжң¬еӯҰиЎ“жҢҜиҲҲдјҡ
иӘӨи§Ј3пјҡдәҲз®—гҒҜеӨҡгҒ‘гӮҢгҒ°еӨҡгҒ„гҒ»гҒ©иүҜгҒ„гҖңй«ҳйЎҚдәҲз®—з”іи«ӢгҒҢжӢӣгҒҸж„ҸеӨ–гҒӘиҗҪгҒЁгҒ—з©ҙ
гҖҢгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸз”іи«ӢгҒҷгӮӢгҒӘгӮүгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘еӨҡгҒҸгҒ®дәҲз®—гӮ’гҖҚгҒЁиҖғгҒҲгӮӢж°—жҢҒгҒЎгҒҜиҮӘ然гҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ‘гӮҢгҒ©гӮӮгҖҒдәҲз®—гҒ§жңҖгӮӮйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜйҮ‘йЎҚгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®гҖҢеҗҲзҗҶжҖ§гҖҚгҒЁгҖҢйҖҸжҳҺжҖ§гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮеҝ…иҰҒд»ҘдёҠгҒ«й«ҳйЎҚгҒӘдәҲз®—гҒҜгҖҒеҜ©жҹ»е“ЎгҒ«гҖҢжң¬еҪ“гҒ«гҒ“гҒ®йҮ‘йЎҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒӢпјҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶз–‘еҝөгӮ’жҠұгҒӢгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҒ©жӯЈгҒӘз©Қз®—ж №жӢ гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹгҖҒиІ»з”ЁеҜҫеҠ№жһңгҒ®й«ҳгҒ„дәҲз®—иЁҲз”»гӮ’з«ӢгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®ж–№гҒҢгҖҒгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гғ’гғігғҲпјҡ
дәҲз®—гӮ’зө„гӮҖйҡӣгҒҜгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®зөҢиІ»й …зӣ®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ізҙ°гҒӘеҶ…иЁігҒЁз©Қз®—ж №жӢ гӮ’жҳҺиЁҳгҒ—гҖҒгҖҢгҒӘгҒңгҒ“гҒ®иІ»з”ЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒӢгҖҚгӮ’第дёүиҖ…гҒ«гӮӮеҲҶгҒӢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«и«–зҗҶзҡ„гҒ«иӘ¬жҳҺгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘжә–еӮҷгҒҢгғқгӮӨгғігғҲгҒ§гҒҷгҖӮиҝ‘е№ҙгҒ®зӣёе ҙдҫЎж јгӮ„йҒҺеҺ»гҒ®йЎһдјјгӮӨгғҷгғігғҲгҒ®е®ҹйҡӣгҒ®иІ»з”ЁгӮ’еҸӮиҖғиіҮж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰж·»д»ҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒйҖҸжҳҺжҖ§гҒЁеҗҲзҗҶжҖ§гӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
иӘӨи§Ј4пјҡй–ӢеӮ¬ж„Ҹзҫ©гҒҜеӯҰиЎ“зҡ„гҒ§гҒӮгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢе…ЁгҒҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖңзӨҫдјҡзҡ„еҪұйҹҝгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§гӮ’иҰӢиҗҪгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒӢ
еӯҰиЎ“йӣҶдјҡгҒ®дёӯеҝғзҡ„гҒӘзӣ®зҡ„гҒҢеӯҰиЎ“зҡ„гҒӘиІўзҢ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜиЁҖгҒҶгҒҫгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—иҝ‘е№ҙгҖҒеҠ©жҲҗж©ҹй–ўгҒ®еӨҡгҒҸгҒҜгҖҒзӨҫдјҡгҒёгҒ®жіўеҸҠеҠ№жһңгӮ„ең°еҹҹиІўзҢ®гҖҒеӨҡж§ҳгҒӘеҸӮеҠ иҖ…гҒёгҒ®й–ҖжҲёй–Ӣж”ҫгҒӘгҒ©гӮӮйҮҚиҰ–гҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҚҳгҒ«з ”究иҖ…еҗҢеЈ«гҒ®зҷәиЎЁгҒ®е ҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒқгҒ®йӣҶдјҡгҒҢзӨҫдјҡе…ЁдҪ“гҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгғқгӮёгғҶгӮЈгғ–гҒӘеӨүеҢ–гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒҷгҒӢгҖҒж–°гҒҹгҒӘеҲҶйҮҺжЁӘж–ӯзҡ„гҒӘдәӨжөҒгӮ„з”ЈеӯҰйҖЈжҗәгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гӮ’з”ҹгӮҖгҒӢгҒӘгҒ©гҖҒеӨҡи§’зҡ„гҒӘж„Ҹзҫ©гӮ’зӣӣгӮҠиҫјгӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз”іи«ӢжӣёгҒ®йӯ…еҠӣгҒҜйЈӣиәҚзҡ„гҒ«й«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ’гғігғҲпјҡ
з”іи«ӢжӣёгҒ«гҒҜгҖҒеӯҰиЎ“зҡ„ж„Ҹзҫ©гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒең°еҹҹзӨҫдјҡгҒёгҒ®иІўзҢ®гӮ„з•°еҲҶйҮҺгғ»з•°ж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҒ®дҝғйҖІгҖҒиӢҘжүӢз ”з©¶иҖ…гҒ®иӮІжҲҗгҖҒдёҖиҲ¬еёӮж°‘гҒёгҒ®з§‘еӯҰжҷ®еҸҠжҙ»еӢ•гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзӨҫдјҡзҡ„гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘е…·дҪ“зҡ„гҒӘдәӢдҫӢгӮ’жҢҷгҒ’гҒҰиЁҳиҝ°гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§иӘ¬еҫ—еҠӣгҒҢеӨ§е№…гҒ«еҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»еӯҰиЎ“йӣҶдјҡеҠ©жҲҗпҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәәиҮЁеәҠз ”з©¶еҘЁеҠұеҹәйҮ‘
иӘӨи§Ј5пјҡз”іи«ӢжӣёгҒҜжӢ…еҪ“иҖ…дёҖдәәгҒ§е®Ңз’§гҒ«д»•дёҠгҒ’гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖңжҲҗеҠҹгҒ®йҚөгҒҜжӯЈгҒ—гҒ„зҗҶи§ЈгҒЁгғҒгғјгғ еҠӣ
гҖҢз”іи«ӢжӣёгҒҜиҮӘеҲҶгҒҢиІ¬д»»гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰе®ҢжҲҗгҒ•гҒӣгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҚгҒЁиҖғгҒҲгӮӢзңҹйқўзӣ®гҒӘжӢ…еҪ“иҖ…гҒ®ж–№гҒ»гҒ©гҖҒгҒ“гҒ®иӘӨи§ЈгҒ«йҷҘгӮҠгҒҢгҒЎгҒ§гҒҷгҖӮеӯҰиЎ“йӣҶдјҡгӮ„еӯҰдјҡеӨ§дјҡгҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒҜгҖҒжұәгҒ—гҒҰдёҖдәәгҒ гҒ‘гҒ®дҪңжҘӯгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгӮҖгҒ—гӮҚгҖҒеӯҰдјҡе…ЁдҪ“гҒ®еҚ”еҠӣдҪ“еҲ¶гҒ“гҒқгҒҢжҲҗеҠҹгҒ®йҚөгӮ’жҸЎгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдјҒз”»жӢ…еҪ“иҖ…гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒдәӢеӢҷеұҖгҖҒдјҡиЁҲжӢ…еҪ“иҖ…гҖҒеәғе ұжӢ…еҪ“иҖ…гҖҒгҒқгҒ—гҒҰйҒҺеҺ»гҒ®й–ӢеӮ¬зөҢйЁ“иҖ…гҒӘгҒ©гҖҒй–ўдҝӮгҒҷгӮӢж–№гҖ…гҒЁеҜҶгҒ«йҖЈжҗәгӮ’еҸ–гӮҠгҒӘгҒҢгӮүйҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒҜгӮӢгҒӢгҒ«иіӘгҒ®й«ҳгҒ„з”іи«ӢжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ’гғігғҲпјҡ
з”іи«ӢжӣёдҪңжҲҗеүҚгҒ«гҖҒеӯҰдјҡеҶ…гҒ®й–ўдҝӮиҖ…пјҲзҗҶдәӢгҖҒе°Ӯй–Җ委員дјҡгғЎгғігғҗгғјгҖҒдәӢеӢҷеұҖгӮ№гӮҝгғғгғ•гҖҒиӢҘжүӢдјҡе“Ўд»ЈиЎЁгҒӘгҒ©пјүгҒЁгҒ®гҖҢдҪңжҲҰдјҡиӯ°гҖҚгӮ’й–ӢеӮ¬гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮзү№гҒ«гҖҒйҒҺеҺ»гҒ®й–ӢеӮ¬гғҮгғјгӮҝгӮ„дәҲз®—е®ҹзёҫгҖҒеҸӮеҠ иҖ…ж•°гҒ®жҺЁз§»гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж•°еҖӨжғ…е ұгӮ’жӯЈзўәгҒ«йӣҶзҙ„гҒ—гҖҒе…ЁдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰж•ҙеҗҲжҖ§гҒ®еҸ–гӮҢгҒҹз”іи«ӢжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒжҺЎжҠһгҒёгҒ®зўәе®ҹгҒӘиҝ‘йҒ“гҒ§гҒҷгҖӮеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒдәӢеүҚгҒ«ж„ҸиҰӢдәӨжҸӣдјҡгӮ„гғ–гғ¬гӮӨгғігӮ№гғҲгғјгғҹгғігӮ°гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігӮ’иЁӯгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»еҠ©жҲҗдәӢжҘӯзҙ№д»ӢпҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәә дҪҸеҸӢиІЎеӣЈ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®иӘӨи§ЈгӮ„е…Ҳе…ҘиҰігӮ’д№—гӮҠи¶ҠгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒҚгҒЈгҒЁиҮӘдҝЎгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰз”іи«ӢгҒ«иҮЁгӮҒгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮеӯҰдјҡгҒҢзӣ®жҢҮгҒҷеӯҰиЎ“зҡ„гҒӘзҷәеұ•гҒЁзӨҫдјҡиІўзҢ®гҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ„ж©ҹдјҡгҒҜгҖҒеҝ…гҒҡгҒӮгҒӘгҒҹгӮ’еҫ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮз”іи«ӢжӣёдҪңжҲҗгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢдәӢеӢҷжүӢз¶ҡгҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеӯҰдјҡгҒ®жңӘжқҘгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«жҸҸгҒҚгҖҒй–ўдҝӮиҖ…е…Ёе“ЎгҒ®жғ…зҶұгӮ’дёҖгҒӨгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒдёҠгҒ’гӮӢеүөйҖ зҡ„гҒ§ж„Ҹзҫ©ж·ұгҒ„гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒңгҒІгҖҒгғҒгғјгғ дёҖдёёгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®жҢ‘жҲҰгӮ’жҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
Q&AпјҡеӯҰиЎ“йӣҶдјҡгғ»еӯҰдјҡеӨ§дјҡй–ӢеӮ¬еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ«гҒҫгҒӨгӮҸгӮӢз–‘е•Ҹ
еӯҰиЎ“йӣҶдјҡгӮ„еӯҰдјҡеӨ§дјҡгҒ®й–ӢеӮ¬гҒ«гҒҜзӣёеҪ“гҒӘиІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘гӮ’дёҠжүӢгҒ«жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒқгҒ®зөҢжёҲзҡ„иІ жӢ…гӮ’еӨ§е№…гҒ«и»ҪжёӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒеӯҰиЎ“йӣҶдјҡй–ӢеӮ¬еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ«й–ўгҒ—гҒҰзү№гҒ«гӮҲгҒҸеҜ„гҒӣгӮүгӮҢгӮӢз–‘е•ҸгҒ«гҒҠзӯ”гҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
Q1пјҡеӯҰиЎ“йӣҶдјҡй–ӢеӮ¬еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ§гҒҜгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиІ»з”ЁгҒҢеҜҫиұЎгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹВ
A1пјҡдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢдё»гҒӘзөҢиІ»гҒҜгҖҒдјҡе ҙиІ»гҖҒи¬ӣжј”иҖ…жӢӣиҒҳиІ»пјҲи¬қйҮ‘гғ»ж—…иІ»гғ»е®ҝжіҠиІ»пјүгҖҒзҷәиЎЁиіҮж–ҷдҪңжҲҗиІ»гҖҒеәғе ұгғ»е®ЈдјқиІ»гҖҒйҒӢе–¶гӮ№гӮҝгғғгғ•дәә件費гҖҒйҖҡдҝЎиІ»гҖҒдјҡиӯ°з”Ёж¶ҲиҖ—е“ҒиІ»гҒӘгҒ©гҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҠ©жҲҗеӣЈдҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҜҫиұЎзөҢиІ»гҒ®и©ізҙ°гҒӘзҜ„еӣІгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҝ…гҒҡеҗ„еӣЈдҪ“гҒ®е…¬еӢҹиҰҒй ҳгҒ«гҒӮгӮӢгҖҢеҠ©жҲҗеҜҫиұЎзөҢиІ»гҖҚгҒ®й …зӣ®гӮ’е…ҘеҝөгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮзү№гҒ«гҖҒйЈІйЈҹиІ»гӮ„жҮҮиҰӘдјҡиІ»гҖҒиЁҳеҝөе“ҒиІ»гҒӘгҒ©гҒҜеҜҫиұЎеӨ–гҒЁгҒӘгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ®зўәиӘҚгҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
Q2пјҡй–ӢеӮ¬еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®еҜ©жҹ»гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒзү№гҒ«йҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢгғқгӮӨгғігғҲгҒҜдҪ•гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
A2пјҡеҜ©жҹ»гҒ§гҒҜдё»гҒ«д»ҘдёӢгҒ®6гҒӨгҒ®иҰізӮ№гҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- еӯҰиЎ“зҡ„ж„Ҹзҫ©гғ»зӣ®зҡ„гҒ®жҳҺзўәгҒ•пјҡгҒӘгҒңгҒ“гҒ®йӣҶдјҡгҒҢд»Ҡеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе…·дҪ“зҡ„гҒӘеӯҰиЎ“зҡ„жҲҗжһңгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢ
- дјҒз”»гҒ®зӢ¬иҮӘжҖ§гғ»ж–°иҰҸжҖ§пјҡд»–гҒ®ж—ўеӯҳгҒ®еӯҰдјҡгӮ„йӣҶдјҡгҒЁгҒ®жҳҺзўәгҒӘе·®еҲҘеҢ–гҖҒйқ©ж–°зҡ„гҒӘи©ҰгҒҝгҒ®жңүз„Ў
- жіўеҸҠеҠ№жһңгғ»зӨҫдјҡиІўзҢ®жҖ§пјҡеҸӮеҠ иҖ…гҒёгҒ®иІўзҢ®еәҰгҖҒеӯҰиЎ“еҲҶйҮҺе…ЁдҪ“гҒёгҒ®еҪұйҹҝгҖҒзӨҫдјҡе…ЁдҪ“гҒёгҒ®й•·жңҹзҡ„гҒӘгӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲ
- дәҲз®—гҒ®еҰҘеҪ“жҖ§гғ»йҖҸжҳҺжҖ§пјҡз©Қз®—ж №жӢ гҒҢжҳҺзўәгҒ§иӘ¬еҫ—еҠӣгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҖҒиІ»з”ЁеҜҫеҠ№жһңгҒҢеҚҒеҲҶгҒ«й«ҳгҒ„гҒӢ
- йҒӢе–¶дҪ“еҲ¶гҒ®е…·дҪ“жҖ§гғ»е®ҹиЎҢеҸҜиғҪжҖ§пјҡе®ҹйҡӣгҒ«иӘ°гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йҒӢе–¶гҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгғӘгӮ№гӮҜз®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶гҒҜдёҮе…ЁгҒӢ
- еҸӮеҠ иҖ…иҰӢиҫјгҒҝгҒЁгҒқгҒ®ж №жӢ пјҡгӮҝгғјгӮІгғғгғҲеұӨгҒёгҒ®гӮўгғ—гғӯгғјгғҒжҲҰз•ҘгҖҒеҸӮеҠ иҖ…ж•°гҒ®еҰҘеҪ“жҖ§
зү№гҒ«иҝ‘е№ҙгҒҜгҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘиӘҳиҮҙиЁҲз”»гӮ„гҖҒеӣҪйҡӣжҖ§гғ»еӨҡж§ҳжҖ§гҒ®зўәдҝқгҖҒгӮӘгғігғ©гӮӨгғій–ӢеӮ¬гҒёгҒ®еҜҫеҝңгҒӘгҒ©гӮӮи©•дҫЎгғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒ—гҒҰйҮҚиҰҒиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
Q3пјҡз”іи«Ӣз· еҲҮгҒҢиҝ«гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӯҰдјҡеҶ…гҒ®жүҝиӘҚгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ«дәҲжғід»ҘдёҠгҒ«жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ©гҒҶеҜҫеҮҰгҒҷгҒ№гҒҚгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
A3пјҡеӨҡгҒҸгҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ§гҒҜгҖҒеӯҰдјҡеҶ…йғЁгҒ®жӯЈејҸгҒӘжүҝиӘҚгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢеҝ…иҰҒжқЎд»¶гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз· еҲҮзӣҙеүҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰж…ҢгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒе…¬еӢҹжғ…е ұгӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҹжҷӮзӮ№гҒ§йҖҹгӮ„гҒӢгҒ«еӯҰдјҡдәӢеӢҷеұҖгӮ„й–ўйҖЈйғЁзҪІгҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘжүҝиӘҚжүӢз¶ҡгҒҚгҒ®е…ЁдҪ“еғҸгҒЁжүҖиҰҒжңҹй–“гӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮжүҝиӘҚгғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒи©ізҙ°гҒ«зўәиӘҚгҒ—гҖҒеҚҒеҲҶгҒӘдҪҷиЈ•гӮ’жҢҒгҒЈгҒҹгӮҝгӮӨгғ гӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§жә–еӮҷгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдҪ•гӮҲгӮҠйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮдёҮгҒҢдёҖгҖҒз· еҲҮгҒ«й–“гҒ«еҗҲгӮҸгҒӘгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒдёҖдәәгҒ§жӮ©гҒҫгҒҡгҖҒйҖҹгӮ„гҒӢгҒ«еҠ©жҲҗж©ҹй–ўгҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒ«йҖЈзөЎгҒ—гҒҰе…·дҪ“зҡ„гҒӘжҢҮзӨәгӮ’д»°гҒҺгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҖҢжңҖеҫҢгҒҫгҒ§гҒӮгҒҚгӮүгӮҒгҒӘгҒ„гҖҚе§ҝеӢўгҒҜгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲд»ҠеӣһгҒ®з”іи«ӢгҒҢеҸ—зҗҶгҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҝ…гҒҡж¬Ўеӣһд»ҘйҷҚгҒ®иІҙйҮҚгҒӘж•ҷиЁ“гҒЁгҒӘгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮ
еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ«еҪ№з«ӢгҒӨжғ…е ұжәҗ
еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеҗ„еӯҰиЎ“ж”ҜжҸҙеӣЈдҪ“гӮ„е…¬зҡ„ж©ҹй–ўгҒҢжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢжңҖж–°гҒ®жғ…е ұгӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢж¬ гҒӢгҒӣгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮд»ҘдёӢгҒ«гҖҒе®ҹеӢҷжӢ…еҪ“иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰзү№гҒ«жңүз”ЁгҒӘжғ…е ұжәҗгӮ’еҺійҒёгҒ—гҒҰгҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғӘгӮҪгғјгӮ№гӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҖҒжҲҰз•Ҙзҡ„гҒ§еҠ№жһңзҡ„гҒӘз”іи«Ӣжә–еӮҷгӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮгҒӘгҒҠгҖҒз”іи«ӢгҒ®жӣёејҸгӮ„жқЎд»¶гҖҒеҲ¶зҙ„дәӢй …гҒҜе№ҙеәҰгҒ”гҒЁгҒ«еӨүжӣҙгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢеӨҡгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒеҝ…гҒҡжңҖж–°гҒ®е…¬еӢҹиҰҒй ҳгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҹдёҠгҒ§з”іи«ӢжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»з§‘еӯҰз ”з©¶иІ»еҠ©жҲҗдәӢжҘӯпҪңзӢ¬з«ӢиЎҢж”ҝжі•дәәж—Ҙжң¬еӯҰиЎ“жҢҜиҲҲдјҡ
гғ»еҝңеӢҹгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжүӢз¶ҡгҒҚпҪңз§‘з ”иІ»йӣ»еӯҗз”іи«ӢгӮ·гӮ№гғҶгғ
гғ»RISTEX зӨҫдјҡжҠҖиЎ“з ”з©¶й–ӢзҷәгӮ»гғігӮҝгғјпҪңеӣҪз«Ӣз ”з©¶й–Ӣзҷәжі•дәә科еӯҰжҠҖиЎ“жҢҜиҲҲж©ҹж§ӢпјҲJSTпјү
гғ»з ”究еҠ©жҲҗпҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәәеҠ и—ӨиЁҳеҝөгғҗгӮӨгӮӘгӮөгӮӨгӮЁгғігӮ№жҢҜиҲҲиІЎеӣЈ
гғ»еӯҰиЎ“гҒЁж•ҷиӮІгҒ®ж”ҜжҸҙгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒзӨҫдјҡгҒ®зҷәеұ•гҒЁгӮӨгғҺгғҷгғјгӮ·гғ§гғігҒ®еүөеҮәгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒҷпҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәәжқ‘з”°еӯҰиЎ“жҢҜиҲҲгғ»ж•ҷиӮІиІЎеӣЈ
гҒҠгӮҸгӮҠгҒ«
гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ§гҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҹеҶ…е®№гҒҢгҖҒзҡҶгҒ•гӮ“гҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢжҲҗеҠҹгҒ®дёҖеҠ©гҒЁгҒӘгӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«й–ўгҒҷгӮӢйҖЈијүиЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒд»ҠеҫҢгӮӮе®ҹи·өзҡ„гҒ§еҪ№з«ӢгҒӨжғ…е ұгӮ„гғ’гғігғҲгӮ’з¶ҷз¶ҡгҒ—гҒҰгҒҠеұҠгҒ‘гҒ—гҒҰгҒҫгҒ„гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж¬Ўеӣһд»ҘйҷҚгҒ§гҒҜгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘жҺЎжҠһеҫҢгҒ®з®ЎзҗҶгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгӮ„йҒ©еҲҮгҒӘдјҡиЁҲеҮҰзҗҶгҖҒжңҖзөӮе ұе‘ҠжӣёгҒ®еҠ№жһңзҡ„гҒӘдҪңжҲҗж–№жі•гҒӘгҒ©гҖҒз”іи«ӢгҒӢгӮүе®ҢдәҶгҒҫгҒ§гҒ®дёҖйҖЈгҒ®жөҒгӮҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮи©ігҒ—гҒҸи§ЈиӘ¬гҒҷгӮӢдәҲе®ҡгҒ§гҒҷгҖӮеҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒҜжұәгҒ—гҒҰдёҖдәәгҒ гҒ‘гҒ§е®ҢзөҗгҒҷгӮӢдҪңжҘӯгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеӯҰдјҡгҒ®д»Ій–“гҒҹгҒЎгҒЁгҒ®еҜҶжҺҘгҒӘеҚ”еҠӣгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮҲгӮҠиіӘгҒ®й«ҳгҒ„з”іи«ӢжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҖҒеӯҰиЎ“гҒ®зҷәеұ•гҒ«гӮҲгӮҠеӨ§гҒҚгҒҸиІўзҢ®гҒҷгӮӢзө¶еҘҪгҒ®ж©ҹдјҡгӮ’жҺҙгӮ“гҒ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮзҡҶгҒ•гӮ“гҒ®еӯҰдјҡгҒҢжҸҸгҒҸжңӘжқҘгҒ®гғ“гӮёгғ§гғігҒҢгҖҒгҒҚгҒЈгҒЁеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҖ…гҒ®еҝғгӮ’еӢ•гҒӢгҒҷгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
еҸӮиҖғгҒЁгҒӘгӮӢйҖЈијүиЁҳдәӢ
гғ»гҖҢеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ§еәғгҒҢгӮӢеӯҰдјҡгҒ®еҸҜиғҪжҖ§пҪһз”іи«ӢгҒ®еҹәжң¬гҒЁжҺЎжҠһзҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢдјҒз”»гғҺгӮҰгғҸгӮҰпҪһгҖҚ
гғ»гҖҢеӯҰиЎ“йӣҶдјҡеҠ©жҲҗйҮ‘гӮ’з”іи«ӢгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜпјҹпҪһеӯҰиЎ“з ”з©¶гҒЁзӨҫдјҡгҒЁгҒ®гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгӮ’иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢпҪһгҖҚ