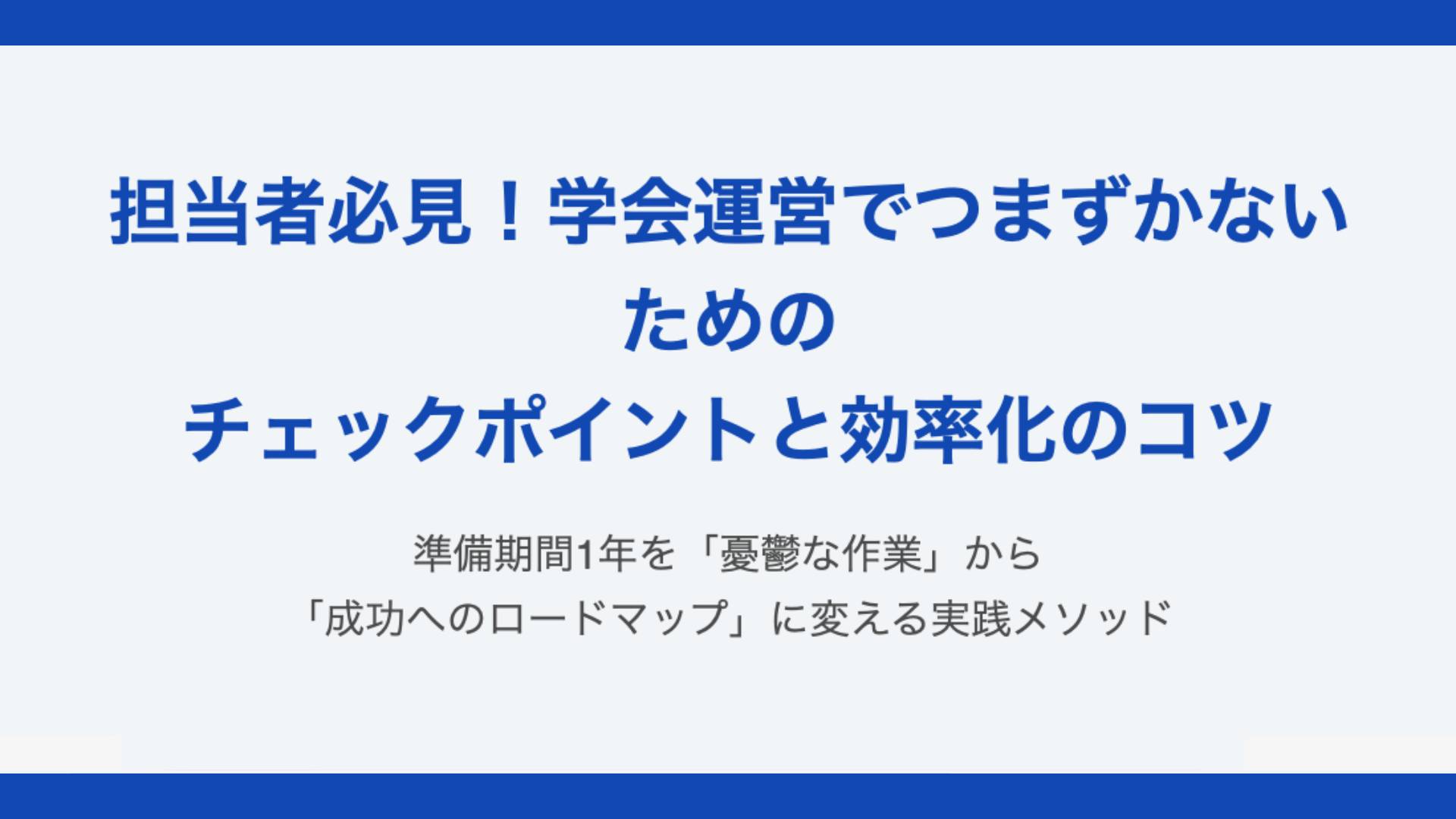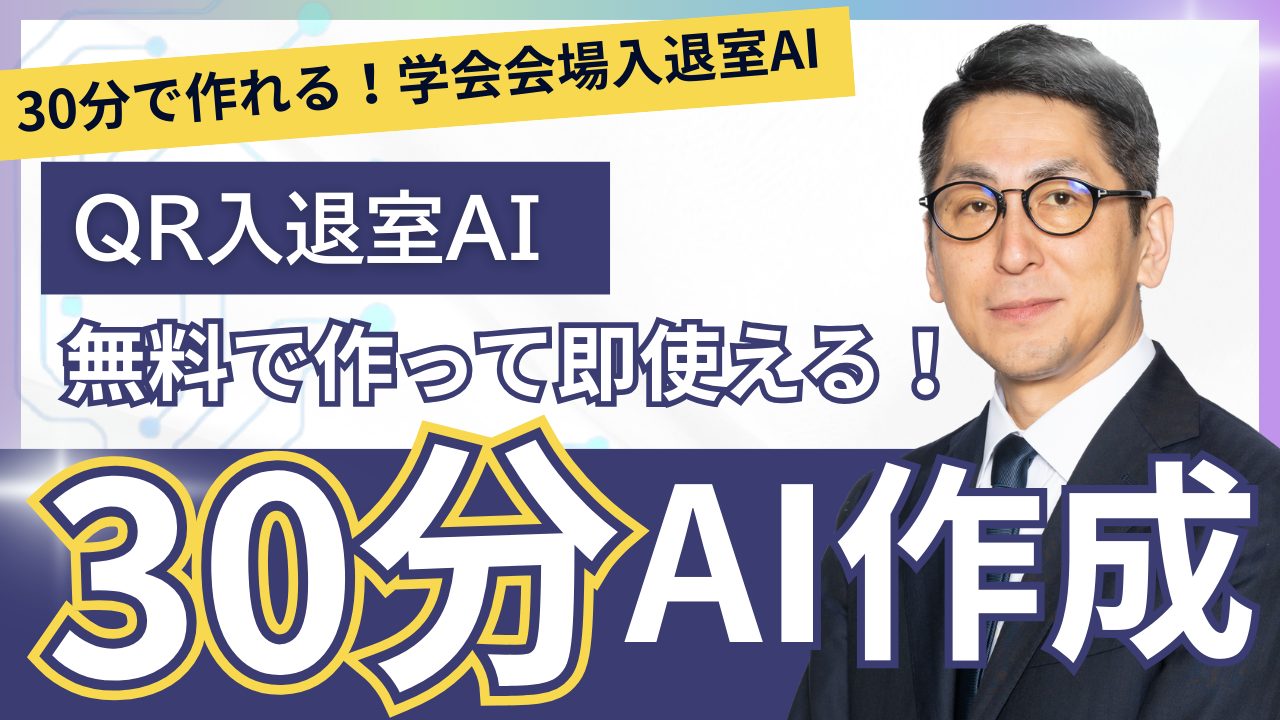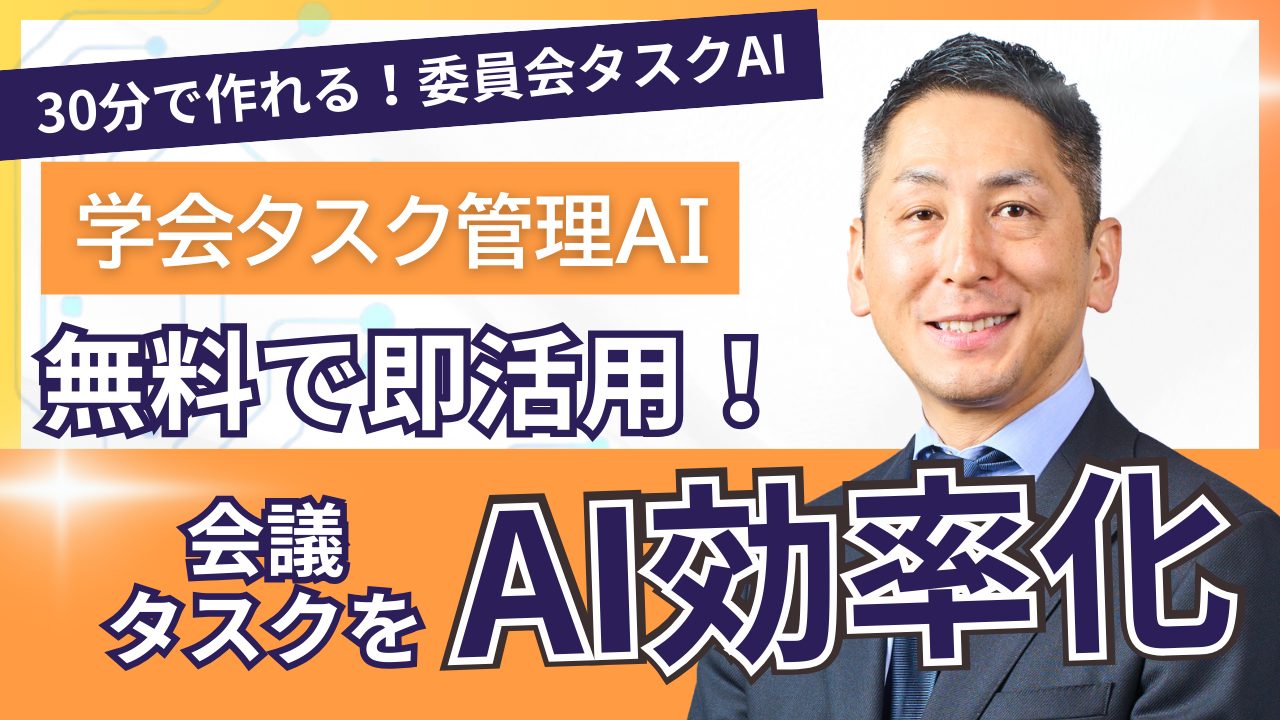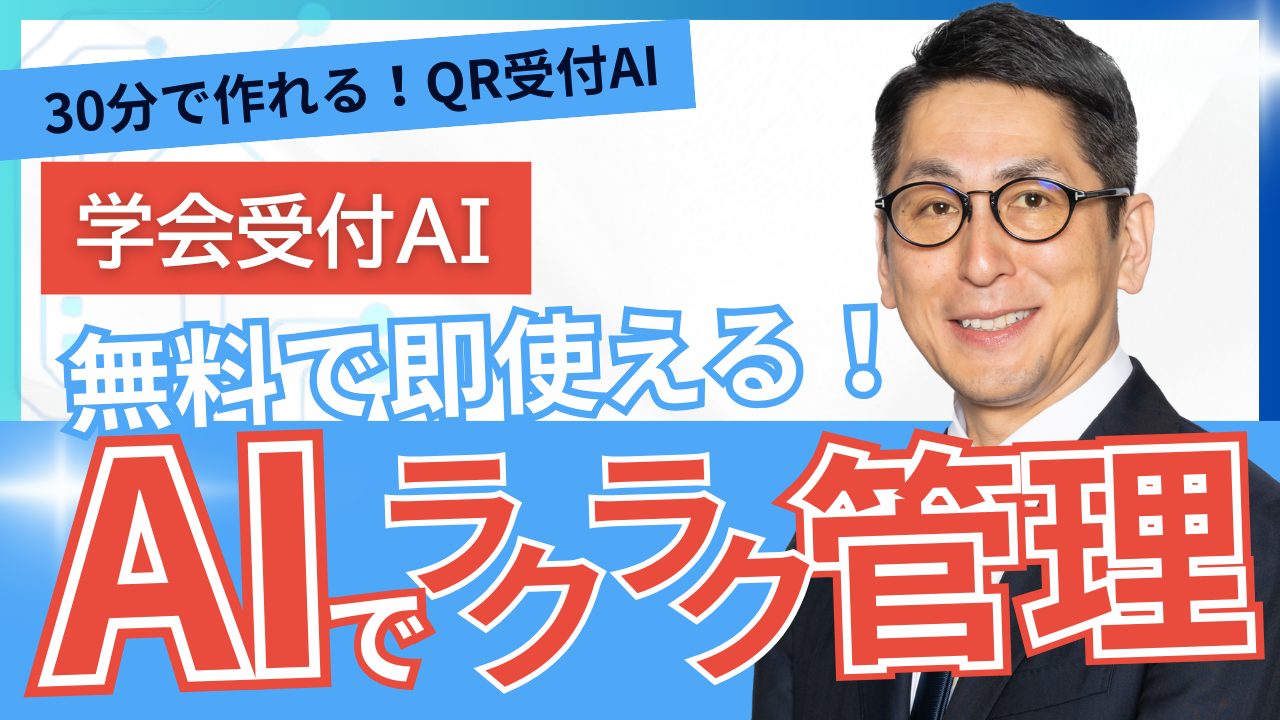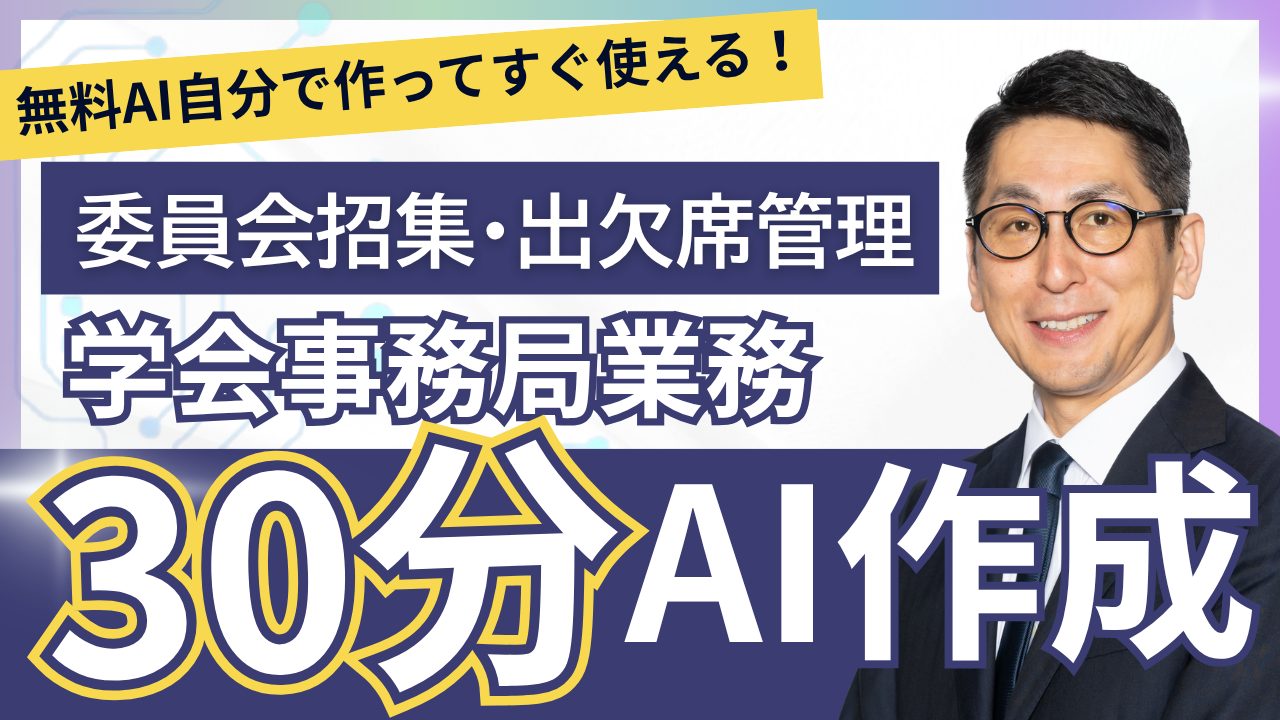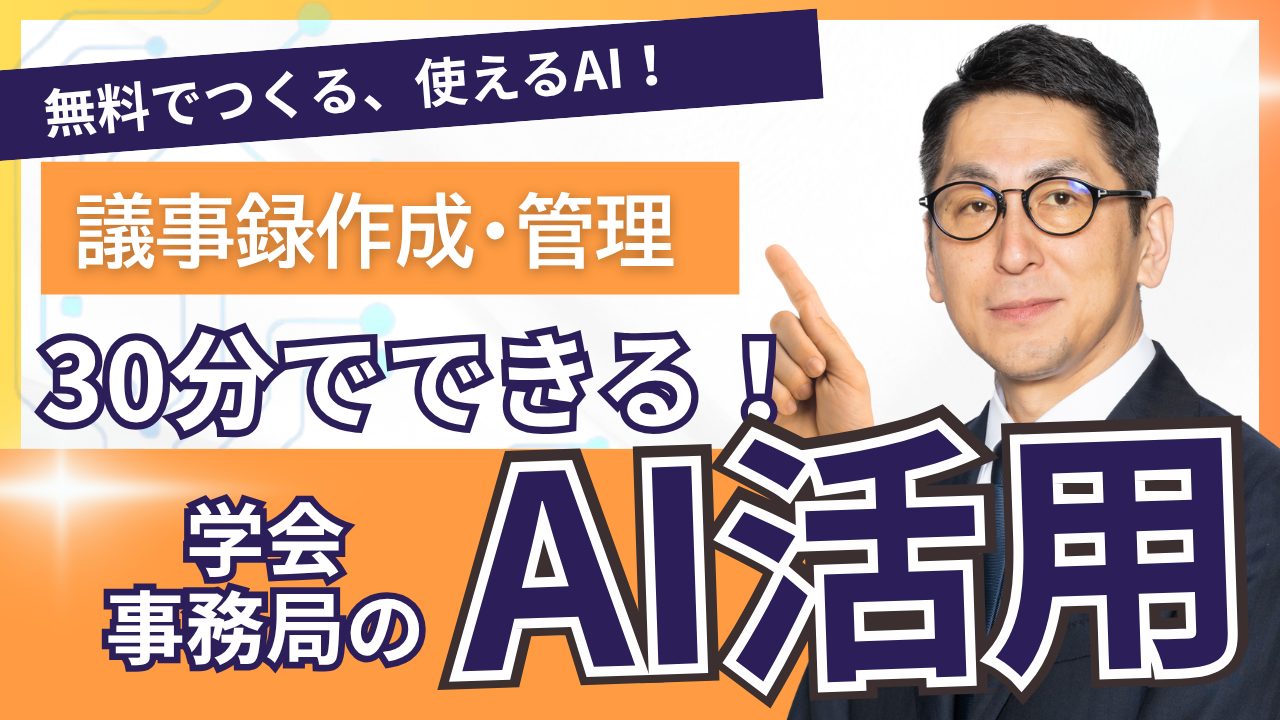ŚĺƜ󕍶ĖŤĀī„ĀßÁ†ĒÁ©∂„Ā®Ś≠¶„Ā≥„āí„Ā§„Ā™„Āź„ÄÄ„ÄúŚ≠¶šľö„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„ĀģŚäĻśěú„Ā®Ś∑•Ś§ę„Äú
2025ŚĻī08śúą19śó•
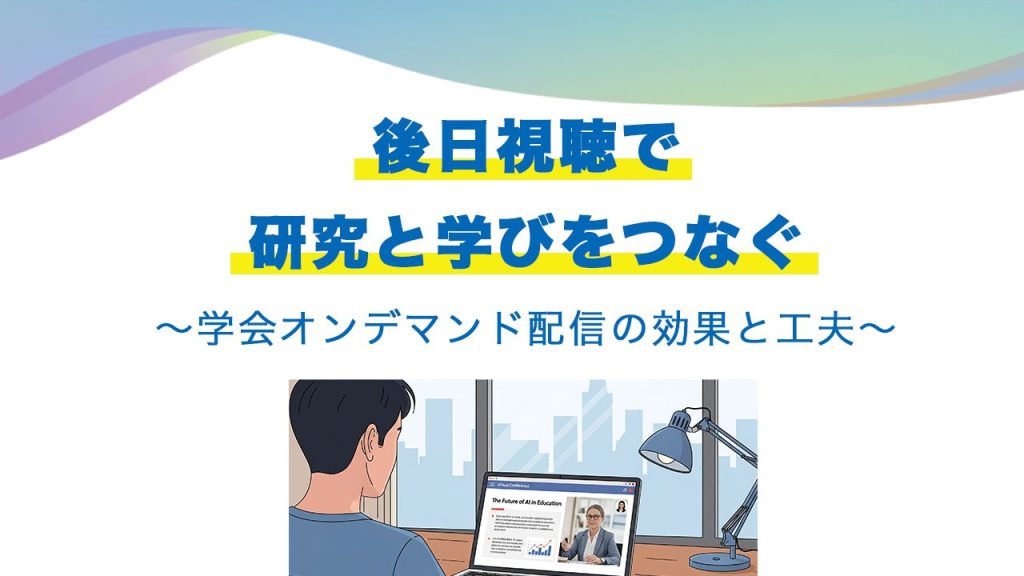
„ĀĮ„Āė„āĀ„Āę„ÄÄ„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČ„ĀģŚįéŚÖ•„ĀߌŹāŚä†ś©üšľö„āíŚļÉ„Āí„āč„É°„É™„ÉÉ„Éą
ŤŅĎŚĻī„ÄĀŚ≠¶šľö„ĀĆťĖčŚā¨„Āô„ā荨õśľĒ„āĄ„ā∑„É≥„ÉĚ„āł„ā¶„Ɇ„ĀģśÉÖŚ†Ī„āí„ā™„É≥„É©„ā§„É≥šłä„Āß„ĀĄ„Ā§„Āß„āāŤ¶ĖŤĀīŚŹĮŤÉĹ„Āę„Āô„āč„ÄĆ„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„Äć„ĀƜĕťÄü„Āęś≥®Áõģ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀŚĺďśĚ•„ĀģŚĮĺťĚĘťĖčŚā¨„ĀģŤ™≤ť°Ć„āíšĻó„āäŤ∂ä„Āą„ÄĀÁČ©ÁźÜÁöĄ„Ā™Śą∂ÁīĄ„āíŤß£ś∂ą„Āó„ÄĀŚúįÁźÜÁöĄ„Ā™Ť∑ĚťõĘ„āĄśôāťĖĮ„ĀęŚ∑¶ŚŹ≥„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Ā™„ĀŹŚŹāŚä†„Āß„Āć„āč„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀŚ§öśßė„Ā™Á†ĒÁ©∂ŤÄÖ„ĀģŚ≠¶„Ā≥„āíśĒĮ„Āą„āčťĚ©śĖįÁöĄ„Ā™śČčśģĶ„Ā®„Āó„Ā¶Ť™ćŤ≠ė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
ÁČĻ„ĀęśĖįŚěč„ā≥„É≠„Éä„ā¶„ā§„Éę„āĻśĄüśüďÁóáÔľąCOVID-19ԾȄĀę„āą„āčÁ§ĺšľöÁöĄŚą∂ÁīĄ„ĀĆ„ā™„É≥„É©„ā§„É≥ŚĆĖ„ĀģŤŅĹ„ĀĄťĘ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„ĀģŚ≠¶šľö„ĀĆ„ÉŹ„ā§„ÉĖ„É™„ÉÉ„ÉČťĖčŚā¨„āĄŚģĆŚÖ®„ā™„É≥„É©„ā§„É≥ťĖčŚā¨„ÄĀ„Āē„āČ„Āę„ĀĮ„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČŤ¶ĖŤĀī„āíÁ©ćś•ĶÁöĄ„ĀęŚįéŚÖ•„Āô„āčśĶĀ„āĆ„Āƌ䆝Äü„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„ĀģśúÄŚ§ß„Āģ„É°„É™„ÉÉ„Éą„ĀĮ„ÄĀÁ†ĒÁ©∂ŤÄÖ„āĄŚąĚŚ≠¶ŤÄÖ„Āƍᙍļę„Āģ„āĻ„āĪ„āł„É•„Éľ„Éę„Āꌟą„āŹ„Āõ„Ā¶Ť¨õśľĒ„ā퍶ĖŤĀī„Āß„Āć„āčÁāĻ„Āß„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀśļÄŚł≠„āĄśôāťĖď„ĀĆťáć„Ā™„ā荧áśēįŚźĆśôā„āĽ„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥„Āģśā©„ĀŅ„ĀĆŤß£ś∂ą„Āē„āĆ„āč„Ā®„Ā®„āā„Āę„ÄĀÁĻį„āäŤŅĒ„ĀóŤ¶ĖŤĀī„Āę„āą„Ā£„Ā¶ÁźÜŤß£„āíś∑Ī„āĀ„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„Āĺ„ĀüŚõĹŚĘÉ„āíŤ∂Ö„Āą„ĀüŚ≠¶Ť°ďšļ§śĶĀ„āāšŅÉťÄ≤„Āó„ÄĀŚ§öśßė„Ā™šĺ°ŚÄ§Ť¶≥„āĄÁ†ĒÁ©∂„āĻ„āŅ„ā§„Éę„ĀģŤě挟ą„ĀęŤ≤ĘÁĆģ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāšłÄśĖĻ„Āß„ÄĀŚćė„Ā™„āčśė†ŚÉŹťÖćšŅ°„Āę„Ā®„Ā©„Āĺ„āČ„Āö„ÄĀŤĎóšĹúś®©ŚĮĺŚŅú„āĄŚŹāŚä†ŤÄÖŤ™ćŤ®ľ„ÄĀŤ≥™ÁĖĎŚŅúÁ≠Ēś©üŤÉĹ„ĀģŤ®≠Ť®ą„Ā™„Ā©„ĀģŤ™≤ť°Ć„āāť°ēŚú®ŚĆĖ„Āó„ÄĀťĀčŚĖ∂ŚĀī„ĀģŚģüŚčôŤ≤†śčÖ„ĀĮŚĘó„Āą„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„ĀģŤ®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀŚ≠¶šľöťĀčŚĖ∂„ĀģÁŹĺŚ†ī„ĀßÁĚÄśČč„Āô„ĀĻ„Āć„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„ĀģšľĀÁĒĽŤ®≠Ť®ą„Āč„āČťĀčÁĒ®„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶śĆĀÁ∂öŚŹĮŤÉĹ„Ā™ťĀčŚĖ∂šĹ∂„ĀģśßčÁĮČ„Āĺ„Āß„ÄĀŚ§öŤßíÁöĄŤ¶ĖÁāĻ„Āß„ĀģŚÖ∑šĹďÁ≠Ė„ā퍩≥ŤŅį„Āó„Āĺ„Āô„Äā
ÁČĻ„Āę„ÄĀŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀģŚ≠¶ÁŅíŚäĻśěú„āíśúÄŚ§ßŚĆĖ„Āó„ÄĀ„Āč„Ā§ťĀčŚĖ∂ŚäĻÁéá„Āę„āāŚĮĄšłé„Āô„āčŚģüŤ∑ĶÁöĄ„Ā™„Éé„ā¶„ÉŹ„ā¶„āíšļčšĺč„Ā®„Ā®„āā„Ā꜏źšĺõ„Āó„ÄĀ„Āď„āĆ„Āč„āČ„ĀģŚ≠¶šľö„ĀģÁôļŚĪē„ĀęŤ≤ĘÁĆģ„Āß„Āć„āč„Āď„Ā®„āíÁõģśĆá„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
1. ťÖćšŅ°Ť®≠Ť®ą„ÉĽÁ∑®ťõÜ„ÉĽ„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆťĀłŚģö„ĀģŚüļśú¨
Ś≠¶šľö„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„ĀģŚüļÁõ§„Ā®„Ā™„āčšľĀÁĒĽŤ®≠Ť®ą„āĄŚčēÁĒĽÁ∑®ťõÜ„ÄĀťÖćšŅ°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇ„ĀģťĀłŚģö„ĀęťĖĘ„Āô„āčśúÄśĖį„Éé„ā¶„ÉŹ„ā¶„ā퍩≥„Āó„ĀŹŤß£Ť™¨„Āó„Āĺ„Āô„ÄāśėéÁĘļ„Ā™„āŅ„Éľ„ā≤„ÉÉ„ÉąŤ®≠Śģö„Ā®ŚäĻÁéáÁöĄ„Ā™ŚŹéťĆ≤„ÉĽÁ∑®ťõÜśČčś≥ē„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶ŚŹāŚä†ŤÄÖšĹďť®ď„āíŚ∑¶ŚŹ≥„Āô„āčťÖćšŅ°ÁíįŚĘÉ„ĀģśúÄťĀ©ŚĆĖ„ĀĆ„ÄĀťĀčŚĖ∂„ĀģśąźŚäü„ĀęÁõīÁĶź„Āó„Āĺ„Āô„Äā
1.1. ťÖćšŅ°„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„ĀģšľĀÁĒĽŤ®≠Ť®ą„Ā®ŚŹéťĆ≤śļĖŚāô
„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„āíŚäĻśěúÁöĄ„ĀęŚģüśĖĹ„Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀšľĀÁĒĽśģĶťöé„Āč„āČŤ®ąÁĒĽÁöĄ„ĀęťÄ≤„āĀ„āč„Āď„Ā®„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„Äā
„Āĺ„Āö„ÄĀśúÄŚąĚ„ĀꜧúŤ®é„Āô„ĀĻ„Āć„ĀĮ„ÄĀ„Ā©„ĀģŤ¨õśľĒ„āĄ„āĽ„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥„āíťÖćšŅ°ŚĮĺŤĪ°„Ā®„Āô„āč„Āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜťĀłŚģö„ĀģŚüļśļĖŤ®≠Śģö„Āß„Āô„ÄāŚ≠¶šľö„ĀĒ„Ā®„ĀęŚĮĺŤĪ°ť†ėŚüü„āĄŚŹāŚä†ŤÄÖŚĪ§„ĀĆÁēį„Ā™„āč„Āü„āĀ„ÄĀťĀéŚéĽ„ĀģŚáļŚł≠Áéá„āĄ„āĘ„É≥„āĪ„Éľ„ÉąÁĶźśěú„ÄĀšłĽŚā¨ŤÄÖ„ĀģśĖĻťáĚ„ā퍳Ź„Āĺ„Āą„ÄĀŤ¶ĖŤĀīťúÄŤ¶Ā„ĀĆťęė„ĀĄŚÜÖŚģĻ„āĄŚÜćÁĒüšĺ°ŚÄ§„Āģ„Āā„ā荨õśľĒ„ā팥™ŚÖąÁöĄ„ĀęťĀł„Ā≥„Āĺ„Āô„Äā
ŚüļŤ™ŅŤ¨õśľĒ„ÉĽÁČĻŚą•Ť¨õśľĒ„ĀĮ„āā„Ā°„āć„āď„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„ĀģŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀĆśÉÖŚ†ĪŚÖĪśúČ„āĄŚ≠¶ÁŅí„ĀęŚĹĻÁęč„Ā¶„Āü„ĀĄ„Ā®śúüŚĺÖ„Āô„āč„ÉĮ„Éľ„āĮ„ā∑„Éß„ÉÉ„Éó„āĄ„ÉĎ„Éć„Éę„Éá„ā£„āĻ„āę„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥„Ā™„Ā©„āāś§úŤ®é„ĀęŚÄ§„Āó„Āĺ„Āô„Äā
ŚŹéťĆ≤„ĀģśģĶťöé„Āß„ĀĮśė†ŚÉŹ„ÉĽťü≥Ś£į„ĀģŚďĀŤ≥™ÁĘļšŅĚ„ĀĆ„ÄĀŤ¶ĖŤĀīŤÄÖśļÄŤ∂≥Śļ¶„āíŚ∑¶ŚŹ≥„Āô„āčťá捶Ā„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„Āß„Āô„Äā
ŚÖ∑šĹďÁöĄ„Āę„ĀĮ„ÄĀÁôļŤ°®šľöŚ†ī„āĄ„āĻ„āŅ„āł„ā™„Āß„Āģś©üśĚźŤ®≠ÁĹģ„Āęťöõ„Āó„ÄĀťü≥Ś£į„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÉĮ„ā§„ɧ„ɨ„āĻ„Éě„ā§„āĮ„āĄśĆጟϜÄß„Éě„ā§„āĮ„ĀģťĀ©Śąá„Ā™ťÖćÁĹģ„ÄĀŚĎ®Ťĺļ„Éé„ā§„āļ„ĀģśúÄŚįŹŚĆĖ„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āüśė†ŚÉŹ„ĀĮÁôļŤ°®„āĻ„É©„ā§„ÉČ„ĀģśĖáŚ≠ó„āĄŚõ≥Ť°®„ĀĆťģģśėé„Āꍙ≠„ĀŅŚŹĖ„āĆ„āč„āą„ĀÜ„ÄĀHDÁĒĽŤ≥™Ôľą1280√ó720„ÉĒ„āĮ„āĽ„Éꚼ•šłäԾȄĀß„ĀģśíģŚĹĪ„ÉĽťÖćšŅ°„ĀƜ鮌•®„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
ŤŅĎŚĻī„ĀĮ4KśíģŚĹĪ„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Ā™ś©üśĚź„āāŚĘó„Āą„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀťÄöšŅ°ÁíįŚĘÉ„āĄťÖćšŅ°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇ„ĀģŚĮĺŚŅú„ÄĀŤ¶ĖŤĀīÁęĮśúę„ĀģŚļÉ„ĀĆ„āä„ĀęťÖćśÖģ„ĀóśúÄťĀ©„Ā™ÁĒĽŤ≥™Ť®≠Śģö„ā휧úŤ®é„Āô„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāŤ¶ĖŤĀīŚĮĺŤĪ°„ɶ„Éľ„ā∂„Éľ„ĀģŚúįŚüüÁČĻśÄß„Ā®Ť¶ĖŤĀīÁęĮśúęÔľą„āĻ„Éě„Éõ„āĄ„āŅ„ÉĖ„ɨ„ÉÉ„Éą„ÄĀPC„Ā™„Ā©ÔľČ„āíŤÄÉśÖģ„Āó„Ā¶ÁĒĽŤ≥™„ĀģŤ®≠Śģö„ā휧úŤ®é„Āó„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā
„Āĺ„ĀüŚŹéťĆ≤ŚČć„ĀģÁôļŤ°®ŤÄÖ„Ā®„Āģ„ā≥„Éü„É•„Éč„āĪ„Éľ„ā∑„Éß„É≥„āāťá捶Ā„Āß„Āô„ÄāŚŹéťĆ≤„āĻ„āĪ„āł„É•„Éľ„Éę„ĀģŤ™Ņśēī„Āģ„ĀŅ„Ā™„āČ„Āö„ÄĀťÖćšŅ°„Āęšľī„ĀÜŤĎóšĹúś®©Śą©ÁĒ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀģŤ™¨śėé„ÄĀŤ≥™ŚēŹ„āŅ„ā§„Ɇ„ĀģŤ®≠Ť®ą„ÄĀŤ¶ĖŤĀīŚĮĺŤĪ°ŤÄÖ„ÉĽśúüťĖď„Āģś°ąŚÜÖ„Ā™„Ā©„ÄĀ„Éą„É©„ÉĖ„Éęťė≤ś≠Ę„Āģ„Āü„āĀ„ĀģšļčŚČ挟ąśĄŹŚĹĘśąź„ĀĆś¨†„Āč„Āõ„Āĺ„Āõ„āď„Äā„É™„ÉŹ„Éľ„āĶ„Éę„āíŚģüśĖĹ„Āó„ÄĀśė†ŚÉŹ„āĄťü≥Ś£į„ĀģÁĘļŤ™ć„ÄĀÁ∑䌾ĶÁ∑©ŚíĆ„āíŚõ≥„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚ•ĹŚćįŤĪ°„ĀģŚŹéťĆ≤„Āę„Ā§„Ā™„ĀĆ„āä„Āĺ„Āô„Äā
šłÄśĖĻ„ÄĀŚúįśĖĻŚú®šĹŹ„āĄśĶ∑Ś§Ė„ĀģÁ†ĒÁ©∂ŤÄÖ„ĀģŚŹāŚä†„ĀĆŚĘó„Āą„āč„āĪ„Éľ„āĻ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ„ā™„É≥„É©„ā§„É≥„É™„ÉŹ„Éľ„āĶ„Éę„āĄšļčŚČć„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥„ĀģťÖ挳ɄĀĆśúČŚäĻ„Āß„Āô„Äā Ť¶ĖŤĀīŤÄÖ„Āč„āČŚ≠¶šľö„āĄŚ≠¶Ť°ďšľöŤ≠į„Āģśú¨Áē™ŚČć„Āę„Éą„É©„ÉĖ„ÉęÁ≠Č„Āģ„Éē„ā£„Éľ„ÉČ„Éź„ÉÉ„āĮ„ā팏ó„ĀĎšĽė„ĀĎś©üśĚź„āĄÁíįŚĘÉ„ĀģšŅģś≠£„Āꌏćśė†„Āē„Āõ„Āĺ„Āô„Äā
1.2. ŚäĻśěúÁöĄ„Ā™Á∑®ťõÜśČčś≥ē„Ā®„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄśúÄťĀ©ŚĆĖ
ŚŹéťĆ≤ŚĺĆ„ĀģÁ∑®ťõÜšĹúś•≠„ĀĮ„ÄĀŤ¶ĖŤĀīŤÄÖ„ĀģťõÜšł≠ŚäõÁ∂≠śĆĀ„Ā®ÁźÜŤß£šŅÉťÄ≤„ĀęÁõīÁĶź„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āö„ÄĀšłćŤ¶Ā„Ā™ś≤ąťĽô„āĄÁĻį„āäŤŅĒ„ĀóÁôļŤ®Ä„Ā™„Ā©ŚÜóťē∑„Ā™ťÉ®ŚąÜ„ĀĮťĀ©Śąá„Āę„āę„ÉÉ„Éą„Āó„ÄĀ„ÉÜ„É≥„ÉĚŤČĮ„ĀŹťĖ≤Ť¶ß„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„Āę„Āó„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„Āģ„ĀÜ„Āą„Āßťá捶Ā„Ā™ÁģáśČÄ„Āę„ĀĮ„ÉÜ„É≠„ÉÉ„Éó„āĄŤ≥áśĖô„Āģśč°Ś§ßŤ°®Á§ļ„āíśĆŅŚÖ•„Āó„ÄĀ„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„ā팾∑Ť™Ņ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀߌÜÖŚģĻÁźÜŤß£„āíŚä©„ĀĎ„Āĺ„Āô„Äā„āĻ„É©„ā§„ÉČ„ĀģŚąá„āäśõŅ„Āą„āŅ„ā§„Éü„É≥„āį„āĄÁôļŤ°®ŤÄÖ„ĀģŚŹ£Ť™Ņ„Ā®śė†ŚÉŹŚźĆśúü„Āę„āāÁīįŚŅÉ„Āģś≥®śĄŹ„āíśČē„ĀĄ„ÄĀŤ¶ĖŤĀī„Āģ„āĻ„Éą„ɨ„āĻŤĽĹśłõ„ĀęŚä™„āĀ„Āĺ„Āô„Äā
„āą„ĀŹ„Āā„āčšļčšĺč„ĀĮÁôļŤ°®ŤÄÖ„ĀģśļĖŚāô„Āó„Āü„āĻ„É©„ā§„ÉČ„Āģ„Éē„ā©„É≥„Éą„ĀĆŚįŹ„Āē„Āô„Āé„Ā¶„āĻ„Éě„Éľ„Éą„Éē„ā©„É≥„Ā™„Ā©„Āߍ¶ĖŤĀī„Āô„āč„Ā®Ť≥áśĖô„ĀĆŤ™≠„āĀ„Ā™„ĀĄ„āĪ„Éľ„āĻ„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™Ś†īŚźą„ĀĮ„ÄĀťÖćšŅ°śôā„ĀęŤ≥áśĖô„Āģ„ĀŅ„āíśč°Ś§ß„Āó„Ā¶ÁĒĽťĚĘ„ĀęŚáļ„Āó„Āü„āä„ÄĀŤ≥áśĖô„āí„ÉÄ„ā¶„É≥„É≠„Éľ„ÉČ„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„Āô„āč„ĀęŚ∑•Ś§ę„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Āü„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„ĀģŤ¶ĖŤĀīŤÄÖ„ĀĮťĖĘŚŅÉ„Āģ„Āā„āč„Éą„ÉĒ„ÉÉ„āĮ„āíŚäĻÁéáÁöĄ„ĀęśéĘ„Āó„Āü„ĀĄ„Āü„āĀ„ÄĀ„ÉĀ„É£„Éó„āŅ„Éľś©üŤÉĹ„ĀģŤ®≠Śģö„ĀĆťĚ쌳ł„ĀęŚäĻśěúÁöĄ„Āß„Āô„ÄāťĆ≤ÁĒĽ„Éá„Éľ„āŅ„āí„ÉÜ„Éľ„Éě„ĀĒ„Ā®„āĄŤ≥™ÁĖĎŚŅúÁ≠Ē„āĽ„āĮ„ā∑„Éß„É≥„ĀĒ„Ā®„ĀęŚĆļŚąá„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŚŅÖŤ¶Ā„Ā™„āĽ„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥„Ā†„ĀĎ„āí„ÉĒ„É≥„ÉĚ„ā§„É≥„Éą„Āߍ¶ĖŤĀī„Āß„Āć„ÄĀŚ≠¶ÁŅíŚäĻśěú„ĀĆťęė„Āĺ„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„ÉĀ„É£„Éó„āŅ„ÉľśÉÖŚ†Ī„ĀĮś§úÁīĘ„ā®„É≥„āł„É≥„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀAI„āíśīĽÁĒ®„Āó„Āüťü≥Ś£įŤ™ćŤ≠ė„āĄŤ¶ĀÁīĄÁĒüśąź„ā®„É≥„āł„É≥„Āę„āą„ā茏Ė„āäŤĺľ„ĀŅ„Āę„āāŚĮĄšłé„Āó„ÄĀś§úÁīĘśĶĀŚÖ•„āĄŚľēÁĒ®ÁéጟϚłä„ĀģšłÄŚä©„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
ÁĒĽŤ≥™„āĄŚģĻťáŹ„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀťĀéŚļ¶„Ā™ŚúßÁłģ„Āę„āą„āčśĖáŚ≠óśĹį„āĆ„Āģťė≤ś≠Ę„āĄŚÜćÁĒüśôā„ĀģťÄĒŚąá„āĆŚĮĺÁ≠Ė„āíšł°Áęč„Āô„āčťĀ©Śąá„Ā™„Éź„É©„É≥„āĻ„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŚä†„Āą„Ā¶„ÄĀŤĀīŤ¶öśĒĮśŹī„Āģ„Āü„āĀ„ĀģŚ≠óŚĻēśŹźšĺõ„āĄŚ§öŤ®ÄŤ™ěŚĮĺŚŅúŚ≠óŚĻē„ĀģŤŅŌ䆄Ā™„Ā©„ÄĀŚ§öśßė„Ā™ŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀęŚĮĺŚŅú„Āô„āčśĖĻś≥ē„āāś§úŤ®é„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„Äā„ĀĚ„ĀģÁĶźśěú„ÄĀťöú„ĀĆ„ĀĄ„Āģ„Āā„āčśĖĻ„ĀģŚŹāŚä†„āĄŚõĹťöõšļ§śĶĀ„ĀģšŅÉťÄ≤„Āę„āāŤ≤ĘÁĆģ„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„ÄźŚŹāŤÄÉ„ÄĎ
śú¨ťÄ£ŤľČ„ā∑„É™„Éľ„āļ„ĀģŤ®ėšļč„āāŚŹāŤÄÉ„Āę„Āó„Ā¶„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā
„ÉĽ„ÄĆZoomśīĽÁĒ®„ĀߌģüÁŹĺ„Āô„āčśĖį„Āó„ĀĄŚ≠¶šľöšľöŤ≠į„āĻ„āŅ„ā§„ÉęÔĹěŚĮ卩Ī„Ā®ŚŹāŚä†„āíśĒĮ„Āą„āč„ÉŹ„ā§„ÉĖ„É™„ÉÉ„ÉČ„ĀģšĽēÁĶĄ„ĀŅÔĹě„Äć
„ÉĽśĖį„Āó„ĀĄŚ≠¶šľö„ĀģŚĹĘÔľĀ„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„āí„Āô„āč„É°„É™„ÉÉ„Éą„Ā®ťÖćšŅ°„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„āí„ĀĒÁīĻšĽčÔľĀÔĹúś†™ŚľŹšľöÁ§ĺInner Resource
2. ŤĎóšĹúś®©„ÉĽ„ā≥„É≥„Éó„É©„ā§„āĘ„É≥„āĻŚĮĺŚŅú„āĄŚŹāŚä†ŤÄÖ„Éč„Éľ„āļ„Āł„ĀģśüĒŤĽü„Ā™ŚĮĺŚŅúÁ≠Ė
„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„Āģśč°Ś§ß„Āęšľī„ĀĄ„ÄĀŤĎóšĹúś®©„ĀģťĀ©Śąá„Ā™Śá¶ÁźÜ„Ā®ŚÄčšļļśÉÖŚ†ĪšŅĚŤ≠∑„ĀĆťá捶Ā„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāÁôļŤ°®ŤÄÖ„āĄÁ¨¨šłČŤÄÖ„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„Āģś®©Śą©ÁĘļŤ™ć„ÄĀ„Éá„Éľ„āŅ„ĀģŚĆŅŚźćŚĆĖ„āĄ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£ŚĮĺÁ≠Ė„Ā®„ĀĄ„Ā£„Āü„É™„āĻ„āĮ„ā퍶荟ńĀ®„Āē„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„Āß„ÄĀšŅ°ť†ľśÄß„Āģťęė„ĀĄťĀčŚĖ∂šĹ∂„ĀĆśßčÁĮČ„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
2.1. ŤĎóšĹúś®©Śá¶ÁźÜ„Ā®ś≥ēÁöĄ„É™„āĻ„āĮ„ĀģŚõěťĀŅÁ≠Ė
„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮśė†ŚÉŹ„ÉĽŤ≥áśĖô„Āꌟę„Āĺ„āĆ„āčŤĎóšĹúś®©ŚēŹť°Ć„ĀĆťĀŅ„ĀĎ„Ā¶ťÄö„āĆ„Āĺ„Āõ„āď„ÄāÁôļŤ°®ŤÄÖ„Āģ„ā™„É™„āł„Éä„ÉęÁ†ĒÁ©∂„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀŚõ≥Ť°®„āĄŚľēÁĒ®śĖáÁĆģ„ÄĀŚÜôÁúü„ÉĽŚčēÁĒĽÁī†śĚź„Ā™„Ā©„Āę„ĀĮ„ÄĀŤĎóšĹúś®©„ĀĆÁ¨¨šłČŤÄÖ„ĀꌳįŚĪě„Āô„āč„āĪ„Éľ„āĻ„ĀĆŚ§ö„ĀŹ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„ĀĚ„Āģ„Āü„āĀśé≤ŤľČŚČć„Āę„Āď„āĆ„āČ„Āģś®©Śą©Śá¶ÁźÜ„āíÁĘļŚģü„ĀꍰƄĀÜ„Āď„Ā®„ĀĮŚ≠¶Ť°ď„ā≥„Éü„É•„Éč„ÉÜ„ā£„ĀģšŅ°ť†ľÁ∂≠śĆĀ„Ā®ś≥ēÁöĄ„É™„āĻ„āĮŤĽĹśłõ„Āꚳ挏Įś¨†„Āß„Āô„Äā
śúÄ„āāŚüļśú¨ÁöĄ„Ā™ŚĮĺŚŅúÁ≠Ė„ĀĮ„ÄĀÁôļŤ°®ŤÄÖ„Ā®„ĀģťĖď„Āßś®©Śą©Śą©ÁĒ®„āíśėéÁ§ļ„Āó„Āü„ÄĆŤ®ĪŤę匕ĎÁīĄ„Äć„āĄ„ÄĆŚźĆśĄŹśõł„Äć„āíÁĶź„Ā∂„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā„ĀĚ„Āď„Āę„ĀĮťÖćšŅ°śúüťĖď„ÄĀŤ¶ĖŤĀīÁĮĄŚõ≤„āĄŚĮĺŤĪ°ŤÄÖ„ĀģťôźŚģö„ÄĀťĆ≤ÁĒĽ„Éá„Éľ„āŅ„ĀģšļĆś¨°Śą©ÁĒ®ŚŹĮŚź¶„Ā™„Ā©Ť©≥Áīį„Ā™śĚ°šĽ∂„āíśė鍮ė„Āó„ÄĀťĀčÁĒ®„Éę„Éľ„Éę„āíŚÖ®šĹď„ĀߌÖĪťÄöÁźÜŤß£„Āó„Āĺ„Āô„Äā
ŚÖĪŚźĆÁ†ĒÁ©∂ŤÄÖ„āĄśČÄŚĪěś©üťĖĘ„Āģś®©Śą©Áä∂ś≥Ā„āāŚŹĮŤÉĹ„Ā™ťôź„āäÁĘļŤ™ć„Āó„ÄĀŤ™§Ťß£„āíśú™ÁĄ∂„Āęťė≤„Āé„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„ÄāŚēÜś•≠ŚáļÁČą„āĄšĽĖŤÄÖ„ĀģÁī†śĚź„ā팾ēÁĒ®„Āô„āčťöõ„ĀĮ„ÄĀŚŅÖŤ¶Ā„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶ŚÄ茹•„Āęś®©Śą©ŤÄÖ„Āč„āČ„ĀģšĹŅÁĒ®Ť®ĪŤęĺ„ā팏ĖŚĺó„Āó„ÄĀŤ®ĪŚŹĮ„ĀĆ„Āä„āä„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„ĀĮŤ©≤ŚĹďťÉ®ŚąÜ„ĀģÁ∑®ťõÜťô§ŚéĽ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āô„Äā
„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüŚĮĺŚŅú„ĀĮťÖćšŅ°ŚĺĆ„Āģ„āĮ„ɨ„Éľ„Ɇ„āĄś≥ēÁöĄ„Éą„É©„ÉĖ„Éę„āíśú™ÁĄ∂„Āęťė≤„ĀźŚäĻśěú„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀÁČĻ„Āę„ā™„É≥„É©„ā§„É≥„ĀߌļÉÁĮĄ„Āę„āĘ„āĮ„āĽ„āĻ„Āß„Āć„āč„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„Āß„ĀĮś≥®śĄŹ„ĀĆś¨†„Āč„Āõ„Āĺ„Āõ„āď„Äā
šĺč„Āą„Āį„ÄĀśó•śú¨ŚÜÖÁßĎŚ≠¶šľö„ĀĮŤá™Ś≠¶šľö„Āģ„ÄĆŤĎóšĹúś®©„ĀęťĖĘ„Āô„āčQ&A„Äć„āíWeb„ĀęŚÖ¨ťĖč„Āó„ÄĀŚ≠¶šľöŚď°„Āƍᙍļę„ĀģŤ¨õśľĒ„āĄŤ≥áśĖô„Āģś®©Śą©Śá¶ÁźÜ„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶ś≠£„Āó„ĀĄÁźÜŤß£„āíŚĺó„āČ„āĆ„āč„āą„ĀÜśĒĮśŹī„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüŚÖ¨ťĖčśÉÖŚ†Ī„āĄÁõłŤęáÁ™ďŚŹ£„ĀģśīĽÁĒ®„āāśúČŚäĻ„Āß„Āô„Äā
2.2. „Éó„É©„ā§„Éź„ā∑„ÉľšŅĚŤ≠∑„Ā®ŚŹāŚä†ŤÄÖŤ™ćŤ®ľ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ
„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„ĀĆťôźŚģöÁöĄ„Ā™šľöŚď°ŚźĎ„ĀĎ„āĄÁČĻŚģö„ĀģÁ†ĒÁ©∂ŤÄÖ„āį„Éę„Éľ„Éó„ĀꌟτĀĎ„Ā¶Ť°Ć„āŹ„āĆ„ā茆īŚźą„ÄĀ„āĘ„āĮ„āĽ„āĻŚą∂Śĺ°ś©üŤÉĹ„ĀĮťĀčŚĖ∂„Āģś†ĻŚĻĻ„āí„Ā™„Āó„Āĺ„Āô„ÄāšľöŚď°Ť™ćŤ®ľ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Ā®„ĀģťÄ£śźļ„ÄĀ„ÉĎ„āĻ„ÉĮ„Éľ„ÉČšŅĚŤ≠∑„Āē„āĆ„ĀüťĖ≤Ť¶ßÁíįŚĘÉ„ĀģśßčÁĮČ„ĀĆŚŅÖť†ą„Āß„ÄĀ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĀčÁĒ®„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚģČŚÖ®śÄß„Ā®Śą©šĺŅśÄß„Āģšł°Áęč„āíŚõ≥„āčŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Āē„āČ„ĀꌏāŚä†ŤÄÖ„ĀģŚÄčšļļśÉÖŚ†ĪšŅĚŤ≠∑„āāŚõĹťöõś®ôśļĖ„ĀģŤ¶≥ÁāĻ„Āč„āČŚé≥„Āó„ĀĄŤ¶ĀšĽ∂„āíśļÄ„Āü„ĀôŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆŚáļ„Ā¶„Āć„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äāś¨ßŚ∑ěťÄ£Śźą„ĀģGDPRÔľąGeneral Data Protection RegulationÔľöšłÄŤą¨„Éá„Éľ„āŅšŅĚŤ≠∑Ť¶ŹŚČáԾȄĀęťôź„āČ„Āö„ÄĀśó•śú¨„ĀģŚÄčšļļśÉÖŚ†ĪšŅĚŤ≠∑ś≥ē„āāŚľ∑ŚĆĖ„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŤ¶ĖŤĀī„É≠„āį„āĄ„ā≥„É°„É≥„Éą„ÄĀŚ≠¶ÁŅíŚĪ•ś≠ī„ĀģŚŹéťõÜ„ÉĽÁģ°ÁźÜ„Āęťöõ„Āó„Ā¶„ĀĮśėéÁĘļ„Ā™Śą©ÁĒ®ÁõģÁöĄ„ĀģśŹźÁ§ļ„Ā®ŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀģŚźĆśĄŹ„āíŚĺó„āč„Āď„Ā®„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
Ť≥™ÁĖĎŚŅúÁ≠Ē„āĽ„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥„ĀߌźćŚČć„āĄśČÄŚĪě„ĀĆŚÖ¨ťĖč„Āē„āĆ„ā茆īŚźą„ĀĮšļčŚČć„ĀęŚĆŅŚźćŚĆĖ„Āģś§úŤ®é„āĄŚźĆśĄŹśČčÁ∂ö„Āć„ā퍰ƄĀĄ„ÄĀśĄŹŚõ≥„Āó„Ā™„ĀĄŚÄčšļļśÉÖŚ†ĪśľŹśī©„āĄŚ∑ģŚą•ÁöĄŚŹĖ„āäśČĪ„ĀĄ„āíťė≤„ĀĄ„Āß„Āä„ĀŹŚŅÖŤ¶Ā„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
Śä†„Āą„Ā¶„ÄĀťĀčŚĖ∂ŚĀī„ĀĮ„āĘ„āĮ„āĽ„āĻ„É≠„āįÁģ°ÁźÜ„āĄ„āĶ„Éľ„Éź„Éľ„Āģ„āĽ„ā≠„É•„É™„ÉÜ„ā£Śľ∑ŚĆĖ„ÄĀ„Éó„É©„ā§„Éź„ā∑„Éľ„ÉĚ„É™„ā∑„Éľ„ĀģśēīŚāô„āíÁ∂ôÁ∂öÁöĄ„ĀęťÄ≤„āĀ„ÄĀŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀĆŚģČŚŅÉ„Āó„Ā¶Śą©ÁĒ®„Āß„Āć„āčÁíįŚĘÉ„ā휏źšĺõ„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā
„ÄźŚŹāŤÄÉ„ÄĎ
„ÉĽŚ≠¶Ť°ďŤ¨õśľĒ„ā퍰ƄĀÜťöõ„ĀģŤĎóšĹúś®©„ĀęťĖĘ„Āô„āčQ&AÔĹúśó•śú¨ŚÜÖÁßĎŚ≠¶šľö
„ÉĽ„ā™„É≥„É©„ā§„É≥Ś≠¶šľöÁôļŤ°®„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„ā¨„ā§„ÉČ„É©„ā§„É≥ÔĹúśó•śú¨śĖáŚĆĖšļļť°ěŚ≠¶šľöÁ¨¨54ŚõěÁ†ĒÁ©∂Ś§ßšľö
3. ťÖćšŅ°ŚäĻśěú„Āģśł¨Śģö„Ā®śĆĀÁ∂öŚŹĮŤÉĹ„Ā™ťĀčŚĖ∂šĹ∂„ĀģśßčÁĮČ
„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„āíťē∑śúüÁöĄ„ĀęÁôļŚĪē„Āē„Āõ„āč„Āę„ĀĮ„ÄĀŤ¶ĖŤĀī„Éá„Éľ„āŅ„ĀģŚąÜśěź„āĄś•≠Śčô„ĀģŚäĻÁéáŚĆĖ„ÄĀŚįāťĖÄ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀģŤā≤śąź„ÄĀ„Āē„āČ„Āę„ĀĮAI„āĄŤá™ŚčēŚĆĖŚįéŚÖ•„Āę„āą„āčťĀčŚĖ∂šĹ∂„ĀģťęėŚļ¶ŚĆĖ„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„Äā„ā≥„āĻ„ÉąÁģ°ÁźÜ„Ā®Ś§ĖťÉ®„Ā®„ĀģťÄ£śźļŚľ∑ŚĆĖ„āāśĆĀÁ∂öŚŹĮŤÉĹ„Ā™ťĀčŚĖ∂„ĀꌟτĀĎ„Āüťá捶Ā„Ā™Ť¶ĀÁī†„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
3.1. „Ā©„ĀÜ„āĄ„Ā£„Ā¶Ť¶ĖŤĀī„Éá„Éľ„āŅ„ā팹ܜ쟄Āô„āč„ĀčÔľüťÖćšŅ°ŚäĻśěú„ĀģŚŹĮŤ¶ĖŚĆĖśĖĻś≥ē
„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„āíÁ∂ôÁ∂öÁöĄ„Āč„Ā§ŚäĻśěúÁöĄ„ĀꍰƄĀÜšłä„Āß„ÄĀťÖćšŅ°ŚäĻśěú„ā팏ĮŤ¶ĖŚĆĖ„ĀóśĒĻŚĖĄ„ĀęÁĻč„Āí„āč„Āü„āĀ„ĀģŤ¶ĖŤĀī„Éá„Éľ„āŅ„ĀģŚŹéťõÜ„ÉĽŚąÜśěź„ĀĮś¨†„Āč„Āõ„Āĺ„Āõ„āď„Äā
Ť¶ĖŤĀīŚõěśēį„ĀĮ„āā„Ā°„āć„āď„ÄĀŚĻ≥ŚĚ፶ĖŤĀīśôāťĖď„ÄĀŤ¶ĖŤĀīŚģĆšļÜÁéá„ÄĀ„É™„āĘ„Éę„āŅ„ā§„ɆťÖćšŅ°„Ā®„ĀģśĮĒŤľÉ„Ā™„Ā©„ÄĀŚ§öŤßíÁöĄ„Ā™śēįŚÄ§śĆáś®ô„āíśīĽÁĒ®„Āó„Ā¶ŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀģŚą©ÁĒ®Áä∂ś≥Ā„āíÁźÜŤß£„Āó„Āĺ„Āô„ÄāŚä†„Āą„Ā¶„ÄĆ„Ā©„ĀģśôāťĖĮ„ĀꍶĖŤĀī„ĀĆťõÜšł≠„Āô„āč„Āč„Äć„ÄĆťÄĒšł≠ťõĘŤĄĪ„ĀĆŚ§ö„ĀĄÁģáśČÄ„ĀĮ„Ā©„Āď„Āč„Äć„Ā™„Ā©„āíÁČĻŚģö„Āó„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ā퍳Ź„Āĺ„Āą„Āü„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄšľĀÁĒĽ„āĄÁ∑®ťõÜšĹúś•≠„ĀģŤ¶čÁõī„Āó„ĀęŚĹĻÁęč„Ā¶„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Āü„ÄĀ„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüŚģöťáŹ„Éá„Éľ„āŅ„ĀęŚä†„Āą„ÄĀŚŹāŚä†ŤÄÖ„Āł„Āģ„āĘ„É≥„āĪ„Éľ„ÉąŤ™ŅśüĽ„Āę„āą„Ā£„Ā¶ÁźÜŤß£Śļ¶„ĀģŚ§ČŚĆĖ„āĄťÖćšŅ°„Āł„ĀģśļÄŤ∂≥śĄü„ÄĀšĽäŚĺĆ„ĀģŤ¶Āśúõ„āíśä䜏°„Āô„āč„Ā™„Ā©„ĀģŚģöśÄß„Éá„Éľ„āŅ„ĀģŚąÜśěź„āāťá捶Ā„Āß„Āô„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀŚćė„ĀꍶĖŤĀī„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āč„Ā©„ĀÜ„Āč„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀŚ≠¶„Ā≥„ĀģŤ≥™„āĄŚŹāŚä†šĹďť®ď„ĀģŚÖÖŚģüŚļ¶„āāŤ©ēšĺ°„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā
Śģüťöõ„ĀęÁĻį„āäŤŅĒ„ĀóŤ¶ĖŤĀī„Āē„āĆ„āč„ÉĀ„É£„Éó„āŅ„Éľ„ĀģÁČĻŚģö„āĄ„ÄĀŚŹāŚä†ŤÄÖŚĪ§„ĀĒ„Ā®„ĀģŤ¶ĖŤĀīŚā匟όąÜśěź„Ā™„Ā©„āāŚ§ö„ĀŹ„ĀģŚ≠¶šľö„ĀߌŹĖ„āäŚÖ•„āĆ„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀś¨°ŚõěťĖčŚā¨„Āł„ĀģŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™„Éē„ā£„Éľ„ÉČ„Éź„ÉÉ„āĮ„ĀęŚĹĻÁęč„Ā¶„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
3.2. śĆĀÁ∂öŚŹĮŤÉĹ„Ā™ťĀčŚĖ∂šĹ∂„Ā®Śįܜ̕ŚĪēśúõ
Ś≠¶šľö„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„ĀģśąźŚäü„āíśĆĀÁ∂ö„Āē„Āõ„ÄĀ„āą„āäťęėŚļ¶„Ā™„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„āíŚĪēťĖč„Āô„āč„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀťĀčŚĖ∂ŚüļÁõ§„ĀģŚľ∑ŚĆĖ„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„Äā„Āĺ„ĀöŚÜ֝ɮÁöĄ„Āę„ĀĮ„ÄĀťÖćšŅ°ś•≠Śčô„ā퍰ƄĀÜŚįāťĖÄ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀģŤā≤śąź„Ā®ťĀ©Śąá„Ā™šļļŚď°ťÖćÁĹģ„ā퍰ƄĀĄ„ÄĀťĀčŚĖ∂„Éé„ā¶„ÉŹ„ā¶„ĀģÁ∂ôśČŅ„āíŚõ≥„āä„Āĺ„Āô„ÄāśäÄŤ°ďÁöĄ„Ā™„āĻ„ā≠„Éę„āĘ„ÉÉ„Éó„ĀģŚźĎšłä„āą„āä„āā„Éó„É≠„Éá„É•„Éľ„āĻ„āĄ„Éě„Éć„āł„É°„É≥„Éą„Āģ„āĻ„ā≠„Éę„āĘ„ÉÉ„Éó„ĀęťáćÁāĻ„āíÁĹģ„ĀćśĆĀÁ∂öŚŹĮŤÉĹ„Ā™ťĀčŚĖ∂šĹ∂„ĀģśįłÁ∂ö„āíŤÄÉ„Āą„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā
Ś§ĖťÉ®„ĀģŚčēÁĒĽŚą∂šĹú„āĄ„ā∑„āĻ„É܄ɆťĀčÁĒ®ŚßĒŤ®óŚÖą„Ā®„ĀģťÄ£śźļšĹ∂„āāśēīŚāô„Āó„ÄĀŚŅÖŤ¶Ā„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶ŚćĒś•≠„ÉĘ„Éá„Éę„āíśč°Ś§ß„Āô„āč„Āď„Ā®„āāś§úŤ®é„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Āĺ„Āü„ÄĀŚŹéťĆ≤ś©üśĚź„ĀĮŤ≥ľŚÖ•„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ɨ„É≥„āŅ„Éę„āĄ„É™„Éľ„āĻ„āíśīĽÁĒ®„ĀóťĀčÁĒ®„ā≥„āĻ„Éą„āíśäĎ„Āą„Ā§„Ā§„ÄĀšŅĚŚģąÁāĻś§ú„āíŚäĻÁéáÁöĄ„Āę„Āä„Āď„Ā™„Āą„āč„āą„ĀÜ„Āę„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀߌÜÜśĽĎ„Ā™Á®ľŚÉć„āíÁ∂≠śĆĀ„Āó„Āĺ„Āô„ÄāÁ∑®ťõÜ„ÉĽťÖćšŅ°ťĚĘ„Āß„ĀĮ„ÄĀŤŅĎŚĻī„ĀģAIśäÄŤ°ď„ā팹©ÁĒ®„Āó„ĀüŤá™ŚčēÁ∑®ťõÜ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ĀģŚįéŚÖ•„āĄ„ÄĀŤá™ŚčēŚ≠óŚĻēÁĒüśąź„ÄĀŚ§öŤ®ÄŤ™ěÁŅĽŤ®≥ś©üŤÉĹ„Ā™„Ā©„ĀģśĖįś©üŤÉĹś§úŤ®ľ„Āę„āāÁ©ćś•ĶÁöĄ„ĀꌏĖ„āäÁĶĄ„āÄ„Āď„Ā®„ĀĆťá捶Ā„Āß„Āô„Äā
„Āď„āĆ„āČ„Āę„āą„āäťĀčŚĖ∂ŚäĻÁéá„ā팟Ϛłä„Āē„Āõ„ÄĀŤ≥™„Āģťęė„ĀĄ„ā≥„É≥„ÉÜ„É≥„ÉĄ„āíŚģČŚģöÁöĄ„ĀęťÖćšŅ°ŚŹĮŤÉĹ„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
ťĀčŚĖ∂Ť≤ĽÁĒ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚąĚśúüŚįéŚÖ•Ť≤ĽÁĒ®„Ā®„É©„É≥„Éč„É≥„āį„ā≥„āĻ„Éą„Āģ„Éź„É©„É≥„āĻ„āíśėéÁĘļ„ĀꍶčÁ©ć„āā„āä„ÄĀŚŹāŚä†ŤÄÖśēįŚĘóŚä†„āĄ„āĶ„Éľ„Éď„āĻ„Āģśč°ŚÖÖ„Āꌟą„āŹ„Āõ„ĀüŤ≥áťáĎŤ®ąÁĒĽ„āíÁ≠ĖŚģö„Āó„Āĺ„Āô„Äā
ÁČĻ„Āę„ā™„É≥„É©„ā§„É≥ťÖćšŅ°„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„Ɇ„ĀģťĀłśäěŤāĘ„ĀĮŚ§öŚ≤ź„Āę„āŹ„Āü„āä„ÄĀśĖôťáĎšĹďÁ≥Ľ„āĄś©üŤÉĹťĚĘ„Āß„ĀģśĮĒŤľÉ„āíšłĀŚĮß„ĀꍰƄĀÜ„Āď„Ā®„ĀĆŚ§ßŚąá„Āß„Āô„Äā
šłÄśĖĻ„ÄĀŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀģŚą©šĺŅśÄߌźĎšłä„āĄŚ≠¶šľöŚÖ®šĹď„Āģ„Éá„āł„āŅ„ÉęŚĆĖšŅÉťÄ≤„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀŚŹāŚä†ÁôĽťĆ≤„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„ÄĀŤęĖśĖáśäēÁ®Ņ„ÄĀšľöŚď°Áģ°ÁźÜ„ā∑„āĻ„É܄Ɇ„Ā®„ĀģťÄ£Śčē„āĄ„ÄĀÁĶĪŚźąÁöĄ„Ā™Áģ°ÁźÜ„Éó„É©„ÉÉ„Éą„Éē„ā©„Éľ„ɆśßčÁĮČ„ĀꌟτĀĎ„ĀüDXÔľą„Éá„āł„āŅ„Éę„Éą„É©„É≥„āĻ„Éē„ā©„Éľ„É°„Éľ„ā∑„Éß„É≥ԾȜ鮝Ä≤„āāśą¶Áē•ÁöĄ„ĀꌏĖ„āäÁĶĄ„āÄ„ĀĻ„Ā捙≤ť°Ć„Āß„Āô„Äā
„Āĺ„Ā®„āĀ„ÄÄ„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČ„Āߌ≠¶„Ā≥„āíÁ∂ôÁ∂ö„Āß„Āć„āčŚ≠¶šľö„Ā•„ĀŹ„āä„Āł
Ś≠¶Ť°ďŚ≠¶šľö„Āę„Āä„ĀĎ„āč„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°„ĀĮ„ÄĀŚćė„Ā™„āčśė†ŚÉŹťÖćšŅ°śäÄŤ°ď„ĀģŚįéŚÖ•„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀÁ†ĒÁ©∂ŤÄÖ„ā≥„Éü„É•„Éč„ÉÜ„ā£„ĀģŚ≠¶„Ā≥„Āģ„āĻ„āŅ„ā§„Éę„ā휆Ļśú¨„Āč„āČŚ§ČťĚ©„Āô„ā茏Ė„āäÁĶĄ„ĀŅ„Āß„Āô„Äā
„Āď„ĀģŤÉĆśôĮ„Āę„ĀĮ„ÄĀŚúįŚüü„āĄśôāťĖď„ĀģŚ£Ā„āíŤ∂Ö„Āą„ĀüŤ≥™„Āģťęė„ĀĄŚ≠¶Ť°ďśÉÖŚ†Ī„ĀģŚÖĪśúČ„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀÁ†ĒÁ©∂„ā≥„Éü„É•„Éč„ÉÜ„ā£ŚÖ®šĹď„ĀģśīĽśÄߌĆĖ„āíšŅÉťÄ≤„Āô„āčśôāšĽ£„ĀģŤ¶ĀŤęč„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāśąźŚäü„Āģ„Āü„āĀ„Āę„ĀĮ„ÄĀťęėŚďĀŤ≥™„Ā™ťÖćšŅ°„ĀģŚģüÁŹĺ„Ā®„Ā®„āā„Āę„ÄĀŤĎóšĹúś®©ťĀĶŚģą„āĄŚÄčšļļśÉÖŚ†ĪšŅĚŤ≠∑„Ā™„Ā©„ĀģŚÄęÁźÜÁöĄ„ÉĽś≥ēÁöĄŚĀīťĚĘ„Āł„ĀģŚćĀŚąÜ„Ā™ťÖćśÖģ„ÄĀŚŹāŚä†ŤÄÖ„Āģ„Éč„Éľ„āļ„ĀęŚĮĄ„āäś∑Ľ„Ā£„Āü„āĶ„Éľ„Éď„āĻŤ®≠Ť®ą„ĀĆšłćŚŹĮś¨†„Āß„Āô„Äā
Śä†„Āą„Ā¶Ť¶ĖŤĀī„Éá„Éľ„āŅŚąÜśěź„āĄŚŹāŚä†ŤÄÖ„Āč„āČ„Āģ„Éē„ā£„Éľ„ÉČ„Éź„ÉÉ„āĮ„āíťÄö„Āė„Ā¶Á∂ôÁ∂öÁöĄ„ĀęśĒĻŚĖĄ„āíťáć„Ā≠„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀŚą©ÁĒ®ŤÄÖ„ĀģśļÄŤ∂≥Śļ¶„āĄŚ≠¶ÁŅíŚäĻśěú„āí„āą„āä„ĀĄ„Ā£„ĀĚ„ĀÜťęė„āĀ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„ÄāŚįܜ̕„ĀꌟτĀĎ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀAI„āĄŤá™ŚčēŚĆĖśäÄŤ°ď„ĀģšĹďÁ≥ĽÁöĄ„Ā™ŚįéŚÖ•„ĀĆťÄ≤ŚĪē„Āô„āč„Ā®šļąśł¨„Āē„āĆ„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™śäÄŤ°ďťĚ©śĖį„ĀĮ„ÄĀŚ§öŤ®ÄŤ™ěŚĮĺŚŅú„Āä„āą„Ā≥ŚÄ茹•śúÄťĀ©ŚĆĖ„Āē„āĆ„ĀüŚ≠¶Ť°ďšľöŤ≠įśĒĮśŹī„ĀģťęėŚļ¶ŚĆĖ„āíšŅÉťÄ≤„Āó„ÄĀŚ≠¶šľöÁíįŚĘÉ„ĀģŚ§öśßėśÄß„Ā®śüĒŤĽüśÄß„ā팧߄Āć„ĀŹŚźĎšłä„Āē„Āõ„Āĺ„Āô„Äā
ÁĶźśěú„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀ„ÉŹ„ā§„ÉĖ„É™„ÉÉ„ÉČťĖčŚā¨ŚĹĘŚľŹ„Āę„ĀĮÁźÜŤęĖÁöĄ„Āä„āą„Ā≥ŚģüŤ∑ĶÁöĄŤ¶≥ÁāĻ„Āč„āČśĖį„Āü„Ā™ŚĪēťĖč„ĀĆśúüŚĺÖ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā
„Āď„āĆ„Āĺ„Āß„ĀßÁ§ļ„Āó„ĀüŚÖ∑šĹďÁöĄ„Ā™„Éé„ā¶„ÉŹ„ā¶„Ā®śúÄśĖį„Éą„ɨ„É≥„ÉČ„āíśīĽÁĒ®„ĀĮ„ÄĀÁ†ĒÁ©∂„ÉĽśēôŤā≤„ĀģÁôļŚĪē„ĀęŤ≤ĘÁĆģ„Āô„āčť≠ÖŚäõÁöĄ„Ā™„ā™„É≥„Éá„Éě„É≥„ÉČťÖćšŅ°ÁíįŚĘÉ„ĀģśßčÁĮČ„āíťÄ≤„āĀ„āč„Éí„É≥„Éą„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ŚŹĖ„āäÁĶĄ„ĀŅ„ĀĆ„ÄĀÁŹĺšĽ£„ĀģÁßĎŚ≠¶śäÄŤ°ď„ā≥„Éü„É•„Éč„ÉÜ„ā£„ĀģśĆĀÁ∂öÁöĄśąźťē∑„āíśĒĮ„Āą„āčťá捶Ā„Ā™ŚüļÁõ§„ĀģšłÄ„Ā§„Ā®„Ā™„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā