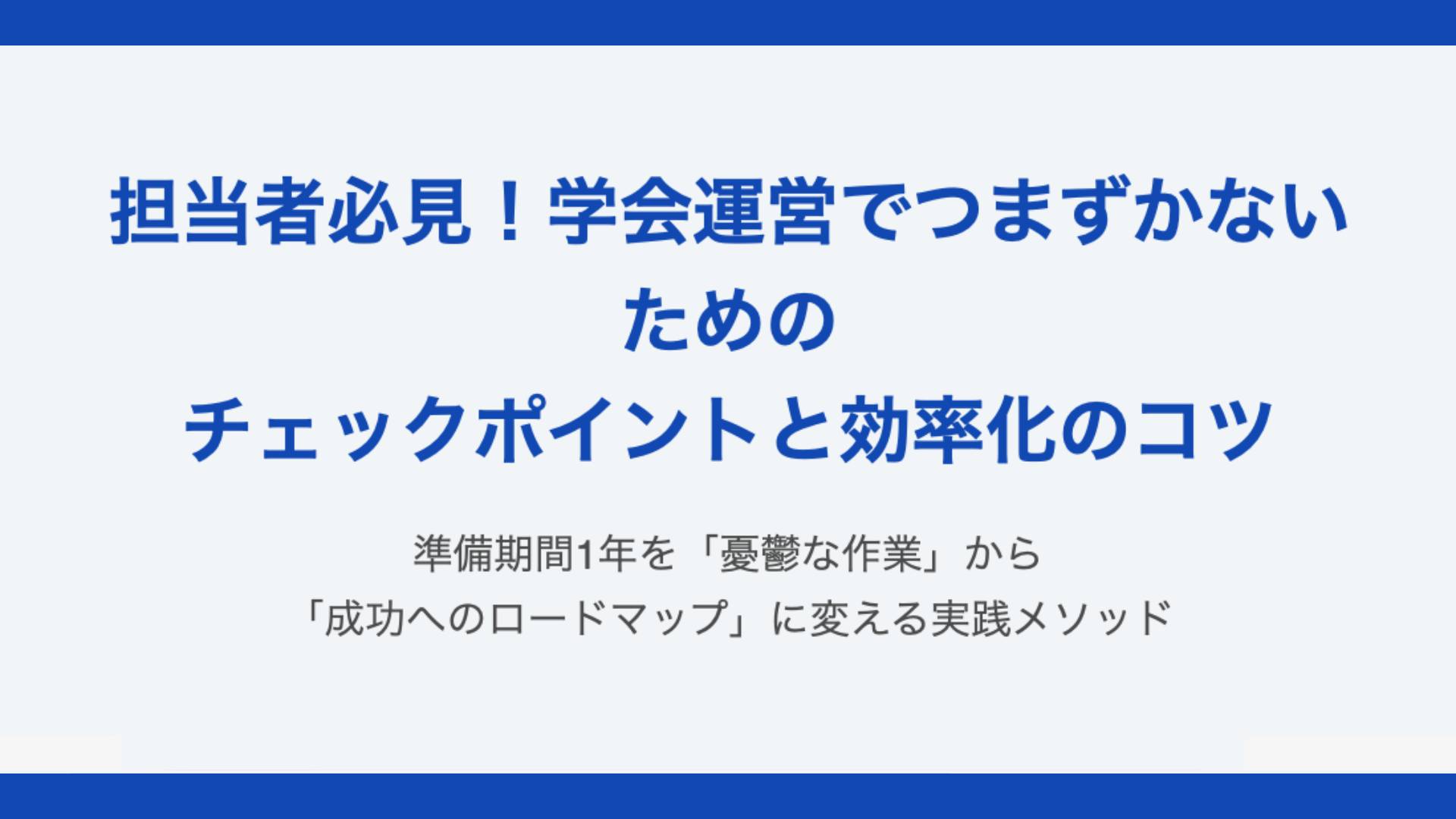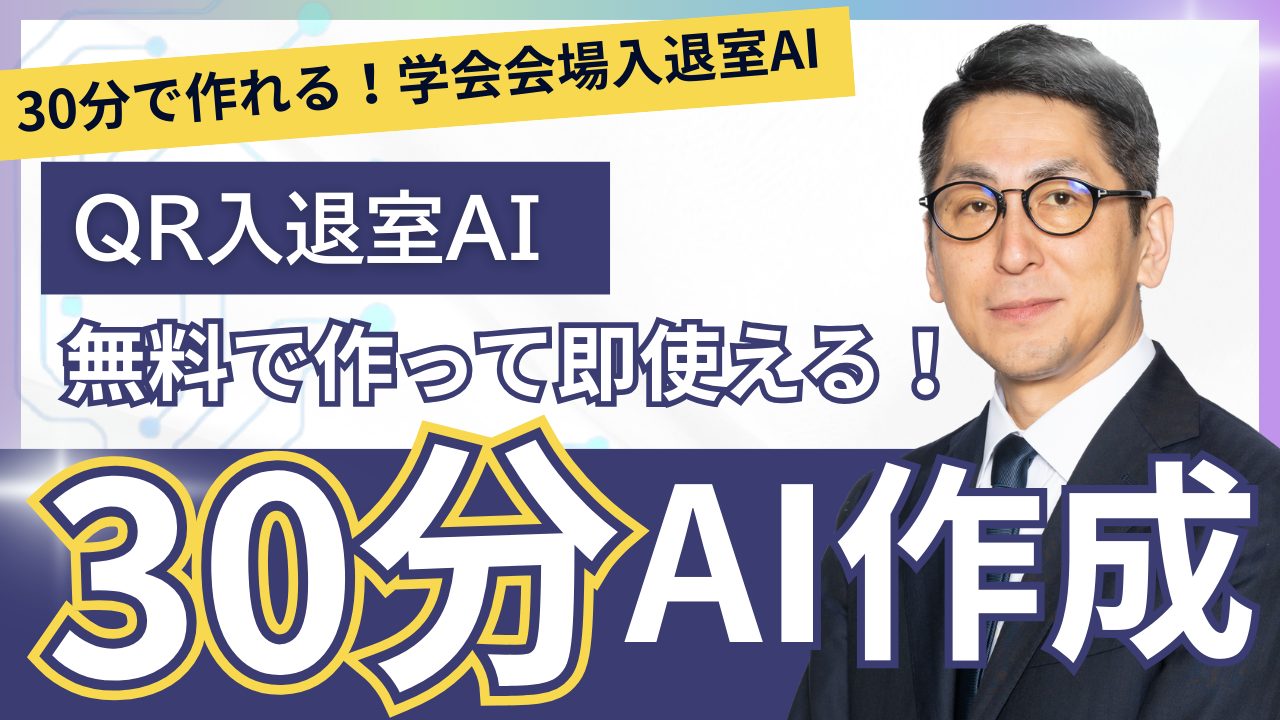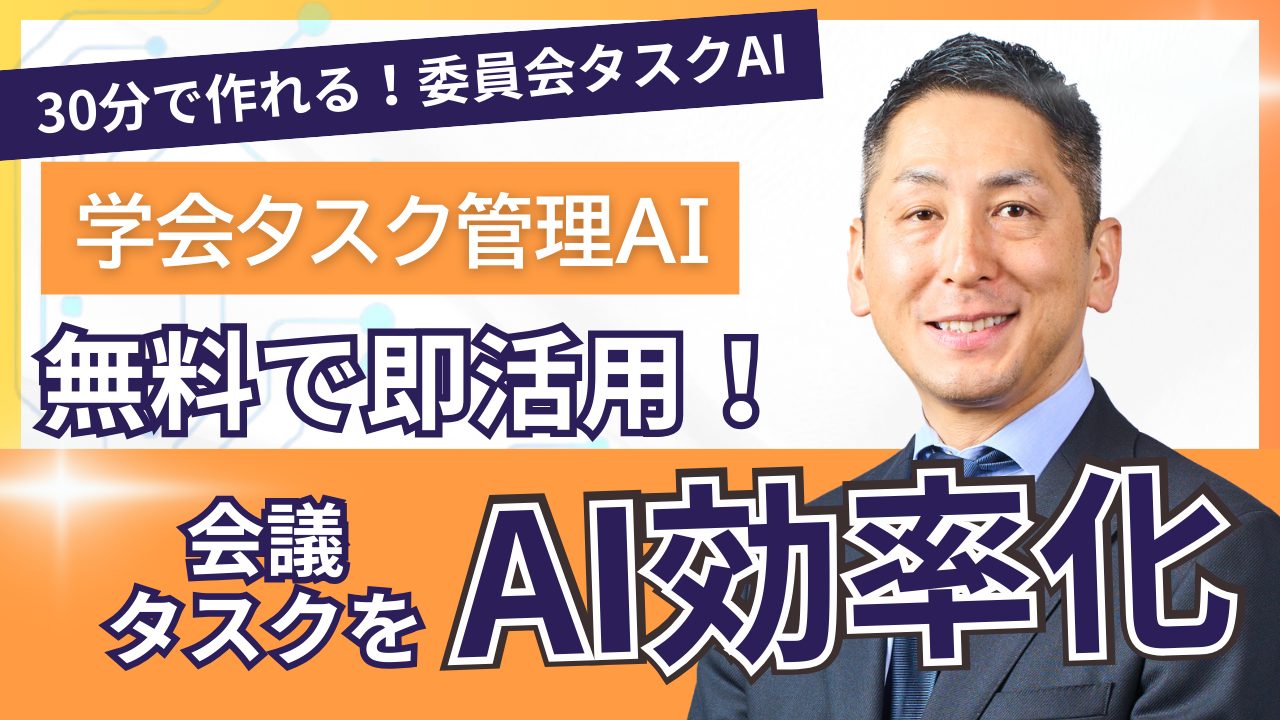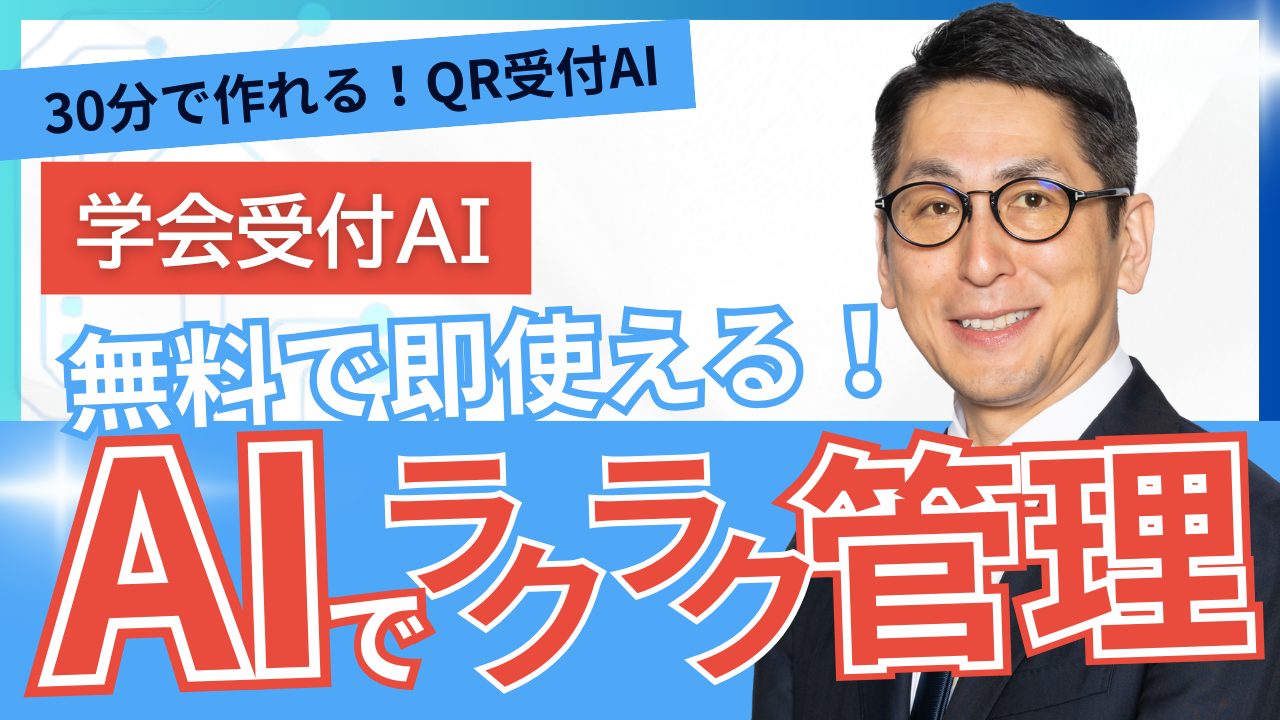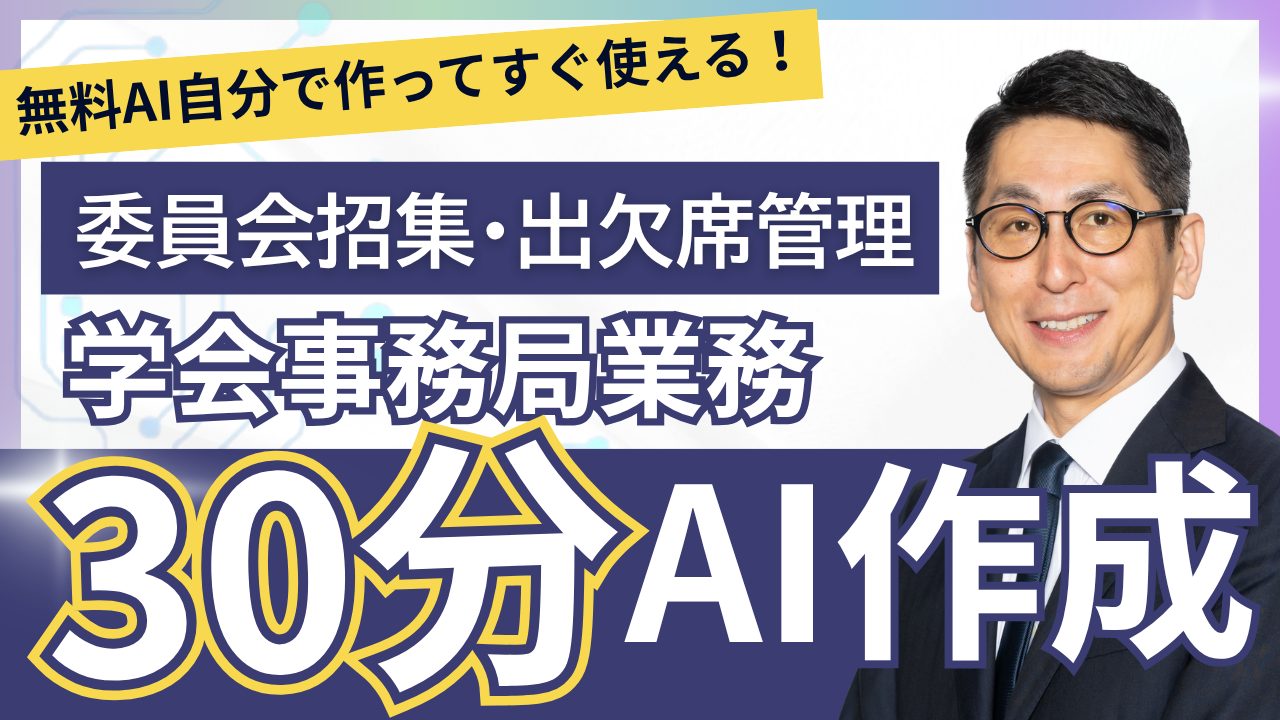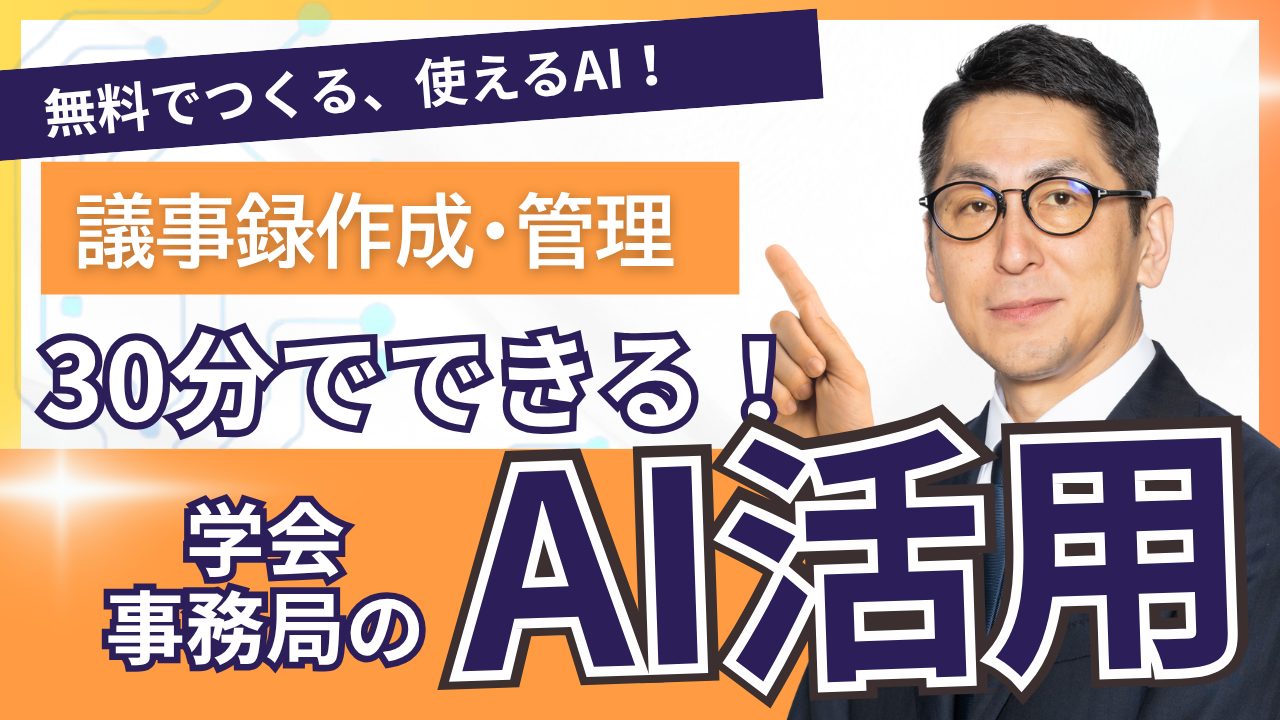Zoomو´»ç”¨مپ§ه®ںçڈ¾مپ™م‚‹و–°مپ—مپ„ه¦ن¼ڑن¼ڑè°م‚¹م‚؟م‚¤مƒ«م€€ï½ه¯¾è©±مپ¨هڈ‚هٹ م‚’و”¯مپˆم‚‹مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰مپ®ن»•çµ„مپ؟ï½
2025ه¹´08وœˆ19و—¥
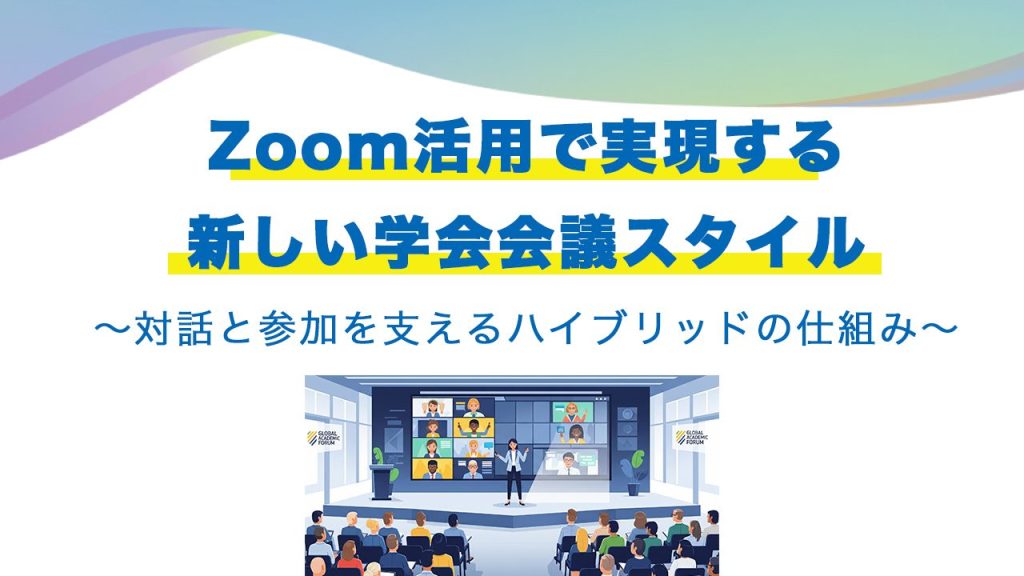
مپ¯مپکم‚پمپ« Zoomمپ«م‚ˆم‚‹ه¦ن¼ڑن؛¤وµپمپ®وœ€و–°م‚¹م‚؟م‚¤مƒ«مپ¨و´»ç”¨è،“
و–°ه‹م‚³مƒمƒٹم‚¦م‚¤مƒ«م‚¹و„ںوں“症(COVID-19)مپ®و‹،ه¤§م‚’و©ںمپ«م€په¤ڑمپڈمپ®ه¦ن¼ڑمپ§م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³é–‹ه‚¬م‚„مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰é–‹ه‚¬مپŒو€¥é€ںمپ«و™®هڈٹمپ—مپ¾مپ—مپںم€‚ه¾“و¥مپ®ن¼ڑه ´مپ§مپ®ه¯¾é¢é–‹ه‚¬مپ«هٹ مپˆم€پZoomم‚’مپ¯مپکم‚پمپ¨مپ™م‚‹Webن¼ڑè°م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’و´»ç”¨مپ—مپںو–°مپ—مپ„ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶م‚¹م‚؟م‚¤مƒ«مپ¯م€پهœ°çگ†çڑ„هˆ¶ç´„م‚’超مپˆمپںهڈ‚هٹ م‚’هڈ¯èƒ½مپ«مپ—م€په¦è،“ن؛¤وµپمپ®مپ‚م‚ٹو–¹م‚’ه¤§مپچمپڈه¤‰مپˆمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه‹مپ®ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ¯م€پçڈ¾هœ°هڈ‚هٹ 者مپ¨م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ®هڈŒو–¹مپ«ن¾،ه€¤مپ‚م‚‹ن½“験م‚’وڈگن¾›مپ—مپ¾مپ™مپŒم€پم€Œن½“験مپ®و ¼ه·®م€چمپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«ه¯¾ه؟œمپ™مپ¹مپچمپ‹و‚©مپ¾م‚Œم‚‹و–¹م‚‚ه°‘مپھمپڈمپھمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
ن¸€و–¹مپ§م€پéپ©هˆ‡مپھو؛–ه‚™مپ¨éپ‹ه–¶ن½“هˆ¶م‚’و•´مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¾“و¥مپ®ه¯¾é¢é–‹ه‚¬م‚’ن¸ٹه›م‚‹ه¤ڑو§کو€§مپ¨هŒ…ه®¹هٹ›م‚’وŒپمپ£مپںه¦ن¼ڑم‚’ه®ںçڈ¾مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پمپ‚م‚‹è£½è–¬ن¼ڑ社مپ®ç ”ن؟®ن¼ڑمپ§مپ¯م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ®و؛€è¶³ه؛¦مپŒ90%م‚’超مپˆم‚‹ن؛‹ن¾‹م‚‚ه ±ه‘ٹمپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پمƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰éپ‹ه–¶مپ®هڈ¯èƒ½و€§م‚’ç¤؛ه”†مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
وœ¬è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€پZoomم‚’و´»ç”¨مپ—مپںمƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه¦ن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ„مپ¦م€پهڈ‚هٹ 者مپ®و؛€è¶³ه؛¦م‚’é«کم‚پم€په¦è،“çڑ„مپھن¾،ه€¤م‚’وœ€ه¤§هŒ–مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®ه®ںè·µçڑ„مپھو‰‹و³•م‚’مپ”ç´¹ن»‹مپ—مپ¾مپ™م€‚وٹ€è،“çڑ„مپھé…چن؟،è¨è¨ˆمپ‹م‚‰çڈ¾ه ´مپ§مپ®م‚µمƒمƒ¼مƒˆن½“هˆ¶مپ¾مپ§م€په¦ن¼ڑن؛‹ه‹™ه±€مپ®çڑ†و§کمپŒç›´é¢مپ™م‚‹èھ²é،Œمپ«ه¯¾مپ™م‚‹ه…·ن½“çڑ„مپھ解و±؛ç–م‚’ن¸€ç·’مپ«è€ƒمپˆمپ¦مپ„مپچمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
وœ¬é€£è¼‰م‚·مƒھمƒ¼م‚؛مپ®è¨کن؛‹م‚‚هڈ‚考مپ«مپ—مپ¦مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
مƒ»م€Œه¯¾é¢é–‹ه‚¬مپ¨م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ®è‰¯مپ•م‚’و´»مپ‹مپ™ï¼پï½مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه¦ن¼ڑمپ®è¨è¨ˆمپ¨éپ‹ه–¶مپ®ه®ںè·µم‚¬م‚¤مƒ‰ï½م€چ
1.مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه¦ن¼ڑم‚’وˆگهٹںمپ•مپ›م‚‹é…چن؟،è¨è¨ˆمپ¨çڈ¾هœ°م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ®ç§ک訣
مپ“مپ“مپ§مپ¯م€پé«که“پè³ھمپھéں³éں؟مƒ»وک هƒڈç’°ه¢ƒمپ®و§‹ç¯‰مپ¨م€پهڈ‚هٹ 者ن½“験مپ®çµ±ن¸€م‚’ه®ںçڈ¾مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®ه…·ن½“çڑ„مپھو‰‹و³•م‚’解èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه‹م‚«مƒ³مƒ•م‚،مƒ¬مƒ³م‚¹مپ§مپ¯م€پé…چن؟،ç’°ه¢ƒمپ®و•´ه‚™مپ¨م‚µمƒمƒ¼مƒˆن½“هˆ¶مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚ه¤§ن¼ڑم‚„ه¦è،“ن¼ڑè°مپ®è¦ڈو¨،م‚„م‚»مƒƒم‚·مƒ§مƒ³مپ®ç‰¹و€§مپ«هگˆم‚ڈمپ›مپ¦م€پZoomمپ®ه¤ڑه½©مپھو©ں能م‚’و´»ç”¨مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
1.1. éں³éں؟مƒ»وک هƒڈç’°ه¢ƒمپ®وœ€éپ©هŒ–مپ¨و©ںوگéپ¸ه®ڑ
مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه¦ن¼ڑمپ®وˆگهٹںمپ¯م€پéں³éں؟مپ¨وک هƒڈمپ®ه“پè³ھمپŒهڈ‚هٹ 者مپ®ن½“験م‚’ه·¦هڈ³مپ™م‚‹é‡چè¦پمپھè¦پç´ مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚çڈ¾هœ°هڈ‚هٹ 者مپ¨م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ®هڈŒو–¹مپŒه؟«éپ©مپ«èپ´è¬›مپ§مپچم‚‹ç’°ه¢ƒم‚’و§‹ç¯‰مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«م€پو¬،مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚’هڈ‚考مپ«مپ—مپ¦مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
(1) éں³éں؟ç’°ه¢ƒ
م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ¨çڈ¾هœ°هڈ‚هٹ 者مپ®é–“مپ«éں³è³ھمƒ»ç”»è³ھمپ®ه·®م‚’و„ںمپکمپ•مپ›مپھمپ„مپ“مپ¨مپŒم€پوˆگهٹںمپ«ه°ژمپڈéچµمپ§مپ™م€‚éں³éں؟é¢مپ§مپ¯م€پن¼ڑه ´مپ®مƒم‚¤م‚¯مپ‹م‚‰ç›´وژ¥Zoomمپ«éں³ه£°م‚’ه…¥هٹ›مپ™م‚‹éڑ›م€پمƒڈم‚¦مƒھمƒ³م‚°م‚„éں³ه£°مپ®é€”هˆ‡م‚Œم‚’éک²مپگمپںم‚پم€پم‚ھمƒ¼مƒ‡م‚£م‚ھم‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒ•م‚§مƒ¼م‚¹مپ®ه°ژه…¥مپŒهٹ¹وœçڑ„مپ§مپ™م€‚مپ¾مپںم€پç™؛è،¨è€…用مپ¨è³ھç–‘ه؟œç”用مپ®مƒم‚¤م‚¯م‚’هˆ†é›¢مپ—م€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®éں³ه£°مƒ¬مƒ™مƒ«م‚’èھ؟و•´مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ«م‚‚èپمپچهڈ–م‚ٹم‚„مپ™مپ„éں³éں؟ç’°ه¢ƒم‚’و•´مپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
(2) وک هƒڈç’°ه¢ƒ
ç™؛è،¨م‚¹مƒ©م‚¤مƒ‰مپ¨ç™؛è،¨è€…مپ®ن¸،و–¹م‚’هگŒو™‚مپ«é…چن؟،مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®م‚«مƒ،مƒ©مƒ¯مƒ¼م‚¯م‚‚é‡چè¦پمپ§مپ™م€‚é«ک解هƒڈه؛¦Webم‚«مƒ،مƒ©م‚’複و•°هڈ°è¨ç½®مپ—م€پç™؛è،¨è€…مپ®è،¨وƒ…م‚„ن¼ڑه ´مپ®é›°ه›²و°—م‚’هٹ¹وœçڑ„مپ«ن¼مپˆم‚‹و§‹وˆگم‚’و¤œè¨ژمپ—مپ¾مپ™م€‚مƒم‚¹م‚؟مƒ¼م‚»مƒƒم‚·مƒ§مƒ³م‚„ه±•ç¤؛مƒ–مƒ¼م‚¹م‚’م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ«م‚‚ن½“験مپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپ†مپںم‚پمپ«مپ¯م€پهڈ¯ه‹•ه¼ڈمپ®م‚«مƒ،مƒ©م‚„360ه؛¦م‚«مƒ،مƒ©مپ®و´»ç”¨م‚‚وœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
وœ¬é€£è¼‰م‚·مƒھمƒ¼م‚؛مپ®è¨کن؛‹م‚‚هڈ‚考مپ«مپ—مپ¦مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
مƒ»م€ŒZoomé…چن؟،مپ«مپٹمپ‘م‚‹éں³éں؟è¨è¨ˆمپ¨ن¼ڑه ´مƒم‚¤م‚¯è¨ه®ڑمپ®هں؛وœ¬م€œن¼م‚ڈم‚‹ه£°مپŒه¦ن¼ڑم‚’ه¤‰مپˆم‚‹م€œم€چ
1.2. هڈ‚هٹ 者ن½“験مپ®çµ±ن¸€مپ¨هڈŒو–¹هگ‘و€§مپ®ç¢؛ن؟
çڈ¾هœ°هڈ‚هٹ 者مپ¨م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ®ن½“験و ¼ه·®م‚’وœ€ه°ڈé™گمپ«وٹ‘مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپ¯م€پمƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®é‡چè¦پمپھèھ²é،Œمپ§مپ™م€‚ن¸،者مپŒهگŒç‰مپ®ه¦è،“çڑ„ن¾،ه€¤م‚’ه¾—م‚‰م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†م€پé…چن؟،ه†…ه®¹مپ®و§‹وˆگم‚„هڈ‚هٹ و–¹و³•مپ«ه‰µو„ڈه·¥ه¤«م‚’ه‡م‚‰مپ™ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
è³ھç–‘ه؟œç”م‚»مƒƒم‚·مƒ§مƒ³مپ§مپ¯م€پçڈ¾هœ°مپ¨م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ®ن¸،و–¹مپ‹م‚‰ç™؛言م‚’هڈ—مپ‘ن»کمپ‘م‚‹مپںم‚پمپ®مƒ«مƒ¼مƒ«è¨è¨ˆمپŒه؟…é ˆمپ§مپ™م€‚Zoomمپ®مƒپمƒ£مƒƒمƒˆو©ں能م‚„مƒھم‚¢م‚¯م‚·مƒ§مƒ³و©ں能م‚’و´»ç”¨مپ—م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ‹م‚‰مپ®è³ھه•ڈم‚’هٹ¹çژ‡çڑ„مپ«هڈژ集مƒ»و•´çگ†مپ™م‚‹ن½“هˆ¶م‚’و•´مپˆمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚هڈ¸ن¼ڑ者مپ¯çڈ¾هœ°مپ®è³ھه•ڈ者مپ¨م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ®è³ھه•ڈ者م‚’ه…¬ه¹³مپ«وŒ‡هگچمپ—م€په…¨هڈ‚هٹ 者مپŒè°è«–مپ«هڈ‚هٹ مپ§مپچم‚‹é›°ه›²و°—مپ¥مپڈم‚ٹمپŒه¤§هˆ‡مپ§مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پمƒچمƒƒمƒˆمƒ¯مƒ¼م‚مƒ³م‚°مپ®و©ںن¼ڑم‚’وڈگن¾›مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«م€پZoomمپ®م€Œمƒ–مƒ¬م‚¤م‚¯م‚¢م‚¦مƒˆمƒ«مƒ¼مƒ و©ں能م€چم‚’و´»ç”¨مپ—مپںه°ڈم‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مƒ‡م‚£م‚¹م‚«مƒƒم‚·مƒ§مƒ³م‚„م€په°‚用مپ®م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³و‡‡è¦ھن¼ڑمپ®é–‹ه‚¬م‚‚و¤œè¨ژمپ«ه€¤مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ†مپ—مپںن؛¤وµپمپ®ه ´مپ“مپمپŒه¦ن¼ڑمپ®é†چé†گه‘³مپ¨è¨€مپˆمپ¾مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»مƒ–مƒ¬م‚¤م‚¯م‚¢م‚¦مƒˆمƒ«مƒ¼مƒ و©ں能مپ®ن½؟مپ„و–¹ï½œو±ن؛¬ه¤§ه¦ utelecon
2.مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«ن؛ˆéک²مƒ»çڈ¾ه ´é€£وگ؛مƒ»و”¯وڈ´ن½“هˆ¶مپ®و•´ه‚™و–¹و³•
مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ§م‚‚ن¸چو¸¬مپ®ن؛‹و…‹مپ¯مپ¤مپچم‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚وœ€و‚ھمپھçٹ¶و³پم‚’وƒ³ه®ڑمپ—مپںن¸مپ§م€په؟…è¦پمپھو؛–ه‚™م‚„ن؛؛ه“،ن½“هˆ¶مپ«مپ¤مپ„مپ¦è€ƒمپˆمپ¦مپ؟مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚ن¸چو¸¬مپ®ن؛‹و…‹مپ«ه‚™مپˆم‚‹مپںم‚پمپ®ن؛‹ه‰چو؛–ه‚™مپ¨م€په½“و—¥مپ®ه††و»‘مپھéپ‹ه–¶م‚’و”¯مپˆم‚‹مƒپمƒ¼مƒ ن½“هˆ¶م‚’و•´مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚م€Œوƒ³ه®ڑه¤–م€چمپ¨ه¾Œم€…مپھم‚‰مپھمپ„م‚ˆمپ†مپ«م€Œوƒ³ه®ڑه†…م€چمپ§و؛–ه‚™م‚’進م‚پم‚‹مپ“مپ¨مپŒمƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ§مپ™م€‚
2.1. ن؛‹ه‰چمƒ†م‚¹مƒˆمپ¨و©ںوگو؛–ه‚™مپ®ه¾¹ه؛•
مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه¦ن¼ڑم‚’وˆگهٹںمپ«ه°ژمپڈمپںم‚پمپ«مپ¯م€په…¥ه؟µمپھن؛‹ه‰چو؛–ه‚™مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚وœ¬ç•ھمپ®و•°و—¥ه‰چمپ‹م‚‰ن¼ڑه ´مپ§مپ®و©ںوگمƒ†م‚¹مƒˆم‚’ه®ںو–½مپ—م€پéں³éں؟مƒ»وک هƒڈمƒ»é€ڑن؟،ç’°ه¢ƒمپ®مپ™مپ¹مپ¦م‚’ç¢؛èھچمپ™م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚特مپ«م€پç™؛è،¨è€…مپŒمƒھمƒ¢مƒ¼مƒˆمپ‹م‚‰هڈ‚هٹ مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ«مپ¯م€پن؛‹ه‰چمپ«وژ¥ç¶ڑمƒ†م‚¹مƒˆم‚’è،Œمپ„م€پç”»é¢ه…±وœ‰م‚„éں³ه£°ه“پè³ھمپ«ه•ڈé،ŒمپŒمپھمپ„مپ“مپ¨م‚’ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
و©ںوگمپ®ه†—é•·هŒ–م‚‚é‡چè¦پمپھè¦پç´ مپ§مپ™م€‚مƒ،م‚¤مƒ³مپ®مƒ‘م‚½م‚³مƒ³م‚„م‚«مƒ،مƒ©مپ«هٹ مپˆم€پمƒگمƒƒم‚¯م‚¢مƒƒمƒ—用مپ®و©ںوگم‚’و؛–ه‚™مپ—م€پمƒˆمƒ©مƒ–مƒ«ç™؛ç”ںو™‚مپ«م‚‚é…چن؟،م‚’継ç¶ڑمپ§مپچم‚‹ن½“هˆ¶م‚’و•´مپˆمپ¾مپ™م€‚م‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆوژ¥ç¶ڑمپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚‚م€پوœ‰ç·ڑLANمپ¨ç„،ç·ڑLANم€پمپ•م‚‰مپ«مپ¯مƒ¢مƒگم‚¤مƒ«ه›ç·ڑم‚’ن½µç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پé€ڑن؟،éڑœه®³مپ®مƒھم‚¹م‚¯م‚’وœ€ه°ڈهŒ–مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚م‚¹م‚؟مƒ¼مƒھمƒ³م‚¯مپ®م‚ˆمپ†مپھéپ éڑ”هœ°مپ§مپ®é€ڑن؟،و‰‹و®µم‚’ç¢؛ن؟مپ—مپ¦مپٹمپڈمپ¨م€پم‚ˆم‚ٹن¸€ه±¤ه®‰ه؟ƒمپ§مپ™م€‚
ç™؛è،¨è€…هگ‘مپ‘مپ«مپ¯م€پZoomمپ®و“چن½œو–¹و³•م‚„ç”»é¢ه…±وœ‰مپ®و‰‹é †م‚’èھ¬وکژمپ—مپںمƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م‚’ن؛‹ه‰چمپ«é…چه¸ƒمپ—م€پن¸چوکژمپھ点مپŒمپ‚م‚Œمپ°ن؛‹ه‰چ相談م‚’هڈ—مپ‘ن»کمپ‘م‚‹çھ“هڈ£م‚’è¨ç½®مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په½“و—¥مپ®مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«م‚’ن؛ˆéک²مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®و؛–ه‚™و®µéڑژمپ§مپ®ن¸په¯§مپھه¯¾ه؟œمپŒم€په½“و—¥مپ®وˆگهٹںمپ«مپ¤مپھمپŒم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
2.2. مƒھم‚¢مƒ«م‚؟م‚¤مƒ ه¯¾ه؟œمƒپمƒ¼مƒ مپ®ه½¹ه‰²هˆ†و‹…
مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه¦ن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶مپ§مپ¯م€پçڈ¾هœ°مپ¨م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ®ن¸،و–¹مپ«ه¯¾ه؟œمپ§مپچم‚‹ه°‚é–€مƒپمƒ¼مƒ مپ®è¨ç½®مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚وٹ€è،“و‹…ه½“者م€پهڈ¸ن¼ڑ進è،Œو‹…ه½“者م€پهڈ‚هٹ 者م‚µمƒمƒ¼مƒˆو‹…ه½“者مپ®ه½¹ه‰²م‚’وکژç¢؛مپ«هˆ†و‹…مپ—م€پمپم‚Œمپم‚ŒمپŒé€£وگ؛مپ—مپ¦ه•ڈé،Œè§£و±؛مپ«مپ‚مپںم‚‹ن½“هˆ¶م‚’و§‹ç¯‰مپ—مپ¾مپ™م€‚
(1) مƒ†م‚¯مƒ‹م‚«مƒ«م‚µمƒمƒ¼مƒˆ
وٹ€è،“و‹…ه½“者مپ¯م€پZoomمپ®و“چن½œه…¨èˆ¬م€پéں³éں؟مƒ»وک هƒڈو©ںه™¨مپ®èھ؟و•´م€پé€ڑن؟،مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«مپ®ه¯¾ه؟œم‚’و‹…ه½“مپ—مپ¾مپ™م€‚
(2) مƒ¢مƒ‡مƒ¬مƒ¼م‚؟مƒ¼
هڈ¸ن¼ڑ進è،Œو‹…ه½“者مپ¯م€پçڈ¾هœ°مپ¨م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ®هڈ‚هٹ 者م‚’çµ±ن¸€çڑ„مپ«مƒمƒچم‚¸مƒ،مƒ³مƒˆمپ—م€پè³ھç–‘ه؟œç”م‚„ن¼‘و†©و™‚é–“مپ®èھ؟و•´م‚’è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚
(3) م‚µمƒمƒ¼م‚؟مƒ¼
هڈ‚هٹ 者م‚µمƒمƒ¼مƒˆو‹…ه½“者مپ¯م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ‹م‚‰مپ®وٹ€è،“çڑ„مپھè³ھه•ڈم‚„وژ¥ç¶ڑمƒˆمƒ©مƒ–مƒ«مپ«ه¯¾ه؟œمپ—م€په¦ن¼ڑمپ¸مپ®هڈ‚هٹ م‚’و”¯وڈ´مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپ“م‚Œم‚‰مپ®و‹…ه½“者間مپ®é€£çµ،و‰‹و®µمپ¨مپ—مپ¦م€په…چ許ن¸چè¦پمپ®ه°ڈé›»هٹ›مƒˆمƒ©مƒ³م‚·مƒ¼مƒگمƒ¼م‚’ن½؟مپ£مپںم‚¤مƒ³م‚«مƒ م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚„ه°‚用مپ®مƒپمƒ£مƒƒمƒˆمƒ„مƒ¼مƒ«م‚’و´»ç”¨مپ—م€پè؟…é€ںمپھوƒ…ه ±ه…±وœ‰مپ¨ه¯¾ه؟œم‚’هڈ¯èƒ½مپ«مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚特مپ«م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ‹م‚‰مپ®مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«ه ±ه‘ٹم‚’çڈ¾هœ°مپ®وٹ€è،“و‹…ه½“者مپ«هچ³ه؛§مپ«ن¼éپ”مپ§مپچم‚‹ن»•çµ„مپ؟مپ®و•´ه‚™مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
2.3. ç·ٹو€¥و™‚ه¯¾ه؟œمƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«مپ®ن½œوˆگمپ¨éپ‹ç”¨
وƒ³ه®ڑمپ•م‚Œم‚‹مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«م‚·مƒٹمƒھم‚ھمپ«ه¯¾مپ™م‚‹ه¯¾ه؟œو‰‹é †م‚’ن؛‹ه‰چمپ«مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«هŒ–مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤§هˆ‡مپ§مپ™م€‚éپ‹ه–¶مƒپمƒ¼مƒ ه…¨ن½“مپ§ه…±وœ‰مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پç·ٹو€¥و™‚مپ«م‚‚ه†·é™مپ‹مپ¤è؟…é€ںمپ«ه¯¾ه؟œمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚é€ڑن؟،éڑœه®³م€پو©ںوگو•…éڑœم€پç™؛è،¨è€…مپ®وژ¥ç¶ڑمƒˆمƒ©مƒ–مƒ«مپھمپ©م€پèµ·مپ“م‚ٹه¾—م‚‹ه•ڈé،Œم‚’وƒ³ه®ڑمپ—مپم‚Œمپم‚Œمپ«ه¯¾مپ™م‚‹ه…·ن½“çڑ„مپھه¯¾ه؟œç–مپ®و؛–ه‚™مپŒه¤§هˆ‡مپ§مپ™م€‚
مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«ç™؛ç”ںو™‚مپ®هڈ‚هٹ 者مپ¸مپ®وƒ…ه ±وڈگن¾›م‚‚é‡چè¦پمپھè¦پç´ مپ§مپ™م€‚Zoomمپ®مƒپمƒ£مƒƒمƒˆو©ں能م‚„ه¦ن¼ڑمپ®Webم‚µم‚¤مƒˆم€پSNSم‚¢م‚«م‚¦مƒ³مƒˆم‚’و´»ç”¨مپ—مپ¦م€پçڈ¾هœ¨مپ®çٹ¶و³پم‚„ه¾©و—§è¦‹è¾¼مپ؟م‚’ه®ڑوœںçڑ„مپ«م‚¢مƒٹم‚¦مƒ³م‚¹مپ—م€پهڈ‚هٹ 者مپ®ن¸چه®‰م‚’軽و¸›مپ™م‚‹هٹھهٹ›مپ«هڈ–م‚ٹ組مپ؟مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚é€ڈوکژو€§مپ®مپ‚م‚‹وƒ…ه ±وڈگن¾›مپ¯م€پهڈ‚هٹ 者مپ®ن¸چه®‰è§£و¶ˆمپ¨ن؟،é ¼ç¶وŒپمپ«مپ¤مپھمپŒم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³ه¦ن¼ڑمپ®مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمƒ»مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¨و´»ç”¨و³•ï½œم‚¨مƒٹم‚´م‚¢م‚«مƒ‡مƒںمƒ¼
3.“مپ¤مپھمپŒم‚‹ه¦ن¼ڑâ€م‚’مپ¤مپڈم‚‹م‚¨مƒ³م‚²مƒ¼م‚¸مƒ،مƒ³مƒˆه¼·هŒ–è،“
مپ“مپ“مپ§مپ¯م€پZoomمپ®و©ں能م‚’و´»ç”¨مپ—م€پهڈ‚هٹ 者مپ®ç©چو¥µçڑ„مپھé–¢ن¸ژم‚’ن؟ƒمپ™مپںم‚پمپ®ه…·ن½“çڑ„مپھو–¹و³•م‚’解èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚
م‚¨مƒ³م‚²مƒ¼م‚¸مƒ،مƒ³مƒˆمپ¨مپ¯م€پهڈ‚هٹ 者مپŒمپ©م‚Œمپ مپ‘ç©چو¥µçڑ„مپ«é–¢م‚ڈمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’ç¤؛مپ™و¦‚ه؟µمپ§مپ™م€‚هڈ‚هٹ 者مپ®و„ڈو¬²م‚„集ن¸ه؛¦م‚’é«کم‚پم‚‹مپںم‚پمپ®ن»•وژ›مپ‘م‚„ن»•çµ„مپ؟م‚’考مپˆمپ¦مپ؟مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
3.1. م‚¤مƒ³م‚؟مƒ©م‚¯مƒ†م‚£مƒ–و©ں能مپ®هٹ¹وœçڑ„و´»ç”¨
Zoomمپ®ه¤ڑه½©مپھو©ں能م‚’و´»ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ®م‚¨مƒ³م‚²مƒ¼م‚¸مƒ،مƒ³مƒˆم‚’ه¤§ه¹…مپ«هگ‘ن¸ٹمپ•مپ›م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚وٹ•ç¥¨و©ں能م‚’ن½؟مپ£مپںمƒھم‚¢مƒ«م‚؟م‚¤مƒ م‚¢مƒ³م‚±مƒ¼مƒˆم‚„م€پمƒ›مƒ¯م‚¤مƒˆمƒœمƒ¼مƒ‰و©ں能م‚’و´»ç”¨مپ—مپںهچ”هƒچن½œو¥مپ¯م€په¾“و¥مپ®ه¯¾é¢é–‹ه‚¬مپ§مپ¯ه®ںçڈ¾ه›°é›£مپھو–°مپ—مپ„ه¦è،“ن؛¤وµپمپ®ه½¢م‚’ç”ںمپ؟ه‡؛مپ—مپ¾مپ™م€‚
特مپ«ه¤§è¦ڈو¨،مپھه¦ن¼ڑمپ«مپٹمپ„مپ¦مپ¯م€پمƒپمƒ£مƒƒمƒˆو©ں能م‚’é€ڑمپکمپںè³ھه•ڈهڈژ集م‚„و„ڈ見ن؛¤وڈ›مپŒو´»ç™؛هŒ–مپ—م€پç™؛è،¨è€…مپ¨هڈ‚هٹ 者م€پمپ•م‚‰مپ«مپ¯هڈ‚هٹ 者هگŒه£«مپ®è°è«–م‚’ن؟ƒé€²مپ™م‚‹هٹ¹وœمپŒوœںه¾…مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®و©ں能م‚’éپ©هˆ‡مپ«و´»ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پ物çگ†çڑ„مپھè·é›¢م‚’超مپˆمپںن¸€ن½“و„ںمپ®مپ‚م‚‹ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھم‚‹مپ®مپ§مپ™م€‚
3.2. م‚¢مƒ¼م‚«م‚¤مƒ–و´»ç”¨مپ«م‚ˆم‚‹ç¶™ç¶ڑçڑ„مپھه¦ç؟’و©ںن¼ڑمپ®وڈگن¾›
Zoomمپ®éŒ²ç”»و©ں能م‚’و´»ç”¨مپ—مپںه¦ن¼ڑم‚¢مƒ¼م‚«م‚¤مƒ–مپ¯م€پهڈ‚هٹ 者مپ«مپ¨مپ£مپ¦è²´é‡چمپھه¦ç؟’مƒھم‚½مƒ¼م‚¹مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مƒھم‚¢مƒ«م‚؟م‚¤مƒ مپ§مپ®هڈ‚هٹ مپŒه›°é›£مپ مپ£مپںç ”ç©¶è€…م‚„م€په¾©ç؟’مپ®مپںم‚پمپ«ه†…ه®¹م‚’ه†چç¢؛èھچمپ—مپںمپ„هڈ‚هٹ 者مپ«مپ¨مپ£مپ¦م€پم‚¢مƒ¼م‚«م‚¤مƒ–مپ¸مپ®م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ¯ه¦ن¼ڑهڈ‚هٹ مپ®ن¾،ه€¤م‚’ه¤§ه¹…مپ«هگ‘ن¸ٹمپ•مپ›مپ¾مپ™م€‚
م‚¢مƒ¼م‚«م‚¤مƒ–مپ®ه…¬é–‹مپ«مپ‚مپںمپ£مپ¦مپ¯م€پç™؛è،¨è€…مپ®è‘—ن½œو¨©م‚„ه¦ن¼ڑمپ®çں¥çڑ„è²،産و¨©مپ«é…چو…®مپ—مپںهˆ©ç”¨è¦ڈç´„مپ®ç–ه®ڑمپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚ن¼ڑه“،é™گه®ڑه…¬é–‹م€پوœںé–“é™گه®ڑه…¬é–‹م€پن¸€éƒ¨م‚»مƒƒم‚·مƒ§مƒ³مپ®مپ؟مپ®ه…¬é–‹مپھمپ©م€په¦ن¼ڑمپ®و–¹é‡مپ«ه؟œمپکمپںوں”è»ںمپھéپ‹ç”¨م‚’و¤œè¨ژمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
مپ•م‚‰مپ«م€پم‚¢مƒ¼م‚«م‚¤مƒ–م‚’و´»ç”¨مپ—مپں継ç¶ڑçڑ„مپھو•™è‚²مƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ مپ®ه±•é–‹م‚‚視é‡ژمپ«ه…¥م‚Œمپںمپ„مپ¨مپ“م‚چمپ§مپ™م€‚è‹¥و‰‹ç ”究者هگ‘مپ‘مپ®ه¦ç؟’م‚³مƒ³مƒ†مƒ³مƒ„مپ¨مپ—مپ¦مپ®و´»ç”¨م‚„関連ه¦ن¼ڑمپ¨مپ®çں¥èکه…±وœ‰مپھمپ©م€پ録画مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ®ن؛Œو¬،هˆ©ç”¨مپ«م‚ˆم‚‹â€œو–°مپںمپھن¾،ه€¤ه‰µé€ â€م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§ه¦ن¼ڑمپ®ç¤¾ن¼ڑçڑ„ه½±éں؟هٹ›م‚’و‹،ه¤§مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
وœ¬é€£è¼‰م‚·مƒھمƒ¼م‚؛مپ®è¨کن؛‹م‚‚هڈ‚考مپ«مپ—مپ¦مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
مƒ»م€Œه¾Œو—¥è¦–èپ´مپ§ç ”究مپ¨ه¦مپ³م‚’مپ¤مپھمپگم€œه¦ن¼ڑم‚ھمƒ³مƒ‡مƒمƒ³مƒ‰é…چن؟،مپ®هٹ¹وœمپ¨ه·¥ه¤«م€œم€چ
مپ¾مپ¨م‚پم€€م‚ˆم‚ٹه¤ڑمپڈمپ®هڈ‚هٹ 者مپ«é–‹مپ‹م‚Œمپںه¦ن¼ڑمپ¥مپڈم‚ٹم‚’م‚پمپ–مپ—مپ¦
Zoomم‚’و´»ç”¨مپ—مپںمƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ¯م€په¾“و¥مپ®ه¯¾é¢é–‹ه‚¬مپ®é™گç•Œم‚’超مپˆمپںو–°مپ—مپ„ه¦è،“ن؛¤وµپمپ®هڈ¯èƒ½و€§م‚’é–‹و‹“مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚هœ°çگ†çڑ„هˆ¶ç´„م‚„物çگ†çڑ„هˆ¶ç´„م‚’超مپˆمپ¦م€پم‚ˆم‚ٹه¤ڑو§کمپھ背و™¯م‚’وŒپمپ¤ç ”究者مپŒه¦ن¼ڑمپ«هڈ‚هٹ مپ§مپچم‚‹ç’°ه¢ƒمپ¯م€په¦è،“م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹مƒ†م‚£ه…¨ن½“مپ®ç™؛ه±•مپ«ه¤§مپچمپڈ貢献مپ—مپ¾مپ™م€‚
وٹ€è،“é¢مپ§مپ®èھ²é،Œم‚„éپ‹ه–¶مپ®è¤‡é›‘مپ•مپ¯ç¢؛مپ‹مپ«هکهœ¨مپ—مپ¾مپ™مپŒم€پéپ©هˆ‡مپھو؛–ه‚™مپ¨ن½“هˆ¶و•´ه‚™مپ«م‚ˆم‚ٹم€پمپ“م‚Œم‚‰مپ®èھ²é،Œم‚’ن¹—م‚ٹè¶ٹمپˆم‚‹مپ“مپ¨مپ¯هچپهˆ†مپ«هڈ¯èƒ½مپ§مپ™م€‚
éں³éں؟مƒ»وک هƒڈç’°ه¢ƒمپ®وœ€éپ©هŒ–م€پمƒˆمƒ©مƒ–مƒ«ه¯¾ه؟œن½“هˆ¶مپ®و§‹ç¯‰م€پهڈ‚هٹ 者م‚¨مƒ³م‚²مƒ¼م‚¸مƒ،مƒ³مƒˆمپ®هگ‘ن¸ٹمپ¨مپ„مپ£مپںè¦پç´ م‚’ç·ڈهگˆçڑ„مپ«و¤œè¨ژمپ—م€پçڈ¾هœ°هڈ‚هٹ 者مپ¨م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 者مپ®هڈŒو–¹مپ«مپ¨مپ£مپ¦ن¾،ه€¤مپ‚م‚‹ن½“験م‚’وڈگن¾›مپ™م‚‹ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶م‚’ه®ںçڈ¾مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
ن»ٹه¾Œم‚‚وٹ€è،“مپ®é€²و©مپ¨مپ¨م‚‚مپ«م€پمƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه¦ن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶و‰‹و³•مپ¯مپ•م‚‰مپ«و´—ç·´مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپچمپ¾مپ™م€‚ه¦ن¼ڑن؛‹ه‹™ه±€مپ®و‹…ه½“者م‚„éپ‹ه–¶è²¬ن»»è€…مپ¯م€پهڈ‚هٹ 者مپ®مƒ‹مƒ¼م‚؛م‚’çڑ„ç¢؛مپ«وٹٹوڈ،مپ—م€پ継ç¶ڑçڑ„مپھو”¹ه–„م‚’é€ڑمپکمپ¦م€پم‚ˆم‚ٹهŒ…ه®¹هٹ›مپ®مپ‚م‚‹ه¦è،“م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹مƒ†م‚£مپ®ه½¢وˆگمپ«è²¢çŒ®مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
و–°مپ—مپ„و™‚ن»£مپ®ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ¯م€پ“وٹ€è،“مپ¨ن؛؛مپ®و¸©مپ‹مپ•م‚’èچهگˆâ€مپ•مپ›مپںم€پمپ“م‚Œمپ¾مپ§مپ«مپھمپ„è±ٹمپ‹مپھه¦è،“ن؛¤وµپمپ®ه ´م‚’ه‰µé€ مپ™م‚‹ه¤§مپچمپھهڈ¯èƒ½و€§م‚’ç§کم‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚