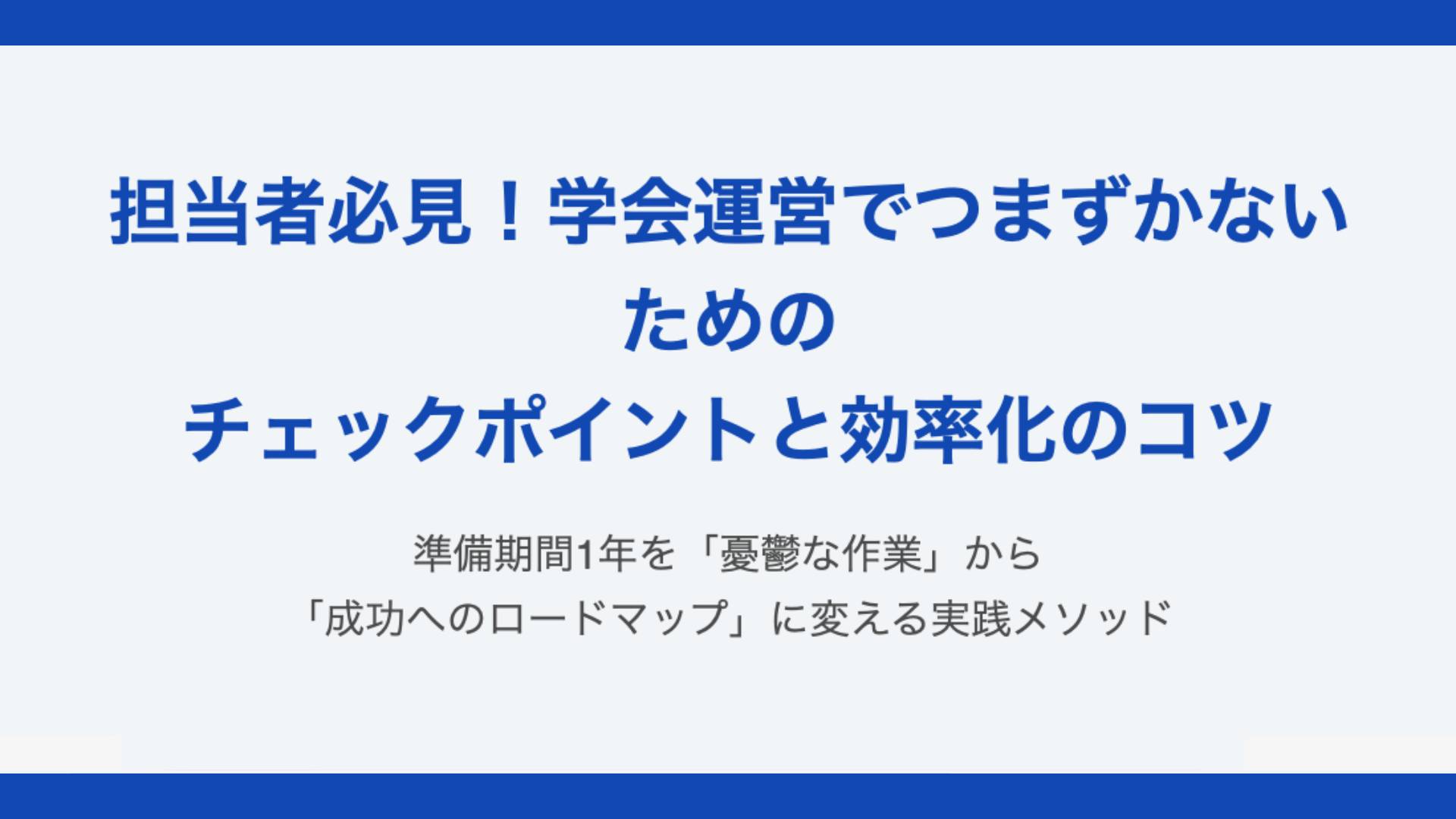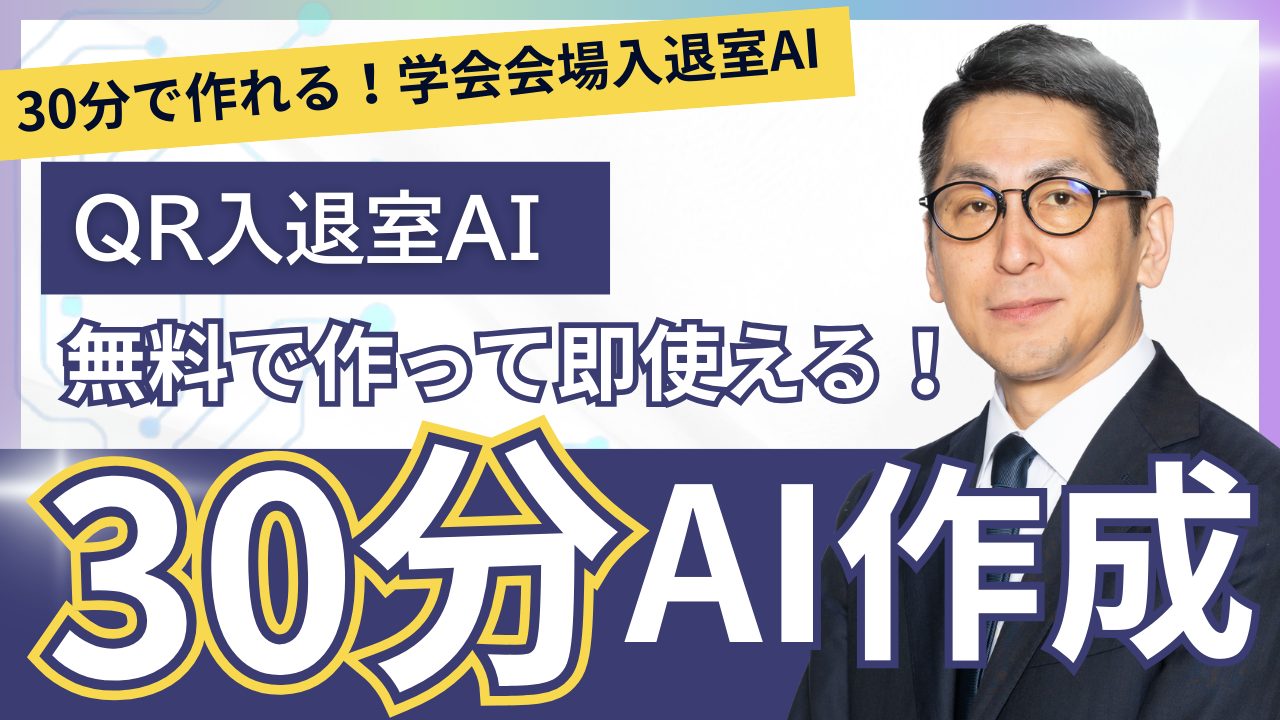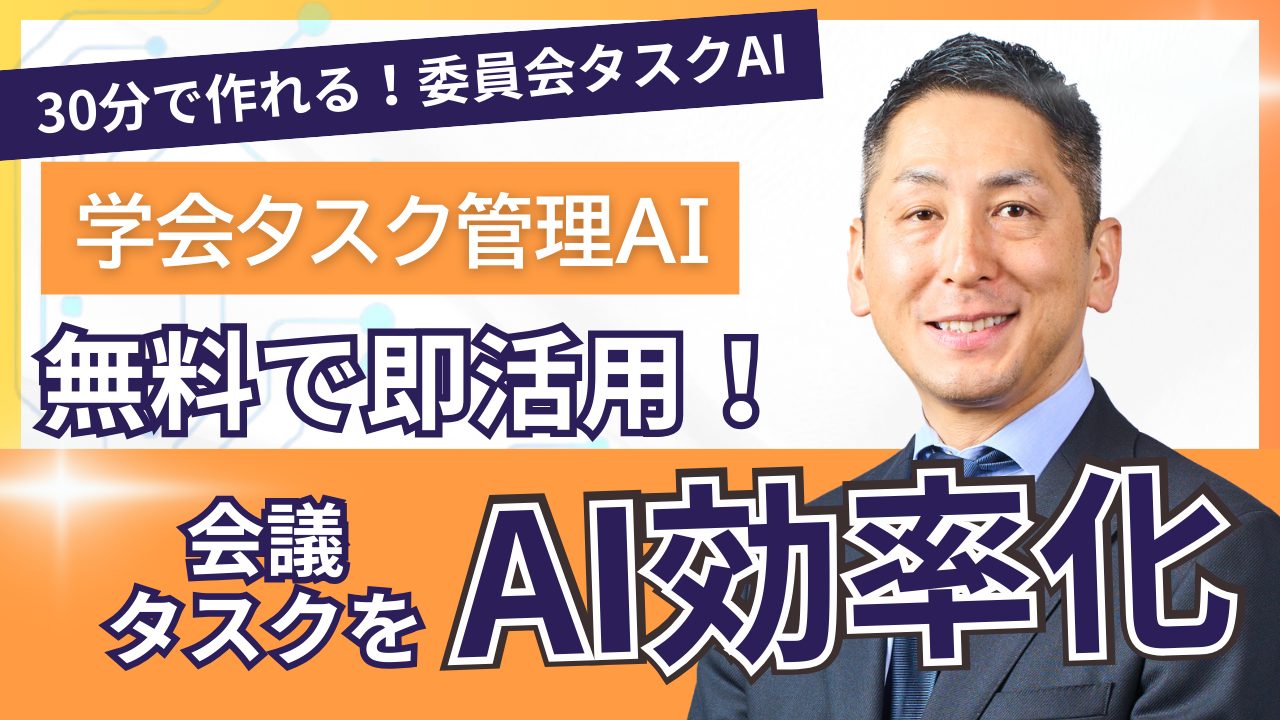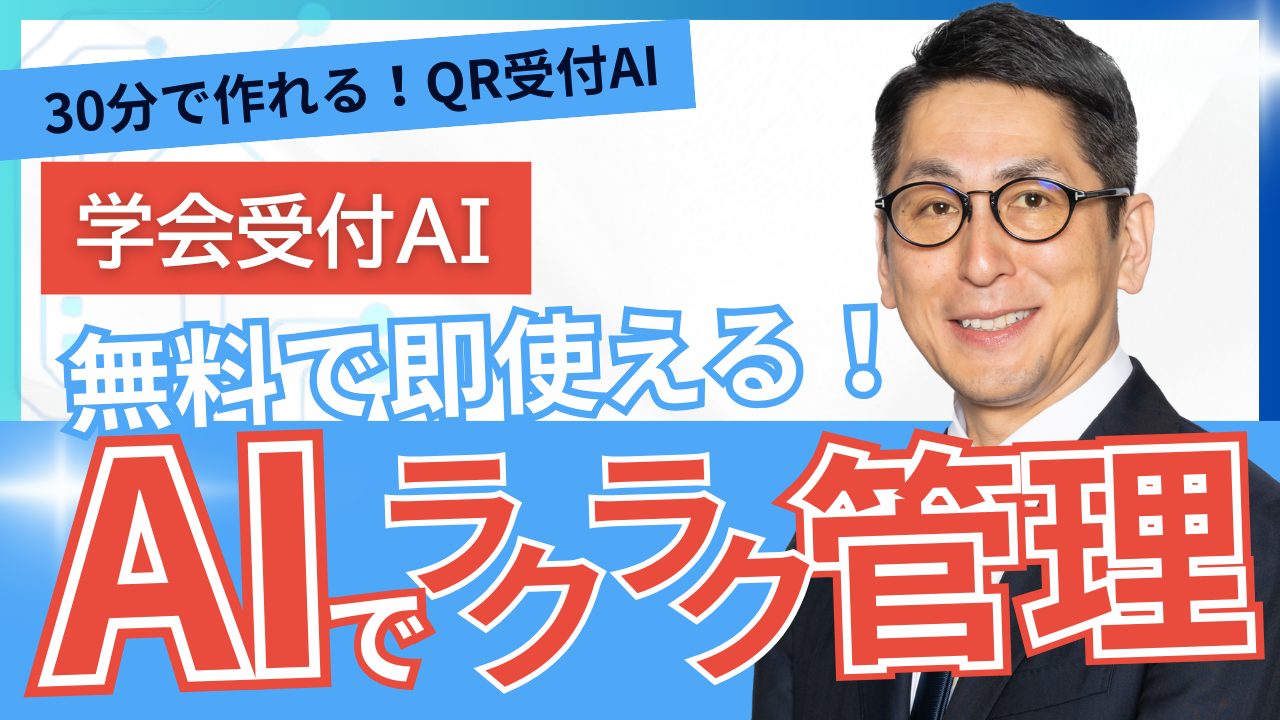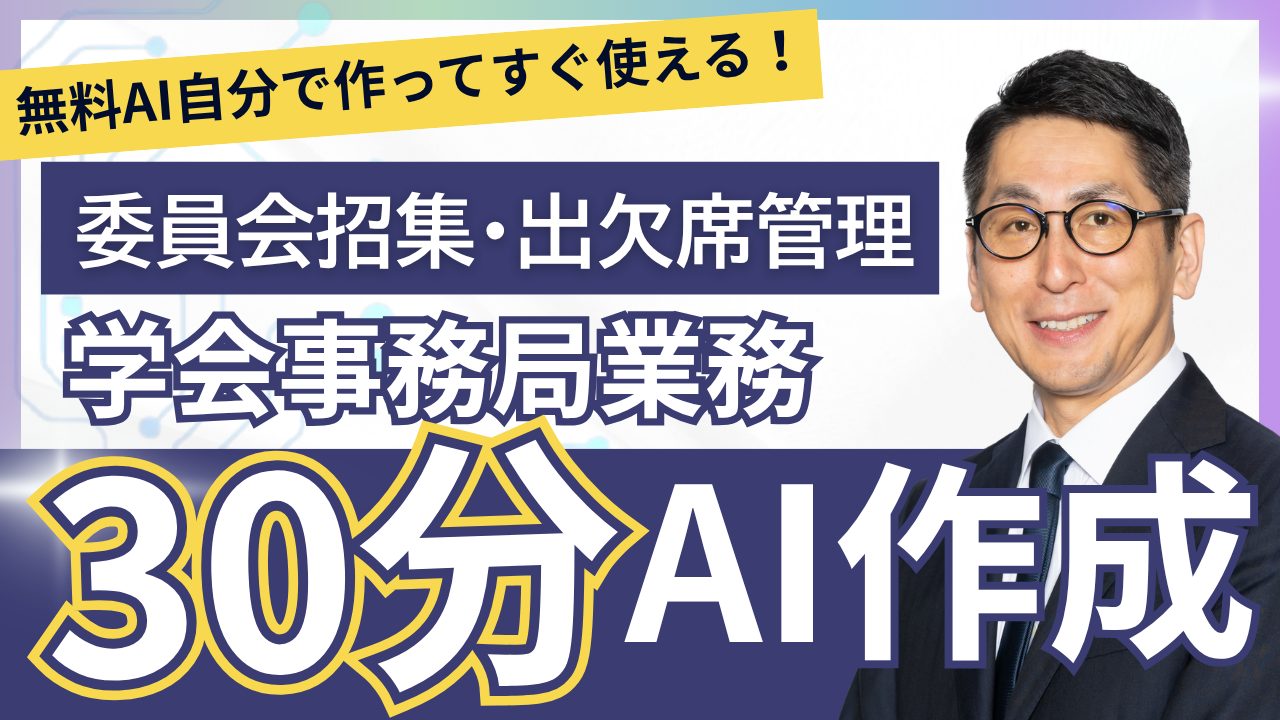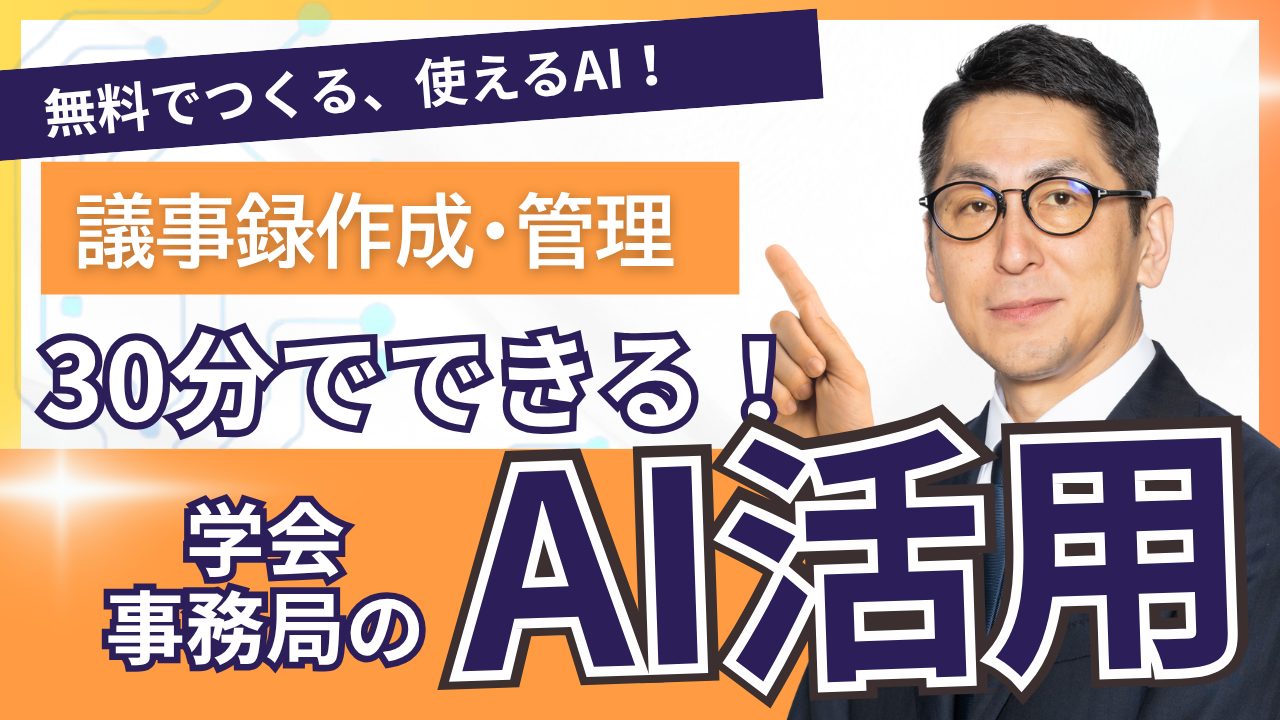ZoomťÖćšŅ°„Āę„Āä„ĀĎ„āčťü≥ťüŅŤ®≠Ť®ą„Ā®šľöŚ†ī„Éě„ā§„āĮŤ®≠Śģö„ĀģŚüļśú¨„ÄÄ„ÄúšľĚ„āŹ„āčŚ£į„ĀĆŚ≠¶šľö„ā팧ȄĀą„āč„Äú
2025ŚĻī08śúą19śó•
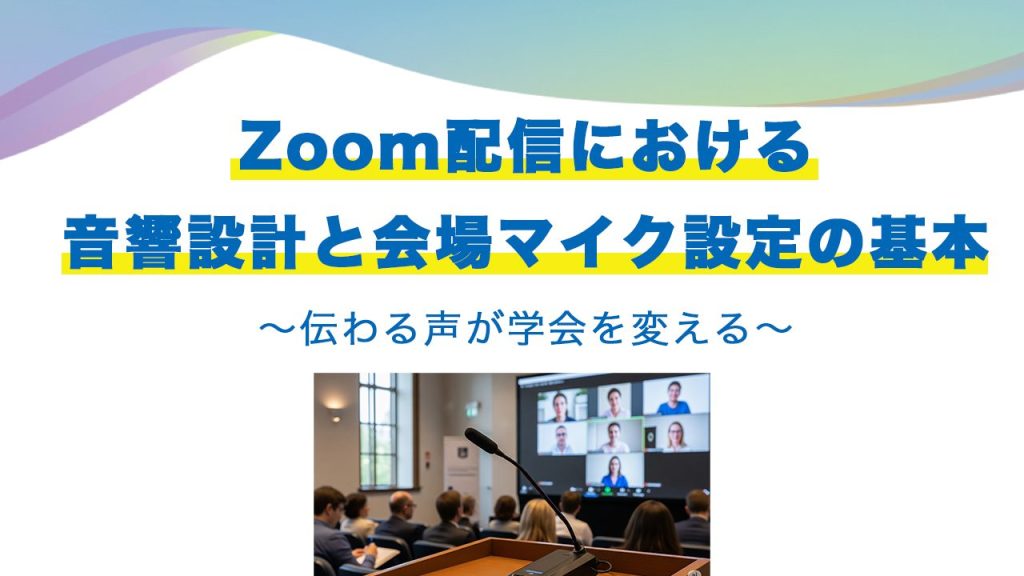
„ĀĮ„Āė„āĀ„Āę„ÄÄŚ≠¶šľöťĀčŚĖ∂„Āę„Āä„ĀĎ„āčťü≥Ś£į„ĀģŤ≥™„ĀĆŚŹāŚä†ŤÄÖśļÄŤ∂≥Śļ¶„āíśĪļŚģö„Ā•„ĀĎ„āč
ŤŅĎŚĻī„ÄĀ„ā™„É≥„É©„ā§„É≥„āĄ„ÉŹ„ā§„ÉĖ„É™„ÉÉ„ÉČŚĹĘŚľŹ„Āę„āą„āčŚ≠¶šľöťĖčŚā¨„ĀĆšłÄŤą¨ŚĆĖ„Āó„ÄĀZoom„Ā™„Ā©„ĀģšľöŤ≠į„ÉĄ„Éľ„Éę„ĀĮŚ≠¶Ť°ďÁēĆ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶šłćŚŹĮś¨†„Ā™Ś≠ėŚú®„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„ÄāŚ≠¶šľöťĀčŚĖ∂„Āęśźļ„āŹ„āčÁßĀ„Āü„Ā°„ĀĆśó•ŚłłÁöĄ„ĀęŤÄ≥„Āę„Āô„āč„Āģ„ĀĮ„ÄĀ„Äéťü≥Ś£į„ĀĆŤĀě„Ā挏Ė„āä„Āę„ĀŹ„ĀŹ„Ā¶ŚÜÖŚģĻ„ĀĆť†≠„ĀęŚÖ•„āČ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„ÄŹ„āĄ„ÄéťÄĒšł≠„Āß„ÉŹ„ā¶„É™„É≥„āį„ĀĆŤĶ∑„Āć„Ā¶ťõÜšł≠„ĀĆťÄĒŚąá„āĆ„Āü„ÄŹ„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀģŚ£į„Āß„Āô„Äā
„Āď„ĀÜ„Āó„ĀüśäÄŤ°ďÁöĄ„Ā™„Éą„É©„ÉĖ„Éę„ĀĆť†ĽÁôļ„Āô„āčÁíįŚĘÉ„Āß„ĀĮ„ÄĀ„Āõ„Ā£„Āč„ĀŹ„ĀģÁ†ĒÁ©∂ÁôļŤ°®„āāŚćĀŚąÜ„Āꚾ̄āŹ„āČ„Āö„ÄĀŚÜÖŚģĻ„ĀģŤ≥™„Ā®ŚźĆÁ≠Č„Āč„ĀĚ„āĆšĽ•šłä„Āęťü≥ťüŅÁíįŚĘÉ„ĀĆťá捶Ė„Āē„āĆ„āčŚā匟τĀę„Āā„āä„Āĺ„Āô„ÄāÁČĻ„Āę„ÉŹ„ā§„ÉĖ„É™„ÉÉ„ÉČŚĹĘŚľŹ„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆšľöŚ†ī„ĀģŤá®Ś†īśĄü„āí„ā™„É≥„É©„ā§„É≥ŚŹāŚä†ŤÄÖ„Āę„ĀĄ„Āč„ĀęŚĪä„ĀĎ„āč„Āč„Äć„ĀĆŚ§ß„Āć„Ā™Ť™≤ť°Ć„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„ÄāšľöŚ†īŚĀī„Āģ„Éě„ā§„āĮŤ®≠ŚģöšłÄ„Ā§„Āß„ÄĀ„ā™„É≥„É©„ā§„É≥ŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀģšĹďť®ď„ĀĮŚäáÁöĄ„ĀꌧȄāŹ„āä„Āĺ„Āô„ÄāŚ≠¶šľöťĀčŚĖ∂„Āęśźļ„āŹ„āčšł≠„Āß„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„Āģ„āĻ„āŅ„ÉÉ„Éē„ĀĮťĀ©Śąá„Ā™ťü≥ťüŅŤ®≠Ť®ą„Āę„āą„Ā£„Ā¶ŚŹāŚä†ŤÄÖ„Āč„āČ„ĀģŤ©ēšĺ°„ĀĆś†ľśģĶ„ĀꌟϚłä„Āó„ĀüÁĶĆť®ď„āíšĹēŚļ¶„āāťáć„Ā≠„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
śú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮ„ÄĀŚŹāŚä†ŤÄÖ„Āę„ÄĆ„Āĺ„ĀüŚŹāŚä†„Āó„Āü„ĀĄ„Äć„Ā®śÄĚ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā†„ĀĎ„āčŚ≠¶šľöťĀčŚĖ∂„āíŚģüÁŹĺ„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„ÄĀZoomťÖćšŅ°śôā„Āģťü≥ťüŅŤ®≠Ť®ą„Ā®„Éě„ā§„āĮŤ®≠Śģö„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŚģüŤ∑ĶÁöĄ„Ā™„Éé„ā¶„ÉŹ„ā¶„āíšĹďÁ≥ĽÁöĄ„Āę„Ā䚾̄Āą„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„ÄźŚŹāŤÄÉ„ÄĎ
śú¨ťÄ£ŤľČ„ā∑„É™„Éľ„āļ„ĀģŤ®ėšļč„āāŚŹāŤÄÉ„Āę„Āó„Ā¶„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā
„ÉĽ„ÄĆZoomśīĽÁĒ®„ĀߌģüÁŹĺ„Āô„āčśĖį„Āó„ĀĄŚ≠¶šľöšľöŤ≠į„āĻ„āŅ„ā§„Éę„ÄúŚĮ卩Ī„Ā®ŚŹāŚä†„āíśĒĮ„Āą„āč„ÉŹ„ā§„ÉĖ„É™„ÉÉ„ÉČ„ĀģšĽēÁĶĄ„ĀŅ„Äú„Äć
1. šľöŚ†īŤ®≠Ť®ą„Ā®„Éě„ā§„āĮťĀłŚģö„ÉĽťÖćÁĹģ„ĀĆŚďĀŤ≥™„Āģ„āę„āģ
1.1 „Éě„ā§„āĮ„ĀģŚüļÁ§éÁü•Ť≠ė„Ā®Á®ģť°ěŚą•śīĽÁĒ®ś≥ē
ťü≥ťüŅŤ®≠Ť®ą„ĀģÁ¨¨šłÄś≠©„ĀĮ„ÄĀÁõģÁöĄ„Ā®ÁíįŚĘÉ„ĀęśúÄťĀ©„Ā™„Éě„ā§„āĮ„āíťĀł„Ā∂„Āď„Ā®„Āß„Āô„Äā„ÄĆ„Ā©„Āģ„Éě„ā§„āĮ„āāŚźĆ„Āė„Äć„Ā®ŤÄÉ„Āą„ĀĆ„Ā°„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀŚģü„ĀĮÁĒ®ťÄĒ„Āę„āą„Ā£„Ā¶Ś§ß„Āć„ĀŹśÄߍÉĹ„ĀĆÁēį„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
(1) „ÉÄ„ā§„Éä„Éü„ÉÉ„āĮ„Éě„ā§„āĮ
„ÉÄ„ā§„Éä„Éü„ÉÉ„āĮ„Éě„ā§„āĮ„ĀĮť†Ďšłą„Āß„ÄĀŚ§ßťü≥ťáŹ„Āę„āāŤÄź„Āą„āčÁČĻśÄß„āíśĆĀ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ÄāśľĒŚŹį„Āß„ĀģŤ¨õśľĒ„āĄ„ÄĀšľöŚ†īŚÜÖ„ĀģŤ≥™ÁĖĎŚŅúÁ≠Ē„ĀęťĀ©„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀťõĽśļźšłćŤ¶Ā„ĀßśČĪ„ĀĄ„āĄ„Āô„ĀĄ„Āģ„ĀĆť≠ÖŚäõ„Āß„Āô„Äā„Āü„Ā†„Āó„ÄĀÁīį„Āč„Ā™ťü≥„Āģ„Éč„É•„āĘ„É≥„āĻ„ĀĮśčĺ„ĀĄ„Āę„ĀŹ„ĀĄťĚĘ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
„ÉĽhttps://amzn.asia/d/7tmGXAj
(2) „ā≥„É≥„Éá„É≥„āĶ„Éľ„Éě„ā§„āĮ
„ā≥„É≥„Éá„É≥„āĶ„Éľ„Éě„ā§„āĮ„ĀĮśĄüŚļ¶„ĀĆťĚ쌳ł„Āęťęė„ĀŹ„ÄĀŤ¨õśľĒŤÄÖ„ĀģŚ£į„ĀģŚĺģÁīį„Ā™Ť°®ÁŹĺ„Āĺ„Āßťģģśėé„Āꌏéťü≥„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äāťü≥ś•Ĺ„Éõ„Éľ„Éę„Āß„ĀģťĆ≤ťü≥„Ā™„Ā©„Āę„āāšĹŅ„āŹ„āĆ„āčťęėŚďĀŤ≥™„Ā™„Éě„ā§„āĮ„Āß„Āô„ÄāšłÄŤą¨ÁöĄ„Āę„ÄĀŚ§ĖťÉ®„Āč„āČ„ĀģťõĽśļźšĺõÁĶ¶Ôľą„Éē„ā°„É≥„āŅ„ɆťõĽśļźÔľČ„āíŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Āô„āč„āŅ„ā§„Éó„ĀĆŚ§ö„ĀĄ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀUSBśé•Á∂ö„āĄšĻĺťõĽśĪ†„Āę„āą„āčŚÜÖŤĒĶťõĽśļź„āŅ„ā§„Éó„āāŚ≠ėŚú®„Āó„ÄĀšĹŅÁĒ®ÁíįŚĘÉ„ĀęŚŅú„Āė„ĀüťĀłśäě„ĀĆŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„Äā
„Āü„Ā†„Āó„ÄĀśßčťÄ†„ĀĆÁĻäÁīį„Ā™„Āü„āĀśĻŅśįó„āĄŤ°ĚśíÉ„Āę„ĀĮŚľĪ„ĀŹ„ÄĀŚŹĖ„āäśČĪ„ĀĄ„Āę„ĀĮŚćĀŚąÜ„Ā™ś≥®śĄŹ„ĀĆśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
„ÉĽhttps://amzn.asia/d/aZHykTH
(3) „ÉĒ„É≥„Éě„ā§„āĮ
„É©„Éô„É™„āĘ„Éě„ā§„āĮÔľą„ÉĒ„É≥„Éě„ā§„āĮԾȄĀĮŤ•üŚÖÉ„ĀęŤ£ÖÁĚÄ„Āô„āč„āŅ„ā§„Éó„Āß„ÄĀŤ¨õśľĒŤÄÖ„ĀĆŚčē„ĀćŚõě„Ā£„Ā¶„āāŚģČŚģö„Āó„Āüťü≥Ś£į„āíÁĘļšŅĚ„Āß„Āć„Āĺ„Āô„Äā„ÉŹ„É≥„āļ„Éē„É™„Éľ„Ā™„Āģ„Āß„ÄĀÁČĻ„ĀęŤļęśĆĮ„āäśČčśĆĮ„āä„āíšļ§„Āą„ĀüÁôļŤ°®„āĻ„āŅ„ā§„Éę„ĀģśĖĻ„Āę„ĀĮś¨†„Āč„Āõ„Āĺ„Āõ„āď„Äā„É܄ɨ„ÉďÁē™ÁĶĄ„ĀߌáļśľĒŤÄÖ„ĀĆŤļę„Āę„Ā§„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄĀ„āą„ĀŹŤ¶č„Āč„ĀĎ„āč„āŅ„ā§„Éó„Āß„Āô„Äā
„ÉĽhttps://amzn.asia/d/cJzjTax
(4) „Éź„ā¶„É≥„ÉÄ„É™„Éľ„Éě„ā§„āĮ
„Éź„ā¶„É≥„ÉÄ„É™„Éľ„Éě„ā§„āĮ„ĀĮ„ÉÜ„Éľ„ÉĖ„Éꍮ≠ÁĹģŚěč„Āß„ÄĀ„ÉĎ„Éć„Éę„Éá„ā£„āĻ„āę„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥„āĄŤ§áśēįšļļ„Āß„ĀģŤ®éŤęĖ„ĀꌮĀŚäõ„āíÁôļśŹģ„Āó„Āĺ„Āô„ÄāšłÄŚŹį„ĀߌļÉÁĮĄŚõ≤„āí„āę„Éź„Éľ„Āß„Āć„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„ā≥„āĻ„ÉąŚäĻÁéá„āāŤČĮŚ•Ĺ„Āß„Āô„Äā
„ÉĽhttps://amzn.asia/d/eBIRfmb
(5) „ā∑„Éß„ÉÉ„Éą„ā¨„É≥„Éě„ā§„āĮ
„ā∑„Éß„ÉÉ„Éą„ā¨„É≥„Éě„ā§„āĮ„ĀĮÁČĻŚģöśĖĻŚźĎ„Āģťü≥„āíťõÜšł≠ÁöĄ„Āęśčĺ„ĀÜśĆጟϜÄßÔľąťü≥„āíśčĺ„ĀÜśĖĻŚźĎśÄßԾȄāíśĆĀ„Ā°„ÄĀŚĎ®Śõ≤„ĀģťõĎťü≥„āíŚäĻśěúÁöĄ„Āęśéíťô§„Āß„Āć„Āĺ„Āô„ÄāšľöŚ†ī„ĀĆť®í„ĀĆ„Āó„ĀĄÁíįŚĘÉ„Āß„ĀģŚŹéťĆ≤„ĀęťĀ©„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
„ÉĽhttps://amzn.asia/d/2f7ad84
„ÄźŚŹāŤÄÉ„ÄĎ
„ÄźŚąĚŚŅÉŤÄÖŚźĎ„ĀĎ„ÄĎÁĒ®ťÄĒŚą•„Āä„Āô„Āô„āĀ„Éě„ā§„āĮÔľĀťü≥ťüŅ„Āģ„Éó„É≠„ĀĆŚüļśú¨„ĀģťĀł„Ā≥śĖĻ„āíŤß£Ť™¨ÔĹúJATO
‚Č™online shop‚Čę
https://www.jato.jp/magazine/audio/microphone-choice
„Éě„ā§„āĮ„Ā®„ĀĮÔľü4„Ā§„ĀģÁ®ģť°ě„Ā®śĆጟϜÄß„ĀģÁČĻśÄßÔĹú„Éě„āĶ„ÉĄ„Ɇ
https://note.com/masatsumu/n/n226a9b0f3d99
ťü≥ťüŅś©üŚô®„ĀģŚüļÁ§éÁü•Ť≠ėÔĹúśó•śú¨ťü≥ťüŅŚ≠¶šľö
https://www.asj.gr.jp
1.2 šľöŚ†īŤ¶Źś®°„ĀęŚŅú„Āė„Āü„Éě„ā§„āĮťÖćÁĹģ„ĀģśúÄťĀ©ŚĆĖ
(1)ŚįŹŤ¶Źś®°šľöŚ†īÔľą30ŚźćšĽ•šłč„ĀģšľöŤ≠įŚģ§„Ā™„Ā©ÔľČ
ŚįŹ„Āē„Ā™šľöŚ†ī„Āß„ĀĮ„ÄĀś©üśĚź„Āģśēį„āíśäĎ„Āą„Ā§„Ā§ŚäĻśěúÁöĄ„Ā™ŚŹéťü≥„āíŚģüÁŹĺ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆťá捶Ā„Āß„Āô„ÄāŚćďšłäŚěč„āĄ„Éź„ā¶„É≥„ÉÄ„É™„Éľ„Éě„ā§„āĮ„āíšľöŤ≠į„ÉÜ„Éľ„ÉĖ„Éę„Āģšł≠Ś§ģ„Āꍮ≠ÁĹģ„Āó„ÄĀŤ¨õśľĒŤÄÖ„Āę„ĀĮ„É©„Éô„É™„āĘ„Éě„ā§„āĮ„āíŤ£ÖÁĚÄ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā†„ĀŹ„Āģ„ĀĆŚüļśú¨„ÉĎ„āŅ„Éľ„É≥„Āß„Āô„Äā
„Āď„Āģťöõ„ÄĀ„āĻ„ÉĒ„Éľ„āę„Éľ„Ā®„Éě„ā§„āĮ„ĀģŤ∑ĚťõĘ„āíśúÄšĹé2„É°„Éľ„Éą„Éꚼ•šłäÁĘļšŅĚ„Āó„ÄĀťü≥„ĀģŚõě„āäŤĺľ„ĀŅ„āíťė≤„ĀźťÖćÁĹģ„āíŚŅÉ„ĀĆ„ĀĎ„Āĺ„Āô„ÄāÁĶĆť®ďšłä„ÄĀŤ∑ĚťõĘ„ĀĆšłćŚćĀŚąÜ„Ā†„Ā®„ÉŹ„ā¶„É™„É≥„āįÔľą„ā≠„Éľ„É≥„Ā®„ĀĄ„ĀÜšłćŚŅę„Ā™ťü≥ԾȄĀĆÁôļÁĒü„Āó„āĄ„Āô„ĀŹ„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
(2)Ś§ßŤ¶Źś®°šľöŚ†īÔľą100ŚźćšĽ•šłä„Āģ„Éõ„Éľ„Éę„Ā™„Ā©ÔľČ
Ś§ß„Āć„Ā™šľöŚ†ī„Āß„ĀĮ„ÄĀśľĒŚŹį„Āę„āį„Éľ„āĻ„Éć„ÉÉ„āĮŚěč„Āģ„Éě„ā§„āĮÔľą„ā¨„ÉĀ„Éß„ā¶„Āģť¶ĖÔľągoose neckԾȄĀģ„āą„ĀÜ„ĀęÁīįťē∑„ĀŹśõ≤„Āí„āČ„āĆ„āčśĒĮśüĪ„āíśĆĀ„Ā§„Éě„ā§„āĮ„Āģ„Āď„Ā®ÔľČ„ā퍮≠ÁĹģ„Āó„ÄĀŤ≥™ŚēŹŤÄÖÁĒ®„Āę„ĀĮŤ§áśēįśú¨„Āģ„ÉĮ„ā§„ɧ„ɨ„āĻ„ÉŹ„É≥„ÉČ„Éě„ā§„āĮ„āíÁĒ®śĄŹ„Āó„Āĺ„Āô„ÄāšľöŚ†ī„ĀģŚ••„Āĺ„Āßťü≥„āíŚĪä„ĀĎ„āč„Āü„āĀ„ÄĀ„Éá„ā£„ɨ„ā§„āĻ„ÉĒ„Éľ„āę„ÉľÔľąťü≥„ĀģťĀÖŚĽ∂„ā퍙Ņśēī„Āô„āč„āĻ„ÉĒ„Éľ„āę„ɾԾȄĀģŤ®≠ÁĹģ„āāś§úŤ®é„Āó„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā
„Āď„Āď„Āßś≥®śĄŹ„Āó„Āü„ĀĄ„Āģ„ĀĮ„ÄĀ„ÉŹ„ā¶„É™„É≥„āįťė≤ś≠Ę„Āģ„Āü„āĀ„Āģ„āĻ„ÉĒ„Éľ„āę„Éľ„Ā®„ĀģšĹćÁĹģťĖĘšŅā„Āß„Āô„Äā„Éě„ā§„āĮ„ĀģśĆጟϜÄß„āíśīĽ„Āč„Āó„ÄĀ„āĻ„ÉĒ„Éľ„āę„Éľ„Āģťü≥„āíÁõīśé•śčĺ„āŹ„Ā™„ĀĄŤßíŚļ¶„Āß„ĀģŤ®≠ÁĹģ„ĀĆŤāĚŤ¶Ā„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äāťü≥ťüŅ„ĀģŚįāťĖÄŚģ∂„ĀĮ„ÄĆ„Éě„ā§„āĮ„ĀĮ„āĻ„ÉĒ„Éľ„āę„Éľ„ĀęŤÉĆ„ā팟τĀĎ„āč„āą„ĀÜ„Āꍮ≠ÁĹģ„Āô„āč„Äć„Ā®„āą„ĀŹŤ°®ÁŹĺ„Āó„Āĺ„Āô„Äā
2. „ÉŹ„ā¶„É™„É≥„āį„ÉĽťü≥ťáŹŚ∑ģ„ÉĽ„Éě„Éę„ÉĀ„Éě„ā§„āĮťĀčÁĒ®„ĀģŚ∑•Ś§ę
2.1 „ÉŹ„ā¶„É™„É≥„āįŚĮĺÁ≠Ė„Ā®„ā®„ā≥„Éľ„ā≠„É£„É≥„āĽ„É™„É≥„āįśäÄŤ°ď
„ÉŹ„ā¶„É™„É≥„āį„ĀĮŚ≠¶šľöťĀčŚĖ∂ŤÄÖ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶śúÄ„āāťĀŅ„ĀĎ„Āü„ĀĄ„Éą„É©„ÉĖ„Éę„ĀģšłÄ„Ā§„Āß„Āô„ÄāŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀĆť©ö„ĀĄ„Ā¶ťõÜšł≠„āíšĻĪ„Āē„āĆ„āč„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀś©üŚô®„ĀęśźćŚā∑„āíšłé„Āą„ā茏ĮŤÉĹśÄß„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
Śüļśú¨ÁöĄ„Ā™ŚĮĺÁ≠Ė„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀ„Éě„ā§„āĮ„Ā®„āĻ„ÉĒ„Éľ„āę„Éľ„ĀģÁČ©ÁźÜÁöĄŤ∑ĚťõĘ„āíŚćĀŚąÜ„ĀęÁĘļšŅĚ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆÁ¨¨šłÄ„Āß„Āô„ÄāŚćėšłÄśĆጟϜÄß„Éě„ā§„āĮÔľąšłÄśĖĻŚźĎ„Āč„āČ„Āģťü≥„āíšłĽ„Āęśčĺ„ĀÜ„Éě„ā§„āĮԾȄāíšĹŅÁĒ®„Āó„ÄĀ„āĻ„ÉĒ„Éľ„āę„Éľ„Āģťü≥„āíÁõīśé•śčĺ„āŹ„Ā™„ĀĄťÖćÁĹģ„āíŚĺĻŚļē„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Éü„ā≠„āĶ„Éľ„Āģ„ā§„ā≥„É©„ā§„ā∂„Éľś©üŤÉĹ„āíśīĽÁĒ®„Āó„ÄĀ„ÉŹ„ā¶„É™„É≥„āį„ĀĆŤĶ∑„Āć„āĄ„Āô„ĀĄÁČĻŚģö„ĀģŚĎ®ś≥ĘśēįŚłĮÔľąťÄöŚłł„ĀĮ2,000Hz„Äú4,000HzšĽėŤŅĎԾȄāíšļą„āĀśäĎŚą∂„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„Āď„Ā®„āāŚäĻśěúÁöĄ„Āß„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀZoom„Āģ„ÄĆ„ā®„ā≥„Éľ„ā≠„É£„É≥„āĽ„É™„É≥„āį„Äćś©üŤÉĹ„āíśúČŚäĻ„Āę„Āó„ÄĀťÖćšŅ°„Éę„Éľ„Éó„āíťė≤„Āź„ÄĆ„Éě„ā§„Éä„āĻ„ÉĮ„É≥„Ä据≠ŚģöÔľąšľöŚ†ī„Āģ„āĻ„ÉĒ„Éľ„āę„Éľ„Āč„āČZoom„Āģťü≥Ś£į„āíťô§Ś§Ė„Āô„ā荮≠ŚģöԾȄāāŚŅė„āĆ„Āö„ĀꍰƄĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
Śģüťöõ„ĀģÁŹĺŚ†ī„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆ„ÉÜ„āĻ„Éąśôā„ĀĮŚēŹť°Ć„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āģ„Āęśú¨Áē™„Āß„ÉŹ„ā¶„É™„É≥„āį„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āĪ„Éľ„āĻ„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„āĆ„ĀĮšľöŚ†ī„Āęšļļ„ĀĆŚÖ•„āč„Āď„Ā®„Āßťü≥„ĀģŚŹćťüŅÁČĻśÄß„ĀĆŚ§Č„āŹ„āč„Āü„āĀ„Āß„Āô„Äā„ĀĚ„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āā„āĆ„ĀįŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀĆŚÖ•„Ā£„ĀüÁä∂śÖč„Āß„Āģ„É™„ÉŹ„Éľ„āĶ„Éę„ā퍰ƄĀÜ„Āď„Ā®„āí„ĀäŚčß„āĀ„Āó„Āĺ„Āô„Äā
ťĖčśľĒŚČć„Āę„āą„ĀŹŤ¶č„Āč„ĀĎ„āč„ÄĆ„ÉĀ„āß„ÉÉ„āĮ„Äā„ÉĀ„āß„ÉÉ„āĮ„Äā„Āü„Ā†„ĀĄ„Āĺ„Éě„ā§„āĮ„Āģ„ÉÜ„āĻ„Éąšł≠ÔľĀ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āʄɨ„Āß„Āô„Ā≠„Äā
„ÄźŚŹāŤÄÉ„ÄĎ
„ÉĽšļąÁģó3šłáŚÜÜ„Āß„Éó„É≠„ɨ„Éô„Éę„ĀģZoomŤá™ŚČćťÖćšŅ°ÔĹú„Āď„āĆ„Āč„āČ„ĀģŚ≠¶šľö.com
„ÉĽ„Éě„ā§„Éä„āĻ„ÉĮ„É≥Ť®≠ŚģöśĖĻś≥ēÔĹú„Āď„āĆ„Āč„āČ„ĀģŚ≠¶šľö.com
2.2 ťü≥ťáŹ„Éź„É©„É≥„āĻ„ĀģŤ™Ņśēī„Ā®„Éü„ā≠„ā∑„É≥„āį„Āģťá捶ĀśÄß
Ť§áśēį„Āģ„Éě„ā§„āĮ„ā팟ƜôāšĹŅÁĒ®„Āô„āčťöõ„ĀĮ„ÄĀťü≥ťáŹ„Éź„É©„É≥„āĻ„ĀģŤ™Ņśēī„ĀĆŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀģŤĀě„Āć„āĄ„Āô„Āē„ā팧߄Āć„ĀŹŚ∑¶ŚŹ≥„Āó„Āĺ„Āô„Äā„Éü„ā≠„āĶ„Éľ„āíšĹŅÁĒ®„Āó„Ā¶ŚźĄ„Éě„ā§„āĮ„Āģťü≥ťáŹ„āíŚÄ茹•„ĀꍙŅśēī„Āó„ÄĀ„Éė„ÉÉ„ÉČ„Éõ„É≥„Āß„É™„āĘ„Éę„āŅ„ā§„Ɇ„ÉĘ„Éč„āŅ„É™„É≥„āį„ā퍰ƄĀĄ„Ā™„ĀĆ„āČśúÄťĀ©„Ā™„Éź„É©„É≥„āĻ„ā퍶č„Ā§„ĀĎ„Āĺ„Āô„Äā
šļčŚČć„ĀęÁôļŤ°®ŤÄÖ„Āł„Éě„ā§„āĮšĹŅÁĒ®ś≥ēÔľąŚŹ£„Ā®„ĀģŤ∑ĚťõĘ„ĀĮ15„Äú20cm„ÄĀšłÄŚģö„ĀģŚ£įťáŹÁ∂≠śĆĀ„Ā™„Ā©ÔľČ„āí„ĀĒś°ąŚÜÖ„Āó„ÄĀŚĹďśó•„Āģťü≥ťáŹŚ§ČŚčē„āíśúÄŚįŹťôź„ĀęśäĎ„Āą„āč„Āď„Ā®„āāŚ§ßŚąá„Āß„Āô„Äā„ÄĆ„Éě„ā§„āĮ„ĀꌟτĀč„Ā£„Ā¶Ť©Ī„Āô„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŚüļśú¨„ā휥ŹŚ§Ė„Āꌧö„ĀŹ„ĀģśĖĻ„ĀĆŚŅė„āĆ„ĀĆ„Ā°„Āß„Āô„Āģ„Āß„ÄĀÁį°Śćė„Ā™„ɨ„āĮ„ÉĀ„É£„Éľ„ĀĆ„Āā„āč„Ā®ŚģČŚŅÉ„Āß„Āô„Äā
„ā™„É≥„É©„ā§„É≥ÁôļŤ®ÄŤÄÖ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„āā„ÄĀťĀ©Śąá„Ā™„Éü„É•„Éľ„ÉąÁģ°ÁźÜ„Ā®ťü≥ťáŹŤ™Ņśēī„āíŚŅÉ„ĀĆ„ĀĎ„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„ÄāŚŹłšľöŤÄÖ„ĀĆ„ā™„É≥„É©„ā§„É≥ŚŹāŚä†ŤÄÖ„Āģťü≥ťáŹ„ā퍙Ņśēī„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„ÄĀšļčŚČć„ĀęśďćšĹúśĖĻś≥ē„āíÁĘļŤ™ć„Āó„Ā¶„Āä„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĆťá捶Ā„Āß„Āô„Äā
3. Zoom„Āģťü≥Ś£įś©üŤÉĹ„Ā®„Éą„É©„ÉĖ„Éę„ā∑„É•„Éľ„ÉÜ„ā£„É≥„āį
3.1 Zoom„Āģ„ā™„Éľ„Éá„ā£„ā™Ť®≠Śģö„Ā®śúÄťĀ©ŚĆĖ
Zoom„Āę„ĀĮŚ§ö„ĀŹ„Āģťü≥Ś£įś©üŤÉĹ„ĀĆśź≠ŤľČ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀŚ≠¶šľöťÖćšŅ°„ĀęÁČĻ„Āęťá捶Ā„Ā™„Āģ„ĀĮ„ÄĆ„ā™„É™„āł„Éä„Éę„āĶ„ā¶„É≥„ÉČ„Äć„ĀģśúČŚäĻŚĆĖ„Āß„Āô„Äā„Āď„Āģś©üŤÉĹ„Āę„āą„āä„ÄĀťü≥ś•Ĺ„āĄś•ĹŚô®ťü≥„Ā™„Ā©„āāŚźę„āĀ„Ā¶ťęėŚďĀŤ≥™„ĀßťÖćšŅ°„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
„Éé„ā§„āļśäĎŚą∂„ɨ„Éô„Éę„ĀĮ„ÄĆšł≠„ÄćÁ®čŚļ¶„Āꍮ≠Śģö„Āó„ÄĀťĀéŚļ¶„Ā™Śá¶ÁźÜ„Āę„āą„āčťü≥Ś£į„ĀģšłćŤá™ÁĄ∂„Āē„āíťĀŅ„ĀĎ„Āĺ„Āô„Äā„ÄĆťęė„Äć„Āꍮ≠Śģö„Āô„āč„Ā®„ÄĀ„Āõ„Ā£„Āč„ĀŹ„ĀģŤá™ÁĄ∂„Ā™Ś£įŤ≥™„ĀĆśźć„Ā™„āŹ„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀšĹŅÁĒ®„Āô„āč„Éě„ā§„āĮ„Ā®„āĻ„ÉĒ„Éľ„āę„Éľ„ĀģťĀłśäě„āíś≠£ÁĘļ„ĀꍰƄĀĄ„ÄĀ„ÉÜ„āĻ„ÉąťÄöŤ©Ī„ĀßšļčŚČćÁĘļŤ™ć„āíśÄ†„āČ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„ĀĆťá捶Ā„Āß„Āô„Äā
Ś§ö„ĀŹ„ĀģÁĶĆť®ďŚČá„Āß„Āā„āč„ÄĀ„ÄĆŤ®≠Śģö„ĀĮŚģĆÁíß„Ā†„Ā£„Āü„Āģ„ĀęŚĹďśó•„ĀÜ„Āĺ„ĀŹ„ĀĄ„Āč„Ā™„ĀĄ„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āĪ„Éľ„āĻ„ĀĮ„ÄĀ„Āď„Āģ„ÉÜ„āĻ„ÉąťÄöŤ©Ī„āíÁúĀÁē•„Āó„Āü„Āď„Ā®„ĀĆŚéüŚõ†„Āß„Āô„Äā5ŚąÜÁ®čŚļ¶„ĀģÁį°Śćė„Ā™„ÉÜ„āĻ„Éą„Āß„āāŚ§ß„Āć„Ā™ťĀē„ĀĄ„ĀĆÁĒü„Āĺ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
3.2 „āą„ĀŹ„Āā„āčťü≥Ś£į„Éą„É©„ÉĖ„Éę„Ā®„ĀĚ„ĀģŤß£śĪļÁ≠Ė
Q: ťü≥Ś£į„ĀĆŚÖ®„ĀŹŤĀě„Āď„Āą„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„ĀĮÔľü
A: „Āĺ„ĀöZoomŚÜÖ„Āģ„ā™„Éľ„Éá„ā£„ā™Ť®≠Śģö„ÄĀś¨°„ĀęOSŚĀī„Āģťü≥Ś£įŤ®≠Śģö„āíÁĘļŤ™ć„Āó„ÄĀ„ā™„Éľ„Éá„ā£„ā™ś©üŚô®„Āģśé•Á∂öÁä∂śÖč„āā„ÉĀ„āß„ÉÉ„āĮ„Āó„Āĺ„Āô„ÄāśĄŹŚ§Ė„Āꌧö„ĀĄ„Āģ„ĀĆ„Éü„É•„Éľ„Éą„Éú„āŅ„É≥„Āģśäľ„ĀóŚŅė„āĆ„Āß„Āô„Äā„ÄĆťü≥Ś£į„ĀꌏāŚä†„Äć„Éú„āŅ„É≥„āíśäľ„ĀóŚŅė„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„āĪ„Éľ„āĻ„āāť†ĽÁĻĀ„Āꍶč„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„Äā
Q: ťü≥Ś£į„ĀĆťÄĒŚąá„āĆ„Āü„āäťĀÖŚĽ∂„ĀĆÁôļÁĒü„Āô„ā茆īŚźą„ĀĮÔľü
A: „Éć„ÉÉ„Éą„ÉĮ„Éľ„āĮÁíįŚĘÉ„ĀģŚģČŚģöŚĆĖ„ĀĆśúÄŚĄ™ŚÖą„Āß„Āô„ÄāŚŹĮŤÉĹ„Ā™ťôź„āäśúČÁ∑öLANśé•Á∂ö„āíšĹŅÁĒ®„Āó„ÄĀWi-FišĹŅÁĒ®śôā„ĀĮ5GHzŚłĮŚüü„āíťĀłśäě„Āó„Āĺ„Āó„āá„ĀÜ„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀšĽĖ„Āģ„āĘ„Éó„É™„āĪ„Éľ„ā∑„Éß„É≥„āíÁĶāšļÜ„Āó„Ā¶Zoom„ĀęŚá¶ÁźÜŤÉĹŚäõ„āíťõÜšł≠„Āē„Āõ„āč„Āď„Ā®„āāŚäĻśěúÁöĄ„Āß„Āô„Äā
Q: ťü≥Ś£į„ĀĆś≠™„āď„Ā†„āä„Éé„ā§„āļ„ĀĆś∑∑ŚÖ•„Āô„ā茆īŚźą„ĀĮÔľü
A: ŚÖ•Śäõ„ɨ„Éô„Éę„ĀĆťĀ錧߄Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Éü„ā≠„āĶ„Éľ„āĄ„ā™„Éľ„Éá„ā£„ā™„ā§„É≥„āŅ„Éľ„Éē„āß„Éľ„āĻ„ĀģŚÖ•Śäõ„ā≤„ā§„É≥„āíšłč„Āí„ÄĀś©üśĚź„Āģśé•Á∂öÁä∂śÖč„āāÁāĻś§ú„Āó„Ā¶„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā„ÄĆŚ§ß„Āć„Ā™Ś£į„Āߍ©Ī„Āõ„ĀįŤČĮ„ĀĄťü≥„Āę„Ā™„āč„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ™§Ťß£„ĀĆŚéüŚõ†„Ā®„Ā™„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā
Q: Ť§áśēįšļļ„ĀģŚ£į„Āģ„Éź„É©„É≥„āĻ„ĀĆśā™„ĀĄŚ†īŚźą„ĀĮÔľü
A: ŚźĄ„Éě„ā§„āĮ„ĀģśĄüŚļ¶Ť®≠Śģö„āíŚÄ茹•„ĀꍙŅśēī„Āó„ÄĀÁôļŤ®ÄŤÄÖ„Āę„ĀĮťĀ©Śąá„Ā™Ť∑ĚťõĘ„Āß„Éě„ā§„āĮ„āíšĹŅÁĒ®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā†„ĀŹ„āą„ĀÜś°ąŚÜÖ„Āó„Āĺ„Āô„Äā„ÉĎ„Éć„Éę„Éá„ā£„āĻ„āę„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥ŚĹĘŚľŹ„Āß„ĀĮ„ÄĀŚŹłšľöŤÄÖ„ĀĆťü≥ťáŹ„Éź„É©„É≥„āĻ„āíÁĘļŤ™ć„Āó„Ā™„ĀĆ„āČťÄ≤Ť°Ć„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚ§ßŚąá„Āß„Āô„Äā
„Āĺ„Ā®„āĀ„ÄÄŚ≠¶šľö„āČ„Āó„Āē„āíšŅĚ„Ā°„Ā™„ĀĆ„āČ„ÄĀťü≥ťüŅÁíįŚĘÉ„āíśēī„Āą„āč„Āü„āĀ„Āę
ZoomťÖćšŅ°„Āę„Āä„ĀĎ„āčťü≥ťüŅŤ®≠Ť®ą„Ā®„Éě„ā§„āĮŤ®≠Śģö„ĀĮ„ÄĀŚćė„Ā™„āčśäÄŤ°ďÁöĄ„Ā™Ť™≤ť°Ć„Āß„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Äā„Ā©„āĆ„ĀĽ„Ā©Áī†śôī„āČ„Āó„ĀĄÁ†ĒÁ©∂ŚÜÖŚģĻ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀťü≥„ĀĆťĀ©Śąá„ĀęŚĪä„Āč„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„ÄĀŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀģÁźÜŤß£„āāśĄüŚčē„āāŚćäśłõ„Āó„Ā¶„Āó„Āĺ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„āĆ„ĀĮ„ÄĀŚ≠¶šľö„ĀģśąźŚäü„Ā®Ś≠¶Ť°ďšļ§śĶĀ„ĀģŚįܜ̕„āíŚ∑¶ŚŹ≥„Āô„āč„ÄĀś•Ķ„āĀ„Ā¶ťá捶Ā„Ā™Ť¶ĀÁī†„Āß„Āô„Äā
ťĀ©Śąá„Ā™śļĖŚāô„Ā®Ś∑•Ś§ę„Āę„āą„āä„ÄĀ„ÉŹ„ā¶„É™„É≥„āį„āĄťü≥ťáŹŚ∑ģ„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüŚēŹť°Ć„ĀĮŤß£śĪļŚŹĮŤÉĹ„Āß„Āô„ÄāŚŹāŚä†ŤÄÖ„ĀģÁę茆ī„ĀęÁęč„Ā£„ĀüŚŅęťĀ©„Ā™ťü≥ťüŅÁíįŚĘÉ„ĀģśēīŚāô„ĀĮ„ÄĀŚÜÜśĽĎ„Ā™Ť≠įŤęĖ„āíšŅÉ„Āó„ÄĀŚ≠¶Ť°ďšļ§śĶĀ„ĀģŤ≥™„ā팟Ϛłä„Āē„Āõ„Āĺ„Āô„ÄāŚłł„ĀęśúÄśĖį„ĀģśÉÖŚ†Ī„Āę„āĘ„É≥„ÉÜ„Éä„ā팾Ķ„āä„ÄĀŚŅÖŤ¶Ā„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶ŚįāťĖÄŚģ∂„ĀģÁü•Ť¶č„āíśīĽÁĒ®„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆ„ÄĀšļčŚčôŚĪÄ„Āę„ĀĮśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āĺ„Āô„ÄāŚúįťĀď„Ā™„ÄĀ„ĀĚ„ĀģšłÄś≠©šłÄś≠©„ĀĆŚ≠¶šľö„ĀģśĖį„Āü„Ā™ŚŹĮŤÉĹśÄß„ā팹á„āäśčď„ĀŹŚäõ„Ā®„Ā™„āä„Āĺ„Āô„Äā
šľĚ„āŹ„āčŚ£į„ĀĆ„ÄĀŚ≠¶šľö„Āģśú™śĚ•„āíśčď„ĀŹŚäõ„Ā®„Ā™„āč„Āß„Āó„āá„ĀÜ„Äā