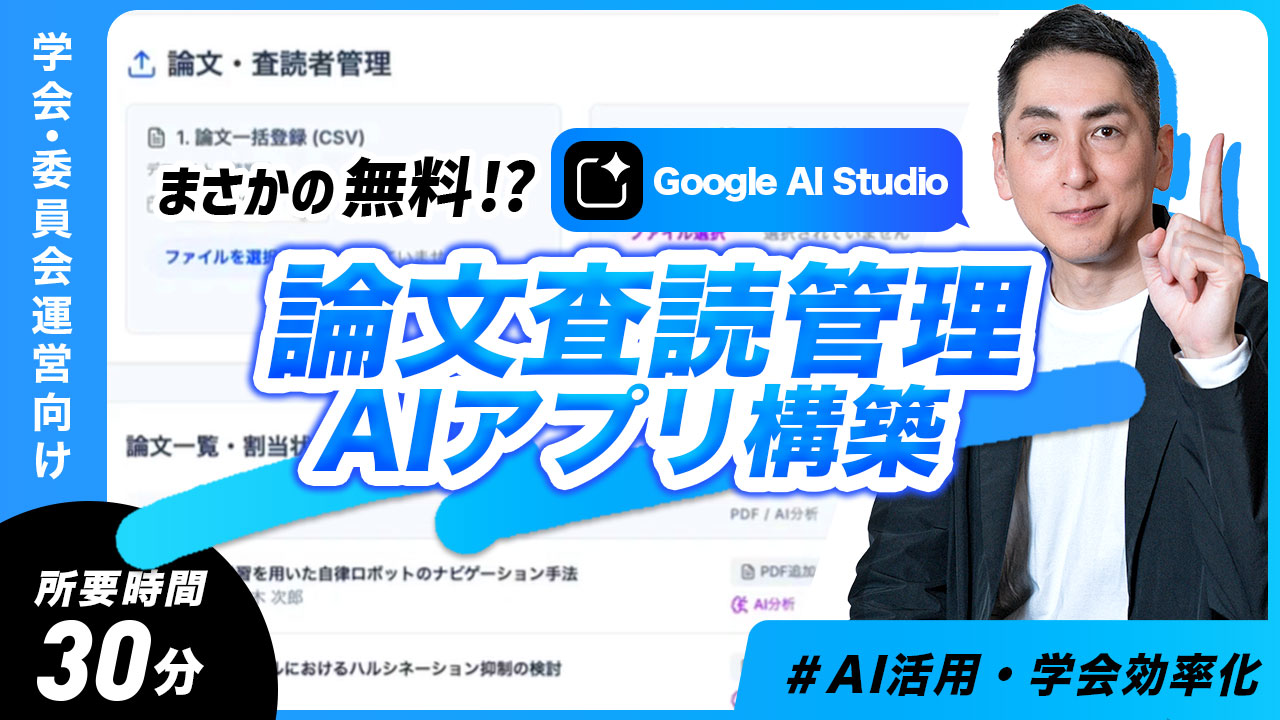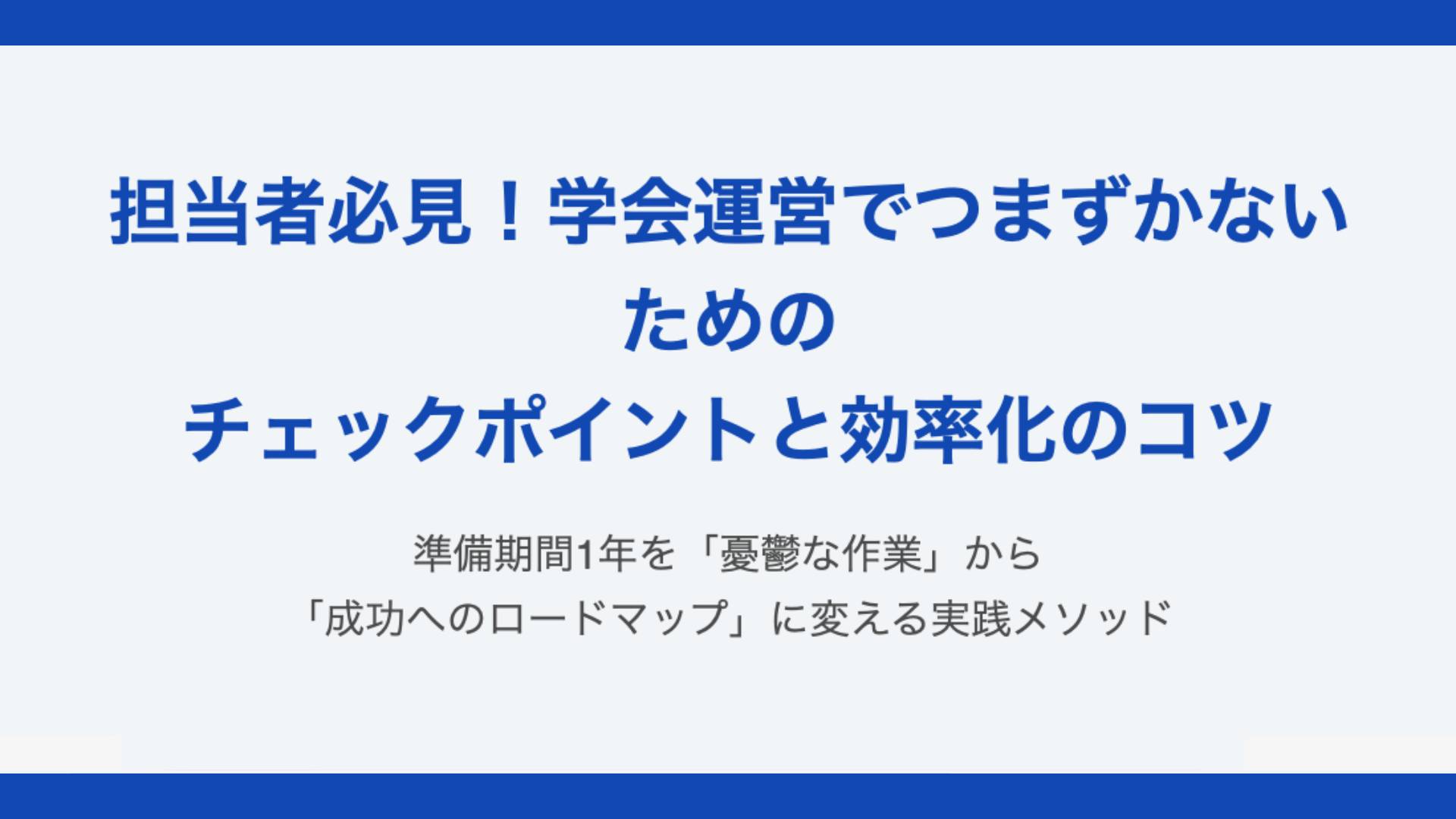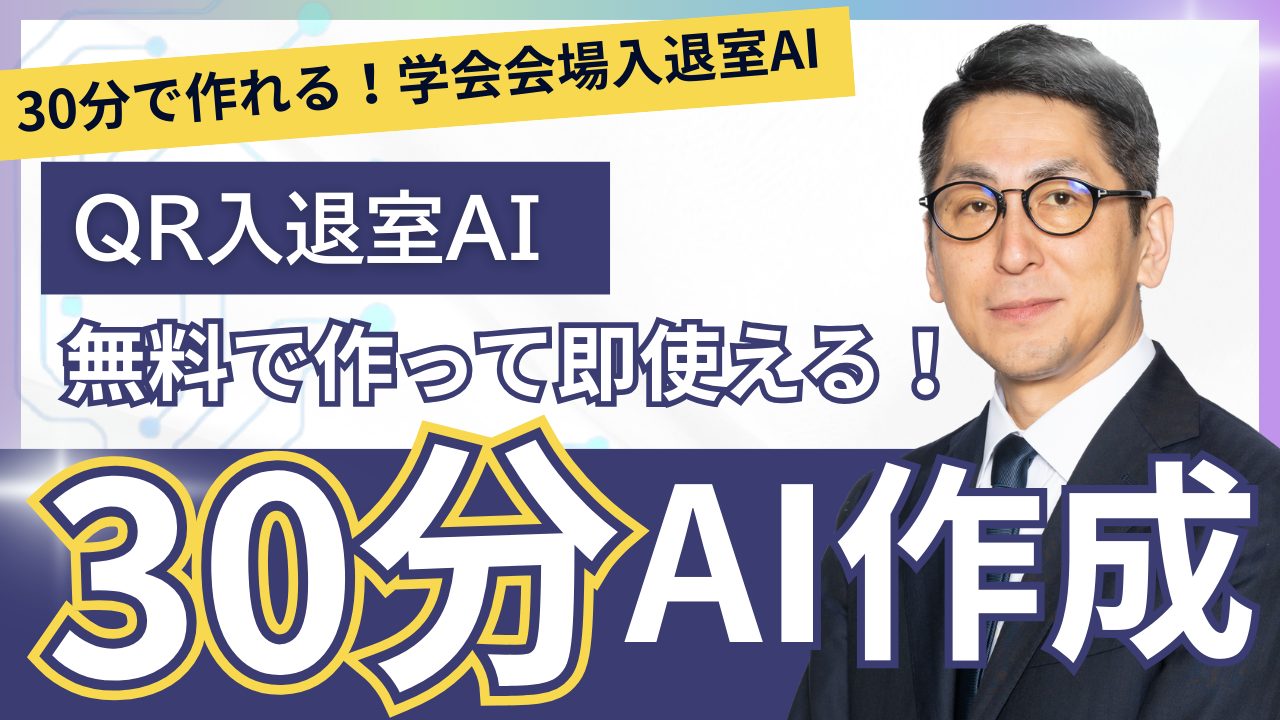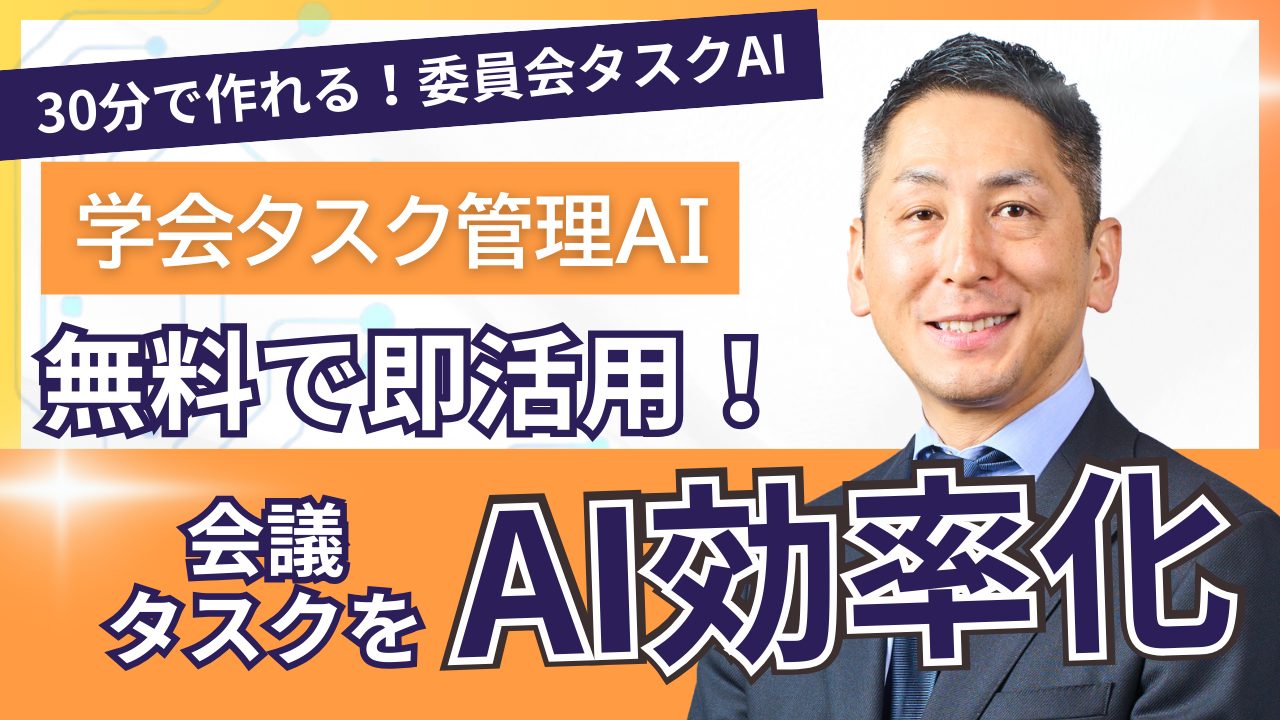ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چم‚’解و¶ˆï¼په††و»‘مپھه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®مپںم‚پمپ®وˆ¦ç•¥
2025ه¹´07وœˆ08و—¥

è؟‘ه¹´م€پن¸ه°ڈè¦ڈو¨،مپ®ه¦ن¼ڑم‚„ه›½éڑ›ن¼ڑè°مپ§مپ¯م€پéپ‹ه–¶مپ«وگ؛م‚ڈم‚‹م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپŒو·±هˆ»مپھèھ²é،Œمپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ن؛‹ه‹™ه±€مپ®ه¤ڑه؟™هŒ–م€پن¸چه®‰ه®ڑمپھن؛؛وگç¢؛ن؟م€پمپمپ—مپ¦è†¨ه¤§مپھو¥ه‹™é‡ڈمپ«م€په¤ڑمپڈمپ®ه¦è،“ه›£ن½“مپŒé م‚’و‚©مپ¾مپ›مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚é™گم‚‰م‚Œمپںمƒھم‚½مƒ¼م‚¹مپ®ن¸مپ§è³ھمپ®é«کمپ„ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶م‚’継ç¶ڑمپ—مپ¦مپ„مپڈمپںم‚پمپ«مپ¯م€پم€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چم‚’ن¹—م‚ٹè¶ٹمپˆم‚‹مپںم‚پمپ®ه…·ن½“çڑ„مپھه¯¾ç–مپ¨م€Œهٹ¹çژ‡çڑ„مپھه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶م€چمپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚ وœ¬è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€په¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ®èƒŒو™¯مپ¨èھ²é،Œم‚’وژکم‚ٹن¸‹مپ’م€په°‘ن؛؛و•°مپ§م‚‚ه††و»‘مپ«ه¦ن¼ڑم‚’éپ‹ه–¶مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®ه®ںè·µçڑ„مپھ解و±؛ç–م‚’解èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ«ç›´é¢مپ—مپ¦مپ„م‚‹éپ‹ه–¶و‹…ه½“者مپ®و–¹م€…مپ«مپ¨مپ£مپ¦م€پوœ¬è¨کن؛‹مپŒه…·ن½“çڑ„مپھمƒ’مƒ³مƒˆمپ¨مپھم‚‹مپ“مپ¨م‚’ç›®وŒ‡مپ—مپ¾مپ™م€‚
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ®çڈ¾çٹ¶مپ¨و¥ه‹™مپ®è² و‹…
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ¨مپ¯م€په¦ن¼ڑمپ®و؛–ه‚™مپ‹م‚‰ه½“و—¥éپ‹ه–¶م€پن؛‹ه¾Œه‡¦çگ†مپ«è‡³م‚‹مپ¾مپ§م€په؟…è¦پمپھن؛؛وگمپŒن¸چ足مپ—م€پو¥ه‹™éپ‚è،Œمپ«و”¯éڑœمپŒç”ںمپکمپ¦مپ„م‚‹çٹ¶و…‹م‚’وŒ‡مپ—مپ¾مپ™م€‚ه¤ڑمپڈمپ®ه¦ن¼ڑمپ§مپ¯م€په¤§ه¦م‚„ç ”ç©¶و©ںé–¢مپ®èپ·ه“،مپŒوœ¬و¥مپ¨ه…¼ن»»مپ§éپ‹ه–¶مپ«وگ؛م‚ڈمپ£مپںم‚ٹم€په¦ç”ںم‚¢مƒ«مƒگم‚¤مƒˆم‚„مƒœمƒ©مƒ³مƒ†م‚£م‚¢مپ«ن¾هکمپ—مپ¦مپ„م‚‹م‚±مƒ¼م‚¹مپŒه¤ڑمپڈ見م‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پمپ“م‚Œم‚‰مپ®ن؛؛وگمپ¯وµپه‹•çڑ„مپ§مپ‚م‚‹مپںم‚پم€په®‰ه®ڑçڑ„مپھن؛؛ه“،ç¢؛ن؟مپŒé›£مپ—مپ„مپ®مپŒçڈ¾çٹ¶مپ§مپ™م€‚
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپ¯ه¤ڑه²گمپ«م‚ڈمپںم‚‹و¥ه‹™مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œم€پمپمپ®ن¸€مپ¤ن¸€مپ¤مپŒو‰‹é–“مپ¨و™‚é–“م‚’è¦پمپ—مپ¾مپ™م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پو¼”é،Œمپ®ç™»éŒ²ç®،çگ†م€پè¦پو—¨é›†مپ®ن½œوˆگم€پهڈ‚هٹ 登録هڈ—ن»کم€پهڈ—ن»که¯¾ه؟œم€پن¼ڑه ´è¨ه–¶م€پو¥ه ´è€…مپ®و،ˆه†…م€پو‡‡è¦ھن¼ڑéپ‹ه–¶م€پم‚¢مƒ³م‚±مƒ¼مƒˆé›†è¨ˆمپھمپ©م€پç´°مپ‹مپڈ煩雑مپھم‚؟م‚¹م‚¯مپŒه±±ç©چمپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚م€Œو™‚é–“مپŒè¶³م‚ٹمپھمپ„م€چم€Œن؛؛و‰‹مپŒè¶³م‚ٹمپھمپ„م€چم€Œم‚³م‚¹مƒˆمپŒمپ‹مپ‹م‚‹م€چمپ¨مپ„مپ£مپںهˆ‡ه®ںمپھه£°مپŒم€په¤ڑمپڈمپ®ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶è€…مپ‹م‚‰èپمپ‹م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®è² و‹…مپŒé‡چمپھم‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پو—¥ه¸¸و¥ه‹™مپ¨ن¸¦è،Œمپ—مپںه¦ن¼ڑو؛–ه‚™مپ«è؟½م‚ڈم‚Œم€پç²¾ç¥çڑ„مƒ»è‚‰ن½“çڑ„مپھç–²ه¼ٹم‚’و‹›مپڈمپ“مپ¨م‚‚ه°‘مپھمپڈمپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپ“م‚ŒمپŒم€پçµگوœçڑ„مپ«م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ®و‚ھه¾ھç’°م‚’ç”ںمپ؟ه‡؛مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپŒèµ·مپ“م‚‹èƒŒو™¯مپ¨èھ²é،Œ
م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپŒو·±هˆ»هŒ–مپ™م‚‹èƒŒو™¯مپ«مپ¯م€پمپ„مپڈمپ¤مپ‹مپ®è¦په› مپŒè¤‡هگˆçڑ„مپ«çµ،مپ؟هگˆمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ ن¼ڑه“،و•°مپ®و¸›ه°‘مپ¨éپ‹ه–¶ن½“هˆ¶مپ®ه›؛ه®ڑهŒ–: ه°‘هگé«کé½¢هŒ–م‚„ç ”ç©¶è€…مپ®ه¤ڑو§کهŒ–مپ«ن¼´مپ„م€په¦ن¼ڑه…¨ن½“مپ®ن¼ڑه“،و•°مپŒو¸›ه°‘ه‚¾هگ‘مپ«مپ‚م‚‹ه›£ن½“م‚‚ه°‘مپھمپڈمپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپمپ®ن¸€و–¹مپ§م€پéپ‹ه–¶ن½“هˆ¶مپ¯ه¾“و¥مپ®مپ¾مپ¾ه¤‰هŒ–مپ›مپڑم€په°‘و•°مپ®مƒ،مƒ³مƒگمƒ¼مپ§ه¤ڑمپڈمپ®و¥ه‹™م‚’وٹ±مپˆè¾¼م‚€ه½¢مپ«مپھم‚ٹمپŒمپ،مپ§مپ™م€‚ ن؛‹ه‹™ه±€م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ®é«کé½¢هŒ–مپ¨ه¾Œç¶™è€…ن¸چ足: é•·ه¹´ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶م‚’و”¯مپˆمپ¦مپچمپںمƒ™مƒ†مƒ©مƒ³م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ®é«کé½¢هŒ–مپŒé€²م‚€ن¸€و–¹مپ§م€پè‹¥و‰‹مپ®è‚²وˆگم‚„ه¾Œç¶™è€…مپ®ç¢؛ن؟مپŒè؟½مپ„ن»کمپ„مپ¦مپ„مپھمپ„م‚±مƒ¼م‚¹مپŒه¤ڑمپڈ見م‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پ特ه®ڑمپ®ه€‹ن؛؛مپ«و¥ه‹™مپŒé›†ن¸مپ—م€په±ن؛؛هŒ–مپŒé€²م‚€مپ“مپ¨مپ§م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ«و‹چè»ٹمپŒمپ‹مپ‹م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مƒ»مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰é–‹ه‚¬مپ¸مپ®ه¯¾ه؟œ:
è؟‘ه¹´و€¥é€ںمپ«و™®هڈٹمپ—مپںم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³ه¦ن¼ڑم‚„مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰ه¦ن¼ڑمپ¯م€پن¼ڑه ´و‰‹é…چم‚„هڈ‚هٹ 者مپ®ç§»ه‹•è² و‹…م‚’軽و¸›مپ™م‚‹ن¸€و–¹مپ§م€پو–°مپںمپھوٹ€è،“çڑ„م‚¹م‚مƒ«م‚„و؛–ه‚™م‚’ه؟…è¦پمپ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚é…چن؟،م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®éپ‹ç”¨م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ§مپ®è³ھç–‘ه؟œç”ç®،çگ†م€پمƒˆمƒ©مƒ–مƒ«م‚·مƒ¥مƒ¼مƒ†م‚£مƒ³م‚°مپھمپ©م€په¾“و¥مپ«مپ¯مپھمپ‹مپ£مپںو¥ه‹™مپŒç™؛ç”ںمپ—م€پو—¢هکمپ®éپ‹ه–¶ن½“هˆ¶مپ«مپ•م‚‰مپھم‚‹è² و‹…م‚’مپ‹مپ‘م‚‹è¦په› مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
é–‹ه‚¬و™‚وœںمپ®é›†ن¸:
ه¤ڑمپڈمپ®ه¦ن¼ڑمپŒوک¥مپ¨ç§‹مپ«é–‹ه‚¬مپŒé›†ن¸مپ™م‚‹ه‚¾هگ‘مپ«مپ‚م‚ٹم€پé™گم‚‰م‚Œمپںو™‚وœںمپ«è¤‡و•°مپ®ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپŒé‡چمپھم‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پéپ‹ه–¶و‹…ه½“者مپ®è² و‹…مپŒه¢—ه¤§مپ—م€پم€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپŒé،•هœ¨هŒ–مپ—م‚„مپ™مپڈمپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚ مپ“م‚Œم‚‰مپ®èھ²é،ŒمپŒè¤‡é›‘مپ«çµ،مپ؟هگˆمپ„م€په¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چم‚’ن¸€ه±¤و·±هˆ»مپھم‚‚مپ®مپ«مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چم‚’解و¶ˆمپ™م‚‹ه…·ن½“çڑ„مپھه¯¾ç–
م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چم‚’解و¶ˆمپ—م€پوŒپç¶ڑهڈ¯èƒ½مپھه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶م‚’ه®ںçڈ¾مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پن»¥ن¸‹مپ®ن¸‰مپ¤مپ®وˆ¦ç•¥مپŒوœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚
و¥ه‹™مپ®م€Œهٹ¹çژ‡هŒ–م€چمپ¨ITمƒ„مƒ¼مƒ«مپ®و´»ç”¨
م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ®و ¹وœ¬çڑ„مپھ解و±؛مپ«مپ¯م€پمپ¾مپڑو¥ه‹™مپمپ®م‚‚مپ®مپ®م€Œهٹ¹çژ‡هŒ–م€چمپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚ç´™هھ’ن½“مپ§مپ®ç®،çگ†م‚„و‰‹ن½œو¥مپ«م‚ˆم‚‹é‡چ複ن½œو¥م‚’ه‰ٹو¸›مپ—م€پITمƒ„مƒ¼مƒ«م‚’ç©چو¥µçڑ„مپ«و´»ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پé™گم‚‰م‚Œمپںن؛؛ه“،مپ§م‚‚ه¯¾ه؟œهڈ¯èƒ½مپھن½“هˆ¶م‚’و§‹ç¯‰مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
ه…·ن½“çڑ„مپ«مپ¯م€په¦ن¼ڑç®،çگ†م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®ه°ژه…¥مپŒوœ€م‚‚هٹ¹وœçڑ„مپ§مپ™م€‚ن¼ڑه“،وƒ…ه ±مپ®ç®،çگ†م€په¹´ن¼ڑè²»مپ®ه¾´هڈژم€پو¼”é،Œمپ®ه‹ں集مƒ»وں»èھم€پهڈ‚هٹ 登録م€پو±؛و¸ˆه‡¦çگ†م€پمپمپ—مپ¦ه½“و—¥مپ®هڈ—ن»کç®،çگ†مپ¨مپ„مپ£مپںن¸€é€£مپ®و¥ه‹™م‚’م‚·م‚¹مƒ†مƒ ن¸ٹمپ§ن¸€ه…ƒهŒ–مƒ»è‡ھه‹•هŒ–مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پن؛‹ه‹™ه±€مپ®ن½œو¥è² و‹…م‚’ه¤§ه¹…مپ«è»½و¸›مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³هڈ‚هٹ 登録م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’ه°ژه…¥مپ™م‚Œمپ°م€پهڈ‚هٹ 者وƒ…ه ±مپ®ه…¥هٹ›مپ‹م‚‰و”¯و‰•مپ„م€پé›»هگمƒپم‚±مƒƒمƒˆمپ®ç™؛è،Œمپ¾مپ§م‚’è‡ھه‹•مپ§è،Œمپˆم€په½“و—¥مپ®هڈ—ن»کم‚‚QRم‚³مƒ¼مƒ‰مپھمپ©م‚’و´»ç”¨مپ—مپ¦è؟…é€ںهŒ–مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚و¼”é،Œمپ®وں»èھمƒ—مƒم‚»م‚¹م‚‚م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ§è،Œمپ†مپ“مپ¨مپ§م€پمƒ،مƒ¼مƒ«مپ§مپ®م‚„م‚ٹهڈ–م‚ٹم‚„ç´™مپ§مپ®è³‡و–™é€پن»کمپ®و‰‹é–“مپŒçœپمپ‘م€پ進وچ—ç®،çگ†م‚‚ه®¹وک“مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پم€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ«م‚ˆم‚‹و¥ه‹™هپœو»م‚’éک²مپژم€پم‚ˆم‚ٹه¤ڑمپڈمپ®و™‚é–“م‚’ن¼پç”»م‚„éپ‹ه–¶مپ®è³ھهگ‘ن¸ٹمپ«ه……مپ¦م‚‹مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ه¤–部مƒھم‚½مƒ¼م‚¹مپ®ç©چو¥µçڑ„مپھو´»ç”¨
م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چم‚’補مپ†مپںم‚پمپ«م€په¤–部مپ®ه°‚é–€مƒھم‚½مƒ¼م‚¹م‚’ç©چو¥µçڑ„مپ«و´»ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚وœ‰هٹ¹مپھو‰‹و®µمپ§مپ™م€‚ ه¦ç”ںم‚¢مƒ«مƒگم‚¤مƒˆمƒ»مƒœمƒ©مƒ³مƒ†م‚£م‚¢مپ®و´»ç”¨: ه¤§ن¼ڑه½“و—¥م‚„و؛–ه‚™مپ®مƒ”مƒ¼م‚¯و™‚مپ«مپ¯م€په¦ç”ںم‚¢مƒ«مƒگم‚¤مƒˆم‚„مƒœمƒ©مƒ³مƒ†م‚£م‚¢م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•م‚’ه‹ںم‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پن¸€و™‚çڑ„مپ«ن؛؛çڑ„مƒھم‚½مƒ¼م‚¹م‚’ه¢—ه¼·مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚هڈ—ن»کم€پن¼ڑه ´و،ˆه†…م€پ資و–™و؛–ه‚™مپھمپ©م€پو¯”較çڑ„ç°،وک“مپھو¥ه‹™م‚’ه§”مپم‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¸¸ه‹¤م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ¯م‚ˆم‚ٹه°‚é–€çڑ„مپ§è¤‡é›‘مپھو¥ه‹™مپ«é›†ن¸مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
م‚³مƒ³مƒ™مƒ³م‚·مƒ§مƒ³ن»£è،Œن¼ڑ社مپ¸مپ®ه§”託: ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه°‚é–€و¥è€…مپ§مپ‚م‚‹م‚³مƒ³مƒ™مƒ³م‚·مƒ§مƒ³ن»£è،Œن¼ڑ社مپ«م€پن¼پ画立و،ˆمپ‹م‚‰ن¼ڑه“،ç®،çگ†م€پن¼ڑه ´و‰‹é…چم€په½“و—¥مپ®éپ‹ه–¶م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³é…چن؟،ه¯¾ه؟œم€پè¨ک録مƒ»ه ±ه‘ٹو¥ه‹™مپ¾مپ§م€په¦ن¼ڑé–‹ه‚¬مپ«é–¢م‚ڈم‚‹مپ‚م‚‰م‚†م‚‹و¥ه‹™م‚’ه§”託مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚وœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚مƒ—مƒمپ®مƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپ¨çµŒé¨“م‚’و´»ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په°‘ن؛؛و•°مپ®ن؛‹ه‹™ه±€مپ§مپ¯ه¯¾ه؟œمپŒé›£مپ—مپ„و¥ه‹™م‚‚è³ھمپ®é«کمپڈéپ‚è،Œمپ§مپچم€پن¸»ه‚¬è€…هپ´مپ®è² و‹…م‚’ه¤§ه¹…مپ«è»½و¸›مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚特مپ«م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³é–‹ه‚¬م‚„مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰é–‹ه‚¬مپھمپ©م€په°‚é–€çڑ„مپھçں¥èکم‚„وٹ€è،“مپŒه؟…è¦پمپھهˆ†é‡ژمپ§مپ¯م€په¤–部ه§”託مپ¯م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چم‚’補مپ†ه¼·هٹ›مپھ解و±؛ç–مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚ن؛ˆç®—م‚„مƒ‹مƒ¼م‚؛مپ«ه؟œمپکمپ¦م€پو¥ه‹™مپ®ن¸€éƒ¨مپ®مپ؟م‚’ه§”託مپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ£مپںوں”è»ںمپھو´»ç”¨م‚‚هڈ¯èƒ½مپ§مپ™م€‚
و¥ه‹™مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ®è¦‹ç›´مپ—مپ¨و¨™و؛–هŒ–
م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®ه°ژه…¥م‚„ه¤–部ه§”託مپ¨ن¸¦è،Œمپ—مپ¦م€پو—¢هکمپ®و¥ه‹™مƒ—مƒم‚»م‚¹è‡ھن½“م‚’見直مپ—م€پو¨™و؛–هŒ–مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چه¯¾ç–مپ«مپ¯ن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚
و¥ه‹™مپ®هڈ¯è¦–هŒ–مپ¨مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«ن½œوˆگ:
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«é–¢م‚ڈم‚‹ه…¨مپ¦مپ®م‚؟م‚¹م‚¯م‚’و´—مپ„ه‡؛مپ—م€پم€Œè¦‹مپˆم‚‹هŒ–م€چمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پو¥ه‹™مپ®ه…¨ن½“هƒڈم‚’وٹٹوڈ،مپ—م€پç„،駄مپھن½œو¥م‚„é‡چ複م‚’特ه®ڑمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚مپم‚Œمپم‚Œمپ®م‚؟م‚¹م‚¯مپ«مپ¤مپ„مپ¦è©³ç´°مپھمƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م‚’ن½œوˆگمپ—م€په…±وœ‰مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پو‹…ه½“者مپ®ç•°ه‹•م‚„ن؛¤ن»£مپŒمپ‚مپ£مپںéڑ›مپ«م‚‚م‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپھه¼•مپچ継مپژمپŒهڈ¯èƒ½مپ¨مپھم‚ٹم€پو¥ه‹™مپ®ه±ن؛؛هŒ–م‚’éک²مپژمپ¾مپ™م€‚
م‚؟م‚¹م‚¯ç®،çگ†مƒ„مƒ¼مƒ«مپ®و´»ç”¨:
Todoistم‚„Trelloمپ®م‚ˆمپ†مپھم‚؟م‚¹م‚¯ç®،çگ†مƒ„مƒ¼مƒ«م‚’و´»ç”¨مپ—م€پم‚؟م‚¹م‚¯مپ”مپ¨مپ«و‹…ه½“者م€پوœںé™گم€پ進وچ—çٹ¶و³پم‚’وکژç¢؛مپ«مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پمƒپمƒ¼مƒ ه…¨ن½“مپ§و¥ه‹™مپ®و¼ڈم‚Œم‚„éپ…ه»¶م‚’éک²مپژمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پé™گم‚‰م‚Œمپںن؛؛ه“،مپ§م‚‚هٹ¹çژ‡çڑ„مپ«و¥ه‹™م‚’éپ‚è،Œمپ§مپچم‚‹ن½“هˆ¶مپŒو•´مپ„مپ¾مپ™م€‚
مƒ†مƒ³مƒ—مƒ¬مƒ¼مƒˆمپ®و´»ç”¨:
éپژهژ»مپ®و،ˆه†…و–‡م€پè°ن؛‹éŒ²م€پهگ„種申請و›¸مپھمپ©مپ®مپ²مپھه½¢م‚’و•´ه‚™مپ—م€پمƒ†مƒ³مƒ—مƒ¬مƒ¼مƒˆمپ¨مپ—مپ¦و´»ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پو›¸é،ن½œوˆگمپ®و‰‹é–“م‚’ه¤§ه¹…مپ«ه‰ٹو¸›مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چ解و±؛مپ®مپںم‚پمپ®ç•™و„ڈ点مپ¨و”¯وڈ´م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹
م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چم‚’解و¶ˆمپ™م‚‹مپںم‚پمپ®ه¯¾ç–م‚’講مپکم‚‹éڑ›مپ«مپ¯م€پمپ„مپڈمپ¤مپ‹مپ®ç•™و„ڈ点مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚ مپ¾مپڑم€پITمƒ„مƒ¼مƒ«م‚’ه°ژه…¥مپ™م‚‹éڑ›م€پم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ«ن¸چو…£م‚Œمپ مپ¨é€†مپ«و··ن¹±م‚’و‹›مپڈوپگم‚ŒمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚و–°مپ—مپ„م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚’ن½؟مپ„مپ“مپھمپ™مپںم‚پمپ®ن؛‹ه‰چç ”ن؟®م‚„م€پهˆ†مپ‹م‚ٹم‚„مپ™مپ„مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«مپ®و•´ه‚™مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚مپ¾مپںم€په½“و—¥مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«مپŒç™؛ç”ںمپ—مپںه ´هگˆمپ«ه‚™مپˆم€پè؟…é€ںمپھم‚µمƒمƒ¼مƒˆن½“هˆ¶م‚’用و„ڈمپ—م€پمƒچمƒƒمƒˆمƒ¯مƒ¼م‚¯éڑœه®³م‚„و©ںه™¨ن¸چèھ؟مپ«ه‚™مپˆمپںمƒگمƒƒم‚¯م‚¢مƒƒمƒ—مƒ—مƒ©مƒ³م‚‚و¤œè¨ژمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
ه¤–部ه§”託مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پم‚³م‚¹مƒˆé¢مپ¨ه¦ن¼ڑمپ®ç‹¬è‡ھو€§مپ®ç¶وŒپمپŒمƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ§مپ™م€‚ه…¨مپ¦م‚’ن»»مپ›م‚‹مپ¨è²»ç”¨مپŒمپ‹مپ•مپ؟م€پé™گم‚‰م‚Œمپںن؛ˆç®—م‚’هœ§è؟«مپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚ه§”託範ه›²مپ¯ه؟…è¦پوœ€ه°ڈé™گمپ«çµم‚ٹم€په¥‘ç´„ه‰چمپ«è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹمپ¨م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹ه†…ه®¹م‚’هچپهˆ†مپ«ç¢؛èھچمپ—م€پç„،çگ†مپ®مپھمپ„計画م‚’ç«‹مپ¦م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚مپ¾مپںم€په¤–部مپ«و©ںه¯†مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’é گمپ‘م‚‹éڑ›مپ«مپ¯م€په§”託ه…ˆمپ®وƒ…ه ±م‚»م‚مƒ¥مƒھمƒ†م‚£ن½“هˆ¶مپŒن؟،é ¼مپ«è¶³م‚‹مپ‹م‚’ç¢؛èھچمپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚و¬ مپ‹مپ›مپ¾مپ›م‚“م€‚ه¤–部مپ®éپ‹ه–¶ن»£è،Œمپ«ن»»مپ›مپچم‚ٹمپ«مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¦ن¼ڑمپھم‚‰مپ§مپ¯مپ®é›°ه›²و°—م‚„ç´°م‚„مپ‹مپھé…چو…®مپŒè،Œمپچه±ٹمپ‹مپھمپڈمپھم‚‹و‡¸ه؟µم‚‚مپ‚م‚‹مپںم‚پم€پو¥è€…مپ¨مپ¯ه¯†مپ«م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³م‚’هڈ–م‚ٹم€پè‡ھه›£ن½“مپ®çگ†ه؟µم‚„و–¹é‡م‚’ه…±وœ‰مپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپ†مپ“مپ¨مپ§م€په¦ن¼ڑمپ®ç‹¬è‡ھو€§م‚’وگچمپھم‚ڈمپڑمپ«و”¯وڈ´م‚’هڈ—مپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ®è§£و¶ˆمپ«هگ‘مپ‘مپ¦م€پن½•م‚’مپ©مپ†مپ—مپںم‚‰è‰¯مپ„مپ®مپ‹مپٹو‚©مپ؟مپ®ه ´هگˆم€په°‚é–€مپ®و”¯وڈ´م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’و´»ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚وœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€په¦è،“ه¤§ن¼ڑمƒ»ه›½éڑ›ن¼ڑè°مپ®éپ‹ه–¶م‚’ن¸€و‹¬ç®،çگ†مپ§مپچم‚‹م€ŒAWARD(م‚¢مƒ¯مƒ¼مƒ‰ï¼‰م€چمپ®م‚ˆمپ†مپھم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¯م€پو¼”é،Œç™»éŒ²مپ‹م‚‰هڈ‚هٹ 登録م€پن¼ڑه ´مپ§مپ®QRم‚³مƒ¼مƒ‰هڈ—ن»کمپ¾مپ§ه¯¾ه؟œمپ—مپںم‚ھمƒ¼مƒ«م‚¤مƒ³مƒ¯مƒ³مپ®ه¤§ن¼ڑç®،çگ†و©ں能م‚’وڈگن¾›مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€په°‘ن؛؛و•°مپ§مپ®éپ‹ه–¶م‚’ه¼·هٹ›مپ«م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ—مپ¾مپ™م€‚هˆوœں費用م‚„وœˆé،چ費用م‚’وٹ‘مپˆمپںمƒ—مƒ©مƒ³م‚‚مپ‚م‚‹مپںم‚پم€پن؛ˆç®—مپŒé™گم‚‰م‚Œمپںه¦ن¼ڑمپ§م‚‚ه°ژه…¥م‚’و¤œè¨ژمپ—م‚„مپ™مپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
مپ¾مپ¨م‚پï¼ڑم€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چم‚’ن¹—م‚ٹè¶ٹمپˆم€پوŒپç¶ڑهڈ¯èƒ½مپھه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ¸
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ¯و·±هˆ»مپھèھ²é،Œمپ§مپ™مپŒم€پéپ©هˆ‡مپھه¯¾ç–م‚’講مپکم‚‹مپ“مپ¨مپ§ن¹—م‚ٹè¶ٹمپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ§مپ™م€‚ITمƒ„مƒ¼مƒ«مپ®و´»ç”¨مپ«م‚ˆم‚‹و¥ه‹™مپ®م€Œهٹ¹çژ‡هŒ–م€چم€په¤–部مƒھم‚½مƒ¼م‚¹مپ®ç©چو¥µçڑ„مپھو´»ç”¨م€پمپمپ—مپ¦و¥ه‹™مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ®è¦‹ç›´مپ—مپ¨و¨™و؛–هŒ–مپ¯م€پé™گم‚‰م‚Œمپںمƒھم‚½مƒ¼م‚¹مپ§è³ھمپ®é«کمپ„ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶م‚’ه®ںçڈ¾مپ™م‚‹مپںم‚پمپ®é‡چè¦پمپھوˆ¦ç•¥مپ§مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑ ن؛؛و‰‹ن¸چ足م€چمپ®è§£و¶ˆمپ¯م€پن؛‹ه‹™ه±€مپ®è² و‹…軽و¸›مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پن¼ڑه“،م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®هگ‘ن¸ٹم€پمپمپ—مپ¦ه¦ن¼ڑوœ¬و¥مپ®ه¦è،“ن؛¤وµپمپ®و´»و€§هŒ–مپ«ç¹‹مپŒم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®ه¯¾ç–م‚’複هگˆçڑ„مپ«ه®ںو–½مپ—م€پوŒپç¶ڑهڈ¯èƒ½مپ§ç™؛ه±•çڑ„مپھه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶م‚’ç›®وŒ‡مپ—مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚