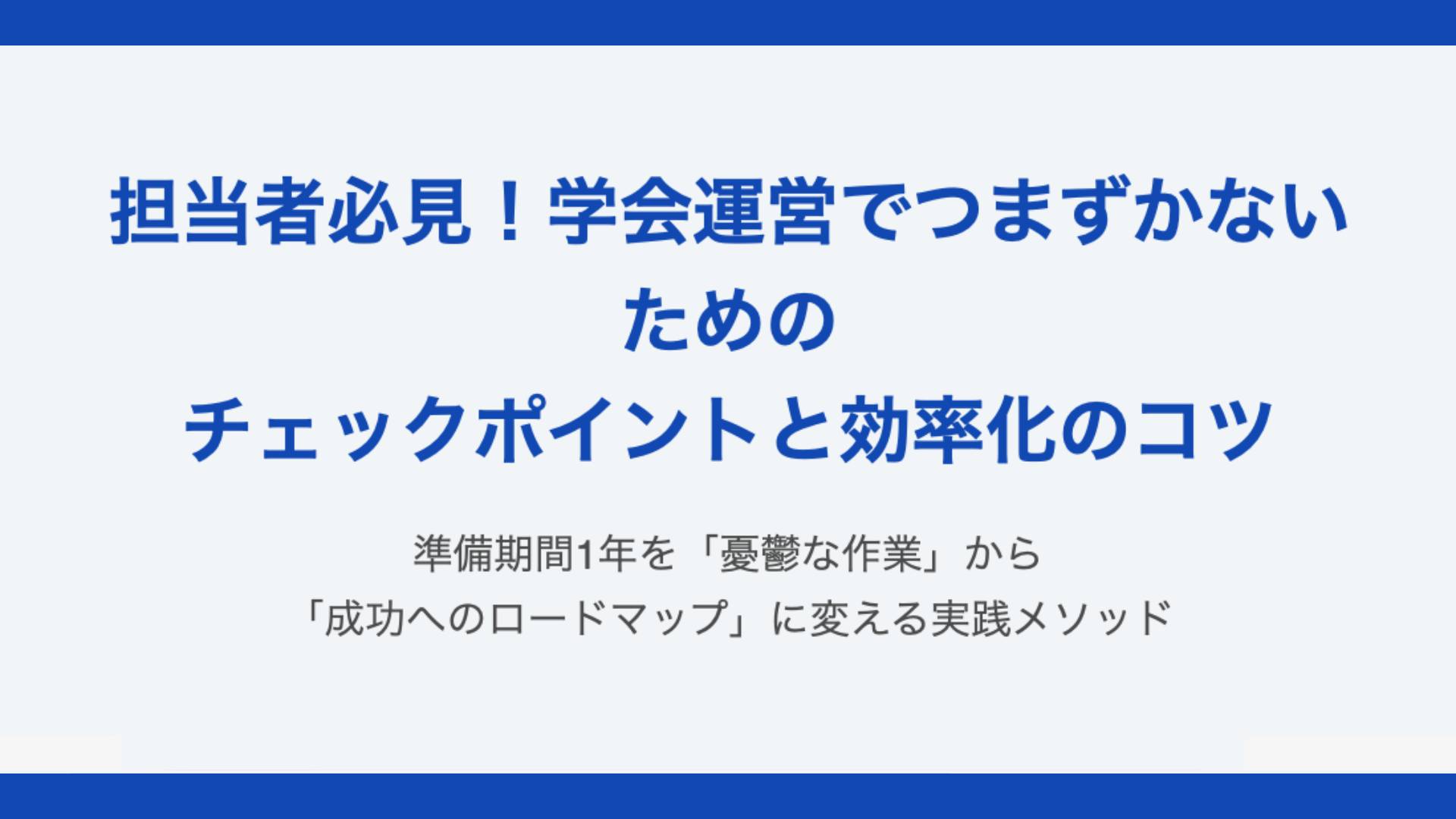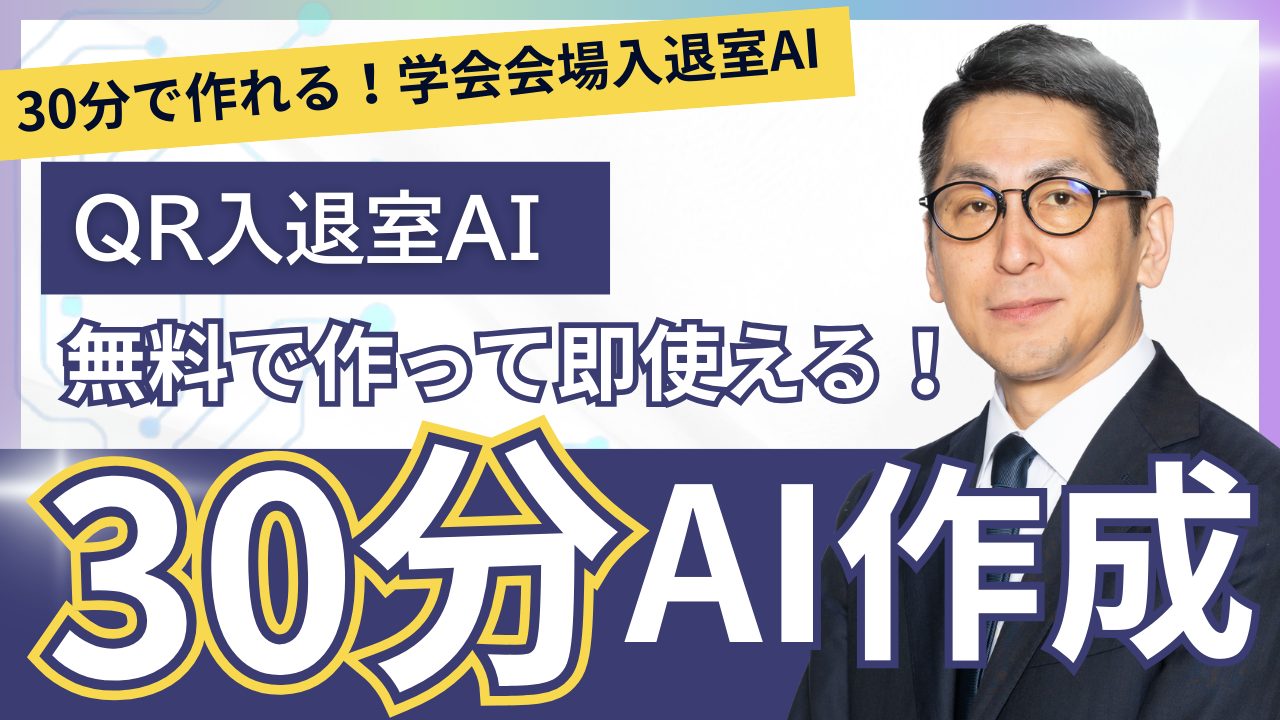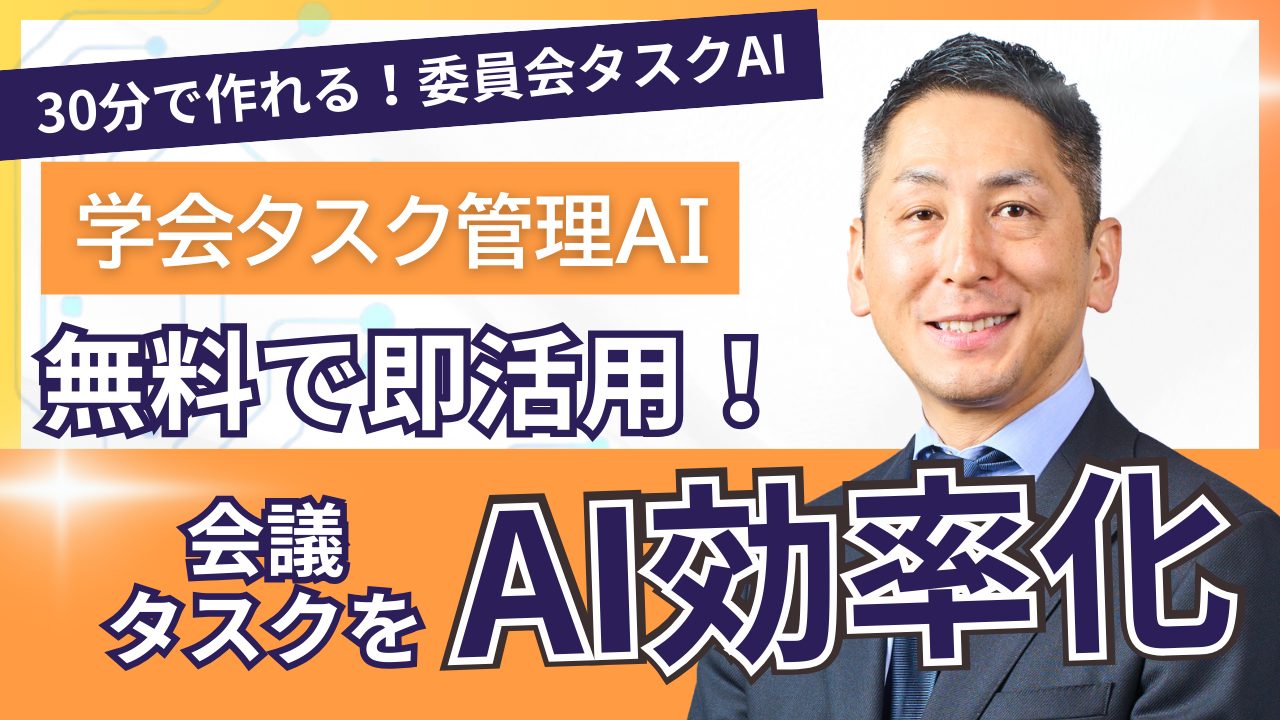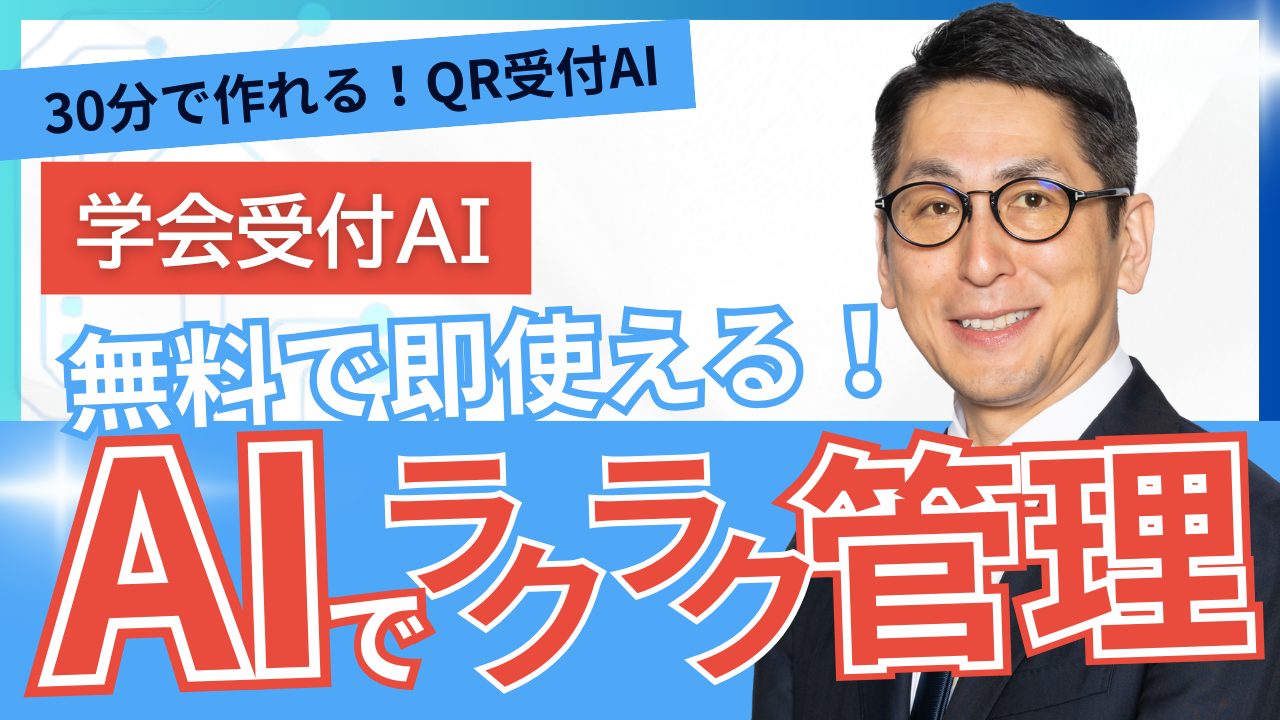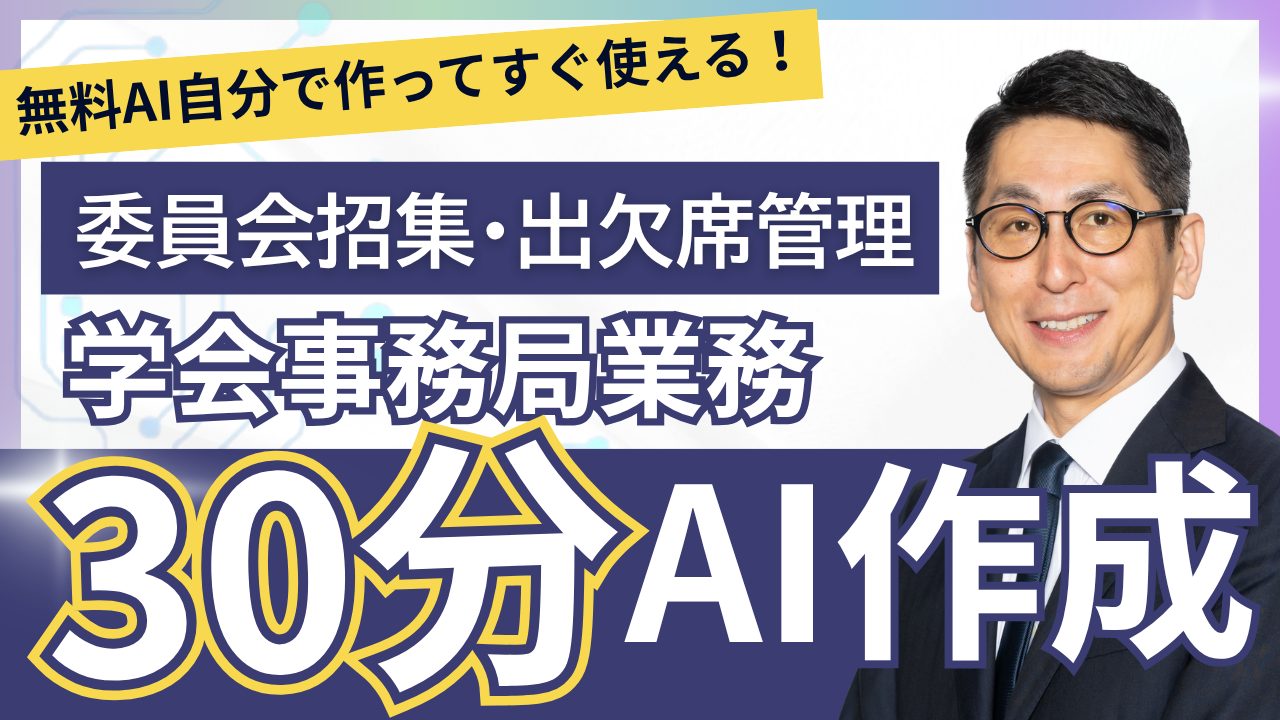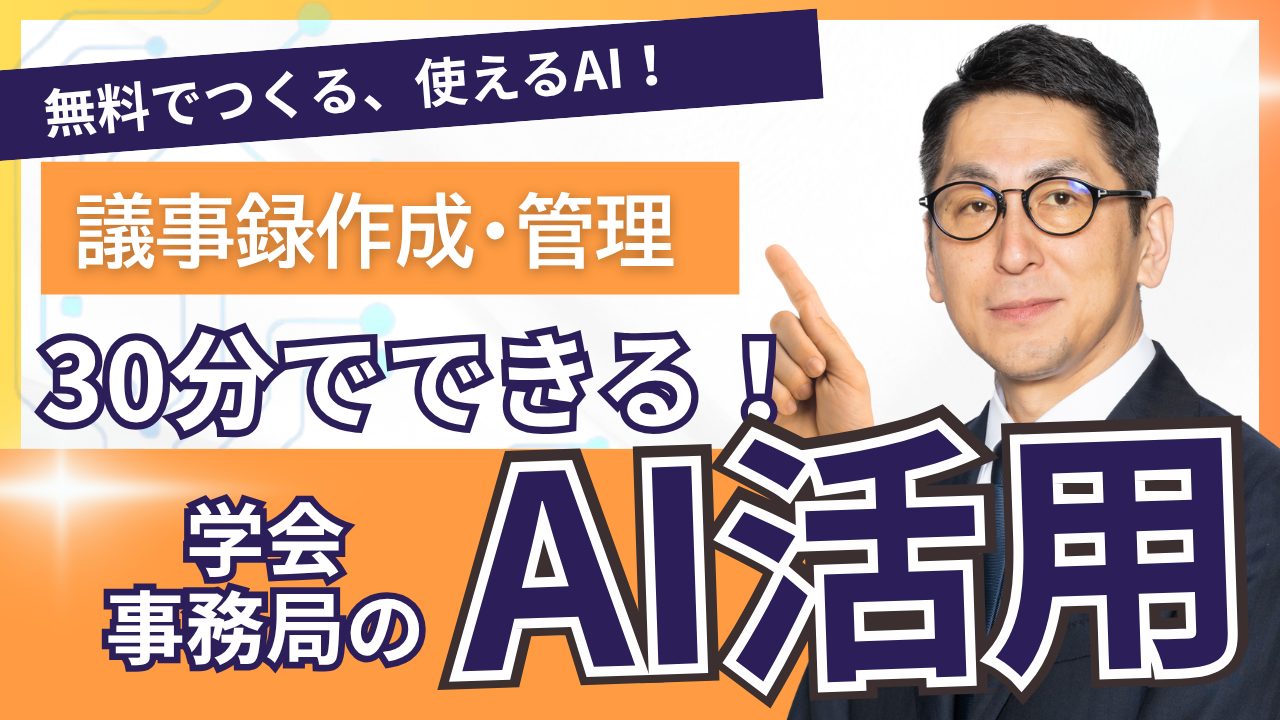م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®ه…¨è²Œï¼ڑم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹ه†…ه®¹مپ¨و´»ç”¨مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم€پمپٹمپ™مپ™م‚پمƒ„مƒ¼مƒ«
2025ه¹´07وœˆ08و—¥

ه¦è،“ç ”ç©¶مپ®ç™؛ه±•مپ«ن¸چهڈ¯و¬ مپھه¦ن¼ڑمپ§مپ™مپŒم€پمپمپ®éپ‹ه–¶مپ¯ه¹´م€…複雑هŒ–مپ—م€په¤ڑه¤§مپھهٹ´هٹ›مپ¨ه°‚é–€çں¥èکم‚’è¦پمپ™م‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ه¤ڑمپڈمپ®ç ”究者مپŒوœ¬و¥مپ¨ن¸¦è،Œمپ—مپ¦éپ‹ه–¶و¥ه‹™مپ«وگ؛م‚ڈم‚‹ن¸مپ§م€پè² و‹…مپ®è»½و¸›مپ¨هٹ¹çژ‡هŒ–م‚’ه›³م‚‹مپںم‚پمپ«م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®هˆ©ç”¨مپŒو³¨ç›®مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
وœ¬è¨کن؛‹مپ§مپ¯م€پم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ¨مپ¯ه…·ن½“çڑ„مپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’وڈگن¾›مپ—م€په¦ن¼ڑمپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھمƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚’م‚‚مپںم‚‰مپ™مپ®مپ‹م‚’詳مپ—مپڈ解èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’éپ¸مپ¶éڑ›مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚„م€پو¥ه‹™هٹ¹çژ‡هŒ–مپ«ه½¹ç«‹مپ¤مپٹمپ™مپ™م‚پمپ®مƒ„مƒ¼مƒ«مپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚‚ç´¹ن»‹مپ—مپ¾مپ™م€‚è²´ه¦ن¼ڑمپŒم‚ˆم‚ٹه††و»‘مپ«م€پمپمپ—مپ¦وŒپç¶ڑçڑ„مپ«و´»ه‹•مپ—مپ¦مپ„مپڈمپںم‚پمپ®ه®ںè·µçڑ„مپھمƒ’مƒ³مƒˆم‚’وڈگن¾›مپ—مپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ¨مپ¯ï¼ںمپمپ®ه½¹ه‰²مپ¨ه؟…è¦پو€§
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ¨مپ¯م€په¦è،“ه›£ن½“م‚„ç ”ç©¶ن¼ڑمپŒن¸»ه‚¬مپ™م‚‹ه¦è،“ه¤§ن¼ڑم€پم‚·مƒ³مƒم‚¸م‚¦مƒ م€پم‚»مƒںمƒٹمƒ¼مپھمپ©مپ®ن¼پç”»مپ‹م‚‰و؛–ه‚™م€په®ںو–½م€پن؛‹ه¾Œه‡¦çگ†مپ«è‡³م‚‹مپ¾مپ§م€پن¸€é€£مپ®éپ‹ه–¶و¥ه‹™م‚’ه°‚é–€çڑ„مپ«è«‹مپ‘è² مپ†م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’وŒ‡مپ—مپ¾مپ™م€‚PCO(Professional Congress Organizer)مپ¨م‚‚ه‘¼مپ°م‚Œم€په¦ن¼ڑ特وœ‰مپ®و…£ç؟’م‚„مƒ‹مƒ¼م‚؛م‚’çگ†è§£مپ—مپںن¸ٹمپ§م€پمپمپ®ه°‚é–€çں¥èکمپ¨مƒژم‚¦مƒڈم‚¦م‚’وڈگن¾›مپ—مپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپŒو‹…مپ†ن¸»مپھو¥ه‹™
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپŒوڈگن¾›مپ™م‚‹و¥ه‹™مپ¯éه¸¸مپ«ه؛ƒç¯„مپ§مپ™م€‚ن¸»مپھم‚‚مپ®مپ¨مپ—مپ¦مپ¯م€پن»¥ن¸‹مپ®م‚ˆمپ†مپھو¥ه‹™مپŒوŒ™مپ’م‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
ن¼پç”»مƒ»و؛–ه‚™و®µéڑژ:
ه¦è،“ه¤§ن¼ڑمپ®م‚³مƒ³م‚»مƒ—مƒˆç«‹و،ˆو”¯وڈ´م€پن؛ˆç®—ç–ه®ڑم€پن¼ڑه ´مپ®éپ¸ه®ڑمƒ»ن؛ˆç´„م€په®؟و³ٹمƒ»ن؛¤é€ڑو‰‹é…چم€پم‚¹مƒمƒ³م‚µمƒ¼ه‹ں集م€پمƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ ç·¨وˆگمپ®م‚µمƒمƒ¼مƒˆم€پو¼”é،Œه‹ں集مƒ»ç®،çگ†م€پوں»èھم‚µمƒمƒ¼مƒˆم€پهڈ‚هٹ 登録م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®و§‹ç¯‰م€پوٹ„録集مپ®ç·¨é›†مƒ»هچ°هˆ·م€‚
ه؛ƒه ±مƒ»é›†ه®¢:
ه¤§ن¼ڑم‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆمپ®هˆ¶ن½œمƒ»ç®،çگ†م€پهڈ‚هٹ 者مپ¸مپ®وƒ…ه ±ç™؛ن؟،م€پSNSمپھمپ©م‚’و´»ç”¨مپ—مپںمƒ—مƒمƒ¢مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³و´»ه‹•م€‚
ه½“و—¥éپ‹ه–¶:
هڈ—ن»کو¥ه‹™م€پن¼ڑه ´è¨ه–¶مƒ»و’¤هژ»م€پو©ںوگو‰‹é…چ(éں³éں؟مƒ»وک هƒڈمپھمپ©ï¼‰م€پç™؛è،¨è€…مƒ»è¬›و¼”者م‚µمƒمƒ¼مƒˆم€پم‚»مƒƒم‚·مƒ§مƒ³ç®،çگ†م€پو‡‡è¦ھن¼ڑéپ‹ه–¶م€پم‚»م‚مƒ¥مƒھمƒ†م‚£ه¯¾ç–م€‚
ن؛‹ه¾Œه‡¦çگ†:
م‚¢مƒ³م‚±مƒ¼مƒˆé›†è¨ˆم€پن¼ڑ計ه ±ه‘ٹم€پè°ن؛‹éŒ²ن½œوˆگم€په ±ه‘ٹو›¸وڈگه‡؛م€پهڈ‚هٹ 者مپ¸مپ®مƒ•م‚©مƒمƒ¼م‚¢مƒƒمƒ—م€‚
è؟‘ه¹´مپ§مپ¯م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³é…چن؟،م‚„مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰é–‹ه‚¬مپھمپ©م€پو–°مپںمپھé–‹ه‚¬ه½¢ه¼ڈمپ¸مپ®ه¯¾ه؟œم‚‚é‡چè¦پمپھه½¹ه‰²مپ¨مپھمپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€په°‚é–€çڑ„مپھوٹ€è،“م‚µمƒمƒ¼مƒˆم‚‚م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®و¥ه‹™ç¯„ه›²مپ«هگ«مپ¾م‚Œمپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ¨ن؛‹ه‹™ه±€ن»£è،Œمپ®éپ•مپ„
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ¨م€Œه¦ن¼ڑن؛‹ه‹™ه±€ن»£è،Œم€چمپ¯ن¼¼مپ¦مپ„مپ¾مپ™مپŒم€پمپم‚Œمپم‚Œç•°مپھم‚‹ه½¹ه‰²م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ¯ن¸»مپ«ه¦è،“ه¤§ن¼ڑم‚„م‚¤مƒ™مƒ³مƒˆمپھمپ©م€پوœںé–“م‚’ه®ڑم‚پمپ¦é–‹ه‚¬مپ•م‚Œم‚‹م‚¤مƒ™مƒ³مƒˆمپ®ن¼پç”»مƒ»éپ‹ه–¶مپ«ç‰¹هŒ–مپ—مپںم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ§مپ™م€‚
ن¸€و–¹مپ§م€Œه¦ن¼ڑن؛‹ه‹™ه±€ن»£è،Œم€چمپ¯م€پن¼ڑه“،ç®،çگ†م€پن¼ڑè²»ه¾´هڈژم€پو—¥ه¸¸çڑ„مپھه•ڈمپ„هگˆم‚ڈمپ›ه¯¾ه؟œمپھمپ©م€په¹´é–“م‚’é€ڑمپکمپ¦ç™؛ç”ںمپ™م‚‹ه®ڑه¸¸çڑ„مپھن؛‹ه‹™ه±€و¥ه‹™م‚’ن»£è،Œمپ™م‚‹م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ§مپ™م€‚ن¸،者مپ¯é€£وگ؛مپ—مپ¦هˆ©ç”¨مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚‚ه¤ڑمپڈم€په¦ن¼ڑمپ®مƒ‹مƒ¼م‚؛مپ«ه؟œمپکمپ¦ن½؟مپ„هˆ†مپ‘م‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چم‚’هˆ©ç”¨مپ™م‚‹مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¨مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆ
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®هˆ©ç”¨مپ¯م€په¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«ه¤ڑه¤§مپھمƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚’م‚‚مپںم‚‰مپ—مپ¾مپ™مپŒم€پهگŒو™‚مپ«è€ƒو…®مپ™مپ¹مپچمƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚‚هکهœ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®مƒ،مƒھمƒƒمƒˆ
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ«و¥ه‹™م‚’ه§”託مپ™م‚‹وœ€ه¤§مپ®مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¯م€په¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®مƒ—مƒمƒ•م‚§مƒƒم‚·مƒ§مƒٹمƒ«مپ«م‚ˆم‚‹ه°‚é–€çڑ„مپھمƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپ¨çµŒé¨“م‚’و´»ç”¨مپ§مپچم‚‹ç‚¹مپ§مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پéپ‹ه–¶مپ®è³ھمپŒé£›è؛چçڑ„مپ«هگ‘ن¸ٹمپ—م€پهڈ‚هٹ 者و؛€è¶³ه؛¦مپ®é«کمپ„ه¦è،“ه¤§ن¼ڑم‚’ه®ںçڈ¾مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚煩雑مپھه®ںه‹™مپ‹م‚‰è§£و”¾مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¦ن¼ڑه½¹ه“،م‚„ن؛‹ه‹™ه±€مپ¯م€په¦è،“ه†…ه®¹مپ®ن¼پç”»م‚„ç ”ç©¶و´»ه‹•مپ¨مپ„مپ£مپںم€پوœ¬و¥مپ®é‡چè¦پمپھو¥ه‹™مپ«é›†ن¸مپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پن؛؛و‰‹ن¸چ足مپ®è§£و¶ˆم€پ特ه®ڑمپ®و¥ه‹™مپ«ç²¾é€ڑمپ—مپںه°‚é–€ن؛؛وگمپ®ç¢؛ن؟م€پهٹ¹çژ‡çڑ„مپھو¥ه‹™مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ®و§‹ç¯‰م€پمپمپ—مپ¦وœ€و–°مپ®ITمƒ„مƒ¼مƒ«م‚„وٹ€è،“م‚’ه°ژه…¥مپ§مپچم‚‹ç‚¹م‚‚ه¤§مپچمپھهˆ©ç‚¹مپ§مپ™م€‚特مپ«م€په›½éڑ›ن¼ڑè°م‚„م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مƒ»مƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰é–‹ه‚¬مپھمپ©م€په°‚é–€و€§مپ®é«کمپ„éپ‹ه–¶مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œم‚‹ه ´é¢مپ§مپ¯م€پم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®هکهœ¨مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پéپ‹ه–¶ن½“هˆ¶مپ®ه¼·هŒ–مپ¨م‚³م‚¹مƒˆمپ®وœ€éپ©هŒ–مپ«م‚‚مپ¤مپھمپŒم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¨و³¨و„ڈ点
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®هˆ©ç”¨مپ«مپ¯مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پمƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚„و³¨و„ڈمپ™مپ¹مپچ点م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚وœ€م‚‚و‡¸ه؟µمپ•م‚Œم‚‹مپ®مپŒè²»ç”¨مپ§مپ™م€‚ه§”託مپ™م‚‹و¥ه‹™ç¯„ه›²م‚„ه¦ن¼ڑمپ®è¦ڈو¨،مپ«م‚ˆمپ£مپ¦مپ¯م€پ費用مپŒé«کé،چمپ«مپھم‚ٹم€په¦ن¼ڑمپ®ن؛ˆç®—م‚’هœ§è؟«مپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚ه¥‘ç´„ه‰چمپ«م€پم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹم‚’詳細مپ«ç¢؛èھچمپ—م€پç´چه¾—مپ„مپڈمپ¾مپ§èھ¬وکژم‚’هڈ—مپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پو¥ه‹™م‚’ه¤–部مپ«ن»»مپ›م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¦ن¼ڑه†…部مپ«éپ‹ه–¶مƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپŒè“„ç©چمپ•م‚Œمپ«مپڈمپڈمپھم‚‹مپ“مپ¨م‚„م€پوƒ…ه ±ه…±وœ‰مپŒن¸چهچپهˆ†مپ«مپھم‚‹مƒھم‚¹م‚¯م‚‚考مپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚و©ںه¯†و€§مپ®é«کمپ„ن¼ڑه“،وƒ…ه ±مپھمپ©م‚’é گمپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھم‚‹مپںم‚پم€په§”託ه…ˆمپ®وƒ…ه ±م‚»م‚مƒ¥مƒھمƒ†م‚£ن½“هˆ¶مپŒن¸‡ه…¨مپ§مپ‚م‚‹مپ‹م‚‚ç¢؛èھچمپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚مپ•م‚‰مپ«م€په¦ن¼ڑ独è‡ھمپ®و…£ç؟’م‚„و–‡هŒ–م‚’çگ†è§£مپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپ„مپ«مپڈمپ„هڈ¯èƒ½و€§م‚‚مپ‚م‚‹مپںم‚پم€په¯†مپھم‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³مپ¨é€£وگ؛مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®è²»ç”¨ç›¸ه ´مپ¨و–™é‡‘ن½“ç³»
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®è²»ç”¨مپ¯م€په§”託مپ™م‚‹و¥ه‹™مپ®ç¯„ه›²م€په¦ن¼ڑمپ®è¦ڈو¨،(هڈ‚هٹ 者و•°ï¼‰م€پé–‹ه‚¬ه½¢ه¼ڈ(çڈ¾هœ°é–‹ه‚¬م€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³é–‹ه‚¬م€پمƒڈم‚¤مƒ–مƒھمƒƒمƒ‰é–‹ه‚¬ï¼‰م€پمپمپ—مپ¦وڈگن¾›مپ•م‚Œم‚‹م‚µمƒمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ™مƒ«مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ه¤§مپچمپڈه¤‰ه‹•مپ—مپ¾مپ™م€‚
و–™é‡‘ن½“ç³»مپ®ن¸€èˆ¬çڑ„مپھ種é،
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®و–™é‡‘ن½“ç³»مپ¯م€پن¸»مپ«ن»¥ن¸‹مپ®مƒ‘م‚؟مƒ¼مƒ³مپ«هˆ†مپ‘م‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
ن¸€و‹¬è«‹è² ه‹:
ه¦è،“ه¤§ن¼ڑمپھمپ©مپ®م‚¤مƒ™مƒ³مƒˆه…¨ن½“م‚’مپ¾مپ¨م‚پمپ¦ه§”託مپ™م‚‹ه½¢ه¼ڈمپ§مپ™م€‚ن¼پç”»مپ‹م‚‰ن؛‹ه¾Œه‡¦çگ†مپ¾مپ§م‚’ن¸€è²«مپ—مپ¦ن»»مپ›م‚‹مپںم‚پم€په…¨ن½“مپ§è²»ç”¨مپŒوڈگç¤؛مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚م‚¤مƒ™مƒ³مƒˆمپ®è¦ڈو¨،مپ«ه؟œمپکمپ¦و•°ç™¾ن¸‡ه††مپ‹م‚‰و•°هچƒن¸‡ه††مپ¨ه¹…مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
و¥ه‹™هˆ¥و–™é‡‘ه‹:
ن¼ڑه“،登録م€پو¼”é،Œç®،çگ†م€پم‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆهˆ¶ن½œمپھمپ©م€په€‹هˆ¥مپ®و¥ه‹™مپ”مپ¨مپ«è²»ç”¨مپŒè¨ه®ڑمپ•م‚Œم‚‹ه½¢ه¼ڈمپ§مپ™م€‚ه؟…è¦پمپھو¥ه‹™مپ مپ‘م‚’م‚¹مƒمƒƒمƒˆمپ§ن¾é ¼مپ—مپںمپ„ه ´هگˆمپ«éپ©مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
وœˆé،چه›؛ه®ڑه‹:
ه®ڑوœںçڑ„مپھن؛‹ه‹™ه±€و¥ه‹™م‚’継ç¶ڑçڑ„مپ«ه§”託مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ«وژ،用مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚وœˆم€…مپ®و¥ه‹™é‡ڈم‚„و‹…ه½“者مپ®ç¨¼هƒچو™‚é–“مپ«ه؟œمپکمپ¦م€پو•°ن¸‡ه††مپ‹م‚‰و•°هچپن¸‡ه††ç¨‹ه؛¦مپŒç›¸ه ´مپ§مپ™م€‚
複و•°مپ®م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چو¥è€…مپ‹م‚‰ç›¸è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹم‚’هڈ–م‚ٹم€پوڈگç¤؛مپ•م‚Œمپں費用مپ¨م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹ه†…ه®¹م‚’و¯”較و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
費用م‚’وٹ‘مپˆم‚‹مپںم‚پمپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆ
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®è²»ç”¨م‚’وٹ‘مپˆم‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پن»¥ن¸‹مپ®ç‚¹م‚’考و…®مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
ه§”託範ه›²مپ®وکژç¢؛هŒ–:
è‡ھه¦ن¼ڑمپ§ه¯¾ه؟œمپ§مپچم‚‹و¥ه‹™مپ¨م€په¤–部مپ«ه§”託مپ—مپںمپ„و¥ه‹™م‚’وکژç¢؛مپ«ç·ڑه¼•مپچمپ—م€په؟…è¦پوœ€ه°ڈé™گمپ®ç¯„ه›²مپ§ن¾é ¼مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§ç„،駄مپھم‚³م‚¹مƒˆم‚’ه‰ٹو¸›مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
و—©وœںمپ®ن¾é ¼مƒ»ن؛ˆç´„:
ه¤§è¦ڈو¨،مپھه¦ن¼ڑمپ®ه ´هگˆم€پé–‹ه‚¬مپ®و•°مƒ¶وœˆه‰چم€پمپ‚م‚‹مپ„مپ¯1ه¹´ن»¥ن¸ٹه‰چمپ«ن¾é ¼مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په‰²ه¼•مپŒéپ©ç”¨مپ•م‚Œمپںم‚ٹم€پم‚ˆم‚ٹ良مپ„و،ن»¶مپ§ه¥‘ç´„مپ§مپچم‚‹ه ´هگˆمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ITم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®و´»ç”¨:
ن¼ڑه“،ç®،çگ†م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚„م‚¤مƒ™مƒ³مƒˆç®،çگ†م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپھمپ©م‚’è‡ھه¦ن¼ڑمپ§ه°ژه…¥مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پن¸€éƒ¨مپ®و¥ه‹™م‚’هٹ¹çژ‡هŒ–مپ—م€پمپمپ®هˆ†م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ«و”¯و‰•مپ†è²»ç”¨م‚’ه‰ٹو¸›مپ§مپچم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚特مپ«م€پهˆوœں費用م‚„وœˆé،چ費用مپŒ0ه††مپ§هˆ©ç”¨مپ§مپچم‚‹م‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰ه‹مپ®م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚‚ه¢—مپˆمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®و´»ç”¨ن؛‹ن¾‹مپ¨وœ€éپ©مپھه¦ن¼ڑ
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ¯م€پو§کم€…مپھم‚؟م‚¤مƒ—مپ®ه¦ن¼ڑمپ§مپمپ®هٹ¹وœم‚’ç™؛وڈ®مپ—مپ¾مپ™م€‚
ه°ڈè¦ڈو¨،ه¦ن¼ڑمƒ»ن¸چه®ڑوœںé–‹ه‚¬مپ®ه¦ن¼ڑ
ن؛؛و‰‹م‚„مƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپŒé™گم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ه°ڈè¦ڈو¨،ه¦ن¼ڑم‚„م€پن¸چه®ڑوœںمپ«مپ—مپ‹é–‹ه‚¬مپ•م‚Œمپھمپ„ه¦ن¼ڑمپ¯م€پم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®وپ©وپµم‚’特مپ«هڈ—مپ‘م‚„مپ™مپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚éپ‹ه–¶çµŒé¨“مپŒه°‘مپھمپڈم€پو¯ژه›و‰‹وژ¢م‚ٹمپ§مپ®و؛–ه‚™مپ«مپھم‚ٹمپŒمپ،مپھه ´هگˆمپ§م‚‚م€په°‚é–€ه®¶مپ®مƒژم‚¦مƒڈم‚¦م‚’و´»ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پهٹ¹çژ‡çڑ„مپھو؛–ه‚™مپ¨ه††و»‘مپھéپ‹ه–¶مپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
ه›½éڑ›ه¦ن¼ڑ
وµ·ه¤–مپ‹م‚‰مپ®هڈ‚هٹ 者مپŒه¤ڑمپ„ه›½éڑ›ه¦ن¼ڑمپ¯م€پ言èھه¯¾ه؟œم‚„و™‚ه·®ه¯¾ه؟œم€پمƒ“م‚¶ç”³è«‹م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپھمپ©ç‰¹وœ‰مپ®èھ²é،ŒمپŒمپ‚م‚ٹم€پم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®و´»ç”¨مپŒéه¸¸مپ«هٹ¹وœçڑ„مپ§مپ™م€‚ه¤ڑ言èھه¯¾ه؟œمپ®هڈ‚هٹ 登録م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚„هگŒو™‚é€ڑ訳مپ®و‰‹é…چمپھمپ©م€په°‚é–€çڑ„مپھçں¥èکمپ¨çµŒé¨“مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œم‚‹مپںم‚پم€په›½éڑ›ه¯¾ه؟œمپ®مƒژم‚¦مƒڈم‚¦م‚’وŒپمپ¤م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چو¥è€…مپ«ن¾é ¼مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پم‚°مƒمƒ¼مƒگمƒ«م‚¹م‚؟مƒ³مƒ€مƒ¼مƒ‰مپ«ه‰‡مپ£مپںéپ‹ه–¶مپŒه®ںçڈ¾مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ«مپٹمپ™مپ™م‚پمپ®م‚·م‚¹مƒ†مƒ مƒ»مƒ„مƒ¼مƒ«
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®هٹ¹çژ‡م‚’مپ•م‚‰مپ«é«کم‚پم‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پéپ©هˆ‡مپھم‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚„مƒ„مƒ¼مƒ«مپ®و´»ç”¨مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚ن»£è،Œن¼ڑ社مپŒوڈگن¾›مپ™م‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚„م€پè‡ھه¦ن¼ڑمپ§ه°ژه…¥م‚’و¤œè¨ژمپ§مپچم‚‹مƒ„مƒ¼مƒ«مپ«مپ¯ن»¥ن¸‹مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚‚مپ®مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰ه‹مپ®هڈ‚هٹ 登録مƒ»ن¼ڑè²»و±؛و¸ˆم‚·م‚¹مƒ†مƒ
هڈ‚هٹ 登録مپ‹م‚‰ن¼ڑè²»و±؛و¸ˆمپ¾مپ§م‚’م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مپ§ن¸€ه…ƒç®،çگ†مپ§مپچم‚‹م‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰ه‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¯م€پم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®و¥ه‹™هٹ¹çژ‡هŒ–مپ«ه¤§مپچمپڈ貢献مپ—مپ¾مپ™م€‚24و™‚é–“مپ„مپ¤مپ§م‚‚登録مƒ»و±؛و¸ˆمپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھم‚‹مپںم‚پم€پن؛‹ه‹™ه±€مپ®و‰‹ن½œو¥مپŒه¤§ه¹…مپ«ه‰ٹو¸›مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پم‚¯مƒ¬م‚¸مƒƒمƒˆم‚«مƒ¼مƒ‰م‚„م‚³مƒ³مƒ“مƒ‹و±؛و¸ˆمپھمپ©ه¤ڑو§کمپھو±؛و¸ˆو–¹و³•مپ«ه¯¾ه؟œمپ§مپچم‚‹مپںم‚پم€پهڈ‚هٹ 者مپ®هˆ©ن¾؟و€§م‚‚هگ‘ن¸ٹمپ—مپ¾مپ™م€‚
و¼”é،Œç®،çگ†م‚·م‚¹مƒ†مƒ
و¼”é،Œï¼ˆوٹ„録)مپ®م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³وٹ•ç¨؟هڈ—ن»کم€پوں»èھمƒ—مƒم‚»م‚¹مپ®ç®،çگ†م€پمƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ ç·¨وˆگمپھمپ©م‚’م‚·م‚¹مƒ†مƒ ن¸ٹمپ§è،Œمپˆم‚‹و¼”é،Œç®،çگ†م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¯م€په¦è،“ه¤§ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®è² و‹…م‚’軽و¸›مپ—مپ¾مپ™م€‚و‰‹ن½œو¥مپ§مپ®مƒ‡مƒ¼م‚؟ه…¥هٹ›م‚„連çµ،مپŒن¸چè¦پمپ«مپھم‚ٹم€پمƒںم‚¹مپ®ه‰ٹو¸›مپ¨هٹ¹çژ‡هŒ–مپŒه›³م‚Œمپ¾مپ™م€‚
م‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆو§‹ç¯‰مƒ»ç®،çگ†م‚·م‚¹مƒ†مƒ
ه¦ن¼ڑمپ®م‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆم‚’ه®¹وک“مپ«و§‹ç¯‰مƒ»و›´و–°مپ§مپچم‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚‚é‡چè¦پمپ§مپ™م€‚وœ€و–°وƒ…ه ±مپ®ç™؛ن؟،م€پمƒ—مƒم‚°مƒ©مƒ مپ®ه…¬é–‹م€پهڈ‚هٹ 登録مپ¸مپ®èھکه°ژمپھمپ©م€پم‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆمپ¯ه¦ن¼ڑمپ®é،”مپ¨مپھم‚‹مپںم‚پم€پن½؟مپ„م‚„مپ™مپڈم€په¸¸مپ«وœ€و–°مپ®وƒ…ه ±م‚’وڈگن¾›مپ§مپچم‚‹م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپŒم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ«مپٹمپ„مپ¦ن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚
مپ¾مپ¨م‚پï¼ڑم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ§ه¦ن¼ڑمپ®وœھو¥م‚’ه…±مپ«ç¯‰مپڈ
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ¯م€په¦ن¼ڑمپŒç›´é¢مپ™م‚‹و§کم€…مپھèھ²é،Œمپ«ه¯¾مپ—م€په¼·هٹ›مپھ解و±؛ç–م‚’وڈگن¾›مپ—مپ¾مپ™م€‚煩雑مپھو¥ه‹™مپ‹م‚‰مپ®è§£و”¾م€پéپ‹ه–¶مپ®è³ھمپ®هگ‘ن¸ٹم€پمپمپ—مپ¦é™گم‚‰م‚Œمپںمƒھم‚½مƒ¼م‚¹مپ®وœ€éپ©هŒ–مپ¯م€په¦ن¼ڑمپŒوœ¬و¥مپ®ç›®çڑ„مپ§مپ‚م‚‹ه¦è،“مپ®ç™؛ه±•مپ¨ç ”究者間مپ®ن؛¤وµپمپ«é›†ن¸مپ§مپچم‚‹ç’°ه¢ƒم‚’و•´مپˆم‚‹ن¸ٹمپ§ن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚
وœ¬è¨کن؛‹مپ§è§£èھ¬مپ—مپںم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹ه†…ه®¹م€پمƒ،مƒھمƒƒمƒˆمƒ»مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم€پ費用相ه ´م€پمپمپ—مپ¦مپٹمپ™مپ™م‚پمƒ„مƒ¼مƒ«م‚’هڈ‚考مپ«م€پè²´ه¦ن¼ڑمپ«وœ€éپ©مپھمƒ‘مƒ¼مƒˆمƒٹمƒ¼م‚’見مپ¤مپ‘مپ¦مپڈمپ مپ•مپ„م€‚éپ©هˆ‡مپھم€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶ن»£è،Œم€چمپ®و´»ç”¨مپ¯م€په¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®è² و‹…م‚’軽و¸›مپ™م‚‹مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€په¦è،“م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹مƒ†م‚£ه…¨ن½“مپ®و´»و€§هŒ–م€پمپمپ—مپ¦م‚ˆم‚ٹè±ٹمپ‹مپھوœھو¥م‚’築مپڈمپںم‚پمپ®é‡چè¦پمپھن¸€و©مپ¨مپھم‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚