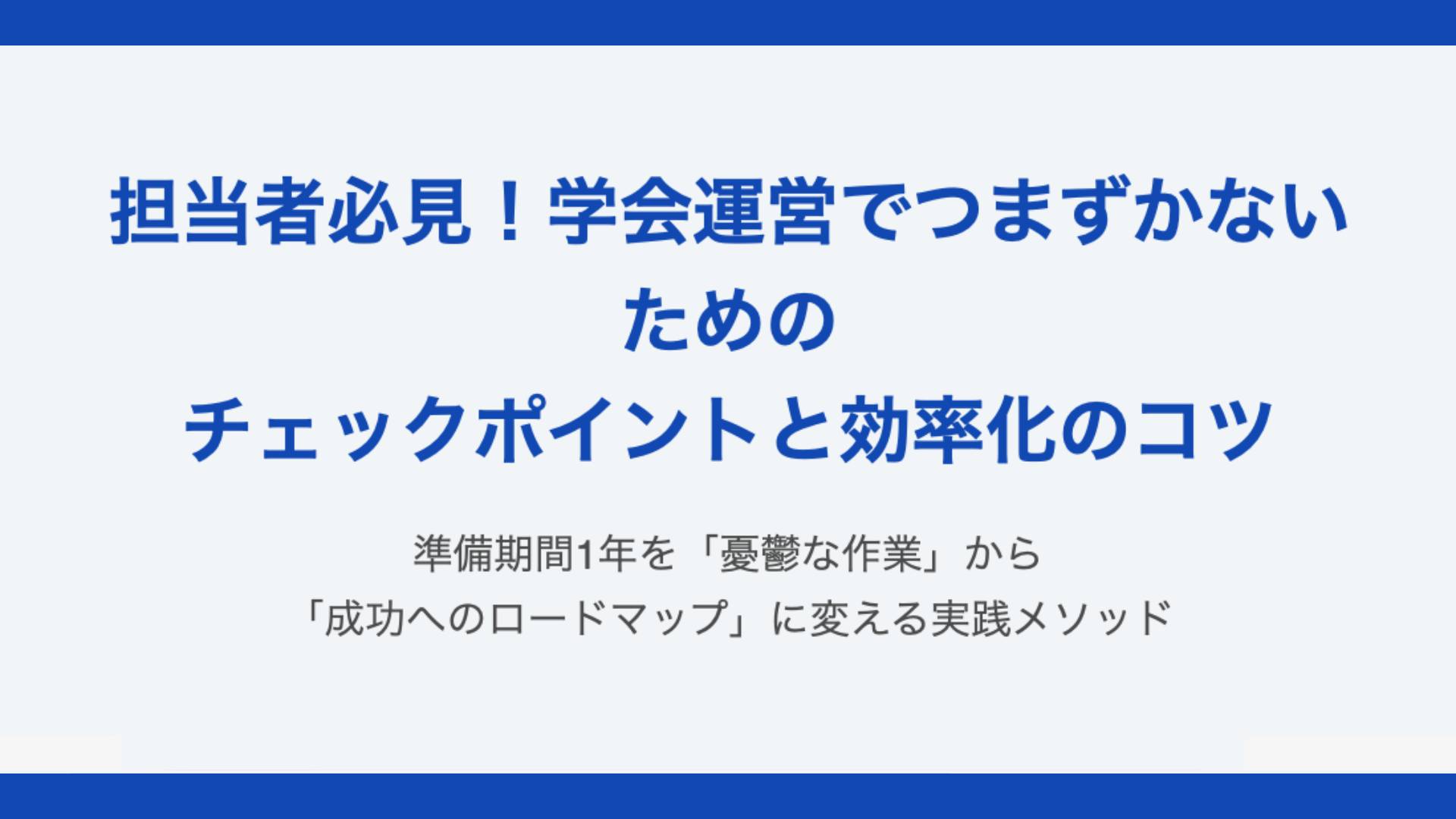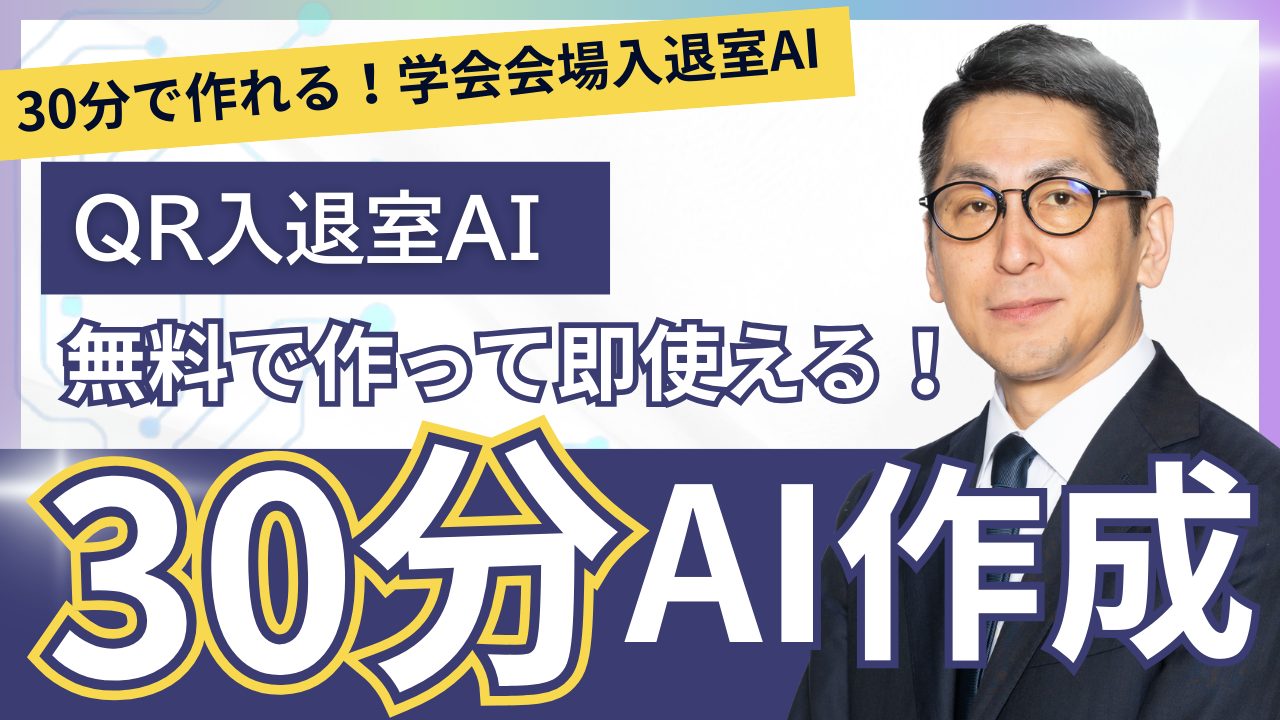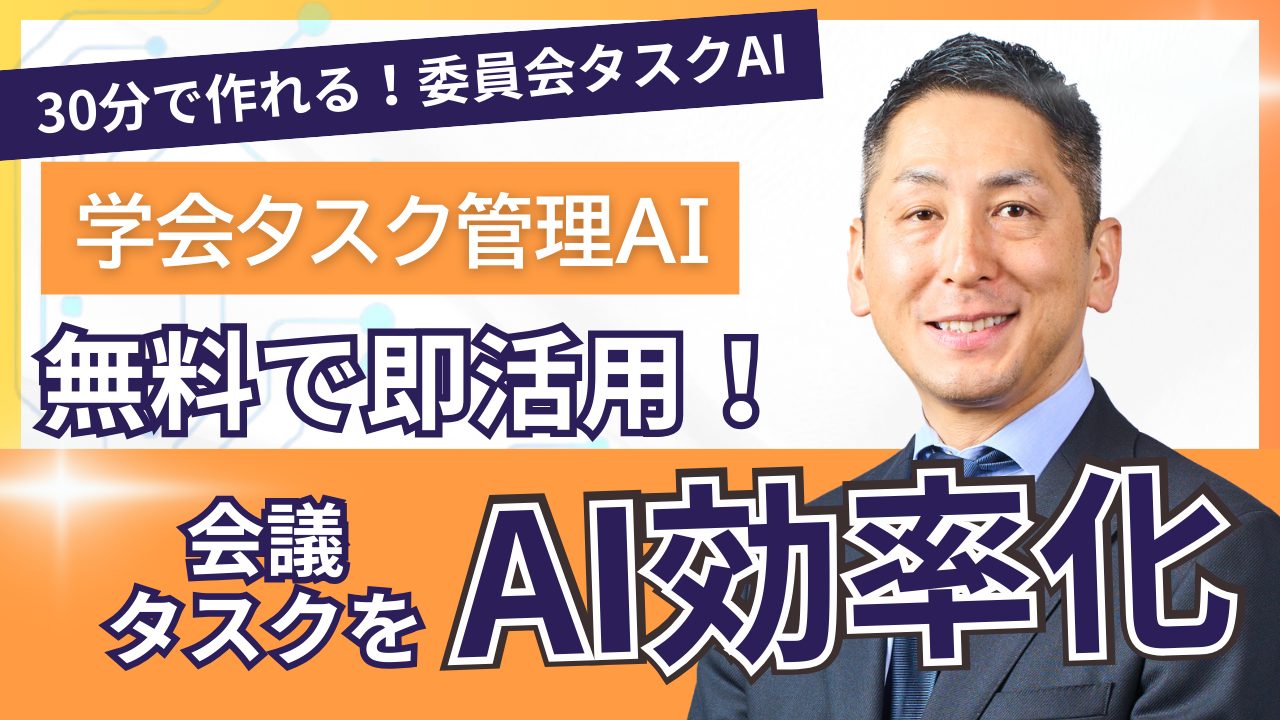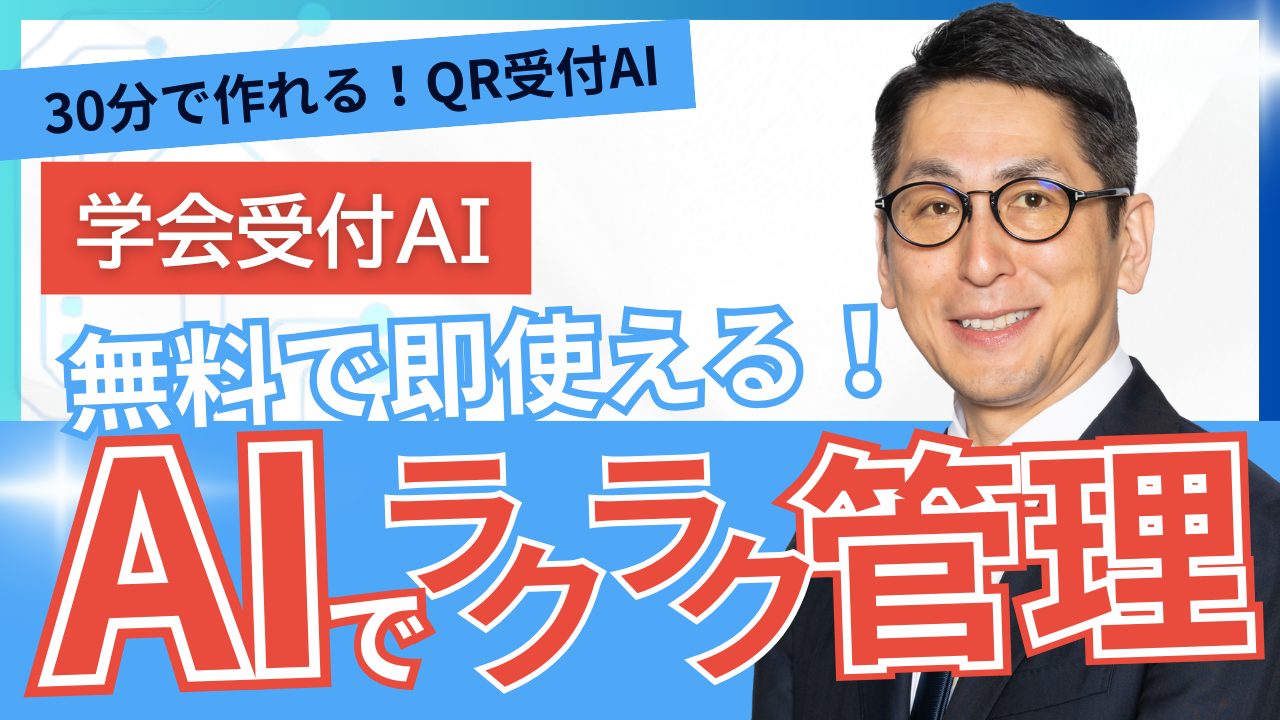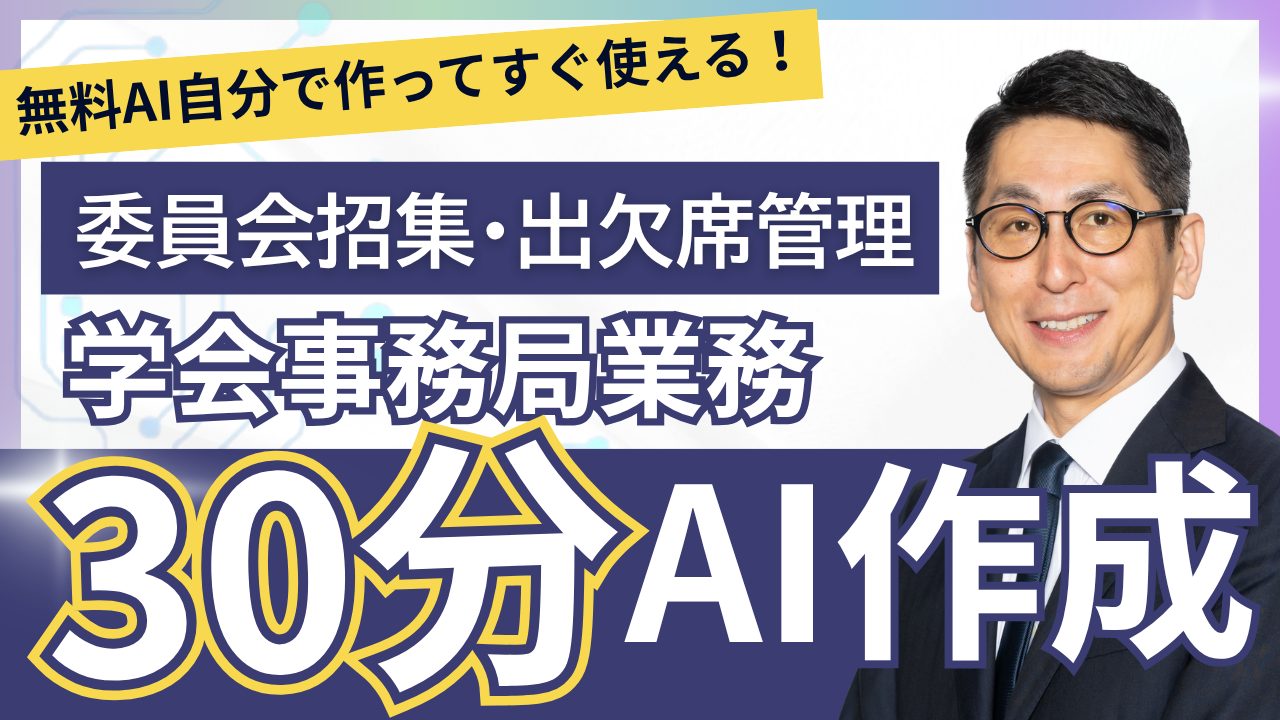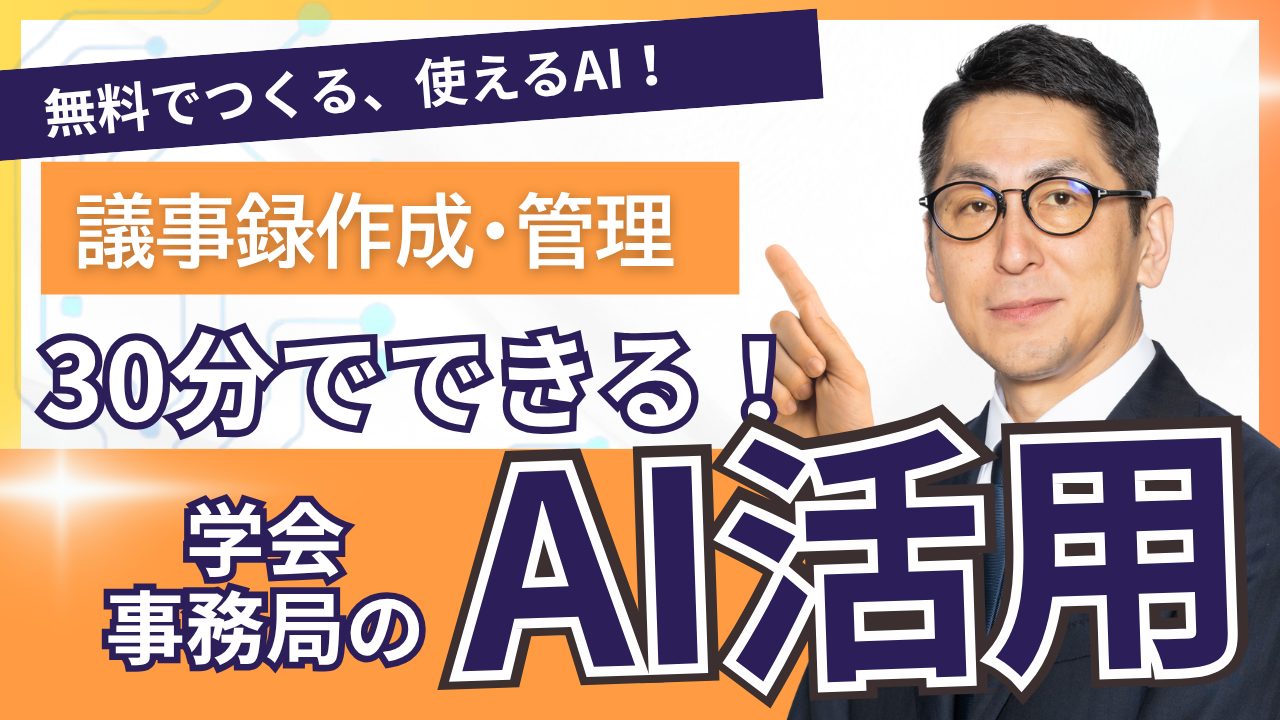ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه¤–部ه§”託م‚’見直مپ™Q&Aï¼ڑم‚ˆمپڈمپ‚م‚‹ç–‘ه•ڈ17مپ«مپٹç”مپˆمپ—مپ¾مپ™
2025ه¹´08وœˆ28و—¥
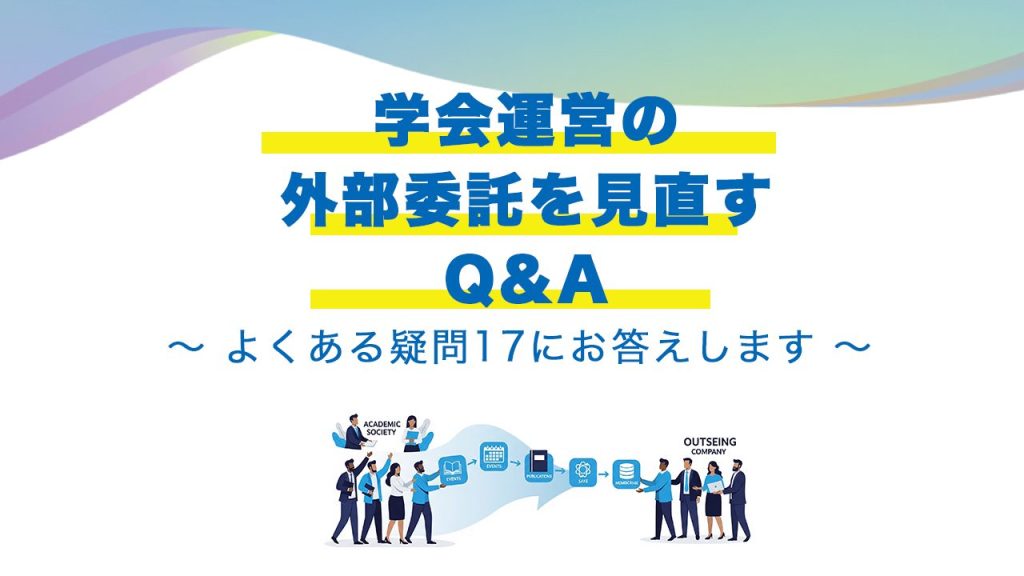
مپ¯مپکم‚پمپ«
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه¤–部ه§”託مپ¯م€پو¥ه‹™هٹ¹çژ‡هŒ–م‚„ه°‚é–€و€§مپ®هگ‘ن¸ٹمپ«مپ¤مپھمپŒم‚‹وœ‰هٹ¹مپھو‰‹و®µمپ§مپ™م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پمپ„مپ–و¤œè¨ژم‚’ه§‹م‚پم‚‹مپ¨م€Œè²»ç”¨مپ¯مپ©م‚Œمپڈم‚‰مپ„مپ‹مپ‹م‚‹مپ®ï¼ںم€چم€Œن¸ه°ڈè¦ڈو¨،مپ®ه¦ن¼ڑمپ§م‚‚هڈ¯èƒ½مپھمپ®ï¼ںم€چمپ¨مپ„مپ£مپںç–‘ه•ڈم‚„ن¸چه®‰مپŒمپ¤مپچم‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚
مپ“مپ®Q&Aمپ§مپ¯م€پوœ€و–°مپ®و³•ن»¤مƒ»è¦ڈهˆ¶ه‹•هگ‘(وœ¬ç¨؟هں·ç†و™‚点;2025ه¹´ï¼‰م‚‚è¸ڈمپ¾مپˆه¤–部ه§”託م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپ«مپ‚مپںمپ£مپ¦م€Œم‚ˆمپڈمپ‚م‚‹ç–‘ه•ڈ17م€چمپ«مپٹç”مپˆمپ—م€په…·ن½“çڑ„مپھمƒ’مƒ³مƒˆمپ¨و¬،مپ®م‚¹مƒ†مƒƒمƒ—مپ«é€²م‚€مپںم‚پمپ®وƒ…ه ±م‚’وڈگن¾›مپ—مپ¾مپ™م€‚
ه°ڑم€پAIمƒھم‚¹م‚¯م‚„م‚»م‚مƒ¥مƒھمƒ†م‚£ه¯¾ه؟œمپ¨مپ„مپ£مپںو–°وٹ€è،“و´»ç”¨ن¸ٹمپ®و³¨و„ڈ点مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€په·»وœ«م‚³مƒ©مƒ مپ§è©³مپ—مپڈ解èھ¬مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™مپ®مپ§م€پ詳細مپ¯مپمپ،م‚‰م‚‚مپ”覧مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
مپ“مپ®Q&Aم‚’هڈ‚考مپ«مپ™م‚Œمپ°م€په¤–部ه§”託مپ®مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمƒ»مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم€پ費用مپ®ç›¸ه ´م€په¥‘ç´„ن¸ٹمپ®و³¨و„ڈ点مپھمپ©م€پمپ¤مپ¾مپڑمپچمپŒمپ،مپھç–‘ه•ڈمپ®ç”مپˆمپŒè¦‹مپ¤مپ‹م‚‹مپ¯مپڑمپ§مپ™م€‚
م€ٹç›®و¬،م€‹
â… . هں؛وœ¬çگ†è§£ç·¨
Q1ï¼ڑه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه¤–部ه§”託مپ«مپ¯م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھمƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¨مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™مپ‹ï¼ں
Q2ï¼ڑن¸ه°ڈè¦ڈو¨،مپ®ه¦ن¼ڑمپ§م‚‚ه¤–部ه§”託مپ¯هڈ¯èƒ½مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
A2ï¼ڑمپ¯مپ„م€پم‚€مپ—م‚چهٹ¹وœمپ¯ه¤§مپچمپ„مپ§مپ™م€‚
â…،. 費用مƒ»م‚³م‚¹مƒˆç®،çگ†ç·¨
Q3ï¼ڑه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه¤–部ه§”託مپ«مپ‹مپ‹م‚‹è²»ç”¨مپ®ç›¸ه ´مپ¯مپ©م‚Œمپڈم‚‰مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
A3ï¼ڑ相ه ´و—©è¦‹è،¨مپ§مƒپم‚§مƒƒم‚¯
Q4ï¼ڑه¤–部ه§”託費用مپ®ç®—ه‡؛هں؛و؛–مپ¯مپ©مپ†è€ƒمپˆمپںم‚‰è‰¯مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
A4ï¼ڑ3مپ¤مپ®è¦پç´ مپ§و±؛مپ¾م‚ٹمپ¾مپ™
Q5ï¼ڑه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œéڑ م‚Œم‚³م‚¹مƒˆم€چمپ«مپ¯م€پمپ©م‚“مپھم‚‚مپ®مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ں
A5ï¼ڑ見مپˆمپھمپ„م‚³م‚¹مƒˆم‚’م€Œè¦‹مپˆم‚‹هŒ–م€چ
Q6ï¼ڑه§”託費用م‚’وٹ‘مپˆم‚‹مپںم‚پمپ«م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھه·¥ه¤«مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™مپ‹ï¼ں
A6ï¼ڑو¥ه‹™مپ®ه„ھه…ˆé †ن½چن»کمپ‘مپ¨AIو´»ç”¨
Q7ï¼ڑه¤–部ه§”託مپ—مپںمپ„مپ‘م‚Œمپ©ن؛ˆç®—مپŒè¶³م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚資金èھ؟éپ”مپ¯مپ©مپ†مپ™م‚Œمپ°è‰¯مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
A7ï¼ڑ複و•°çµ„مپ؟هگˆم‚ڈمپ›مپ«م‚ˆم‚‹و¤œè¨ژ
â…¢. ه§”託ه…ˆéپ¸ه®ڑمƒ»ه¥‘ç´„ç·¨
Q8ï¼ڑه¤–部ه§”託مپ®م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ¯م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«éپ¸مپ¹مپ°è‰¯مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
Q9ï¼ڑه¤–部ه§”託م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹éڑ›م€پ特مپ«و³¨و„ڈمپ™مپ¹مپچه¥‘ç´„ن¸ٹمپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ¯ن½•مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
Q10ï¼ڑه¤–部ه§”託مپ®éڑ›مپ®ن¼ڑه“،ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±مپ®هڈ–م‚ٹو‰±مپ„مپŒن¸چه®‰مپ§مپ™م€‚مپ©مپ“مپ¾مپ§é–‹ç¤؛مپ™م‚‹مپ¹مپچمپ§مپ™مپ‹ï¼ں
A10ï¼ڑوœ€ه°ڈé™گمپ®وƒ…ه ±مپ«é™گه®ڑ
Q11ï¼ڑمƒ¨مƒ¼مƒمƒƒمƒ‘(ن¸»مپ«EUهœڈه†…)مپ‹م‚‰مپ®ه¦ن¼ڑهڈ‚هٹ 者(講و¼”者م‚‚هگ«م‚€ï¼‰م‚’هڈ—مپ‘ه…¥م‚Œم‚‹éڑ›مپ«DPO(مƒ‡مƒ¼م‚؟ن؟è·è²¬ن»»è€…)مپ®ه¤–部ه§”託مپ¯هڈ¯èƒ½مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ں
A11ï¼ڑمپ¯مپ„م€په°‚é–€ه®¶مپ¸مپ®ه§”託مپŒهڈ¯èƒ½مپ§مپ™
â…£. مƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†ç·¨
Q12ï¼ڑه¤–部ه§”託مپ«ن¼´مپ†مƒھم‚¹م‚¯مپ«مپ¯مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚‚مپ®مپŒمپ‚م‚ٹم€پمپ©مپ†ه¯¾ç–مپ™م‚Œمپ°è‰¯مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
A12ï¼ڑ5مپ¤مپ®ن¸»è¦پمƒھم‚¹م‚¯مپ¨ه¯¾ç–
â…¤. éپ‹ه–¶ن½“هˆ¶مƒ»هچ”هƒچç·¨
Q13ï¼ڑه¤–部ه§”託م‚’مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په†…部مپ®éپ‹ه–¶م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ®ه½¹ه‰²مپ¯مپ©مپ†ه¤‰م‚ڈم‚ٹمپ¾مپ™مپ‹ï¼ں
A13ï¼ڑن؛‹ه‹™ن½œو¥مپ‹م‚‰وˆ¦ç•¥ç–ه®ڑمپ¸
Q14ï¼ڑه§”託ه…ˆمپ¨مپ®هچ”هƒچم‚’進م‚پم‚‹ن¸ٹمپ§مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ¯ن½•مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
A14ï¼ڑمƒ‘مƒ¼مƒˆمƒٹمƒ¼م‚·مƒƒمƒ—و§‹ç¯‰مپŒéچµ
Q15ï¼ڑه¤–部ه§”託مپ—مپںن؛‹ه‹™ه±€مپ®و¥ه‹™ه“پè³ھمپ¯م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«è©•ن¾،مپ™م‚Œمپ°è‰¯مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
A15ï¼ڑه®ڑé‡ڈمƒ»ه®ڑو€§è©•ن¾،مپŒهٹ¹وœçڑ„
â…¥. 特ه®ڑو¥ه‹™مپ®ه§”託ن؛‹ن¾‹ç·¨
Q16ï¼ڑه¤–部مپ‹م‚‰è¬›و¼”者م‚’و‹›مپڈéڑ›م€په§”託مپ§مپچم‚‹و¥ه‹™مپ«مپ¯ن½•مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™مپ‹ï¼ں
A16ï¼ڑو—…è²»مƒ»و‰‹é…چمپ‹م‚‰ه½“و—¥مپ®م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ¾مپ§
Q17ï¼ڑè¨ک者ç™؛è،¨م‚„مƒم‚¹م‚³مƒںمپ¨مپ®ه¯¾ه؟œمپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®ه§”託مپ¯هڈ¯èƒ½مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
A17ï¼ڑمپ¯مپ„م€په؛ƒه ±مپ®ه°‚é–€ه®¶مپ«ن»»مپ›م‚‰م‚Œمپ¾مپ™
م€گه·»وœ«م‚³مƒ©مƒ م€‘ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹AIمƒھم‚¹م‚¯مپ¾مپ¨م‚پ & مƒپم‚§مƒƒم‚¯مƒھم‚¹مƒˆ
Q1ï¼ڑه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه¤–部ه§”託مپ«مپ¯م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھمƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¨مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™مپ‹ï¼ں
ه¤–部ه§”託مپ«مپ¯م€پو¥ه‹™هٹ¹çژ‡هŒ–م‚„م‚³م‚¹مƒˆه‰ٹو¸›مپ¨مپ„مپ£مپںمƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپŒمپ‚م‚‹ن¸€و–¹مپ§م€پمƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپ®è“„ç©چم‚„م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³م‚³م‚¹مƒˆمپ¨مپ„مپ£مپںمƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚‚هکهœ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰م‚’ن؛‹ه‰چمپ«çگ†è§£مپ—مپ¦مپٹمپڈمپ“مپ¨مپŒم€په§”託م‚’وˆگهٹںمپ•مپ›م‚‹éچµمپ¨مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
| هˆ†é، | مƒ،مƒھمƒƒمƒˆ | مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆ |
| و¥ه‹™هٹ¹çژ‡ | مƒ«مƒ¼مƒ†م‚£مƒ³مƒ¯مƒ¼م‚¯م‚’ه§”託مپ—م€پو•™èپ·ه“،مƒ»ç ”究者مپ¯وœ¬و¥مپ«é›†ن¸مپ§مپچم‚‹ ه°‚é–€ه®¶مپ«م‚ˆم‚‹هٹ¹çژ‡çڑ„مپھو¥ه‹™éپ‚è،ŒمپŒهڈ¯èƒ½ | ه¤–部و¥è€…مپ¨مپ®é€£وگ؛م‚„وƒ…ه ±ه…±وœ‰مپ«و‰‹é–“مپ¨و™‚é–“مپŒç™؛ç”ںمپ™م‚‹ |
| ه°‚é–€و€§ مƒژم‚¦مƒڈم‚¦ | ه¦ن¼ڑمپ«مپھمپ„ه°‚é–€çڑ„مپھçں¥èکم‚„وœ€و–°وٹ€è،“(Webم€په؛ƒه ±مپھمپ©ï¼‰م‚’و´»ç”¨مپ§مپچم‚‹ | 組織ه†…مپ«مƒژم‚¦مƒڈم‚¦م‚„çں¥èک(وڑ—é»™çں¥ï¼‰مپŒè“„ç©چمپ•م‚Œمپ«مپڈمپ„ |
| éپ‹ه–¶ن½“هˆ¶ | و‹…ه½“者مپ®ç•°ه‹•م‚„退èپ·مپ«م‚ˆم‚‹و¥ه‹™مپ®م€Œه±ن؛؛هŒ–م€چم‚’éک²مپژم€پéپ‹ه–¶مپŒه®‰ه®ڑمپ™م‚‹ | و¥ه‹™çµ‚ن؛†و™‚مپ®م‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپھه¼•مپچ継مپژو؛–ه‚™مپŒه؟…è¦پمپ«مپھم‚‹ |
| م‚³م‚¹مƒˆ | 見مپˆمپ«مپڈمپ„ن؛؛ن»¶è²»م‚„é–“وژ¥م‚³م‚¹مƒˆï¼ˆéڑ م‚Œم‚³م‚¹مƒˆï¼‰م‚’ه‰ٹو¸›مپ§مپچم‚‹ | ه¤–部ه§”託費用مپŒç™؛ç”ںمپ™م‚‹ |
| ه¼•مپچ継مپژ | ه®ڑوœںçڑ„مپھمƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«و›´و–°مپ«م‚ˆم‚ٹم€پو¥ه‹™ه†…ه®¹مپŒم€Œه±ن؛؛هŒ–م€چمپ›مپڑم€پم‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپھه¼•مپچ継مپژمپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھم‚‹ | و¥ه‹™çµ‚ن؛†و™‚مپ®م‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپھه¼•مپچ継مپژو؛–ه‚™مپŒه؟…è¦پمپ«مپھم‚‹ و¥ه‹™çµ‚ن؛†و™‚مپ®وƒ…ه ±مپ®ه¼•مپچ継مپژمپ«و‰‹é–“م‚„費用مپŒمپ‹مپ‹م‚‹ |
مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¨مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚’و¯”較مپ—م€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®ه¦ن¼ڑمپ«مپ¨مپ£مپ¦مپ©مپ،م‚‰مپ®هپ´é¢مپŒه¤§مپچمپ„مپ‹م‚’هˆ¤و–مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒه¤§هˆ‡مپ§مپ™م€‚
م€گ補足م€‘ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹و¥ه‹™ه§”託مپ®مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¨èھ²é،Œ
مƒ،مƒھمƒƒمƒˆ
- و¥ه‹™هٹ¹çژ‡مپ®هگ‘ن¸ٹï¼ڑه§”託ه…ˆمپ«مƒ«مƒ¼مƒ†م‚£مƒ³مƒ¯مƒ¼م‚¯م‚’ن»»مپ›م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پو•™èپ·ه“،م‚„ç ”ç©¶è€…مپ¯وœ¬و¥مپ®ç ”究مƒ»و•™è‚²و´»ه‹•مپ«é›†ن¸مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
- ه°‚é–€و€§مپ®و´»ç”¨ï¼ڑن¼ڑه“،ç®،çگ†م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚„Webم‚µم‚¤مƒˆمپ®وœ€و–°وٹ€è،“م€په؛ƒه ±مپ®مƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپھمپ©م€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®ه¦ن¼ڑمپ«مپ¯مپھمپ„ه°‚é–€çڑ„مپھçں¥èکم‚„م‚¹م‚مƒ«مپŒو´»ç”¨مپ§مپچم‚‹و©ںن¼ڑمپŒه¾—م‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
- éپ‹ه–¶مپ®ه®‰ه®ڑهŒ–ï¼ڑو‹…ه½“者مپ®ç•°ه‹•م‚„退èپ·مپ«م‚ˆم‚‹و¥ه‹™مپ®م€Œه±ن؛؛هŒ–م€چم‚’éک²مپژم€پéپ‹ه–¶ن½“هˆ¶مپ®ه®‰ه®ڑم‚’ç›®وŒ‡مپ›مپ¾مپ™م€‚
- م‚³م‚¹مƒˆه‰ٹو¸›ï¼ڑه°‚é–€ه®¶مپ«م‚ˆم‚‹هٹ¹çژ‡çڑ„مپھو¥ه‹™éپ‚è،Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پ見مپˆمپ«مپڈمپ„ن؛؛ن»¶è²»م‚„é–“وژ¥م‚³م‚¹مƒˆç‰مپ®م€Œéڑ م‚Œم‚³م‚¹مƒˆم€چمپ®ه‰ٹو¸›مپ«مپ¤مپھمپŒم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆ
- م‚³م‚¹مƒˆمپ®ç™؛ç”ںï¼ڑه¤–部ه§”託مپ«مپ¯è²»ç”¨مپŒç™؛ç”ںمپ—مپ¾مپ™م€‚مپںمپ مپ—م€پ費用ه¯¾هٹ¹وœم‚’考و…®مپ™م‚Œمپ°م€پهچکç´”مپھم‚³م‚¹مƒˆم‚¢مƒƒمƒ—مپ«مپ¯مپھم‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚
- مƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپ®è“„ç©چï¼ڑه¤–部مپ«و¥ه‹™م‚’ه§”託مپ™م‚‹مپ¨م€پمپمپ®éپژ程مپ§ه¾—م‚‰م‚Œمپںمƒژم‚¦مƒڈم‚¦م‚„çں¥èکمپŒم€پ組織ه†…مپ«è“„ç©چمپ•م‚Œمپ«مپڈمپ„مپ¨مپ„مپ†èھ²é،ŒمپŒç”ںمپکمپ¾مپ™م€‚特مپ«م€پ言èھهŒ–مپ—مپ¥م‚‰مپ„経験ه‰‡م‚„م‚³مƒ„مپ¨مپ„مپ£مپںم€Œوڑ—é»™çں¥م€چمپ¯م€په¤–部مپ«وµپه‡؛مپ—مپŒمپ،مپ§مپ™م€‚مپ“مپ®èھ²é،Œم‚’ه…‹وœچمپ™م‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯AIمپ®و´»ç”¨مپŒوœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚AIمپ¯و§کم€…مپھمƒ‡مƒ¼م‚؟(ه ±ه‘ٹو›¸م€پè°ن؛‹éŒ²م€پمƒپمƒ£مƒƒمƒˆمپ®ه±¥و´مپھمپ©ï¼‰م‚’è‡ھه‹•çڑ„مپ«هˆ†وگمپ—م€پمپمپ“مپ«هں‹م‚‚م‚Œمپ¦مپ„م‚‹وڑ—é»™çں¥م‚’وٹ½ه‡؛مپ—م€پم€Œه½¢ه¼ڈçں¥م€چمپ¨مپ—مپ¦مƒٹمƒ¬مƒƒم‚¸مƒ™مƒ¼م‚¹ï¼ˆknowledge base)مپ«è“„ç©چمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
- م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³م‚³م‚¹مƒˆï¼ڑه¤–部و¥è€…مپ¨مپ®é€£وگ؛م‚„وƒ…ه ±ه…±وœ‰مپ«و‰‹é–“م‚„و™‚é–“مپŒç™؛ç”ںمپ—مپ¾مپ™م€‚مپںمپ مپ—م€پوœ€éپ©مپھم‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³مƒ»مƒ„مƒ¼مƒ«مپ®هˆ©ç”¨مپ§م‚³م‚¹مƒˆهœ§ç¸®مپ¯ه……هˆ†مپ«هڈ¯èƒ½مپ§مپ™م€‚
- وƒ…ه ±مپ®ه¼•مپچ継مپژï¼ڑو¥ه‹™ه§”託م‚’終ن؛†مپ™م‚‹éڑ›م€پم‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپھه¼•مپچ継مپژمپ®مپںم‚پمپ®و؛–ه‚™مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚ن¸€و–¹مپ§م€پمƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«م‚’م€Œو¼ڈم‚Œمپھمپڈم€چم€Œمƒ€مƒ–مƒھمپھمپڈم€چم€Œهˆ†مپ‹م‚ٹم‚„مپ™مپڈم€چو•´ه‚™مپ—م€په®ڑوœںçڑ„مپ«م‚¢مƒƒمƒ—مƒ‡مƒ¼مƒˆمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§ه¼•مپچ継مپژم‚‚ه®¹وک“مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م€ٹمپ”و،ˆه†…م€‹
Q2ï¼ڑن¸ه°ڈè¦ڈو¨،مپ®ه¦ن¼ڑمپ§م‚‚ه¤–部ه§”託مپ¯هڈ¯èƒ½مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
مپ¯مپ„م€‚ن؛‹ه‹™ه±€م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ®è² و‹…مپŒه¤§مپچمپ„ن¸ه°ڈè¦ڈو¨،ه¦ن¼ڑمپ»مپ©م€په¤–部ه§”託مپ§éپ‹ه–¶هٹ¹çژ‡هŒ–م‚„è³ھهگ‘ن¸ٹمپ®هٹ¹وœمپŒه¤§مپچمپڈçڈ¾م‚Œمپ¾مپ™م€‚
ه¤–部ه§”託مپ¯ه¤§è¦ڈو¨،مپھه¦ن¼ڑمپ مپ‘مپ®م‚‚مپ®مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚م‚€مپ—م‚چم€پن؛‹ه‹™ه±€مپ®م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپŒه°‘مپھمپڈم€پن¸€ن؛؛مپ‚مپںم‚ٹمپ®و¥ه‹™è² و‹…مپŒه¤§مپچمپ„ن¸ه°ڈè¦ڈو¨،مپ®ه¦ن¼ڑمپ»مپ©م€پن؛‹ه‹™ه±€ن»£è،Œمپ®هٹ¹وœمپ¯ه¤§مپچمپڈمپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م‚³م‚¢مپ¨مپھم‚‹ç ”究و´»ه‹•مپ«و³¨هٹ›مپ™م‚‹مپںم‚پم€پن¼ڑه“،ç®،çگ†م‚„ن¼ڑ計ه‡¦çگ†مپ¨مپ„مپ£مپںمƒ«مƒ¼مƒ†م‚£مƒ³مƒ¯مƒ¼م‚¯م‚’ه°‚é–€و¥è€…مپ«ه§”託مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پéپ‹ه–¶مپ®هٹ¹çژ‡هŒ–مپ¨è³ھمپ®هگ‘ن¸ٹمپŒوœںه¾…مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
وœ€è؟‘مپ§مپ¯م€پن¸ه°ڈè¦ڈو¨،مپ®ه¦ن¼ڑهگ‘مپ‘مپ«م€په؟…è¦پمپھو¥ه‹™مپ مپ‘م‚’وں”è»ںمپ«éپ¸مپ¹م‚‹مƒ—مƒ©مƒ³م‚’用و„ڈمپ—مپ¦مپ„م‚‹و¥è€…م‚‚ه¢—مپˆمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپڑمپ¯م€پçڈ¾هœ¨مپ®و¥ه‹™ه†…ه®¹م‚’و•´çگ†مپ—م€پ特مپ«è² و‹…مپ«و„ںمپکمپ¦مپ„م‚‹و¥ه‹™مپ‹م‚‰ه¤–部ه§”託م‚’و¤œè¨ژمپ—مپ¦مپ؟م‚‹مپ®مپŒè‰¯مپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚ن¾‹مپˆمپ°م€په¦ن¼ڑèھŒم‚„ه¦è،“ن¼ڑè°مپ®è«–و–‡é›†مپ®م‚ˆمپ†مپھم€پ編集م‚„و ،و£مپŒن½•ه؛¦م‚‚و±‚م‚پم‚‰م‚Œم‚‹م‚؟م‚¹م‚¯م‚’هچ°هˆ·ن¼ڑ社م‚„ه‡؛版社مپ¨وڈگوگ؛مپ—مپ¦è² و‹…م‚’軽و¸›مپ™م‚‹مپ®م‚‚وœ‰هٹ¹مپھو–¹و³•مپ§مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»ه¦ن¼ڑمپ®ن؛‹ه‹™ه±€ن»£è،Œم‚„ه§”託م‚’و¤œè¨ژمپ—مپ¦مپ„م‚‹و–¹مپ¸ï¼پ費用م‚„م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’ه¾¹ه؛•è§£èھ¬ï½œمپ“م‚Œمپ‹م‚‰مپ®ه¦ن¼ڑ.com
مƒ»م€گه¦ن¼ڑèھŒهچ°هˆ·م€‘費用مƒ»ن¾،و ¼مپ®ن»•çµ„مپ؟|相ه ´مپ¨ه†…訳م€پم‚³م‚¹مƒˆه‰ٹو¸›مپ®مƒ’مƒ³مƒˆ4éپ¸ï½œو—¥وœ¬هچ°هˆ·ه‡؛版و ھه¼ڈن¼ڑ社
Q3ï¼ڑه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه¤–部ه§”託مپ«مپ‹مپ‹م‚‹è²»ç”¨مپ®ç›¸ه ´مپ¯مپ©م‚Œمپڈم‚‰مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه¤–部ه§”託費用مپ¯م€پè¦ڈو¨،مƒ»و¥ه‹™ه†…ه®¹مپ«م‚ˆم‚ٹوœˆé،چ5ï½10ن¸‡ه††مپ‹م‚‰و•°ç™¾ن¸‡ه††مپ¾مپ§ه¹…مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚ن¸€èˆ¬çڑ„مپ«مپ¯م€پوœˆé،چه›؛ه®ڑè²»مپ¨ه€‹هˆ¥و¥ه‹™مپ®è²»ç”¨مپ§و§‹وˆگمپ•م‚Œم‚‹م‚±مƒ¼م‚¹مپŒه¤ڑمپ„مپ§مپ™م€‚
- وœˆé،چه›؛ه®ڑè²»ï¼ڑه¦ن¼ڑمپ®ن¼ڑه“،و•°م‚„ه¹´é–“ن؛ˆç®—è¦ڈو¨،مپ«ه؟œمپکمپ¦ه¤‰ه‹•مپ—مپ¾مپ™م€‚ن¼ڑه“،و•°مپŒو•°ç™¾ن؛؛è¦ڈو¨،مپ®ه¦ن¼ڑمپ¯م€پوœˆé،چ5ن¸‡ï½10ن¸‡ه††ç¨‹ه؛¦مپŒç›®ه®‰مپ¨مپھم‚‹ه ´هگˆمپŒه¤ڑمپ„مپ§مپ™م€‚
- ه€‹هˆ¥و¥ه‹™مپ®è²»ç”¨ï¼ڑه¦è،“ه¤§ن¼ڑمپ®ن¼پç”»مƒ»éپ‹ه–¶م€پم‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆمپ®و§‹ç¯‰مƒ»ن؟ه®ˆم€په¦ن¼ڑèھŒمپ®ç·¨é›†مƒ»هچ°هˆ·مƒ»ç™؛é€پمپھمپ©م€پهچکç™؛مپ¾مپںمپ¯ç‰¹ه®ڑمپ®و¥ه‹™م‚’ه§”託مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ«مپ‹مپ‹م‚‹è²»ç”¨مپ§مپ™م€‚
مپںمپ¨مپˆمپ°م€په¦è،“ه¤§ن¼ڑمپ®ن¼پç”»مƒ»éپ‹ه–¶مپ§مپ‚م‚Œمپ°م€پé–‹ه‚¬è¦ڈو¨،م‚„ه†…ه®¹مپ«م‚ˆمپ£مپ¦و•°هچپن¸‡ï½و•°ç™¾ن¸‡ه††مپ®è²»ç”¨مپŒمپ‹مپ‹م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ“م‚Œم‚‰مپ®è²»ç”¨مپ«هٹ مپˆمپ¦م€پ郵é€پè²»م‚„هچ°هˆ·è²»مپھمپ©مپ®ه®ںè²»مپŒهˆ¥é€”ç™؛ç”ںمپ™م‚‹ه ´هگˆم‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م€گ費用相ه ´و—©è¦‹è،¨م€‘※2025ه¹´و™‚点
| ه¦ن¼ڑè¦ڈو¨، | ن¼ڑه“،و•° | ن¸»مپھه§”託範ه›² | وœˆé،چç›®ه®‰(ه††) | ه¹´é،چç›®ه®‰(ه††) |
| ه°ڈè¦ڈو¨، | م€œ300ن؛؛ | ن¼ڑه“،ç®،çگ†مƒ»ن¼ڑ計 | 50,000م€œ80,000 | 600,000م€œ960,000 |
| ن¸è¦ڈو¨، | 300م€œ800ن؛؛ | ن¼ڑه“،ç®،çگ†مƒ»ن¼ڑ計مƒ»ه¤§ن¼ڑéپ‹ه–¶è£œهٹ© | 80,000م€œ150,000 | 960,000م€œ1,800,000 |
| ه¤§è¦ڈو¨، | 800ن؛؛م€œ | ن¸ٹè¨ک+ه¦ن¼ڑèھŒهˆ¶ن½œمƒ»ه؛ƒه ± | 200,000م€œ | 2,400,000م€œ |
特مپ«م€پو™‚وœںم‚„هœ°هںںه·®مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™مپ®مپ§è¦‹ç©چو¯”較مپ¯ه؟…é ˆمپ§مپ™م€‚و£ç¢؛مپھ費用م‚’çں¥م‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پ複و•°مپ®و¥è€…مپ‹م‚‰è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹم‚’هڈ–م‚ٹم€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®ه¦ن¼ڑمپ®مƒ‹مƒ¼م‚؛مپ«هگˆمپ£مپںمƒ—مƒ©مƒ³م‚’و¯”較و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚
ن¾‹مپˆمپ°م€په¹´é–“ن؛ˆç®—مپŒ300ن¸‡ه††ç¨‹ه؛¦مپ®ه¦ن¼ڑمپ§م€پن؛‹ه‹™ه±€و¥ه‹™ï¼ˆن¼ڑه“،ç®،çگ†مƒ»ه•ڈمپ„هگˆم‚ڈمپ›ه¯¾ه؟œمƒ»ن¼ڑ計ه‡¦çگ†مپھمپ©ï¼‰م‚’ه§”託مپ™م‚‹ه ´هگˆم€پوœˆé،چ8ن¸‡ه††أ—12مƒ¶وœˆï¼ç´„96ن¸‡ه††/ه¹´ç¨‹ه؛¦مپ§مپ™م€‚
ه§”託費用مپ¯ه¦ن¼ڑمپ®ه¹´é–“ن؛ˆç®—مپ®هچٹهˆ†مپڈم‚‰مپ„مپ¾مپ§مپŒç›®ه®‰مپ§م€پمپم‚Œم‚’超مپˆم‚‹ه ´هگˆم€په§”託ه…ˆمپ«ن½•مپ‹مپ‚مپ£مپںéڑ›مپ«ه¦ن¼ڑه…¨ن½“مپ®éپ‹ه–¶مپ«ه¤§مپچمپھو”¯éڑœم‚’مپچمپںمپ—مپ¦مپ—مپ¾مپ„مپ¾مپ™م€‚مپںمپ مپ—م€په¤–部ه§”託مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ه¤§ه¹…مپھو¥ه‹™و”¹ه–„م‚„هڈژه…¥ه¢—مپŒè¦‹è¾¼م‚پم‚‹ه ´هگˆمپ¯م€پمپ“مپ®ه‰²هگˆم‚’超مپˆم‚‹مپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚ٹه¾—مپ¾مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
Q4ï¼ڑه¤–部ه§”託費用مپ®ç®—ه‡؛هں؛و؛–مپ¯مپ©مپ†è€ƒمپˆمپںم‚‰è‰¯مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶م‚¢م‚¦مƒˆم‚½مƒ¼م‚·مƒ³م‚°è²»ç”¨مپ®ç®—ه‡؛هں؛و؛–مپ¯م€په¤§مپچمپڈهˆ†مپ‘مپ¦â‘ ن؛؛ن»¶è²»م€پâ‘،و¥ه‹™é‡ڈمƒ»ه°‚é–€و€§م€پâ‘¢ه¥‘ç´„ه½¢و…‹مپ®3مپ¤مپ®è¦پç´ مپ§و§‹وˆگمپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®è¦پç´ م‚’çگ†è§£مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پوڈگç¤؛مپ•م‚Œمپں費用مپŒéپ©و£مپ‹مپ©مپ†مپ‹م‚’هˆ¤و–مپ—م‚„مپ™مپڈمپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
- ن؛؛ن»¶è²»ï¼ˆو‹…ه½“者مپ®م‚¹م‚مƒ«مƒ¬مƒ™مƒ«ï¼‰ï¼ڑه§”託費用مپ«مپ¯م€په§”託ه…ˆمپ®و‹…ه½“者مپ®ن؛؛ن»¶è²»مپŒهگ«مپ¾م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“مپ®ن؛؛ن»¶è²»مپ¯م€پو‹…ه½“者مپŒوŒپمپ¤م‚¹م‚مƒ«م‚„ه°‚é–€و€§مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ه¤‰ه‹•مپ—مپ¾مپ™م€‚
- و¥ه‹™é‡ڈمƒ»ه°‚é–€و€§ï¼ˆمپ‹مپ‹م‚‹و™‚é–“مپ¨هٹ´هٹ›ï¼‰ï¼ڑو¥ه‹™مپ«مپ‹مپ‹م‚‹و™‚é–“م‚„هٹ´هٹ›م‚‚م€پ費用مپ®é‡چè¦پمپھç®—ه‡؛هں؛و؛–مپ§مپ™م€‚ه‡¦çگ†مپ™م‚‹ن¼ڑه“،و•°م€پç™؛è،Œمپ™م‚‹ه¦ن¼ڑèھŒمپ®مƒڑمƒ¼م‚¸و•°مپھمپ©م€پè¦ڈو¨،مپŒه¤§مپچمپڈمپھم‚‹مپ»مپ©è²»ç”¨مپ¯é«کمپڈمپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
- ه¥‘ç´„ه½¢و…‹ï¼ˆه§”託مپ®ن»•و–¹ï¼‰ï¼ڑمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھه½¢مپ§و¥ه‹™م‚’ه§”託مپ™م‚‹مپ‹مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م‚‚م€پ費用مپ¯ه¤‰م‚ڈم‚ٹمپ¾مپ™م€‚وœˆé،چه›؛ه®ڑè²»مپ¯ن؛ˆç®—ç®،çگ†مپŒمپ—م‚„مپ™مپڈم€په€‹هˆ¥ï¼ˆم‚¹مƒمƒƒمƒˆï¼‰è²»ç”¨مپ¯ه؟…è¦پمپھو¥ه‹™مپ مپ‘م‚’ن¾é ¼مپ§مپچم‚‹مپںم‚پم€پç„،駄مپھم‚³م‚¹مƒˆم‚’وٹ‘مپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
مپ“م‚Œم‚‰مپ®ç®—ه‡؛هں؛و؛–م‚’考و…®مپ—مپ¦م€په§”託مپ—مپںمپ„و¥ه‹™م‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«و•´çگ†مپ—م€پ複و•°مپ®و¥è€…مپ‹م‚‰è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹم‚’هڈ–م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®ه¦ن¼ڑمپ«مپ¨مپ£مپ¦وœ€éپ©مپھ費用م‚’見و¥µم‚پم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚見ç©چو›¸م‚’هڈ—مپ‘هڈ–مپ£مپںéڑ›مپ¯م€پهچکç´”مپھهگˆè¨ˆé‡‘é،چمپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پمپ“م‚Œم‚‰مپ®é …ç›®مپŒمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«ه†…訳مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’ç¢؛èھچمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
é›»هگه¸³ç°؟ن؟هکو³•مپ®ه¯¾ه؟œمپ¯ن¼ڑ計م‚·م‚¹مƒ†مƒ م‚„経çگ†م‚¢م‚¦مƒˆم‚½مƒ¼م‚·مƒ³م‚°و™‚مپ®و¥ه‹™مƒ•مƒمƒ¼مƒ»è²»ç”¨و§‹é€ مپ¨é–¢é€£مپ—م€په§”託è¦پن»¶م‚„م‚³م‚¹مƒˆه‰ٹو¸›ç–مپ®و–°مپںمپھ論点مپ¨مپ—مپ¦ç•™و„ڈمپ™مپ¹مپچن؛‹é …مپ§مپ™م€‚
Q5ï¼ڑه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹م€Œéڑ م‚Œم‚³م‚¹مƒˆم€چمپ«مپ¯م€پمپ©م‚“مپھم‚‚مپ®مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ں
م€Œéڑ م‚Œم‚³م‚¹مƒˆم€چمپ¨مپ¯م€پè،¨é¢çڑ„مپھ費用مپ«مپ¯هگ«مپ¾م‚Œمپھمپ„م€پو•™èپ·ه“،مپ®هٹ´هٹ›م‚„و¥ه‹™هپœو»مپھمپ©م‚’وŒ‡مپ—مپ¾مپ™م€‚و™‚é–“ه¤–هٹ´هƒچم€پç ”ç©¶و™‚é–“مپ®هœ§è؟«م€په±ن؛؛هŒ–مپ«م‚ˆم‚‹و¥ه‹™هپœو»مپŒن»£è،¨çڑ„مپھن¾‹مپ§مپ™م€‚è،¨é¢ن¸ٹمپ¯è²»ç”¨م‚¼مƒمپ«è¦‹مپˆم‚‹ه†…製و¥ه‹™مپ§م‚‚م€په®ںمپ¯ه¤ڑمپڈمپ®م‚³م‚¹مƒˆمپŒç™؛ç”ںمپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
- و‹…ه½“者مپ®ن¼‘و—¥مƒ»ه¤œé–“ه¯¾ه؟œï¼ˆمƒ،مƒ¼مƒ«è؟”ن؟،م€پن¼ڑè²»ç£ن؟ƒمپھمپ©ï¼‰
- ه°‚é–€ه¤–مپ®ن½œو¥مپ«و™‚é–“م‚’هڈ–م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ï¼ˆCMS[Content Management System]و›´و–°م€پPDFهٹ ه·¥مپھمپ©ï¼‰
- و‹…ه½“ن؛¤ن»£و™‚مپ®ه¼•مپچ継مپژمƒم‚¹مƒ»ه¤±ه؟µمپ«م‚ˆم‚‹مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«م€‚
- ç”ںوˆگAIمپ®هˆ©ç”¨و–™م‚„م€پAIمپ«ه¦ç؟’مپ•مپ›م‚‹مپںم‚پمپ®مƒ‡مƒ¼م‚؟و•´ه‚™مپ«مپ‹مپ‹م‚‹ن؛؛ن»¶è²»
مپ“م‚Œم‚‰مپ¯م€Œé‡‘é،چمپ¨مپ—مپ¦مپ¯هڈ¯è¦–هŒ–مپ—مپ¥م‚‰مپڈمپ¨م‚‚م€پ継ç¶ڑçڑ„مپ«وگچه¤±مپ¨مپ—مپ¦è“„ç©چمپ™م‚‹م‚³م‚¹مƒˆم€چمپ§مپ™م€‚ه¤–部ه§”託مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پمپ“مپ†مپ—مپںن؛؛çڑ„資و؛گمپ®ç›®و¸›م‚ٹم‚’وœ€ه°ڈé™گمپ«وٹ‘مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒم€پé–“وژ¥م‚³م‚¹مƒˆمپ®ه‰ٹو¸›مپ§مپ‚م‚ٹم€په¦ن¼ڑمپ®وŒپç¶ڑهڈ¯èƒ½و€§م‚’é«کم‚پم‚‹و‰‹و®µمپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
Q6ï¼ڑه§”託費用م‚’وٹ‘مپˆم‚‹مپںم‚پمپ«م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھه·¥ه¤«مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™مپ‹ï¼ں
ه§”託範ه›²م‚’çµم‚ٹè¾¼م‚€مپ“مپ¨م€پ複و•°مپ®و¥è€…م‚’و¯”較و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپ“مپ¨م€پمپمپ—مپ¦ه†…部مپ§هڈ¯èƒ½مپھو¥ه‹™مپ¯و®‹مپ™مپ“مپ¨مپŒن¸»مپھه·¥ه¤«ç‚¹مپ§مپ™م€‚
- و¥ه‹™مپ®ه„ھه…ˆé †ن½چن»کمپ‘ï¼ڑمپ™مپ¹مپ¦مپ®و¥ه‹™م‚’ه§”託مپ™م‚‹مپ®مپ§مپ¯مپھمپڈم€په¦ن¼ڑو¥ه‹™مپ®م€Œç‰¹مپ«è² و‹…مپŒه¤§مپچمپ„و¥ه‹™م€چم‚„م€Œه°‚é–€و€§مپŒé«کمپڈم€په†…部مپ§مپ¯ه¯¾ه؟œمپŒé›£مپ—مپ„و¥ه‹™م€چمپ«çµمپ£مپ¦ه§”託範ه›²م‚’و¤œè¨ژمپ—مپ¾مپ™م€‚
- 複و•°مپ®è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹو¯”較ï¼ڑ1社مپ مپ‘مپ§مپھمپڈ複و•°مپ®و¥è€…مپ‹م‚‰è¦‹ç©چم‚‚م‚ٹم‚’هڈ–م‚ٹم€پ費用مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹ه†…ه®¹م‚„ه®ں績م‚’و¯”較مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پم‚ˆم‚ٹ費用ه¯¾هٹ¹وœمپ®é«کمپ„و¥è€…م‚’見مپ¤مپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
- ه†…部مƒھم‚½مƒ¼م‚¹مپ®و´»ç”¨ï¼ڑه¤–部مپ«ه§”託مپ™م‚‹و¥ه‹™م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹ن¸€و–¹مپ§م€پم€Œه†…部مپ§هٹ¹çژ‡هŒ–مپ§مپچم‚‹و¥ه‹™م€چمپŒمپھمپ„مپ‹è¦‹ç›´مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
- AIمپ®و´»ç”¨ï¼ڑهچکç´”ن½œو¥م‚„ç¹°م‚ٹè؟”مپ—ن½œو¥مپھمپ©AIمپ«ن»»مپ›م‚‰م‚Œم‚‹éƒ¨هˆ†مپ¯ç©چو¥µçڑ„مپ«هˆ©ç”¨مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚مپ¾مپںم€پهگ„種مپ®و–‡و›¸ن½œوˆگم‚„مƒ†مƒ³مƒ—مƒ¬مƒ¼مƒˆمپ®ç”ںوˆگمپ«م‚‚وœ‰هٹ¹مپ§مپ™م€‚特مپ«ç”»هƒڈç”ںوˆگAIمپ¯م€پم‚¤مƒ©م‚¹مƒˆم‚„ه›³è،¨مپ®è‘—ن½œو¨©مƒ»ç‰ˆو¨©ç¢؛èھچم€پ許諾و‰؟èھچمپ®و‰‹é–“م‚’ç°،ç´ هŒ–مپ§مپچم‚‹مپںم‚پم€په؟œç”¨ç¯„ه›²مپŒه؛ƒمپڈمپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ¾مپںم€پé•·وœںه¥‘ç´„م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پهچکç™؛مپ®ن¾é ¼م‚ˆم‚ٹم‚‚費用م‚’وٹ‘مپˆم‚‰م‚Œم‚‹م‚±مƒ¼م‚¹م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپںمپ مپ—م€پé•·وœںه¥‘ç´„مپ«مپ¯م€Œé¦´م‚Œهگˆمپ„م€چمپ¨مپ„مپ†مƒھم‚¹م‚¯م€پمƒ‡مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚‚هکهœ¨مپ™م‚‹مپ®مپ§و³¨و„ڈمپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»ه¦ن¼ڑن؛‹ه‹™ه±€مپ¯ه§”託مپ™مپ¹مپچï¼ں費用م‚„ه†…ه®¹مپ¯ï¼ں|مپ“م‚Œمپ‹م‚‰مپ®ه¦ن¼ڑ.com
Q7ï¼ڑه¤–部ه§”託مپ—مپںمپ„مپ‘م‚Œمپ©ن؛ˆç®—مپŒè¶³م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚資金èھ؟éپ”مپ¯مپ©مپ†مپ™م‚Œمپ°è‰¯مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
ه¤–部ه§”託مپ®مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¯çگ†è§£مپ—مپ¦مپ„مپ¦م‚‚م€پن؛ˆç®—ن¸چ足مپŒéڑœه£پمپ¨مپھم‚‹مپ“مپ¨مپ¯ه°‘مپھمپڈمپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚مپ‘م‚Œمپ©م‚‚م€په¦ن¼ڑمپ®ç‰¹و€§م‚’و´»مپ‹مپ—مپں資金èھ؟éپ”مپ®و–¹و³•مپ¯è¤‡و•°مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
- ن¼ڑè²»مپ®è¦‹ç›´مپ—ï¼ڑه§”託مپ«م‚ˆم‚ٹم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹ه“پè³ھمپŒهگ‘ن¸ٹمپ™م‚‹è¦‹è¾¼مپ؟مپŒمپ‚م‚‹ه ´هگˆم€پمپمپ®مƒ،مƒھمƒƒمƒˆم‚’ن¼ڑه“،مپ«وکژç¢؛مپ«وڈگç¤؛مپ—مپںن¸ٹمپ§م€پن¼ڑè²»مپ®ه€¤ن¸ٹمپ’م‚’و¤œè¨ژمپ—مپ¾مپ™م€‚
- è³›هٹ©ن¼ڑه“،م‚„م‚¹مƒمƒ³م‚µمƒ¼مپ®çچ²ه¾—ï¼ڑه¦è،“ه¤§ن¼ڑمپ®é–‹ه‚¬م‚„ه؛ƒه ±و´»ه‹•مپ®ه¼·هŒ–م‚’ه¤–部ه§”託مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پم‚ˆم‚ٹه¤ڑمپڈمپ®ن¼پو¥م‚„ه›£ن½“مپ«م‚¢مƒ”مƒ¼مƒ«مپ™م‚‹و©ںن¼ڑمپŒç”ںمپ¾م‚Œمپ¾مپ™م€‚ه¦ن¼ڑمپ®و´»ه‹•مپ«è³›هگŒمپ—م€پو”¯وڈ´مپ—مپ¦مپڈم‚Œم‚‹è³›هٹ©ن¼ڑه“،م‚„م‚¹مƒمƒ³م‚µمƒ¼م‚’ه‹ںم‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په®‰ه®ڑمپ—مپںهڈژç›ٹو؛گم‚’ç¢؛ن؟مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
- ه…¬çڑ„و”¯وڈ´ï¼ˆهٹ©وˆگ金مƒ»è£œهٹ©é‡‘)مپ®و´»ç”¨ï¼ڑç ”ç©¶و´»ه‹•مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€په¦ن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶مپمپ®م‚‚مپ®مپ«ه¯¾مپ™م‚‹ه…¬çڑ„مپھهٹ©وˆگ金م‚„補هٹ©é‡‘مپŒهکهœ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚
- هœ°و–¹è‡ھو²»ن½“م‚„è²،ه›£مپŒم€پهœ°هںںمپ¸مپ®çµŒو¸ˆهٹ¹وœم‚„ه¦è،“ن؛¤وµپمپ®و´»و€§هŒ–م‚’ç›®çڑ„مپ¨مپ—مپ¦م€په¦ن¼ڑمپ®é–‹ه‚¬è²»ç”¨م‚’補هٹ©مپ™م‚‹هˆ¶ه؛¦م‚’è¨مپ‘مپ¦مپ„م‚‹ن¾‹م‚‚ç¢؛èھچمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚ه¦ن¼ڑمپ®ه…¬ç›ٹو€§م‚„社ن¼ڑ貢献و€§م‚’م‚¢مƒ”مƒ¼مƒ«مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پمپ¾مپ¨مپ¾مپ£مپں資金م‚’èھ؟éپ”مپ§مپچم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
- م‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰مƒ•م‚،مƒ³مƒ‡م‚£مƒ³م‚°مپ®هˆ©ç”¨ï¼ڑ特ه®ڑمپ®مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆï¼ˆن¾‹ï¼ڑه›½éڑ›ن¼ڑè°مپ®é–‹ه‚¬م€په¦ن¼ڑèھŒمپ®é›»هگهŒ–)مپ«ه؟…è¦پمپھ資金م‚’م€پم‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆم‚’é€ڑمپکمپ¦ه؛ƒمپڈن¸€èˆ¬مپ‹م‚‰ه‹ںم‚‹م‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰مƒ•م‚،مƒ³مƒ‡م‚£مƒ³م‚°م‚‚وœ‰هٹ¹مپھو‰‹و®µمپ§مپ™م€‚
特مپ«م€په¦è،“ç ”ç©¶مپ«ç‰¹هŒ–مپ—مپںم‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰مƒ•م‚،مƒ³مƒ‡م‚£مƒ³م‚°م‚µم‚¤مƒˆم‚‚هکهœ¨مپ—م€پç ”ç©¶مƒ†مƒ¼مƒمپ®ç¤¾ن¼ڑçڑ„مپھو„ڈ義م‚’م‚¢مƒ”مƒ¼مƒ«مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پن¼ڑه“،ن»¥ه¤–مپ‹م‚‰مپ®و”¯وڈ´م‚‚وœںه¾…مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚ه›½ç«‹ç§‘ه¦هچڑ物館م‚’و”¯مپˆم‚‹م‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰مƒ•م‚،مƒ³مƒ‡م‚£مƒ³م‚°مپ®م‚ˆمپ†مپھهکç«‹و”¯وڈ´مپ®ه®ںن¾‹م‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپ“م‚Œم‚‰مپ®è³‡é‡‘èھ؟éپ”ç–م‚’هچکن½“مپ§ه®ںè،Œمپ™م‚‹مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€په¤–部ه§”託ه…ˆمپ¨é€£وگ؛مپ—مپ¦ه؛ƒه ±و´»ه‹•م‚’ه¼·هŒ–مپ™م‚‹مپھمپ©م€پ複و•°مپ®و–½ç–م‚’組مپ؟هگˆم‚ڈمپ›م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پم‚ˆم‚ٹهٹ¹وœçڑ„مپ«ن؛ˆç®—ن¸چ足م‚’解و¶ˆمپ§مپچم‚‹ه ´هگˆمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»ه¦ن¼ڑ経費補هٹ©é‡‘|و—©ç¨²ç”°ه¤§ه¦
مƒ»ه¦è،“ç³»م‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰مƒ•م‚،مƒ³مƒ‡م‚£مƒ³م‚°م€Œم‚¢م‚«مƒ‡مƒںم‚¹مƒˆم€چمپ®وŒ‘وˆ¦ï½œimidas
Q8ï¼ڑه¤–部ه§”託مپ®م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ¯م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«éپ¸مپ¹مپ°è‰¯مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
ه¤–部ه§”託و¥è€…م‚’éپ¸مپ¶éڑ›مپ¯م€پ費用مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پو¬،مپ®م‚ˆمپ†مپھمƒم‚¤مƒ³مƒˆم‚’ç·ڈهگˆçڑ„مپ«و¯”較و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
ه®ں績مپ¨ه°‚é–€و€§
- éپژهژ»مپ®ه®ں績ï¼ڑمپ“م‚Œمپ¾مپ§مپ«مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھه¦ن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶م‚’م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ—مپ¦مپچمپںمپ‹م€په®ں績م‚’ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚مپںمپ مپ—م€پé©و–°çڑ„مپھو‰‹و³•م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„م‚‹و¥è€…مپ®ه ´هگˆمپ¯éپژهژ»مپ®ه®ں績مپ«وچ‰م‚ڈم‚Œم‚‹ه؟…è¦پمپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚
- ه°‚é–€هˆ†é‡ژï¼ڑمپم‚Œمپم‚Œمپ®ه¦ن¼ڑمپ¨هگŒمپکم€پمپ‚م‚‹مپ„مپ¯è؟‘مپ„هˆ†é‡ژمپ®ه°‚é–€و€§م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’ç¢؛èھچمپ™م‚‹مپ¨م€پم‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³مپŒم‚ˆم‚ٹم‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپ«مپھم‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م‚µمƒمƒ¼مƒˆن½“هˆ¶
- و‹…ه½“者مپ®è³ھï¼ڑçھ“هڈ£مپ¨مپھم‚‹و‹…ه½“者مپ¨مپ®م€Œç›¸و€§م€چم‚„م€پ連çµ،مپ®هڈ–م‚ٹم‚„مپ™مپ•مپ¯é‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
- م€Œمپھم‚“مپ¨مپھمپڈم‚¦مƒمپŒهگˆمپ†م€چمپ¯ه°ٹمپ¶مپ¹مپچè¦پç´ مپ§مپ™م€‚(هڈ‚考ï¼ڑGoogleمپŒè§£وکژï¼په؟ƒçگ†çڑ„ه®‰ه…¨و€§مپ®é‡چè¦پو€§مپ¨مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆم‚¢مƒھم‚¹مƒˆمƒ†مƒ¬م‚¹م‚’解èھ¬ï½œUniposو ھه¼ڈن¼ڑ社)
ه¯¾ه؟œç¯„ه›²ï¼ڑé€ڑه¸¸مپ®ن؛‹ه‹™ن½œو¥مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پç·ٹو€¥و™‚مپ®ه¯¾ه؟œم‚„çھپç™؛çڑ„مپھو¥ه‹™مپ«م‚‚وں”è»ںمپ«ه¯¾ه؟œمپ—مپ¦مپڈم‚Œم‚‹مپ‹م‚’ç¢؛èھچمپ—مپ¦مپٹمپچمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
و–™é‡‘ن½“ç³»
- é€ڈوکژو€§ï¼ڑو–™é‡‘ن½“ç³»مپŒوکژç¢؛مپ§م€پè؟½هٹ 費用مپŒç™؛ç”ںمپ™م‚‹و،ن»¶مپŒمپ¯مپ£مپچم‚ٹمپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
- 費用ه¯¾هٹ¹وœï¼ڑوڈگç¤؛مپ•م‚Œمپں費用مپŒم€پوœںه¾…مپ™م‚‹م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹ه†…ه®¹مپ«è¦‹هگˆمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’複و•°مپ®و¥è€…مپ¨و¯”較و¤œè¨ژمپ—مپ¾مپ™م€‚
م‚»م‚مƒ¥مƒھمƒ†م‚£
- وƒ…ه ±ç®،çگ†ن½“هˆ¶ï¼ڑPمƒمƒ¼م‚¯ï¼ˆمƒ—مƒ©م‚¤مƒگم‚·مƒ¼مƒمƒ¼م‚¯ï¼ڑJISQ15001)مپ®هڈ–ه¾—çٹ¶و³پم‚„م€پوƒ…ه ±ç®،çگ†مپ«é–¢مپ™م‚‹ن½“هˆ¶مپŒمپ—مپ£مپ‹م‚ٹمپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م‚’ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
مپ“م‚Œم‚‰مپ®è¦پç´ م‚’و¯”較مپ—م€پمپم‚Œمپم‚Œمپ®ه¦ن¼ڑمپ®مƒ‹مƒ¼م‚؛مپ¨و–‡هŒ–مپ«هگˆمپ£مپںم€Œمƒ‘مƒ¼مƒˆمƒٹمƒ¼م€چم‚’見مپ¤مپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپŒم€په¤–部ه§”託م‚’وˆگهٹںمپ•مپ›م‚‹éچµمپ§مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
Q9ï¼ڑه¤–部ه§”託م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹éڑ›م€پ特مپ«و³¨و„ڈمپ™مپ¹مپچه¥‘ç´„ن¸ٹمپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ¯ن½•مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
ه¥‘ç´„ه†…ه®¹م‚’詳細مپ«ç¢؛èھچمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒوœ€م‚‚é‡چè¦پمپ§مپ™م€‚و¬،مپ®ç‚¹مپ«ç‰¹مپ«و³¨و„ڈمپ—مپ¦مپ؟مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
- و¥ه‹™ç¯„ه›²مپ®وکژç¢؛هŒ–ï¼ڑه¥‘ç´„و›¸مپ«è¨ک載مپ•م‚Œمپںو¥ه‹™ç¯„ه›²مپŒم€پ見ç©چم‚‚م‚ٹه†…ه®¹مپ¨ن¸€è‡´مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚م€Œمپ©مپ“مپ‹م‚‰مپ©مپ“مپ¾مپ§م‚’ه§”託مپ™م‚‹مپ®مپ‹م€چم‚’ه…·ن½“çڑ„مپ«è¨€èھهŒ–مپ—م€پèھچèکمپ®م‚؛مƒ¬مپŒمپھمپ„م‚ˆمپ†مپ«مپ—مپ¾مپ™م€‚
- è؟½هٹ 費用مپ®è¦ڈه®ڑï¼ڑ見ç©چم‚‚م‚ٹمپ«مپ¯هگ«مپ¾م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ‹مپ£مپںمپŒم€په¾Œمپ‹م‚‰ç™؛ç”ںمپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپ®مپ‚م‚‹è²»ç”¨مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھه ´هگˆمپ«م€پمپ„مپڈم‚‰è؟½هٹ 費用مپŒç™؛ç”ںمپ™م‚‹مپ®مپ‹م‚’وکژç¢؛مپ«مپ—مپ¦مپٹمپڈمپ“مپ¨مپŒه¤§هˆ‡مپ§مپ™م€‚
- و©ںه¯†ن؟وŒپه¥‘約(NDAï¼ڑNon-Disclosure Agreement)ï¼ڑن¼ڑه“،وƒ…ه ±م‚„ç ”ç©¶مƒ‡مƒ¼م‚؟مپھمپ©م€پو©ںه¯†و€§مپ®é«کمپ„وƒ…ه ±م‚’و‰±مپ†مپںم‚پم€پوƒ…ه ±و¼ڈو´©ه¯¾ç–م‚„ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±ن؟è·و³•éپµه®ˆمپ®ن½“هˆ¶مپŒه¥‘ç´„و›¸مپ«وکژè¨کمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ‹ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
- ه¥‘ç´„وœںé–“مپ¨è§£ç´„و،ن»¶ï¼ڑه¥‘ç´„وœںé–“مپŒéپ©هˆ‡مپ‹م€پمپ¾مپںم€پم‚„م‚€م‚’ه¾—مپھمپ„ن؛‹وƒ…مپ§ه¥‘ç´„م‚’解約مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ®و،ن»¶م‚„éپ•ç´„金مپ«مپ¤مپ„مپ¦ç¢؛èھچمپ—مپ¦مپٹمپڈمپ“مپ¨م‚‚é‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
هڈ£é مپ§مپ®هگˆو„ڈمپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پو›¸é¢مپ§è©³ç´°مپ«ç¢؛èھچمپ—م€پç´چه¾—مپ—مپںن¸ٹمپ§ه¥‘ç´„م‚’çµگمپ¶م‚ˆمپ†مپ«مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚AIم‚„م‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰هˆ©ç”¨و™‚مپ®ç•™و„ڈن؛‹é …مپ¯ه·»وœ«م‚³مƒ©مƒ مپ«مپ¦è©³ç´°م‚’مپ”ç¢؛èھچمپڈمپ مپ•مپ„
Q10ï¼ڑه¤–部ه§”託مپ®éڑ›مپ®ن¼ڑه“،ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±مپ®هڈ–م‚ٹو‰±مپ„مپŒن¸چه®‰مپ§مپ™م€‚مپ©مپ“مپ¾مپ§é–‹ç¤؛مپ™م‚‹مپ¹مپچمپ§مپ™مپ‹ï¼ں
وœ€ه°ڈé™گمپ®ه؟…è¦پوƒ…ه ±مپ«é™گه®ڑمپ—م€په¥‘ç´„و™‚مپ«وƒ…ه ±ن؟è·و،é …م‚’وکژè¨کمپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’مپٹه‹§م‚پمپ—مپ¾مپ™م€‚ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±مپ®هڈ–م‚ٹو‰±مپ„مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ®ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±ن؟è·و³•م‚„م€پGDPR(EUن¸€èˆ¬مƒ‡مƒ¼م‚؟ن؟è·è¦ڈه‰‡ï¼‰مپھمپ©م€په›½ه†…ه¤–مپ®وœ€و–°مپ®و³•ن»¤م‚’éپµه®ˆمپ™م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
- ه§”託ه…ˆمپ¸مپ®ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±وڈگن¾›مپ¯م€پç›®çڑ„éپ”وˆگمپ®مپںم‚پمپ«م€Œوœ€ه°ڈé™گه؟…è¦پمپھ範ه›²م€چمپ«مپ¨مپ©م‚پمپ¾مپ™ï¼ˆن¾‹ï¼ڑن¼ڑه“،ç•ھهڈ·م€پو°ڈهگچم€پو‰€ه±م€پمƒ،مƒ¼مƒ«م‚¢مƒ‰مƒ¬م‚¹مپ®مپ؟)م€‚
- ه§”託ه¥‘ç´„مپ«مپ¯م€پو¬،مپ®ن؛‹é …م‚’وکژè¨کمپ—مپ¦مپٹمپڈمپ¨ه®‰ه؟ƒمپ§مپ™م€‚
- وƒ…ه ±مپ®هˆ©ç”¨ç›®çڑ„مپ¨ç¯„ه›²مپ®é™گه®ڑ
- وƒ…ه ±مپ®ç¬¬ن¸‰è€…وڈگن¾›ç¦پو¢
- EUمپ‹م‚‰مپ®هڈ‚هٹ 者(講و¼”者هگ«م‚€ï¼‰مپ¸مپ®GDPRمپ¸مپ®ه¯¾ه؟œ
- ه§”託ه…ˆمپ«م‚ˆم‚‹وƒ…ه ±ç®،çگ†è²¬ن»»ï¼ˆن؛‹و•…ه¯¾ه؟œهگ«م‚€ï¼‰
- ه¥‘約終ن؛†ه¾Œمپ®مƒ‡مƒ¼م‚؟è؟”هچ´مƒ»ه‰ٹ除責ن»»
مپ¾مپںم€پPمƒمƒ¼م‚¯ï¼ˆمƒ—مƒ©م‚¤مƒگم‚·مƒ¼مƒمƒ¼م‚¯ï¼ڑJISQ15001)هڈ–ه¾—و¸ˆمپ؟ن¼پو¥مپ‹م‚’ç¢؛èھچمپ—م€پNDA(و©ںه¯†ن؟وŒپه¥‘約)م‚’ç· çµگمپ™م‚‹مپ®مپŒن¸€èˆ¬çڑ„مپ§مپ™م€‚Pمƒمƒ¼م‚¯هڈ–ه¾—م‚„ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±ن؟è·و³•مپ®و”¹è¨‚مپ¯م€په§”託و™‚مپ®وƒ…ه ±ç®،çگ†ن½“هˆ¶م‚„ه¥‘ç´„و،ن»¶مپ«ç›´çµگمپ—مپ¾مپ™م€‚
ç”ںوˆگAIمپ®و´»ç”¨مپ«مپٹمپ„مپ¦مپ¯م€په€‹ن؛؛وƒ…ه ±ن؟è·و³•مپŒو”¹و£مپ•م‚Œم€په€‹ن؛؛مƒ‡مƒ¼م‚؟م€پ特مپ«è¦پé…چو…®ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±ï¼ˆو©ںه¾®وƒ…ه ±ï¼‰مپ®هˆ©ç”¨مپ«é–¢مپ™م‚‹è¦ڈهˆ¶مپŒه¼·هŒ–مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ç‚¹مپ«و³¨و„ڈمپŒه؟…è¦پمپ§مپ™م€‚ه§”託ه…ˆمپŒAIم‚’مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«و´»ç”¨مپ—م€پمƒ‡مƒ¼م‚؟مپŒمپ©مپ“مپ«ن؟ç®،مپ•م‚Œم‚‹مپ®مپ‹م‚’وکژç¢؛مپ«ç¢؛èھچمپ—م€په¥‘ç´„و›¸مپ«وکژè¨کمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
Q11ï¼ڑمƒ¨مƒ¼مƒمƒƒمƒ‘(ن¸»مپ«EUهœڈه†…)مپ‹م‚‰مپ®ه¦ن¼ڑهڈ‚هٹ 者(講و¼”者م‚‚هگ«م‚€ï¼‰م‚’هڈ—مپ‘ه…¥م‚Œم‚‹éڑ›مپ«DPO(مƒ‡مƒ¼م‚؟ن؟è·è²¬ن»»è€…)مپ®ه¤–部ه§”託مپ¯هڈ¯èƒ½مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ں
مپ¯مپ„م€‚ه°‚é–€ه®¶مپ¸ه¤–部ه§”託مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§GDPRه¯¾ه؟œمپ¨م‚³م‚¹مƒˆهٹ¹çژ‡مپŒن¸،ç«‹مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
GDPR(General Data Protection Regulationï¼ڑEUن¸€èˆ¬مƒ‡مƒ¼م‚؟ن؟è·è¦ڈه‰‡ï¼‰مپ§مپ¯م€پ特ه®ڑمپ®و،ن»¶ن¸‹مپ§DPO(Data Protection Officer)مپ®ن»»ه‘½مپŒç¾©ه‹™ن»کمپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پمپمپ®ه½¹ه‰²م‚’ه¤–部مپ®ن¼پو¥م‚„ه€‹ن؛؛مپ«ه§”託مپ™م‚‹م€Œه¤–部ه§”託DPOم€چمپ¨مپ„مپ†éپ¸وٹè‚¢مپŒèھچم‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
ه¤–部DPOمپ®ن¸»مپھمƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¯ن»¥ن¸‹مپ®é€ڑم‚ٹمپ§مپ™م€‚
- ه°‚é–€و€§مپ®ç¢؛ن؟: GDPRمپ¯è¤‡é›‘مپ‹مپ¤ه¸¸مپ«و›´و–°مپ•م‚Œم‚‹مپںم‚پم€په°‚é–€çڑ„مپھçں¥èکم‚’وŒپمپ£مپںDPOمپ¯م€په¦ن¼ڑمپŒم‚³مƒ³مƒ—مƒ©م‚¤م‚¢مƒ³م‚¹م‚’ç¶وŒپمپ™م‚‹ن¸ٹمپ§ن¸چهڈ¯و¬ مپھهکهœ¨مپ§مپ™م€‚
- ه®¢è¦³و€§مپ®ن؟وŒپ: ه¤–部مپ®ه°‚é–€ه®¶مپ§مپ‚م‚‹مپںم‚پم€په†…部مپ®هˆ©ه®³é–¢ن؟‚مپ«ç¸›م‚‰م‚Œمپڑم€په®¢è¦³çڑ„مپ‹مپ¤ç‹¬ç«‹مپ—مپںç«‹ه ´مپ§هٹ©è¨€م‚„監視م‚’è،Œمپˆمپ¾مپ™م€‚
- م‚³م‚¹مƒˆهٹ¹çژ‡: ه°‚ن»»مپ®DPOم‚’雇مپ†م‚ˆم‚ٹم‚‚م€په؟…è¦پمپھو™‚مپ«ه°‚é–€ه®¶مپ®م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’هˆ©ç”¨مپ™م‚‹و–¹مپŒم€پ費用م‚’وٹ‘مپˆم‚‰م‚Œم‚‹ه ´هگˆمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مپںمپ مپ—م€پDPOمپ®ه¤–部ه§”託م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚‹éڑ›مپ¯م€پمپمپ®ه°‚é–€ه®¶مپŒGDPRمپ«é–¢مپ™م‚‹و·±مپ„çں¥èکمپ¨ه®ںه‹™çµŒé¨“م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨م‚’ç¢؛èھچمپ—م€په¥‘ç´„و›¸مپ«DPOمپ®ه½¹ه‰²مپ¨è²¬ن»»ç¯„ه›²م‚’وکژç¢؛مپ«è¦ڈه®ڑمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒو¥µم‚پمپ¦é‡چè¦پمپ§مپ™م€‚مپ¾مپںم€پEUهںںه†…مپ«ن»£çگ†ن؛؛م‚’ç«‹مپ¦م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚‹ه ´هگˆم‚‚مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™مپ®مپ§م€پن½µمپ›مپ¦ç¢؛èھچمپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’مپٹه‹§م‚پمپ—مپ¾مپ™م€‚
Q12ï¼ڑه¤–部ه§”託مپ«ن¼´مپ†مƒھم‚¹م‚¯مپ«مپ¯مپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚‚مپ®مپŒمپ‚م‚ٹم€پمپ©مپ†ه¯¾ç–مپ™م‚Œمپ°è‰¯مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
ه¤–部ه§”託مپ®مƒھم‚¹م‚¯مپ¯م€په¥‘ç´„ه†…ه®¹مپ®وکژç¢؛هŒ–م‚„ن؟é™؛مپ®و´»ç”¨مپ§ه¯¾ç–مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚ه¤–部ه§”託مپ«مپ¯م€پوƒ…ه ±و¼ڈو´©م‚„مƒژم‚¦مƒڈم‚¦مپ®وµپه‡؛مپ¨مپ„مپ£مپںمƒھم‚¹م‚¯مپŒن¼´مپ„مپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®مƒھم‚¹م‚¯مپ«ه‚™مپˆم€پن؟é™؛مپ®و´»ç”¨م‚‚و¤œè¨ژمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
ه¤–部ه§”託مپ«مپٹمپ‘م‚‹ن¸»مپھمƒھم‚¹م‚¯مپ¨ه¯¾ç–
م€گن»£è،¨çڑ„مƒھم‚¹م‚¯5هˆ†é،مپ¨ه¯¾ç–م€‘
| مƒھم‚¹م‚¯ | ه¯¾ç– |
| وƒ…ه ±و¼ڈو´© | NDAç· çµگم€پ وœ€ه°ڈé™گمپ®وƒ…ه ±وڈگن¾›م€پ ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±ن؟è·ن؟é™؛مپ®هٹ ه…¥ |
| ç”ںوˆگAIهˆ©ç”¨ | èھ¤وƒ…ه ±مƒ»è‘—ن½œو¨©مƒ»ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±هڈ–و‰±مپ®و³¨و„ڈم€پ وœ€و–°م‚¬م‚¤مƒ‰مƒ©م‚¤مƒ³و؛–و‹ |
| مƒژم‚¦مƒڈم‚¦وµپه‡؛ | مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«و•´ه‚™م€پ ه®ڑوœںه ±ه‘ٹن¼ڑم€پ ه†…部ه…±وœ‰DBو§‹ç¯‰ |
| ه“پè³ھن½ژن¸‹ | KPIè¨ه®ڑم€پ ه®ڑوœںçڑ„مپھè©•ن¾،مپ¨مƒ•م‚£مƒ¼مƒ‰مƒگمƒƒم‚¯ |
| 費用ه¢—هٹ | ه¥‘約範ه›²مپ®وکژç¢؛هŒ–م€پ複و•°و¥è€…مپ®è¦‹ç©چو¯”較 |
وƒ…ه ±و¼ڈو´©مپ¸مپ®ه¯¾ç–
- و©ںه¯†ن؟وŒپه¥‘約(NDA)م‚’ç· çµگمپ—م€پوڈگن¾›مپ™م‚‹وƒ…ه ±مپ¯ه؟…è¦پوœ€ه°ڈé™گمپ«مپ¨مپ©م‚پمپ¾مپ™م€‚
- ن¸‡مپŒن¸€مپ®ن؛‹و•…مپ«ه‚™مپˆم€په§”託ه…ˆمپŒه€‹ن؛؛وƒ…ه ±ن؟è·ن؟é™؛مپ«هٹ ه…¥مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚مپ¾مپںم€په¦ن¼ڑè‡ھè؛«مپ§مپ“مپ®ن؟é™؛مپ«هٹ ه…¥مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚‚éپ¸وٹè‚¢مپ®ن¸€مپ¤مپ§مپ™م€‚
ç”ںوˆگAIمپ®و´»ç”¨مپ«م‚ˆم‚‹مƒھم‚¹م‚¯
- ç”ںوˆگAIمپ®و´»ç”¨مپ¯م€پوƒ…ه ±و¼ڈو´©مپ®مƒھم‚¹م‚¯مپŒن¼´مپ„مپ¾مپ™م€‚
- AIمپ«ه¦ç؟’مپ•مپ›م‚‹مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ®ç®،çگ†مپ¯هژ³و ¼مپ«è،Œمپ†ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
مƒژم‚¦مƒڈم‚¦وµپه‡؛مپ¸مپ®ه¯¾ç–
- ه®ڑوœںçڑ„مپھه ±ه‘ٹن¼ڑم‚„مƒمƒ‹مƒ¥م‚¢مƒ«مپ®و•´ه‚™مپ§م€پمƒژم‚¦مƒڈم‚¦م‚’ه¦ن¼ڑه†…مپ«è“„ç©چمپ—مپ¾مپ™م€‚
ه“پè³ھن½ژن¸‹مپ¸مپ®ه¯¾ç–
- و¥ه‹™مپ®è©•ن¾،هں؛و؛–م‚’وکژç¢؛مپ«مپ—م€په¯†مپھم‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³م‚’é€ڑمپکمپ¦ه“پè³ھم‚’ç¶وŒپمپ—مپ¾مپ™م€‚
وگچه®³ç™؛ç”ںمپ¸مپ®ه¯¾ç–
- ه§”託ه…ˆمپ®éپژه¤±مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ه¦ن¼ڑمپ«وگچه®³مپŒç™؛ç”ںمپ—مپںه ´هگˆمپ«ه‚™مپˆم€په§”託مپ«م‚ˆم‚‹وگچه®³è³ ه„ں責ن»»ن؟é™؛مپ«هٹ ه…¥مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ™م€‚
費用ه¢—هٹ مپ¸مپ®ه¯¾ç–
- ه¥‘ç´„ه‰چمپ«و¥ه‹™ç¯„ه›²مپ¨è؟½هٹ 費用مپ®و،ن»¶م‚’ç¢؛èھچمپ—م€پ複و•°مپ®و¥è€…م‚’و¯”較و¤œè¨ژمپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
- ن؟é™؛هٹ ه…¥مپ«مپ¯م€په§”託ه…ˆمپŒهٹ ه…¥مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ¨ه¦ن¼ڑè‡ھè؛«مپŒهٹ ه…¥مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ®ن؛Œمپ¤مپ®م‚±مƒ¼م‚¹مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚
م€گن؟é™؛هٹ ه…¥ن¸ٹمپ®ç•™و„ڈ点م€‘
ه§”託ه…ˆمپŒهٹ ه…¥مپ™م‚‹ن؟é™؛مپ¯م€پن¸»مپ«ه§”託ه…ˆمپ®éپژه¤±مپ«م‚ˆم‚‹وگچه®³م‚’م‚«مƒگمƒ¼مپ™م‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ™م€‚ن¸€و–¹م€په¦ن¼ڑè‡ھè؛«مپŒن؟é™؛مپ«هٹ ه…¥مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په§”託ه…ˆمپ§مپ¯م‚«مƒگمƒ¼مپ—مپچم‚Œمپھمپ„ه؛ƒç¯„مپھمƒھم‚¹م‚¯مپ«ه‚™مپˆم‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
ه¤–部ه§”託مپ¯م€Œن¸¸وٹ•مپ’م€چمپ§مپ¯مپھمپڈم€په§”託ه…ˆمپ¨مپ®مƒ‘مƒ¼مƒˆمƒٹمƒ¼م‚·مƒƒمƒ—مپ¨مپ—مپ¦وچ‰مپˆم€پمƒھم‚¹م‚¯ç®،çگ†م‚’هگ«م‚پمپںهچ”هƒچن½“هˆ¶م‚’築مپڈمپ“مپ¨مپŒوˆگهٹںمپ®éچµمپ§مپ™م€‚
م€ٹمپ”و،ˆه†…م€‹
Q13ï¼ڑه¤–部ه§”託م‚’مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په†…部مپ®éپ‹ه–¶م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ®ه½¹ه‰²مپ¯مپ©مپ†ه¤‰م‚ڈم‚ٹمپ¾مپ™مپ‹ï¼ں
ه¤–部ه§”託مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€په†…部مپ®éپ‹ه–¶م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ¯ن؛‹ه‹™ن½œو¥مپ‹م‚‰è§£و”¾مپ•م‚Œم€پم‚ˆم‚ٹوˆ¦ç•¥çڑ„مپ§ه°‚é–€çڑ„مپھو¥ه‹™مپ«é›†ن¸مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚مپںمپ¨مپˆمپ°م€پو¬،مپ®ه½¹ه‰²مپŒوœںه¾…مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚
- و–¹é‡و±؛ه®ڑمپ¨é€²وچ—ç®،çگ†ï¼ڑه§”託ه…ˆمپ¨مپ®çھ“هڈ£مپ¨مپ—مپ¦م€په¦ن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶و–¹é‡م‚’ن¼مپˆم€پو¥ه‹™مپ®é€²وچ—çٹ¶و³پم‚’ç®،çگ†مپ—مپ¾مپ™م€‚
- ه°‚é–€çڑ„مƒ»ن¼پç”»و¥ه‹™ï¼ڑç ”ç©¶ن¼ڑم‚„م‚·مƒ³مƒم‚¸م‚¦مƒ مپ®ن¼پç”»م€پو–°مپںمپھن¼ڑه“،م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®و¤œè¨ژمپھمپ©م€په¦ن¼ڑمپ®وœ¬è³ھçڑ„مپھو´»ه‹•مپ«é–¢مپ™م‚‹ن¼پ画立و،ˆم‚’è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚
- ه§”託ه…ˆمپ¨مپ®هچ”هƒچï¼ڑه§”託ه…ˆمپ¨ه¯†مپ«م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³م‚’هڈ–م‚ٹم€پم‚ˆم‚ٹهٹ¹وœçڑ„مپھéپ‹ه–¶ن½“هˆ¶م‚’築مپڈمپںم‚پمپ®مƒ‘مƒ¼مƒˆمƒٹمƒ¼مپ¨مپ—مپ¦مپ®ه½¹ه‰²م‚’و‹…مپ„مپ¾مپ™م€‚
ه¤–部ه§”託مپ¯م€Œو¥ه‹™مپ®ن¸¸وٹ•مپ’م€چمپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ›م‚“م€‚ه§”託ه…ˆمپ¨هچ”هٹ›مپ—مپ¦م€په¦ن¼ڑمپ®ç™؛ه±•م‚’م‚پمپ–مپ™م€Œهچ”هƒچن½“هˆ¶م€چم‚’築مپڈمپ“مپ¨مپŒم€پوˆگهٹںمپ¸مپ®éپ“و¨™مپ§مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»ه¦ن¼ڑه¤§ن¼ڑéپ‹ه–¶ه§”ه“،مپ«مپھمپ£مپںم‚‰مپ¾مپڑم‚„م‚‹ن؛‹ï½œمپ“م‚Œمپ‹م‚‰مپ®ه¦ن¼ڑ.com
Q14ï¼ڑه§”託ه…ˆمپ¨مپ®هچ”هƒچم‚’進م‚پم‚‹ن¸ٹمپ§مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ¯ن½•مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
ه§”託ه…ˆمپ¨مپ®هچ”هƒچم‚’وˆگهٹںمپ•مپ›م‚‹ن¸ٹمپ§مپ®مƒم‚¤مƒ³مƒˆمپ¯م€پو¬،مپ®3مپ¤مپ§مپ™م€‚
1.PDCAم‚µم‚¤م‚¯مƒ«مپ®ه…±هگŒéپ‹ç”¨
PDCAم‚µم‚¤م‚¯مƒ«م‚’ه§”託ه…ˆمپ¨ه…±هگŒمپ§éپ‹ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پم‚ˆم‚ٹهٹ¹وœçڑ„مپھه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپ¤مپھمپŒم‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ“م‚Œمپ¯م€Œن¸¸وٹ•مپ’م€چمپ¨مپ¯ه¯¾ç…§çڑ„مپ«م€په†…部م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ¨ه§”託ه…ˆمپŒن¸€ن½“مپ¨مپھمپ£مپ¦و”¹ه–„م‚’ç¹°م‚ٹè؟”مپ™ن½“هˆ¶مپ§مپ™م€‚
Plan(計画)ï¼ڑه†…部م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپŒن¸ه؟ƒمپ¨مپھم‚ٹم€په¦ن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶و–¹é‡م‚„ç›®و¨™م‚’ç–ه®ڑمپ—مپ¾مپ™م€‚
Do(ه®ںè،Œï¼‰ï¼ڑه§”託ه…ˆمپŒه°‚é–€و€§م‚’و´»مپ‹مپ—م€پ計画مپ«هں؛مپ¥مپ„مپںه…·ن½“çڑ„مپھن؛‹ه‹™ن½œو¥م‚„ه¤§ن¼ڑéپ‹ه–¶م‚’و‹…مپ„مپ¾مپ™م€‚
Check(評ن¾،)ï¼ڑه†…部م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپ¨ه§”託ه…ˆمپŒمپ¨م‚‚مپ«مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’ه…±وœ‰مپ—م€پوˆگوœم‚„èھ²é،Œم‚’ه®¢è¦³çڑ„مپ«و¤œè¨¼مپ—مپ¾مپ™م€‚
Action(و”¹ه–„)ï¼ڑè©•ن¾،çµگوœم‚’م‚‚مپ¨مپ«م€پéپ‹ه–¶و–¹و³•م‚„計画مپ®ن؟®و£م€پو”¹ه–„ç–م‚’هڈŒو–¹مپ®و„ڈ見م‚’ه‡؛مپ—هگˆمپ£مپ¦ه®ںè،Œمپ—م€پو¬،مپ®م‚µم‚¤م‚¯مƒ«مپ¸مپ¨مپ¤مپھمپ’مپ¾مپ™م€‚
2.م‚¹مƒمƒ¼مƒ„مپ®ç›£ç£مپ¨éپ¸و‰‹مپ®م‚ˆمپ†مپھé–¢ن؟‚و€§مپ®و§‹ç¯‰
مپ“مپ®é–¢ن؟‚و€§مپ¯م€پوکژç¢؛مپھه½¹ه‰²هˆ†و‹…مپ¨ن؟،é ¼مپ«هں؛مپ¥مپ„مپںهچ”هƒچن½“هˆ¶م‚’وŒ‡مپ—مپ¾مپ™م€‚
- 監ç£ï¼ˆن؛‹ه‹™ه±€ï¼‰ï¼ڑه¦ن¼ڑمپ®éپ‹ه–¶و–¹é‡م‚„ç›®و¨™م‚’وکژç¢؛مپ«ن¼مپˆم€پوœ€çµ‚çڑ„مپھو„ڈو€و±؛ه®ڑم‚’è،Œمپ„مپ¾مپ™م€‚éپ¸و‰‹مپ®èƒ½هٹ›م‚’ن؟،مپکم€پوœ€ه¤§مپ®مƒ‘مƒ•م‚©مƒ¼مƒمƒ³م‚¹م‚’ç™؛وڈ®مپ§مپچم‚‹ç’°ه¢ƒم‚’و•´مپˆم‚‹ه½¹ه‰²مپ§مپ™م€‚
- éپ¸و‰‹ï¼ˆه§”託ه…ˆï¼‰ï¼ڑ監ç£مپ®وŒ‡ç¤؛م‚’و£ç¢؛مپ«çگ†è§£مپ—م€په°‚é–€çڑ„مپھم‚¹م‚مƒ«م‚’وœ€ه¤§é™گمپ«و´»مپ‹مپ—مپ¦ه®ںه‹™م‚’éپ‚è،Œمپ—مپ¾مپ™م€‚مپ¾مپںم€پçڈ¾ه ´مپ®çٹ¶و³پم‚’監ç£مپ«مƒ•م‚£مƒ¼مƒ‰مƒگمƒƒم‚¯مپ—م€پوˆ¦ç•¥مپ®ç²¾ه؛¦م‚’é«کم‚پم‚‹ه½¹ه‰²م‚‚و‹…مپ„مپ¾مپ™م€‚
3.ه§”託ه…ˆمپ®ه°‚é–€و€§مپ®ç™؛وڈ®
ه§”託ه…ˆمپ«و¥ه‹™م‚’ن¾é ¼مپ™م‚‹ه¤§مپچمپھمƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپ¯م€پمپمپ®ه°‚é–€و€§م‚’و´»ç”¨مپ§مپچم‚‹مپ“مپ¨مپ«مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚هچکمپ«وŒ‡ç¤؛مپ•م‚Œمپںن½œو¥م‚’مپ“مپھمپ™مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€په§”託ه…ˆمپŒوŒپمپ¤ه°‚é–€çں¥èکم‚„経験م‚’ç©چو¥µçڑ„مپ«ه¼•مپچه‡؛مپ™مپ“مپ¨مپŒé‡چè¦پمپ§مپ™م€‚
- ه•ڈé،Œè§£و±؛مپ¸مپ®و´»ç”¨ï¼ڑه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ§ç”ںمپکم‚‹ه•ڈé،Œمپ«ه¯¾مپ—م€په§”託ه…ˆمپ®وŒپمپ¤مƒژم‚¦مƒڈم‚¦م‚„وœ€و–°وƒ…ه ±مپ«هں؛مپ¥مپ„مپں解و±؛ç–م‚’وڈگو،ˆمپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپ„مپ¾مپ™م€‚
- و”¹ه–„وڈگو،ˆمپ®ن؟ƒé€²ï¼ڑو—¢هکمپ®و¥ه‹™مƒ—مƒم‚»م‚¹م‚„مƒ„مƒ¼مƒ«مپ®و”¹ه–„مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€په°‚é–€çڑ„مپھ視点مپ‹م‚‰مپ®م‚¢مƒ‰مƒگم‚¤م‚¹م‚’و±‚م‚پمپ¾مپ™م€‚
- و–°مپ—مپ„م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®ه‰µه‡؛ï¼ڑه§”託ه…ˆمپ®ن¼پç”»هٹ›م‚’و´»مپ‹مپ—م€پو–°مپںمپھن¼ڑه“،م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚„م‚¤مƒ™مƒ³مƒˆمپ®ن¼پç”»مپ«مپ¤مپ„مپ¦هچ”هƒچمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¦ن¼ڑمپ®ن¾،ه€¤هگ‘ن¸ٹمپ«مپ¤مپھمپ’مپ¾مپ™م€‚
Q15ï¼ڑه¤–部ه§”託مپ—مپںن؛‹ه‹™ه±€مپ®و¥ه‹™ه“پè³ھمپ¯م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپ«è©•ن¾،مپ™م‚Œمپ°è‰¯مپ„مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
هچکمپ«م€Œè²»ç”¨مپ«è¦‹هگˆمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ‹م€چمپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€په®¢è¦³çڑ„مپھوŒ‡و¨™ï¼ˆه®ڑé‡ڈçڑ„مپھè©•ن¾،)مپ¨ه®ڑو€§çڑ„مپھè©•ن¾،مپ®ن¸،é¢مپ‹م‚‰è©•ن¾،مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒهٹ¹وœçڑ„مپ§مپ™م€‚
- ه®¢è¦³çڑ„مپھوŒ‡و¨™ï¼ڑن¼ڑه“،مپ‹م‚‰مپ®ه•ڈمپ„هگˆم‚ڈمپ›ه¯¾ه؟œو™‚é–“م€پن¼ڑè²»ه›هڈژçژ‡م€پم‚¤مƒ™مƒ³مƒˆهڈ‚هٹ 者و؛€è¶³ه؛¦م‚¢مƒ³م‚±مƒ¼مƒˆمپ®çµگوœم€پو¥ه‹™ه ±ه‘ٹو›¸مپ®وڈگه‡؛çٹ¶و³پمپھمپ©م‚’ه®ڑوœںçڑ„مپ«ç¢؛èھچمپ—مپ¾مپ™م€‚
- ه®ڑو€§çڑ„مپھè©•ن¾،ï¼ڑو‹…ه½“者مپ¨مپ®م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³مپ®ه††و»‘مپ•م€پوڈگو،ˆه†…ه®¹مپ®è³ھم€په•ڈé،Œç™؛ç”ںو™‚مپ®ه¯¾ه؟œهٹ›مپھمپ©م€پو•°ه€¤مپ§مپ¯و¸¬م‚Œمپھمپ„部هˆ†م‚‚è©•ن¾،مپ®ه¯¾è±،مپ¨مپ—مپ¾مپ™م€‚
مپ“م‚Œم‚‰مپ®è©•ن¾،é …ç›®م‚’ه¥‘ç´„ه‰چمپ«ه§”託ه…ˆمپ¨ه…±وœ‰مپ—م€په®ڑوœںçڑ„مپھمƒںمƒ¼مƒ†م‚£مƒ³م‚°مپ§مƒ•م‚£مƒ¼مƒ‰مƒگمƒƒم‚¯م‚’è،Œمپ†مپ“مپ¨مپ§م€پو¥ه‹™ه“پè³ھم‚’継ç¶ڑçڑ„مپ«و”¹ه–„مپ—مپ¦مپ„مپڈمپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ™م€‚ه§”託ه…ˆمپ¯م€پهچکمپھم‚‹ن½œو¥è€…مپ§مپ¯مپھمپڈم€په¦ن¼ڑم‚’ه…±مپ«وˆگé•·مپ•مپ›م‚‹مƒ‘مƒ¼مƒˆمƒٹمƒ¼مپ§مپ™م€‚良ه¥½مپھé–¢ن؟‚م‚’築مپچمپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
Q16ï¼ڑه¤–部مپ‹م‚‰è¬›و¼”者م‚’و‹›مپڈéڑ›م€په§”託مپ§مپچم‚‹و¥ه‹™مپ«مپ¯ن½•مپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™مپ‹ï¼ں
講و¼”者مپ¨مپ®é€£çµ،م‚„و‰‹é…چمپ«é–¢مپ™م‚‹و¥ه‹™مپ¯م€په¤–部ه§”託مپŒهڈ¯èƒ½مپ§مپ™م€‚
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه§”託ه…ˆمپ¯م€پ講و¼”者مپ¨مپ®م‚„م‚ٹهڈ–م‚ٹم‚’م‚¹مƒ مƒ¼م‚؛مپ«é€²م‚پم‚‹مپںم‚پمپ®مƒژم‚¦مƒڈم‚¦م‚’وŒپمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚ن¸»مپ«و¬،مپ®م‚ˆمپ†مپھو¥ه‹™م‚’ه§”託مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
- 講و¼”ن¾é ¼çٹ¶مپ®é€پن»ک
- 講و¼”ه†…ه®¹مپ®ç¢؛èھچمپ¨èھ؟و•´
- و—…è²»مƒ»è¬ç¤¼مپ®و”¯و‰•مپ„و‰‹é…چ(ç¨ژه‹™ه‡¦çگ†ï¼‰
- ه®؟و³ٹو–½è¨م‚„ن؛¤é€ڑو‰‹و®µمپ®و‰‹é…چ
- 講و¼”ه½“و—¥مپ®م‚µمƒمƒ¼مƒˆï¼ˆن¼ڑه ´و،ˆه†…م€پو©ںوگو؛–ه‚™مپھمپ©ï¼‰
مپ“م‚Œم‚‰مپ®و¥ه‹™م‚’ه§”託مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¦ن¼ڑن؛‹ه‹™ه±€مپ¯وœ¬و¥مپ®ن¼پç”»م‚„ه¦è،“ه†…ه®¹مپ®ه……ه®ںمپ«é›†ن¸مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚特مپ«وµ·ه¤–مپ‹م‚‰مپ®è¬›و¼”者م‚’و‹›مپڈه ´هگˆم€په¤ڑ言èھه¯¾ه؟œم‚„و™‚ه·®م‚’考و…®مپ—مپں連çµ،èھ؟و•´مپŒه؟…è¦پمپ¨مپھم‚‹مپںم‚پم€په°‚é–€و¥è€…مپ«ن»»مپ›م‚‹مپ“مپ¨مپ§è² و‹…م‚’ه¤§مپچمپڈ軽و¸›مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
ن¾‹مپˆمپ°م€پوµ·ه¤–مپ‹م‚‰مپ®و‹›èپکمپ®ه ´هگˆم€په¤§و‰‹مپ®و—…è،Œن¼ڑ社م‚„و—…è،Œن»£çگ†ه؛—مپ¸ه§”託م‚’و¤œè¨ژمپ™م‚Œمپ°م€پ飛è،Œو©ںمپ®و‰‹é…چمپ‹م‚‰مƒ›مƒ†مƒ«م€پé€ڑ訳م‚’هگ«م‚پمپںمƒ¯مƒ³م‚¹مƒˆمƒƒمƒ—مƒ»م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپŒهڈ—مپ‘م‚‰م‚Œم‚‹مپ®مپ§ه¤§ه¤‰ن¾؟هˆ©مپ§مپ™م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
Q17ï¼ڑè¨ک者ç™؛è،¨م‚„مƒم‚¹م‚³مƒںمپ¨مپ®ه¯¾ه؟œمپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®ه§”託مپ¯هڈ¯èƒ½مپ§مپ™مپ‹ï¼ں
مپ¯مپ„م€‚ه؟…è¦پو¥ه‹™مپ”مپ¨مپ®ه§”託م‚‚هڈ¯èƒ½مپ§مپ™م€‚
ه؛ƒه ±و´»ه‹•مپ¯ه°‚é–€و€§مپŒé«کمپڈم€په¤–部ه§”託مپ®مƒ،مƒھمƒƒمƒˆمپŒه¤§مپچمپ„و¥ه‹™مپ§مپ™م€‚
ه¦ن¼ڑمپ®وˆگوœم‚„ه¦è،“ه¤§ن¼ڑمپ®وƒ…ه ±م‚’ه؛ƒمپڈ社ن¼ڑمپ«ç™؛ن؟،مپ™م‚‹مپںم‚پم€په؛ƒه ±مپ®ه°‚é–€çں¥èکم‚’وŒپمپ¤و¥è€…مپ«و¬،مپ®م‚ˆمپ†مپھو¥ه‹™م‚’ه§”託مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
- مƒ—مƒ¬م‚¹مƒھمƒھمƒ¼م‚¹مپ®ن½œوˆگمƒ»é…چن؟،
- è¨ک者ç™؛è،¨ن¼ڑمپ®ن¼پç”»مƒ»éپ‹ه–¶
- ه°‚é–€مƒ،مƒ‡م‚£م‚¢م‚„ن¸€èˆ¬مƒ،مƒ‡م‚£م‚¢مپ¸مپ®وƒ…ه ±وڈگن¾›
- هڈ–وگه¯¾ه؟œçھ“هڈ£مپ®è¨ç½®
- SNSم‚„م‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆمپ§مپ®وƒ…ه ±ç™؛ن؟،
- ç™؛è،¨ه¾Œمپ®هڈچéں؟مپ®مƒ•م‚£مƒ¼مƒ‰مƒگمƒƒم‚¯مپ®مپ¾مپ¨م‚پ
特مپ«م€په¦ن¼ڑمپ®é‡چè¦پمپھç ”ç©¶وˆگوœم‚’社ن¼ڑمپ«ç™؛ن؟،مپ™م‚‹éڑ›مپ«مپ¯م€په°‚é–€ه®¶مپ«م‚ˆم‚‹éپ©هˆ‡مپھه؛ƒه ±و´»ه‹•ï¼ˆو³•çڑ„مƒپم‚§مƒƒم‚¯م‚„مƒھم‚¹م‚¯ه¯¾ç–م‚’هگ«م‚€ï¼‰مپŒن¸چهڈ¯و¬ مپ§مپ™م€‚ه§”託ه…ˆمپ®مƒژم‚¦مƒڈم‚¦م‚’و´»ç”¨مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پم‚ˆم‚ٹهٹ¹وœçڑ„مپھوƒ…ه ±ç™؛ن؟،مپŒوœںه¾…مپ§مپچمپ¾مپ™م€‚
مپٹم‚ڈم‚ٹمپ«
ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه¤–部ه§”託مپ¯م€پن¸چه®‰م‚’解و¶ˆمپ—م€پéپ©هˆ‡مپھمƒ‘مƒ¼مƒˆمƒٹمƒ¼م‚’見مپ¤مپ‘م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€په¦ن¼ڑمپ®وŒپç¶ڑçڑ„مپھç™؛ه±•مپ«ه¤§مپچمپڈ貢献مپ—مپ¾مپ™م€‚ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±ن؟è·و³•م‚„é›»هگه¸³ç°؟ن؟هکو³•م€پGDPRم‚„ç”ںوˆگAIمپ®مƒھم‚¹م‚¯ه¯¾ه؟œمپھمپ©مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯2025ه¹´و™‚点مپ§مپ¯وµپه‹•çڑ„مپ§مپ‚م‚ٹم€پ詳細مپھو³•è¦ڈه¯¾ه؟œم‚„éپ‹ç”¨ن¸ٹمپ®و³¨و„ڈ点م€پم‚¬م‚¤مƒ‰مƒ©م‚¤مƒ³ه¤‰و›´ç‰مپ¯ه·»وœ«م‚³مƒ©مƒ مپ§مپ¾مپ¨م‚پمپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚éپ©ه®œوœ€و–°وƒ…ه ±م‚’مپ”هڈ‚ç…§مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
éپ©هˆ‡مپھه¤–部ه§”託م‚’è،Œمپ†مپںم‚پمپ«مپ¯م€پ
çڈ¾çٹ¶هˆ†وگ → ه„ھه…ˆه؛¦و•´çگ† → 見ç©چمƒ»و¯”較→مƒھم‚¹م‚¯هˆ†وگ→ه¤–部ه§”託(ه¥‘約)
مپ®هگ„مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ®وœ€و–°وƒ…ه ±م‚’ه…ƒمپ«م€په®ڑé‡ڈمƒ»ه®ڑو€§هˆ†وگم‚’経مپ¦م‚¹مƒ†مƒƒمƒ—م‚¢مƒƒمƒ—مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
ه¦ن¼ڑمپ®هڈ¯èƒ½و€§م‚’ه؛ƒمپ’م‚‹مپںم‚پمپ«م€پمپ¾مپڑمپ¯çڈ¾çٹ¶هˆ†وگمپ‹م‚‰م‚¹م‚؟مƒ¼مƒˆمپ§مپ™ï¼پ
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»هڈ‚考مپ¨مپھم‚‹é€£è¼‰è¨کن؛‹
م€Œه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه§”託費用م‚’見直مپ™ï½ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®ه¤–部ه§”託مپ§è²»ç”¨ه¯¾هٹ¹وœم‚’وœ€ه¤§هŒ–مپ™م‚‹و–¹و³•ï½ï½œمپ“م‚Œمپ‹م‚‰مپ®ه¦ن¼ڑ.com
(ن»ک録)
م€گه·»وœ«م‚³مƒ©مƒ م€‘ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹AIمƒھم‚¹م‚¯مپ¾مپ¨م‚پ & مƒپم‚§مƒƒم‚¯مƒھم‚¹مƒˆï¼ˆ2025ه¹´ç‰ˆï¼‰
ç”ںوˆگAIمپ¯و–‡و›¸ن½œوˆگم€پمƒ‡مƒ¼م‚؟هˆ†وگم€په•ڈمپ„هگˆم‚ڈمپ›ه¯¾ه؟œمپھمپ©ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®هٹ¹çژ‡هŒ–مپ«ه¤§مپچمپڈ貢献مپ™م‚‹ن¸€و–¹م€پ特وœ‰مپ®مƒھم‚¹م‚¯م‚‚ن¼´مپ„مپ¾مپ™م€‚
وœ¬م‚³مƒ©مƒ مپ§مپ¯م€پ2025ه¹´مپ®وœ€و–°ه‹•هگ‘م‚’è¸ڈمپ¾مپˆمپںمƒھم‚¹م‚¯هˆ†é،مپ¨م€په…·ن½“çڑ„مپھç®،çگ†مƒ»ه¯¾ç–و–¹و³•م‚’解èھ¬مپ—مپ¾مپ™م€‚AIمپ®ن¾؟هˆ©مپ•مپ¨مƒھم‚¹م‚¯مپ¯ه¸¸مپ«م‚»مƒƒمƒˆمپ§ç®،çگ†مپŒو±‚م‚پم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚
ه·»وœ«مƒپم‚§مƒƒم‚¯مƒھم‚¹مƒˆم‚’و´»ç”¨مپ—مپ¦م€په¤–部ه§”託مƒ»ه؛ƒه ±مƒ»ه¦ن¼ڑèھŒéپ‹ه–¶مپ«مپٹمپ‘م‚‹م‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹مپ®هں؛盤ه¼·هŒ–م‚’ه®ڑه¸¸هŒ–مپ—مپ¾مپ—م‚‡مپ†م€‚
ç”ںوˆگAIو´»ç”¨5ه¤§مƒھم‚¹م‚¯مپ®و•´çگ†
1.وƒ…ه ±و¼ڈو´©مƒھم‚¹م‚¯
- AIمƒ„مƒ¼مƒ«مپ¸ه…¥هٹ›مپ™م‚‹وƒ…ه ±مپ«م€په€‹ن؛؛وƒ…ه ±م‚„و©ںه¯†مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’هگ«م‚پمپھمپ„مپ“مپ¨مپŒوœ€é‡چè¦پم€‚
- ه¦ن¼ڑن¼ڑه“،وƒ…ه ±م€پوœھç™؛è،¨ç ”究مƒ‡مƒ¼م‚؟مپھمپ©و©ںه¯†وƒ…ه ±مپ¯ه؟…مپڑمƒم‚¹م‚مƒ³م‚°مپ‹é™¤ه¤–م€‚
- AIم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®م€Œم‚ھمƒ—مƒˆم‚¢م‚¦مƒˆè¨ه®ڑم€چم‚’و´»ç”¨مپ—م€په¦ç؟’مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ¨مپ—مپ¦هˆ©ç”¨مپ•م‚Œمپھمپ„م‚ˆمپ†مپ«مپ™م‚‹م€‚
- ه¤–部ه§”託و¥è€…مپ«م‚‚هگŒو§کمپ®ç®،çگ†م‚’ه¥‘ç´„مپ§ç¾©ه‹™ن»کمپ‘م‚‹م€‚
2.è‘—ن½œو¨©مƒ»و³•ن»¤مƒھم‚¹م‚¯
- AIمپŒç”ںوˆگمپ™م‚‹و–‡و›¸مƒ»ه›³è،¨مپŒè‘—ن½œو¨©ن¾µه®³مپ™م‚‹و‡¸ه؟µمپŒمپ‚م‚‹م€‚
- 2025ه¹´çڈ¾هœ¨م€پهˆ¤ن¾‹مƒ»م‚¬م‚¤مƒ‰مƒ©م‚¤مƒ³مپ¯وµپه‹•çڑ„مپ§مپ‚م‚ٹم€په¸¸مپ«وœ€و–°ç¢؛èھچمپŒن¸چهڈ¯و¬ م€‚
- AIمپ«ه¦ن¼ڑ独è‡ھ資و–™م‚’ه¦ç؟’مپ•مپ›م‚‹éڑ›مپ¯م€په¥‘ç´„مƒ»هˆ©ç”¨è¦ڈç´„مپ§è²¬ن»»ç¯„ه›²م‚’وکژç¢؛هŒ–م€‚
3.مƒگم‚¤م‚¢م‚¹مƒ»ه€«çگ†مƒھم‚¹م‚¯
- AIمپ®ه¦ç؟’مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ«هپڈم‚ٹمپŒمپ‚م‚‹مپ¨ه·®هˆ¥çڑ„مƒ»هپڈ見و··ه…¥مپ®هچ±é™؛مپŒمپ‚م‚‹م€‚
- ه¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ§ç”¨مپ„م‚‹AIم‚¢م‚¦مƒˆمƒ—مƒƒمƒˆمپ¯ه…¬ه¹³و€§م‚’ن؟مپ¤م‚ˆمپ†è¨è¨ˆمƒ»ç›£è¦–م‚’è،Œمپ†مپ“مپ¨م€‚
4.مƒڈمƒ«م‚·مƒچمƒ¼م‚·مƒ§مƒ³ï¼ˆèھ¤وƒ…ه ±ï¼‰مƒھم‚¹م‚¯
- AIمپ¯è™ڑهپ½وƒ…ه ±م‚„ن؛‹ه®ںèھ¤èھچم‚’ç”ںوˆگمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹ï¼ˆمƒڈمƒ«م‚·مƒچمƒ¼م‚·مƒ§مƒ³ï¼‰م€‚
- 特مپ«ه¦è،“ç™؛è،¨و–‡و›¸م‚„ه؛ƒه ±è³‡و–™ن½œوˆگمپ§مپ¯م€په؟…مپڑه°‚é–€م‚¹م‚؟مƒƒمƒ•مپŒه†…ه®¹م‚’مƒ€مƒ–مƒ«مƒپم‚§مƒƒم‚¯مپ—訂و£مپ™م‚‹مƒ—مƒم‚»م‚¹م‚’è¨مپ‘م‚‹م€‚
5.م‚»م‚مƒ¥مƒھمƒ†م‚£مƒ»و‚ھ用مƒھم‚¹م‚¯
- AIم‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¯م‚µم‚¤مƒگمƒ¼و”»و’ƒمپ®و¨™çڑ„مپ¨مپھم‚‹هڈ¯èƒ½و€§م‚‚مپ‚م‚‹م€‚
- م‚¯مƒ©م‚¦مƒ‰م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®هˆ©ç”¨ه¥‘ç´„م€پمƒ‡مƒ¼م‚؟ن؟ç®،ه ´و‰€م€پم‚¢م‚¯م‚»م‚¹و¨©é™گم‚’هژ³ه¯†ç®،çگ†مپ—م€په§”託ه…ˆمپ«م‚‚éپµه®ˆمپ•مپ›م‚‹م€‚
م€گç”ںوˆگAIو´»ç”¨مپ®مپںم‚پمپ®ه®ںè·µمƒپم‚§مƒƒم‚¯مƒھم‚¹مƒˆم€‘
| مƒپم‚§مƒƒم‚¯ | é …ç›®ï¼ˆç¢؛èھچه†…ه®¹ï¼‰ | م‚³مƒ،مƒ³مƒˆمƒ»ç•™و„ڈ点 |
| م€€ | و©ںه¯†وƒ…ه ±مƒ»ه€‹ن؛؛وƒ…ه ±مپ¯AIه…¥هٹ›ه‰چمپ«ه؟…مپڑç¢؛èھچمƒ»ه‰ٹ除مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹ | ن¼ڑه“،هگچç°؟مƒ»ه†…部資و–™مپ¯ç›´وژ¥AIمپ¸م‚¢مƒƒمƒ—مƒمƒ¼مƒ‰مپ—مپھمپ„ |
| م€€ | ه§”託ه¥‘ç´„و›¸مپ«AIهˆ©ç”¨مƒ»مƒ‡مƒ¼م‚؟ن؟هکه ´و‰€مƒ»م‚ھمƒ—مƒˆم‚¢م‚¦مƒˆو–¹é‡مپŒوکژè¨کمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ‹ | مƒ‡مƒ¼م‚؟مپŒç¬¬ن¸‰è€…AIمپ«ه¦ç؟’مپ•م‚Œمپھمپ„è¨ه®ڑمپ‹و…ژé‡چمپ«ç¢؛èھچ |
| م€€ | ç”ںوˆگAIمپ®ه¦ç؟’ه…ƒمƒ»ç”ںوˆگو–¹و³•مƒ»è‘—ن½œو¨©مپ®و‰±مپ„م‚’وœ€و–°م‚¬م‚¤مƒ‰مƒ©م‚¤مƒ³مپ§ç¢؛èھچمپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹ | ه؟…è¦پمپ«ه؟œمپکمپ¦ه°‚é–€ه®¶مƒ»مƒ™مƒ³مƒ€مƒ¼ç…§ن¼ڑم‚‚م‚»مƒƒمƒˆمپ§ه®ںو–½ |
| م€€ | ç”ںوˆگAIمپ®م‚¢م‚¦مƒˆمƒ—مƒƒمƒˆم‚’ن؛؛مپ®ç›®مپ§مƒ€مƒ–مƒ«مƒپم‚§مƒƒم‚¯مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹ï¼ˆمƒ•م‚،م‚¯مƒˆمƒپم‚§مƒƒم‚¯ï¼‰ | 特مپ«è«–و–‡م€په؛ƒه ±م€پو،ˆه†…و–‡و›¸مپھمپ©مپ¯مƒ€مƒ–مƒ«مƒپم‚§مƒƒم‚¯م‚’ه؟…é ˆمپ¨مپ™م‚‹ |
| م€€ | AIو´»ç”¨è¨ک録(مپ©مپ®مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’مپ©مپ†ن½؟مپ£مپںمپ‹ï¼‰م‚’و®‹مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹ | مƒˆمƒ©مƒ–مƒ«ç™؛ç”ںو™‚مپ«èھ¬وکژ責ن»»مپŒهڈ–م‚Œم‚‹éپ‹ç”¨ |
| م€€ | AIمƒگم‚¤م‚¢م‚¹مƒ»ه€«çگ†مƒھم‚¹م‚¯مپ¸مپ®é…چو…®مƒ»و³¨و„ڈه–ڑèµ·مپŒمپھمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ‹ | ن¸چه½“مپھه·®هˆ¥è،¨çڈ¾م‚„ه¦è،“çڑ„ن¸ç«‹و€§م‚’وگچمپھم‚ڈمپھمپ„م‚ˆمپ†ه…¨ن½“مپ§ç®،çگ† |
| م€€ | ه¤–部ه§”託ه…ˆمپ®وƒ…ه ±ç®،çگ†مƒ»ن؟é™؛هٹ ه…¥مƒ»AIéپ‹ç”¨ن½“هˆ¶مپŒç¢؛èھچمپ§مپچمپ¦مپ„م‚‹مپ‹ | ه§”託ه…ˆم‚‚وœ¬مƒھم‚¹مƒˆç›¸ه½“مپ®ه†…部éپ‹ç”¨م‚’ه¾¹ه؛•مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ‹مƒ’م‚¢مƒھمƒ³م‚°مپ™م‚‹ |
وœ¬و–‡هگ„و‰€مپ§AIمƒ»مƒ†م‚¯مƒژمƒم‚¸مƒ¼و´»ç”¨مƒھم‚¹م‚¯مپ«مپ¤مپ„مپ¦ç°،هچکمپ«è§¦م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ه ´هگˆم‚‚م€پ詳細مپ¯ه½“م‚³مƒ©مƒ م‚’éپ©ه®œهڈ‚ç…§مپ™م‚‹م‚ˆمپ†مپٹé،کمپ„مپ„مپںمپ—مپ¾مپ™م€‚ن»ٹه¾Œمپ®و³•ن»¤مƒ»هˆ¤ن¾‹مƒ»م‚¬م‚¤مƒ‰مƒ©م‚¤مƒ³ه¤‰و›´مپ«م‚‚éڑڈو™‚و³¨è¦–مپ—م€په¦ن¼ڑéپ‹ه–¶مپ®çڈ¾ه ´ه®ںه‹™مپ¸هڈچوک م‚’進م‚پمپ¦مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
م€گهڈ‚考م€‘
مƒ»AIمپ¨è‘—ن½œو¨©مپ«é–¢مپ™م‚‹ مƒپم‚§مƒƒم‚¯مƒھم‚¹مƒˆï¼†م‚¬م‚¤مƒ€مƒ³م‚¹ï½œو–‡هŒ–ه؛پ
مƒ»AIن؛‹و¥è€…م‚¬م‚¤مƒ‰مƒ©م‚¤مƒ³و،ˆï½œçµŒو¸ˆç”£و¥çœپ
مƒ»ç”ںوˆگAIو´»ç”¨مپ«مپٹمپ‘م‚‹م‚»م‚مƒ¥مƒھمƒ†م‚£مƒھم‚¹م‚¯ه¯¾ç–مپ®ه‹کو‰€ï½œNTTمƒ‡مƒ¼م‚؟
مƒ»و—¥وœ¬مپ®مƒ•م‚،م‚¯مƒˆمƒپم‚§مƒƒم‚¯مپ®çڈ¾çٹ¶مپ¨èھ²é،Œ – ç·ڈه‹™çœپ|ç·ڈه‹™çœپ
مƒ»AI مƒگم‚¤م‚¢م‚¹مپ¨مپ¯ï¼ں|SAP م‚¸مƒ£مƒ‘مƒ³و ھه¼ڈن¼ڑ
مƒ»AIو´»ç”¨مپ®م€Œمƒھم‚¹م‚¯م€چمپ«مپ©مپ†هگ‘مپچهگˆمپ†ï¼ں è¦ڑمپˆمپ¦مپٹمپچمپںمپ„م€ŒAIم‚¬مƒگمƒٹمƒ³م‚¹م€چو§‹ç¯‰مپ®و‰‹و³•ï½œمƒ“م‚¸مƒچم‚¹+IT