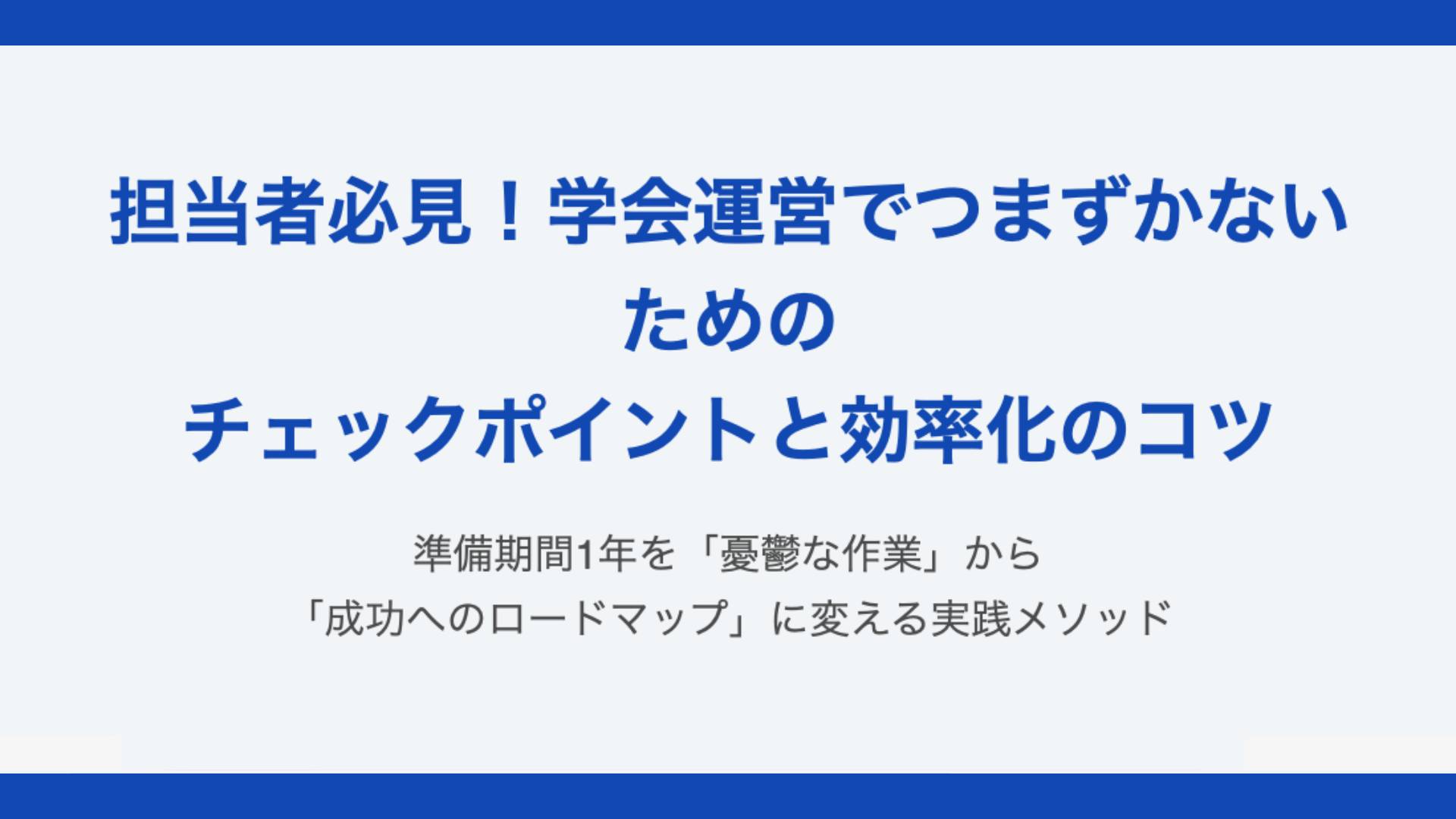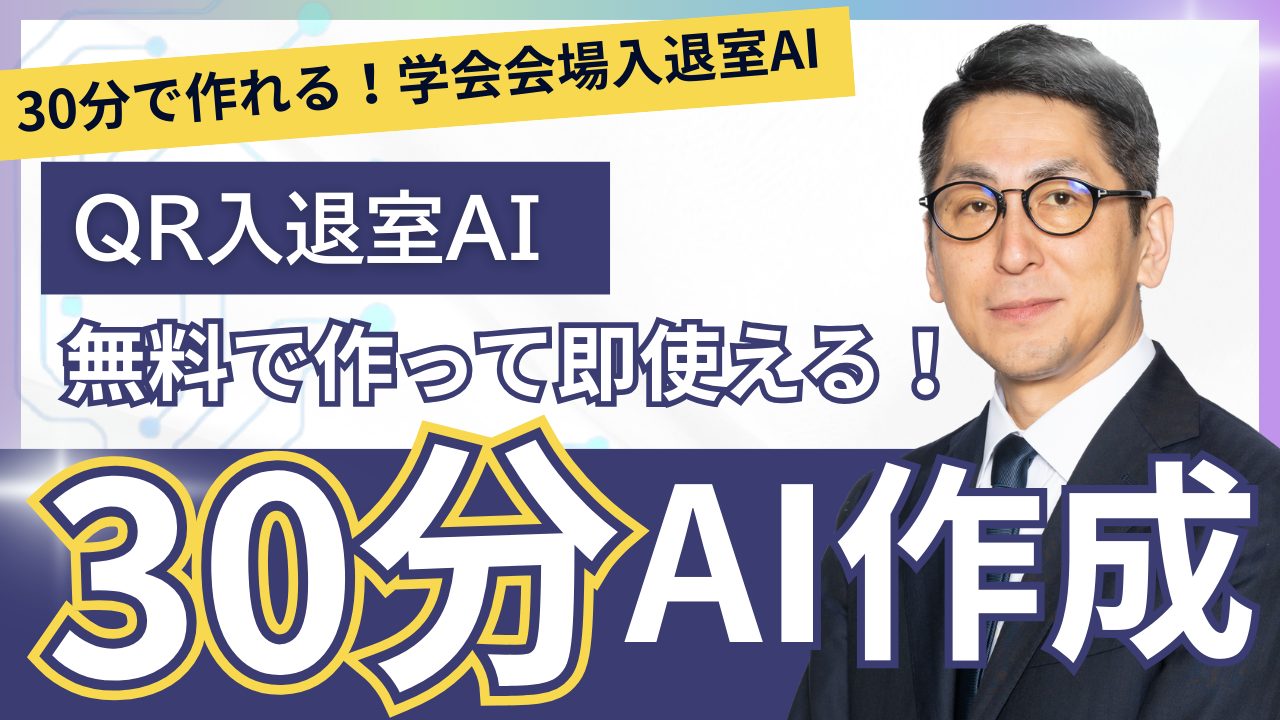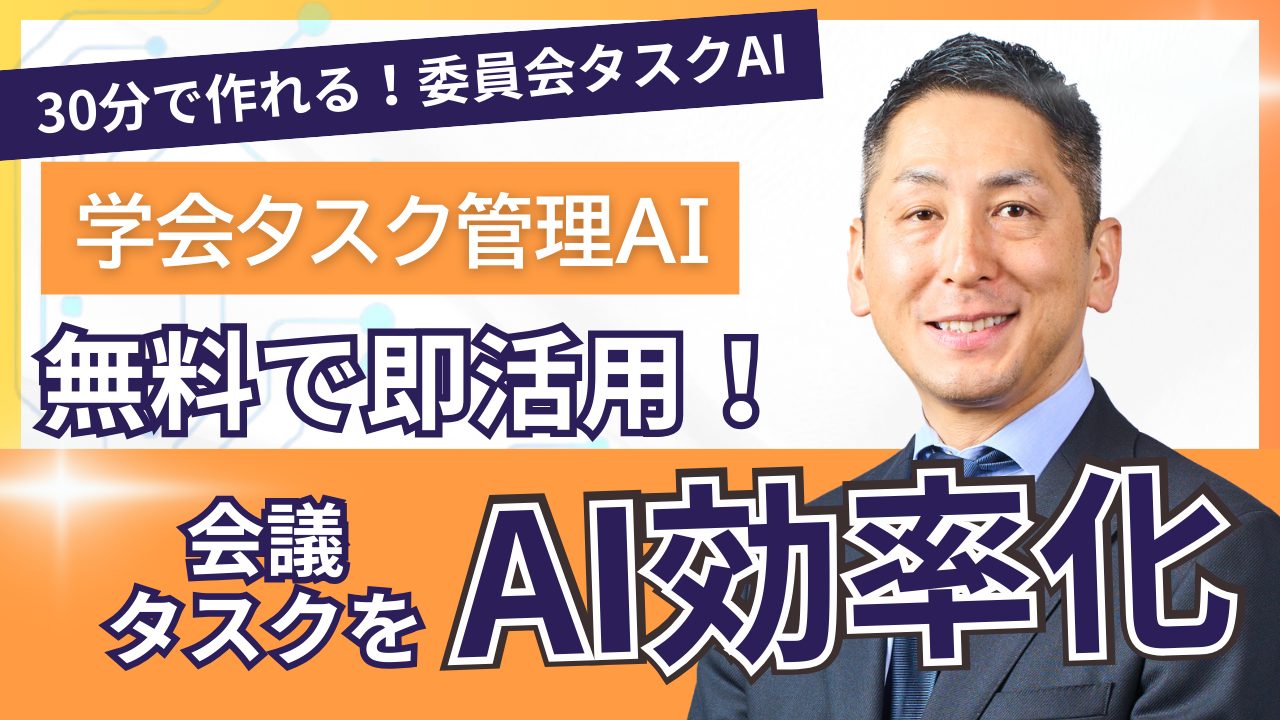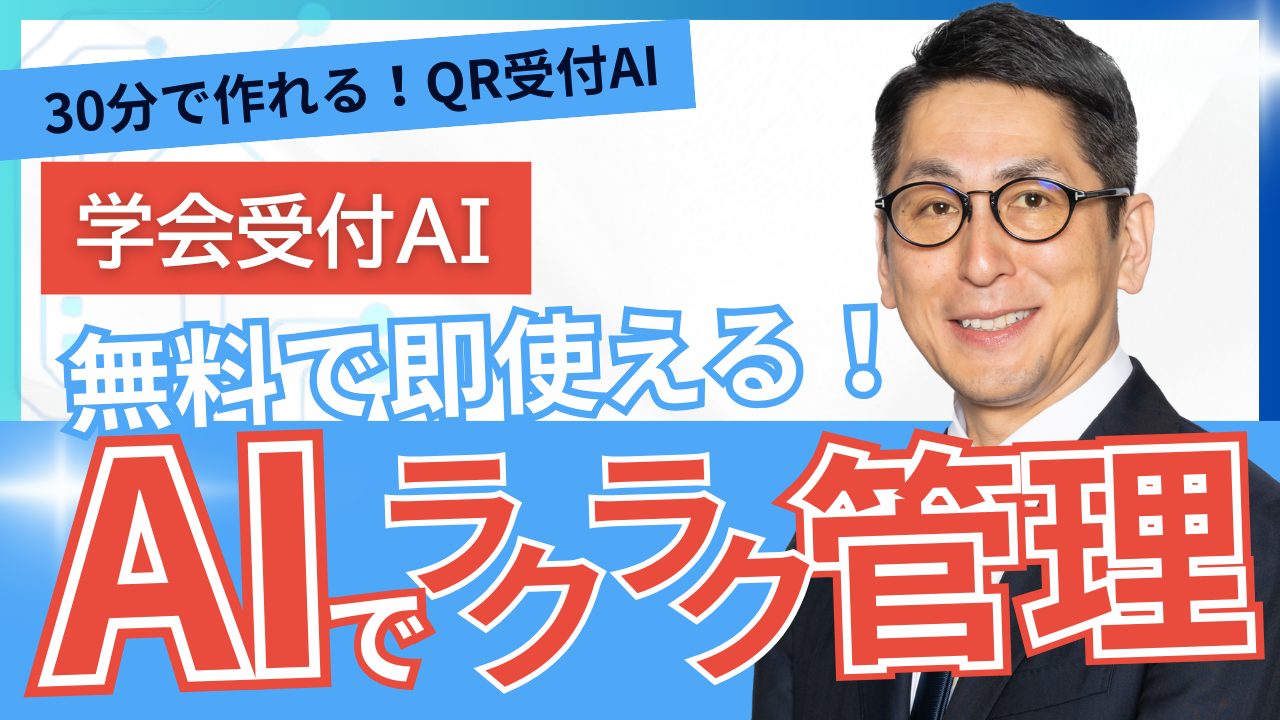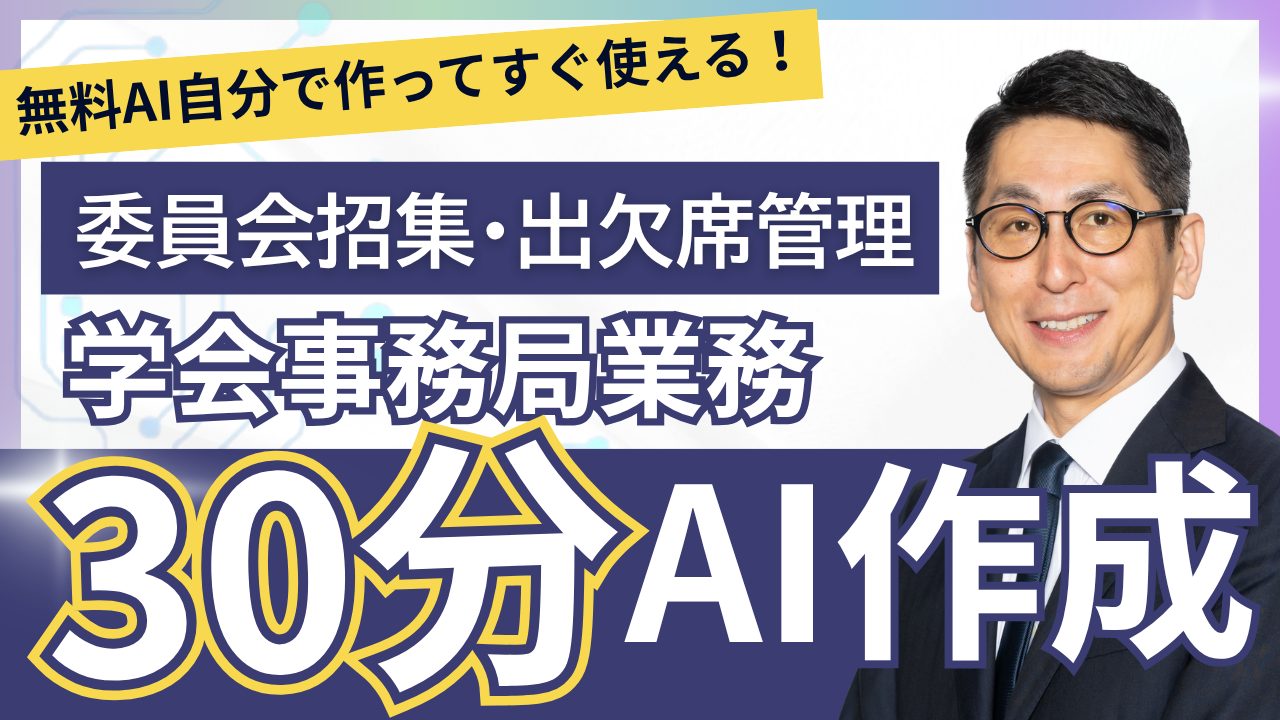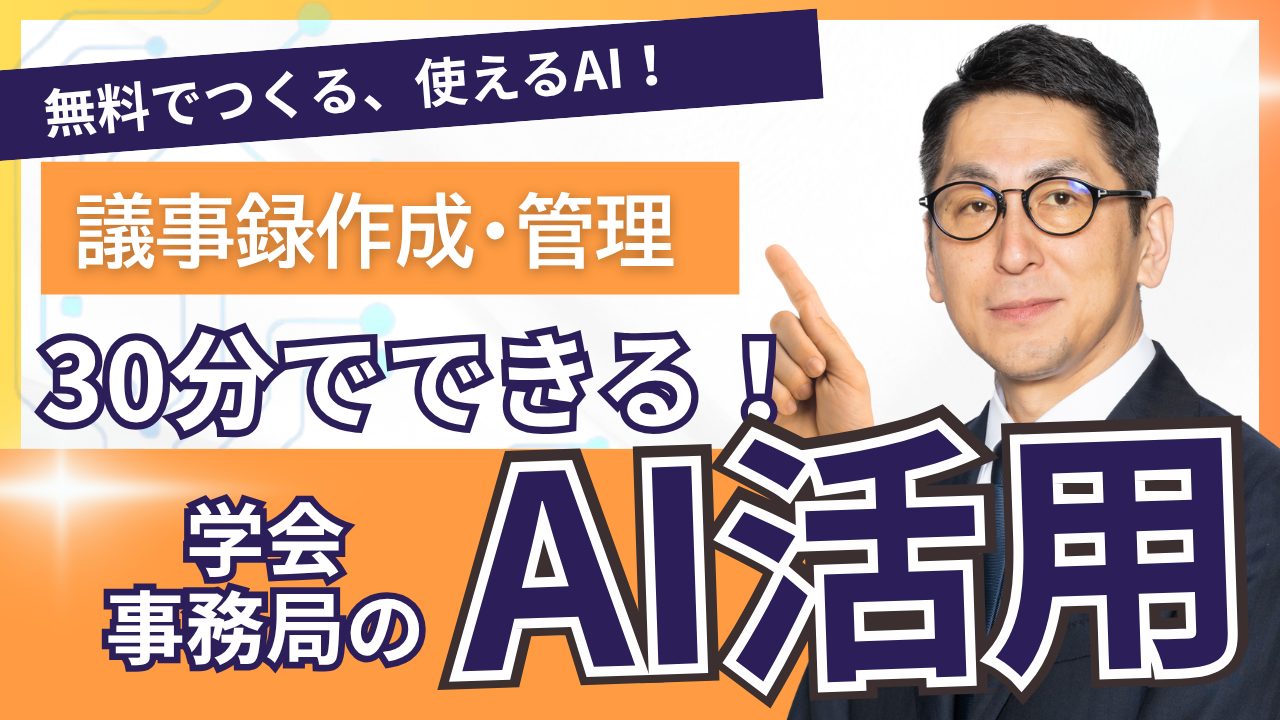гӮўгғігӮұгғјгғҲзөҗжһңгӮ’еӯҰдјҡйҒӢе–¶ж”№е–„гҒ«жҙ»гҒӢгҒҷгҒ«гҒҜпјҹгҖҖпҪһеҸӮеҠ иҖ…гҒ®еЈ°гҒӢгӮүеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгғ’гғігғҲпҪһ
2025е№ҙ08жңҲ27ж—Ҙ
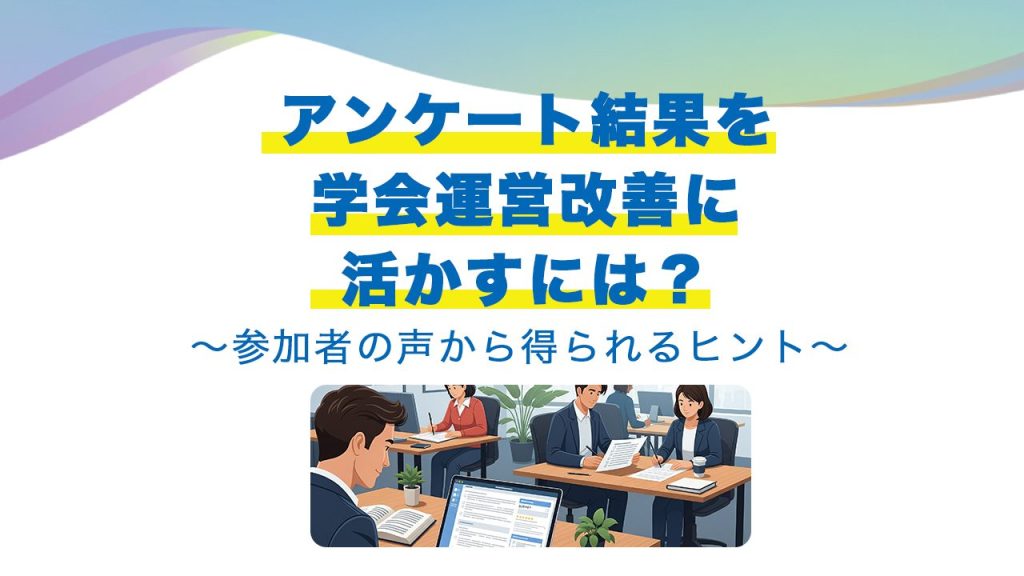
гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«гҖҖгӮўгғігӮұгғјгғҲгҒҢеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«гӮӮгҒҹгӮүгҒҷж°—гҒҘгҒҚгҒЁдҫЎеҖӨ
гӮўгғігӮұгғјгғҲгҒҜгҖҒеӯҰдјҡгҒҢиҮӘгӮүгҒ®йҒӢе–¶гҒЁеҗ‘гҒҚеҗҲгҒ„гҖҒж”№е–„гҒёгҒЁиёҸгҒҝеҮәгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘжүӢгҒҢгҒӢгӮҠгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҸӮеҠ иҖ…гҒ®еЈ°гҒҜгҖҒеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиіӘгҒ®еҗ‘дёҠгӮ„ж–№еҗ‘жҖ§гҒ®жӨңиЁҺгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒӘжғ…е ұжәҗгҒ§гҒҷгҖӮ
еӯҰдјҡгҒ«гҒҜз ”з©¶иҖ…гҖҒеӨ§еӯҰз”ҹгғ»йҷўз”ҹгҖҒдјҒжҘӯгҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҖҒдёҖиҲ¬еёӮж°‘гҒӘгҒ©гҖҒеӨҡж§ҳгҒӘз«Ӣе ҙгҒ®дәәгҖ…гҒҢй–ўгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖдәәгҒІгҒЁгӮҠгҒҢз•°гҒӘгӮӢиҰ–еә§гӮ’жҢҒгҒЎиҫјгӮҖгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгӮҢгӮүгӮ’дёҒеҜ§гҒ«еҸҺйӣҶгҒ—ж•ҙзҗҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒзө„з№”гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жҢҒз¶ҡеҸҜиғҪжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒйҖҸжҳҺжҖ§гӮ’дҝқиЁјгҒҷгӮӢе–¶гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж–Үи„ҲгҒ§гҖҢгӮўгғігӮұгғјгғҲиӘҝжҹ»гҖҚгҒҜеҸӨе…ёзҡ„гҒӢгҒӨжҷ®йҒҚзҡ„гҒӘжүӢжі•гҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиіӘе•ҸзҙҷгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҚҳзҙ”жҖ§гӮ’жҢҒгҒӨеҸҚйқўгҖҒгҒқгҒ®иғҢеҫҢгҒ«гҒҜзҸҫе ҙиӘІйЎҢгӮ„жҪңеңЁзҡ„гғӢгғјгӮәгӮ’еҸҜиҰ–еҢ–гҒ—гҖҒе°ҶжқҘеғҸгӮ’жҸҸгҒҸжҢҮйҮқгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҠӣгҒҢйҡ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮўгғігӮұгғјгғҲгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢдёҖж–№зҡ„гҒӘжғ…е ұеҸҺйӣҶгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒЁйҒӢе–¶еҒҙгҒЁгҒ®й–“гҒ«гҖҢеҜҫи©ұгҒ®гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҖҚгӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еЈ°гӮ’дёҒеҜ§гҒ«иӘӯгҒҝи§ЈгҒҚгҖҒзңҹж‘ҜгҒ«еҝңгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒҜиҮӘиә«гҒҢеӯҰдјҡгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢдёҖе“ЎгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮЁгғігӮІгғјгӮёгғЎгғігғҲпјҲеё°еұһж„ҸиӯҳгҖҒзөҶпјүгӮ’еј·гӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒиЁӯе•ҸиЁӯиЁҲгҒҢйҒҺеәҰгҒ«иӨҮйӣ‘еҢ–гҒ—гҒҹгӮҠйӣҶиЁҲгӮ„еҲҶжһҗгҒ«иҝҪгӮҸгӮҢгӮӢгҒЁгҖҒйӣҶгӮҒгҒҹеЈ°гӮ’жҙ»гҒӢгҒ—гҒҚгӮҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгӮўгғігӮұгғјгғҲгӮ’гҖҢе®ҹж–ҪгҒ—гҒҰе®үеҝғгҖҚгҒ§зөӮгӮҸгӮүгҒӣгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒеӣһзӯ”гӮ’иӘӯгҒҝи§ЈгҒҚгҖҒеҸҜиҰ–еҢ–гҒ—гҖҒзқҖе®ҹгҒ«йҒӢе–¶гҒёгҒЁгғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒиЁӯе•ҸиЁӯиЁҲгҒӢгӮүеҸҺйӣҶгҖҒеҲҶжһҗгҖҒгҒқгҒ—гҒҰж”№е–„гҒёгҒ®иҗҪгҒЁгҒ—иҫјгҒҝгҒҫгҒ§гҒ®дёҖйҖЈгҒ®е·ҘзЁӢгӮ’дҪ“зі»зҡ„гҒ«ж•ҙзҗҶгҒ—гҖҒеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«жҙ»гҒӢгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®иҰ–зӮ№гҒЁе·ҘеӨ«гӮ’иҖғгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
1. иЁӯе•ҸиЁӯиЁҲгҒЁе®ҹж–ҪгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§зҺҮзӣҙгҒӘж„ҸиҰӢгӮ’йӣҶгӮҒгӮӢ
еҸӮеҠ иҖ…гҒ®зҺҮзӣҙгҒӘеЈ°гӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиіӘе•ҸгӮ’гҖҒгҒ„гҒӨе°ӢгҒӯгӮӢгҒӢгҖҚгҒ«еҚҒеҲҶгҒӘй…Қж…®гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгӮўгғігӮұгғјгғҲгҒ®е“ҒиіӘгҒҜгҖҒиЁӯе•ҸеҶ…е®№гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгӮүгҒ„гҖҒе®ҹж–ҪгҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ„зҠ¶жіҒиЁӯе®ҡгҒ«гӮӮдҫқеӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
1.1. еӣһзӯ”гҒ®иІ жӢ…гӮ’жёӣгӮүгҒҷиЁӯе•ҸиЁӯиЁҲгҒ®гӮігғ„
еӣһзӯ”иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҢзӯ”гҒҲгӮ„гҒҷгҒ•гҖҚгҒҜжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘжқЎд»¶гҒ§гҒҷгҖӮиЁӯе•Ҹж•°гҒҢйҒҺеү°гҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜиіӘе•ҸгҒ®зӢҷгҒ„гҒҢжӣ–жҳ§гҒ§гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҖҒеӣһзӯ”гҒ®йҖ”дёӯйӣўи„ұгҒҢз”ҹгҒҳгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзөҗжһңзҡ„гҒ«жңүеҠ№еӣһзӯ”ж•°гҒҢжёӣе°‘гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒиӘҝжҹ»иҮӘдҪ“гҒ®дҝЎй јжҖ§гӮӮжҸәгӮүгҒҺгҒҫгҒҷгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒӘиЁӯе•ҸиЁӯиЁҲдҫӢпјҡ
- жҠҪиұЎзҡ„пјҡгҖҢе…ЁдҪ“зҡ„гҒ«гҒ”жәҖи¶ігҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҒӢпјҹгҖҚ
- е…·дҪ“зҡ„пјҡгҖҢи¬ӣжј”гҒ®еҶ…е®№гӮ„гғңгғӘгғҘгғјгғ гҖҒжҷӮй–“й…ҚеҲҶгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ©гҒ®зЁӢеәҰгҒ”жәҖи¶ігҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҒӢпјҹгҖҚ
иЁӯе•ҸгҒҜгҖҢжң¬еҪ“гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжғ…е ұгҖҚгӮ’жҠҪеҮәгҒҷгӮӢеҪўгҒ§иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еүҚжҸҗгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе•ҸгҒ„гҒ®ж–№еҗ‘жҖ§гҒҢж•ҙзҗҶгҒ•гӮҢгҖҒеӣһзӯ”иҖ…гҒ®и§ЈйҮҲгҒ¶гӮҢгҒҢе°‘гҒӘгҒ„иЁӯе•ҸгҒҜгҖҒиіӘгҒ®й«ҳгҒ„гғҮгғјгӮҝгҒ®еҸ–еҫ—гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒиіӘе•ҸиЎЁзҸҫгҒ«гӮӮе·ҘеӨ«гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеӯҰдјҡгҒЁгҒ„гҒҶе°Ӯй–ҖиүІгҒ®еј·гҒ„е ҙгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮеҸӮеҠ иҖ…е…Ёе“ЎгҒҢеҗҢеҲҶйҮҺгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘиЎЁзҸҫгӮ’йҒҝгҒ‘е№іжҳ“гҒӘиЁҖи‘үгҒ«зҪ®гҒҚжҸӣгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӨҡж§ҳгҒӘз«Ӣе ҙгҒ®еҸӮеҠ иҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰзӯ”гҒҲгӮ„гҒҷгҒ„е•ҸгҒ„гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒж•°еҖӨеҢ–гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе…ЁдҪ“гҒ®еӮҫеҗ‘гӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢиЁӯе•ҸгҒ«еҠ гҒҲгҖҒиҮӘз”ұиЁҳиҝ°гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еӣһзӯ”иҖ…гҒ®еЈ°гӮ’гӮҲгӮҠиұҠгҒӢгҒ«гҒҷгҒҸгҒ„дёҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢи¬ӣжј”гҒёгҒ®ж„ҹжғігҖҚгӮ„гҖҢж¬ЎеӣһгҒ«жңҹеҫ…гҒҷгӮӢдјҒз”»еҶ…е®№гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹи»ҪгҒ„гӮ¬гӮӨгғүгӮ’ж·»гҒҲгӮҢгҒ°гҖҒиҮӘз”ұиЁҳиҝ°гҒёгҒ®еҝғзҗҶзҡ„гғҸгғјгғүгғ«гӮӮдҪҺдёӢгҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘж”№е–„жЎҲгҒ«зөҗгҒігҒӨгҒҸж„ҸиҰӢгҒҢеҫ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иЁӯе•ҸеҪўејҸгҒ®йҒёжҠһгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеӨҡиӮўйҒёжҠһејҸгӮ„еҚҳдёҖйҒёжҠһејҸгҒҜеӣһзӯ”иІ жӢ…гҒҢи»ҪгҒҸгҖҒи©•дҫЎгҒ®е…ЁдҪ“еғҸгӮ’зҙ ж—©гҒҸжҺҙгӮҖгҒ®гҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒ5ж®өйҡҺи©•дҫЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮ№гӮұгғјгғ«еҪўејҸгҒҜгҖҒеӣһзӯ”гҒ®гҖҢгӮ°гғ©гғҮгғјгӮ·гғ§гғігҖҚгӮ’жҚүгҒҲгӮӢгҒ®гҒ«жңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮгӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢйҡӣгҒҜгҖҒеӣһзӯ”йҖІжҚ—гғҗгғјгҒ®иЎЁзӨәгӮ„гҖҒиіӘе•ҸеҲҶеІҗж©ҹиғҪгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеӣһзӯ”иҖ…гҒ®гғўгғҒгғҷгғјгӮ·гғ§гғіз¶ӯжҢҒгӮ’дҝқгҒӨгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
1.2. е®ҹж–ҪгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒҢеӣһзӯ”зҺҮгҒЁеӣһзӯ”гҒ®иіӘгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢ
гҖҢгҒ„гҒӨе®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҒӢгҖҚгҒ§гӮўгғігӮұгғјгғҲгҒ®иіӘгҒЁеӣһеҸҺзҺҮгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸеӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеӯҰдјҡй–үдјҡзӣҙеҫҢгҒ«еҸ—д»ҳгӮ„гӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§жЎҲеҶ…гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒеұ•зӨәгӮ„и¬ӣжј”гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҳжҶ¶гҒҢй®®жҳҺгҒӘзҠ¶ж…ӢгҒ§е®ҹеӢҷзҡ„гҒӘж„ҸиҰӢгӮ’еј•гҒҚеҮәгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮеҚіжҷӮжҖ§гӮ’жҙ»гҒӢгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе®ҹеғҚзҡ„гҒ§е…·дҪ“зҡ„гҒӘж”№е–„гғ’гғігғҲгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹж–ҪгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°еҲҘгҒ®еҠ№жһңпјҡ
- еҚіжҷӮе®ҹж–ҪпјҲеӯҰдјҡзӣҙеҫҢпјүпјҡиЁҳжҶ¶гҒҢй®®жҳҺгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘж„ҸиҰӢеҸҺйӣҶгҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ
- ж•°ж—ҘеҫҢе®ҹж–ҪпјҡеҶ·йқҷгҒӘжҢҜгӮҠиҝ”гӮҠгҒҢеҸҜиғҪгҖҒе»әиЁӯзҡ„гҒӘжҸҗжЎҲгҒҢеҫ—гӮ„гҒҷгҒ„
- 1йҖұй–“еҫҢе®ҹж–Ҫпјҡе…ЁдҪ“зҡ„гҒӘеҚ°иұЎгҒЁе…·дҪ“зҡ„иӘІйЎҢгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢиүҜгҒ„
дёҖж–№гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ«гҖҢзөӮдәҶеҫҢгӮўгғігӮұгғјгғҲгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒҷгӮӢдәҲе®ҡгҒ§гҒҷгҖҚгҒЁеҸӮеҠ иҖ…гҒ«дјқгҒҲгҒҰгҒҠгҒ‘гҒ°гҖҒеҝғзҗҶзҡ„гҒ«вҖқи©•дҫЎгӮ’еүҚжҸҗгҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢиҰ–зӮ№вҖқгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеӣһзӯ”жҷӮгҒ«гҒҜж—ўгҒ«еҸӮеҠ иҖ…гҒ®й ӯгҒ®дёӯгҒ§ж•ҙзҗҶгҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰеӣһзӯ”гҒ®ж·ұеәҰгӮ„е…·дҪ“жҖ§гҒҢеў—гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеӯҰдјҡжҠ„йҢІгӮ„гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ еҶҠеӯҗгҒ«гӮўгғігӮұгғјгғҲгҒ®е°Һз·ҡгӮ’еҗ«гӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒ®гӮӮгҖҒиҮӘ然гҒ§еҠ№жһңзҡ„гҒӘе°Һе…Ҙзӯ–гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒеӯҰдјҡгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ®ж–№еҗ‘жҖ§гӮ„й•·жңҹзҡ„иӘІйЎҢгӮ’е•ҸгҒ„гҒҹгҒ„е ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒз·ҸдјҡеүҚгҒӘгҒ©жҷӮй–“зҡ„и·қйӣўгӮ’зҪ®гҒ„гҒҹиӘҝжҹ»гҒҢйҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжҷӮй–“гӮ’е°‘гҒ—з©әгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҶ·йқҷгҒӘжҢҜгӮҠиҝ”гӮҠгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒйҒӢе–¶е…ЁдҪ“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҹж„ҸиҰӢгӮ„ж–№йҮқжҸҗиЁҖгӮ’йӣҶгӮҒгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
2. йӣҶиЁҲгғ»еҲҶжһҗгғ»ж”№е–„гғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгҒёгҒ®жҙ»з”ЁгӮ№гғҶгғғгғ—
гӮўгғігӮұгғјгғҲгҒҜгҖҢйӣҶгӮҒгҒҹгҒҫгҒҫгҖҚгҒ§гҒҜж„Ҹе‘ігӮ’гҒӘгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮйӣҶиЁҲгӮ„еҸҜиҰ–еҢ–гҖҒеҲҶжһҗгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгҒ•гӮүгҒ«е®ҹйҡӣгҒ®ж”№е–„гҒёгҒЁзөҗгҒігҒӨгҒ‘гҒҰеҲқгӮҒгҒҰдҫЎеҖӨгҒҢз”ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜж®өйҡҺгӮ’иёҸгӮ“гҒ гӮ№гғҶгғғгғ—гӮ’дҪ“зі»зҡ„гҒ«зө„гҒҝиҫјгҒҝгҖҒжөҒгӮҢгҒЁгҒ—гҒҰзўәз«ӢгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
2.1. еӣһзӯ”гӮ’гҖҢиҰӢгҒҲгӮӢеҢ–гҖҚгҒ—гҒҰе…ЁдҪ“еғҸгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢ
гҒҜгҒҳгӮҒгҒ«еӣһзӯ”гӮ’йӣҶиЁҲгҒ—гҖҒеҶ…е®№гӮ’иҰ–иҰҡзҡ„гҒ«жҚүгҒҲгӮ„гҒҷгҒ„еҪўејҸгҒёгҒЁеӨүжҸӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒӢгӮүе§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮе®ҡйҮҸгғҮгғјгӮҝгҒЁе®ҡжҖ§гғҮгғјгӮҝгҒ®дёЎи»ёгҒӢгӮүе…ЁдҪ“еғҸгӮ’жҸҸгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеҹәжң¬гҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҡйҮҸеҲҶжһҗ
гҒҫгҒҡеӣһзӯ”гӮ’йӣҶиЁҲгҒ—гҒҹеҫҢгҒҜгҖҒжЈ’гӮ°гғ©гғ•гӮ„еҶҶгӮ°гғ©гғ•гҒӘгҒ©гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҖҒгғҮгғјгӮҝгӮ’иҰ–иҰҡеҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒпј•ж®өйҡҺи©•дҫЎгҒ®еӣһзӯ”гғҮгғјгӮҝгӮ’гӮ°гғ©гғ•еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒ®жәҖи¶іеәҰгҒ®еҲҶеёғгӮ„еӮҫеҗ‘гҒҢгҒІгҒЁзӣ®гҒ§еҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жәҖи¶іеәҰгҒӘгҒ©гҒҜгҖҒгҖҢжәҖи¶ігҖҚгҖҢгӮ„гӮ„жәҖи¶ігҖҚгҖҢжҷ®йҖҡгҖҚгҖҢгӮ„гӮ„дёҚжәҖгҖҚгҖҢдёҚжәҖгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҢәеҲҶгҒ”гҒЁгҒ«йӣҶиЁҲгҒ—гҖҒиүІеҲҶгҒ‘гҒ—гҒҰж•ҙзҗҶгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒдјҡе ҙгҒ§гҒ®еҸӮеҠ иҖ…гҒ®ж„ҹи§ҰгӮ’зӣҙж„ҹзҡ„гҒ«гҒӨгҒӢгҒҝгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒгӮҜгғӯгӮ№йӣҶиЁҲгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒиіӘе•Ҹй …зӣ®еҗҢеЈ«гҒ®й–ўйҖЈеҲҶжһҗгӮӮйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒе№ҙд»ЈеҲҘгҒ«жәҖи¶іеәҰгӮ„й–ўеҝғеҲҶйҮҺгӮ’жҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиӢҘжүӢгҒЁгғҷгғҶгғ©гғігҖҒдјҒжҘӯеҸӮеҠ иҖ…гҒӘгҒ©гҖҒеҗ„еұӨгҒ”гҒЁгҒ®зү№еҫҙгӮ„иҰҒжңӣгҒҢжө®гҒӢгҒідёҠгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе·ҘеӨ«гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиӨҮж•°й …зӣ®гҒ®еҲҶжһҗзөҗжһңгӮӮгҖҒжөҒгӮҢгҒ®гҒӮгӮӢиӘ¬жҳҺж–ҮгҒ®гҒҫгҒҫиҮӘ然гҒ«иӘӯгҒҝгӮ„гҒҷгҒҸгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒз®ҮжқЎжӣёгҒҚгҒ®еҲ©зӮ№пјҲиӘӯгҒҝгӮ„гҒҷгҒ•гғ»жғ…е ұж•ҙзҗҶпјүгҒЁгҖҒжөҒгӮҢгӮӢиҮӘ然гҒӘиӘ¬жҳҺж–ҮгҒ®иӘҝе’ҢгӮ’дҝқгҒҰгҒҫгҒҷгҖӮ
еҝ…иҰҒгҒӘгӮүгҖҢгғқгӮӨгғігғҲгҖҚгҖҢдәӢдҫӢгҖҚгҖҢж•ҷиЁ“гҖҚгҒӘгҒ©зӣ®зҡ„еҲҘгҒ«гӮ»гғҹиҰӢеҮәгҒ—гҒ§еҢәеҲҮгӮӢгҒ®гӮӮеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮгҖҢжәҖи¶іеәҰгҒ®й«ҳгҒ„еӣһзӯ”иҖ…гҒ®еұһжҖ§гҖҚгӮ„гҖҢдәӨжөҒж©ҹдјҡгӮ’жұӮгӮҒгӮӢеЈ°гҒҢгҒ©гҒ®е№ҙд»ЈгҒ«еӨҡгҒ„гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҖҒгӮҲгӮҠж·ұгҒ„еӮҫеҗ‘гӮ’жҺўгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ҹйҡӣгҒ®еҲҶжһҗдәӢдҫӢпјҡж—Ҙжң¬ж°—иұЎеӯҰдјҡгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еӯҰдјҡгҒ§гҒҜгҖҒгӮҜгғӯгӮ№йӣҶиЁҲгҒ«гӮҲгӮҠд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӮҫеҗ‘гҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- иӢҘжүӢз ”з©¶иҖ…пјҲ20-30д»ЈпјүпјҡгҖҢдәӨжөҒж©ҹдјҡгҒ®е……е®ҹгҖҚгӮ’йҮҚиҰ–гҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘
- гғҷгғҶгғ©гғіз ”究иҖ…пјҲ50д»Јд»ҘдёҠпјүпјҡгҖҢе°Ӯй–ҖжҖ§гҒ®ж·ұгҒ„и¬ӣжј”гҖҚгӮ’е„Әе…ҲгҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘
- дјҒжҘӯеҸӮеҠ иҖ…пјҡгҖҢе®ҹз”Ёзҡ„гҒӘжғ…е ұжҸҗдҫӣгҖҚгҒ«й«ҳгҒ„й–ўеҝғгӮ’зӨәгҒҷеӮҫеҗ‘
е®ҡжҖ§еҲҶжһҗ
иҮӘз”ұиЁҳиҝ°гҒ®еӣһзӯ”гҒҜгҖҒеҶ…е®№гҒҢеӨҡж§ҳгҒ§и§ЈйҮҲгҒ«гҒ°гӮүгҒӨгҒҚгҒҢеҮәгӮ„гҒҷгҒ„зү№еҫҙгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжңҖиҝ‘гҒ§гҒҜгҖҒгҒқгҒ®ж–Үз« гӮ’гӮігғігғ”гғҘгғјгӮҝгҒ§и§ЈжһҗгҒ—гҖҒгӮҲгҒҸдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢиЁҖи‘үгӮ„й–ўйҖЈгҒ®ж·ұгҒ„иЁҖи‘үгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮ’иҮӘеӢ•зҡ„гҒ«иҰӢгҒӨгҒ‘еҮәгҒҷгҖҺгғҶгӮӯгӮ№гғҲгғһгӮӨгғӢгғігӮ°гҖҸгҒЁгҒ„гҒҶжҠҖиЎ“гҒҢжіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒҢеӨҡгҒҸжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе•ҸйЎҢгҒ®гӮӯгғјгғҜгғјгғүгӮ„гҖҒиӨҮж•°гҒ®ж„ҸиҰӢгҒҢе…ұйҖҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғқгӮӨгғігғҲгӮ’科еӯҰзҡ„гҒ«жҠҪеҮәгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиҶЁеӨ§гҒӘж„ҸиҰӢгҒ®дёӯгҒӢгӮүе…ұйҖҡгҒ®гғҶгғјгғһгӮ„иӘІйЎҢгӮ’еҠ№зҺҮгӮҲгҒҸиҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҖҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе•ҸйЎҢж„ҸиӯҳгҒҢеӨҡгҒҸиӘһгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢгҖҚгҖҢиӨҮж•°гҒ®иҰізӮ№гҒҢгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дәӨе·®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒӢгҖҚгҒҢе®ҡйҮҸжҢҮжЁҷгҒЁгҒ—гҒҰжҠҠжҸЎгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒйӣҶгӮҒгҒҹж„ҸиҰӢгӮ’гҖҢеј·гҒҝгҖҚпјҲStrengthпјүгҖҢејұгҒҝгҖҚпјҲWeaknessпјүгҖҢж©ҹдјҡгҖҚпјҲOpportunityпјүгҖҢжіЁж„ҸгҒҷгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҖҚпјҲThreatпјүгҒ®пј”гҒӨгҒ«еҲҶгҒ‘гӮӢгҖҺSWOTеҲҶжһҗгҖҸгҒЁгҒ„гҒҶж–№жі•гӮ’дҪҝгҒҲгҒ°гҖҒеӯҰдјҡгҒ®зҸҫзҠ¶гӮ’еҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸж•ҙзҗҶгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒд»ҠеҫҢгҒ©гӮ“гҒӘж”№е–„гҒҢеҠ№жһңзҡ„гҒӢгӮ’иҖғгҒҲгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеӯҰдјҡгҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶жіҒгӮ’е®ўиҰізҡ„гҒ«жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒгӮҲгӮҠжҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘж”№е–„зӯ–гӮ’з«ӢгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еҪ№з«ӢгҒҰгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘
гғ»зөұиЁҲеӯҰгҒ®еҹәзӨҺгҒӢгӮүеҝңз”ЁгҒҫгҒ§пјҡгҒӘгӮӢгҒ»гҒ©зөұиЁҲеӯҰең’пҪңз·ҸеӢҷзңҒзөұиЁҲеұҖ
гғ»SWOTеҲҶжһҗгҒЁгҒҜпјҹгғҶгғігғ—гғ¬гғјгғҲгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгҒӢгӮ“гҒҹгӮ“гҒӘгӮ„гӮҠж–№гҖҗе…·дҪ“дҫӢд»ҳгҒҚгҖ‘пҪңferret One
гғ»иӢҘжүӢз ”з©¶иҖ…гӮўгғігӮұгғјгғҲгҒ®еӣһзӯ”йӣҶиЁҲзөҗжһңгҒ®е…¬й–ӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰпҪңж—Ҙжң¬ж°—иұЎеӯҰдјҡ
2.2. зөҗжһңгӮ’йҒӢе–¶ж”№е–„гҒ«жҙ»гҒӢгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®гғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜ
йӣҶиЁҲгҒЁеҲҶжһҗгҒ®жҲҗжһңгӮ’ж”№е–„гҒ«иҗҪгҒЁгҒ—иҫјгӮҖж®өйҡҺгҒ§гҒҜгҖҢе„Әе…Ҳй ҶдҪҚгӮ’гҒ©гҒҶгҒӨгҒ‘гӮӢгҒӢгҖҚгҒҢйҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиҰҒжңӣгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰе®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜйқһзҸҫе®ҹзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҖҢеҸӮеҠ иҖ…гҒ®дёҚжәҖгҒҢйӣҶдёӯгҒ—гҒҹй ҳеҹҹгҖҚгҖҢеӯҰдјҡгҒ®зҗҶеҝөгҒЁзӣҙзөҗгҒҷгӮӢиӘІйЎҢгҖҚгҒӢгӮүеҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢзҸҫе®ҹзҡ„гҒӢгҒӨзҙҚеҫ—ж„ҹгҒ®гҒӮгӮӢж”№е–„зӯ–гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
ж”№е–„дәӢдҫӢпјҡ
дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҖҒгҖҢдәӨжөҒгҒ®ж©ҹдјҡгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеЈ°гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе…·дҪ“зҡ„ж”№е–„зӯ–гҒҢеҠ№жһңзҡ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- гғҶгғјгғһеҲҘгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒ®ж–°иЁӯ
- зҷәиЎЁиҖ…гҒЁгҒ®е°ҸиҰҸжЁЎеҜҫи©ұжһ гҒ®е°Һе…Ҙ
- гӮӘгғігғ©гӮӨгғідәӨжөҒгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒ®ж§ӢзҜү
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж”№е–„гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҸӮеҠ иҖ…жәҖи¶іеәҰгҒ®еҗ‘дёҠгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒж”№е–„гҒ®йҒҺзЁӢгӮ„иЁҲз”»гӮ’е ұе‘ҠжӣёгӮ„WebгӮөгӮӨгғҲгҒ§еәғгҒҸзӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҜйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеҸӮеҠ иҖ…гҒ«гҖҢеЈ°гӮ’еҸ—гҒ‘жӯўгӮҒгҖҒж”№е–„гҒҢйҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁдјқгӮҸгӮӢгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҒҢгҖҒеӯҰдјҡгҒёгҒ®дҝЎй јгӮ’йҶёжҲҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгҒҜеҸӮеҠ иҖ…гӮ„зӨҫдјҡгҒЁгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ§гҒҷгҖӮ
3. гӮўгғігӮұгғјгғҲзөҗжһңгӮ’жңҖеӨ§йҷҗгҒ«жҙ»гҒӢгҒҷиҰ–зӮ№гҒЁе·ҘеӨ«
гӮўгғігӮұгғјгғҲгҒҜйҒҺеҺ»гҒ®е•ҸйЎҢгӮ’жӢҫгҒҶгғ„гғјгғ«гҒЁгҒ„гҒҶгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжңӘжқҘгӮ’гҒӨгҒҸгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иЁӯиЁҲиіҮж–ҷгҒЁгҒӘгӮҠеҫ—гҒҫгҒҷгҖӮиіӘе•ҸгҒ®з«ӢгҒҰж–№гӮ„ж—ўеӯҳгғҮгғјгӮҝгҒЁгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣж–№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒжҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘйҒӢе–¶гӮ’гғҗгғғгӮҜгӮўгғғгғ—гҒҷгӮӢеј·еҠӣгҒӘиіҮжәҗгҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
3.1. е•ҸйЎҢи§ЈжұәгҒ«з•ҷгҒҫгӮүгҒӘгҒ„жңӘжқҘеҝ—еҗ‘гҒ®иЁӯе•ҸиЁӯе®ҡ
иЁӯе•ҸгӮ’гҖҢзҸҫзҠ¶и©•дҫЎгҖҚгҒ«йҷҗе®ҡгҒӣгҒҡгҖҒгҖҢе°ҶжқҘеғҸгӮ’е•ҸгҒҶеҪўгҖҚгҒ«гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒҜи©•дҫЎиҖ…гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸе…ұеүөиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
жңӘжқҘеҝ—еҗ‘гҒ®иЁӯе•ҸдҫӢпјҡ
- гҖҢж¬ЎеӣһеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒ»гҒ—гҒ„з ”з©¶гғҶгғјгғһгҒҜдҪ•гҒ§гҒҷгҒӢпјҹгҖҚ
- гҖҢд»ҠеҫҢеј·еҢ–гҒҷгҒ№гҒҚж–Ҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰжңҹеҫ…гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜпјҹгҖҚ
- гҖҢ5е№ҙеҫҢгҒ®еӯҰдјҡгҒ«жңҹеҫ…гҒҷгӮӢе§ҝгӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖҚ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжңӘжқҘеҝ—еҗ‘гҒ®иЁӯе•ҸгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҫ“жқҘгҒ®иЁәж–ӯжҠҖиЎ“гҒӢгӮүжңҖж–°гҒ®AIжҠҖиЎ“гҒҫгҒ§гҖҒе№…еәғгҒ„иҰҒжңӣгӮ’еҸҺйӣҶгҒ—гҖҒж¬Ўе№ҙеәҰдјҒз”»гҒ®еҸӮиҖғгҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҸҢж–№еҗ‘жҖ§гҒҢеј·иӘҝгҒ•гӮҢгҖҒеӯҰдјҡгҒҢеҚҳгҒӘгӮӢжҸҗдҫӣиҖ…гҒӢгӮүгҖҢе…ұгҒ«гҒӨгҒҸгӮӢе ҙгҖҚгҒёгҒЁйҖІеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
3.2. ж—ўеӯҳгғҮгғјгӮҝгҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰиҰӢгҒҲгҒҰгҒҸгӮӢж–°гҒҹгҒӘдҫЎеҖӨ
гӮўгғігӮұгғјгғҲеҚҳзӢ¬гҒ®еҲҶжһҗгҒ«еҠ гҒҲгҖҒеҸӮеҠ иҖ…еұһжҖ§гғҮгғјгӮҝгӮ„йҒҺеҺ»гҒ®е®ҹзёҫгҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮеӯҰдјҡгҒ®гҖҢж§ӢйҖ зҡ„зү№жҖ§гҖҚгҒҢжө®гҒӢгҒідёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҮгғјгӮҝзөұеҗҲеҲҶжһҗгҒ®жүӢжі•пјҡ
еӨҡгҒҸгҒ®еӯҰдјҡгҒ§гҒҜгҖҒй•·жңҹй–“гҒ®гғҮгғјгӮҝеҲҶжһҗгҒ«гӮҲгӮҠд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӮҫеҗ‘гҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- иӢҘжүӢз ”з©¶иҖ…пјҡгҖҢдәәи„ҲеҪўжҲҗгҖҚгҒёгҒ®й–ўеҝғгҒҢе№ҙгҖ…еў—еҠ гҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘
- гғҷгғҶгғ©гғіз ”究иҖ…пјҡгҖҢжңҖж–°жҠҖиЎ“еӢ•еҗ‘гҖҚгҒёгҒ®й–ўеҝғгҒҢдёҠжҳҮгҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘
гҒ“гҒ®еӨүеҢ–гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒдё–д»ЈжЁӘж–ӯеһӢгҒ®гғЎгғігӮҝгғӘгғігӮ°гӮ»гғғгӮ·гғ§гғіпјҲе…Ҳиј©з ”з©¶иҖ…гҒ«гӮҲгӮӢиӢҘжүӢеҗ‘гҒ‘гҒ®жҢҮе°Һгғ»зӣёи«ҮдјҡпјүгӮ’ж–°иЁӯгҒҷгӮӢеӯҰдјҡгҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«йҒҺеҺ»гҒ®зөҗжһңгҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҢж”№е–„зӮ№гҒҢгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘еҸҚжҳ гҒ•гӮҢгҒҹгҒӢгҖҚгӮ’и©•дҫЎгҒ§гҒҚгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜеҚҳгҒӘгӮӢйҒӢе–¶ж”№е–„гӮ’и¶…гҒҲгҒҰгҖҢеҠӘеҠӣгҒ®еҸҜиҰ–еҢ–гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮж©ҹиғҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҸӮеҠ иҖ…гҒҜзө„з№”гҒҢз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«йҖІеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж§ҳеӯҗгӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҖҒдҝЎй јеҹәзӣӨгҒ®еј·еҢ–гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®дёҖйҖЈгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒгҒ„гӮҸгҒ°гҖҢPDCAгӮөгӮӨгӮҜгғ«гҖҚгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгӮўгғігӮұгғјгғҲгҒ§иӘІйЎҢпјҲPlanпјүгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҖҒж”№е–„зӯ–гӮ’е®ҹиЎҢпјҲDoпјүгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҠ№жһңгӮ’и©•дҫЎпјҲCheckпјүгҒ—гҖҒж¬ЎгҒ®йҒӢе–¶иЁҲз”»гҒёгҒЁеҸҚжҳ пјҲActionпјүгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҸгҖӮгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮҜгғ«гӮ’з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«еӣһгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮўгғігӮұгғјгғҲгҒҜдёҖжҷӮзҡ„гҒӘиӘҝжҹ»гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжҒ’еёёзҡ„гҒӘзө„з№”ж”№е–„гҒ®гӮЁгғігӮёгғігҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—е§ӢгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒгҖҖеҸӮеҠ иҖ…гҒ®еЈ°гӮ’е°ҶжқҘгҒ®еӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«зөҗгҒігҒӨгҒ‘гӮӢж–№жі•
гӮўгғігӮұгғјгғҲгҒҜгҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒЁйҒӢе–¶еҒҙгҒЁгҒ®еҜҫи©ұгҒ®еҮәзҷәзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®дёӯгҒ«гҒҜеӯҰдјҡгҒҢй–ӢгҒӢгӮҢгҒҹе ҙгҒЁгҒ—гҒҰзҷәеұ•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒҹгӮҒгҒ®гғ’гғігғҲгҒҢеҮқзё®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиЁӯе•ҸиЁӯиЁҲгӮ„гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гӮ’е·ҘеӨ«гҒ—гҖҒзөҗжһңгӮ’зңҹж‘ҜгҒ«еҸ—гҒ‘жӯўгӮҒж”№е–„гҒёгҒЁйӮ„е…ғгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеЈ°гҒҜеҚҳгҒӘгӮӢж„ҹжғігӮ„жү№еҲӨгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҢжңӘжқҘгӮ’гҒЁгӮӮгҒ«гҒӨгҒҸгӮӢзҹҘгҖҚгҒёгҒЁи»ўжҸӣгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
жҲҗеҠҹгҒҷгӮӢеӯҰдјҡгӮўгғігӮұгғјгғҲгҒ®иҰҒзҙ пјҡ
- жҲҰз•Ҙзҡ„иЁӯе•ҸиЁӯиЁҲпјҡеӣһзӯ”гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒ§гҖҒжңӘжқҘеҝ—еҗ‘
- йҒ©еҲҮгҒӘе®ҹж–ҪгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°пјҡиЁҳжҶ¶гҒ®й®®жҳҺжҖ§гҒЁеҶ·йқҷгҒӘеҲӨж–ӯгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№
- дҪ“зі»зҡ„еҲҶжһҗпјҡе®ҡйҮҸгғ»е®ҡжҖ§дёЎйқўгҒӢгӮүгҒ®еӨҡи§’зҡ„и©•дҫЎ
- зўәе®ҹгҒӘж”№е–„е®ҹиЎҢпјҡе„Әе…Ҳй ҶдҪҚгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒ—гҒҹе…·дҪ“зҡ„ж”№е–„зӯ–
- йҖҸжҳҺжҖ§гҒ®й«ҳгҒ„гғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜпјҡж”№е–„йҒҺзЁӢгҒ®еҸҜиҰ–еҢ–гҒЁе…ұжңү
ж°‘з„ЎдҝЎдёҚз«Ӣ
и«–иӘһгҒ«гҒӮгӮӢгҖҺж°‘гҖҒдҝЎз„ЎгҒҸгӮ“гҒ°з«ӢгҒҹгҒҡгҖҸгҒҢзӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒдҝЎй јгҒ“гҒқгҒҢеӯҰдјҡгҒ®ж №е№№гҒ§гҒҷгҖӮеҸӮеҠ иҖ…гҒ®еЈ°гӮ’жӯЈйқўгҒӢгӮүеҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҖҒж”№е–„гҒёгҒЁжҙ»гҒӢгҒҷе§ҝеӢўгҒҜгҖҒеӯҰдјҡгӮ’жҢҒз¶ҡзҡ„гҒ«зҷәеұ•гҒ•гҒӣгӮӢеҺҹеӢ•еҠӣгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҖҢеЈ°гӮ’гҒ©гҒҶжҙ»гҒӢгҒ—гҒҹгҒӢгҖҚгӮ’иҰӢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—е…ұжңүгҒҷгӮӢе§ҝеӢўгӮ’еӨ§еҲҮгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ“гҒқгҖҒж¬ЎгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ®иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ