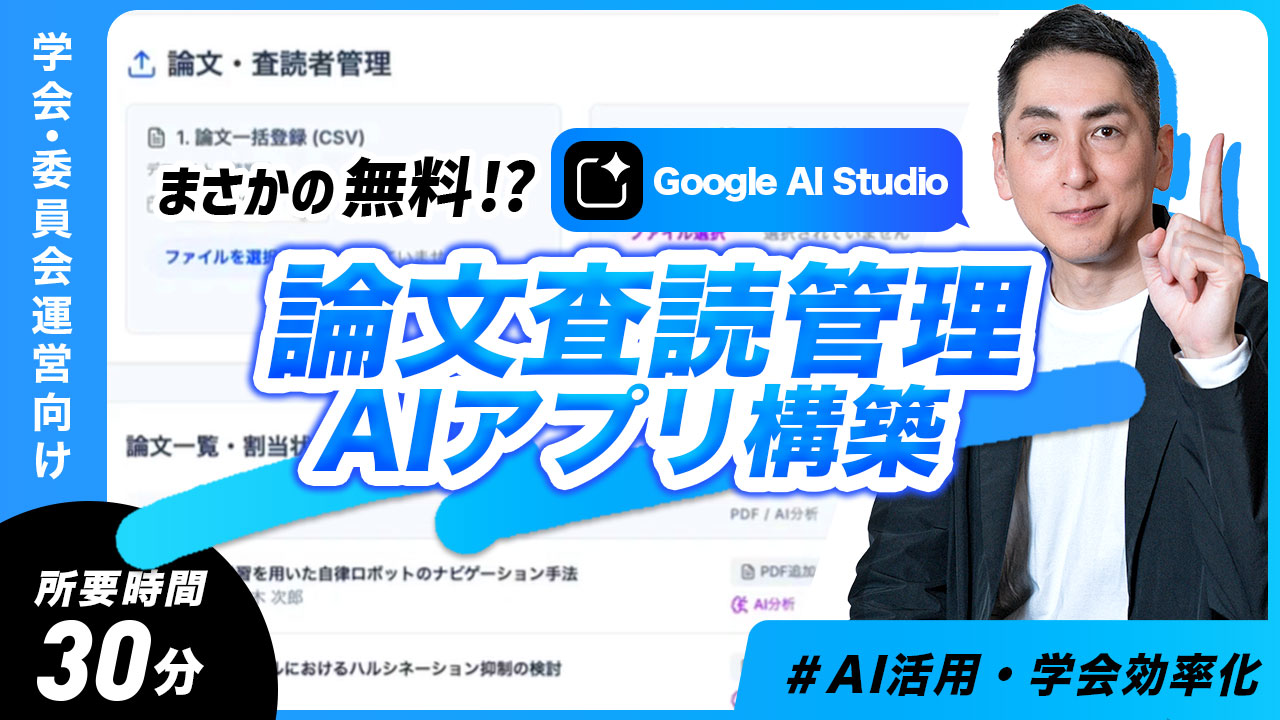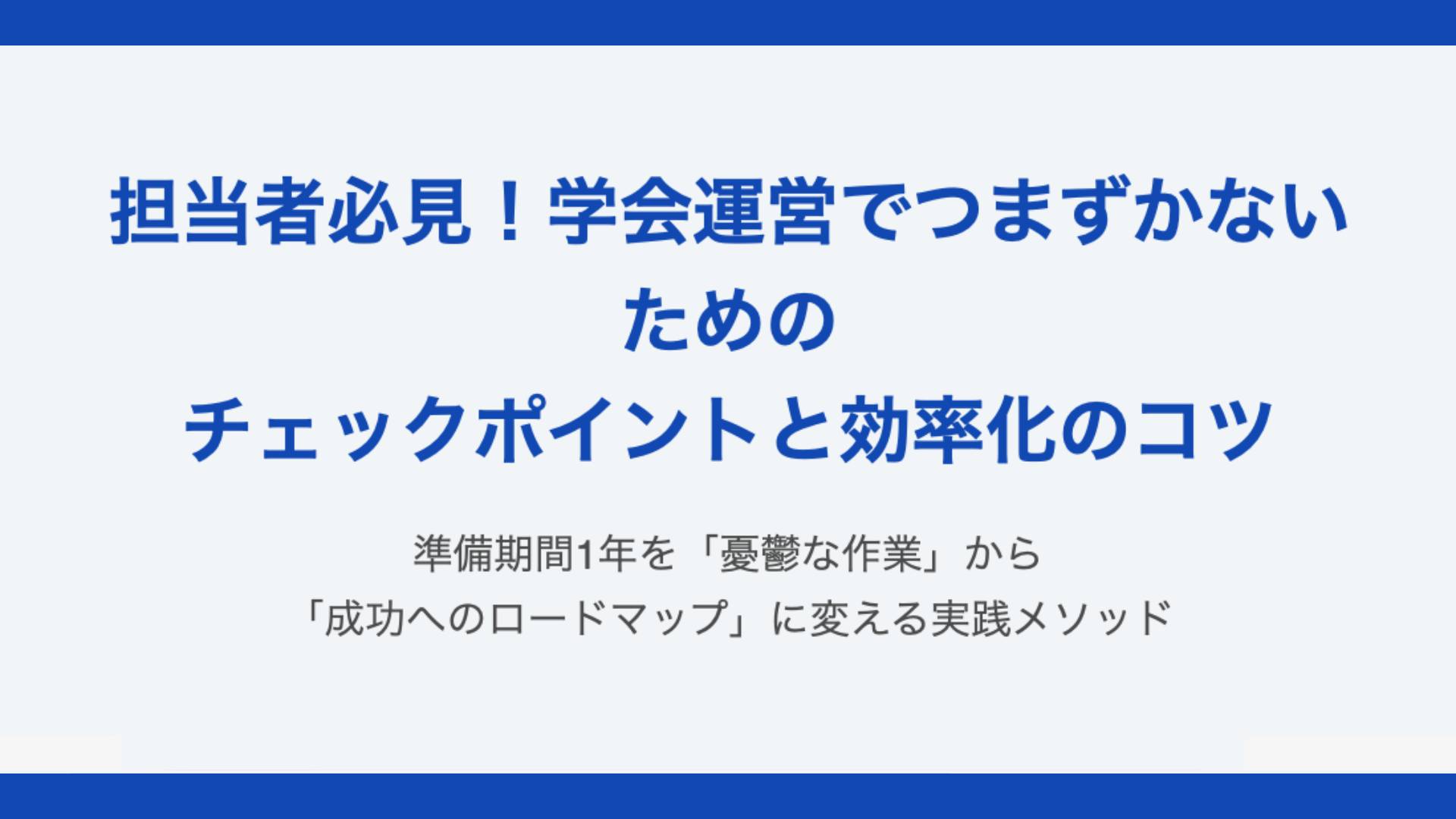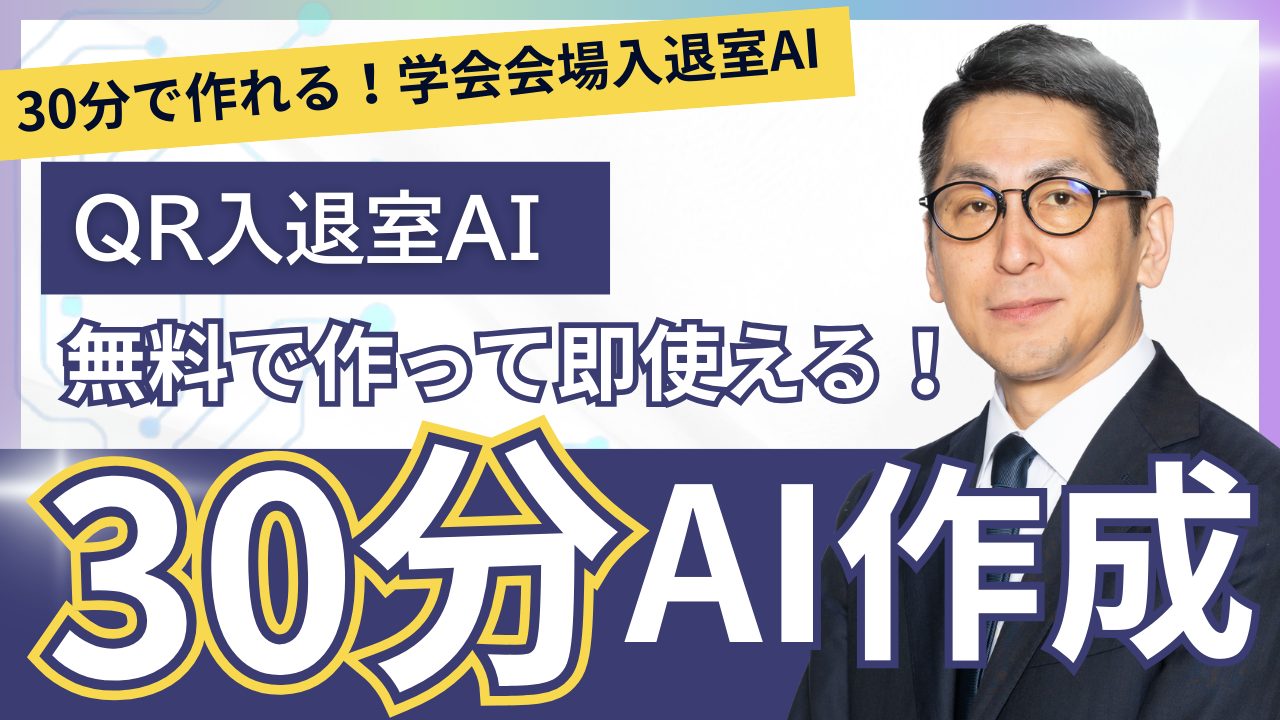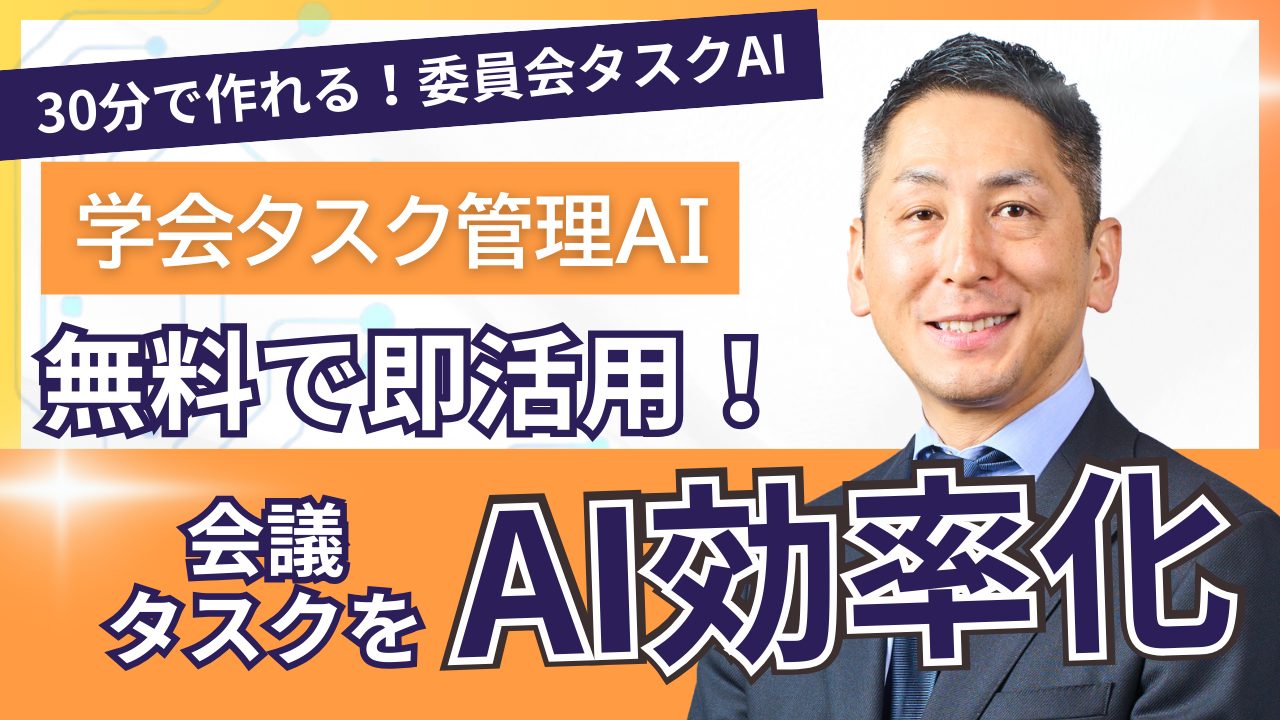гӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҒ®гҒҷгҒ№гҒҰпјҡй–ӢеӮ¬гҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒӢгӮүжҲҗеҠҹгҒ®з§ҳиЁЈгҒҫгҒ§еҫ№еә•и§ЈиӘ¬
2025е№ҙ06жңҲ30ж—Ҙ

иҝ‘е№ҙгҖҒеӯҰиЎ“зҷәиЎЁгӮ„з ”з©¶дәӨжөҒгҒ®е ҙгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒҢжҖҘйҖҹгҒ«жҷ®еҸҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҘ‘ж©ҹгҒ«гҖҒзү©зҗҶзҡ„гҒӘеҲ¶зҙ„гӮ’и¶…гҒҲгҒҰз ”з©¶жҲҗжһңгӮ’е…ұжңүгҒ—гҖҒж„ҸиҰӢдәӨжҸӣгӮ’иЎҢгҒҶж–°гҒ—гҒ„еҪўејҸгҒЁгҒ—гҒҰе®ҡзқҖгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮйҢІз”»гҒ«гӮҲгӮӢгӮӘгғігғҮгғһгғігғүй…ҚдҝЎгӮ„гҖҒзҸҫең°й–ӢеӮ¬гҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүеҪўејҸгҒӘгҒ©гҖҒгҒқгҒ®йҖІеҢ–гҒҜгҒЁгҒ©гҒҫгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮ’зҹҘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жң¬иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘжҰӮеҝөгҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгғ»гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҖҒй–ӢеӮ¬жҷӮгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘжөҒгӮҢгӮ„жә–еӮҷгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҒҜгӮ№гғ гғјгӮәгҒӘйҒӢе–¶гӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж”ҜжҸҙгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҫгҒ§гҖҒз¶Ізҫ…зҡ„гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒ®й–ӢеӮ¬гӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҖҒйҒӢе–¶гҒ«жҗәгӮҸгӮӢж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒе®ҹи·өзҡ„гҒӘжғ…е ұгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҒЁгҒҜпјҹгҒқгҒ®еӨҡж§ҳгҒӘеҪўејҸ
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰй–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгӮӢеӯҰиЎ“еӨ§дјҡгҖҒз ”з©¶дјҡгҖҒи¬ӣжј”дјҡгҒӘгҒ©гӮ’жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮZoomгӮ„WebexгҒӘгҒ©гҒ®гғ“гғҮгӮӘдјҡиӯ°гғ„гғјгғ«гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜе°Ӯз”ЁгҒ®гӮӨгғҷгғігғҲгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒҢжҙ»з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҒЁгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүеӯҰдјҡгҒ®йҒ•гҒ„
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒҜгҖҒеҸӮеҠ иҖ…е…Ёе“ЎгҒҢгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҸӮеҠ гҒҷгӮӢеҪўејҸгҒ§гҒҷгҖӮзҷәиЎЁгӮӮиіӘз–‘еҝңзӯ”гӮӮе…ЁгҒҰгӮӘгғігғ©гӮӨгғідёҠгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒгҖҢгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүеӯҰдјҡгҖҚгҒҜгҖҒзҸҫең°гҒ§гҒ®еҜҫйқўеҸӮеҠ гҒЁгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеҸӮеҠ гӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹеҪўејҸгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдёҖйғЁгҒ®гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒҜдјҡе ҙгҒ§иЎҢгҒ„гҖҒгҒқгҒ®ж§ҳеӯҗгӮ’гӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§гғ©гӮӨгғ–й…ҚдҝЎгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒзҷәиЎЁиҖ…гҒҢзҸҫең°гҒЁгӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰеҸӮеҠ гҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүеҪўејҸгҒҜгҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒҢиҮӘиә«гҒ®зҠ¶жіҒгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰеҸӮеҠ ж–№жі•гӮ’йҒёгҒ№гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮҲгӮҠеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҖ…гҒ«еҸӮеҠ гҒ®ж©ҹдјҡгӮ’жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҲ©зӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдјҡе ҙгҒ®гӮӯгғЈгғ‘гӮ·гғҶгӮЈгҒ«еҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҡгҒ«еҸӮеҠ иҖ…ж•°гӮ’еў—гӮ„гҒӣгӮӢзӮ№гӮӮеӨ§гҒҚгҒӘйӯ…еҠӣгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҒ®еҲ©зӮ№гҒЁиҖғж…®зӮ№
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚеҪўејҸгҒ®е°Һе…ҘгҒ«гҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒиҖғж…®гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгӮ’дәӢеүҚгҒ«жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠеҠ№жһңзҡ„гҒӘйҒӢе–¶иЁҲз”»гӮ’з«ӢгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҒҢгӮӮгҒҹгӮүгҒҷгғЎгғӘгғғгғҲ
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒ®жңҖеӨ§гҒ®еҲ©зӮ№гҒҜгҖҒе ҙжүҖгӮ„жҷӮй–“гҒ®еҲ¶зҙ„гӮ’и¶…гҒҲгҒҰеӨҡгҒҸгҒ®з ”究иҖ…гӮ„еӯҰз”ҹгҒҢеҸӮеҠ гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮйҒ йҡ”ең°гҒ«гҒ„гӮӢгҒҹгӮҒзҸҫең°еҸӮеҠ гҒҢйӣЈгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒж—ҘзЁӢгҒ®йғҪеҗҲгҒҢгҒӨгҒ‘гҒ«гҒҸгҒӢгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҹдәәгҖ…гӮӮгҖҒиҮӘе®…гӮ„иҒ·е ҙгҒӢгӮүжүӢи»ҪгҒ«еҸӮеҠ гҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҸӮеҠ иҖ…еұӨгҒ®жӢЎеӨ§гҒЁеӯҰиЎ“дәӨжөҒгҒ®жҙ»жҖ§еҢ–гҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒйҒӢе–¶еҒҙгҒ®иҰ–зӮ№гҒ§гҒҜгҖҒдјҡе ҙгҒ®гғ¬гғігӮҝгғ«иІ»з”ЁгӮ„иЁӯе–¶иІ»з”ЁгҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒ®з§»еӢ•гғ»е®ҝжіҠиІ»гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮігӮ№гғҲгӮ’еӨ§е№…гҒ«еүҠжёӣгҒ§гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«еӨ§иҰҸжЁЎгҒӘдјҡе ҙгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдәҲз®—гҒ®еҠ№зҺҮзҡ„гҒӘжҙ»з”ЁгҒ«з№ӢгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒйҢІз”»гҒ«гӮҲгӮӢгӮӘгғігғҮгғһгғігғүй…ҚдҝЎгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ§еҸӮеҠ гҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹдәәгӮӮеҫҢгҒӢгӮүеҶ…е®№гӮ’иҰ–иҒҙгҒ§гҒҚгҖҒзҷәиЎЁеҶ…е®№гҒ®жөёйҖҸеәҰгҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒз ”з©¶жҲҗжһңгҒ®жӢЎж•ЈеҠ№жһңгӮӮй«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҒ®иҖғж…®гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒ®гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҜҫйқўгҒ§гҒ®дәӨжөҒж©ҹдјҡгҒ®жёӣе°‘гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдј‘жҶ©жҷӮй–“гӮ„жҮҮиҰӘдјҡгҒ§гҒ®еҒ¶зҷәзҡ„гҒӘеҮәдјҡгҒ„гӮ„йқһе…¬ејҸгҒӘиӯ°и«–гҒҜгҖҒеӯҰиЎ“дәӨжөҒгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйҮҚиҰҒгҒӘеҒҙйқўгҒ§гҒҷгҖӮгӮӘгғігғ©гӮӨгғіз’°еўғгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹиҮӘ然гҒӘгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒ«гҒҸгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒеҲҘйҖ”гӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§гҒ®дәӨжөҒж©ҹдјҡгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҹгӮҠгҖҒе·ҘеӨ«гӮ’еҮқгӮүгҒ—гҒҹгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ иЁӯиЁҲгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒйҖҡдҝЎз’°еўғгӮ„ж©ҹеҷЁгҒ®гғҲгғ©гғ–гғ«гӮӮиҖғж…®гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮеҸӮеҠ иҖ…еҒҙгҒ®гӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲжҺҘз¶ҡдёҚиүҜгӮ„ж©ҹеҷЁгҒ®дёҚиӘҝгҒҢеҺҹеӣ гҒ§гҖҒзҷәиЎЁгӮ„иҰ–иҒҙгҒ«ж”ҜйҡңгҒҢеҮәгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҒӢе–¶еҒҙгӮӮгҖҒе®үе®ҡгҒ—гҒҹй…ҚдҝЎз’°еўғгҒ®зўәдҝқгӮ„гҖҒгғҲгғ©гғ–гғ«зҷәз”ҹжҷӮгҒ®иҝ…йҖҹгҒӘгӮөгғқгғјгғҲдҪ“еҲ¶гҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮжҠҖиЎ“зҡ„гҒӘжә–еӮҷгҒЁгғӘгғҸгғјгӮөгғ«гҒ«гҒҜеҚҒеҲҶгҒӘжҷӮй–“гӮ’еүІгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒзҷәиЎЁиҖ…гҒҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§гҒ®зҷәиЎЁгҒ«дёҚж…ЈгӮҢгҒӘе ҙеҗҲгҖҒгғ—гғ¬гӮјгғігғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒ®иіӘгҒ«еҪұйҹҝгҒҢеҮәгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзҷәиЎЁиҖ…еҗ‘гҒ‘гҒ®дәӢеүҚгҒ®гӮ¬гӮӨгғҖгғігӮ№гӮ„з·ҙзҝ’ж©ҹдјҡгҒ®жҸҗдҫӣгӮӮйҮҚиҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡй–ӢеӮ¬гҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘжөҒгӮҢгҒЁжә–еӮҷ
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгӮ’жҲҗеҠҹгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒдәӢеүҚгҒ®з¶ҝеҜҶгҒӘжә–еӮҷгҒЁгҖҒй–ӢеӮ¬дёӯгҒ®гӮ№гғ гғјгӮәгҒӘйҒӢз”ЁгҖҒгҒқгҒ—гҒҰй–ӢеӮ¬еҫҢгҒ®дёҒеҜ§гҒӘгғ•гӮ©гғӯгғјгӮўгғғгғ—гҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
й–ӢеӮ¬еүҚгҒ®жә–еӮҷгғ•гӮ§гғјгӮә:
й–ӢеӮ¬еүҚгҒ®жә–еӮҷгҒҜгҖҒгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҒ®жҲҗеҗҰгӮ’еҲҶгҒ‘гӮӢжңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘж®өйҡҺгҒ§гҒҷгҖӮ
й–ӢеӮ¬еҪўејҸгҒ®жұәе®ҡгҒЁгӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«зӯ–е®ҡ:
е®Ңе…ЁгҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒӢгҖҒгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүеҪўејҸгҒӢгҖҒгӮӘгғігғҮгғһгғігғүй…ҚдҝЎгӮӮиЎҢгҒҶгҒӢгҒӘгҒ©гҖҒй–ӢеӮ¬еҪўејҸгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹи©ізҙ°гҒӘгӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ йҒёе®ҡ:
ZoomгҖҒWebexгҖҒMicrosoft TeamsгҒӘгҒ©гҒ®жұҺз”Ёгғ„гғјгғ«гҒӢгҖҒгӮӨгғҷгғігғҲгҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҹе°Ӯз”Ёгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒӢгҖҒеӯҰдјҡгҒ®иҰҸжЁЎгӮ„зӣ®зҡ„гҒ«еҝңгҒҳгҒҰжңҖйҒ©гҒӘгғ„гғјгғ«гӮ’йҒёе®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жј”йЎҢеӢҹйӣҶгғ»еҸӮеҠ зҷ»йҢІ:
гӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§гҒ®жј”йЎҢзҷ»йҢІгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҖҒеӢҹйӣҶгӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒеҸӮеҠ зҷ»йҢІгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮӮз”Ёж„ҸгҒ—гҖҒеҸӮеҠ иІ»гҒ®жұәжёҲж–№жі•пјҲгӮҜгғ¬гӮёгғғгғҲгӮ«гғјгғүгҖҒйҠҖиЎҢжҢҜиҫјгҒӘгҒ©пјүгӮ’иЁӯе®ҡгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
WebгӮөгӮӨгғҲгҒ®й–ӢиЁӯгҒЁеәғе ұ:
еӯҰдјҡгҒ®е…¬ејҸWebгӮөгӮӨгғҲгӮ’й–ӢиЁӯгҒ—гҖҒй–ӢеӮ¬жҰӮиҰҒгҖҒгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒеҸӮеҠ гғ»зҷәиЎЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжғ…е ұгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ еҲ©з”ЁгғһгғӢгғҘгӮўгғ«гҒӘгҒ©гӮ’жҺІијүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮSNSгӮ„гғЎгғјгғ«гғһгӮ¬гӮёгғігӮ’йҖҡгҒҳгҒҹеәғе ұжҙ»еӢ•гӮӮз©ҚжҘөзҡ„гҒ«иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зҷәиЎЁиҖ…гғ»еә§й•·гҒёгҒ®гӮ¬гӮӨгғҖгғігӮ№:
зҷәиЎЁж–№жі•гӮ„дҪҝз”Ёгғ„гғјгғ«гҒ«й–ўгҒҷгӮӢи©ізҙ°гҒӘгғһгғӢгғҘгӮўгғ«гӮ’дәӢеүҚгҒ«й…ҚеёғгҒ—гҖҒеҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгғӘгғҸгғјгӮөгғ«гӮ„еҖӢеҲҘзӣёи«ҮгҒ®ж©ҹдјҡгӮ’иЁӯгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§гҒ®зҷәиЎЁгҒ«дёҚж…ЈгӮҢгҒӘж–№гҒёгҒ®жүӢеҺҡгҒ„гӮөгғқгғјгғҲгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
жҠҖиЎ“гғҶгӮ№гғҲгҒЁгғӘгғҸгғјгӮөгғ«:
е®ҹйҡӣгҒ«дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢж©ҹжқҗгӮ„гғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒйҹіеЈ°гҖҒжҳ еғҸгҖҒз”»йқўе…ұжңүгҒӘгҒ©гҒҢе•ҸйЎҢгҒӘгҒҸж©ҹиғҪгҒҷгӮӢгҒӢгӮ’еҫ№еә•зҡ„гҒ«гғҶгӮ№гғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзҷәиЎЁиҖ…гӮ„еә§й•·гҒЁгҒ®жҺҘз¶ҡгғҶгӮ№гғҲгӮӮе…ҘеҝөгҒ«иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҒӢе–¶гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒ®й…ҚзҪ®гҒЁеҪ№еүІеҲҶжӢ…:
еҸёдјҡгҖҒгӮҝгӮӨгғ гӮӯгғјгғ‘гғјгҖҒгғҒгғЈгғғгғҲгғўгғҮгғ¬гғјгӮҝгғјгҖҒжҠҖиЎ“гӮөгғқгғјгғҲгҖҒгғҲгғ©гғ–гғ«еҜҫеҝңгҒӘгҒ©гҖҒгӮӘгғігғ©гӮӨгғізү№жңүгҒ®еҪ№еүІгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒ—гҖҒжӢ…еҪ“иҖ…гӮ’й…ҚзҪ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ӢеӮ¬дёӯгҒ®йҒӢе–¶гғ•гӮ§гғјгӮә
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒ®й–ӢеӮ¬дёӯгҒҜгҖҒгғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ§гҒ®еҶҶж»‘гҒӘйҖІиЎҢгҒЁгҖҒгғҲгғ©гғ–гғ«гҒёгҒ®иҝ…йҖҹгҒӘеҜҫеҝңгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
йҖІиЎҢз®ЎзҗҶ:
дәӢеүҚгҒ«дҪңжҲҗгҒ—гҒҹгӮ·гғҠгғӘгӮӘгҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒеҸёдјҡиҖ…гҒҢгӮ»гғғгӮ·гғ§гғігӮ’еҶҶж»‘гҒ«йҖІиЎҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮҝгӮӨгғ гӮӯгғјгғ‘гғјгҒҜжҷӮй–“з®ЎзҗҶгӮ’еҫ№еә•гҒ—гҖҒгӮ»гғғгӮ·гғ§гғій–“гҒ®гӮ№гғ гғјгӮәгҒӘ移иЎҢгӮ’дҝғгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жҠҖиЎ“гӮөгғқгғјгғҲ:
еҸӮеҠ иҖ…гӮ„зҷәиЎЁиҖ…гҒӢгӮүгҒ®жҺҘз¶ҡгғҲгғ©гғ–гғ«гҖҒйҹіеЈ°гғ»жҳ еғҸгҒ®е•ҸйЎҢгҒӘгҒ©гҖҒжҠҖиЎ“зҡ„гҒӘе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒ«иҝ…йҖҹгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢзӘ“еҸЈгӮ’иЁӯзҪ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иіӘз–‘еҝңзӯ”гғ»гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®жҙ»жҖ§еҢ–:
гғҒгғЈгғғгғҲж©ҹиғҪгӮ„Q&Aгғ•гӮ©гғјгғ гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒӢгӮүгҒ®иіӘе•ҸгӮ’еҠ№зҺҮзҡ„гҒ«еҸ—гҒ‘д»ҳгҒ‘гҖҒзҷәиЎЁиҖ…гӮ„еә§й•·гҒ«дјқгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гҒ®гӮўгғігӮұгғјгғҲж©ҹиғҪгҒӘгҒ©гӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒеҸҢж–№еҗ‘жҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢе·ҘеӨ«гӮӮжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮ
гғҲгғ©гғ–гғ«еҜҫеҝң:
дёҮгҒҢдёҖгҒ®гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜйҡңе®ігӮ„гӮ·гӮ№гғҶгғ дёҚиӘҝгҒ«еӮҷгҒҲгҖҒдәҲеӮҷгҒ®еӣһз·ҡгӮ„д»ЈжӣҝжүӢж®өгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒӘгҒ©гҖҒз·ҠжҖҘжҷӮгҒ®еҜҫеҝңиЁҲз”»гӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
й–ӢеӮ¬еҫҢгҒ®гғ•гӮ©гғӯгғјгӮўгғғгғ—гғ•гӮ§гғјгӮә
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚзөӮдәҶеҫҢгӮӮгҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒӢгӮүгҒ®гғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜеҸҺйӣҶгӮ„гӮӘгғігғҮгғһгғігғүй…ҚдҝЎгҒ®жә–еӮҷгҒӘгҒ©гҖҒйҮҚиҰҒгҒӘгӮҝгӮ№гӮҜгҒҢз¶ҡгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҜҫеҝңгҒҢгҖҒж¬Ўеӣһд»ҘйҷҚгҒ®гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒ®ж”№е–„гҒ«зӣҙзөҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮўгғігӮұгғјгғҲе®ҹж–ҪгҒЁеҲҶжһҗ:
еҸӮеҠ иҖ…гӮўгғігӮұгғјгғҲгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҖҒйҒӢе–¶гҒ®иүҜгҒӢгҒЈгҒҹзӮ№гӮ„ж”№е–„гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гӮ’и©ізҙ°гҒ«еҲҶжһҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӘгғігғҮгғһгғігғүй…ҚдҝЎ:
йҢІз”»гҒ•гӮҢгҒҹгӮ»гғғгӮ·гғ§гғіеӢ•з”»гӮ’ж•ҙзҗҶгғ»з·ЁйӣҶгҒ—гҖҒй…ҚдҝЎгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒёгӮўгғғгғ—гғӯгғјгғүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғҮгғјгӮҝж•ҙзҗҶгҒЁе ұе‘Ҡ:
еҸӮеҠ иҖ…гғҮгғјгӮҝгҖҒжұәжёҲжғ…е ұгҖҒгӮўгғігӮұгғјгғҲзөҗжһңгҒӘгҒ©гӮ’ж•ҙзҗҶгҒ—гҖҒй–ӢеӮ¬е ұе‘ҠжӣёгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўдҝӮиҖ…гҒёгҒ®еҫЎзӨј:
зҷәиЎЁиҖ…гҖҒеә§й•·гҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҖҒгӮ№гғқгғігӮөгғјгҒӘгҒ©гҖҒй–ўдҝӮиҖ…гҒёгҒ®еҫЎзӨјйҖЈзөЎгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ№гғ гғјгӮәгҒӘгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғ’гғігғҲ
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгӮ’гӮҲгӮҠгӮ№гғ гғјгӮәгҒ«йҒӢе–¶гҒ—гҖҒеҸӮеҠ иҖ…жәҖи¶іеәҰгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®иҝҪеҠ зҡ„гҒӘе·ҘеӨ«гҒҢеҪ№з«ӢгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
е°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгғ»зөҢйЁ“гҒ®жҙ»з”Ё:
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒ®йҒӢе–¶гҒ«гҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®зҸҫең°й–ӢеӮ¬гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘзҹҘиӯҳгӮ„жҠҖиЎ“гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«еӨ§иҰҸжЁЎгҒӘеӯҰдјҡгӮ„гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬гҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгӮӘгғігғ©гӮӨгғігӮӨгғҷгғігғҲгҒ®йҒӢе–¶гӮ’е°Ӯй–ҖгҒЁгҒҷгӮӢеӨ–йғЁжҘӯиҖ…гҒ«еҚ”еҠӣгӮ’дҫқй јгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдё»еӮ¬иҖ…еҒҙгҒ®иІ жӢ…гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸи»ҪжёӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгғ—гғӯгҒ®гғҺгӮҰгғҸгӮҰгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиіӘгҒ®й«ҳгҒ„й…ҚдҝЎгӮ„гғҲгғ©гғ–гғ«еҜҫеҝңгҒҢе®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®е·ҘеӨ«:
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒ§гҒҜгҖҒеҸӮеҠ иҖ…й–“гҒ®еҒ¶зҷәзҡ„гҒӘдәӨжөҒгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒ«гҒҸгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶиӘІйЎҢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮZoomгҒ®гғ–гғ¬гӮӨгӮҜгӮўгӮҰгғҲгғ«гғјгғ ж©ҹиғҪгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгӮ°гғ«гғјгғ—гғҮгӮЈгӮ№гӮ«гғғгӮ·гғ§гғігҖҒе°Ӯз”ЁгҒ®дәӨжөҒгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ®иЁӯзҪ®гҖҒзҷәиЎЁгӮ№гғ©гӮӨгғүгҒёгҒ®гғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ гӮігғЎгғігғҲж©ҹиғҪгҒ®е°Һе…ҘгҒӘгҒ©гҖҒиҒҙиЎҶгҒЁгҒ®еҸҢж–№еҗ‘жҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгӮӢд»•зө„гҒҝгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒеҸӮеҠ иҖ…гҒ®жәҖи¶іеәҰеҗ‘дёҠгҒ«з№ӢгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дәӢеҫҢгӮўгғігӮұгғјгғҲгҒ®жҙ»з”Ё:
еӯҰдјҡзөӮдәҶеҫҢгҒ®гӮўгғігӮұгғјгғҲгҒҜгҖҒйҒӢе–¶ж”№е–„гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®иІҙйҮҚгҒӘжғ…е ұжәҗгҒ§гҒҷгҖӮгҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒӘгӮүгҒ§гҒҜгҒ®жәҖи¶іеәҰгӮ„иӘІйЎҢзӮ№пјҲдҫӢпјҡйҹіеЈ°гғ»жҳ еғҸе“ҒиіӘгҖҒгӮ·гӮ№гғҶгғ ж“ҚдҪңжҖ§гҒӘгҒ©пјүгӮ’йҮҚзӮ№зҡ„гҒ«иіӘе•ҸгҒ—гҖҒеҫ—гӮүгӮҢгҒҹгғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгӮ’ж¬Ўеӣһй–ӢеӮ¬гҒ®иЁҲз”»гҒ«жҙ»гҒӢгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒЁгӮҒпјҡгҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒ§еӯҰиЎ“дәӨжөҒгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гӮ’еәғгҒ’гӮӢ
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®еӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж§ҳгҖ…гҒӘиӘІйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒ—гҖҒеӯҰиЎ“дәӨжөҒгҒ®ж–°гҒҹгҒӘеҸҜиғҪжҖ§гӮ’еҲҮгӮҠжӢ“гҒҸз”»жңҹзҡ„гҒӘеҪўејҸгҒ§гҒҷгҖӮе ҙжүҖгӮ„жҷӮй–“гҒ®еҲ¶зҙ„гӮ’и¶…гҒҲгҒҹгӮўгӮҜгӮ»гӮ№жҖ§гҖҒгӮігӮ№гғҲеүҠжёӣгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгӮӘгғігғҮгғһгғігғүй…ҚдҝЎгҒ«гӮҲгӮӢжғ…е ұжөёйҖҸеәҰгҒ®еҗ‘дёҠгҒӘгҒ©гҖҒгҒқгҒ®гғЎгғӘгғғгғҲгҒҜеӨҡеІҗгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒеҜҫйқўдәӨжөҒгҒ®ж©ҹдјҡгҒ®жёӣе°‘гӮ„жҠҖиЎ“зҡ„гҒӘиӘІйЎҢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиҖғж…®гҒҷгҒ№гҒҚзӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдәӢеүҚгҒ®з¶ҝеҜҶгҒӘжә–еӮҷгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘгғ„гғјгғ«гҒ®жҙ»з”ЁгҖҒгҒқгҒ—гҒҰе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгӮ’жҢҒгҒӨеӨ–йғЁгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒЁгҒ®йҖЈжҗәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иӘІйЎҢгҒҜе…ӢжңҚеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгҒ®жҲҗеҠҹгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«еӯҰдјҡгӮ’ж»һгӮҠгҒӘгҒҸй–ӢеӮ¬гҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгӮҲгӮҠеӨҡгҒҸгҒ®з ”究иҖ…гҒ«зҷәиЎЁгҒЁиӯ°и«–гҒ®е ҙгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҖҒеӯҰиЎ“гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈе…ЁдҪ“гҒ®жҙ»жҖ§еҢ–гҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеҫҢгӮӮйҖІеҢ–гӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҖҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеӯҰдјҡгҖҚгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«жҙ»з”ЁгҒ—гҖҒзҹҘгҒ®дәӨжөҒгӮ’ж·ұгӮҒгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ